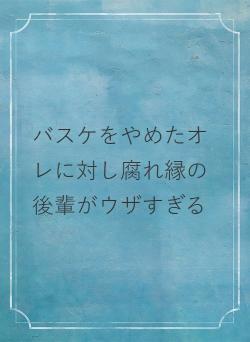そして家に帰ってのち、色々と考え事をした。
濃密な一日だったな。しかし、まだ飲み込めてはいないんだよな。
……榊原さんを信用しないわけではないが、やはり、夢で余命宣告を受けたなんて言われたらなあ。
難しいことは考えたくはないのだが……。
というか、何気に今日は大胆なことをしてしまったな。女子を、しかも榊原さんみたいなかわいい人をおんぶするなんて……。しかも今も背中にその感触が残って変な気分だ。
考えれば考えるほど変な思考になってしまう。
うん、もう寝よう。そしてご飯食べるとすぐにベッドに寝ころぶのであった。
ちなみに興奮で中々眠ることが出来なかったというのは言うまでもないだろう。
「迎えに来たわよ」
翌日、家の前に出ると、彼女がすでに待ち受けていた。
「なんだよ、一緒に登校するとか聞いてないぞ」
「だって、私が一緒に登校したいもん。余命僅かだし」
「それを言うなよ。こっちが弱いだろ」
「ふふふ」
そして彼女は手を握ってきた。俺が拒否する暇もなく。
「何するんだ」
今手には彼女のぬくもりが残っている。手の暖かさが。俺は今まで女子と手をつないだこともない。
今この瞬間にもドキドキが止まらない。
だめだこんなのでは。相手のペースに巻き込まれてしまう。
決してドキドキしてるということはばれないようにしよう。
そう決めた……瞬間だった。
「へー、ドキドキしないの? 私みたいな美少女に手を繫がれて」
うぅ、核心を突かれた。だが、
「ドキドキなんかしてない」
あくまでもそう言い張る。
疑問形だからばれてはないはずだ。
「私なりのプレゼントなのに。私の余命を大事に使いたいだけなの」
「何だよその考え方」
変な考え方だ。つまり死ぬまでに俺を喜ばせるようなことをいっぱいしたいってか?
「私はね」
そう思っていると、彼女が口を開いた。
「こういう異性の友達とかいなかったからさ。死ぬまでにやりたいってね」
「それ自分がやりたいだけじゃねえのか?」
「ばれた?」
そう言って笑った。
そう言えばこの子はクラスでモテてたな……
「そういや、彼氏とかはいなかったのか?」
「うん。いないよ。……そう聞くってことは私に彼女になってほしいってこと? なってほしいならいつでもなるけど」
「いや、いいわ」
よくわからない質問にはとりあえず否定で答えておいた。まあ、そう言われて「え? いいの?」なんて言ったら負けみたいだ。
だが、彼女はあくまでもそのスタイルを崩さないみたいで「えー、人の好意はおとなしく受け取ったほうが得だよ?」なんて言われた。
俺は別に損得勘定で動いているわけではないんだが。
「まあ、でも」
数歩歩いた先でまた彼女が口に出した。
「余命四ヶ月の彼女なんていらないかあ……」
そんな自虐的なことを言って悲しそうな顔をした。
俺はどうしたらいいんだよ。
とりあえず慰めればいいのか?
「別にそんなんじゃねえ、なんかそう言われてOKするのが嫌なだけだ」
そう、静かに言った。
これ本心だしな。
「じゃあ、彼氏になったらいいじゃん」
「友達になっての次は彼氏になってかよ。図々しいな」
「えー。まあいっか。その代わり放課後に付き合ってくれる?」
「まあ、いいけど」
「おはよー!!!!」
今日も笑顔で皆におはようを告げていた。昨日泣いていたのが嘘みたいに。それに呼応してみんなも「おはよう」などと返していた。
そんな中、
「なんで、町田君が一緒にいるの?」
と、榊原さんの友達の相原さんが言った。まあそりゃあ不思議には思うだろう。
こんな友達いない奴と、榊原さんが一緒に登校するなんて。
「えへへー、不思議でしょ?」
とぼけた表情で榊原さんはそう返した。
「とぼけないでよ!!」
相原さんが語彙を強めに発した。
「昨日友達になったの。ねー浩二君」
そう言って俺の肩に手をのせてきた。
「なあ」
「何?」
「怪しまれるようなことをすんなよ。俺たちはあくまでも友達なんだから」
肩に手をのせるなんてことはあまりしない方がいい。
てか、もう下の名前呼びだし。
「じゃあ、こういうの嫌なの?」
「……嫌ではないが」
「ならいいじゃん!」
「……」
「それに私は男女の友情が通用すると思っている派の人間だしね」
「……お前なあ」
さっきまで彼女になってもいいなんて言っていた人と同一人物に思えない。
「まあでも、二人の仲の良さは伝わったわよ」
相原さんがそう言った。なるほど、この変なやり取りは仲がいいという判定なのか。
「さて、浩二君。授業までお話しよっか」
「ああ」
「とりあえず私の余命の話だけど、誰にも言ったらだめだからね」
「分かってるよ」
「へー。ならよかった」
そして、俺の頬を触り、
「これからよろしくね」
と、小声で言った。まじでなんだ。俺をドキドキさせたいのか?
「さてと、一緒にトイレ行きましょっか」
「なんだよ。普通男女の連れションとかないだろ」
「いいじゃない」
と、半ば強引に連れていかれた。もうホームルームまで三分しかないが、時間的に大丈夫なのだろうか。
「さあて、浩二君。私の話を聞いてくれる?」
「なんだ? 時間ないから手早く頼む」
「私ね、やっぱり怖いの。頭なでてくれる?」
「……俺、いいように使われてないか?」
「まあね。でも、こんなこと頼めるの浩二君だけだし、お願い」
「はいはい、分かったよ」
そう言って頭をなでる。完全にかわいさとおどけさを使って俺をこき使っている気もするが、まあ俺自身も嫌なわけではないので、許せる範囲だ。
さて、もう時間がない。
「じゃあ、行くか」
「……うん」
元気のなさそうな顔だ。これは演技なのか、それとも本当の彼女なのかもうわからなくなってきた。
「おまたせー。時間大丈夫?」
「うん。全然大丈夫だよ」
「だって、良かったね! 浩二君」
「ああ」
間に合わなかったらどうしようかと思っていた。
無事に間に合ってよかった。
濃密な一日だったな。しかし、まだ飲み込めてはいないんだよな。
……榊原さんを信用しないわけではないが、やはり、夢で余命宣告を受けたなんて言われたらなあ。
難しいことは考えたくはないのだが……。
というか、何気に今日は大胆なことをしてしまったな。女子を、しかも榊原さんみたいなかわいい人をおんぶするなんて……。しかも今も背中にその感触が残って変な気分だ。
考えれば考えるほど変な思考になってしまう。
うん、もう寝よう。そしてご飯食べるとすぐにベッドに寝ころぶのであった。
ちなみに興奮で中々眠ることが出来なかったというのは言うまでもないだろう。
「迎えに来たわよ」
翌日、家の前に出ると、彼女がすでに待ち受けていた。
「なんだよ、一緒に登校するとか聞いてないぞ」
「だって、私が一緒に登校したいもん。余命僅かだし」
「それを言うなよ。こっちが弱いだろ」
「ふふふ」
そして彼女は手を握ってきた。俺が拒否する暇もなく。
「何するんだ」
今手には彼女のぬくもりが残っている。手の暖かさが。俺は今まで女子と手をつないだこともない。
今この瞬間にもドキドキが止まらない。
だめだこんなのでは。相手のペースに巻き込まれてしまう。
決してドキドキしてるということはばれないようにしよう。
そう決めた……瞬間だった。
「へー、ドキドキしないの? 私みたいな美少女に手を繫がれて」
うぅ、核心を突かれた。だが、
「ドキドキなんかしてない」
あくまでもそう言い張る。
疑問形だからばれてはないはずだ。
「私なりのプレゼントなのに。私の余命を大事に使いたいだけなの」
「何だよその考え方」
変な考え方だ。つまり死ぬまでに俺を喜ばせるようなことをいっぱいしたいってか?
「私はね」
そう思っていると、彼女が口を開いた。
「こういう異性の友達とかいなかったからさ。死ぬまでにやりたいってね」
「それ自分がやりたいだけじゃねえのか?」
「ばれた?」
そう言って笑った。
そう言えばこの子はクラスでモテてたな……
「そういや、彼氏とかはいなかったのか?」
「うん。いないよ。……そう聞くってことは私に彼女になってほしいってこと? なってほしいならいつでもなるけど」
「いや、いいわ」
よくわからない質問にはとりあえず否定で答えておいた。まあ、そう言われて「え? いいの?」なんて言ったら負けみたいだ。
だが、彼女はあくまでもそのスタイルを崩さないみたいで「えー、人の好意はおとなしく受け取ったほうが得だよ?」なんて言われた。
俺は別に損得勘定で動いているわけではないんだが。
「まあ、でも」
数歩歩いた先でまた彼女が口に出した。
「余命四ヶ月の彼女なんていらないかあ……」
そんな自虐的なことを言って悲しそうな顔をした。
俺はどうしたらいいんだよ。
とりあえず慰めればいいのか?
「別にそんなんじゃねえ、なんかそう言われてOKするのが嫌なだけだ」
そう、静かに言った。
これ本心だしな。
「じゃあ、彼氏になったらいいじゃん」
「友達になっての次は彼氏になってかよ。図々しいな」
「えー。まあいっか。その代わり放課後に付き合ってくれる?」
「まあ、いいけど」
「おはよー!!!!」
今日も笑顔で皆におはようを告げていた。昨日泣いていたのが嘘みたいに。それに呼応してみんなも「おはよう」などと返していた。
そんな中、
「なんで、町田君が一緒にいるの?」
と、榊原さんの友達の相原さんが言った。まあそりゃあ不思議には思うだろう。
こんな友達いない奴と、榊原さんが一緒に登校するなんて。
「えへへー、不思議でしょ?」
とぼけた表情で榊原さんはそう返した。
「とぼけないでよ!!」
相原さんが語彙を強めに発した。
「昨日友達になったの。ねー浩二君」
そう言って俺の肩に手をのせてきた。
「なあ」
「何?」
「怪しまれるようなことをすんなよ。俺たちはあくまでも友達なんだから」
肩に手をのせるなんてことはあまりしない方がいい。
てか、もう下の名前呼びだし。
「じゃあ、こういうの嫌なの?」
「……嫌ではないが」
「ならいいじゃん!」
「……」
「それに私は男女の友情が通用すると思っている派の人間だしね」
「……お前なあ」
さっきまで彼女になってもいいなんて言っていた人と同一人物に思えない。
「まあでも、二人の仲の良さは伝わったわよ」
相原さんがそう言った。なるほど、この変なやり取りは仲がいいという判定なのか。
「さて、浩二君。授業までお話しよっか」
「ああ」
「とりあえず私の余命の話だけど、誰にも言ったらだめだからね」
「分かってるよ」
「へー。ならよかった」
そして、俺の頬を触り、
「これからよろしくね」
と、小声で言った。まじでなんだ。俺をドキドキさせたいのか?
「さてと、一緒にトイレ行きましょっか」
「なんだよ。普通男女の連れションとかないだろ」
「いいじゃない」
と、半ば強引に連れていかれた。もうホームルームまで三分しかないが、時間的に大丈夫なのだろうか。
「さあて、浩二君。私の話を聞いてくれる?」
「なんだ? 時間ないから手早く頼む」
「私ね、やっぱり怖いの。頭なでてくれる?」
「……俺、いいように使われてないか?」
「まあね。でも、こんなこと頼めるの浩二君だけだし、お願い」
「はいはい、分かったよ」
そう言って頭をなでる。完全にかわいさとおどけさを使って俺をこき使っている気もするが、まあ俺自身も嫌なわけではないので、許せる範囲だ。
さて、もう時間がない。
「じゃあ、行くか」
「……うん」
元気のなさそうな顔だ。これは演技なのか、それとも本当の彼女なのかもうわからなくなってきた。
「おまたせー。時間大丈夫?」
「うん。全然大丈夫だよ」
「だって、良かったね! 浩二君」
「ああ」
間に合わなかったらどうしようかと思っていた。
無事に間に合ってよかった。