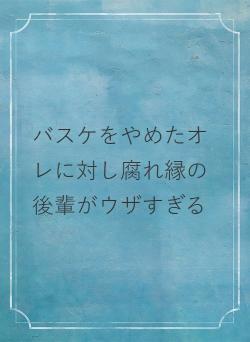俺は平凡な高校生だ。だが、二つだけ他と違うことがある。高校生の身で一人暮らししていることと、悲しいことに友達と言える存在がいないけど。だけど、俺は学校を苦とは思わない。
一つ気になる事と言えば、一週間前から来なくなった隣の席の榊原鈴奈さんのことくらいか。
授業料払っているんだから、来ればいいのに……
だがそれは俺に関することではない。
だって俺は今受験生なんだから自分のことを考えればいい。
そしてノートを開いて勉強をする。だが、やる気は出ない、受験生だというのに。
俺には夢がないのだ。どこの大学に行って何を学ぼうとかそんな事を一切考えたことがない。
そして学校が終わって、一人で帰る。大体みんな友達と帰っているものだが、一人で帰るのもいいものだ。
イヤホンで好きな音楽を聴きながら帰れる。こんなに幸せなことはない。
今日はいつもより疲れたなと思い、思い切っていつもと違う道で帰ることにした。
五分長く時間がかかる代わりに、いつもと違う景色を見られるのだ。
だが、この時はこの何気ない気まぐれが俺の人生に転機をもたらすとは思っていなかった。
それは公園の隣を歩いていた時だった。公園からすすり泣く声が聴こえた。それも女性の声だ。
俺はたぶんこの声を知っている、この声の主の存在を知っている。
この特徴的な声はもうあの人しかいない。そう、クラスメイトの榊原さんだろう。
泣いている理由は分からない。もしかして学校を休んでいることに関係しているのだろうか。
そして、公園を覗く。
どうやら、俺の予想は正解だったようだ。
槇原さんが一人公園のブランコに乗りながら泣いていたのだ。
「なんで泣いているんだ?」
声をかけた。
これは俺にしては大胆な行動だ。いくらクラスメイトとは言え、友達じゃない女子に関わろうとするなんて。
この行為は彼女にとって迷惑かもしれない。
でも、俺には見過ごせなかった。
「……別に泣いててもいいでしょ。私にかかわらないで」
そう低音ボイスで拒絶された。
まあ、友達ですらない奴が言ったらこうなることは明白だとは思っていたが。
いつもならこう言われたらもう放っておくだろう。
だけど今日は違った。そんなことを言われた程度で引き下がるような気持ちではなかった。
「泣いてる奴にかかわらないでって言われても、俺には見過ごせねえよ」
俺の気持ちを単刀直入に答える。
「……何かあるんだったら俺に言えよ。何か吐き出せば楽になるかもしれないだろ?」
「……あなたには関係ないから」
どうやらそう簡単には話してくれないらしい。
別に俺はこのまま帰ってもいい。だが、もし今帰ったら後悔する。今心が消えかかっている彼女を放っておくようなことは。
「いいから、俺はどんな理由でも馬鹿にしたりはしないから」
「……なんで……?」
「え?」
「なんで……かまってくれるの?」
「クラスメイトだろ」
「……でも、いいの」
涙が一粒彼女の頬を伝った。
「こんなこと言っても何にもならないから」
消えそうな声だ。掠れていて、注意深く聴かないと聞こえない感じだ。
「じゃあね」
と、たどたどしく歩いていく。けれど、その足取りは到底歩けているとは言えない。
誰から見ても無理して歩いてると思われそうな足取りだ。
「はあ、歩けねえなら無理して歩くなよ。さっきからほぼ移動出来てねえじゃねえか」
実際、歩き始めてから二〇秒くらい経っているが、五メートル程度しか進めていないように見える。
「とりあえず、これで涙吹けよ」
ハンカチを貸す。頬にしみついている水分が邪魔そうに見えた。
「……うん」
そして彼女は観念したのか、ブランコに戻る。
俺はそんな彼女に一言「隣良いか?」と言って、隣に座る。
無言の時間が流れている。だが、今は彼女のためにただ待っているのがいいだろう。
「……私ね……」
口を開いた。
「余命もう四か月無いの」
「え?」
「私は九月の末に死ぬの」
その言葉を俺は呑み込めなかった。余命と言う言葉を受け入れられなかった。だって隣にいるのは、いかにも元気そうな女の子だ。なのに余命四か月。
意味が分からない。
「私は、夢で余命宣告を受けたの……君は十八になるタイミングで死ぬって。私の誕生日は九月十八だからもう四か月しかない」
「……」
「非科学的だと思われるかもしれない。でも、事実なの。馬鹿みたいよね。両親も、友達も信じてくれなかったのに。友達でもないあなたに言うなんて」
「……」
「信じなくていいよ。信じるのは私がいなくなってからでいい」
「……信じるよ」
「え?」
「俺は君のいう事を信じるよ」
確かに夢で余命を伝えられるなんて非科学的で、信じる根拠なんてどこにもない。だが、こんな悲痛な顔をしている彼女が嘘なんて言っているはずがない。少なくとも俺は……信じたい。
根拠なんて今の彼女の悲痛な顔だけでいいじゃないか。
「いいの?」
「いいのって、信じるしかねえだろ。そんな顔をされたらさ」
「……ありがと」
「どういたしまして」
「……私は死にたくない」
「……」
「まだしたいこともやりたいことも決まってないのに。死にたくない……」
「……」
「私親に何も恩返ししてないのに」
俺はそれから彼女の心の叫びを十分間聞いた。
今の俺にできることは聞く事だけだ。
「……ねえ、嫌じゃなかったらでいいんだけど」
涙が止まった様子の彼女が静かに言う。
「なんだ?」
「友達になって?」
「……俺でいいのか?」
「なんでそんなこと言うの?」
「だって、俺根暗だし」
俺には友達なんていないし、そもそも俺は人に好かれるタイプだなんて一ミリも思っていない。
少なくとも彼女のような美人とは釣り合わないはずだ。
「そんなこと言って、謙遜でしょ?」
「いや、違うんだが」
ここで俺が謙遜する意味なんてない。だって、彼女みたいなかわいい女子が友達になるというチャンスをみすみす謙遜で逃す馬鹿はいないと思うし。
「まあ、兎に角、友達になってください。あ、彼女でもいいよ?」
「え!?」
「ふふ、それはさすがに冗談よ。でも、友達は本気。お願いします」
「……ああ、分かった」
流石にそんな真剣な顔で言われたら、俺はそれを断る術を知らない。
そして、俺は帰ろうとしたが、
「ううーん」
彼女はブランコから立ち上がれそうになかったみたいだ。
「……手を貸そうか?」
「……ありがとう」
そしてそのまま、俺が彼女をおんぶする感じになった。ある意味友達になるよりもハードルが高いことをしている気がする。
人生で女子をおんぶするなんて機会があるとは思っていなかった。しかもこんな状況で。
「なんか悪いね」
「いや、いいさ。友達を助けるのは当たり前の事だろ」
「ふふ、うれしい」
俺は彼女の家の前で彼女を下ろした。
「ねえ、悪いんだけど……」
「どうした?」
「まだ帰りたくない」
そう言って彼女は抱き着いてきた。
「……安心しろ。君は一人じゃない」
俺は臭いセリフを言ってしまった。まるでフィクションのような状況に気持ちが高揚していたのだろう。
言った後で、厨二病すぎるセリフだと、言ってて恥ずかしくなった。しかし、それでもうれしいようで、
「ありがとう」
と言われた。その後五分くらい抱き着かれた。そのハグは嫌な感じはしなかった。