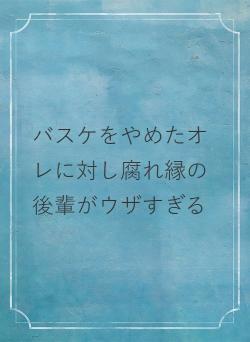そして次の日、俺はまた学校に向かうために家を出た。テスト返却日の翌日から普通に授業が始まるというのがうちの学校のきついところだ。
家を出ると、鈴奈がいた。今日も一緒に登校するために家の前に来たのだろうか。
そして、早速、鈴奈に「おはよう」と告げた。いつもみたいに明るい「おはよう!!」が返ってくると思いながら。だが存外、意外なことに「……おはよう……」と、暗いテンションの返事が返ってきた。
「どうしたんだよ、いったい」
昨日の感じだったら元気いっぱいの感じで来ると思っていたのだが。何か、事件でもあったのか?
「私ね、また不安になっちゃって」
「不安?」
「そう、普段通りの笑顔でいたいんだけどね。どうやらそれもきついみたい」
「どうした? いったい」
「死の恐怖がまた襲ってきて、昨日一睡もできなかった。それどころか、今も押しつぶされそうで……」
「……」
「だから、ごめんね。私もう、歩けそうにない」
そう言って、彼女は、その場に倒れこんだ。今まで鈴奈の元気の前に忘れていたのだが、余命三ヶ月なのだ。俺だったら、もう動けなくなりそうな状況なのだ。
今までの鈴奈がおかしかっただけなのだ。
「じゃあ、どうやってここまで来たんだ」
「それは……根性?」
「根性って、おい」
「だからごめん。私学校行けないかも」
泣きそうな鈴奈、俺にはどう元気づけることが出来るだろうか。数秒考えた後、
「……はあ、仕方ない。さぼるか」
と言った。この状況の鈴奈を学校に行かせるわけにも、一人でいさせるわけにもいかない。
「え? 私のために?」
「……大体、そのために来たんだろうか」
「えへ、ばれた?」
そして、俺たちはそのまま学校ではなく、別の場所へと向かった。彼女が行きたいといった場所へ。
「で、なんでここなんだよ」
まさか遊園地とは思わなかった。俺が想像していたのは、何というか、もう少し落ち着いた場所だったのだ。
「いいでしょ」
そう言って鈴奈は俺の手を引っ張ってきた。
「で、ここに乗りましょう!」
そこにあったのは泣く子も黙るジェットコースターだった。
「ジェットコースターか」
正直嫌だ。俺はこういう絶叫マシーンが苦手なのだ。
そんな俺に対して、「文句あるの?」と、鈴奈が睨んできた。俺の心の内はただわかりらしい。
「あるよ。という訳で一人で楽しんでくれ」
文句なら死ぬほどある。鈴奈は元気付けたいが、それとこれは話が違う。他の遊具には付き合うから、ジェットコースター系の乗り物には乗りたくない。そしてその場から逃走しようとしたが、
「いや、浩二君も行くんだよ?」
そのまま、俺が抵抗する暇なく手をがっしりとホールドされたまま、列に並ばれた。
しかも最悪なことに今日が本来平日だから人がそこまで並んでない。このままだと順番がすぐに来る。
「ああ、嫌だ」
「だったら私と出会ってしまったことを後悔するんだね」
「なんか、テンション上げてないか?」
「無理やり上げているだけだよ。本当なら今も恐怖で押しつぶされそうだからね。いま、浩二君をいじめてる今だからこそ、全力で楽しめるってわけ」
「いじめてるのかよ」
まあ、それで楽しいのならいいけど……良くねえ、乗りたくねえよ。
そして精いっぱいの抵抗を試みるが、周りの目もあるので、そこまで強くは抵抗できない。
そしてそのまま、ジェットコースターに乗せられてしまった。
「覚悟はいい?」
「良いわけがあるか。俺は今からでもここから降りたいんだよ」
「だめ!!」
「っくそ」
そして、そんな会話をしている間にもどんどん発射準備は整っていく。もはや抵抗できないところまで来ている。
そしてそのままジェットコースターは発車した。
「ん? やけに静かだな」
意外にそこまでアップダウンがない。これならいけそうだ。
「ふっふっふ。大変なのはここからなの」
「は?」
少しずつ上に上がっていき、そのまま……急降下した。
「いや、ちょっと待て」
ものすごいスピードで下る。向かい風がものすごい勢いで遅い、さらにその恐ろしいアップダウンにより、俺の三半規管がおかしくなっていく。そして段々、俺はしんどくなってきた。具体的に言うと、普通に吐きそうだ。
隣では、鈴奈が「いえーい!!!!」と言って、気持ちよさそうな顔をしている。もしかして気持ち悪くなってるの俺だけ?
しかも別のお客さんも楽しんでいるみたいだし。
そりゃあふつう乗りたくない人は乗らんよな。っくそ、本当に最悪だ。
「ちょっとたんまたんまたんまたんま!!!」
そのまま黙ってもいられず、そのようなことを吐く。黙っていては、ストレスに押しつぶされそうだ。
「いいじゃん、浩二君。その意気だよ」
「その意気って、俺はもう死にそうなんだが、今からでもおろしてもらいたいんだが」
「だめ、それにまだ半分言ってないよ。たぶん」
え⁉ まだ半分残ってる????????????
死んだーーーーーーー。
そして、頂上に向かって一気に駆け上がっていく。
「っちょ、これって」
「お察しの通りだよ」
「は?」
まさか第二弾?
そして、一気に降下した。しかも、先ほどよりもはやい速度で。
「dすcjんhくぢjcsんじょkdんjdkls」
もう言葉にもならない叫びが俺の口の中から流れてくる。
俯瞰してみている自分が、自分を見ているような気分になる。
ああ、もう嫌だ。ああ、もう嫌だ。もう帰りたい。もう帰りたい。
そして俺の精神が百回ほど死んだところで、ジェットコースターは終わった。
「はあはあ、死ぬかと思った。いや、死んだ。絶対死んだ。一〇回は死んだ」
「えへへ、楽しかったねー」
「あれを楽しいと思えるお前は異常だ」
本当にあれはおかしかった。もう人間が乗る乗り物じゃなかった。本当にあれはやばい、やばすぎた。もう、死ぬ気分を味わいたい異常者が乗る乗り物だ。これを金払ってきている人はマジで変態だ。
「私ね……」
「ん?」
「あれ、乗ったらさ、人生楽しめてる感じがするのよ。しっかりとね」
「いや、寿命減るわ。あれはさ」
「私は元から寿命ないから大丈夫なの?」
そう言って笑う。ブラックジョークやめい。今の俺には声を出してツッコむ体力なんて残されてないし。
「そういやもう大丈夫なのか?」
気持ちの落ち込みは。
「いや、でもまあ大分浩二君の叫びで吹き飛んだかな」
「なんだよ、それ」
「まあ、でもありがとうね。一緒に学校さぼってくれて」
「……」
「じゃあ、次は浩二君が死なないようなやつに乗ろう!!!」
「ああ、今度は頼むぞ」
次もまた絶叫系だったら、本当に鈴奈を殴ってしまうかもしれない。
そして次に行ったのは、コーヒーカップだった。
「これだったらいけるでしょ?」
「ああ、いけるな」
「じゃあ、決まりね」
そして俺たちはコーヒーカップに乗った。
「あはは、回るねえ」
「回るなあ」
「グールグルあははは」
「ははは」
そして様々なところ(きついやつ以外)乗ったところで、昼ご飯を食べようということになった。
家を出ると、鈴奈がいた。今日も一緒に登校するために家の前に来たのだろうか。
そして、早速、鈴奈に「おはよう」と告げた。いつもみたいに明るい「おはよう!!」が返ってくると思いながら。だが存外、意外なことに「……おはよう……」と、暗いテンションの返事が返ってきた。
「どうしたんだよ、いったい」
昨日の感じだったら元気いっぱいの感じで来ると思っていたのだが。何か、事件でもあったのか?
「私ね、また不安になっちゃって」
「不安?」
「そう、普段通りの笑顔でいたいんだけどね。どうやらそれもきついみたい」
「どうした? いったい」
「死の恐怖がまた襲ってきて、昨日一睡もできなかった。それどころか、今も押しつぶされそうで……」
「……」
「だから、ごめんね。私もう、歩けそうにない」
そう言って、彼女は、その場に倒れこんだ。今まで鈴奈の元気の前に忘れていたのだが、余命三ヶ月なのだ。俺だったら、もう動けなくなりそうな状況なのだ。
今までの鈴奈がおかしかっただけなのだ。
「じゃあ、どうやってここまで来たんだ」
「それは……根性?」
「根性って、おい」
「だからごめん。私学校行けないかも」
泣きそうな鈴奈、俺にはどう元気づけることが出来るだろうか。数秒考えた後、
「……はあ、仕方ない。さぼるか」
と言った。この状況の鈴奈を学校に行かせるわけにも、一人でいさせるわけにもいかない。
「え? 私のために?」
「……大体、そのために来たんだろうか」
「えへ、ばれた?」
そして、俺たちはそのまま学校ではなく、別の場所へと向かった。彼女が行きたいといった場所へ。
「で、なんでここなんだよ」
まさか遊園地とは思わなかった。俺が想像していたのは、何というか、もう少し落ち着いた場所だったのだ。
「いいでしょ」
そう言って鈴奈は俺の手を引っ張ってきた。
「で、ここに乗りましょう!」
そこにあったのは泣く子も黙るジェットコースターだった。
「ジェットコースターか」
正直嫌だ。俺はこういう絶叫マシーンが苦手なのだ。
そんな俺に対して、「文句あるの?」と、鈴奈が睨んできた。俺の心の内はただわかりらしい。
「あるよ。という訳で一人で楽しんでくれ」
文句なら死ぬほどある。鈴奈は元気付けたいが、それとこれは話が違う。他の遊具には付き合うから、ジェットコースター系の乗り物には乗りたくない。そしてその場から逃走しようとしたが、
「いや、浩二君も行くんだよ?」
そのまま、俺が抵抗する暇なく手をがっしりとホールドされたまま、列に並ばれた。
しかも最悪なことに今日が本来平日だから人がそこまで並んでない。このままだと順番がすぐに来る。
「ああ、嫌だ」
「だったら私と出会ってしまったことを後悔するんだね」
「なんか、テンション上げてないか?」
「無理やり上げているだけだよ。本当なら今も恐怖で押しつぶされそうだからね。いま、浩二君をいじめてる今だからこそ、全力で楽しめるってわけ」
「いじめてるのかよ」
まあ、それで楽しいのならいいけど……良くねえ、乗りたくねえよ。
そして精いっぱいの抵抗を試みるが、周りの目もあるので、そこまで強くは抵抗できない。
そしてそのまま、ジェットコースターに乗せられてしまった。
「覚悟はいい?」
「良いわけがあるか。俺は今からでもここから降りたいんだよ」
「だめ!!」
「っくそ」
そして、そんな会話をしている間にもどんどん発射準備は整っていく。もはや抵抗できないところまで来ている。
そしてそのままジェットコースターは発車した。
「ん? やけに静かだな」
意外にそこまでアップダウンがない。これならいけそうだ。
「ふっふっふ。大変なのはここからなの」
「は?」
少しずつ上に上がっていき、そのまま……急降下した。
「いや、ちょっと待て」
ものすごいスピードで下る。向かい風がものすごい勢いで遅い、さらにその恐ろしいアップダウンにより、俺の三半規管がおかしくなっていく。そして段々、俺はしんどくなってきた。具体的に言うと、普通に吐きそうだ。
隣では、鈴奈が「いえーい!!!!」と言って、気持ちよさそうな顔をしている。もしかして気持ち悪くなってるの俺だけ?
しかも別のお客さんも楽しんでいるみたいだし。
そりゃあふつう乗りたくない人は乗らんよな。っくそ、本当に最悪だ。
「ちょっとたんまたんまたんまたんま!!!」
そのまま黙ってもいられず、そのようなことを吐く。黙っていては、ストレスに押しつぶされそうだ。
「いいじゃん、浩二君。その意気だよ」
「その意気って、俺はもう死にそうなんだが、今からでもおろしてもらいたいんだが」
「だめ、それにまだ半分言ってないよ。たぶん」
え⁉ まだ半分残ってる????????????
死んだーーーーーーー。
そして、頂上に向かって一気に駆け上がっていく。
「っちょ、これって」
「お察しの通りだよ」
「は?」
まさか第二弾?
そして、一気に降下した。しかも、先ほどよりもはやい速度で。
「dすcjんhくぢjcsんじょkdんjdkls」
もう言葉にもならない叫びが俺の口の中から流れてくる。
俯瞰してみている自分が、自分を見ているような気分になる。
ああ、もう嫌だ。ああ、もう嫌だ。もう帰りたい。もう帰りたい。
そして俺の精神が百回ほど死んだところで、ジェットコースターは終わった。
「はあはあ、死ぬかと思った。いや、死んだ。絶対死んだ。一〇回は死んだ」
「えへへ、楽しかったねー」
「あれを楽しいと思えるお前は異常だ」
本当にあれはおかしかった。もう人間が乗る乗り物じゃなかった。本当にあれはやばい、やばすぎた。もう、死ぬ気分を味わいたい異常者が乗る乗り物だ。これを金払ってきている人はマジで変態だ。
「私ね……」
「ん?」
「あれ、乗ったらさ、人生楽しめてる感じがするのよ。しっかりとね」
「いや、寿命減るわ。あれはさ」
「私は元から寿命ないから大丈夫なの?」
そう言って笑う。ブラックジョークやめい。今の俺には声を出してツッコむ体力なんて残されてないし。
「そういやもう大丈夫なのか?」
気持ちの落ち込みは。
「いや、でもまあ大分浩二君の叫びで吹き飛んだかな」
「なんだよ、それ」
「まあ、でもありがとうね。一緒に学校さぼってくれて」
「……」
「じゃあ、次は浩二君が死なないようなやつに乗ろう!!!」
「ああ、今度は頼むぞ」
次もまた絶叫系だったら、本当に鈴奈を殴ってしまうかもしれない。
そして次に行ったのは、コーヒーカップだった。
「これだったらいけるでしょ?」
「ああ、いけるな」
「じゃあ、決まりね」
そして俺たちはコーヒーカップに乗った。
「あはは、回るねえ」
「回るなあ」
「グールグルあははは」
「ははは」
そして様々なところ(きついやつ以外)乗ったところで、昼ご飯を食べようということになった。