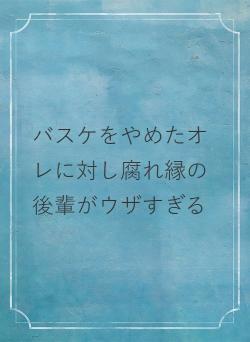そして授業が始まった。つまらない授業が。
(はあ)
心の中で溜息をつく。彼がいたところで、授業がつまらないことには変わりがないのだ。
山村君がいるから楽しくなった、なんてそんな都合のいいことはない。
確かに、授業前は楽しかった。
だが授業中はしゃべることなど出来ない。
窮屈だ。
だが、隣で必死にノートを取っている彼を見ると、少しだけだけどやる気が出た。
本当馬鹿みたいだ、他人に影響されているなんて。
私はこんなにもノートを取るのが苦痛なのに。
そして黒板の板書が書かれては消され、書かれては消されていく。普段真面目にノートを取っていない私がそのスピードに追いつける訳が無かった。
途中からひらがなで書いていたが、追いつけずに諦めた。
私には結局、真面目に授業を受けるのは無理だったのだ。そしてやはり授業は面白くない。
そう言えば周りの子は結構塾に行っているなと感じた。
私ももし塾に行けたら何か変わるのだろうか。
だけど、それは何ら関係のない話だ。
それに、私は本来学力なんてどうでもいい、人生にはあまり関係が無いと思う派だし。
だが、それでも彼の隣で授業について行けない私に軽く嫌気が差す。
そして残りの二〇分は軽くだけノートを取って、授業を眺めていた。
それを見て彼が「大丈夫か?」と聞いてくるが、無視をした。
私のことを可愛いと言ってくれる人にこんな顔は見せたくない。
軽く絶望している私の顔は。
そして授業が終わり、再び彼が「大丈夫か? ちゃんとノート取れた?」と聞いて来た。
それを聞いて私は、
「取れなかった。私バカだから」
と、愛想笑いをした。
実際私の成績は380人中337番目で下の方だ。
勉強ができる訳ではない。
私の学力なんて、本来なら赤点何個? とかふざけ合う陽キャみたいな物だ。
「自分のことをバカって言うなよ」
山村君は真剣な顔で言った。
「どうして?」
「やっぱり自分を不幸に置こうとしてるじゃん。俺に言わせたらお前はその顔を持ってるだけで勝ち組なんだよ!」
と、怒って来た。でも、私は……
「褒めてくれるのはありがたいけど……私は勉強はやっぱり出来ないの。いつも学年一位を争っている貴方にはわからないよ。授業がわからない苦痛なんて」
「じゃあ教えてあげよっか?」
先程とは違って軽い感じで彼が言った。私のことを想っている感じがする。でも、
「私、勉強したくない」
そう、したくないのだ。勉強なんて頭が疲れることしたくない。だからこそ学校が嫌いだと言うのに。
そして、私は逃げるように「トイレ行ってくる」と言ってトイレに駆け込んで行った。
「ハア」
トイレで溜息をつく。
私、だめだな。
彼は私のことを想ってそんな言葉をかけてくれたのに、一方的に否定して。
勉強が嫌いなのは事実だ。それは変わらない。
さっきは少し勉強してもいいかなと思った。だけど、私には勉強などとは無縁の人間なのだ。
私だって分かっている、もし勉強が出来たら今の状況を変えることができるかもしれないって。
私の家の中の立場が上がるかもしれないって。
でも、だからって勉強するモチベーションにはならない。
私は馬鹿のままでいいのだ。そ
れに私は女だ。どうせ勉強したところで、子育てや色々でその成果を発揮できないだろう。
彼には悪いけど、私は勉強しない。
別の方法を探したい。
私は色々思考をまとめた後、教室に戻った。
「おかえり」
優しくそう言われた。
そんな山村君を見ると、私が恥ずかしくなってくる。
大人すぎる。
「……ただいま」
「なあやっぱり……」
「だめ!」
彼の言葉を遮って言った。勉強なんてしたくない。
「まだなんも言ってないだろ。まあともかく、俺はお前の明るい顔を見たいんだよ。お前自分では気付いてないけど暗い顔してたぞ。もしさあ、それで授業が楽しくなったらもうけもんじゃねえか。別にやって嫌だったらやめてもいいからさあ」
紛れもない正論だ。これを論破することなど私には出来ない。ただ、私も理屈では無いのだ。理屈じゃ無いからこそ、正論を言われてもやる気は出ない。
「じゃあ、放課後、図書室で勉強するか」
「……嫌です」
「え?」
「私、もう勉強自体が嫌いで、理屈じゃなくて、その……」
言葉がまとまらない。ただ私の意思を伝えたいだけなのに。
「分かった。じゃあ、カフェでやろう。カフェラテとかケーキとか奢ってやるから」
「いや、そんなの悪いよ」
「いやいいから」
「え、でも」
「いいから」
(はあ)
心の中で溜息をつく。彼がいたところで、授業がつまらないことには変わりがないのだ。
山村君がいるから楽しくなった、なんてそんな都合のいいことはない。
確かに、授業前は楽しかった。
だが授業中はしゃべることなど出来ない。
窮屈だ。
だが、隣で必死にノートを取っている彼を見ると、少しだけだけどやる気が出た。
本当馬鹿みたいだ、他人に影響されているなんて。
私はこんなにもノートを取るのが苦痛なのに。
そして黒板の板書が書かれては消され、書かれては消されていく。普段真面目にノートを取っていない私がそのスピードに追いつける訳が無かった。
途中からひらがなで書いていたが、追いつけずに諦めた。
私には結局、真面目に授業を受けるのは無理だったのだ。そしてやはり授業は面白くない。
そう言えば周りの子は結構塾に行っているなと感じた。
私ももし塾に行けたら何か変わるのだろうか。
だけど、それは何ら関係のない話だ。
それに、私は本来学力なんてどうでもいい、人生にはあまり関係が無いと思う派だし。
だが、それでも彼の隣で授業について行けない私に軽く嫌気が差す。
そして残りの二〇分は軽くだけノートを取って、授業を眺めていた。
それを見て彼が「大丈夫か?」と聞いてくるが、無視をした。
私のことを可愛いと言ってくれる人にこんな顔は見せたくない。
軽く絶望している私の顔は。
そして授業が終わり、再び彼が「大丈夫か? ちゃんとノート取れた?」と聞いて来た。
それを聞いて私は、
「取れなかった。私バカだから」
と、愛想笑いをした。
実際私の成績は380人中337番目で下の方だ。
勉強ができる訳ではない。
私の学力なんて、本来なら赤点何個? とかふざけ合う陽キャみたいな物だ。
「自分のことをバカって言うなよ」
山村君は真剣な顔で言った。
「どうして?」
「やっぱり自分を不幸に置こうとしてるじゃん。俺に言わせたらお前はその顔を持ってるだけで勝ち組なんだよ!」
と、怒って来た。でも、私は……
「褒めてくれるのはありがたいけど……私は勉強はやっぱり出来ないの。いつも学年一位を争っている貴方にはわからないよ。授業がわからない苦痛なんて」
「じゃあ教えてあげよっか?」
先程とは違って軽い感じで彼が言った。私のことを想っている感じがする。でも、
「私、勉強したくない」
そう、したくないのだ。勉強なんて頭が疲れることしたくない。だからこそ学校が嫌いだと言うのに。
そして、私は逃げるように「トイレ行ってくる」と言ってトイレに駆け込んで行った。
「ハア」
トイレで溜息をつく。
私、だめだな。
彼は私のことを想ってそんな言葉をかけてくれたのに、一方的に否定して。
勉強が嫌いなのは事実だ。それは変わらない。
さっきは少し勉強してもいいかなと思った。だけど、私には勉強などとは無縁の人間なのだ。
私だって分かっている、もし勉強が出来たら今の状況を変えることができるかもしれないって。
私の家の中の立場が上がるかもしれないって。
でも、だからって勉強するモチベーションにはならない。
私は馬鹿のままでいいのだ。そ
れに私は女だ。どうせ勉強したところで、子育てや色々でその成果を発揮できないだろう。
彼には悪いけど、私は勉強しない。
別の方法を探したい。
私は色々思考をまとめた後、教室に戻った。
「おかえり」
優しくそう言われた。
そんな山村君を見ると、私が恥ずかしくなってくる。
大人すぎる。
「……ただいま」
「なあやっぱり……」
「だめ!」
彼の言葉を遮って言った。勉強なんてしたくない。
「まだなんも言ってないだろ。まあともかく、俺はお前の明るい顔を見たいんだよ。お前自分では気付いてないけど暗い顔してたぞ。もしさあ、それで授業が楽しくなったらもうけもんじゃねえか。別にやって嫌だったらやめてもいいからさあ」
紛れもない正論だ。これを論破することなど私には出来ない。ただ、私も理屈では無いのだ。理屈じゃ無いからこそ、正論を言われてもやる気は出ない。
「じゃあ、放課後、図書室で勉強するか」
「……嫌です」
「え?」
「私、もう勉強自体が嫌いで、理屈じゃなくて、その……」
言葉がまとまらない。ただ私の意思を伝えたいだけなのに。
「分かった。じゃあ、カフェでやろう。カフェラテとかケーキとか奢ってやるから」
「いや、そんなの悪いよ」
「いやいいから」
「え、でも」
「いいから」