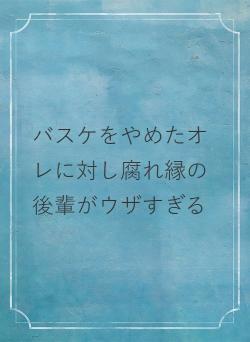「「はあはあ」」
「つっかれたー」
教室ついての彼の第一声はそれだった。私はそれにつられて「疲れたあ」と珍しく口を開く。学校で口を開くことなんて、授業の時にしかなかったのに。
「え? なに? なんで山村が鈴村さんと?」
そんな時、一人の女が山村君に話しかけた。クラスメイトの村林鳩さんだ。いつも山村君と一緒にいた人で、山村君の元カノだった気がする。
「俺の彼女」
そう群がる群衆どもに向かって彼は一言そう言い放った。それを聞いた周りの人たちは状況が呑み込めていないようで、「え? え?」「どういう事?」「どうして鈴村さんが……」みたいなことを言っている。
……一つ失礼な言葉が入っていた気がしたけど、まあいいか。釣り合わないのは事実だし。
だけど、そんな言葉さえどうでもいいくらいこうして俺の彼女と言われてという事で、少しうれしくなった。認められた感じがして。
「どういうこと?」
「今まで接点なかったよね」
「ちょっと飲み込めてないんだけど」
だけど、陽キャたちはしつこく山村君に群がってくる。
そしてその集団の中に私も呑み込まれてしまった。やばい、正直しんどい。この陽キャオーラに私は耐えられる気がしない。
やばい頭がくらくらとしてきた。これじゃあ、私……
「ちょっと」
山村君は集団の中から私を連れて出て来た。
「質問多すぎるって、俺、聖徳太子じゃないんだから」
その言葉で周りが笑いの渦に巻き込まれた、その片側で彼は、「大丈夫か?」と声をかけてくれた。
気恥ずかしく「大丈夫」などと答えると、「それは良かった」と言ってきれいな笑顔を見せてくれた。
そして質問に答えていく山村君。
もしかしたらこの人と一緒なら、学校ももしかしたら少し楽しくなるかもしれない。そう思った。
「よ!」
私の隣に座った山村くんが、私に声をかけてくる。そうだった、隣の席なんだった。
「よ?」
私も真似する。でも羞恥心が邪魔をして上手く出来なかった。
「まあ……とはいえさっきはありがとう」
それを聞いて彼は「お礼言うほどじゃない」と前置きした後、
「それに、こっちが謝ることだ」
そう、静かに言った。
「なんで貴方が謝る必要があるの?」
「そりゃあ俺の友達がデリカシーのないことを言ったからに決まってるだろ」
「でもそれは貴方が悪いわけじゃないじゃん」
「そうだな。でも謝って損なことはないだろ」
それに対して、「自分のため?」と返しておいた。
やっぱりこの人は不思議な人だ。だが、だからこその温もりもある。