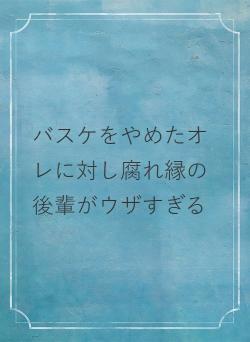「それでなんで死のうとしてたんだ?」
「……それは山村くんには関係ないでしょ」
「今ここで二人きりでいる時点で関係あるよ。俺ならいくらでも話聞くからさ」
「嫌だ。話したくない」
話す必要性が見えない。
どうせ甘えんなって言われるだけだし。
「まあそれは話したくなったらで良いよ。それで本題なんだけど……俺たち付き合わないか?」
付き合わない? なぜこの陽キャはこう言ってくるんだ。
いつも「可愛い」って言っている子と付き合えば良いじゃないか。
いや、そう言えば付き合っていたな。
まあ別れたって言っていたけど。
とはいえ、私なんかと付き合わなくても他に代わりはいるはずだ。クラスの中に何人も。
「私じゃあ釣り合わないと思う」
「ああ、俺じゃあまだ足りないってこと?」
「それって嫌み?」
どう考えてもすべての面でこの人の方が私よりも上だ。
釣り合わないのはどう考えても私の方だ。
「私はさあ、もう、どうでもいいのよ。全てが。勉強もできない、友達付き合いもよくない、家での立場も弱い、常に暗い気持ちの私に医者の息子で、クラスでもちやほやされてるあなたと釣り合うと思う? 私は絶対にそんなこと思わない。彼女が欲しいだけなら他の女子と付き合ったらいいじゃない!!」
言った後ではっと我に返り、怒鳴ったことを後悔した。
教えないって決めたはずなのに、どうして……
なぜ、私は怒ったんだろう。なあなあな会話をしようと思っただけなのに。
頬に水分を感じる。
何で泣いているんだろう、全てを諦めたはずなのに。
どうやら私は人の顔色を伺いすぎて、自分が分からなくなったらしい。
「泣いてもいいんだよ。ここにはお前を責めるようなやつはいない。お前をストレスの捌け口にするようなやつも」
「え?」
私はそんなこと彼にも、クラスメイトにも話したことがないはずだ。なぜ知っているんだろう。そう思ったらすぐに、
「カフェラテと、ハーブティーです」
店員さんが運んできてくれた。
「わ、いいにおい」
「だろ。ここおすすめなんだ」
「そうなんだ……」
「お前も、飲みたくなったら飲めよ。ここの紅茶とかカフェラテはコンビニとかのとは全然違うから」
「……うん」
不思議な包容力だ。こういうのを大人と言うんだろうか。
私と同じ年だというのを疑いたくなってしまう。神は二物を与えんと言うが、それは間違っていると思う。
私みたいに一物ももらえなかった人の代わりにこういう人が二物をもらえるんだ。この世は不公平だ。
いつもはクラスではしゃいでいるうるさいやつと言う印象しかなかったんだけど。
「まあでも……」
彼が口を開いた。
「冷めないうちに飲めよ。」
「うん」
そして、一口飲む。カフェラテの味全てが私の中に入ってくる。なんておいしいんだろう。こんなに美味しい物は飲んだことがない。
「な! おいしいだろ。つらい時にはおいしいもの飲んですっきりするほうがいいさ。人生100年。出来るだけ楽しい気分で痛いだろ」
「うん。そうだね」
私にはそんな時間はほぼ用意されてはいないけれど。家でも学校でも。
でも今は、今だけは少しだけ胸の痛みが晴れた気がする。
「俺、やっぱりお前を助けてよかったわ。お前やっぱりかわいいし」
「それ……セクハラじゃない?」
「いやー俺もいいことしたわ。お前を見殺しにしてたら世界の損だわ」
聞いてないし……でも。
「ありがとう」
「お、素直だな」
「だって、褒められることなんてほとんどなかったし」
「そうか。でも、これからはお前が自殺しないようにたくさん褒めてやる」
「ありがとう……まあ褒められが足りなくて自殺したわけじゃないけど」
「よーし、俺の本格的な目標が決まった! お前を幸せにする。そしてお前に生きることを選ばせてやる」
「ありがとう」
私にとってこの退屈な日常が終わるかもしれないというのは願ってもない話だ。これで明日にも少しだけ希望が見えてきた。
「そろそろ帰るか。じゃあまた明日な」
「うん、また明日」
とはいえ、これからまたあの地獄のような家に帰らないといけないのか。はあ、
「嫌だなあ」
そう、一言呟いた。
その後山村君に家に着いて来てもらった。
一人であの家に帰ることが少々気まずかった私にとっては願ってもない提案だった。
そしてその帰り道、私は彼と連絡先を交換した。
「これでいつでも連絡を取れるな」
「うん」
「しんどい時にはいつでも送ってくれ。愚痴位いつでも聞くから」
「ありがとう」
私はお礼を言った。
確かにいつでも愚痴を言えるという環境はありがたい。
いつもストレスを身に抱え、放出なんて学校の屋上から景色を見ることでしかできなかったのだから。
そんな事を言っている間に家までたどり着いた。
「じゃあ、また明日」
そう、笑って山村君は言った。
それに対し私も、「また明日」と笑顔で言った。
明日から、少しは楽しい事が起こりそうだ。