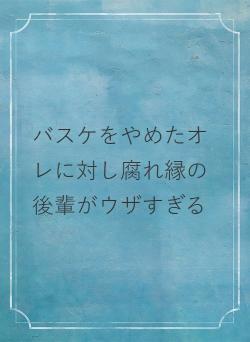翌日。
「おはよう愛香」
そんなことを言って茂くんは平然と私の部屋に入ってきた。二階の窓からこっそりと。
「何やってるの!?」
驚いた。まさか不法侵入してくるなんて。
「もしかして迷惑かけた判定?」
「判定に決まっているじゃん」
もし見つかったら怒られるのは完全に私だ。そもそも部屋に人が来ること自体うちの家からしたらアウトだ。
「まあでも、その分お前を楽しませるよ」
「楽しませるって言っても……」
「やっぱり見てられないし。これから二日間、愛香が悲しい顔してると思うとさ」
「ありがとう」
「どういたしまして」
なんやかんやいっても、ありがたい。
彼の引っ張る手は暖かくて、不思議な気持ちがする。
私は今悪い事をしているのだろう。
でも、彼と一緒にいると、罪悪感が無く、楽しさを感じる。
あとで怒られることは分かってると言うのに。
それよりもワクワク感が勝っているのだ。
「ここが俺の家だ」
「ここが……」
さすが医者の家といった所か、庭に池があり、岩が積まれていて、作るのにお金がかかったであろう事は一目でわかる。家も、大きな造りとなっていて、三階までありそうな家だ。
ここで茂君は何不自由無く暮らせていたんだなあと。
住む世界が違うなあという感想を抱いてしまう。
私とは違って……
「じゃあ入るか」
「うん……お邪魔……します」
そして恐る恐る入っていく。
「いらっしゃい」
と、4代後半くらいの見た目のおばさんが私を出迎えてくれた。茂くんのお母さんかな? まあ召使とか家政婦とかの可能性もあるけど。
とりあえず「お邪魔します」と、一言返し、茂くんについていく。すると彼女も私たちを追ってついてきた。
「母さん。大丈夫だって、俺がおもてなしするから」
「そんなこと言ったって、わたしだって息子の彼女に挨拶したいし」
それを聞いて、茂くんは「わかったよ」と言って、そのまま三人でリビングっぽい場所へ来た。
「ねえ」
「はい」
茂君のお母さんが話しかけてきた。要件は何なのだろうか。
「ねえ、あの子と上手くやれてる?」
「別に大丈夫です。むしろ優しいですし、私じゃあ釣り合わな……」
「釣り合わないとかいうんじゃねえよ。お前がいるだけで俺が助かってるしさ。俺の方が力をもらってるよ」
「うん」
茂君はいつも、私を褒めてくれる。
「これだったら信用できるわね。それで私にもできることない?」
「え?」
「私も話聞いたからさ。息子の彼女なんて私の娘みたいなものだから」
「ありがとう……ございます」
茂くんは「お母さんいいから」とか言っていたが、私はうれしい。
茂くんとかももちろんだが、お母さんみたいな存在にこんな言葉を受けるのはシンプルに嬉しい。
私のお母さんはお父さんの影響で常に機嫌悪いし。
「……私お父さんに虐待と言うか、常に瓶出されている生活を受けていて、最近つらいんです。しかも最近は茂君たちの影響で家以外が楽しくなってきていて、それが逆につらくて。私は別にお父さんの、あいつの子どもに好き好んで生まれたかったわけじゃないんです。なのに……なのに……」
私の悪い癖だ。優しくされたらもう私の全てをさらけ出してしまう。
こんな悪癖が付いたのは、私が普段優しくされ慣れてないからなのだろうか。
そんな中、私の頭に手の感触を感じた。その次の瞬間、手が優しく私の頭をなでてくれる。
それを感じ、頭上をふと見ると、茂くんのお母さんだった。
「え?」
「え? だめだった?」
茂くんのお母さんが私の言葉に反応し、分かりやすく戸惑う。違う、私はそんなつもりで言ったわけじゃないのに。
「ううん。私、優しくされるの慣れてなくて、その……うれしいです」
「私に今できるのはこれだけだからねえ、最近は茂も気軽に頭触らせてくれないし」
茂くんは「うるせえ。いいじゃねえか」と言っていたが、私の頭でいいならいくらでも差し出したい。むしろ私の方から差し出したいくらいだ。
親に頭をなでられた記憶なんてほとんどない。
あったとしても、所詮しょうもない話だ。つまるところ、感情のない一撫で、義務的な物だ。
でも、今の茂君のお母さんからはすごく深い愛情を感じた。絶対に息子の彼女だからと言う理由だけではないと思う。
ああ、私もこんな善人の子どもだったらなと思うが、今更こんなことを思っても仕方がない。
ああ、いいなあ、こういうの。これまで歴代最高の非を日々更新していたが、これも最高の人はいかないまでも、十分ないい日だ。
ああ、幸せだ。
そうこう考えていると、目から涙が流れてきた。私にも分からない涙が、いや、さっきから流れていたのかもしれない。私が気づかなかっただけで。
「ごめんなさい。私……涙が」
「いいのよ。そりゃあ泣いて当たり前だわ。そんな不条理な出来事を経験してきてたんだから」
「ありがとうございます」
この人に抱かれたい。そんな欲が出てきた。この人の前なら赤ちゃんにだってなれそう。
それは言い過ぎかもしれないが、本当に、好きだ。この人は。
「私、こういう親がよかったです」
私何を言っているんだろう、私は。
こんなこと言ったら迷惑かもしれないのに。
「あら嬉しいわね」
だか、美智子さんは優しく私をなでながらそう返してくれた。
「良かったな、愛香」
そう、茂君は私を見てそう言ってくれた。
「じゃあ、さてと、計画を立てるか」
「計画?」
私の涙が止まったころ、茂君が私に向かってそう言い放った。そうだった、彼は最初に出来ることはないかと言ったのだった。
おそらく今から私を解放する方法を考えてくれるのだろう。あのくそ両親から。
「まず、後期の試験で高得点を取ることだな……まあ模試でも良いけど」
「なんで?」
「そしたら出来る子だと認められて、少しは親の態度も変わるだろ」
勉強のことを言われて思わずうっとなる。確かに茂君のおかげで勉強は大分出来るようにはなってきたが、勉強にはやはり自信が無い。そもそも今までの勉強に対する怠惰をたったの三週間程度で取り返せるわけがないのだ。
だが、もし本当に茂君が言うとおりになる可能性があるなら、やってみる価値はある。
「そんな心配そうな顔すんな。俺が教えてやるから」
「うん」
ただ、彼がいる。それだけでなんとかなりそうな気もする。
「あとは、お父さん……」
「プリリュリュリュ」
私のスマホが鳴った。