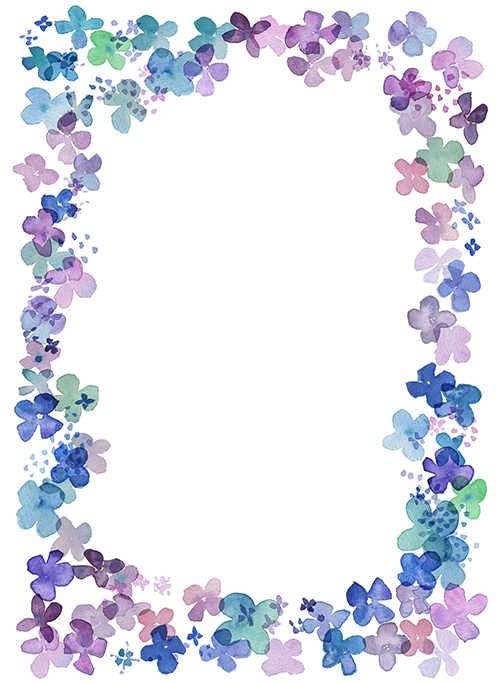一歩、その白い空間に足を踏み入れた瞬間、背後で扉が音もなく閉じた。しかし、もうそんなことはどうでもよかった。私の視線は、ただ一点、空間の中央で意識を失っているレイカさんの姿に釘付けになっていた。
私は彼女の元へと駆け寄った。近づくにつれて、彼女の様子がよりはっきりと見えてくる。穏やかな寝息一つ立てていない。ただ、深く、深く眠っているかのようだ。けれど、その頬には血の気が全くなく、触れたら氷のように冷たいのではないかと思わせるほどだった。
「レイカさん! しっかりして!」
私は彼女の肩を掴み、揺さぶった。しかし、何の反応も示さない。どうすればいい。どうすれば、彼女は目を覚ますんだ。
そうだ。あの偽物を倒した時のように。私の『想い』を、彼女にぶつけるんだ。
「ねえ、レイカさん! 聞いてる!?」私は彼女の耳元で叫んだ。「あなたが転校してきたせいで、私の日常はめちゃくちゃになったんだから!」
返事はない。けれど、私は構わずに続けた。
「でも……」声が、少し震えた。「あなたがいなくなってから、世界が、全然、面白くなくなった」
そうだ。それが、私の本心だった。
「誰も、私の名字に変なこじつけをして騒いだりしない。誰も、私の背後に霊がいるなんて馬鹿なこと言わない。誰も、私に気味の悪い弁当を突きつけてきたりしない」
平穏な日常。私が、あれほどまでに望んでいたはずの、静かな毎日。
「退屈で、退屈で、息が詰まりそうだった」
ぽろり、と私の目から熱い雫がこぼれ落ち、レイカさんの白いブラウスの上に小さな染みを作った。
「迷惑で、腹が立って、いなくなればいいって何度も思った。でも、いざ、あなたがいなくなったら……寂しいなんて、思ってる自分がいて」
もう、格好なんてつけていられなかった。私は机に突っ伏している彼女にしがみつくようにして、泣きじゃくった。
「だから、お願い……。目を、覚ましてよ、レイカ……っ」
私の最後の言葉が、その真っ白な空間に溶けていく。その、瞬間だった。
ゆっくりと、本当にゆっくりと、レイカさんの長い睫毛に縁取られた瞼が持ち上がった。現れたのは、黒曜石のような深い色の瞳。その瞳は、やがて目の前で泣いている私の姿を、はっきりと捉えた。
「……サ、ヤカ……?」かすれた、ほとんど空気のような声だった。けれど、それは紛れもなく、私の知っている西園寺レイカの声だった。「……なんで、あなたが、ここに……? それに、どうして、泣いているのです……?」
彼女は、状況が理解できていないのか、不思議そうに私を見つめている。そのいつもと変わらない、少しだけ呑気な表情を見て、私の涙腺は完全に決壊した。
「……っ、うわあああああん!」
私は子供のように声を上げて泣いた。安堵と、喜びと、これまでの全ての感情がごちゃ混ぜになって涙となって溢れ出す。そんな私を、レイカさんはただ、困ったような、それでいてどこか優しい眼差しで見つめていた。
二人の『認識』が、再び一つに揃った、その瞬間。
カチリ、と、この空間のどこかで小さな鍵が開くような音がした。次の瞬間、どこまでも白い空間が、まるで薄いガラスのようにぱりんと音を立てて砕け散る。視界が一瞬、真っ白な光に包まれ、次に目を開けた時、私たちは元の、あの乱雑な物置のような『お墓』の教室に戻っていた。
何も変わっていない。ただ、一つだけ、固く閉ざされていたはずの教室の扉が、わずかに開いている。そして、その隙間から、眩しい朝の光が一本の筋となって差し込んでいた。いつの間にか、長い、長い夜が明けていたのだ。
◇
「……どうやら、わたくし、とんでもないご迷惑を、おかけしてしまったようですわね」
朝日が差し込む教室の中で、レイカさんがぽつりと呟いた。彼女はまだ少し頭がぼんやりとしているようだったが、意識ははっきりしている。私が泣きながら断片的に状況を説明するのを、静かに聞いていた。
「迷惑なのは、いつものことでしょ」私はまだしゃくり上げながら、憎まれ口を叩いた。
「それにしても……。まさか、あの呪いがこれほど強力なものだったとは。私の見立てが、甘かったですわ」彼女は悔しそうに唇を噛んだ。「本来なら、席に触れた者だけが記憶を消され、異空間に閉じ込められるはず。ですが、サヤカがとっさに私を突き飛ばしたことで、呪いの効果が私たち二人に不完全に分散されてしまった……。私が『存在を消される』側、そして、サヤカが『私を忘れるための精神世界』に閉じ込められる側、として」
彼女は淡々と分析していく。その様子は、いつものオカルトマニアの彼女に戻りつつある証拠のようだった。
「ですが、そのおかげで呪いには僅かな綻びが生まれた。サヤカが、私とのあの強烈な記憶を頼りに偽物の世界を拒絶してくれたおかげで……わたくしはこうして、意識を取り戻すことができたのですわね」
彼女はそう言うと、私に向かって深く、深く頭を下げた。
「ありがとうございます、サヤカ。あなたに、命を救われましたわ」
「……別に、あなたのためじゃないし」私はそっぽを向いてぶっきらぼうに言った。「あなたがいないと、退屈だったから、仕方なく、助けに来てあげただけよ」
その言葉に、レイカさんは一瞬きょとんとしたが、やがてふわりと花が咲くように微笑んだ。それは、私が知っている、いつもの彼女の笑顔だった。
「……立てる?」
「ええ、なんとか」
私は彼女に手を貸し、その体を支えてやった。彼女の体はまだ少しふらついている。二人で支え合いながら、ゆっくりと教室の扉へと向かった。
もう、私の日常は、二度とあの退屈で平穏な日々には戻らないだろう。隣に、この歩く厄災がいる限りは。
けれど、不思議と、それは嫌ではなかった。
私たちは顔を見合わせて、小さく笑った。
私は彼女の元へと駆け寄った。近づくにつれて、彼女の様子がよりはっきりと見えてくる。穏やかな寝息一つ立てていない。ただ、深く、深く眠っているかのようだ。けれど、その頬には血の気が全くなく、触れたら氷のように冷たいのではないかと思わせるほどだった。
「レイカさん! しっかりして!」
私は彼女の肩を掴み、揺さぶった。しかし、何の反応も示さない。どうすればいい。どうすれば、彼女は目を覚ますんだ。
そうだ。あの偽物を倒した時のように。私の『想い』を、彼女にぶつけるんだ。
「ねえ、レイカさん! 聞いてる!?」私は彼女の耳元で叫んだ。「あなたが転校してきたせいで、私の日常はめちゃくちゃになったんだから!」
返事はない。けれど、私は構わずに続けた。
「でも……」声が、少し震えた。「あなたがいなくなってから、世界が、全然、面白くなくなった」
そうだ。それが、私の本心だった。
「誰も、私の名字に変なこじつけをして騒いだりしない。誰も、私の背後に霊がいるなんて馬鹿なこと言わない。誰も、私に気味の悪い弁当を突きつけてきたりしない」
平穏な日常。私が、あれほどまでに望んでいたはずの、静かな毎日。
「退屈で、退屈で、息が詰まりそうだった」
ぽろり、と私の目から熱い雫がこぼれ落ち、レイカさんの白いブラウスの上に小さな染みを作った。
「迷惑で、腹が立って、いなくなればいいって何度も思った。でも、いざ、あなたがいなくなったら……寂しいなんて、思ってる自分がいて」
もう、格好なんてつけていられなかった。私は机に突っ伏している彼女にしがみつくようにして、泣きじゃくった。
「だから、お願い……。目を、覚ましてよ、レイカ……っ」
私の最後の言葉が、その真っ白な空間に溶けていく。その、瞬間だった。
ゆっくりと、本当にゆっくりと、レイカさんの長い睫毛に縁取られた瞼が持ち上がった。現れたのは、黒曜石のような深い色の瞳。その瞳は、やがて目の前で泣いている私の姿を、はっきりと捉えた。
「……サ、ヤカ……?」かすれた、ほとんど空気のような声だった。けれど、それは紛れもなく、私の知っている西園寺レイカの声だった。「……なんで、あなたが、ここに……? それに、どうして、泣いているのです……?」
彼女は、状況が理解できていないのか、不思議そうに私を見つめている。そのいつもと変わらない、少しだけ呑気な表情を見て、私の涙腺は完全に決壊した。
「……っ、うわあああああん!」
私は子供のように声を上げて泣いた。安堵と、喜びと、これまでの全ての感情がごちゃ混ぜになって涙となって溢れ出す。そんな私を、レイカさんはただ、困ったような、それでいてどこか優しい眼差しで見つめていた。
二人の『認識』が、再び一つに揃った、その瞬間。
カチリ、と、この空間のどこかで小さな鍵が開くような音がした。次の瞬間、どこまでも白い空間が、まるで薄いガラスのようにぱりんと音を立てて砕け散る。視界が一瞬、真っ白な光に包まれ、次に目を開けた時、私たちは元の、あの乱雑な物置のような『お墓』の教室に戻っていた。
何も変わっていない。ただ、一つだけ、固く閉ざされていたはずの教室の扉が、わずかに開いている。そして、その隙間から、眩しい朝の光が一本の筋となって差し込んでいた。いつの間にか、長い、長い夜が明けていたのだ。
◇
「……どうやら、わたくし、とんでもないご迷惑を、おかけしてしまったようですわね」
朝日が差し込む教室の中で、レイカさんがぽつりと呟いた。彼女はまだ少し頭がぼんやりとしているようだったが、意識ははっきりしている。私が泣きながら断片的に状況を説明するのを、静かに聞いていた。
「迷惑なのは、いつものことでしょ」私はまだしゃくり上げながら、憎まれ口を叩いた。
「それにしても……。まさか、あの呪いがこれほど強力なものだったとは。私の見立てが、甘かったですわ」彼女は悔しそうに唇を噛んだ。「本来なら、席に触れた者だけが記憶を消され、異空間に閉じ込められるはず。ですが、サヤカがとっさに私を突き飛ばしたことで、呪いの効果が私たち二人に不完全に分散されてしまった……。私が『存在を消される』側、そして、サヤカが『私を忘れるための精神世界』に閉じ込められる側、として」
彼女は淡々と分析していく。その様子は、いつものオカルトマニアの彼女に戻りつつある証拠のようだった。
「ですが、そのおかげで呪いには僅かな綻びが生まれた。サヤカが、私とのあの強烈な記憶を頼りに偽物の世界を拒絶してくれたおかげで……わたくしはこうして、意識を取り戻すことができたのですわね」
彼女はそう言うと、私に向かって深く、深く頭を下げた。
「ありがとうございます、サヤカ。あなたに、命を救われましたわ」
「……別に、あなたのためじゃないし」私はそっぽを向いてぶっきらぼうに言った。「あなたがいないと、退屈だったから、仕方なく、助けに来てあげただけよ」
その言葉に、レイカさんは一瞬きょとんとしたが、やがてふわりと花が咲くように微笑んだ。それは、私が知っている、いつもの彼女の笑顔だった。
「……立てる?」
「ええ、なんとか」
私は彼女に手を貸し、その体を支えてやった。彼女の体はまだ少しふらついている。二人で支え合いながら、ゆっくりと教室の扉へと向かった。
もう、私の日常は、二度とあの退屈で平穏な日々には戻らないだろう。隣に、この歩く厄災がいる限りは。
けれど、不思議と、それは嫌ではなかった。
私たちは顔を見合わせて、小さく笑った。