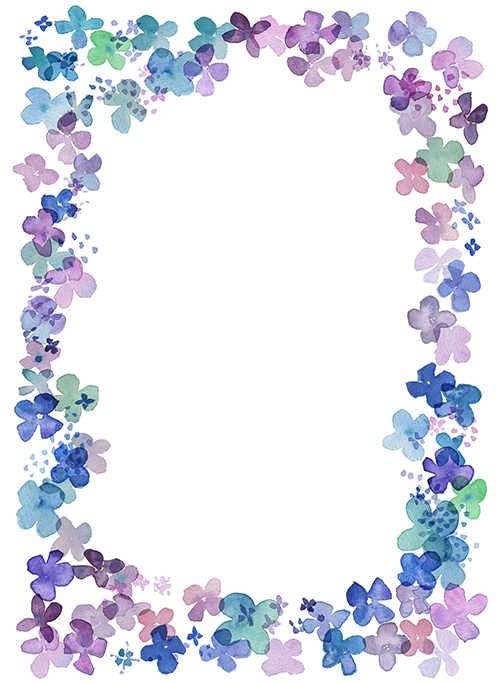私の額に伸ばされた、氷のように冷たい指先。目を閉じ、全てを受け入れようとした、まさにその刹那だった。
ぷつん、と。脳裏で、何かが弾けた。
予兆もなく、唐突に現れた光景。
――赤黒いケチャップで血糊のように彩られたご飯。その上に転がる、人間の指の形をしたソーセージ。爪にはアーモンドが埋め込まれ、横にはうずらの卵でできた無数の目玉がこちらを見つめている。
『コトリバコ弁当』。
西園寺レイカが、友情の証として、精魂込めて作り上げたあの悪夢の造形物。そのあまりにも冒涜的で悪趣味なビジュアルが、瞼の裏に鮮烈に蘇ったのだ。
「さあ、サヤカ。まずは一口、いかがです? あーん、ですわ」
あの時の、胃の底からせり上がってくる強烈な不快感。続けて、別の記憶がフラッシュバックする。夕日に照らされた住宅街と、それに添えられた忌まわしい一文。
『運命の友、サヤカさんの背後霊ですわ♡』
クラスメイトたちの嘲笑と好奇の視線。全身から血の気が引いていく冷たい屈辱と、腹の底で燃え上がった激しい怒り。さらに記憶は遡り、転校初日に教室中で高らかに宣言された、あの言葉。
「鮫島サヤカさん! あなたこそ、私が探し求めていた、たった一人の『運命の友』なのです!」
そうだ。西園寺レイカとの出会いから、私の毎日は常に迷惑と、困惑と、怒りと、屈辱に満ちていた。私の都合のいい、幻?私の孤独が生み出した、都合のいい、友人?
冗談じゃない。
こんなにも腹立たしい記憶が、自分の都合のいい幻想であるはずがないだろうが! 人間が、自分を慰めるために、こんなにも不快で胸糞の悪い記憶を、わざわざ好き好んで作り出すものか!
私の内側で、何かが確かな形を取り戻していく。それは、西園寺レイカという『厄災』に対する、純粋で正当な怒り。そして、その怒りこそが、彼女がこの世界に確かに存在したという、何よりも雄弁な証拠だった。
目の前の『それ』は、私の心の変化に気づいていないのか、冷たい笑みを浮かべたまま、私の額に指先をそっと触れさせようとしていた。
「さあ、全てを忘れなさい。そして、楽になるのです」
もう、その囁き声は私の心には届かなかった。私は、閉じていた瞼をカッと見開いた。
「ふざけないで」
自分でも驚くほど低く、冷たい声が出た。私は目の前の『それ』が伸ばしてきた手を、力いっぱい振り払う。パシン、と乾いた音が廊下に響き渡った。
『それ』の能面のような顔に、初めて亀裂が走る。焦点の合っていなかった瞳が、驚きに見開かれ、はっきりと私を捉えた。
「……何を、するのですか」その声には、わずかな動揺の色が滲んでいた。
「うるさい」私は一歩前に出た。
「あなたは、誰?」
「ですから、私は、西園寺れ……」
「違う!」私は彼女の言葉を遮った。「あなたは、西園寺レイカじゃない! 私の知ってるレイカさんは、もっと……もっと、迷惑な人だった!」
私は、堰を切ったように叫んでいた。頭に蘇る腹立たしい記憶を、感情のままに目の前の偽物へと叩きつけていく。
「転校初日に『鮫島事件の当事者ですね!』なんて決めつけたり、教室のど真ん中で『運命の友なのです!』なんて叫んだり! 勝手に撮った写真を心霊写真みたいに加工してネットに晒したり! そして極めつけは、あの弁当よ! コトリバコ弁当! 人の指とか目玉とか、よくもまあ、あんなグロテスクなものを嬉々として作れるわよね!」
私の怒涛の言葉を浴びて、偽物のレイカは明らかに狼狽していた。その姿はもはや、超越的な存在のそれではなかった。
「私の知ってるレイカさんは、自分の興味のためなら周りの迷惑なんて一切顧みない! 自分の信じる『真実』を、善意百パーセントで人に押し付けてくる! 常識が全く通用しない、とんでもないオカルトマニアで、歩く厄災みたいな、とんでもないお嬢様! それが、私の知ってる、西園寺レイカよ!」
そうだ。彼女は、そういう人間だった。迷惑で、腹立たしくて、理解不能で。けれど、彼女は、確かに、そこにいた。私の退屈な日常を、めちゃくちゃにかき乱していった。
「それに比べて、あなたは何?」私は目の前の偽物を冷ややかに見下ろした。「あなたはただ、私が、レイカさんのことを忘れて、諦めて、一人になるのを待ってただけでしょ。私の知ってるレイカさんは、こんな、陰気で、卑屈で、人の心の弱みに付け込むような、卑怯な真似は、絶対にしない!」
私の言葉が、とどめになったようだった。偽物のレイカの体がぐらりと揺れ、その顔に走った亀裂が一気に全身へと広がっていく。
「私の『運命の友』は、あなたなんかじゃない」
私は静かにそう告げた。その言葉は、私自身の心からの叫びだった。
迷惑で、腹立たしくて、いなくなればいいとさえ思った、あの少女。けれど、彼女がいないこの世界は、あまりにも色褪せていて、息苦しい。
私は、彼女に会いたい。本物の、西園寺レイカに。
私のその強い『想い』が、目の前の偽物の存在を完全に否定した。偽物のレイカは最期の苦悶の声を上げると、その体がぱりんと音を立てて砕け散る。無数の黒い蝶のような破片になって、それは闇の中へと吸い込まれるように消えていった。
後には、静まり返った薄暗い廊下だけが広がっていた。
先ほどまでの激しい怒りが嘘のように抜け落ち、後に残ったのはひどい疲労感と、何も解決していないという重たい現実だけだった。
偽物はいなくなった。けれど、本物のレイカはどこにいるのか。そんな得体の知れない不安が再び心に広がっていく。
その時だった。みしり、とどこかで何かが軋む音を皮切りに、私の周りの世界がゆっくりとその姿を変え始めた。目の前の廊下の風景が古い映像のようにちらつき、床の木目がぐにゃりと蠢く。キーンという耳鳴りと、不気味なざわめきが私の平衡感覚をかき乱していく。
これが、呪いが作り出した偽りの世界の、最期の断末魔なのだろうか。
しかし、不思議と恐怖はなかった。私の心の中には、ただ一つの確かな想いだけが、燃え盛る炎のように輝いていた。
レイカさんに、会いたい。
本物の、あの、迷惑で、腹立たしくて、常識の通じない、私の『運命の友』に。
その想いだけを道標に、私は一歩、また一歩と前へ進んだ。目指す場所は分かっていた。この偽りの世界の中心。全ての始まりの場所。北校舎三階、一番奥の、あの空き教室。『お墓』。
やがて、私の目の前に一つの扉が現れた。他の風景がどれだけ歪み、崩れ落ちても、その扉だけは確かな形を保ってそこに存在していた。私はその扉に手をかけたが、びくともしない。何か見えない力で固く封じられているのが肌で感じられた。
「レイカさん!」私は扉に向かって叫んだ。「いるんでしょ!? そこにいるなら返事をして!」
返事はない。しかし、分かる。彼女はこの向こうにいる。何の根拠もない、確信があった。
「開けてよ! 私よ、サヤカよ! あなたが勝手に『運命の友』に指名した、鮫島サヤカが、迎えに来たんだから!」
心の底からそう叫んだ、その瞬間だった。
ごとり、と扉の向こう側から何かが倒れるような小さな音がした。そして、私が手をかけていた扉が、ぎ、ぎぎ……と重たい音を立て、ゆっくりと内側へと開いていったのだ。
隙間から、白い光が洪水のように溢れ出してくる。私はその眩しさに目を細め、意を決して扉の向こう側を覗き込んだ。
その光景に、私は息を呑んだ。
そこは、私が知っている乱雑な物置のような『お墓』ではなかった。どこまでも、どこまでも、真っ白な空間が広がっている。床も、壁も、天井も、全てが継ぎ目のない純白の素材でできていた。
そして、そのだだっ広い空間のど真ん中に、ぽつんと一つだけ、あの『決して座ってはいけない席』が置かれていた。
その椅子に、一人の少女が座っていた。
長い、艶やかな黒髪。白いブラウスと、チェックのスカート。紛れもなく、西園寺レイカさんだった。彼女は机に突っ伏すようにしてぐったりと意識を失い、その顔色は紙のように白い。まるで精巧に作られた、眠り姫の人形のようだ。
「……レイカさん」
私の口から、かすれた声が漏れた。いた。本当に、いたんだ。
安堵と、こみ上げてくる強い感情に突き動かされるようにして、私はその真っ白な空間へと、足を踏み入れた。
ぷつん、と。脳裏で、何かが弾けた。
予兆もなく、唐突に現れた光景。
――赤黒いケチャップで血糊のように彩られたご飯。その上に転がる、人間の指の形をしたソーセージ。爪にはアーモンドが埋め込まれ、横にはうずらの卵でできた無数の目玉がこちらを見つめている。
『コトリバコ弁当』。
西園寺レイカが、友情の証として、精魂込めて作り上げたあの悪夢の造形物。そのあまりにも冒涜的で悪趣味なビジュアルが、瞼の裏に鮮烈に蘇ったのだ。
「さあ、サヤカ。まずは一口、いかがです? あーん、ですわ」
あの時の、胃の底からせり上がってくる強烈な不快感。続けて、別の記憶がフラッシュバックする。夕日に照らされた住宅街と、それに添えられた忌まわしい一文。
『運命の友、サヤカさんの背後霊ですわ♡』
クラスメイトたちの嘲笑と好奇の視線。全身から血の気が引いていく冷たい屈辱と、腹の底で燃え上がった激しい怒り。さらに記憶は遡り、転校初日に教室中で高らかに宣言された、あの言葉。
「鮫島サヤカさん! あなたこそ、私が探し求めていた、たった一人の『運命の友』なのです!」
そうだ。西園寺レイカとの出会いから、私の毎日は常に迷惑と、困惑と、怒りと、屈辱に満ちていた。私の都合のいい、幻?私の孤独が生み出した、都合のいい、友人?
冗談じゃない。
こんなにも腹立たしい記憶が、自分の都合のいい幻想であるはずがないだろうが! 人間が、自分を慰めるために、こんなにも不快で胸糞の悪い記憶を、わざわざ好き好んで作り出すものか!
私の内側で、何かが確かな形を取り戻していく。それは、西園寺レイカという『厄災』に対する、純粋で正当な怒り。そして、その怒りこそが、彼女がこの世界に確かに存在したという、何よりも雄弁な証拠だった。
目の前の『それ』は、私の心の変化に気づいていないのか、冷たい笑みを浮かべたまま、私の額に指先をそっと触れさせようとしていた。
「さあ、全てを忘れなさい。そして、楽になるのです」
もう、その囁き声は私の心には届かなかった。私は、閉じていた瞼をカッと見開いた。
「ふざけないで」
自分でも驚くほど低く、冷たい声が出た。私は目の前の『それ』が伸ばしてきた手を、力いっぱい振り払う。パシン、と乾いた音が廊下に響き渡った。
『それ』の能面のような顔に、初めて亀裂が走る。焦点の合っていなかった瞳が、驚きに見開かれ、はっきりと私を捉えた。
「……何を、するのですか」その声には、わずかな動揺の色が滲んでいた。
「うるさい」私は一歩前に出た。
「あなたは、誰?」
「ですから、私は、西園寺れ……」
「違う!」私は彼女の言葉を遮った。「あなたは、西園寺レイカじゃない! 私の知ってるレイカさんは、もっと……もっと、迷惑な人だった!」
私は、堰を切ったように叫んでいた。頭に蘇る腹立たしい記憶を、感情のままに目の前の偽物へと叩きつけていく。
「転校初日に『鮫島事件の当事者ですね!』なんて決めつけたり、教室のど真ん中で『運命の友なのです!』なんて叫んだり! 勝手に撮った写真を心霊写真みたいに加工してネットに晒したり! そして極めつけは、あの弁当よ! コトリバコ弁当! 人の指とか目玉とか、よくもまあ、あんなグロテスクなものを嬉々として作れるわよね!」
私の怒涛の言葉を浴びて、偽物のレイカは明らかに狼狽していた。その姿はもはや、超越的な存在のそれではなかった。
「私の知ってるレイカさんは、自分の興味のためなら周りの迷惑なんて一切顧みない! 自分の信じる『真実』を、善意百パーセントで人に押し付けてくる! 常識が全く通用しない、とんでもないオカルトマニアで、歩く厄災みたいな、とんでもないお嬢様! それが、私の知ってる、西園寺レイカよ!」
そうだ。彼女は、そういう人間だった。迷惑で、腹立たしくて、理解不能で。けれど、彼女は、確かに、そこにいた。私の退屈な日常を、めちゃくちゃにかき乱していった。
「それに比べて、あなたは何?」私は目の前の偽物を冷ややかに見下ろした。「あなたはただ、私が、レイカさんのことを忘れて、諦めて、一人になるのを待ってただけでしょ。私の知ってるレイカさんは、こんな、陰気で、卑屈で、人の心の弱みに付け込むような、卑怯な真似は、絶対にしない!」
私の言葉が、とどめになったようだった。偽物のレイカの体がぐらりと揺れ、その顔に走った亀裂が一気に全身へと広がっていく。
「私の『運命の友』は、あなたなんかじゃない」
私は静かにそう告げた。その言葉は、私自身の心からの叫びだった。
迷惑で、腹立たしくて、いなくなればいいとさえ思った、あの少女。けれど、彼女がいないこの世界は、あまりにも色褪せていて、息苦しい。
私は、彼女に会いたい。本物の、西園寺レイカに。
私のその強い『想い』が、目の前の偽物の存在を完全に否定した。偽物のレイカは最期の苦悶の声を上げると、その体がぱりんと音を立てて砕け散る。無数の黒い蝶のような破片になって、それは闇の中へと吸い込まれるように消えていった。
後には、静まり返った薄暗い廊下だけが広がっていた。
先ほどまでの激しい怒りが嘘のように抜け落ち、後に残ったのはひどい疲労感と、何も解決していないという重たい現実だけだった。
偽物はいなくなった。けれど、本物のレイカはどこにいるのか。そんな得体の知れない不安が再び心に広がっていく。
その時だった。みしり、とどこかで何かが軋む音を皮切りに、私の周りの世界がゆっくりとその姿を変え始めた。目の前の廊下の風景が古い映像のようにちらつき、床の木目がぐにゃりと蠢く。キーンという耳鳴りと、不気味なざわめきが私の平衡感覚をかき乱していく。
これが、呪いが作り出した偽りの世界の、最期の断末魔なのだろうか。
しかし、不思議と恐怖はなかった。私の心の中には、ただ一つの確かな想いだけが、燃え盛る炎のように輝いていた。
レイカさんに、会いたい。
本物の、あの、迷惑で、腹立たしくて、常識の通じない、私の『運命の友』に。
その想いだけを道標に、私は一歩、また一歩と前へ進んだ。目指す場所は分かっていた。この偽りの世界の中心。全ての始まりの場所。北校舎三階、一番奥の、あの空き教室。『お墓』。
やがて、私の目の前に一つの扉が現れた。他の風景がどれだけ歪み、崩れ落ちても、その扉だけは確かな形を保ってそこに存在していた。私はその扉に手をかけたが、びくともしない。何か見えない力で固く封じられているのが肌で感じられた。
「レイカさん!」私は扉に向かって叫んだ。「いるんでしょ!? そこにいるなら返事をして!」
返事はない。しかし、分かる。彼女はこの向こうにいる。何の根拠もない、確信があった。
「開けてよ! 私よ、サヤカよ! あなたが勝手に『運命の友』に指名した、鮫島サヤカが、迎えに来たんだから!」
心の底からそう叫んだ、その瞬間だった。
ごとり、と扉の向こう側から何かが倒れるような小さな音がした。そして、私が手をかけていた扉が、ぎ、ぎぎ……と重たい音を立て、ゆっくりと内側へと開いていったのだ。
隙間から、白い光が洪水のように溢れ出してくる。私はその眩しさに目を細め、意を決して扉の向こう側を覗き込んだ。
その光景に、私は息を呑んだ。
そこは、私が知っている乱雑な物置のような『お墓』ではなかった。どこまでも、どこまでも、真っ白な空間が広がっている。床も、壁も、天井も、全てが継ぎ目のない純白の素材でできていた。
そして、そのだだっ広い空間のど真ん中に、ぽつんと一つだけ、あの『決して座ってはいけない席』が置かれていた。
その椅子に、一人の少女が座っていた。
長い、艶やかな黒髪。白いブラウスと、チェックのスカート。紛れもなく、西園寺レイカさんだった。彼女は机に突っ伏すようにしてぐったりと意識を失い、その顔色は紙のように白い。まるで精巧に作られた、眠り姫の人形のようだ。
「……レイカさん」
私の口から、かすれた声が漏れた。いた。本当に、いたんだ。
安堵と、こみ上げてくる強い感情に突き動かされるようにして、私はその真っ白な空間へと、足を踏み入れた。