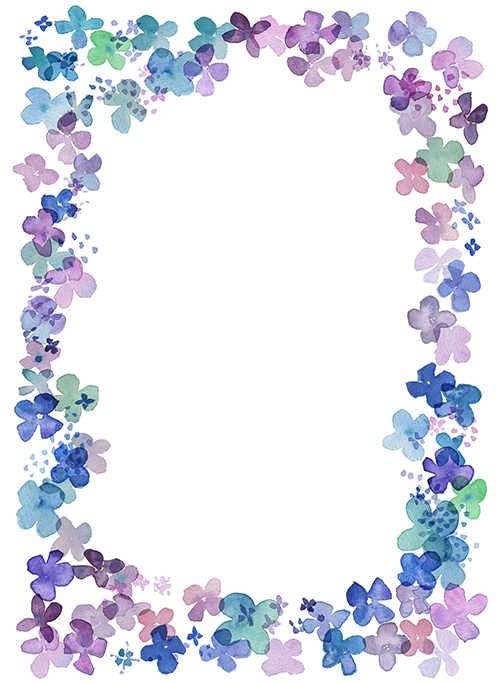どれくらい、そうしていただろうか。
私は、放課後の、誰もいない南校舎の廊下の真ん中で、ただ、立ち尽くしていた。日はとっくに傾き、窓から差し込む光は、頼りないオレンジ色から、やがて深い藍色へとその姿を変えていく。床に伸びた自分の姿も、徐々にその形を失い、周囲の闇に溶け込んでいくようだった。
運動部の掛け声も、吹奏楽部の楽器の音も、もう聞こえない。完全な静寂が、この校舎を支配していた。その静けさが、私の孤独を、まるで分厚い壁のように、じわじわと締め付けてくる。
西園寺レイカは、いなかった。
最初から、この世界に、存在などしていなかった。
クラスメイトも、先生も、誰も彼女を覚えていない。出席簿にも、私のスマートフォンの履歴にも、彼女が生きていた痕跡は、どこにもない。
あるのは、私の、この頭の中にある、あまりにも鮮明で、色鮮やかな記憶だけ。
迷惑だった。腹立たしかった。腹の底から、怒りが湧き上がってくるような、そんな出来事ばかりだった。
なのに。
どうして、彼女がいないこの世界は、こんなにも、息苦しいのだろう。
どうして、私の胸には、こんなにも大きな穴が、ぽっかりと空いてしまっているのだろう。
もしかしたら、本当に、おかしいのは、私の方なのかもしれない。
友人たちが言ったように、私は、少し疲れているだけなのかもしれない。そして、その疲れが、西園寺レイカという、都合のいい、非日常的な友人を生み出してしまったのかもしれない。私の退屈な日常を、めちゃくちゃにかき乱してくれる、迷惑で、手のかかる、けれど、決して私を一人にはしない、幻の友人を。
その考えは、あまりにも恐ろしく、そして、妙な説得力を持って、私の心を蝕んでいく。
自分の足元が、ぐらぐらと揺れているような感覚。自分の存在そのものが、不確かなものになっていくような、言いようのない不安。
もう、何も信じられない。自分の記憶さえも。
私は、力なく、その場に座り込んだ。冷たい廊下の床の感触が、制服のスカート越しに、じわりと伝わってくる。
もう、どうでもいいか。
家に帰って、温かいお風呂に入って、ベッドで眠ってしまえば、明日には、全て元通りになっているかもしれない。西園寺レイカなんていう、奇妙な幻の記憶も、綺麗さっぱり消え去って。そして、また、あの退屈で、平穏な、一人きりの日常が戻ってくる。
それで、いいじゃないか。
私は、そう、自分に言い聞かせようとした。
その時だった。
こつん、と。
静まり返った廊下の向こう側から、一つの、硬い音が聞こえた。
誰かが、歩いている。
こんな時間に、まだ誰か残っていたのか。用務員さんか、あるいは、見回りの先生か。
私は、慌てて立ち上がろうとした。こんな場所で座り込んでいるのを見られたら、何を言われるか分からない。
しかし、私の体は、まるで床に縫い付けられたかのように、動かなかった。
こつん、こつん、と、その足音は、一定のリズムを保ったまま、ゆっくりと、しかし確実に、こちらに近づいてくる。それは、教師の履くようなスリッパの音ではない。革靴の、硬いヒールが、床を叩く音だ。
そして、その姿が、廊下の角から、ぬっと現れた。
その瞬間、私は、息をすることを忘れた。
「……レイカ、さん?」
私の口から、かすれた声が漏れた。
そこに立っていたのは、西園寺レイカさんだった。
艶のある長い黒髪。指定の制服を、寸分の隙もなく着こなした、完璧な立ち姿。薄暗い廊下の中でも、彼女の存在は、まるでそこだけが明るく照らし出されているかのように、際立って見えた。
どうして。
なんで、ここに。
誰も、あなたのことを覚えていなかったはずじゃ。
私の頭の中は、疑問符で埋め尽くされる。しかし、それと同時に、安堵にも似た、温かい感情が、胸の奥から込み上げてくるのを感じた。
ああ、よかった。
やっぱり、彼女は、いたんだ。私の記憶は、間違っていなかった。
私は、彼女に駆け寄ろうとして、一歩、足を踏み出した。
だが、その足は、ぴたりと、止まった。
何かが、おかしい。
目の前にいる彼女は、確かに、西園寺レイカさんのはずなのに。
どこか、違う。
何が違うのか、すぐには分からなかった。けれど、私の本能が、けたたましく警鐘を鳴らしていた。
目の前にいる『それ』は、私の知っている西園寺レイカではない、と。
彼女は、ただ、そこに立っているだけだった。私を見ても、何の反応も示さない。いつもなら、私を見つけた瞬間に、花が咲くような笑顔を浮かべて、「サヤカ!」と、嬉しそうに駆け寄ってくるはずなのに。
その表情。
そうだ、表情が、ないのだ。
彼女の美しい顔は、まるで、精巧に作られた能面のようだった。喜怒哀楽、その全ての感情が、綺麗に削ぎ落とされている。その瞳は、私を映しているはずなのに、どこか、焦点が合っていない。まるで、分厚いガラスの向こう側から、こちらを眺めているかのようだ。
そして、その声。
「……何か、用ですか?」
ようやく発せられたその声は、私の知っている、鈴の鳴るような、涼やかで、けれど温かみのある声ではなかった。
それは、まるで、機械が合成したかのような、抑揚のない、無機質な音の響きだった。人間的な温かみが、全く、含まれていない。
全身の毛が、ぶわりと逆立つのが分かった。
目の前にいるのは、西園寺レイカの姿をした、何か別の、得体の知れないナニカだ。
「あなた……誰?」
私の口から、震える声が漏れた。
その問いに、『それ』は、わずかに、こてん、と首を傾げた。その動きもまた、どこか人間離れしていて、ぎこちない。
「私は、西園寺レイカです。」
「嘘よ! あなたは、レイカさんじゃない!」
「どうして、そう思うのですか?」
「だって、声も、表情も、全然違う! レイカさんは、もっと、うるさくて、迷惑で、人の話を聞かなくて……でも、もっと、人間らしい人だった!」
私の必死の叫びにも、『それ』は、全く動じる様子を見せなかった。その能面のような顔は、ただ、静かに、私を見つめている。
「人間らしい、とは、どういうことですか?」
「とぼけないで! あなたは、一体、何なの!?」
私が一歩後ずさると、『それ』は、ゆっくりと、一歩、こちらに近づいてきた。その動きに合わせて、私の心臓が、大きく跳ねる。
「私は、あなたを、助けに来ました」
その声は、相変わらず無機質だったが、その言葉の内容は、私の混乱を、さらに加速させた。
助けに?
何を、言っているんだ?
「あなたは、今、とても混乱している。あなたの頭の中は、存在しない人間の、偽りの記憶で、満たされています」
偽りの、記憶。
その言葉に、私は、はっとした。
「西園寺レイカという、派手で、風変わりで、あなたの退屈な日常を壊してくれる、都合のいい友人。そんな人間は、最初から、どこにも存在しませんでした」
『それ』の言葉は、まるで、私の心の中を、全て見透かしているかのようだった。
私が、先ほどまで、一人で抱えていた、あの恐ろしい疑念。
それを、目の前のナニカは、こともなげに、肯定してみせた。
「違う……! 彼女は、いた! 確かに、いたんだ!」
「では、どうして、誰も彼女のことを覚えていないのですか? どうして、あなたのスマートフォンのどこにも、彼女の痕跡は残っていないのですか?」
『それ』は、淡々と、事実を突きつけてくる。その一つ一つが、鋭い刃物のように、私の自信を、少しずつ、削り取っていく。
「それは……何かの、呪いか何かで……」
「呪い? 随分と非合理的ですね。あなたは、そういうものを嫌っていたのでは?」
その言葉に、私は、ぐっと、息を詰まらせた。
そうだ。私は、オカルトなんて信じていなかった。非科学的なものは、全て、馬鹿馬鹿しい作り話だと思っていた。
なのに、今、私は、その非科学的な『呪い』に、必死に、しがみつこうとしている。
そうでもしないと、自分の正気が、保てそうになかったからだ。
「おかしいのは、世界ではありません」
『それ』は、さらに一歩、こちらに近づいた。私と、そのナニカとの距離は、もう、手を伸ばせば届くほどに、縮まっていた。
ふわりと、あの、品のいい花の香りがした。
レイカさんの、香りだ。
その香りが、この状況の異常さを、さらに際立たせていた。
「おかしいのは、あなたの、その記憶なのです」
その声は、囁きかけるように、優しく、そして、冷たかった。
「あなたは、寂しかったのでしょう。変化のない、退屈な毎日に、うんざりしていた。誰かに、その日常を、壊してほしかった。だから、あなたは、作り出した。西園寺レイカという、理想の……いいえ、あなたにとって、最も都合のいい、存在を」
違う。
違う、違う、違う。
私が、そんなことを、望むはずがない。
私は、平穏を、愛していたはずだ。
「本当に、そうですか?」
『それ』は、私の心を読んだかのように、そう問いかけた。
「あなたは、心のどこかで、退屈していた。刺激を、求めていた。だから、あなたの無意識は、あなたにぴったりの友人を、作り上げてみせたのです。あなたの名字に、特別な意味を見出し、一方的に『運命の友』だと騒ぎ立て、あなたを無視して、あなたを振り回す、美しいお嬢様を」
その言葉は、あまりにも、的確に、私の心の、一番柔らかい部分を、抉ってきた。
そうだ。私は、退屈していたのかもしれない。
レイカさんが現れてからの毎日は、確かに、迷惑で、腹立たしいことばかりだったけれど。
けれど、退屈では、なかった。
一日一日が、予測不能な出来事で、満ち溢れていた。
私は、その刺激に、心のどこかで、喜びを、感じてしまっていたのでは、ないだろうか。
「認めなさい」
『それ』は、すっと、その白い手を、私の頬に、伸ばしてきた。
その手つきは、ひどく、優しかった。
けれど、その指先は、氷のように、冷たかった。
「西園寺レイカは、あなたの孤独が生み出した、都合のいい、幻なのだと」
その言葉が、とどめだった。
私の足元が、ぐらり、と、大きく揺れた。
世界が、反転するような感覚。
そうだ。
そうだったのかもしれない。
私が、間違っていたんだ。
レイカさんなんて、最初から、いなかったんだ。
全て、私の、見ていた、長い、長い、夢だったんだ。
そう、認めてしまえば、どれだけ、楽になれるだろう。
この、世界と自分との間に生じた、致命的なズレから、解放される。
私は、ただの、少しだけ夢見がちな、普通の女子高生に戻れるのだ。
「それで、よいのです」
『それ』は、私の表情の変化を読み取ったのか、満足げに、頷いた。
その能面のような顔に、初めて、かすかな、笑みのようなものが、浮かんだように見えた。
それは、勝利を確信した者の、冷たい、冷たい、笑みだった。
「さあ、サヤカ。その辛い、偽りの記憶をすべて断ち切ってください」
『それ』は、私の頬を撫でていた手を、ゆっくりと、私の額へと、移動させた。
その指先が、私の前髪を、優しくかき分ける。
もう、抵抗する気力は、なかった。
私は、ただ、されるがままに、そのナニカの前に、立ち尽くしていた。
目を、閉じる。
これで、全てが、終わる。
私の、短くも、騒がしい、非日常が。
さようなら、レイカさん。
私の、幻の、友人。
心の中で、そう、呟いた、その瞬間だった。
私は、放課後の、誰もいない南校舎の廊下の真ん中で、ただ、立ち尽くしていた。日はとっくに傾き、窓から差し込む光は、頼りないオレンジ色から、やがて深い藍色へとその姿を変えていく。床に伸びた自分の姿も、徐々にその形を失い、周囲の闇に溶け込んでいくようだった。
運動部の掛け声も、吹奏楽部の楽器の音も、もう聞こえない。完全な静寂が、この校舎を支配していた。その静けさが、私の孤独を、まるで分厚い壁のように、じわじわと締め付けてくる。
西園寺レイカは、いなかった。
最初から、この世界に、存在などしていなかった。
クラスメイトも、先生も、誰も彼女を覚えていない。出席簿にも、私のスマートフォンの履歴にも、彼女が生きていた痕跡は、どこにもない。
あるのは、私の、この頭の中にある、あまりにも鮮明で、色鮮やかな記憶だけ。
迷惑だった。腹立たしかった。腹の底から、怒りが湧き上がってくるような、そんな出来事ばかりだった。
なのに。
どうして、彼女がいないこの世界は、こんなにも、息苦しいのだろう。
どうして、私の胸には、こんなにも大きな穴が、ぽっかりと空いてしまっているのだろう。
もしかしたら、本当に、おかしいのは、私の方なのかもしれない。
友人たちが言ったように、私は、少し疲れているだけなのかもしれない。そして、その疲れが、西園寺レイカという、都合のいい、非日常的な友人を生み出してしまったのかもしれない。私の退屈な日常を、めちゃくちゃにかき乱してくれる、迷惑で、手のかかる、けれど、決して私を一人にはしない、幻の友人を。
その考えは、あまりにも恐ろしく、そして、妙な説得力を持って、私の心を蝕んでいく。
自分の足元が、ぐらぐらと揺れているような感覚。自分の存在そのものが、不確かなものになっていくような、言いようのない不安。
もう、何も信じられない。自分の記憶さえも。
私は、力なく、その場に座り込んだ。冷たい廊下の床の感触が、制服のスカート越しに、じわりと伝わってくる。
もう、どうでもいいか。
家に帰って、温かいお風呂に入って、ベッドで眠ってしまえば、明日には、全て元通りになっているかもしれない。西園寺レイカなんていう、奇妙な幻の記憶も、綺麗さっぱり消え去って。そして、また、あの退屈で、平穏な、一人きりの日常が戻ってくる。
それで、いいじゃないか。
私は、そう、自分に言い聞かせようとした。
その時だった。
こつん、と。
静まり返った廊下の向こう側から、一つの、硬い音が聞こえた。
誰かが、歩いている。
こんな時間に、まだ誰か残っていたのか。用務員さんか、あるいは、見回りの先生か。
私は、慌てて立ち上がろうとした。こんな場所で座り込んでいるのを見られたら、何を言われるか分からない。
しかし、私の体は、まるで床に縫い付けられたかのように、動かなかった。
こつん、こつん、と、その足音は、一定のリズムを保ったまま、ゆっくりと、しかし確実に、こちらに近づいてくる。それは、教師の履くようなスリッパの音ではない。革靴の、硬いヒールが、床を叩く音だ。
そして、その姿が、廊下の角から、ぬっと現れた。
その瞬間、私は、息をすることを忘れた。
「……レイカ、さん?」
私の口から、かすれた声が漏れた。
そこに立っていたのは、西園寺レイカさんだった。
艶のある長い黒髪。指定の制服を、寸分の隙もなく着こなした、完璧な立ち姿。薄暗い廊下の中でも、彼女の存在は、まるでそこだけが明るく照らし出されているかのように、際立って見えた。
どうして。
なんで、ここに。
誰も、あなたのことを覚えていなかったはずじゃ。
私の頭の中は、疑問符で埋め尽くされる。しかし、それと同時に、安堵にも似た、温かい感情が、胸の奥から込み上げてくるのを感じた。
ああ、よかった。
やっぱり、彼女は、いたんだ。私の記憶は、間違っていなかった。
私は、彼女に駆け寄ろうとして、一歩、足を踏み出した。
だが、その足は、ぴたりと、止まった。
何かが、おかしい。
目の前にいる彼女は、確かに、西園寺レイカさんのはずなのに。
どこか、違う。
何が違うのか、すぐには分からなかった。けれど、私の本能が、けたたましく警鐘を鳴らしていた。
目の前にいる『それ』は、私の知っている西園寺レイカではない、と。
彼女は、ただ、そこに立っているだけだった。私を見ても、何の反応も示さない。いつもなら、私を見つけた瞬間に、花が咲くような笑顔を浮かべて、「サヤカ!」と、嬉しそうに駆け寄ってくるはずなのに。
その表情。
そうだ、表情が、ないのだ。
彼女の美しい顔は、まるで、精巧に作られた能面のようだった。喜怒哀楽、その全ての感情が、綺麗に削ぎ落とされている。その瞳は、私を映しているはずなのに、どこか、焦点が合っていない。まるで、分厚いガラスの向こう側から、こちらを眺めているかのようだ。
そして、その声。
「……何か、用ですか?」
ようやく発せられたその声は、私の知っている、鈴の鳴るような、涼やかで、けれど温かみのある声ではなかった。
それは、まるで、機械が合成したかのような、抑揚のない、無機質な音の響きだった。人間的な温かみが、全く、含まれていない。
全身の毛が、ぶわりと逆立つのが分かった。
目の前にいるのは、西園寺レイカの姿をした、何か別の、得体の知れないナニカだ。
「あなた……誰?」
私の口から、震える声が漏れた。
その問いに、『それ』は、わずかに、こてん、と首を傾げた。その動きもまた、どこか人間離れしていて、ぎこちない。
「私は、西園寺レイカです。」
「嘘よ! あなたは、レイカさんじゃない!」
「どうして、そう思うのですか?」
「だって、声も、表情も、全然違う! レイカさんは、もっと、うるさくて、迷惑で、人の話を聞かなくて……でも、もっと、人間らしい人だった!」
私の必死の叫びにも、『それ』は、全く動じる様子を見せなかった。その能面のような顔は、ただ、静かに、私を見つめている。
「人間らしい、とは、どういうことですか?」
「とぼけないで! あなたは、一体、何なの!?」
私が一歩後ずさると、『それ』は、ゆっくりと、一歩、こちらに近づいてきた。その動きに合わせて、私の心臓が、大きく跳ねる。
「私は、あなたを、助けに来ました」
その声は、相変わらず無機質だったが、その言葉の内容は、私の混乱を、さらに加速させた。
助けに?
何を、言っているんだ?
「あなたは、今、とても混乱している。あなたの頭の中は、存在しない人間の、偽りの記憶で、満たされています」
偽りの、記憶。
その言葉に、私は、はっとした。
「西園寺レイカという、派手で、風変わりで、あなたの退屈な日常を壊してくれる、都合のいい友人。そんな人間は、最初から、どこにも存在しませんでした」
『それ』の言葉は、まるで、私の心の中を、全て見透かしているかのようだった。
私が、先ほどまで、一人で抱えていた、あの恐ろしい疑念。
それを、目の前のナニカは、こともなげに、肯定してみせた。
「違う……! 彼女は、いた! 確かに、いたんだ!」
「では、どうして、誰も彼女のことを覚えていないのですか? どうして、あなたのスマートフォンのどこにも、彼女の痕跡は残っていないのですか?」
『それ』は、淡々と、事実を突きつけてくる。その一つ一つが、鋭い刃物のように、私の自信を、少しずつ、削り取っていく。
「それは……何かの、呪いか何かで……」
「呪い? 随分と非合理的ですね。あなたは、そういうものを嫌っていたのでは?」
その言葉に、私は、ぐっと、息を詰まらせた。
そうだ。私は、オカルトなんて信じていなかった。非科学的なものは、全て、馬鹿馬鹿しい作り話だと思っていた。
なのに、今、私は、その非科学的な『呪い』に、必死に、しがみつこうとしている。
そうでもしないと、自分の正気が、保てそうになかったからだ。
「おかしいのは、世界ではありません」
『それ』は、さらに一歩、こちらに近づいた。私と、そのナニカとの距離は、もう、手を伸ばせば届くほどに、縮まっていた。
ふわりと、あの、品のいい花の香りがした。
レイカさんの、香りだ。
その香りが、この状況の異常さを、さらに際立たせていた。
「おかしいのは、あなたの、その記憶なのです」
その声は、囁きかけるように、優しく、そして、冷たかった。
「あなたは、寂しかったのでしょう。変化のない、退屈な毎日に、うんざりしていた。誰かに、その日常を、壊してほしかった。だから、あなたは、作り出した。西園寺レイカという、理想の……いいえ、あなたにとって、最も都合のいい、存在を」
違う。
違う、違う、違う。
私が、そんなことを、望むはずがない。
私は、平穏を、愛していたはずだ。
「本当に、そうですか?」
『それ』は、私の心を読んだかのように、そう問いかけた。
「あなたは、心のどこかで、退屈していた。刺激を、求めていた。だから、あなたの無意識は、あなたにぴったりの友人を、作り上げてみせたのです。あなたの名字に、特別な意味を見出し、一方的に『運命の友』だと騒ぎ立て、あなたを無視して、あなたを振り回す、美しいお嬢様を」
その言葉は、あまりにも、的確に、私の心の、一番柔らかい部分を、抉ってきた。
そうだ。私は、退屈していたのかもしれない。
レイカさんが現れてからの毎日は、確かに、迷惑で、腹立たしいことばかりだったけれど。
けれど、退屈では、なかった。
一日一日が、予測不能な出来事で、満ち溢れていた。
私は、その刺激に、心のどこかで、喜びを、感じてしまっていたのでは、ないだろうか。
「認めなさい」
『それ』は、すっと、その白い手を、私の頬に、伸ばしてきた。
その手つきは、ひどく、優しかった。
けれど、その指先は、氷のように、冷たかった。
「西園寺レイカは、あなたの孤独が生み出した、都合のいい、幻なのだと」
その言葉が、とどめだった。
私の足元が、ぐらり、と、大きく揺れた。
世界が、反転するような感覚。
そうだ。
そうだったのかもしれない。
私が、間違っていたんだ。
レイカさんなんて、最初から、いなかったんだ。
全て、私の、見ていた、長い、長い、夢だったんだ。
そう、認めてしまえば、どれだけ、楽になれるだろう。
この、世界と自分との間に生じた、致命的なズレから、解放される。
私は、ただの、少しだけ夢見がちな、普通の女子高生に戻れるのだ。
「それで、よいのです」
『それ』は、私の表情の変化を読み取ったのか、満足げに、頷いた。
その能面のような顔に、初めて、かすかな、笑みのようなものが、浮かんだように見えた。
それは、勝利を確信した者の、冷たい、冷たい、笑みだった。
「さあ、サヤカ。その辛い、偽りの記憶をすべて断ち切ってください」
『それ』は、私の頬を撫でていた手を、ゆっくりと、私の額へと、移動させた。
その指先が、私の前髪を、優しくかき分ける。
もう、抵抗する気力は、なかった。
私は、ただ、されるがままに、そのナニカの前に、立ち尽くしていた。
目を、閉じる。
これで、全てが、終わる。
私の、短くも、騒がしい、非日常が。
さようなら、レイカさん。
私の、幻の、友人。
心の中で、そう、呟いた、その瞬間だった。