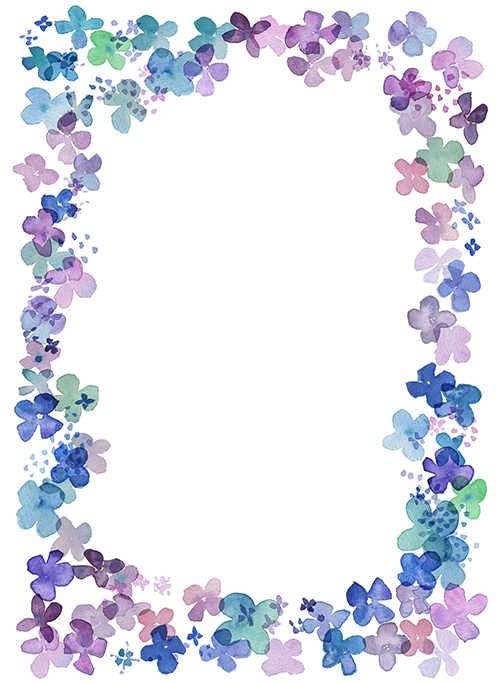意識が、ゆっくりと水底から浮上してくるような、奇妙な感覚があった。
瞼の裏側で、白く、ぼんやりとした光が明滅している。誰かの声が聞こえる。低く、抑揚のない声。それは、かなり遠くから聞こえてくるかのようで、何を言っているのか、はっきりと聞き取ることはできない。
ここは、どこだ。
確か私は、北校舎の空き教室……通称『お墓』で、あの不気味な机に触れて……。
そうだ。レイカさんを突き飛ばして、代わりに私が。
そして、教室の扉が閉まって、体の感覚が消えて……。
そこからの記憶が、ない。
私は、ゆっくりと、重たい瞼を持ち上げた。
最初に目に飛び込んできたのは、見慣れた、黒板の景色だった。チョークで書かれた、びっしりとした数式。それを背にして、抑揚のない声で何かを説明している、見慣れた数学教師の背中。
そして、周囲には、見慣れたクラスメイトたちの姿。誰もが、真面目な顔で、あるいは退屈そうに、黒板を見つめている。
私の、教室だった。
南校舎二階にある、二年四組の、私のクラス。
私は、自分の席に、ちゃんと座っていた。右手には、いつものシャープペンシルが握られている。目の前のノートには、先ほどまで教師が説明していたらしい、二次関数のグラフが途中まで描かれていた。
何が、起こったんだ?
頭が、うまく働かない。あの『お墓』での出来事は、一体何だったというのか。
夢?
そうか、夢だ。きっと、そうに違いない。
私は、あの後、どうにかして教室に戻り、自分の席で眠ってしまっていたのだろう。そして、あの気味の悪い怪談に影響されて、悪夢を見ていたのだ。あまりにも、現実感のある、嫌な夢を。
そう考えると、全ての辻褄が合った。私は、そっと安堵のため息をついた。心なしか、体も鉛のように重く感じる。きっと、変な体勢で眠ってしまったせいだろう。
私は、何事もなかったかのように、再びノートに視線を落とした。だが、どうにも集中できない。先ほど見た夢の光景が、瞼の裏に焼き付いて離れないのだ。
あの、埃一つない、ぽつんと置かれた机と椅子。
うっとりとした表情で、それに近づいていくレイカさんの姿。
そして、私が彼女を突き飛ばし、代わりに机に触れてしまった、あの瞬間。
自分の右の手のひらを見つめる。ごく普通の、私の手だ。あの夢の中で感じた、急速に感覚が失われていく、氷のような冷たさなど、どこにもない。
やはり、夢だったのだ。
私は、自分に強く言い聞かせた。そうでもしないと、心の平静を保てそうになかった。
ふと、隣の席に視線を移す。
そこに、彼女の姿はなかった。
西園寺レイカさんの席は、空席になっていた。机の上には、教科書もノートも、何も置かれていない。まるで、最初から誰もいなかったかのように、綺麗さっぱりと片付いている。
トイレにでも、行っているのだろうか。
あるいは、あの後、私と同じように気分が悪くなって、保健室にでも。いや、彼女に限って、それはないか。あの人は、怪異を前にして体調を崩すような、か弱い人間ではない。むしろ、水を得た魚のように、生き生きとするタイプだ。
まあ、いい。どこに行っていようと、今の私には関係ない。むしろ、いない方が、ありがたいくらいだ。彼女がいるだけで、私の精神は、無駄に消耗させられるのだから。
私は、そう自分を納得させると、再び黒板に向き直った。
やがて、授業の終わりを告げるチャイムが鳴り響く。その音で、教室の張り詰めた空気は一気に緩み、生徒たちのざわめきが、あちこちから湧き上がった。
結局、レイカさんは、授業が終わるまで、席に戻ってくることはなかった。
◇
休み時間になっても、レイカさんは戻ってこなかった。
私は、特に気にも留めず、前の席の友人と、昨日のテレビドラマの感想などを話して過ごした。いつもと変わらない、平和な休み時間。レイカさんがいないだけで、こんなにも空気が穏やかなのかと、私は、少しだけ感動すら覚えていた。
しかし、次の授業が始まっても、その次の授業が始まっても、彼女の席は、空いたままだった。
さすがに、少しだけ、気になってくる。あれだけ目立つ人間が、何の連絡もなしに、長時間席を外すというのは、少し不自然だ。
まさか、本当に体調でも崩して、早退したのだろうか。あの、鉄人のようなレイカさんが?
そんなことを考えているうちに、午前中の授業は全て終わり、昼休みを知らせるチャイムが鳴り響いた。
私は、自分の弁当を手に、いつも昼食を共にしている友人たちの輪に加わった。
「そういえばさ」
卵焼きを口に運びながら、私は、何気ないふうを装って、切り出した。
「西園寺さん、今日、どうしたんだろうね。朝からずっといないけど」
私のその一言に、友人たちは、きょとんとした顔で、顔を見合わせた。
「……え?」
グループの一人が、代表するように、怪訝な声を上げる。
「誰、それ?」
その言葉の意味を、私は、すぐには理解できなかった。
誰、それ?
何を、言っているんだ?
「え、だから、西園寺さんだよ。西園寺レイカさん。私の隣の席の……」
「サヤカの隣? 空席じゃん」
「いや、だから、そこにいつも座ってる、転校生の……」
私の言葉は、どんどん尻すぼみになっていった。友人たちの視線が、痛い。それは、『この子、何を言ってるんだろう』という、明確な不審の色を帯びた視線だった。
「サヤカ、どうしたの? 寝ぼけてる?」
「西園寺、なんて名字の人、うちのクラスにいたっけ?」
「聞いたことない名前だよね」
彼女たちは、本気で、そう言っているようだった。冗談や、からかいの類ではない。その表情は、純粋な疑問と、私に対するわずかな困惑に満ちていた。
全身から、急速に、温度が失われていくような感覚に襲われた。
まさか。
そんな、はずは、ない。
「……うそでしょ? だって、ついこの間、転校してきたばかりじゃない。あの、西園寺グループの令嬢だって、噂になってた……」
「西園寺グループ? ああ、あの有名な。でも、そんな人が、うちに転校してくるわけなくない?」
「サヤカ、疲れてるんじゃない? 最近、なんか変だよ?」
友人たちの言葉が、私を、さらに混乱の渦へと突き落としていく。
変なのは、私?
違う。おかしいのは、あなたたちの方だ。どうして、忘れているんだ。あんなに強烈な個性を持った人間を、忘れられるはずがないだろう。
私は、何かを確かめるように、教室の中を、ぐるりと見回した。
他の生徒たちも、いつもと同じように、それぞれのグループで、楽しそうに昼食をとっている。その誰もが、西園寺レイカという存在など、まるで初めからいなかったかのような、平然とした顔をしていた。
いや、一人くらいは、覚えているはずだ。
私は、友人たちの輪から離れると、教室の隅で一人、本を読んでいた男子生徒に、声をかけた。彼は、クラスの中でも特に真面目で、記憶力の良いことで知られていた。
「ねえ、ちょっといい?」
「……ん? なんだ、鮫島」
彼は、本から顔を上げて、いぶかしげに私を見た。
「西園寺さんって子、知らない? この間、転校してきた……」
「西園寺? 知らないな。そんな奴、いたか?」
彼の答えも、同じだった。
嘘だ。
嘘だ、嘘だ、嘘だ。
何かの、集団催眠か何かにかかっているのか? それとも、手の込んだ、ドッキリか?
だとしたら、あまりにも、悪趣味すぎる。
私は、震える足で、教卓へと向かった。そこに置かれた、出席簿。これを見れば、全てがはっきりするはずだ。
私は、周囲の視線も気にせず、その出席簿を、乱暴にめくった。
二年四組の、生徒名簿。
あ行から、順番に、名前が並んでいる。
私の指は、さ行の欄を探した。
西園寺レイカ。
その名前は、どこにも、なかった。
五十音順に並んだ名前のリストの中に、彼女が存在した痕跡は、どこにも見当たらなかったのだ。
出席簿が、手から滑り落ちた。ばさりと、乾いた音が、静かな教室に響く。
何人かの生徒が、何事かと、こちらを振り返った。
頭が、真っ白になった。
何が、どうなっているのか、全く、理解できない。
私の記憶が、おかしいのか?
それとも、この世界が、おかしいのか?
脳裏に、あの怪談が、不気味に蘇る。
『決して座ってはいけない席』
『その席に座った生徒は、次の日、学校に来なくなる』
『その生徒の存在そのものが、まるで初めからいなかったかのように、皆の記憶から、綺麗に消え去ってしまう』
まさか。
あの呪いは、本物だったというのか?
そして、その呪いにかかったのは、レイカさん……?
いや、でも、おかしい。私は、覚えている。西園寺レイカという人間が、確かに、このクラスにいたことを。彼女と交わした、数々の迷惑で、腹立たしい、けれど、強烈に色鮮やかな記憶を。
どうして、私だけが。
圧倒的な、孤独感が、私を襲った。
この教室で、この世界で、西園寺レイカという存在を知っているのは、私、ただ一人。
その事実は、私を、完全な孤立へと追い込んでいく。
私は、自分が、この世界から、たった一人、切り離されてしまったような、途方もない恐怖に、襲われていた。
◇
午後の授業が、どのように進んだのか、私には、全く記憶がなかった。
ただ、自分の席で、石のように固まっていたことだけを、覚えている。教師の声も、クラスメイトたちのざわめきも、全てが、遠い世界の出来事のように感じられた。
私の頭の中は、ただ一つの疑問で、埋め尽くされていた。
何故、私だけが、覚えているのか。
あの呪いは、対象者の存在を、全ての人の記憶から消し去るはずではなかったのか。だとしたら、私の記憶も、改変されていなければ、おかしい。
それとも、これは、呪いなどではない、別の何か……?
考えても、答えは出なかった。ただ、混乱だけが、雪だるま式に、大きくなっていく。
放課後を告げるチャイムが鳴り、生徒たちが、一斉に席を立つ。私は、その喧騒の中を、まるで幽霊のように、すり抜けて、教室を出た。
どこへ行くというあても、なかった。ただ、このまま家に帰って、一人でこの恐怖と向き合う自信が、なかったのだ。
私は、無意識のうちに、自分のスマートフォンを取り出していた。
震える指で、メッセージアプリを開く。
レイカさんとの、トーク履歴を探す。
昼休み、半ば無理やり交換させられた、あのアカウント。昨夜、あの心霊写真を巡って、激しい口論を繰り広げた、あの履歴。
それさえ見れば、彼女が、確かに存在したという、動かぬ証拠になるはずだ。
しかし。
トークリストを、いくらスクロールしても、西園寺レイカの名前は、見つからなかった。
まるで、最初から、そんな人間と、やり取りなどしていなかったかのように。
次に、私は、写真共有アプリを開いた。
クラスの友人たちが、今日の出来事を、次々と投稿している。その中に、あの、忌まわしい写真は、なかった。
それどころか、西園寺レイカというアカウントそのものが、どこにも、存在していなかった。
全ての、デジタルな痕跡が、綺麗に、消え去っている。
その事実は、私に、新たな、そして、より深刻な疑念を抱かせた。
もしかして、本当に、おかしいのは、私の方なのではないか。
西園寺レイカという人間は、最初から、存在しなかったのではないか。
彼女は、私の孤独が生み出した、都合の良い、幻の友人だったのではないか。
転校初日から、私にだけ、異常なほど親しげに接してきた、美しいお嬢様。ネットロアに詳しく、私のありふれた名字を、特別なものだと言ってくれた、風変わりな少女。
考えてみれば、あまりにも、出来すぎている。
まるで、私が、心のどこかで、望んでいたような、理想の……いや、理想とは、少し違うか。
けれど、私の退屈な日常に、強烈な刺激を与えてくれる存在。
そんな人間を、私が、無意識のうちに、作り出してしまった……?
その考えは、あまりにも恐ろしく、そして、妙な説得力を持っていた。
もし、そうだとしたら。
私は、ただの、頭のおかしい、可哀想な子供だということになる。
集団幻覚よりも、そちらの方が、よっぽど、現実的なのかもしれない。
私は、その場に、へなへなと、座り込みそうになった。
自分の足元が、ぐらぐらと、揺れているような感覚。自分の存在そのものが、不確かなものになっていくような、言いようのない不安。
もう、何も、信じられない。
自分の記憶さえも。
私は、ただ、誰もいない廊下の真ん中で、呆然と、立ち尽くすことしかできなかった。
日が傾き、廊下に差し込む光が、オレンジ色に変わっていく。運動部の掛け声や、吹奏楽部の楽器の音が、窓の外から、遠くに聞こえる。
世界は、いつも通りに、回っている。
私一人だけを、置き去りにして。
迷惑だった。
腹立たしかった。
一刻も早く、目の前から消えてほしいと、何度も、何度も、願った。
なのに。
彼女がいないこの世界は、どうして、こんなにも、色褪せて見えるのだろう。
どうして、こんなにも、息が詰まるほど、静かなのだろう。
胸に、ぽっかりと、大きな穴が空いてしまったような、途方もない喪失感。
私は、ようやく、気づいた。
自分が、西園寺レイカという『厄災』を、いつの間にか、受け入れてしまっていたことに。
いや、それどころか。
その非日常的な刺激に、どこかで、依存してしまっていたのかもしれない。
その事実に気づいた時、私の目から、熱いものが、一筋、こぼれ落ちた。
それは、悲しみなのか、悔しさなのか、それとも、ただの混乱なのか。
自分でも、よく、分からなかった。
瞼の裏側で、白く、ぼんやりとした光が明滅している。誰かの声が聞こえる。低く、抑揚のない声。それは、かなり遠くから聞こえてくるかのようで、何を言っているのか、はっきりと聞き取ることはできない。
ここは、どこだ。
確か私は、北校舎の空き教室……通称『お墓』で、あの不気味な机に触れて……。
そうだ。レイカさんを突き飛ばして、代わりに私が。
そして、教室の扉が閉まって、体の感覚が消えて……。
そこからの記憶が、ない。
私は、ゆっくりと、重たい瞼を持ち上げた。
最初に目に飛び込んできたのは、見慣れた、黒板の景色だった。チョークで書かれた、びっしりとした数式。それを背にして、抑揚のない声で何かを説明している、見慣れた数学教師の背中。
そして、周囲には、見慣れたクラスメイトたちの姿。誰もが、真面目な顔で、あるいは退屈そうに、黒板を見つめている。
私の、教室だった。
南校舎二階にある、二年四組の、私のクラス。
私は、自分の席に、ちゃんと座っていた。右手には、いつものシャープペンシルが握られている。目の前のノートには、先ほどまで教師が説明していたらしい、二次関数のグラフが途中まで描かれていた。
何が、起こったんだ?
頭が、うまく働かない。あの『お墓』での出来事は、一体何だったというのか。
夢?
そうか、夢だ。きっと、そうに違いない。
私は、あの後、どうにかして教室に戻り、自分の席で眠ってしまっていたのだろう。そして、あの気味の悪い怪談に影響されて、悪夢を見ていたのだ。あまりにも、現実感のある、嫌な夢を。
そう考えると、全ての辻褄が合った。私は、そっと安堵のため息をついた。心なしか、体も鉛のように重く感じる。きっと、変な体勢で眠ってしまったせいだろう。
私は、何事もなかったかのように、再びノートに視線を落とした。だが、どうにも集中できない。先ほど見た夢の光景が、瞼の裏に焼き付いて離れないのだ。
あの、埃一つない、ぽつんと置かれた机と椅子。
うっとりとした表情で、それに近づいていくレイカさんの姿。
そして、私が彼女を突き飛ばし、代わりに机に触れてしまった、あの瞬間。
自分の右の手のひらを見つめる。ごく普通の、私の手だ。あの夢の中で感じた、急速に感覚が失われていく、氷のような冷たさなど、どこにもない。
やはり、夢だったのだ。
私は、自分に強く言い聞かせた。そうでもしないと、心の平静を保てそうになかった。
ふと、隣の席に視線を移す。
そこに、彼女の姿はなかった。
西園寺レイカさんの席は、空席になっていた。机の上には、教科書もノートも、何も置かれていない。まるで、最初から誰もいなかったかのように、綺麗さっぱりと片付いている。
トイレにでも、行っているのだろうか。
あるいは、あの後、私と同じように気分が悪くなって、保健室にでも。いや、彼女に限って、それはないか。あの人は、怪異を前にして体調を崩すような、か弱い人間ではない。むしろ、水を得た魚のように、生き生きとするタイプだ。
まあ、いい。どこに行っていようと、今の私には関係ない。むしろ、いない方が、ありがたいくらいだ。彼女がいるだけで、私の精神は、無駄に消耗させられるのだから。
私は、そう自分を納得させると、再び黒板に向き直った。
やがて、授業の終わりを告げるチャイムが鳴り響く。その音で、教室の張り詰めた空気は一気に緩み、生徒たちのざわめきが、あちこちから湧き上がった。
結局、レイカさんは、授業が終わるまで、席に戻ってくることはなかった。
◇
休み時間になっても、レイカさんは戻ってこなかった。
私は、特に気にも留めず、前の席の友人と、昨日のテレビドラマの感想などを話して過ごした。いつもと変わらない、平和な休み時間。レイカさんがいないだけで、こんなにも空気が穏やかなのかと、私は、少しだけ感動すら覚えていた。
しかし、次の授業が始まっても、その次の授業が始まっても、彼女の席は、空いたままだった。
さすがに、少しだけ、気になってくる。あれだけ目立つ人間が、何の連絡もなしに、長時間席を外すというのは、少し不自然だ。
まさか、本当に体調でも崩して、早退したのだろうか。あの、鉄人のようなレイカさんが?
そんなことを考えているうちに、午前中の授業は全て終わり、昼休みを知らせるチャイムが鳴り響いた。
私は、自分の弁当を手に、いつも昼食を共にしている友人たちの輪に加わった。
「そういえばさ」
卵焼きを口に運びながら、私は、何気ないふうを装って、切り出した。
「西園寺さん、今日、どうしたんだろうね。朝からずっといないけど」
私のその一言に、友人たちは、きょとんとした顔で、顔を見合わせた。
「……え?」
グループの一人が、代表するように、怪訝な声を上げる。
「誰、それ?」
その言葉の意味を、私は、すぐには理解できなかった。
誰、それ?
何を、言っているんだ?
「え、だから、西園寺さんだよ。西園寺レイカさん。私の隣の席の……」
「サヤカの隣? 空席じゃん」
「いや、だから、そこにいつも座ってる、転校生の……」
私の言葉は、どんどん尻すぼみになっていった。友人たちの視線が、痛い。それは、『この子、何を言ってるんだろう』という、明確な不審の色を帯びた視線だった。
「サヤカ、どうしたの? 寝ぼけてる?」
「西園寺、なんて名字の人、うちのクラスにいたっけ?」
「聞いたことない名前だよね」
彼女たちは、本気で、そう言っているようだった。冗談や、からかいの類ではない。その表情は、純粋な疑問と、私に対するわずかな困惑に満ちていた。
全身から、急速に、温度が失われていくような感覚に襲われた。
まさか。
そんな、はずは、ない。
「……うそでしょ? だって、ついこの間、転校してきたばかりじゃない。あの、西園寺グループの令嬢だって、噂になってた……」
「西園寺グループ? ああ、あの有名な。でも、そんな人が、うちに転校してくるわけなくない?」
「サヤカ、疲れてるんじゃない? 最近、なんか変だよ?」
友人たちの言葉が、私を、さらに混乱の渦へと突き落としていく。
変なのは、私?
違う。おかしいのは、あなたたちの方だ。どうして、忘れているんだ。あんなに強烈な個性を持った人間を、忘れられるはずがないだろう。
私は、何かを確かめるように、教室の中を、ぐるりと見回した。
他の生徒たちも、いつもと同じように、それぞれのグループで、楽しそうに昼食をとっている。その誰もが、西園寺レイカという存在など、まるで初めからいなかったかのような、平然とした顔をしていた。
いや、一人くらいは、覚えているはずだ。
私は、友人たちの輪から離れると、教室の隅で一人、本を読んでいた男子生徒に、声をかけた。彼は、クラスの中でも特に真面目で、記憶力の良いことで知られていた。
「ねえ、ちょっといい?」
「……ん? なんだ、鮫島」
彼は、本から顔を上げて、いぶかしげに私を見た。
「西園寺さんって子、知らない? この間、転校してきた……」
「西園寺? 知らないな。そんな奴、いたか?」
彼の答えも、同じだった。
嘘だ。
嘘だ、嘘だ、嘘だ。
何かの、集団催眠か何かにかかっているのか? それとも、手の込んだ、ドッキリか?
だとしたら、あまりにも、悪趣味すぎる。
私は、震える足で、教卓へと向かった。そこに置かれた、出席簿。これを見れば、全てがはっきりするはずだ。
私は、周囲の視線も気にせず、その出席簿を、乱暴にめくった。
二年四組の、生徒名簿。
あ行から、順番に、名前が並んでいる。
私の指は、さ行の欄を探した。
西園寺レイカ。
その名前は、どこにも、なかった。
五十音順に並んだ名前のリストの中に、彼女が存在した痕跡は、どこにも見当たらなかったのだ。
出席簿が、手から滑り落ちた。ばさりと、乾いた音が、静かな教室に響く。
何人かの生徒が、何事かと、こちらを振り返った。
頭が、真っ白になった。
何が、どうなっているのか、全く、理解できない。
私の記憶が、おかしいのか?
それとも、この世界が、おかしいのか?
脳裏に、あの怪談が、不気味に蘇る。
『決して座ってはいけない席』
『その席に座った生徒は、次の日、学校に来なくなる』
『その生徒の存在そのものが、まるで初めからいなかったかのように、皆の記憶から、綺麗に消え去ってしまう』
まさか。
あの呪いは、本物だったというのか?
そして、その呪いにかかったのは、レイカさん……?
いや、でも、おかしい。私は、覚えている。西園寺レイカという人間が、確かに、このクラスにいたことを。彼女と交わした、数々の迷惑で、腹立たしい、けれど、強烈に色鮮やかな記憶を。
どうして、私だけが。
圧倒的な、孤独感が、私を襲った。
この教室で、この世界で、西園寺レイカという存在を知っているのは、私、ただ一人。
その事実は、私を、完全な孤立へと追い込んでいく。
私は、自分が、この世界から、たった一人、切り離されてしまったような、途方もない恐怖に、襲われていた。
◇
午後の授業が、どのように進んだのか、私には、全く記憶がなかった。
ただ、自分の席で、石のように固まっていたことだけを、覚えている。教師の声も、クラスメイトたちのざわめきも、全てが、遠い世界の出来事のように感じられた。
私の頭の中は、ただ一つの疑問で、埋め尽くされていた。
何故、私だけが、覚えているのか。
あの呪いは、対象者の存在を、全ての人の記憶から消し去るはずではなかったのか。だとしたら、私の記憶も、改変されていなければ、おかしい。
それとも、これは、呪いなどではない、別の何か……?
考えても、答えは出なかった。ただ、混乱だけが、雪だるま式に、大きくなっていく。
放課後を告げるチャイムが鳴り、生徒たちが、一斉に席を立つ。私は、その喧騒の中を、まるで幽霊のように、すり抜けて、教室を出た。
どこへ行くというあても、なかった。ただ、このまま家に帰って、一人でこの恐怖と向き合う自信が、なかったのだ。
私は、無意識のうちに、自分のスマートフォンを取り出していた。
震える指で、メッセージアプリを開く。
レイカさんとの、トーク履歴を探す。
昼休み、半ば無理やり交換させられた、あのアカウント。昨夜、あの心霊写真を巡って、激しい口論を繰り広げた、あの履歴。
それさえ見れば、彼女が、確かに存在したという、動かぬ証拠になるはずだ。
しかし。
トークリストを、いくらスクロールしても、西園寺レイカの名前は、見つからなかった。
まるで、最初から、そんな人間と、やり取りなどしていなかったかのように。
次に、私は、写真共有アプリを開いた。
クラスの友人たちが、今日の出来事を、次々と投稿している。その中に、あの、忌まわしい写真は、なかった。
それどころか、西園寺レイカというアカウントそのものが、どこにも、存在していなかった。
全ての、デジタルな痕跡が、綺麗に、消え去っている。
その事実は、私に、新たな、そして、より深刻な疑念を抱かせた。
もしかして、本当に、おかしいのは、私の方なのではないか。
西園寺レイカという人間は、最初から、存在しなかったのではないか。
彼女は、私の孤独が生み出した、都合の良い、幻の友人だったのではないか。
転校初日から、私にだけ、異常なほど親しげに接してきた、美しいお嬢様。ネットロアに詳しく、私のありふれた名字を、特別なものだと言ってくれた、風変わりな少女。
考えてみれば、あまりにも、出来すぎている。
まるで、私が、心のどこかで、望んでいたような、理想の……いや、理想とは、少し違うか。
けれど、私の退屈な日常に、強烈な刺激を与えてくれる存在。
そんな人間を、私が、無意識のうちに、作り出してしまった……?
その考えは、あまりにも恐ろしく、そして、妙な説得力を持っていた。
もし、そうだとしたら。
私は、ただの、頭のおかしい、可哀想な子供だということになる。
集団幻覚よりも、そちらの方が、よっぽど、現実的なのかもしれない。
私は、その場に、へなへなと、座り込みそうになった。
自分の足元が、ぐらぐらと、揺れているような感覚。自分の存在そのものが、不確かなものになっていくような、言いようのない不安。
もう、何も、信じられない。
自分の記憶さえも。
私は、ただ、誰もいない廊下の真ん中で、呆然と、立ち尽くすことしかできなかった。
日が傾き、廊下に差し込む光が、オレンジ色に変わっていく。運動部の掛け声や、吹奏楽部の楽器の音が、窓の外から、遠くに聞こえる。
世界は、いつも通りに、回っている。
私一人だけを、置き去りにして。
迷惑だった。
腹立たしかった。
一刻も早く、目の前から消えてほしいと、何度も、何度も、願った。
なのに。
彼女がいないこの世界は、どうして、こんなにも、色褪せて見えるのだろう。
どうして、こんなにも、息が詰まるほど、静かなのだろう。
胸に、ぽっかりと、大きな穴が空いてしまったような、途方もない喪失感。
私は、ようやく、気づいた。
自分が、西園寺レイカという『厄災』を、いつの間にか、受け入れてしまっていたことに。
いや、それどころか。
その非日常的な刺激に、どこかで、依存してしまっていたのかもしれない。
その事実に気づいた時、私の目から、熱いものが、一筋、こぼれ落ちた。
それは、悲しみなのか、悔しさなのか、それとも、ただの混乱なのか。
自分でも、よく、分からなかった。