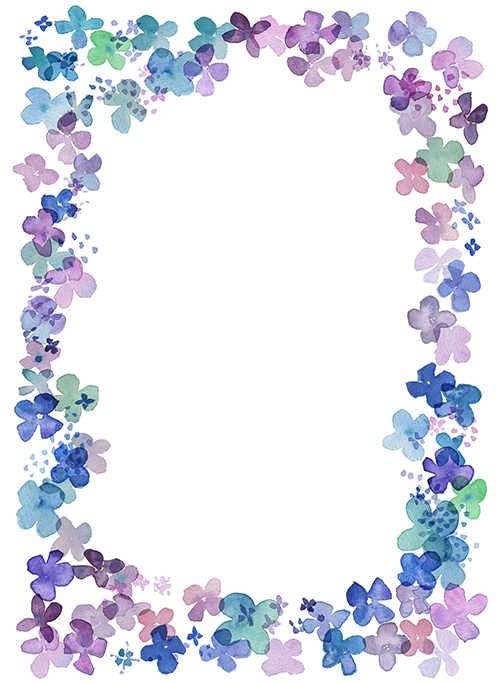レイカさんは、私の返事を待つまでもなく、手をかけた引き戸をスライドさせていく。
ガラガラ、と、油の切れた車輪がレールの上をこするような、耳障りな音が薄暗い廊下に響き渡った。どうも、立て付けが悪いのか、ドアはすんなりとは開かず、彼女は少し力を込めて、それをさらに横に引いた。
「さあ、サヤカ。私たちの記念すべき、怪談探索の始まりですわ」
振り返って私に手招きする彼女の顔は、未知との遭遇を前にした、好奇心に満ち足りた顔。その表情は、これからお化け屋敷に入るというよりは、宝探しの冒険に出かける子供のそれに近い。その底抜けの能天気さが、この状況では、逆に私の不安を煽った。
「大丈夫ですわ、サヤカ。私がついておりますもの」
その言葉に、少しも安心などできなかった。むしろ、この人こそが、全ての元凶なのだ。私がこの世で最も恐れているのは、幽霊や呪いなどではなく、目の前で輝くような笑みを浮かべている、この西園寺レイカという名の『厄災』そのものなのだから。
私は、観念して、重たい足取りで彼女の元へと歩み寄った。もう、何を言っても無駄だ。こうなってしまった以上、さっさとこの茶番を終わらせて、一刻も早く家に帰る。それだけを目標にしよう。
レイカさんに続いて、私も教室の中へと足を踏み入れた。
予想に反して、そこは他の教室と何ら変わらない、清潔な空間だった。床は埃一つなく磨かれており、窓ガラスも綺麗に拭かれている。西日がまっすぐに差し込み、空気中を舞う塵をきらきらと照らし出していた。もしこの怪談を知らなければ、誰もがただの、日当たりの良い空き教室だとしか思わないだろう。
しかし、その一方で、そこは彼女が語った通りの、物置として使われている空間でもあった。教室の壁際には、使われなくなった長机や、脚の折れた椅子、埃をかぶった段ボール箱などが、無造作に積み上げられている。床には、何の備品か分からない、用途不明の金属の棒や、破れたプリント類が散らばっていた。
「ふむ……。思ったよりも、霊的な汚染は進んでいないようですわね」
レイカさんは、教室の中央に立つと、スマホのコンパスアプリを使用して、きょろきょろと周囲を見回している。
「磁場の乱れも、観測されません。ですが、油断は禁物ですわ。こういう場所ほど、強力な地縛霊が、その気配を巧妙に隠しているものですから」
彼女は、一人で納得したように頷くと、懐から取り出したお札を、教室の四隅に向かって、ぱ、ぱ、と手際よく貼り付けていく。その動きには、一切の無駄がない。彼女が、これまでの人生で、同じようなことを何度も繰り返してきたであろうことが、その手慣れた様子からうかがえた。
「これで、簡易的な結界は完成ですわ。万が一のことがあっても、この中であれば、外部からの霊的干渉をある程度は防げるはず」
「……ねえ、もう良くない?」
私は、壁に積み上げられた机の山を背にして、腕を組みながら言った。
「ただの物置だよ、ここ。何もなさそうだし、さっさと帰ろうよ」
「まあ、サヤカ。何を弱気なことをおっしゃいますの」
レイカさんは、呆れたように、しかし、どこか楽しそうに、くすくすと笑った。
「本番は、これからですのに。ごらんなさい、あちらを」
彼女が、すっと指差した先。
その光景に、私は、思わず息を呑んだ。
教室の、窓際の一番奥。
乱雑に物が積み上げられたこの部屋の中で、そこだけ、まるで世界の理から切り離されたかのように、ぽつんと、一組の机と椅子が、整然と置かれていたのだ。
それは、私たちが普段使っているものと、何ら変わらない、ごく普通の学習机と椅子だった。
しかし、周囲の荒れ果てた光景とはあまりにも不釣り合いなその佇まいは、かえって異様な存在感を放っている。机の上にも、椅子の座面にも、この部屋を覆っているはずの埃が、全く積もっていない。まるで、ついさっきまで、誰かがそこに座って、何かをしていたかのように、清潔で、生々しい。
西日が、汚れた窓ガラスを通して、その机と椅子にだけ、スポットライトのように降り注いでいる。その光景は、どこか神々しくさえあり、同時に、底知れない不気味さを感じさせた。
「……あれが、『決して座ってはいけない席』」
私の口から、かすれた声が漏れた。
ただの噂話だと思っていた。子供だましの、馬鹿馬鹿しい作り話だと。けれど、目の前に、その『舞台装置』が、あまりにも完璧な形で存在しているのを見て、私の心に、じわりと、冷たい恐怖が染み出してくるのを感じた。
「ええ。間違いありませんわ」
レイカさんの声には、抑えきれない興奮の色が滲んでいた。彼女の瞳は、獲物を見つけた狩人のように、爛々と輝いている。
「素晴らしい……。これほどまでに、噂話のイメージを忠実に再現した怪異は、そうそうお目にかかれるものではございませんわ。この、周囲の雑然とした風景との、見事なまでのコントラスト。まるで、この空間だけが、別の法則で支配されているかのよう。ああ、なんという芸術的な演出でしょう!」
彼女は、うっとりとした表情で、その席を眺めている。その感性は、私には到底理解できない。私には、あれが、ただの不吉な罠にしか見えなかった。
「ねえ、レイカさん。あれは、絶対におかしいよ。誰かが、意図的に置いたんじゃないの? いたずらとか……」
「いたずら、ですって? とんでもない」
彼女は、私の言葉を、一笑に付した。
「これほどの霊気を放つオブジェクトを、ただの人間のいたずらで作り出せるものですか。これは、間違いなく、この場所に根付いた『想い』が、物理的な形となって現出したものですわ。長年語り継がれてきた『決して座ってはいけない席』という物語が、この教室という舞台の上で、現実の形を得たのです」
「想いが、形に……?」
「ええ。人々が『そこに在る』と信じ、語り継ぐことで、怪異は力を得て、現実世界に影響を及ぼす。これこそが、現代怪談の根幹をなす、最も重要なセオリーですわ」
彼女は、得意げにそう語る。その理論の真偽は、私には分からない。けれど、目の前にある、あの異様な机と椅子を見ていると、彼女の言葉が、妙な説得力を持って、私の頭に響いてきた。
レイカさんは、おもむろに、その席へと、一歩、また一歩と、歩み寄っていく。その足取りには、何の迷いもなかった。
「待って、レイカさん! 危ないよ!」
私は、思わず叫んでいた。頭では、馬鹿馬鹿しいと分かっている。ただの机と椅子だ。触ったところで、どうなるものでもない。
けれど、私の本能が、警鐘を鳴らしていた。
あれに、近づいてはいけない、と。
「大丈夫ですわ、サヤカ。私には、この清めの塩がありますもの」
彼女は、振り返って、にこりと微笑むと、懐から取り出した巾着袋を、得意げに振って見せた。
「それに、ただ近づくだけですわ。まさか、座ったりなどいたしません。この怪異の正体を見極めるには、まず、対象を詳細に観察することが、何よりも重要ですから」
そう言うと、彼女は再び前を向き、その席のすぐそばまで近づいた。そして、まるで貴重な美術品でも鑑定するかのように、身をかがめて、机の表面や、椅子の脚を、じろじろと眺め始めた。
「ふむ……。傷一つありませんわね。長年使われてきたにしては、あまりにも綺麗すぎる。まるで、新品のようですわ。ですが、この、机の天板の木目……。どこか、人の顔のようにも見えませんこと?」
「見えないよ! 普通の木目だって!」
私は、教室の入り口近くから、一歩も動けずにいた。彼女と、あの席との距離が、あまりにも近すぎる。見ているだけで、心臓が早鐘を打つのが分かった。
「いや、待ってくださいな。この椅子の背もたれに、何か、引っかいたような跡が……。これは、文字? いや、何かの記号……?」
レイカさんは、さらに興味を引かれたように、その椅子に顔を近づけていく。その探究心は、もはや、誰にも止められないようだった。
やめて。
それ以上、近づかないで。
私の心の叫びは、しかし、彼女には届かない。
そして、ついに、その瞬間は訪れた。
「少し、触れてみましょう。この怪異が、どのような物質で構成されているのか、確かめる必要がありますわ」
彼女は、こともなげにそう言うと、その白い、陶器のようになめらかな指を、すっと、机の天板へと伸ばした。
その光景は、まるでスローモーションのように、私の目に映った。
彼女の指先が、あと数センチで、机に触れようとしている。
ダメだ。
その瞬間、私の体は、考えるよりも先に、動いていた。
「危ないっ!」
私は、床に散らばっていたがらくたを蹴散らし、全力で彼女の元へと駆け寄った。そして、机に触れようとしていた彼女の体を、力いっぱい、突き飛ばした。
「きゃっ!?」
レイカさんは、不意の衝撃に、驚きの声を上げて、床に尻餅をついた。
私は、彼女を突き飛ばした勢いで、前のめりによろめく。
そして。
私の手が、彼女の代わりに、その冷たい机の表面に、ぴたりと、触れてしまった。
その瞬間だった。
バタンッ!!
背後で、凄まじい音が響き渡った。
私たちが唯一の出口としていた、教室の引き戸が、まるで巨大な手で叩きつけられたかのように、乱暴に、そして完全に、閉ざされたのだ。
風など、吹いていなかった。誰かが、外から閉めたわけでもない。
それは、明らかに、この部屋の内部で発生した、物理法則を無視した現象だった。
「え……?」
床に座り込んだままのレイカさんが、呆然とした声を上げる。
私も、何が起こったのか理解できず、ただ、閉ざされた扉を、見つめることしかできなかった。
そして、私の体に、異変が起きた。
机に触れていた、右の手のひらから、急速に、感覚が失われていく。まるで、分厚い氷に触れているかのように、じんと痺れ、やがて、それが自分の体の一部であるという実感さえも、薄れていく。
その冷たい感覚は、手首から、腕へ、そして肩へと、這い上がってくる。抗うことができない。それは、絶対的な、拒絶しようのない、力だった。
視界が、ぐにゃりと、形を失い始めた。
教室の風景が、水の中に落とした絵の具のように、ゆっくりと、しかし確実に、その色彩を失っていく。積み上げられた机も、汚れた窓も、床に座り込むレイカさんの姿も、全てが、曖昧な色の塊になっていく。
「サヤカ……? サヤカ、どうかなさいましたの!?」
レイカさんの声が、どこか遠くで聞こえる。まるで、遠くから呼びかけられているかのようだ。返事をしようとしたが、口から出るのは、意味をなさない、かすれた息の音だけだった。
ああ、これは、まずい。
そう思ったのを最後に、私の意識は、ぷつりと、途切れた。
ガラガラ、と、油の切れた車輪がレールの上をこするような、耳障りな音が薄暗い廊下に響き渡った。どうも、立て付けが悪いのか、ドアはすんなりとは開かず、彼女は少し力を込めて、それをさらに横に引いた。
「さあ、サヤカ。私たちの記念すべき、怪談探索の始まりですわ」
振り返って私に手招きする彼女の顔は、未知との遭遇を前にした、好奇心に満ち足りた顔。その表情は、これからお化け屋敷に入るというよりは、宝探しの冒険に出かける子供のそれに近い。その底抜けの能天気さが、この状況では、逆に私の不安を煽った。
「大丈夫ですわ、サヤカ。私がついておりますもの」
その言葉に、少しも安心などできなかった。むしろ、この人こそが、全ての元凶なのだ。私がこの世で最も恐れているのは、幽霊や呪いなどではなく、目の前で輝くような笑みを浮かべている、この西園寺レイカという名の『厄災』そのものなのだから。
私は、観念して、重たい足取りで彼女の元へと歩み寄った。もう、何を言っても無駄だ。こうなってしまった以上、さっさとこの茶番を終わらせて、一刻も早く家に帰る。それだけを目標にしよう。
レイカさんに続いて、私も教室の中へと足を踏み入れた。
予想に反して、そこは他の教室と何ら変わらない、清潔な空間だった。床は埃一つなく磨かれており、窓ガラスも綺麗に拭かれている。西日がまっすぐに差し込み、空気中を舞う塵をきらきらと照らし出していた。もしこの怪談を知らなければ、誰もがただの、日当たりの良い空き教室だとしか思わないだろう。
しかし、その一方で、そこは彼女が語った通りの、物置として使われている空間でもあった。教室の壁際には、使われなくなった長机や、脚の折れた椅子、埃をかぶった段ボール箱などが、無造作に積み上げられている。床には、何の備品か分からない、用途不明の金属の棒や、破れたプリント類が散らばっていた。
「ふむ……。思ったよりも、霊的な汚染は進んでいないようですわね」
レイカさんは、教室の中央に立つと、スマホのコンパスアプリを使用して、きょろきょろと周囲を見回している。
「磁場の乱れも、観測されません。ですが、油断は禁物ですわ。こういう場所ほど、強力な地縛霊が、その気配を巧妙に隠しているものですから」
彼女は、一人で納得したように頷くと、懐から取り出したお札を、教室の四隅に向かって、ぱ、ぱ、と手際よく貼り付けていく。その動きには、一切の無駄がない。彼女が、これまでの人生で、同じようなことを何度も繰り返してきたであろうことが、その手慣れた様子からうかがえた。
「これで、簡易的な結界は完成ですわ。万が一のことがあっても、この中であれば、外部からの霊的干渉をある程度は防げるはず」
「……ねえ、もう良くない?」
私は、壁に積み上げられた机の山を背にして、腕を組みながら言った。
「ただの物置だよ、ここ。何もなさそうだし、さっさと帰ろうよ」
「まあ、サヤカ。何を弱気なことをおっしゃいますの」
レイカさんは、呆れたように、しかし、どこか楽しそうに、くすくすと笑った。
「本番は、これからですのに。ごらんなさい、あちらを」
彼女が、すっと指差した先。
その光景に、私は、思わず息を呑んだ。
教室の、窓際の一番奥。
乱雑に物が積み上げられたこの部屋の中で、そこだけ、まるで世界の理から切り離されたかのように、ぽつんと、一組の机と椅子が、整然と置かれていたのだ。
それは、私たちが普段使っているものと、何ら変わらない、ごく普通の学習机と椅子だった。
しかし、周囲の荒れ果てた光景とはあまりにも不釣り合いなその佇まいは、かえって異様な存在感を放っている。机の上にも、椅子の座面にも、この部屋を覆っているはずの埃が、全く積もっていない。まるで、ついさっきまで、誰かがそこに座って、何かをしていたかのように、清潔で、生々しい。
西日が、汚れた窓ガラスを通して、その机と椅子にだけ、スポットライトのように降り注いでいる。その光景は、どこか神々しくさえあり、同時に、底知れない不気味さを感じさせた。
「……あれが、『決して座ってはいけない席』」
私の口から、かすれた声が漏れた。
ただの噂話だと思っていた。子供だましの、馬鹿馬鹿しい作り話だと。けれど、目の前に、その『舞台装置』が、あまりにも完璧な形で存在しているのを見て、私の心に、じわりと、冷たい恐怖が染み出してくるのを感じた。
「ええ。間違いありませんわ」
レイカさんの声には、抑えきれない興奮の色が滲んでいた。彼女の瞳は、獲物を見つけた狩人のように、爛々と輝いている。
「素晴らしい……。これほどまでに、噂話のイメージを忠実に再現した怪異は、そうそうお目にかかれるものではございませんわ。この、周囲の雑然とした風景との、見事なまでのコントラスト。まるで、この空間だけが、別の法則で支配されているかのよう。ああ、なんという芸術的な演出でしょう!」
彼女は、うっとりとした表情で、その席を眺めている。その感性は、私には到底理解できない。私には、あれが、ただの不吉な罠にしか見えなかった。
「ねえ、レイカさん。あれは、絶対におかしいよ。誰かが、意図的に置いたんじゃないの? いたずらとか……」
「いたずら、ですって? とんでもない」
彼女は、私の言葉を、一笑に付した。
「これほどの霊気を放つオブジェクトを、ただの人間のいたずらで作り出せるものですか。これは、間違いなく、この場所に根付いた『想い』が、物理的な形となって現出したものですわ。長年語り継がれてきた『決して座ってはいけない席』という物語が、この教室という舞台の上で、現実の形を得たのです」
「想いが、形に……?」
「ええ。人々が『そこに在る』と信じ、語り継ぐことで、怪異は力を得て、現実世界に影響を及ぼす。これこそが、現代怪談の根幹をなす、最も重要なセオリーですわ」
彼女は、得意げにそう語る。その理論の真偽は、私には分からない。けれど、目の前にある、あの異様な机と椅子を見ていると、彼女の言葉が、妙な説得力を持って、私の頭に響いてきた。
レイカさんは、おもむろに、その席へと、一歩、また一歩と、歩み寄っていく。その足取りには、何の迷いもなかった。
「待って、レイカさん! 危ないよ!」
私は、思わず叫んでいた。頭では、馬鹿馬鹿しいと分かっている。ただの机と椅子だ。触ったところで、どうなるものでもない。
けれど、私の本能が、警鐘を鳴らしていた。
あれに、近づいてはいけない、と。
「大丈夫ですわ、サヤカ。私には、この清めの塩がありますもの」
彼女は、振り返って、にこりと微笑むと、懐から取り出した巾着袋を、得意げに振って見せた。
「それに、ただ近づくだけですわ。まさか、座ったりなどいたしません。この怪異の正体を見極めるには、まず、対象を詳細に観察することが、何よりも重要ですから」
そう言うと、彼女は再び前を向き、その席のすぐそばまで近づいた。そして、まるで貴重な美術品でも鑑定するかのように、身をかがめて、机の表面や、椅子の脚を、じろじろと眺め始めた。
「ふむ……。傷一つありませんわね。長年使われてきたにしては、あまりにも綺麗すぎる。まるで、新品のようですわ。ですが、この、机の天板の木目……。どこか、人の顔のようにも見えませんこと?」
「見えないよ! 普通の木目だって!」
私は、教室の入り口近くから、一歩も動けずにいた。彼女と、あの席との距離が、あまりにも近すぎる。見ているだけで、心臓が早鐘を打つのが分かった。
「いや、待ってくださいな。この椅子の背もたれに、何か、引っかいたような跡が……。これは、文字? いや、何かの記号……?」
レイカさんは、さらに興味を引かれたように、その椅子に顔を近づけていく。その探究心は、もはや、誰にも止められないようだった。
やめて。
それ以上、近づかないで。
私の心の叫びは、しかし、彼女には届かない。
そして、ついに、その瞬間は訪れた。
「少し、触れてみましょう。この怪異が、どのような物質で構成されているのか、確かめる必要がありますわ」
彼女は、こともなげにそう言うと、その白い、陶器のようになめらかな指を、すっと、机の天板へと伸ばした。
その光景は、まるでスローモーションのように、私の目に映った。
彼女の指先が、あと数センチで、机に触れようとしている。
ダメだ。
その瞬間、私の体は、考えるよりも先に、動いていた。
「危ないっ!」
私は、床に散らばっていたがらくたを蹴散らし、全力で彼女の元へと駆け寄った。そして、机に触れようとしていた彼女の体を、力いっぱい、突き飛ばした。
「きゃっ!?」
レイカさんは、不意の衝撃に、驚きの声を上げて、床に尻餅をついた。
私は、彼女を突き飛ばした勢いで、前のめりによろめく。
そして。
私の手が、彼女の代わりに、その冷たい机の表面に、ぴたりと、触れてしまった。
その瞬間だった。
バタンッ!!
背後で、凄まじい音が響き渡った。
私たちが唯一の出口としていた、教室の引き戸が、まるで巨大な手で叩きつけられたかのように、乱暴に、そして完全に、閉ざされたのだ。
風など、吹いていなかった。誰かが、外から閉めたわけでもない。
それは、明らかに、この部屋の内部で発生した、物理法則を無視した現象だった。
「え……?」
床に座り込んだままのレイカさんが、呆然とした声を上げる。
私も、何が起こったのか理解できず、ただ、閉ざされた扉を、見つめることしかできなかった。
そして、私の体に、異変が起きた。
机に触れていた、右の手のひらから、急速に、感覚が失われていく。まるで、分厚い氷に触れているかのように、じんと痺れ、やがて、それが自分の体の一部であるという実感さえも、薄れていく。
その冷たい感覚は、手首から、腕へ、そして肩へと、這い上がってくる。抗うことができない。それは、絶対的な、拒絶しようのない、力だった。
視界が、ぐにゃりと、形を失い始めた。
教室の風景が、水の中に落とした絵の具のように、ゆっくりと、しかし確実に、その色彩を失っていく。積み上げられた机も、汚れた窓も、床に座り込むレイカさんの姿も、全てが、曖昧な色の塊になっていく。
「サヤカ……? サヤカ、どうかなさいましたの!?」
レイカさんの声が、どこか遠くで聞こえる。まるで、遠くから呼びかけられているかのようだ。返事をしようとしたが、口から出るのは、意味をなさない、かすれた息の音だけだった。
ああ、これは、まずい。
そう思ったのを最後に、私の意識は、ぷつりと、途切れた。