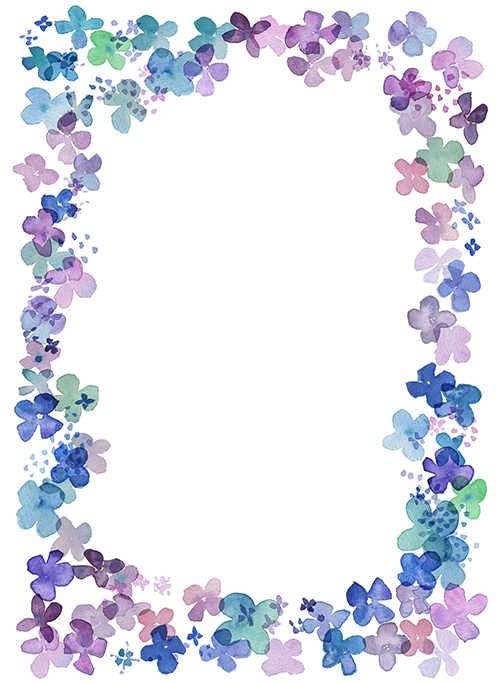あれから数日が経過した。
私の日常は、もはや私の知るそれとは似ても似つかないものへと変貌を遂げていた。『コトリバコ弁当』事件は、瞬く間に学年中に知れ渡り、私はすっかり有名人になってしまった。もちろん、悪い意味で。
廊下を歩けば、ひそひそと囁かれる。『あれが西園寺様のお友達の……』『指の弁当食べさせられそうになった子でしょ?』『なんかヤバい人らしいよ』。その一つ一つが、小さな針のように私の心をちくちくと刺す。もはや、教室の隅で静かに過ごすことなど、夢のまた夢だった。
そして、その全ての元凶である西園寺レイカさんは、そんな私の苦悩などどこ吹く風、といった様子で、毎日を謳歌していた。彼女の周りには常に人が集まり、その中心で彼女は、私の『霊的資質の高さ』や、いかに私たちが『運命の友』であるかを、嬉々として語るのだ。そのたびに、周囲の生徒たちは、面白がるような、あるいは同情するような、複雑な視線を私に向ける。私は、まるで檻の中の見世物になったような気分だった。
私は、レイカさんに対して、明確な『拒絶』の態度を取るようになっていた。休み時間になれば、彼女が話しかけてくる前に教室を飛び出し、昼休みは人の少ない中庭のベンチで一人、息を潜めるようにして過ごす。彼女からのメッセージには当たり障りのない返信だけを返し、決して会話が続かないように細心の注意を払った。
しかし、そんな私のささやかな抵抗は、彼女の前ではほとんど無意味だった。彼女は、私が避ければ避けるほど、それを『霊的資質の高い者が無意識に行う防衛本能』などと、彼女の都合の良いオカルト理論で解釈し、むしろ喜び勇んで追いかけてくるのだ。その執念は、もはやストーカーの域に達しているとさえ言えた。
今日もまた、昼休みを知らせるチャイムが鳴ると同時に、私は弁当を掴んで席を立った。目指すは屋上。今は立ち入り禁止になっているが、フェンスの鍵が壊れている場所を知っている。そこならば、彼女も追っては来られないだろう。
しかし、私の計画は、教室のドアにたどり着く前に、あっけなく頓挫した。
「サヤカ、お待ちになって」
腕を、ぐいと掴まれた。振り返るまでもない。この涼やかで、しかし有無を言わさぬ力強さを持つ声の主は、世界に一人しかいない。
「……何、レイカさん。私、急いでるんだけど」
私は、できるだけ不機嫌を隠さずにそう言った。腕を振り払おうとしたが、彼女の力は意外なほど強く、びくともしない。
「まあ、そんなに急がずともよろしいではありませんか。今日は、サヤカにぜひともお伝えしたい、素晴らしいお話があるのです」
素晴らしいお話。その言葉を聞いただけで、私の全身に警戒警報が鳴り響いた。彼女の言う『素晴らしい』は、私にとっては『この上なく迷惑』の同義語だ。
「悪いけど、興味ないから」
「まあ、そうおっしゃらずに。これは、サヤカにこそ聞いていただきたい、とっておきの怪談ですのよ?」
怪談。またその手の話か。私は、深く、深いため息をついた。もう、何度目になるか分からない。
「いい加減にしてよ。私は、そういう話は嫌いだって、いつも言ってるでしょ」
「ええ、存じておりますわ。ですが、今日の話は、ただの怪談ではございませんの。この、私たちの第一北高校に、古くから伝わる、由緒正しき伝承なのですから」
彼女は、私の抵抗などまるで意に介さず、その瞳をきらきらと輝かせている。その純粋な探求心に満ちた表情を見るだけで、私は、これから始まるであろう長話を予感し、頭が痛くなってくるのを感じた。
周囲のクラスメイトたちが、また始まった、とでも言いたげな顔で、こちらを遠巻きに見ている。その視線が、私の逃げ道を塞いでいた。
「ねえ、サヤカ。ご存じかしら? この学校の、北校舎の三階の一番端にある、今は使われていない空き教室のことを」
「……知らない」
「そこは、通称『お墓』と呼ばれておりますの」
お墓。その不吉な響きに、私は思わず顔をしかめた。レイカさんは、そんな私の反応を楽しんでいるかのように、にこりと微笑む。
「そして、その『お墓』には、一つだけ、ぽつんと机と椅子が置かれているそうですわ。そして、その席こそが、この学校に伝わる怪談の舞台……『決して座ってはいけない席』なのです」
彼女は、まるで舞台役者のように、芝居がかった口調でそう言った。その言葉に、周りで聞き耳を立てていた生徒たちが、小さく息を呑むのが分かった。どうやら、その怪談は、私以外の生徒たちには、ある程度知られているらしい。
「決して座ってはいけない席……。その席に座った者は、どうなるかご存じ?」
「……知らないし、知りたくもない」
「ふふ、そうおっしゃらずに。その席に座った生徒は、次の日、学校に来なくなるそうですわ」
「……ただの不登校でしょ、それ」
私の冷めたツッコミに、レイカさんは、いいえ、とゆっくりと首を振った。その表情は、いつになく真剣だった。
「ただ来なくなるのではございませんの。その生徒の存在そのものが、まるで初めからいなかったかのように、皆の記憶から、綺麗に消え去ってしまうのですわ」
その言葉に、教室の空気が、わずかに冷たくなったような気がした。記憶から、消える?
「クラスメイトも、先生も、親兄弟でさえも、その生徒のことを、誰も覚えていない。机も、ロッカーも、名簿からも、その生徒が生きていた痕跡は、全て消え失せる。まるで、神隠しのように……。いいえ、神隠しよりももっと残酷。誰からも忘れ去られ、たった一人で、この世ならざる場所に、永遠に囚われ続けるのです」
レイカさんの語りは、妙な説得力を持っていた。彼女が紡ぐ言葉は、ただの作り話とは思えない、奇妙な現実感を帯びて、聞く者の想像力を掻き立てる。周りの生徒たちも、固唾を飲んで彼女の話に聞き入っていた。
「そんなの、ただの作り話でしょ。誰かが面白がって広めた、よくある学校の怪談だよ」
私は、自分に言い聞かせるように、そう言った。そうだ、これはただの噂話だ。非科学的で、馬鹿馬鹿しい、子供だましの与太話に過ぎない。
「本当に、そうですかしら?」
レイカさんは、意味ありげに微笑むと、声を潜めて続けた。
「数年前、実際に、一人の生徒がその席に座ってしまった、という話がありますの。二年生の、大人しい女子生徒だったそうですわ。彼女は、その日の放課後、友人との他愛ない賭けで、その席に座ってしまった。そして、次の日……」
彼女は、そこで一度言葉を切った。教室の静寂が、いやに耳につく。
「彼女は、学校に来なかった。そして、誰も、彼女のことを覚えていなかった。クラス名簿からも、卒業アルバムからも、彼女の名前は綺麗に消えていたそうですわ。ただ一人、一緒にいた友人を除いては」
「……その友人が、全部でっち上げた話なんじゃないの」
「その友人は、必死に周りに訴えたそうですわ。『昨日まで、ここに彼女がいたんだ』と。けれど、誰も信じてはくれなかった。それどころか、頭がおかしくなったのだと、気味悪がられ、孤立していった。そして、その友人も、しばらくして、学校に来なくなってしまった……」
救いのない結末。それは、よくできたホラーストーリーの定石だ。けれど、レイカさんの口から語られると、それがまるで、つい最近、すぐ近くで起こった現実の事件のように聞こえてしまうから不思議だった。
「……で、その話が、私と何の関係があるの?」
私は、ようやく本題を切り出した。彼女が、ただ怪談を語りたかっただけではないことくらい、私にも分かっていた。
その問いに、レイカさんは、待ってましたとばかりに、ぱあっと顔を輝かせた。そして、私の手を、再び両手で、がっしと掴んだ。
「もちろん、大ありですわ!」
彼女は、高らかに、それはもう、実に高らかに、宣言した。
「この、現代に残された聖域とも言うべきミステリースポットを、この私と、そして『運命の友』であるサヤカとで、探訪しようではありませんか!」
やはり、そう来たか。
私は、心の底から、深くて長いため息をついた。もう、驚きもしない。彼女の発想が、常に私の予想の斜め上を行くことには、慣れてしまった。
「絶対に、嫌」
私は、きっぱりと、そして明確に、そう言い放った。掴まれた手を、今度こそ、力ずくで振り払う。
「冗談じゃない。どうして私が、そんな気味の悪い場所に行かなきゃいけないの。私は、オカルトも、怪談も、心霊スポットも、全部、全部、大嫌いなの!」
思わず、声が大きくなる。教室中の視線が、面白いほど綺麗に、私と彼女の二人に集中した。誰もが、何が起こっているのか理解できず、ただ呆然とこちらを見ている。もちろん、私もその一人だ。
「もう、あなたの趣味に付き合うのは、うんざりなの! 私の平穏な日常を返してよ!」
溜まりに溜まった鬱憤が、堰を切ったように溢れ出した。もう、周りの目など気にしていられなかった。
『鮫島事件』の濡れ衣も、『心霊写真』の投稿も、そして、あの悪夢の『コトリバコ弁当』も。これまでの、彼女から受けた全ての迷惑行為が、私の頭の中で、ぐるぐると回り続けていた。
私の剣幕に、さすがのレイカさんも、一瞬、虚を突かれたような顔をした。そのアーモンド形の瞳が、驚きに見開かれている。
やった。ようやく、私の気持ちが、少しは通じたかもしれない。
そんな淡い期待が、私の胸をよぎった。
しかし、その期待は、次の瞬間に、音を立てて崩れ去ることになる。
レイカさんは、私の剣幕に怯むどころか、むしろ、うっとりとした表情で、ほう、と感嘆のため息を漏らしたのだ。
「……素晴らしい」
彼女は、ぽつりと、そう呟いた。
「え……?」
聞き間違いだろうか。今、この人、素晴らしい、と。
「素晴らしいですわ、サヤカ! その、魂の底からの拒絶! それこそが、あなたが本物の霊的資質の持ち主である、何よりの証拠ですわ!」
彼女は、恍惚とした表情で、そう断言した。その瞳は、もう私を見ていなかった。彼女は、彼女自身の作り上げた世界の中で、一人、壮大な物語を紡いでいる。
ダメだ。この人には、何を言っても、通じない。
常識が、とか、プライバシーが、とか、そういう次元の話ではないのだ。彼女は、私の怒りさえも、彼女のオカルトフィルターを通して、ポジティブなエネルギーに変換してしまうのだ。
「感受性の強い人間ほど、危険な場所を本能的に察知し、避けようとするものですわ。あなたのその強い拒絶反応は、まさに、その『お墓』が、本物の怪異が渦巻く場所であることの裏返し! ああ、私の見立てに、間違いはなかった……!」
彼女は、一人で興奮し、一人で納得し、そして、再び、その燃えるような視線を私に向けた。
「やはり、あなたしかいませんわ、サヤカ。私の、唯一無二のパートナーとして、この謎に挑む資格があるのは」
「だから、嫌だって言ってるでしょ!」
「大丈夫ですわ。私に、策がありますもの」
彼女は、自信満々にそう言うと、どこから取り出したのか、小さな巾着袋を私の目の前に突きつけた。中から、じゃらり、と乾いた音がする。
「これは、私が懇意にしている神社の宮司様から、特別に譲っていただいた、清めの塩ですわ。古来より、塩には邪気を払う力があるとされてきました。これさえあれば、いかなる悪霊も、私たちに手出しはできません」
「そんなもの、気休めにしかならないでしょ!」
「気休めなどではございませんわ。これは、伊勢神宮の御神域で採取された、特別な岩塩を、満月の光に三日三晩晒し、さらに祝詞を九十九回唱えて清めた、超弩級の霊的アイテムなのですから!」
彼女が熱っぽく語る、その塩のありがたい由来など、私にはどうでもよかった。問題は、そこではない。
「それに、万が一のことがあったとしても、ご安心くださいな。私、西園寺家のコネクションを使い、日本屈指の霊能力者の方々を、すでに数名、スタンバイさせてありますの。何かあれば、すぐに駆けつけてくださる手筈になっておりますわ」
「……それ、本当なの?」
「ええ、もちろん。高名なイタコの方から、現代的な除霊を行うサイキッカーの方まで、多種多様な専門家を揃えております。報酬は、成功報酬で一件あたり数百万円から、と少々お高めでしたけれど」
彼女は、こともなげにそう言った。数百万円。その、あまりにも現実離れした金額に、私の思考は、一瞬、停止した。この人は、本気だ。本気で、そんなことに、大金をつぎ込んでいる。
私の絶望をよそに、レイカさんの独演会は続く。
「さあ、サヤカ。もう、何も恐れることはありませんわ。全ての準備は、整いました。あとは、あなたが、その一歩を踏み出すだけなのです」
彼女は、私の両肩を、がっしと掴んだ。その瞳には、一点の曇りもない、純粋な期待の色が浮かんでいる。
「共に、真実の扉を開きましょう。この手で!」
その言葉を合図にしたかのように、昼休みを知らせるチャイムが、無情にも鳴り響いた。
周りの生徒たちは、弁当を広げたり、グループで教室を出て行ったりと、それぞれの昼休みを始めている。その喧騒の中で、私とレイカさんだけが、まるで舞台の上の演者のように、取り残されていた。
もう、どうにでもなれ。
私の心の中で、何かが、ぷつりと、切れた。抵抗する気力も、怒るエネルギーも、もう、残っていなかった。
私は、ただ、力なく、こくりと頷くことしかできなかった。
その瞬間、レイカさんの顔が、ぱあっと、花が咲くように輝いた。
「ああ、サヤカ! やはり、あなたなら、分かってくださると信じておりましたわ!」
彼女は、心底嬉しそうにそう言うと、私を力強く抱きしめた。ふわりと、いつもの、品のいい花の香りが、私の鼻先をかすめる。
その温かさが、なぜだか、ひどく、虚しかった。
◇
放課後を告げるチャイムが鳴り響く。その音は、私にとって、死刑執行の宣告のように聞こえた。
私は、重たい体を引きずるようにして、カバンに教科書を詰めた。隣の席では、レイカさんが、実に楽しそうに鼻歌などを歌いながら、探検の準備を整えている。その手には、昼間に見せられた清めの塩の入った巾着袋の他に、方位磁石や、何やら怪しげな文様の描かれたお札のようなものまで握られていた。彼女は、本気で、ピクニックにでも行くかのような気分なのだろう。
「準備はよろしいですこと? サヤカ」
「……まあね」
気の抜けた返事をすると、彼女は満足げに頷き、意気揚々と席を立った。
「では、参りましょう。私たちの記念すべき、怪談探索へ!」
こうして、私は、レイカさんに引きずられるようにして、問題の場所とされる北校舎へと向かうことになった。
南校舎と北校舎を繋ぐ渡り廊下を歩く。窓の外では、運動部の生徒たちが、元気な掛け声を上げながら練習に励んでいた。それは、いつもと変わらない、平和な放課後の光景だった。しかし、今から私たちが向かおうとしている場所だけが、その平和な日常から、切り離されているように感じられた。
「北校舎は、この学校ができた当初からある、何の変哲もない校舎、そして、建物ですの。」
レイカさんは、まるでツアーガイドのように、流暢な口調で説明を始めた。
「ただ、私たちが目指す『お墓』は、三階の一番奥。元々は、物置として使われていた教室らしいのですが、いつからか、誰も近寄らなくなったそうです。備品を取りに行った教師が、そこで原因不明の高熱を出して倒れたり、掃除に入った生徒が、誰もいないはずの教室で、人の話し声を聞いたり……。そういった、小さな怪異が積み重なり、いつしか、そこは禁足地となったのですわ」
聞きたくもない情報を、彼女は次々と私の耳に流し込んでくる。そのたびに、私の足取りは、その怪談を聞けば聞くほど重くなっていった。
北校舎の階段を上る。一階、二階と上がるにつれて、周囲の喧騒が遠ざかり、空気がひんやりとしてくるような気がした。壁や床のタイルの様子は変わらないが、怪談を聞いた心が何か周囲の雰囲気を感じてしまう。
「そして、私たちが目指す『お墓』は、三階の一番奥。元々は、物置として使われていた教室らしいのですが、いつからか、誰も近寄らなくなったそうです。備品を取りに行った教師が、そこで原因不明の高熱を出して倒れたり、掃除に入った生徒が、誰もいないはずの教室で、人の話し声を聞いたり……。そういった、小さな怪異が積み重なり、いつしか、そこは禁足地となったのですわ」
聞きたくもない情報を、彼女は次々と私の耳に流し込んでくる。そのたびに、私の足取りは、さらに重さを増していった。
「……ねえ、やっぱり、やめない?」
三階にたどり着いた時、私は、最後の抵抗を試みた。
「今からでも、引き返そうよ。こんなの絶対におかしいよ」
「まあ、サヤカ。何を今更おっしゃいますの」
レイカさんは、呆れたように、しかし、どこか楽しそうに、くすくすと笑った。
「ここまで来て、引き返すなどという選択肢は、ございませんわ。それに、ごらんなさい。もう、すぐそこですわよ」
彼女が指差した先。薄暗い廊下の、一番突き当たりに、一つのドアが見えた。他の教室のドアと何ら違わない。
空き教室のようで、ドアの上には、プレートが取り付けられていた跡があるが、今は何もない。
ごくり、と喉が鳴った。自分でも気づかないうちに、息を詰めていたらしい。
レイカさんは、私の緊張などお構いなしに、そのドアへと、まっすぐに歩いていく。そして、その空き教室のドアにためらうことなく手をかけた。
その顔は、未知との遭遇を前にした、純粋な喜びに満ち溢れていた。
私の日常は、もはや私の知るそれとは似ても似つかないものへと変貌を遂げていた。『コトリバコ弁当』事件は、瞬く間に学年中に知れ渡り、私はすっかり有名人になってしまった。もちろん、悪い意味で。
廊下を歩けば、ひそひそと囁かれる。『あれが西園寺様のお友達の……』『指の弁当食べさせられそうになった子でしょ?』『なんかヤバい人らしいよ』。その一つ一つが、小さな針のように私の心をちくちくと刺す。もはや、教室の隅で静かに過ごすことなど、夢のまた夢だった。
そして、その全ての元凶である西園寺レイカさんは、そんな私の苦悩などどこ吹く風、といった様子で、毎日を謳歌していた。彼女の周りには常に人が集まり、その中心で彼女は、私の『霊的資質の高さ』や、いかに私たちが『運命の友』であるかを、嬉々として語るのだ。そのたびに、周囲の生徒たちは、面白がるような、あるいは同情するような、複雑な視線を私に向ける。私は、まるで檻の中の見世物になったような気分だった。
私は、レイカさんに対して、明確な『拒絶』の態度を取るようになっていた。休み時間になれば、彼女が話しかけてくる前に教室を飛び出し、昼休みは人の少ない中庭のベンチで一人、息を潜めるようにして過ごす。彼女からのメッセージには当たり障りのない返信だけを返し、決して会話が続かないように細心の注意を払った。
しかし、そんな私のささやかな抵抗は、彼女の前ではほとんど無意味だった。彼女は、私が避ければ避けるほど、それを『霊的資質の高い者が無意識に行う防衛本能』などと、彼女の都合の良いオカルト理論で解釈し、むしろ喜び勇んで追いかけてくるのだ。その執念は、もはやストーカーの域に達しているとさえ言えた。
今日もまた、昼休みを知らせるチャイムが鳴ると同時に、私は弁当を掴んで席を立った。目指すは屋上。今は立ち入り禁止になっているが、フェンスの鍵が壊れている場所を知っている。そこならば、彼女も追っては来られないだろう。
しかし、私の計画は、教室のドアにたどり着く前に、あっけなく頓挫した。
「サヤカ、お待ちになって」
腕を、ぐいと掴まれた。振り返るまでもない。この涼やかで、しかし有無を言わさぬ力強さを持つ声の主は、世界に一人しかいない。
「……何、レイカさん。私、急いでるんだけど」
私は、できるだけ不機嫌を隠さずにそう言った。腕を振り払おうとしたが、彼女の力は意外なほど強く、びくともしない。
「まあ、そんなに急がずともよろしいではありませんか。今日は、サヤカにぜひともお伝えしたい、素晴らしいお話があるのです」
素晴らしいお話。その言葉を聞いただけで、私の全身に警戒警報が鳴り響いた。彼女の言う『素晴らしい』は、私にとっては『この上なく迷惑』の同義語だ。
「悪いけど、興味ないから」
「まあ、そうおっしゃらずに。これは、サヤカにこそ聞いていただきたい、とっておきの怪談ですのよ?」
怪談。またその手の話か。私は、深く、深いため息をついた。もう、何度目になるか分からない。
「いい加減にしてよ。私は、そういう話は嫌いだって、いつも言ってるでしょ」
「ええ、存じておりますわ。ですが、今日の話は、ただの怪談ではございませんの。この、私たちの第一北高校に、古くから伝わる、由緒正しき伝承なのですから」
彼女は、私の抵抗などまるで意に介さず、その瞳をきらきらと輝かせている。その純粋な探求心に満ちた表情を見るだけで、私は、これから始まるであろう長話を予感し、頭が痛くなってくるのを感じた。
周囲のクラスメイトたちが、また始まった、とでも言いたげな顔で、こちらを遠巻きに見ている。その視線が、私の逃げ道を塞いでいた。
「ねえ、サヤカ。ご存じかしら? この学校の、北校舎の三階の一番端にある、今は使われていない空き教室のことを」
「……知らない」
「そこは、通称『お墓』と呼ばれておりますの」
お墓。その不吉な響きに、私は思わず顔をしかめた。レイカさんは、そんな私の反応を楽しんでいるかのように、にこりと微笑む。
「そして、その『お墓』には、一つだけ、ぽつんと机と椅子が置かれているそうですわ。そして、その席こそが、この学校に伝わる怪談の舞台……『決して座ってはいけない席』なのです」
彼女は、まるで舞台役者のように、芝居がかった口調でそう言った。その言葉に、周りで聞き耳を立てていた生徒たちが、小さく息を呑むのが分かった。どうやら、その怪談は、私以外の生徒たちには、ある程度知られているらしい。
「決して座ってはいけない席……。その席に座った者は、どうなるかご存じ?」
「……知らないし、知りたくもない」
「ふふ、そうおっしゃらずに。その席に座った生徒は、次の日、学校に来なくなるそうですわ」
「……ただの不登校でしょ、それ」
私の冷めたツッコミに、レイカさんは、いいえ、とゆっくりと首を振った。その表情は、いつになく真剣だった。
「ただ来なくなるのではございませんの。その生徒の存在そのものが、まるで初めからいなかったかのように、皆の記憶から、綺麗に消え去ってしまうのですわ」
その言葉に、教室の空気が、わずかに冷たくなったような気がした。記憶から、消える?
「クラスメイトも、先生も、親兄弟でさえも、その生徒のことを、誰も覚えていない。机も、ロッカーも、名簿からも、その生徒が生きていた痕跡は、全て消え失せる。まるで、神隠しのように……。いいえ、神隠しよりももっと残酷。誰からも忘れ去られ、たった一人で、この世ならざる場所に、永遠に囚われ続けるのです」
レイカさんの語りは、妙な説得力を持っていた。彼女が紡ぐ言葉は、ただの作り話とは思えない、奇妙な現実感を帯びて、聞く者の想像力を掻き立てる。周りの生徒たちも、固唾を飲んで彼女の話に聞き入っていた。
「そんなの、ただの作り話でしょ。誰かが面白がって広めた、よくある学校の怪談だよ」
私は、自分に言い聞かせるように、そう言った。そうだ、これはただの噂話だ。非科学的で、馬鹿馬鹿しい、子供だましの与太話に過ぎない。
「本当に、そうですかしら?」
レイカさんは、意味ありげに微笑むと、声を潜めて続けた。
「数年前、実際に、一人の生徒がその席に座ってしまった、という話がありますの。二年生の、大人しい女子生徒だったそうですわ。彼女は、その日の放課後、友人との他愛ない賭けで、その席に座ってしまった。そして、次の日……」
彼女は、そこで一度言葉を切った。教室の静寂が、いやに耳につく。
「彼女は、学校に来なかった。そして、誰も、彼女のことを覚えていなかった。クラス名簿からも、卒業アルバムからも、彼女の名前は綺麗に消えていたそうですわ。ただ一人、一緒にいた友人を除いては」
「……その友人が、全部でっち上げた話なんじゃないの」
「その友人は、必死に周りに訴えたそうですわ。『昨日まで、ここに彼女がいたんだ』と。けれど、誰も信じてはくれなかった。それどころか、頭がおかしくなったのだと、気味悪がられ、孤立していった。そして、その友人も、しばらくして、学校に来なくなってしまった……」
救いのない結末。それは、よくできたホラーストーリーの定石だ。けれど、レイカさんの口から語られると、それがまるで、つい最近、すぐ近くで起こった現実の事件のように聞こえてしまうから不思議だった。
「……で、その話が、私と何の関係があるの?」
私は、ようやく本題を切り出した。彼女が、ただ怪談を語りたかっただけではないことくらい、私にも分かっていた。
その問いに、レイカさんは、待ってましたとばかりに、ぱあっと顔を輝かせた。そして、私の手を、再び両手で、がっしと掴んだ。
「もちろん、大ありですわ!」
彼女は、高らかに、それはもう、実に高らかに、宣言した。
「この、現代に残された聖域とも言うべきミステリースポットを、この私と、そして『運命の友』であるサヤカとで、探訪しようではありませんか!」
やはり、そう来たか。
私は、心の底から、深くて長いため息をついた。もう、驚きもしない。彼女の発想が、常に私の予想の斜め上を行くことには、慣れてしまった。
「絶対に、嫌」
私は、きっぱりと、そして明確に、そう言い放った。掴まれた手を、今度こそ、力ずくで振り払う。
「冗談じゃない。どうして私が、そんな気味の悪い場所に行かなきゃいけないの。私は、オカルトも、怪談も、心霊スポットも、全部、全部、大嫌いなの!」
思わず、声が大きくなる。教室中の視線が、面白いほど綺麗に、私と彼女の二人に集中した。誰もが、何が起こっているのか理解できず、ただ呆然とこちらを見ている。もちろん、私もその一人だ。
「もう、あなたの趣味に付き合うのは、うんざりなの! 私の平穏な日常を返してよ!」
溜まりに溜まった鬱憤が、堰を切ったように溢れ出した。もう、周りの目など気にしていられなかった。
『鮫島事件』の濡れ衣も、『心霊写真』の投稿も、そして、あの悪夢の『コトリバコ弁当』も。これまでの、彼女から受けた全ての迷惑行為が、私の頭の中で、ぐるぐると回り続けていた。
私の剣幕に、さすがのレイカさんも、一瞬、虚を突かれたような顔をした。そのアーモンド形の瞳が、驚きに見開かれている。
やった。ようやく、私の気持ちが、少しは通じたかもしれない。
そんな淡い期待が、私の胸をよぎった。
しかし、その期待は、次の瞬間に、音を立てて崩れ去ることになる。
レイカさんは、私の剣幕に怯むどころか、むしろ、うっとりとした表情で、ほう、と感嘆のため息を漏らしたのだ。
「……素晴らしい」
彼女は、ぽつりと、そう呟いた。
「え……?」
聞き間違いだろうか。今、この人、素晴らしい、と。
「素晴らしいですわ、サヤカ! その、魂の底からの拒絶! それこそが、あなたが本物の霊的資質の持ち主である、何よりの証拠ですわ!」
彼女は、恍惚とした表情で、そう断言した。その瞳は、もう私を見ていなかった。彼女は、彼女自身の作り上げた世界の中で、一人、壮大な物語を紡いでいる。
ダメだ。この人には、何を言っても、通じない。
常識が、とか、プライバシーが、とか、そういう次元の話ではないのだ。彼女は、私の怒りさえも、彼女のオカルトフィルターを通して、ポジティブなエネルギーに変換してしまうのだ。
「感受性の強い人間ほど、危険な場所を本能的に察知し、避けようとするものですわ。あなたのその強い拒絶反応は、まさに、その『お墓』が、本物の怪異が渦巻く場所であることの裏返し! ああ、私の見立てに、間違いはなかった……!」
彼女は、一人で興奮し、一人で納得し、そして、再び、その燃えるような視線を私に向けた。
「やはり、あなたしかいませんわ、サヤカ。私の、唯一無二のパートナーとして、この謎に挑む資格があるのは」
「だから、嫌だって言ってるでしょ!」
「大丈夫ですわ。私に、策がありますもの」
彼女は、自信満々にそう言うと、どこから取り出したのか、小さな巾着袋を私の目の前に突きつけた。中から、じゃらり、と乾いた音がする。
「これは、私が懇意にしている神社の宮司様から、特別に譲っていただいた、清めの塩ですわ。古来より、塩には邪気を払う力があるとされてきました。これさえあれば、いかなる悪霊も、私たちに手出しはできません」
「そんなもの、気休めにしかならないでしょ!」
「気休めなどではございませんわ。これは、伊勢神宮の御神域で採取された、特別な岩塩を、満月の光に三日三晩晒し、さらに祝詞を九十九回唱えて清めた、超弩級の霊的アイテムなのですから!」
彼女が熱っぽく語る、その塩のありがたい由来など、私にはどうでもよかった。問題は、そこではない。
「それに、万が一のことがあったとしても、ご安心くださいな。私、西園寺家のコネクションを使い、日本屈指の霊能力者の方々を、すでに数名、スタンバイさせてありますの。何かあれば、すぐに駆けつけてくださる手筈になっておりますわ」
「……それ、本当なの?」
「ええ、もちろん。高名なイタコの方から、現代的な除霊を行うサイキッカーの方まで、多種多様な専門家を揃えております。報酬は、成功報酬で一件あたり数百万円から、と少々お高めでしたけれど」
彼女は、こともなげにそう言った。数百万円。その、あまりにも現実離れした金額に、私の思考は、一瞬、停止した。この人は、本気だ。本気で、そんなことに、大金をつぎ込んでいる。
私の絶望をよそに、レイカさんの独演会は続く。
「さあ、サヤカ。もう、何も恐れることはありませんわ。全ての準備は、整いました。あとは、あなたが、その一歩を踏み出すだけなのです」
彼女は、私の両肩を、がっしと掴んだ。その瞳には、一点の曇りもない、純粋な期待の色が浮かんでいる。
「共に、真実の扉を開きましょう。この手で!」
その言葉を合図にしたかのように、昼休みを知らせるチャイムが、無情にも鳴り響いた。
周りの生徒たちは、弁当を広げたり、グループで教室を出て行ったりと、それぞれの昼休みを始めている。その喧騒の中で、私とレイカさんだけが、まるで舞台の上の演者のように、取り残されていた。
もう、どうにでもなれ。
私の心の中で、何かが、ぷつりと、切れた。抵抗する気力も、怒るエネルギーも、もう、残っていなかった。
私は、ただ、力なく、こくりと頷くことしかできなかった。
その瞬間、レイカさんの顔が、ぱあっと、花が咲くように輝いた。
「ああ、サヤカ! やはり、あなたなら、分かってくださると信じておりましたわ!」
彼女は、心底嬉しそうにそう言うと、私を力強く抱きしめた。ふわりと、いつもの、品のいい花の香りが、私の鼻先をかすめる。
その温かさが、なぜだか、ひどく、虚しかった。
◇
放課後を告げるチャイムが鳴り響く。その音は、私にとって、死刑執行の宣告のように聞こえた。
私は、重たい体を引きずるようにして、カバンに教科書を詰めた。隣の席では、レイカさんが、実に楽しそうに鼻歌などを歌いながら、探検の準備を整えている。その手には、昼間に見せられた清めの塩の入った巾着袋の他に、方位磁石や、何やら怪しげな文様の描かれたお札のようなものまで握られていた。彼女は、本気で、ピクニックにでも行くかのような気分なのだろう。
「準備はよろしいですこと? サヤカ」
「……まあね」
気の抜けた返事をすると、彼女は満足げに頷き、意気揚々と席を立った。
「では、参りましょう。私たちの記念すべき、怪談探索へ!」
こうして、私は、レイカさんに引きずられるようにして、問題の場所とされる北校舎へと向かうことになった。
南校舎と北校舎を繋ぐ渡り廊下を歩く。窓の外では、運動部の生徒たちが、元気な掛け声を上げながら練習に励んでいた。それは、いつもと変わらない、平和な放課後の光景だった。しかし、今から私たちが向かおうとしている場所だけが、その平和な日常から、切り離されているように感じられた。
「北校舎は、この学校ができた当初からある、何の変哲もない校舎、そして、建物ですの。」
レイカさんは、まるでツアーガイドのように、流暢な口調で説明を始めた。
「ただ、私たちが目指す『お墓』は、三階の一番奥。元々は、物置として使われていた教室らしいのですが、いつからか、誰も近寄らなくなったそうです。備品を取りに行った教師が、そこで原因不明の高熱を出して倒れたり、掃除に入った生徒が、誰もいないはずの教室で、人の話し声を聞いたり……。そういった、小さな怪異が積み重なり、いつしか、そこは禁足地となったのですわ」
聞きたくもない情報を、彼女は次々と私の耳に流し込んでくる。そのたびに、私の足取りは、その怪談を聞けば聞くほど重くなっていった。
北校舎の階段を上る。一階、二階と上がるにつれて、周囲の喧騒が遠ざかり、空気がひんやりとしてくるような気がした。壁や床のタイルの様子は変わらないが、怪談を聞いた心が何か周囲の雰囲気を感じてしまう。
「そして、私たちが目指す『お墓』は、三階の一番奥。元々は、物置として使われていた教室らしいのですが、いつからか、誰も近寄らなくなったそうです。備品を取りに行った教師が、そこで原因不明の高熱を出して倒れたり、掃除に入った生徒が、誰もいないはずの教室で、人の話し声を聞いたり……。そういった、小さな怪異が積み重なり、いつしか、そこは禁足地となったのですわ」
聞きたくもない情報を、彼女は次々と私の耳に流し込んでくる。そのたびに、私の足取りは、さらに重さを増していった。
「……ねえ、やっぱり、やめない?」
三階にたどり着いた時、私は、最後の抵抗を試みた。
「今からでも、引き返そうよ。こんなの絶対におかしいよ」
「まあ、サヤカ。何を今更おっしゃいますの」
レイカさんは、呆れたように、しかし、どこか楽しそうに、くすくすと笑った。
「ここまで来て、引き返すなどという選択肢は、ございませんわ。それに、ごらんなさい。もう、すぐそこですわよ」
彼女が指差した先。薄暗い廊下の、一番突き当たりに、一つのドアが見えた。他の教室のドアと何ら違わない。
空き教室のようで、ドアの上には、プレートが取り付けられていた跡があるが、今は何もない。
ごくり、と喉が鳴った。自分でも気づかないうちに、息を詰めていたらしい。
レイカさんは、私の緊張などお構いなしに、そのドアへと、まっすぐに歩いていく。そして、その空き教室のドアにためらうことなく手をかけた。
その顔は、未知との遭遇を前にした、純粋な喜びに満ち溢れていた。