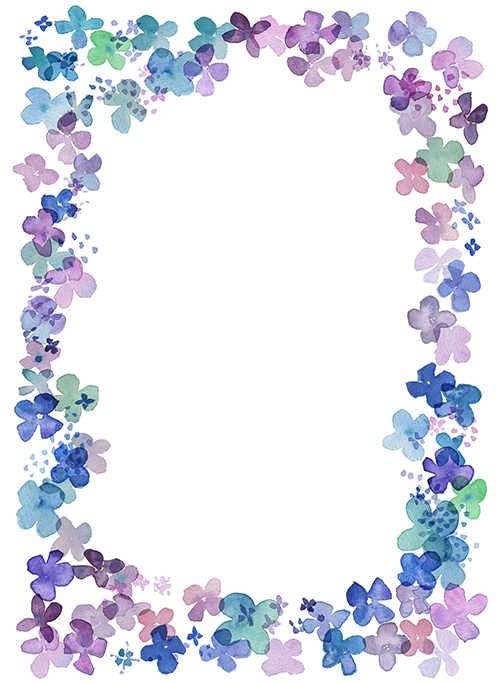翌朝、私の意識は重たい泥の底から無理やり引きずり出されるようにして浮上した。スマートフォンのアラームが、けたたましく鳴り響いている。いつもと同じ時間、いつもと同じ音のはずなのに、今日のそれは、まるで私の頭蓋骨に直接響いてくるかのような不快な音だった。のろのろと手を伸ばしてそれを止めると、部屋はしんと静まり返る。その静寂が、かえって私の孤独と不安を際立たせた。
ベッドから起き上がる気力が、どうしても湧いてこない。瞼の裏に焼き付いているのは、昨夜、クラスメイトから送りつけられてきた、あの悪趣味な写真。私の姿、その周りに浮かぶ白い球体、そして黒い靄。何よりも、それに添えられた『運命の友、サヤカさんの背後霊ですわ♡』という、悪意なき悪意に満ちた一文。
西園寺レイカ。
その名前を心の中で反芻するだけで、胃のあたりがずしりと重くなるのを感じた。彼女と出会って、まだたったの一日。それなのに、私の日常は、もう原形を留めていない。平穏だった昨日までの日々が、まるで遠い昔のことのように思えた。
学校へ行きたくない。
心の底から、そう思った。教室に入った瞬間、クラス中の視線が私に集まるのが目に見えるようだ。『鮫島さん、マジでヤバい人だったんだ』『レイカ様、逃げてー!』。メッセージアプリに書き込まれていた、心ない言葉の数々が、脳内で繰り返し再生される。笑いものにされるか、あるいは気味悪がられて距離を置かれるか。どちらにしても、私が今まで築き上げてきた、目立たず、誰とも深く関わらない、安全なテリトリーは、もう存在しないのだ。
そして何より、あの張本人の顔を、平常心で見られる自信がなかった。きっと彼女は、いつものように優雅な微笑みを浮かべて、当たり前のように私の隣の席に座っているのだろう。昨夜の私の怒りなど、まるで意に介していないかのように。彼女にとっては、あれは『友情の証』であり、『霊的資質の証明』なのだから。話が通じない相手と向き合うことが、これほどまでに精神を消耗させるものだとは、今まで知らなかった。
しかし、私には学校を休むという選択肢はなかった。そんなことをすれば、かえって噂に拍車をかけるだけだ。それに、ここで逃げ出してしまえば、私は本当に『厄災』に負けたことになる。それは、私のけちなプライドが許さなかった。
私は、重たい体を無理やり起こすと、機械的に制服へと着替えた。顔を洗い、髪をとかし、朝食を喉に流し込む。その一つ一つの動作が、ひどく億劫だった。
「いってきます」
誰に言うでもなくそう呟いて玄関のドアを開ける。いつもと同じ通学路。けれど、見える風景は、どこか色褪せて見えた。道端の電柱も、住宅の塀も、すれ違う人々の顔も、全てが私を監視しているように感じられる。自意識過剰だとは分かっている。けれど、一度植え付けられた疑心暗鬼は、そう簡単には消えてくれなかった。
校門をくぐり、昇降口で靴を履き替える。廊下を歩いていると、すれ違う生徒たちが、ちらりと私を見て、ひそひそと何かを囁き合っているのが分かった。気のせいではない。彼らの視線には、明らかに昨日までとは違う種類の好奇の色が含まれていた。
ああ、もう始まっている。
私は、できるだけ表情を変えないように努めながら、自分の教室へと向かった。教室の引き戸に手をかける。この扉の向こうには、私の日常を破壊した元凶と、その結果生まれた好奇と嘲笑の視線が待っている。深呼吸を一つ。そして、意を決して、扉を開けた。
予想通り、教室の中にいた生徒たちの視線が、一斉に私へと向けられた。それは一瞬のことで、すぐにそれぞれがおしゃべりに戻っていったが、その一瞬の沈黙が、私の心に重くのしかかる。
私は、誰とも視線を合わせないようにしながら、自分の席へと向かった。そして、そこに、彼女はいた。
西園寺レイカさんは、すでに席に着き、優雅な仕草でハードカバーの本を読んでいた。朝の光が彼女の長い黒髪を照らし、まるで一枚の絵画のようだ。私が近づいたことに気づくと、彼女は本から顔を上げ、ふわりと微笑んだ。
「おはようございます、サヤカ」
その声も、表情も、いつもと何も変わらない。昨夜、メッセージアプリであれだけのやり取りをしたことなど、まるでなかったかのような、完璧なまでの普段通り。その態度に、私の胸の奥で、怒りとも呆れともつかない感情が、黒い煙のように立ち上った。
「……おはよう」
私は、かろうじてそれだけを返すと、乱暴に椅子を引いて席に着いた。カバンを机の横にかけ、教科書の準備を始める。その間も、レイカさんの視線がこちらに向けられているのを感じたが、私は意地でも彼女の方を見ようとはしなかった。
やがて、ホームルームを告げるチャイムが鳴り、担任が入ってくる。いつもと同じ、退屈な連絡事項。けれど、その内容も、ほとんど私の頭には入ってこなかった。ただ、早く時間が過ぎてほしい。早く、この地獄のような一日が終わってほしい。そればかりを考えていた。
◇
午前中の授業は、まさに苦行そのものだった。
教師が黒板に向かって何かを説明している間も、私は周囲の視線から逃れることができなかった。ノートを取るふりをしながら、すぐ隣に座るレイカさんの気配を、嫌でも感じてしまう。彼女は、時折こちらに何か言いたげな視線を向けてくるが、私がそれに気づかないふりをしていると、やがて諦めたように正面を向く。その繰り返しだった。
休み時間になれば、状況はさらに悪化した。クラスメイトたちが、遠巻きに、しかし明らかに私とレイカさんの様子を窺っている。何人かの女子生徒が、おそるおそるといった体で私の机に近づいてきた。
「ねえ、鮫島さん……。昨日の写真、見たよ」
「あれ、本物なの? なんか、すごいね……」
彼女たちの声には、面白がる気持ちと、気味悪がる気持ちが、半々くらいで含まれているように聞こえた。私は、引きつった笑みを浮かべることしかできない。
「さあ、どうなんだろうね。私もよく分からなくて」
曖昧にそう答えると、彼女たちは顔を見合わせ、困ったような、それでいて納得したような表情で去っていく。そんなやり取りを、何度か繰り返した。そのたびに、私の精神は少しずつ、だが確実に削られていった。
一方のレイカさんは、そんな私の苦悩などどこ吹く風、といった様子だった。彼女の周りには、相変わらず人が集まっている。けれど、その話題の中心は、昨日までとは少し違っていた。
「レイカさん、あの写真、どうやって撮ったの?」
「鮫島さんって、やっぱり何か特別な力がある人なんですか?」
質問の多くが、私に関連することだった。そしてレイカさんは、その一つ一つに、実に嬉々として答えている。
「ふふ、企業秘密ですわ。ですが、一つだけ言えるのは、サヤカが類い稀なる霊的資質の持ち主である、ということです」
「彼女の周りには、常に高位の霊的存在が集まってくるのです。私の目には、それがはっきりと見えますもの」
聞いているだけで、頭が痛くなってくる。彼女がそうやって面白おかしく語れば語るほど、私の『ヤバい人』というイメージは、クラスの中で確固たるものになっていく。もう、誰も私を『普通のクラスメイト』としては見てくれないだろう。
私は、机に突っ伏して、ただ時間が過ぎるのを待った。耳を塞ぎたい衝動に駆られたが、そんなことをすれば、さらに奇異の目で見られるだけだ。
早く、昼休みになってほしい。そうすれば、食堂にでも逃げ込んで、一人で静かに過ごせる。今日こそは、絶対に彼女のペースに巻き込まれたりしない。私は、固く、固く、そう決意していた。
そして、ようやく、その時は来た。四時間目の終わりを告げるチャイムが、解放の鐘のように鳴り響く。
「よし……」
私は、誰にも聞こえないくらいの声で呟くと、弁当を掴んで、素早く席を立った。一刻も早く、この教室から脱出する。その一心だった。
しかし、そんな私のささやかな希望は、いとも簡単に打ち砕かれた。
「サヤカ、お待ちになって」
背後からかけられた、涼やかな声。振り返るまでもない。西園寺レイカさん、その人だ。
私は、無視してそのまま歩き去ろうか、と一瞬本気で考えた。けれど、教室中の視線が突き刺さるこの状況で、そんな行動を取る勇気は、残念ながら私にはなかった。
私は、ゆっくりと、本当にゆっくりと、振り返った。そこには、予想通り、にこやかな表情のレイカさんが立っていた。
「……何?」
我ながら、ずいぶんと刺々しい声が出たと思う。だが、今の私には、これ以上愛想よく振る舞う余裕はなかった。
私のその態度に、レイカさんは、一瞬だけ、きょとんとした表情を見せた。しかし、すぐにいつもの優雅な微笑みに戻ると、深く、そして厳かに、頭を下げた。
「サヤカ。昨夜は、大変申し訳ありませんでした」
その、あまりにも予想外の言葉に、私は、思わず自分の耳を疑った。
謝罪?
この、西園寺レイカが?
私の怒りが、ようやく彼女に届いたのだろうか。だとしたら、少しは、ほんの少しだけ、見直してやってもいいかもしれない。私の胸に、淡い期待が芽生えた。
しかし、その期待が、いかに見当違いなものであったかを、私は次の瞬間に思い知らされることになる。
顔を上げたレイカさんは、真剣な、それでいてどこか憐れむような眼差しで、私を見つめていた。
「私の配慮が、あまりにも足りませんでしたわ。あのような形で、ご自身の偉大な力を公にされて、さぞかし驚かれたことでしょう。人知を超えた力を持つがゆえの孤独……。そのお気持ち、お察しいたします」
……は?
私の頭の中が、一瞬、真っ白になった。
今、この人、何て言った?
配慮が足りなかった? 驚かせたことに対して、謝っている? そうじゃない。私が怒っているのは、そこじゃない。勝手に写真を撮って、勝手に加工して、勝手にネットに晒したことに対してだろうが。
私の内心の叫びなど、もちろん彼女に届くはずもない。レイカさんは、一人で納得したように、こくこくと頷いている。
「ですが、ご安心くださいな。そんなサヤカのために、お詫びと言ってはなんですが、今日は私が、特別なものを用意してまいりましたの」
そう言うと、彼女は自分のカバンから、何かを取り出した。
それは、およそ弁当箱と呼ぶには、あまりにも異様な代物だった。
古びた、黒ずんだ木で組まれた、小さな箱。大きさは、一般的な弁当箱より一回り大きいくらいだろうか。しかし、その表面には、見たこともない、不気味な文様のようなものがびっしりと刻まれている。継ぎ目は荒く、まるで素人が無理やり釘で打ち付けたかのような、粗雑な作り。全体から、なんとも言えない、禍々しい雰囲気が放たれていた。
「……何、これ」
私の口から、思わず、素の疑問が漏れた。
その問いに、レイカさんは、まるで最高の賛辞でも受け取ったかのように、ぱあっと顔を輝かせた。そして、その異様な木箱を、恭しく私の机の上に置くと、満面の笑みで、高らかに宣言した。
「『コトリバコ』ですわ!」
ことりばこ。
その単語は、私の耳に、意味をなさない音の羅列として届いた。知らない言葉だ。何かのブランド名だろうか。いや、だとしたら、あまりにも悪趣味すぎる。
私の困惑した表情を、彼女は肯定的な興味と受け取ったらしい。嬉々として、その説明を始めた。その瞳は、昨日、私に『鮫島事件』について語った時と同じ、探求者のそれだった。
「ご存じありませんこと? 『コトリバコ』とは、インターネット上の一部の好事家の間では、あまりにも有名な呪物ですわ。ある地方に古くから伝わる、それはそれは恐ろしい呪いの箱……」
呪物。呪いの箱。
不穏な単語が、次々と私の鼓膜を揺らす。周りを見ると、教室に残っていた生徒たちも、何事かとこちらを遠巻きに眺めている。その誰もが、レイカさんが持ってきた不気味な箱と、私の顔を、交互に見比べていた。
「その製法は、実に凄惨を極めますの。まず、間引きされた子供……特に、女子供の体の一部を箱に詰めるのです。指、耳、鼻……。そして、特殊な呪術を用いて、その箱に怨念を封じ込める。そうして完成した『コトリバコ』は、標的とした相手の家に送りつけられ、その家の女子供を、次々と祟り殺していくと言われていますわ」
レイカさんの口から、淀みなく語られる、おぞましい逸話。その内容のグロテスクさに、私は、思わず顔をしかめた。周囲で見ている生徒たちの中には、小さく悲鳴を上げる者さえいる。
「一説によれば、この呪いを受けた家は、女が七代にわたって不幸に見舞われるとか。まさに、ジャパニーズ・ホラーの真髄とも言うべき、陰湿で、救いのない呪いですわね。素晴らしい……!」
うっとりとした表情で、彼女はそう締めくくった。
素晴らしいわけがあるか。
私は、目の前の木箱から、そっと視線を外した。こんな物騒な話をされた後では、直視することさえはばかられる。
私の反応を見て、レイカさんは、はっと我に返ったように、あわてて手を振った。
「まあ、ご安心くださいな、サヤカ。もちろん、これは本物の『コトリバコ』ではございませんわ。私が、古文書やネット上の情報を元に、食用可能な材料だけを使って、精巧に再現した『レプリカ弁当』ですもの」
レプリカ、弁当。
その二つの単語が、私の頭の中で、うまく結びつかなかった。
「友情の証として、そして昨夜のお詫びとして、ぜひ、召し上がっていただきたいのです」
彼女はそう言うと、にっこりと微笑み、その呪物の蓋に、そっと手をかけた。
やめて。
開けないで。
私の心の叫びは、しかし、無情にも無視された。
ぎ、ぎぎ……という、木が軋むような、不快な音を立てて、箱の蓋が開けられていく。そして、その中身が、私の目の前に、完全に晒された。
その瞬間、私は、言葉を失った。
箱の中に詰められていたのは、料理と呼ぶには、あまりにも、あまりにもグロテスクな光景だった。
赤黒いケチャップで血糊のように彩られたご飯の上には、人間の指の形に成形された、生々しい色のソーセージが、何本も転がっている。爪の部分には、アーモンドが埋め込まれていた。その横には、うずらの卵で作られた、いくつもの目玉。中央には、黒いオリーブが瞳のように置かれ、こちらをじっと見つめている。隙間を埋めるように詰められたブロッコリーは、まるで腐敗した何かを連想させた。
全体から、甘ったるいような、それでいて食欲を著しく減退させる、冒涜的な匂いが立ち上っている。
それは、悪夢そのものだった。悪趣味という言葉では、到底生ぬるい。人間の持つ、根源的な恐怖と嫌悪感を、的確に、そして執拗に刺激してくる、芸術的なまでの『嫌がらせ弁当』。
周囲から、ひっ、という、息を呑む音が聞こえた。何人かの女子生徒は、顔を青くして、口元を押さえている。男子生徒たちも、さすがにドン引きしている様子だった。
しかし、この惨状を作り出した張本人だけは、自分の作品を前に、恍惚とした表情を浮かべていた。
「いかがです、サヤカ? この指は、仔牛肉をベースにした特製のソーセージ。この目玉は、黄身を一度取り出し、ハーブとスパイスで味付けしたものを詰め直した、こだわりの一品ですのよ。見た目だけでなく、味にも、もちろん自信がありますわ」
自信満々にそう語る彼女の顔は、一点の曇りもなく、晴れやかですらあった。彼女は、本気で、これが私への友情の証であり、素晴らしい贈り物だと信じているのだ。
その、あまりにも絶望的なまでの認識のズレを前にして、私の怒りは、すでにどこかへ消え去っていた。後に残ったのは、ただ、深い、深い、虚無感だけだった。
ダメだ。もう、何を言っても無駄だ。
この人は、私の常識が、私の価値観が、一切通用しない、異世界の住人なのだ。
私が、ただ呆然と立ち尽くしていると、レイカさんは、箱の中から、指の形をしたソーセージを一つ、箸でつまみ上げた。そして、それを、私の口元へと、すっと差し出した。
「さあ、サヤカ。まずは一口、いかがです? あーん、ですわ」
にこやかに、悪戯っぽく、彼女はそう言った。
その光景は、あまりにもシュールで、非現実的だった。教室の真ん中で、美少女が、手作りの指を、もう一人の少女に食べさせようとしている。周囲には、恐怖と好奇の入り混じった視線を向ける、大勢のギャラリー。
私は、抵抗する気力もなかった。ただ、目の前で差し出されている、妙にリアルな造形の『指』を、見つめることしかできなかった。
「私たちの友情を、このお弁当で、さらに深く、深く、結びつけましょう……」
レイカさんの声が、どこか遠くに聞こえた。
人間は、本当に追い詰められると、怒りや悲しみといった感情さえも、どこか遠くへ行ってしまうらしい。
今の私が、まさにその状態だった。目の前で繰り広げられる光景は、あまりにも非現実的で、私のちっぽけな常識など、もはや何の役にも立たないことを、ただただ証明しているだけだった。
昼休みの喧騒が嘘のように静まり返った教室の中央で、私の意識がただただそこにあった。目の前の机には、禍々しい『コトリバコ弁当』が置かれている。そして、その制作者である西園寺レイカさんは、人間の指を模したソーセージを箸でつまみ、満面の笑みで私の口元に差し出してきた。
「さあ、サヤカ。あーん、ですわ」
その言葉は、まるで春の陽だまりの中で交わされる恋人たちの戯れのようでありながら、その手に持つものが持つグロテスクさによって、この世のものとは思えないほど歪な光景を現出させていた。周囲を取り囲むクラスメイトたちの視線が、痛いほどに突き刺さる。好奇、ドン引き、そしてほんの少しの同情。それらが複雑に絡み合った視線の網の中で、私は完全に身動きが取れなくなっていた。
食べられるわけがない。こんなものを口にしたら、私は私でなくなってしまう。そんな根源的な恐怖が、私の体を支配していた。しかし、ここで彼女の申し出を拒絶すれば、一体どうなるというのか。彼女はきっと、悲しそうな顔をして、そして次の瞬間には、さらに斜め上の発想で、私との『友情』を深めようとしてくるに違いない。どちらに転んでも、待っているのは地獄だけだ。
私が、ただ唇を固く結んで動けずにいると、レイカさんは、こてん、と不思議そうに首を傾げた。
「あら、お嫌いですの? でしたら、こちらの目玉はいかがでしょう。特製のハーブソースが、きっとサヤカのお口に合いますわ」
そう言って、彼女は指ソーセージを箱に戻し、今度はうずらの卵で作られた目玉を、器用な箸さばきでつまみ上げた。黒オリーブの瞳が、じっと、私を見つめている。
もう、限界だった。
「……ごめん。」
私の口から、かろうじて、それだけの言葉が絞り出された。
「私、ちょっと、気分が……」
そう言い終えるのが早いか、私は背を向け、ほとんど逃げ出すようにして教室の扉へと向かった。背後で、レイカさんの「まあ、サヤカ!?」という、心底驚いたような声が聞こえた気がしたが、もう振り返る余裕はなかった。
廊下を抜け、階段を駆け下り、向かった先は保健室だった。幸い、養護教諭は不在で、私は「少し頭が痛くて」とだけ書き置きを残すと、一番奥のベッドのカーテンを閉め、そこに倒れ込んだ。ひんやりとしたシーツの感触が、火照った頬に心地よかった。
暗く、静かな、狭い空間。ここなら、誰も私を見つけることはないだろう。レイカさんの、あの悪意なき善意からも、クラスメイトたちの好奇の視線からも、一時的に逃れることができる。私は、深く、深く、安堵のため息をついた。
瞼を閉じると、脳裏にあの弁当の光景がちらついて、すぐに目を開ける。駄目だ。あれは、一種のトラウマとして、私の記憶に深く刻み込まれてしまったらしい。これから先、私はもう、普通のお弁当を普通に見ることができなくなってしまったかもしれない。
西園寺レイカ。彼女は、私の平穏な日常を破壊しただけでは飽き足らず、私の食生活にまで、深刻なダメージを与えていくつもりなのだろうか。考えているだけで、また胃が重くなるのを感じた。
結局、私は昼休みが終わるまでの時間、ずっと保健室のベッドの上で過ごした。遠くで昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴り、午後の授業が始まったことを知らせる。廊下を生徒たちが移動する音が遠ざかり、校舎全体が静けさを取り戻していく。その静けさだけが、今の私にとっての救いだった。
このまま、今日の授業が終わるまで、ここにいよう。そう固く心に決めた、その時だった。
ベッドの横のカーテンが、さっ、と軽い音を立てて開かれた。
「サヤカ、お体は大丈夫ですの?」
なんの気配も感じさせずに現れたのは、もちろん、西園寺レイカさんだった。彼女は、少し心配そうな顔で、ベッドに横たわる私を覗き込んでいる。どうして、ここが分かったのか。いや、この人に常識的な疑問をぶつけるだけ無駄か。
「……うん、まあ」
私は、起き上がる気力もなく、あいまいに答えた。
「よかったですわ。けれど、無理はいけませんことよ」
彼女は、私の返事に安心したように表情を緩めると、一人で納得したようにこくこくと頷いた。
「やはり、霊的な感受性が強い方は、人混みや特定の場所からの影響を受けやすいものですわ。サヤカは、ご自身が思っている以上に、デリケートなのですから、もっと自分を大切になさらないと」
彼女の口から語られる言葉は、私が体調を崩した原因が、自分の差し出したあのグロテスクな弁当にあるなどとは、微塵も考えていないようだった。全ての原因は、私の『霊媒体質』のせい。彼女の中では、そういう筋書きになっているのだ。
私は、もう反論する気力もなかった。ただ、彼女の存在そのものが、私の体力を根こそぎ奪っていくのを感じた。
「では、私はこれで。ゆっくりお休みになってくださいな」
言うだけ言うと、レイカさんは嵐のように保健室から去っていった。再び、静寂が訪れる。
私は、彼女が残していった言葉を反芻していたが、やがて、意識を手放した。
◇
はっと気が付いた時、保健室の窓の外は、オレンジ色に染まっていた。一日の終わりを告げるチャイムの音が、遠くでかすかに聞こえる。どうやら、午後の授業が終わるまで、眠ってしまっていたらしい。
重たい体をゆっくりと起こし、制服の乱れを直す。カバンを置いたままの教室に戻らなければならない。その事実が、ひどく憂鬱だった。
ふと、枕元に置いていたスマートフォンに、一件の通知が来ていることに気が付く。画面を開くと、それはレイカさんからのメッセージだった。
『サヤカへ。お口に合わなかったようなので、コトリバコ弁当は、私が責任を持って供養しておきましたわ。ご安心くださいな。 レイカより』
供養。
その単語のチョイスに、私は、もはや乾いた笑いしか出てこなかった。
ベッドから起き上がる気力が、どうしても湧いてこない。瞼の裏に焼き付いているのは、昨夜、クラスメイトから送りつけられてきた、あの悪趣味な写真。私の姿、その周りに浮かぶ白い球体、そして黒い靄。何よりも、それに添えられた『運命の友、サヤカさんの背後霊ですわ♡』という、悪意なき悪意に満ちた一文。
西園寺レイカ。
その名前を心の中で反芻するだけで、胃のあたりがずしりと重くなるのを感じた。彼女と出会って、まだたったの一日。それなのに、私の日常は、もう原形を留めていない。平穏だった昨日までの日々が、まるで遠い昔のことのように思えた。
学校へ行きたくない。
心の底から、そう思った。教室に入った瞬間、クラス中の視線が私に集まるのが目に見えるようだ。『鮫島さん、マジでヤバい人だったんだ』『レイカ様、逃げてー!』。メッセージアプリに書き込まれていた、心ない言葉の数々が、脳内で繰り返し再生される。笑いものにされるか、あるいは気味悪がられて距離を置かれるか。どちらにしても、私が今まで築き上げてきた、目立たず、誰とも深く関わらない、安全なテリトリーは、もう存在しないのだ。
そして何より、あの張本人の顔を、平常心で見られる自信がなかった。きっと彼女は、いつものように優雅な微笑みを浮かべて、当たり前のように私の隣の席に座っているのだろう。昨夜の私の怒りなど、まるで意に介していないかのように。彼女にとっては、あれは『友情の証』であり、『霊的資質の証明』なのだから。話が通じない相手と向き合うことが、これほどまでに精神を消耗させるものだとは、今まで知らなかった。
しかし、私には学校を休むという選択肢はなかった。そんなことをすれば、かえって噂に拍車をかけるだけだ。それに、ここで逃げ出してしまえば、私は本当に『厄災』に負けたことになる。それは、私のけちなプライドが許さなかった。
私は、重たい体を無理やり起こすと、機械的に制服へと着替えた。顔を洗い、髪をとかし、朝食を喉に流し込む。その一つ一つの動作が、ひどく億劫だった。
「いってきます」
誰に言うでもなくそう呟いて玄関のドアを開ける。いつもと同じ通学路。けれど、見える風景は、どこか色褪せて見えた。道端の電柱も、住宅の塀も、すれ違う人々の顔も、全てが私を監視しているように感じられる。自意識過剰だとは分かっている。けれど、一度植え付けられた疑心暗鬼は、そう簡単には消えてくれなかった。
校門をくぐり、昇降口で靴を履き替える。廊下を歩いていると、すれ違う生徒たちが、ちらりと私を見て、ひそひそと何かを囁き合っているのが分かった。気のせいではない。彼らの視線には、明らかに昨日までとは違う種類の好奇の色が含まれていた。
ああ、もう始まっている。
私は、できるだけ表情を変えないように努めながら、自分の教室へと向かった。教室の引き戸に手をかける。この扉の向こうには、私の日常を破壊した元凶と、その結果生まれた好奇と嘲笑の視線が待っている。深呼吸を一つ。そして、意を決して、扉を開けた。
予想通り、教室の中にいた生徒たちの視線が、一斉に私へと向けられた。それは一瞬のことで、すぐにそれぞれがおしゃべりに戻っていったが、その一瞬の沈黙が、私の心に重くのしかかる。
私は、誰とも視線を合わせないようにしながら、自分の席へと向かった。そして、そこに、彼女はいた。
西園寺レイカさんは、すでに席に着き、優雅な仕草でハードカバーの本を読んでいた。朝の光が彼女の長い黒髪を照らし、まるで一枚の絵画のようだ。私が近づいたことに気づくと、彼女は本から顔を上げ、ふわりと微笑んだ。
「おはようございます、サヤカ」
その声も、表情も、いつもと何も変わらない。昨夜、メッセージアプリであれだけのやり取りをしたことなど、まるでなかったかのような、完璧なまでの普段通り。その態度に、私の胸の奥で、怒りとも呆れともつかない感情が、黒い煙のように立ち上った。
「……おはよう」
私は、かろうじてそれだけを返すと、乱暴に椅子を引いて席に着いた。カバンを机の横にかけ、教科書の準備を始める。その間も、レイカさんの視線がこちらに向けられているのを感じたが、私は意地でも彼女の方を見ようとはしなかった。
やがて、ホームルームを告げるチャイムが鳴り、担任が入ってくる。いつもと同じ、退屈な連絡事項。けれど、その内容も、ほとんど私の頭には入ってこなかった。ただ、早く時間が過ぎてほしい。早く、この地獄のような一日が終わってほしい。そればかりを考えていた。
◇
午前中の授業は、まさに苦行そのものだった。
教師が黒板に向かって何かを説明している間も、私は周囲の視線から逃れることができなかった。ノートを取るふりをしながら、すぐ隣に座るレイカさんの気配を、嫌でも感じてしまう。彼女は、時折こちらに何か言いたげな視線を向けてくるが、私がそれに気づかないふりをしていると、やがて諦めたように正面を向く。その繰り返しだった。
休み時間になれば、状況はさらに悪化した。クラスメイトたちが、遠巻きに、しかし明らかに私とレイカさんの様子を窺っている。何人かの女子生徒が、おそるおそるといった体で私の机に近づいてきた。
「ねえ、鮫島さん……。昨日の写真、見たよ」
「あれ、本物なの? なんか、すごいね……」
彼女たちの声には、面白がる気持ちと、気味悪がる気持ちが、半々くらいで含まれているように聞こえた。私は、引きつった笑みを浮かべることしかできない。
「さあ、どうなんだろうね。私もよく分からなくて」
曖昧にそう答えると、彼女たちは顔を見合わせ、困ったような、それでいて納得したような表情で去っていく。そんなやり取りを、何度か繰り返した。そのたびに、私の精神は少しずつ、だが確実に削られていった。
一方のレイカさんは、そんな私の苦悩などどこ吹く風、といった様子だった。彼女の周りには、相変わらず人が集まっている。けれど、その話題の中心は、昨日までとは少し違っていた。
「レイカさん、あの写真、どうやって撮ったの?」
「鮫島さんって、やっぱり何か特別な力がある人なんですか?」
質問の多くが、私に関連することだった。そしてレイカさんは、その一つ一つに、実に嬉々として答えている。
「ふふ、企業秘密ですわ。ですが、一つだけ言えるのは、サヤカが類い稀なる霊的資質の持ち主である、ということです」
「彼女の周りには、常に高位の霊的存在が集まってくるのです。私の目には、それがはっきりと見えますもの」
聞いているだけで、頭が痛くなってくる。彼女がそうやって面白おかしく語れば語るほど、私の『ヤバい人』というイメージは、クラスの中で確固たるものになっていく。もう、誰も私を『普通のクラスメイト』としては見てくれないだろう。
私は、机に突っ伏して、ただ時間が過ぎるのを待った。耳を塞ぎたい衝動に駆られたが、そんなことをすれば、さらに奇異の目で見られるだけだ。
早く、昼休みになってほしい。そうすれば、食堂にでも逃げ込んで、一人で静かに過ごせる。今日こそは、絶対に彼女のペースに巻き込まれたりしない。私は、固く、固く、そう決意していた。
そして、ようやく、その時は来た。四時間目の終わりを告げるチャイムが、解放の鐘のように鳴り響く。
「よし……」
私は、誰にも聞こえないくらいの声で呟くと、弁当を掴んで、素早く席を立った。一刻も早く、この教室から脱出する。その一心だった。
しかし、そんな私のささやかな希望は、いとも簡単に打ち砕かれた。
「サヤカ、お待ちになって」
背後からかけられた、涼やかな声。振り返るまでもない。西園寺レイカさん、その人だ。
私は、無視してそのまま歩き去ろうか、と一瞬本気で考えた。けれど、教室中の視線が突き刺さるこの状況で、そんな行動を取る勇気は、残念ながら私にはなかった。
私は、ゆっくりと、本当にゆっくりと、振り返った。そこには、予想通り、にこやかな表情のレイカさんが立っていた。
「……何?」
我ながら、ずいぶんと刺々しい声が出たと思う。だが、今の私には、これ以上愛想よく振る舞う余裕はなかった。
私のその態度に、レイカさんは、一瞬だけ、きょとんとした表情を見せた。しかし、すぐにいつもの優雅な微笑みに戻ると、深く、そして厳かに、頭を下げた。
「サヤカ。昨夜は、大変申し訳ありませんでした」
その、あまりにも予想外の言葉に、私は、思わず自分の耳を疑った。
謝罪?
この、西園寺レイカが?
私の怒りが、ようやく彼女に届いたのだろうか。だとしたら、少しは、ほんの少しだけ、見直してやってもいいかもしれない。私の胸に、淡い期待が芽生えた。
しかし、その期待が、いかに見当違いなものであったかを、私は次の瞬間に思い知らされることになる。
顔を上げたレイカさんは、真剣な、それでいてどこか憐れむような眼差しで、私を見つめていた。
「私の配慮が、あまりにも足りませんでしたわ。あのような形で、ご自身の偉大な力を公にされて、さぞかし驚かれたことでしょう。人知を超えた力を持つがゆえの孤独……。そのお気持ち、お察しいたします」
……は?
私の頭の中が、一瞬、真っ白になった。
今、この人、何て言った?
配慮が足りなかった? 驚かせたことに対して、謝っている? そうじゃない。私が怒っているのは、そこじゃない。勝手に写真を撮って、勝手に加工して、勝手にネットに晒したことに対してだろうが。
私の内心の叫びなど、もちろん彼女に届くはずもない。レイカさんは、一人で納得したように、こくこくと頷いている。
「ですが、ご安心くださいな。そんなサヤカのために、お詫びと言ってはなんですが、今日は私が、特別なものを用意してまいりましたの」
そう言うと、彼女は自分のカバンから、何かを取り出した。
それは、およそ弁当箱と呼ぶには、あまりにも異様な代物だった。
古びた、黒ずんだ木で組まれた、小さな箱。大きさは、一般的な弁当箱より一回り大きいくらいだろうか。しかし、その表面には、見たこともない、不気味な文様のようなものがびっしりと刻まれている。継ぎ目は荒く、まるで素人が無理やり釘で打ち付けたかのような、粗雑な作り。全体から、なんとも言えない、禍々しい雰囲気が放たれていた。
「……何、これ」
私の口から、思わず、素の疑問が漏れた。
その問いに、レイカさんは、まるで最高の賛辞でも受け取ったかのように、ぱあっと顔を輝かせた。そして、その異様な木箱を、恭しく私の机の上に置くと、満面の笑みで、高らかに宣言した。
「『コトリバコ』ですわ!」
ことりばこ。
その単語は、私の耳に、意味をなさない音の羅列として届いた。知らない言葉だ。何かのブランド名だろうか。いや、だとしたら、あまりにも悪趣味すぎる。
私の困惑した表情を、彼女は肯定的な興味と受け取ったらしい。嬉々として、その説明を始めた。その瞳は、昨日、私に『鮫島事件』について語った時と同じ、探求者のそれだった。
「ご存じありませんこと? 『コトリバコ』とは、インターネット上の一部の好事家の間では、あまりにも有名な呪物ですわ。ある地方に古くから伝わる、それはそれは恐ろしい呪いの箱……」
呪物。呪いの箱。
不穏な単語が、次々と私の鼓膜を揺らす。周りを見ると、教室に残っていた生徒たちも、何事かとこちらを遠巻きに眺めている。その誰もが、レイカさんが持ってきた不気味な箱と、私の顔を、交互に見比べていた。
「その製法は、実に凄惨を極めますの。まず、間引きされた子供……特に、女子供の体の一部を箱に詰めるのです。指、耳、鼻……。そして、特殊な呪術を用いて、その箱に怨念を封じ込める。そうして完成した『コトリバコ』は、標的とした相手の家に送りつけられ、その家の女子供を、次々と祟り殺していくと言われていますわ」
レイカさんの口から、淀みなく語られる、おぞましい逸話。その内容のグロテスクさに、私は、思わず顔をしかめた。周囲で見ている生徒たちの中には、小さく悲鳴を上げる者さえいる。
「一説によれば、この呪いを受けた家は、女が七代にわたって不幸に見舞われるとか。まさに、ジャパニーズ・ホラーの真髄とも言うべき、陰湿で、救いのない呪いですわね。素晴らしい……!」
うっとりとした表情で、彼女はそう締めくくった。
素晴らしいわけがあるか。
私は、目の前の木箱から、そっと視線を外した。こんな物騒な話をされた後では、直視することさえはばかられる。
私の反応を見て、レイカさんは、はっと我に返ったように、あわてて手を振った。
「まあ、ご安心くださいな、サヤカ。もちろん、これは本物の『コトリバコ』ではございませんわ。私が、古文書やネット上の情報を元に、食用可能な材料だけを使って、精巧に再現した『レプリカ弁当』ですもの」
レプリカ、弁当。
その二つの単語が、私の頭の中で、うまく結びつかなかった。
「友情の証として、そして昨夜のお詫びとして、ぜひ、召し上がっていただきたいのです」
彼女はそう言うと、にっこりと微笑み、その呪物の蓋に、そっと手をかけた。
やめて。
開けないで。
私の心の叫びは、しかし、無情にも無視された。
ぎ、ぎぎ……という、木が軋むような、不快な音を立てて、箱の蓋が開けられていく。そして、その中身が、私の目の前に、完全に晒された。
その瞬間、私は、言葉を失った。
箱の中に詰められていたのは、料理と呼ぶには、あまりにも、あまりにもグロテスクな光景だった。
赤黒いケチャップで血糊のように彩られたご飯の上には、人間の指の形に成形された、生々しい色のソーセージが、何本も転がっている。爪の部分には、アーモンドが埋め込まれていた。その横には、うずらの卵で作られた、いくつもの目玉。中央には、黒いオリーブが瞳のように置かれ、こちらをじっと見つめている。隙間を埋めるように詰められたブロッコリーは、まるで腐敗した何かを連想させた。
全体から、甘ったるいような、それでいて食欲を著しく減退させる、冒涜的な匂いが立ち上っている。
それは、悪夢そのものだった。悪趣味という言葉では、到底生ぬるい。人間の持つ、根源的な恐怖と嫌悪感を、的確に、そして執拗に刺激してくる、芸術的なまでの『嫌がらせ弁当』。
周囲から、ひっ、という、息を呑む音が聞こえた。何人かの女子生徒は、顔を青くして、口元を押さえている。男子生徒たちも、さすがにドン引きしている様子だった。
しかし、この惨状を作り出した張本人だけは、自分の作品を前に、恍惚とした表情を浮かべていた。
「いかがです、サヤカ? この指は、仔牛肉をベースにした特製のソーセージ。この目玉は、黄身を一度取り出し、ハーブとスパイスで味付けしたものを詰め直した、こだわりの一品ですのよ。見た目だけでなく、味にも、もちろん自信がありますわ」
自信満々にそう語る彼女の顔は、一点の曇りもなく、晴れやかですらあった。彼女は、本気で、これが私への友情の証であり、素晴らしい贈り物だと信じているのだ。
その、あまりにも絶望的なまでの認識のズレを前にして、私の怒りは、すでにどこかへ消え去っていた。後に残ったのは、ただ、深い、深い、虚無感だけだった。
ダメだ。もう、何を言っても無駄だ。
この人は、私の常識が、私の価値観が、一切通用しない、異世界の住人なのだ。
私が、ただ呆然と立ち尽くしていると、レイカさんは、箱の中から、指の形をしたソーセージを一つ、箸でつまみ上げた。そして、それを、私の口元へと、すっと差し出した。
「さあ、サヤカ。まずは一口、いかがです? あーん、ですわ」
にこやかに、悪戯っぽく、彼女はそう言った。
その光景は、あまりにもシュールで、非現実的だった。教室の真ん中で、美少女が、手作りの指を、もう一人の少女に食べさせようとしている。周囲には、恐怖と好奇の入り混じった視線を向ける、大勢のギャラリー。
私は、抵抗する気力もなかった。ただ、目の前で差し出されている、妙にリアルな造形の『指』を、見つめることしかできなかった。
「私たちの友情を、このお弁当で、さらに深く、深く、結びつけましょう……」
レイカさんの声が、どこか遠くに聞こえた。
人間は、本当に追い詰められると、怒りや悲しみといった感情さえも、どこか遠くへ行ってしまうらしい。
今の私が、まさにその状態だった。目の前で繰り広げられる光景は、あまりにも非現実的で、私のちっぽけな常識など、もはや何の役にも立たないことを、ただただ証明しているだけだった。
昼休みの喧騒が嘘のように静まり返った教室の中央で、私の意識がただただそこにあった。目の前の机には、禍々しい『コトリバコ弁当』が置かれている。そして、その制作者である西園寺レイカさんは、人間の指を模したソーセージを箸でつまみ、満面の笑みで私の口元に差し出してきた。
「さあ、サヤカ。あーん、ですわ」
その言葉は、まるで春の陽だまりの中で交わされる恋人たちの戯れのようでありながら、その手に持つものが持つグロテスクさによって、この世のものとは思えないほど歪な光景を現出させていた。周囲を取り囲むクラスメイトたちの視線が、痛いほどに突き刺さる。好奇、ドン引き、そしてほんの少しの同情。それらが複雑に絡み合った視線の網の中で、私は完全に身動きが取れなくなっていた。
食べられるわけがない。こんなものを口にしたら、私は私でなくなってしまう。そんな根源的な恐怖が、私の体を支配していた。しかし、ここで彼女の申し出を拒絶すれば、一体どうなるというのか。彼女はきっと、悲しそうな顔をして、そして次の瞬間には、さらに斜め上の発想で、私との『友情』を深めようとしてくるに違いない。どちらに転んでも、待っているのは地獄だけだ。
私が、ただ唇を固く結んで動けずにいると、レイカさんは、こてん、と不思議そうに首を傾げた。
「あら、お嫌いですの? でしたら、こちらの目玉はいかがでしょう。特製のハーブソースが、きっとサヤカのお口に合いますわ」
そう言って、彼女は指ソーセージを箱に戻し、今度はうずらの卵で作られた目玉を、器用な箸さばきでつまみ上げた。黒オリーブの瞳が、じっと、私を見つめている。
もう、限界だった。
「……ごめん。」
私の口から、かろうじて、それだけの言葉が絞り出された。
「私、ちょっと、気分が……」
そう言い終えるのが早いか、私は背を向け、ほとんど逃げ出すようにして教室の扉へと向かった。背後で、レイカさんの「まあ、サヤカ!?」という、心底驚いたような声が聞こえた気がしたが、もう振り返る余裕はなかった。
廊下を抜け、階段を駆け下り、向かった先は保健室だった。幸い、養護教諭は不在で、私は「少し頭が痛くて」とだけ書き置きを残すと、一番奥のベッドのカーテンを閉め、そこに倒れ込んだ。ひんやりとしたシーツの感触が、火照った頬に心地よかった。
暗く、静かな、狭い空間。ここなら、誰も私を見つけることはないだろう。レイカさんの、あの悪意なき善意からも、クラスメイトたちの好奇の視線からも、一時的に逃れることができる。私は、深く、深く、安堵のため息をついた。
瞼を閉じると、脳裏にあの弁当の光景がちらついて、すぐに目を開ける。駄目だ。あれは、一種のトラウマとして、私の記憶に深く刻み込まれてしまったらしい。これから先、私はもう、普通のお弁当を普通に見ることができなくなってしまったかもしれない。
西園寺レイカ。彼女は、私の平穏な日常を破壊しただけでは飽き足らず、私の食生活にまで、深刻なダメージを与えていくつもりなのだろうか。考えているだけで、また胃が重くなるのを感じた。
結局、私は昼休みが終わるまでの時間、ずっと保健室のベッドの上で過ごした。遠くで昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴り、午後の授業が始まったことを知らせる。廊下を生徒たちが移動する音が遠ざかり、校舎全体が静けさを取り戻していく。その静けさだけが、今の私にとっての救いだった。
このまま、今日の授業が終わるまで、ここにいよう。そう固く心に決めた、その時だった。
ベッドの横のカーテンが、さっ、と軽い音を立てて開かれた。
「サヤカ、お体は大丈夫ですの?」
なんの気配も感じさせずに現れたのは、もちろん、西園寺レイカさんだった。彼女は、少し心配そうな顔で、ベッドに横たわる私を覗き込んでいる。どうして、ここが分かったのか。いや、この人に常識的な疑問をぶつけるだけ無駄か。
「……うん、まあ」
私は、起き上がる気力もなく、あいまいに答えた。
「よかったですわ。けれど、無理はいけませんことよ」
彼女は、私の返事に安心したように表情を緩めると、一人で納得したようにこくこくと頷いた。
「やはり、霊的な感受性が強い方は、人混みや特定の場所からの影響を受けやすいものですわ。サヤカは、ご自身が思っている以上に、デリケートなのですから、もっと自分を大切になさらないと」
彼女の口から語られる言葉は、私が体調を崩した原因が、自分の差し出したあのグロテスクな弁当にあるなどとは、微塵も考えていないようだった。全ての原因は、私の『霊媒体質』のせい。彼女の中では、そういう筋書きになっているのだ。
私は、もう反論する気力もなかった。ただ、彼女の存在そのものが、私の体力を根こそぎ奪っていくのを感じた。
「では、私はこれで。ゆっくりお休みになってくださいな」
言うだけ言うと、レイカさんは嵐のように保健室から去っていった。再び、静寂が訪れる。
私は、彼女が残していった言葉を反芻していたが、やがて、意識を手放した。
◇
はっと気が付いた時、保健室の窓の外は、オレンジ色に染まっていた。一日の終わりを告げるチャイムの音が、遠くでかすかに聞こえる。どうやら、午後の授業が終わるまで、眠ってしまっていたらしい。
重たい体をゆっくりと起こし、制服の乱れを直す。カバンを置いたままの教室に戻らなければならない。その事実が、ひどく憂鬱だった。
ふと、枕元に置いていたスマートフォンに、一件の通知が来ていることに気が付く。画面を開くと、それはレイカさんからのメッセージだった。
『サヤカへ。お口に合わなかったようなので、コトリバコ弁当は、私が責任を持って供養しておきましたわ。ご安心くださいな。 レイカより』
供養。
その単語のチョイスに、私は、もはや乾いた笑いしか出てこなかった。