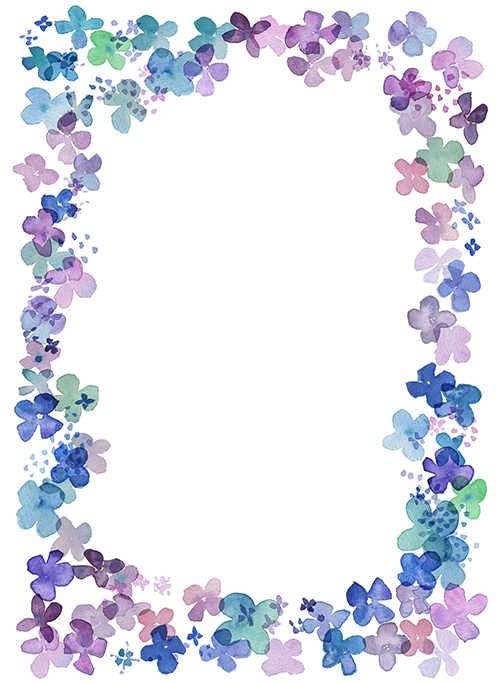なんとかレイカさんとの嵐のような昼休みを乗り切り、午後の授業も上の空でやり過ごした。ようやく、一日の終わりを告げるチャイムが鳴り響く。
平穏だった日常は、もうどこにもない。私の城は、外からやってきた侵略者によって、完全に占拠されてしまったのだ。
せめて放課後くらいは一人で静かに帰りたい。私は、他の生徒たちが部活や寄り道の話で盛り上がるのを背に、そそくさとカバンに教科書を詰め込んだ。一刻も早く、この教室から脱出しなければ。
私が席を立とうとした、まさにその時だった。
「あら、サヤカ。もうお帰りですの?」
隣の席から、鈴の鳴るような声がした。見ると、レイカさんが分厚いハードカバーの本を優雅にカバンにしまいながら、こちらに微笑みかけている。しまった、と心の中で舌打ちする。彼女の存在を、一瞬でも忘れていたなんて。
「ええ、まあ……用事とかはないけど」
「それはちょうどよかったですわ。でしたら、途中までご一緒しましょう。私たちの友情を、もっと深めるために」
にっこりと微笑む彼女に、断るという選択肢は存在しないようだった。有無を言わさぬオーラを放ち、私の返事を待つまでもなく、ごく自然に隣に並んで歩き始める。
こうして、私はレイカさんと二人で帰路につくことになった。学校から駅までの道は、いつもは一人で考え事をするための、何でもない道だった。しかし、今は違う。隣を歩く彼女の存在が、周囲の生徒たちの視線を嫌でも集めてしまう。
「今日の授業、少し退屈ではありませんでしたか?」
「え? ああ、まあ、普通かな」
「私、以前の学校では、もっと専門的な時間もありましたの。例えば、古代ケルト民族におけるドルイド信仰の変遷や、日本の陰陽道が民間に与えた影響についてなど……」
滔々と語られる、私の全く興味のない分野の話。私は、適当な相槌を打ちながら、ただ早くこの状況が終わることだけを願っていた。
そんな時だった。
夕日に照らされた住宅街の、何の変哲もない道端で、彼女は不意に足を止めた。そして、スマートフォンをすっと取り出す。
「サヤカ、少しだけ、そこに立っていてくださる?」
「え?」
彼女がスマートフォンを向けた先には、私がいた。夕日を背にして、怪訝な顔で立ち尽くす私。
カシャッ、という、控えめながらも明確な電子音が鳴り響いた。
「……今、何したの?」
私の問いに、レイカさんは悪びれる様子もなく、にこりと微笑んだ。
「いえ、夕日を背にしたサヤカがあまりに絵になるものですから。つい」
「つい、じゃないでしょ。勝手に写真撮らないでよ」
思わず、少し強い口調になってしまう。プライバシーとか、肖像権とか、そういう難しい言葉を持ち出すつもりはない。ただ、単純に、嫌だった。
「まあ、そんなに固いことをおっしゃらずに。これも私たちの友情の記録ですわ」
彼女はそう言うと、スマートフォンの画面を指で数回なぞり、満足げに頷いた。
「うん、いい写真が撮れました。ありがとうございます、サヤカ」
「ありがとう、じゃないってば……」
私の抗議の声は、彼女の耳には届いていないようだった。彼女は再び何事もなかったかのように歩き始め、私は、言いようのないもやもやとした気持ちを抱えたまま、その後ろをついていくしかなかった。
きっと、彼女にとっては、これもコミュニケーションの一環なのだろう。普通の女子高生が、友達と一緒にふざけて写真を撮る。それと、同じ感覚。ただ、彼女の場合、その相手が一方的に『運命の友』と認定しただけの、他人だという点を除けば。
この時の私は、まだ、事の重大さを理解していなかった。彼女の『常識外れ』が、一体どこまでの広がりを見せるのか、想像もできていなかったのだ。
その夜、自宅のベッドの上で、私はスマートフォンの画面を眺めながら、ため息をついた。今日一日だけで、ここ数年分の精神をすり減らした気がする。
そんな時、メッセージアプリに一件の通知が届いた。クラスの、あまり話したことのない女子からだった。
『鮫島さん、これ、見た?』
そのメッセージの下には、一枚の写真がプレビュー表示されていた。それは、見覚えのある住宅街の風景。そして、夕日を浴びて立つ、見覚えのある、私の姿。
帰り道、レイカさんが勝手に撮った、あの写真だった。
しかし、その写真は、私が知っているものとは、明らかに異なっていた。
私の肩のあたりに、ぼんやりとした、白い球体がいくつも浮かんでいる。それは、心霊写真の特集などでよく見る『霊魂』と呼ばれるものにそっくりだった。さらに、私の背後には、黒い靄のようなものが、まるで意思を持っているかのようにまとわりついている。
そして、その写真には、こんな一文が添えられていた。
『運命の友、サヤカさんの背後霊ですわ♡』
投稿者の名前は、西園寺レイカ。
その投稿は、多くの生徒が利用している、写真共有のアプリ上で行われていた。いわゆる、鍵のかかっていない、誰でも閲覧可能なアカウントだ。投稿時間の表示は、約一時間前。すでに、何十件もの『いいね』が押され、いくつかのコメントが書き込まれている。
『え、マジ!?』
『これ、合成でしょ?』
『鮫島さん、ガチでヤバい人だったんだ……』
『レイカ様、逃げてー!』
コメント欄をスクロールする指が、カタカタと小さく揺れる。
頭の奥で、何かがぷつりと切れる音がした。
これは、ない。
断じて、ない。
これまでの、一方的な『運命の友』宣言も、強引な距離の詰め方も、我慢してきた。彼女が特殊な趣味の持ち主で、少しばかり常識が欠けているだけなのだと、自分に言い聞かせてきた。
だが、これは違う。
これは、私の知らないところで、私の肖像を勝手に使い、事実無根の、悪趣味な加工を施し、不特定多数の人間の目に晒すという、明確な『攻撃』だ。
友情の記録?
背後霊?
なんだこれは?
いや、その前に私の平穏な日常を返せ。
怒りよりも先に、全身から急速に血の気が引いていくような、冷たい感覚に襲われた。画面の中の、見知らぬ誰かからの嘲笑や好奇の視線が、現実の私に突き刺さるようだった。
私は、勢いよくベッドから起き上がると、ほとんど無意識のうちに、レイカさんの連絡先を探していた。昼休み、半ば無理やり交換させられた、メッセージアプリのアカウント。
『あの写真、どういうこと?』
打ち込んだ文字は、自分でも驚くほど、冷たく、そして硬い響きを持っていた。
送信ボタンを押して、数秒も経たないうちに、画面に『既読』の文字が表示された。そして、すぐに返信が来る。
『ああ、ご覧になりましたか、サヤカ。素晴らしい写りだと思いませんこと?』
その、あまりにも呑気な、そして見当違いな返信に、私の頭は真っ白になった。
『素晴らしいわけないでしょ! 何であんなもの勝手に投稿してるの!? 今すぐ消して!』
怒りに任せて、立て続けにメッセージを送る。指がもどかしい。直接、電話をかけた方が早いかもしれない。いや、それよりも、今すぐ彼女の住んでいるという高級マンションに乗り込んで、問い詰めてやりたい気分だった。
『消す? どうしてですの?』
返ってきたのは、純粋な疑問だった。
『これほどまでに、あなたの霊的な資質の高さを証明する写真はありませんのに。あなたの背後に控えるその霊体は、おそらく、あなたの先祖、あるいは、あなたという存在に強く惹きつけられた、位の高い霊格を持つものですわ。守護霊と呼ぶには、あまりに強大すぎる。そう、言うなれば……』
レイカさんからのメッセージは、そこから、私の理解の範疇を完全に超えた、長々としたオカルト講釈へと突入した。専門用語が並び、古今東西の文献からの引用らしきものが飛び交う。彼女が、自分の趣味の世界にどっぷりと浸かっているのが、文面からありありと伝わってきた。
違う。
私が聞きたいのは、そんなことじゃない。
私が求めているのは、謝罪と、投稿の即時削除だ。
『いいから、今すぐ消して!』
私は、彼女の長文を無視して、それだけを再び送った。
しばらく、返信はなかった。ようやく、彼女も事の異常さに気づいたのかもしれない。そう、一瞬だけ期待した。
だが、次に送られてきたメッセージは、私のその淡い期待を、木っ端微塵に打ち砕くものだった。
『……分かりましたわ。サヤカがそこまでおっしゃるのでしたら』
その一文に、私は、わずかに安堵した。やっと、話が通じた。
『ですが、一つだけよろしいでしょうか』
しかし、その安堵は、すぐに不穏な予感へと変わる。
『この写真の現象は、私の手による加工などではありませんのよ?』
は?
何を、言っているんだ、この人は。
『これは、撮影した瞬間に、ありのままに写り込んだ、正真正銘の心霊写真なのですから。私が少し手を加えたのは、その霊的な波動がより皆様に伝わりやすくなるよう、ほんの少しだけ、この輪郭を強調したに過ぎませんわ』
その言葉を理解するのに、数秒かかった。
そして、理解した瞬間、私は、怒りを通り越して、一種の虚無感に襲われた。
ダメだ。この人には、何を言っても、通じない。
常識が、とか、プライバシーが、とか、そういう次元の話ではないのだ。彼女は、彼女自身の揺るぎない『真実』の中に生きている。その世界では、私の背後に霊がいて、それが写真に写ることは、当たり前の事実なのだ。
私の中で、西園寺レイカという存在の定義が、この瞬間、決定的に変わった。
彼女は、理解不能な人物、ではない。
少し変わった、迷惑な転校生、でもない。
彼女は、私の日常を、私の平穏を、私の価値観を、悪意なく、善意のもとに、根こそぎ破壊し尽くす、歩く『厄災』そのものなのだ。
スマートフォンを、ベッドの上に放り投げる。画面には、まだレイカさんからのメッセージが続いている。
『もしご自身の霊媒体質についてお悩みでしたら、いつでもご相談に乗りますわ。私、そういう方面の専門家には、たくさん心当たりがございますので。これも、運命の友としての、私の務めですもの……』
もう、何も考えたくなかった。
ただ、明日、学校へ行って、クラスメイトたちの前に、どんな顔で立てばいいのか。それだけが、私の思考を支配していた。
平穏だった日常は、もうどこにもない。私の城は、外からやってきた侵略者によって、完全に占拠されてしまったのだ。
せめて放課後くらいは一人で静かに帰りたい。私は、他の生徒たちが部活や寄り道の話で盛り上がるのを背に、そそくさとカバンに教科書を詰め込んだ。一刻も早く、この教室から脱出しなければ。
私が席を立とうとした、まさにその時だった。
「あら、サヤカ。もうお帰りですの?」
隣の席から、鈴の鳴るような声がした。見ると、レイカさんが分厚いハードカバーの本を優雅にカバンにしまいながら、こちらに微笑みかけている。しまった、と心の中で舌打ちする。彼女の存在を、一瞬でも忘れていたなんて。
「ええ、まあ……用事とかはないけど」
「それはちょうどよかったですわ。でしたら、途中までご一緒しましょう。私たちの友情を、もっと深めるために」
にっこりと微笑む彼女に、断るという選択肢は存在しないようだった。有無を言わさぬオーラを放ち、私の返事を待つまでもなく、ごく自然に隣に並んで歩き始める。
こうして、私はレイカさんと二人で帰路につくことになった。学校から駅までの道は、いつもは一人で考え事をするための、何でもない道だった。しかし、今は違う。隣を歩く彼女の存在が、周囲の生徒たちの視線を嫌でも集めてしまう。
「今日の授業、少し退屈ではありませんでしたか?」
「え? ああ、まあ、普通かな」
「私、以前の学校では、もっと専門的な時間もありましたの。例えば、古代ケルト民族におけるドルイド信仰の変遷や、日本の陰陽道が民間に与えた影響についてなど……」
滔々と語られる、私の全く興味のない分野の話。私は、適当な相槌を打ちながら、ただ早くこの状況が終わることだけを願っていた。
そんな時だった。
夕日に照らされた住宅街の、何の変哲もない道端で、彼女は不意に足を止めた。そして、スマートフォンをすっと取り出す。
「サヤカ、少しだけ、そこに立っていてくださる?」
「え?」
彼女がスマートフォンを向けた先には、私がいた。夕日を背にして、怪訝な顔で立ち尽くす私。
カシャッ、という、控えめながらも明確な電子音が鳴り響いた。
「……今、何したの?」
私の問いに、レイカさんは悪びれる様子もなく、にこりと微笑んだ。
「いえ、夕日を背にしたサヤカがあまりに絵になるものですから。つい」
「つい、じゃないでしょ。勝手に写真撮らないでよ」
思わず、少し強い口調になってしまう。プライバシーとか、肖像権とか、そういう難しい言葉を持ち出すつもりはない。ただ、単純に、嫌だった。
「まあ、そんなに固いことをおっしゃらずに。これも私たちの友情の記録ですわ」
彼女はそう言うと、スマートフォンの画面を指で数回なぞり、満足げに頷いた。
「うん、いい写真が撮れました。ありがとうございます、サヤカ」
「ありがとう、じゃないってば……」
私の抗議の声は、彼女の耳には届いていないようだった。彼女は再び何事もなかったかのように歩き始め、私は、言いようのないもやもやとした気持ちを抱えたまま、その後ろをついていくしかなかった。
きっと、彼女にとっては、これもコミュニケーションの一環なのだろう。普通の女子高生が、友達と一緒にふざけて写真を撮る。それと、同じ感覚。ただ、彼女の場合、その相手が一方的に『運命の友』と認定しただけの、他人だという点を除けば。
この時の私は、まだ、事の重大さを理解していなかった。彼女の『常識外れ』が、一体どこまでの広がりを見せるのか、想像もできていなかったのだ。
その夜、自宅のベッドの上で、私はスマートフォンの画面を眺めながら、ため息をついた。今日一日だけで、ここ数年分の精神をすり減らした気がする。
そんな時、メッセージアプリに一件の通知が届いた。クラスの、あまり話したことのない女子からだった。
『鮫島さん、これ、見た?』
そのメッセージの下には、一枚の写真がプレビュー表示されていた。それは、見覚えのある住宅街の風景。そして、夕日を浴びて立つ、見覚えのある、私の姿。
帰り道、レイカさんが勝手に撮った、あの写真だった。
しかし、その写真は、私が知っているものとは、明らかに異なっていた。
私の肩のあたりに、ぼんやりとした、白い球体がいくつも浮かんでいる。それは、心霊写真の特集などでよく見る『霊魂』と呼ばれるものにそっくりだった。さらに、私の背後には、黒い靄のようなものが、まるで意思を持っているかのようにまとわりついている。
そして、その写真には、こんな一文が添えられていた。
『運命の友、サヤカさんの背後霊ですわ♡』
投稿者の名前は、西園寺レイカ。
その投稿は、多くの生徒が利用している、写真共有のアプリ上で行われていた。いわゆる、鍵のかかっていない、誰でも閲覧可能なアカウントだ。投稿時間の表示は、約一時間前。すでに、何十件もの『いいね』が押され、いくつかのコメントが書き込まれている。
『え、マジ!?』
『これ、合成でしょ?』
『鮫島さん、ガチでヤバい人だったんだ……』
『レイカ様、逃げてー!』
コメント欄をスクロールする指が、カタカタと小さく揺れる。
頭の奥で、何かがぷつりと切れる音がした。
これは、ない。
断じて、ない。
これまでの、一方的な『運命の友』宣言も、強引な距離の詰め方も、我慢してきた。彼女が特殊な趣味の持ち主で、少しばかり常識が欠けているだけなのだと、自分に言い聞かせてきた。
だが、これは違う。
これは、私の知らないところで、私の肖像を勝手に使い、事実無根の、悪趣味な加工を施し、不特定多数の人間の目に晒すという、明確な『攻撃』だ。
友情の記録?
背後霊?
なんだこれは?
いや、その前に私の平穏な日常を返せ。
怒りよりも先に、全身から急速に血の気が引いていくような、冷たい感覚に襲われた。画面の中の、見知らぬ誰かからの嘲笑や好奇の視線が、現実の私に突き刺さるようだった。
私は、勢いよくベッドから起き上がると、ほとんど無意識のうちに、レイカさんの連絡先を探していた。昼休み、半ば無理やり交換させられた、メッセージアプリのアカウント。
『あの写真、どういうこと?』
打ち込んだ文字は、自分でも驚くほど、冷たく、そして硬い響きを持っていた。
送信ボタンを押して、数秒も経たないうちに、画面に『既読』の文字が表示された。そして、すぐに返信が来る。
『ああ、ご覧になりましたか、サヤカ。素晴らしい写りだと思いませんこと?』
その、あまりにも呑気な、そして見当違いな返信に、私の頭は真っ白になった。
『素晴らしいわけないでしょ! 何であんなもの勝手に投稿してるの!? 今すぐ消して!』
怒りに任せて、立て続けにメッセージを送る。指がもどかしい。直接、電話をかけた方が早いかもしれない。いや、それよりも、今すぐ彼女の住んでいるという高級マンションに乗り込んで、問い詰めてやりたい気分だった。
『消す? どうしてですの?』
返ってきたのは、純粋な疑問だった。
『これほどまでに、あなたの霊的な資質の高さを証明する写真はありませんのに。あなたの背後に控えるその霊体は、おそらく、あなたの先祖、あるいは、あなたという存在に強く惹きつけられた、位の高い霊格を持つものですわ。守護霊と呼ぶには、あまりに強大すぎる。そう、言うなれば……』
レイカさんからのメッセージは、そこから、私の理解の範疇を完全に超えた、長々としたオカルト講釈へと突入した。専門用語が並び、古今東西の文献からの引用らしきものが飛び交う。彼女が、自分の趣味の世界にどっぷりと浸かっているのが、文面からありありと伝わってきた。
違う。
私が聞きたいのは、そんなことじゃない。
私が求めているのは、謝罪と、投稿の即時削除だ。
『いいから、今すぐ消して!』
私は、彼女の長文を無視して、それだけを再び送った。
しばらく、返信はなかった。ようやく、彼女も事の異常さに気づいたのかもしれない。そう、一瞬だけ期待した。
だが、次に送られてきたメッセージは、私のその淡い期待を、木っ端微塵に打ち砕くものだった。
『……分かりましたわ。サヤカがそこまでおっしゃるのでしたら』
その一文に、私は、わずかに安堵した。やっと、話が通じた。
『ですが、一つだけよろしいでしょうか』
しかし、その安堵は、すぐに不穏な予感へと変わる。
『この写真の現象は、私の手による加工などではありませんのよ?』
は?
何を、言っているんだ、この人は。
『これは、撮影した瞬間に、ありのままに写り込んだ、正真正銘の心霊写真なのですから。私が少し手を加えたのは、その霊的な波動がより皆様に伝わりやすくなるよう、ほんの少しだけ、この輪郭を強調したに過ぎませんわ』
その言葉を理解するのに、数秒かかった。
そして、理解した瞬間、私は、怒りを通り越して、一種の虚無感に襲われた。
ダメだ。この人には、何を言っても、通じない。
常識が、とか、プライバシーが、とか、そういう次元の話ではないのだ。彼女は、彼女自身の揺るぎない『真実』の中に生きている。その世界では、私の背後に霊がいて、それが写真に写ることは、当たり前の事実なのだ。
私の中で、西園寺レイカという存在の定義が、この瞬間、決定的に変わった。
彼女は、理解不能な人物、ではない。
少し変わった、迷惑な転校生、でもない。
彼女は、私の日常を、私の平穏を、私の価値観を、悪意なく、善意のもとに、根こそぎ破壊し尽くす、歩く『厄災』そのものなのだ。
スマートフォンを、ベッドの上に放り投げる。画面には、まだレイカさんからのメッセージが続いている。
『もしご自身の霊媒体質についてお悩みでしたら、いつでもご相談に乗りますわ。私、そういう方面の専門家には、たくさん心当たりがございますので。これも、運命の友としての、私の務めですもの……』
もう、何も考えたくなかった。
ただ、明日、学校へ行って、クラスメイトたちの前に、どんな顔で立てばいいのか。それだけが、私の思考を支配していた。