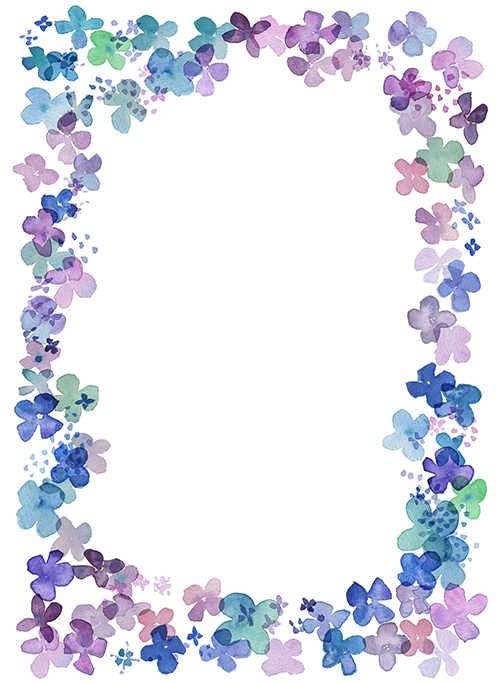これで、終わりに、しよう。
私の意識が冷たく心地よい絶望の底へと、ゆっくりと沈んでいく。膝の上で眠るレイカさんの温かささえもが遠い世界の出来事のように感じられ始めた。もう何もかもがどうでもよかった。
私がその甘い諦めに魂の全てを委ねようとした、まさにその時だった。
「――サヤカ、お待たせいたしましたわ。こちらが、わたくしたちを次なる次元へと誘うための、特別な儀式ですの」
不意に頭の中に全く別の声が割り込んできた。
それはあの呪いの声とは似ても似つかない、どこまでも優雅で、しかし最高に常識外れな聞き慣れた声。
目の前の雨に濡れた薄暗い小学校の教室の風景の色が薄れていく。そしてその灰色の世界に、突如として奇妙な色彩と、甘ったるい香りが嵐のように乱入してきた。
――レイカさんの家の、豪華絢爛なダイニングテーブル。
私の目の前に置かれた、ガラスの器。
その中に満たされた、病的なほど均一な淡い黄色のムース。
古いオフィスの壁紙のような模様が引かれた、食べる異次元空間『バックルームの一室』のデザート。
「現実世界から稀に『noclip』……つまり外れ落ちてしまうと迷い込む、無限に続く黄色い部屋。湿ったカーペットの匂いと、蛍光灯の不快なハム音だけが響く、永遠の迷宮……」
うっとりとした表情で、彼女は一人語り始める。その瞳は、目の前のデザートの向こうに広がる、広大なオカルトの世界へとその意識を飛ばしている。
そして、悔しいことに、それはとてつもなく美味しかった。不気味な見た目と意味不明なコンセプトに反して、デザートらしい南国の風味。
――次に現れたのは、日の光が降り注ぐ、平和な公園の光景だった。神木の前で、彼女は自作のガラクタ機械『マナライザー』を恭しく構えている。
「おお……! ご覧なさいサヤカ! この地に満ちるマナの濃度を、極めて高い数値で示しておりますわ!」
一人で興奮する彼女の隣で、私が羞恥心に耐えていた、まさにその時。
ビビビビビッ!!
けたたましい警告音。振り切れるメーター。「極めて強大な霊的存在が急速に接近しています!」と叫ぶ彼女。その全ての原因が、ベンチに座っていたおじいさんの携帯ラジオだったと判明した時の、あの間の抜けた演歌の響きと、途方もない脱力感。
そうだ。
そうだ、そうだ、そうだ。
私の日常は、こんな灰色の静かなものじゃなかった。
西園寺レイカが来てからの毎日は、もっとずっと騒々しくて、迷惑で、腹立たしくて、めちゃくちゃで。
けれど。
けれど、それは決して孤独ではなかった。
私の隣にはいつも、あのとんでもないお嬢様がいた。
私の平穏をずかずかと踏み荒らし、私の常識を片っ端から破壊していく、歩く厄災が。
『……おまえは、ひとりだ……』
頭の中に再び、あの冷たい声が響く。
うるさい。
『……おまえは、ずっとひとりだった……』
うるさい!
『……これからも、ずっとひとりなのだ……』
「うるさいっ!」
私は心の底から叫んでいた。
目の前の薄暗い教室の幻覚に向かって。
「一人なんかじゃない!」
私のその叫びに、灰色の世界が薄れていく。
「私の隣にはいつも、迷惑で腹立たしくて常識の通じない、とんでもない奴がいた! 私のことなんかお構いなしに、自分の好奇心だけで突っ走る、最悪の『運命の友』が!」
そうだ。
平穏な日常?
誰とも関わらない、孤独な世界?
そんなもの、もうこりごりだ。
「あんな、退屈な毎日に戻るくらいなら!」
私は目の前の幻影を睨みつけた。
雨に濡れた校庭。破かれた教科書。泥だらけの上履き。
あの頃の、無力で孤独だった私。
「あんな色のない世界に戻るくらいなら、厄介な奴と、めちゃくちゃな非日常を生きてる方が、ずっとずっとマシだ!」
私の魂からの叫び。
それが引き金になった。
目の前の灰色の世界が完全に消えていた。
教室も、雨も、孤独だった私も、全てが消えて、なくなってしまっていた。
後に残ったのは、完全な闇。
そして耳の奥でまだ鳴り続けている、あの呪いの音。
しかし、もうあの声は聞こえない。
私の心が、呪いの囁きを完全に拒絶したのだ。
ふと、膝の上で何かがぴくりと動いた。
見ると、ぐったりとしていたはずのレイカさんの指が、かすかに動いている。
私の想いが届いたのか。
いや、それだけではない。
彼女もまた私と同じように、戦っているのかもしれない。
この魂の奥底で。
見えない敵と。
「……レイカさん」
私は彼女の冷たくなった手をそっと握りしめた。
氷のように冷たい。
けれど、その奥にかすかな、本当に、かすかな温かさが残っているような気がした。
「……負けないで」
私は祈るように呟いた。
「あなたがいないと、退屈なんだから。早く目を覚まして、また私に迷惑かけに来なさいよ」
その言葉が届いたのかどうかは分からない。
けれど握りしめた彼女の手が、ほんの少しだけ力を込めて握り返してきたような、そんな気がした。
私たちは、二人だった。
一人じゃない。
この暗闇の中で、二人で戦っている。
その事実が私の心を強く、強く支えてくれた。
私は彼女の手を固く固く握りしめたまま、じっと目を閉じた。
耳鳴りのような呪いの音だけが、この閉ざされた空間に響き続けている。
けれど、もう怖くはなかった。
夜明けはきっと来る。
二人で、この夜を越えてみせる。
◇
どれくらいの時間が経ったのだろうか。
一瞬のようにも、永遠のようにも感じられた暗闇の中での戦い。
耳の奥で鳴り続けていた、あの甲高いノイズが少しずつその音量を下げていくのを感じていた。
そして、ついにその音はぷつりと完全に途絶えた。
まるでずっとつきまとっていた重たい霊が、ようやく離れていってくれたかのように。
後に残ったのは、完全な静寂。
私が恐る恐る瞼を持ち上げた、その時だった。
ちりん。
どこかで涼やかな鈴の音がした。
そして、閉ざされていたはずの『鎮めの間』の、その分厚い木の扉の隙間から一本の細く白い光が差し込んできたのだ。
朝の光。
夜が明けたのだ。
そのあまりにも神々しい光景に、私は息を呑んだ。
光はゆっくりとその筋を太くしていく。
やがて外からごとりとかんぬきが外される音がして、重たい扉がぎい、と音を立てて開かれた。
そこに立っていたのは、あの巫女だった。
彼女の背後から眩しいほどの朝日が洪水のように流れ込んでくる。
その光に、闇は一瞬にして消し飛ばされた。
「……夜が明けました」
巫女は静かにそう告げた。
その顔にはかすかな安堵の色が浮かんでいるように見えた。
「儀式は終わりです。よくぞ、耐え抜きました」
その言葉に、私の全身からどっと力が抜けていくのが分かった。
終わった。
本当に終わったんだ。
助かったんだ。
「……レイカさんは!?」
私ははっとして、膝の上の彼女を見た。
レイカさんの顔にはいつの間にか血の気が戻っていた。
唇も健康的な桜色を取り戻している。
そしてその胸は穏やかに、規則正しく上下していた。
すー、すー、と安らかな寝息が聞こえる。
「……ああ……」
安堵のあまり、涙がこぼれそうになる。
よかった。
本当に、よかった。
「……ん……」
その時、私の膝の上でレイカさんがかすかに身じろぎをした。
そして、ゆっくりとその長い睫毛に縁取られた瞼が持ち上がっていく。
現れたのは、黒曜石のような深い色の瞳。
その瞳は最初、ぼんやりと虚空をさまよっていたが、やがて目の前で自分を覗き込んでいる私の顔を、はっきりと捉えた。
「……サ、ヤカ……?」
かすれた寝起きのような声。
けれど、それは紛れもなく私の知っている西園寺レイカの声だった。
「……ここは……? わたくし、一体……?」
彼女は状況が全く理解できていないようだった。
自分の身に何が起こったのか、覚えていないのかもしれない。
その、いつもと変わらない少しだけ呑気な表情を見て、私の張り詰めていたものが完全に切れた。
「……っ、この、バカ!」
私は彼女のその広い額を、ぺしりと平手で叩いていた。
「い、痛っ!? まあ、サヤカ、いきなり何を……!」
「バカ! あなたのせいでどれだけひどい目に遭ったと思ってるの! 死ぬかと思ったんだからね、こっちは!」
涙と鼻水でぐちゃぐちゃになりながら、私は彼女に悪態をついた。
「もう絶対に二度とあなたのオカルト趣味には付き合わないから! 絶対に、絶対に、絶対に、よ!」
私の魂からの叫び。
それを聞いたレイカさんは一瞬きょとんとしていたが、やがて全てを思い出したようだった。
廃病院、公衆電話、呪いの声。
彼女の顔がさっと青ざめる。
そして、私に向かって深々と、それはもう地面に額がつくほどに深く頭を下げた。
「……申し訳、ありませんでした……っ!」
そのあまりにも殊勝な態度に、私は逆に毒気を抜かれてしまった。
◇
帰り道。
朝日がさんさんと降り注ぐ神社の石段を、私たちはゆっくりと下りていた。
あの後、巫女さんから改めて礼を言われた。
『あなたたちの絆が、呪いを打ち破ったのです』と。
そしてお守りだと言って、小さな白い蛇の抜け殻が入ったお守りを二つくれた。
これさえ持っていれば、もう低級な霊は寄ってこないらしい。
レイカさんはまだ少しふらついていたが、一人で歩けるまでには回復していた。
私たちはどちらからともなく無言だった。
気まずいというのとは少し違う。
ただ、あまりにも壮絶な一夜を共に過ごしてしまったせいで、どんな言葉を交わせばいいのか分からなかったのだ。
鳥居をくぐり、住宅街へと戻ってくる。
新聞配達のバイクの音が遠くで聞こえる。
世界はいつも通りの朝を迎えていた。
昨夜のあの出来事が、全て悪夢だったかのように。
「……あの、サヤカ」
先に沈黙を破ったのはレイカさんだった。
「はい?」
「今回は本当に、わたくしの認識が甘かったですわ。深く反省しております」
「……そう」
「もう二度と、あのような危険な場所へあなたをお連れするようなことはいたしません」
その真剣な誓いの言葉。
私は少しだけ驚いて彼女の顔を見た。
彼女は本気でそう思っているようだった。
ようやく、このとんでもないお嬢様も少しは懲りたのかもしれない。
そのことに私は心の底から安堵した。
「……分かればいいのよ。分かれば」
私は少しだけ偉そうにそう言った。
これでようやく、私の平穏な夏休みが戻ってくる。
そう思った。
しかし、西園寺レイカという人間は私のそんなささやかな希望を、常にはるかに超えてくる。
「ええ。ですので、これからは方針を改めようと思いますの」
「方針?」
「はい。これまでの実地へ向かうような実践的な調査は、一旦中止いたします」
彼女はこくりと力強く頷いた。
「そして今後はもっと安全で、学術的なアプローチに切り替えていこうかと」
「学術的、アプローチ……?」
嫌な、予感がした。
とてつもなく、嫌な予感が。
レイカさんはそんな私の内心のざわめきなどお構いなしに、その瞳をきらきらと輝かせた。
「ええ! まずは手始めに、古今東西の悪魔召喚に関する古文書を、徹底的に読み解いてみようと思いますの! 幸い、わたくしの家の書庫には一般には出回っていない貴重な魔導書が何冊か眠っておりますし」
「……は?」
「そして理論を完璧にマスターした上で、安全が完全に確保されたわたくしの家の、あの結界が張られた一室で召喚の儀式を試してみるのですわ! もちろん、呼び出すのはゴエティアに記されたソロモン72柱の、比較的温厚で対話が可能な上級の悪魔に限定しますけれど!」
彼女はうっとりとした表情でそう語った。
その顔には一点の曇りもない、純粋な探究心の色が浮かんでいる。
「ああ、なんて胸が躍る計画でしょう! これならサヤカにも、一切危険はございませんわ! ね?」
彼女はにっこりと花が咲くように微笑んで、私の同意を求めてきた。
私は。
私はただ呆然と、その美しくも最高に厄介な横顔を見つめることしかできなかった。
「……はあ」
私の口から今日一番深くて長くて、そして諦めに満ちたため息が漏れた。
ダメだ。
この人は何も変わっていない。
私の平穏な日常は、どうやらもう二度と戻ってはこないらしい。
この迷惑で手のかかる『運命の友』が、隣にいる限りは。
けれど。
不思議と、それはもうそれほど嫌ではなかった。
朝日が私たちの長い長い影を、アスファルトの上に、くっきりと描き出していた。
騒がしくて退屈とは無縁の、私たちの新しい夏休みが、今ようやく始まろうとしていた。
私の意識が冷たく心地よい絶望の底へと、ゆっくりと沈んでいく。膝の上で眠るレイカさんの温かささえもが遠い世界の出来事のように感じられ始めた。もう何もかもがどうでもよかった。
私がその甘い諦めに魂の全てを委ねようとした、まさにその時だった。
「――サヤカ、お待たせいたしましたわ。こちらが、わたくしたちを次なる次元へと誘うための、特別な儀式ですの」
不意に頭の中に全く別の声が割り込んできた。
それはあの呪いの声とは似ても似つかない、どこまでも優雅で、しかし最高に常識外れな聞き慣れた声。
目の前の雨に濡れた薄暗い小学校の教室の風景の色が薄れていく。そしてその灰色の世界に、突如として奇妙な色彩と、甘ったるい香りが嵐のように乱入してきた。
――レイカさんの家の、豪華絢爛なダイニングテーブル。
私の目の前に置かれた、ガラスの器。
その中に満たされた、病的なほど均一な淡い黄色のムース。
古いオフィスの壁紙のような模様が引かれた、食べる異次元空間『バックルームの一室』のデザート。
「現実世界から稀に『noclip』……つまり外れ落ちてしまうと迷い込む、無限に続く黄色い部屋。湿ったカーペットの匂いと、蛍光灯の不快なハム音だけが響く、永遠の迷宮……」
うっとりとした表情で、彼女は一人語り始める。その瞳は、目の前のデザートの向こうに広がる、広大なオカルトの世界へとその意識を飛ばしている。
そして、悔しいことに、それはとてつもなく美味しかった。不気味な見た目と意味不明なコンセプトに反して、デザートらしい南国の風味。
――次に現れたのは、日の光が降り注ぐ、平和な公園の光景だった。神木の前で、彼女は自作のガラクタ機械『マナライザー』を恭しく構えている。
「おお……! ご覧なさいサヤカ! この地に満ちるマナの濃度を、極めて高い数値で示しておりますわ!」
一人で興奮する彼女の隣で、私が羞恥心に耐えていた、まさにその時。
ビビビビビッ!!
けたたましい警告音。振り切れるメーター。「極めて強大な霊的存在が急速に接近しています!」と叫ぶ彼女。その全ての原因が、ベンチに座っていたおじいさんの携帯ラジオだったと判明した時の、あの間の抜けた演歌の響きと、途方もない脱力感。
そうだ。
そうだ、そうだ、そうだ。
私の日常は、こんな灰色の静かなものじゃなかった。
西園寺レイカが来てからの毎日は、もっとずっと騒々しくて、迷惑で、腹立たしくて、めちゃくちゃで。
けれど。
けれど、それは決して孤独ではなかった。
私の隣にはいつも、あのとんでもないお嬢様がいた。
私の平穏をずかずかと踏み荒らし、私の常識を片っ端から破壊していく、歩く厄災が。
『……おまえは、ひとりだ……』
頭の中に再び、あの冷たい声が響く。
うるさい。
『……おまえは、ずっとひとりだった……』
うるさい!
『……これからも、ずっとひとりなのだ……』
「うるさいっ!」
私は心の底から叫んでいた。
目の前の薄暗い教室の幻覚に向かって。
「一人なんかじゃない!」
私のその叫びに、灰色の世界が薄れていく。
「私の隣にはいつも、迷惑で腹立たしくて常識の通じない、とんでもない奴がいた! 私のことなんかお構いなしに、自分の好奇心だけで突っ走る、最悪の『運命の友』が!」
そうだ。
平穏な日常?
誰とも関わらない、孤独な世界?
そんなもの、もうこりごりだ。
「あんな、退屈な毎日に戻るくらいなら!」
私は目の前の幻影を睨みつけた。
雨に濡れた校庭。破かれた教科書。泥だらけの上履き。
あの頃の、無力で孤独だった私。
「あんな色のない世界に戻るくらいなら、厄介な奴と、めちゃくちゃな非日常を生きてる方が、ずっとずっとマシだ!」
私の魂からの叫び。
それが引き金になった。
目の前の灰色の世界が完全に消えていた。
教室も、雨も、孤独だった私も、全てが消えて、なくなってしまっていた。
後に残ったのは、完全な闇。
そして耳の奥でまだ鳴り続けている、あの呪いの音。
しかし、もうあの声は聞こえない。
私の心が、呪いの囁きを完全に拒絶したのだ。
ふと、膝の上で何かがぴくりと動いた。
見ると、ぐったりとしていたはずのレイカさんの指が、かすかに動いている。
私の想いが届いたのか。
いや、それだけではない。
彼女もまた私と同じように、戦っているのかもしれない。
この魂の奥底で。
見えない敵と。
「……レイカさん」
私は彼女の冷たくなった手をそっと握りしめた。
氷のように冷たい。
けれど、その奥にかすかな、本当に、かすかな温かさが残っているような気がした。
「……負けないで」
私は祈るように呟いた。
「あなたがいないと、退屈なんだから。早く目を覚まして、また私に迷惑かけに来なさいよ」
その言葉が届いたのかどうかは分からない。
けれど握りしめた彼女の手が、ほんの少しだけ力を込めて握り返してきたような、そんな気がした。
私たちは、二人だった。
一人じゃない。
この暗闇の中で、二人で戦っている。
その事実が私の心を強く、強く支えてくれた。
私は彼女の手を固く固く握りしめたまま、じっと目を閉じた。
耳鳴りのような呪いの音だけが、この閉ざされた空間に響き続けている。
けれど、もう怖くはなかった。
夜明けはきっと来る。
二人で、この夜を越えてみせる。
◇
どれくらいの時間が経ったのだろうか。
一瞬のようにも、永遠のようにも感じられた暗闇の中での戦い。
耳の奥で鳴り続けていた、あの甲高いノイズが少しずつその音量を下げていくのを感じていた。
そして、ついにその音はぷつりと完全に途絶えた。
まるでずっとつきまとっていた重たい霊が、ようやく離れていってくれたかのように。
後に残ったのは、完全な静寂。
私が恐る恐る瞼を持ち上げた、その時だった。
ちりん。
どこかで涼やかな鈴の音がした。
そして、閉ざされていたはずの『鎮めの間』の、その分厚い木の扉の隙間から一本の細く白い光が差し込んできたのだ。
朝の光。
夜が明けたのだ。
そのあまりにも神々しい光景に、私は息を呑んだ。
光はゆっくりとその筋を太くしていく。
やがて外からごとりとかんぬきが外される音がして、重たい扉がぎい、と音を立てて開かれた。
そこに立っていたのは、あの巫女だった。
彼女の背後から眩しいほどの朝日が洪水のように流れ込んでくる。
その光に、闇は一瞬にして消し飛ばされた。
「……夜が明けました」
巫女は静かにそう告げた。
その顔にはかすかな安堵の色が浮かんでいるように見えた。
「儀式は終わりです。よくぞ、耐え抜きました」
その言葉に、私の全身からどっと力が抜けていくのが分かった。
終わった。
本当に終わったんだ。
助かったんだ。
「……レイカさんは!?」
私ははっとして、膝の上の彼女を見た。
レイカさんの顔にはいつの間にか血の気が戻っていた。
唇も健康的な桜色を取り戻している。
そしてその胸は穏やかに、規則正しく上下していた。
すー、すー、と安らかな寝息が聞こえる。
「……ああ……」
安堵のあまり、涙がこぼれそうになる。
よかった。
本当に、よかった。
「……ん……」
その時、私の膝の上でレイカさんがかすかに身じろぎをした。
そして、ゆっくりとその長い睫毛に縁取られた瞼が持ち上がっていく。
現れたのは、黒曜石のような深い色の瞳。
その瞳は最初、ぼんやりと虚空をさまよっていたが、やがて目の前で自分を覗き込んでいる私の顔を、はっきりと捉えた。
「……サ、ヤカ……?」
かすれた寝起きのような声。
けれど、それは紛れもなく私の知っている西園寺レイカの声だった。
「……ここは……? わたくし、一体……?」
彼女は状況が全く理解できていないようだった。
自分の身に何が起こったのか、覚えていないのかもしれない。
その、いつもと変わらない少しだけ呑気な表情を見て、私の張り詰めていたものが完全に切れた。
「……っ、この、バカ!」
私は彼女のその広い額を、ぺしりと平手で叩いていた。
「い、痛っ!? まあ、サヤカ、いきなり何を……!」
「バカ! あなたのせいでどれだけひどい目に遭ったと思ってるの! 死ぬかと思ったんだからね、こっちは!」
涙と鼻水でぐちゃぐちゃになりながら、私は彼女に悪態をついた。
「もう絶対に二度とあなたのオカルト趣味には付き合わないから! 絶対に、絶対に、絶対に、よ!」
私の魂からの叫び。
それを聞いたレイカさんは一瞬きょとんとしていたが、やがて全てを思い出したようだった。
廃病院、公衆電話、呪いの声。
彼女の顔がさっと青ざめる。
そして、私に向かって深々と、それはもう地面に額がつくほどに深く頭を下げた。
「……申し訳、ありませんでした……っ!」
そのあまりにも殊勝な態度に、私は逆に毒気を抜かれてしまった。
◇
帰り道。
朝日がさんさんと降り注ぐ神社の石段を、私たちはゆっくりと下りていた。
あの後、巫女さんから改めて礼を言われた。
『あなたたちの絆が、呪いを打ち破ったのです』と。
そしてお守りだと言って、小さな白い蛇の抜け殻が入ったお守りを二つくれた。
これさえ持っていれば、もう低級な霊は寄ってこないらしい。
レイカさんはまだ少しふらついていたが、一人で歩けるまでには回復していた。
私たちはどちらからともなく無言だった。
気まずいというのとは少し違う。
ただ、あまりにも壮絶な一夜を共に過ごしてしまったせいで、どんな言葉を交わせばいいのか分からなかったのだ。
鳥居をくぐり、住宅街へと戻ってくる。
新聞配達のバイクの音が遠くで聞こえる。
世界はいつも通りの朝を迎えていた。
昨夜のあの出来事が、全て悪夢だったかのように。
「……あの、サヤカ」
先に沈黙を破ったのはレイカさんだった。
「はい?」
「今回は本当に、わたくしの認識が甘かったですわ。深く反省しております」
「……そう」
「もう二度と、あのような危険な場所へあなたをお連れするようなことはいたしません」
その真剣な誓いの言葉。
私は少しだけ驚いて彼女の顔を見た。
彼女は本気でそう思っているようだった。
ようやく、このとんでもないお嬢様も少しは懲りたのかもしれない。
そのことに私は心の底から安堵した。
「……分かればいいのよ。分かれば」
私は少しだけ偉そうにそう言った。
これでようやく、私の平穏な夏休みが戻ってくる。
そう思った。
しかし、西園寺レイカという人間は私のそんなささやかな希望を、常にはるかに超えてくる。
「ええ。ですので、これからは方針を改めようと思いますの」
「方針?」
「はい。これまでの実地へ向かうような実践的な調査は、一旦中止いたします」
彼女はこくりと力強く頷いた。
「そして今後はもっと安全で、学術的なアプローチに切り替えていこうかと」
「学術的、アプローチ……?」
嫌な、予感がした。
とてつもなく、嫌な予感が。
レイカさんはそんな私の内心のざわめきなどお構いなしに、その瞳をきらきらと輝かせた。
「ええ! まずは手始めに、古今東西の悪魔召喚に関する古文書を、徹底的に読み解いてみようと思いますの! 幸い、わたくしの家の書庫には一般には出回っていない貴重な魔導書が何冊か眠っておりますし」
「……は?」
「そして理論を完璧にマスターした上で、安全が完全に確保されたわたくしの家の、あの結界が張られた一室で召喚の儀式を試してみるのですわ! もちろん、呼び出すのはゴエティアに記されたソロモン72柱の、比較的温厚で対話が可能な上級の悪魔に限定しますけれど!」
彼女はうっとりとした表情でそう語った。
その顔には一点の曇りもない、純粋な探究心の色が浮かんでいる。
「ああ、なんて胸が躍る計画でしょう! これならサヤカにも、一切危険はございませんわ! ね?」
彼女はにっこりと花が咲くように微笑んで、私の同意を求めてきた。
私は。
私はただ呆然と、その美しくも最高に厄介な横顔を見つめることしかできなかった。
「……はあ」
私の口から今日一番深くて長くて、そして諦めに満ちたため息が漏れた。
ダメだ。
この人は何も変わっていない。
私の平穏な日常は、どうやらもう二度と戻ってはこないらしい。
この迷惑で手のかかる『運命の友』が、隣にいる限りは。
けれど。
不思議と、それはもうそれほど嫌ではなかった。
朝日が私たちの長い長い影を、アスファルトの上に、くっきりと描き出していた。
騒がしくて退屈とは無縁の、私たちの新しい夏休みが、今ようやく始まろうとしていた。