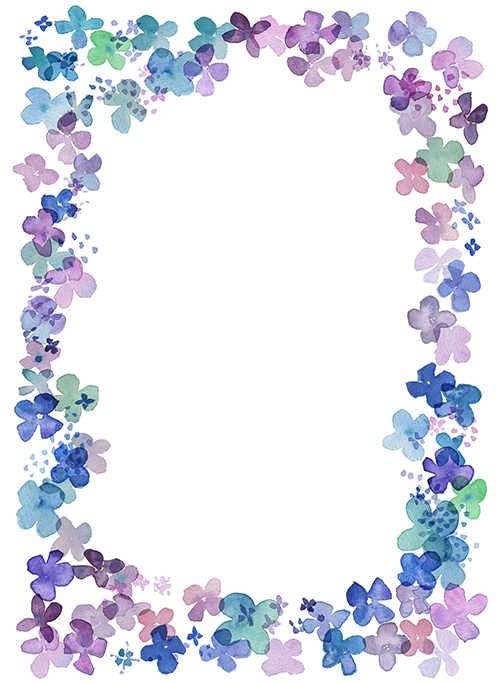肺が焼け付くように熱い。足はもうただの肉の塊になったかのように感覚がなく、それでも前に、前へと動き続けている。肩に担いだレイカさんの重みが私のけして多くない体力を根こそぎ奪っていく。けれど、ここで足を止めるわけにはいかなかった。止まってしまえば、あの黒いナニカに追いつかれる。
スマートフォンの地図が示す『白蛇神社』は、小高い丘の上にあるようだった。住宅街を抜け、緩やかな上り坂に差し掛かる。アスファルトの道が途切れ、目の前に現れたのは闇の中にどこまでも続いているかのように見える、長い長い石段だった。その入り口には古びた石造りの鳥居が、まるで異世界への門のように静かにたたずんでいる。
「……はぁっ、はあっ……!」
鳥居をくぐった瞬間、空気がわずかに変わったのを感じた。まとわりつくような夏の夜の湿気がすっと薄れ、代わりにひんやりとした清浄な空気が肌を撫でる。植物の匂い。土の匂い。それは明らかに麓の住宅街とは違う、神聖な場所が持つ特別な匂いだった。
背後で、何かが蠢く気配が遠のいたような気がした。あのじっとりとした視線が鳥居の向こう側で、ためらっているかのように感じられる。
マダム・オリビアの言った通りだ。神社の境内は奴らにとって、簡単には踏み入れない領域なのだろう。
ほんのわずかな安堵が私の胸に広がる。しかし、まだ安心はできない。完全に奴らを振り切ったわけではないのだ。
「……あと、少し……」
私は自分に言い聞かせるように呟くと、目の前の石段を見上げた。終わりが見えない。けれど行くしかないのだ。
一段、また一段と鉛のように重い足を、持ち上げる。レイカさんを担いだままの体勢では、バランスを取るのも一苦労だった。何度かよろけて、石段に手をつきそうになる。そのたびに奥歯を食いしばり、必死に体勢を立て直した。
耳の奥で、まだあの音が鳴っている。キィィィ……という甲高いノイズ。それは少しだけ小さくなったような気もしたが、決して消えてはくれなかった。この呪いは私の魂に、深く、深く刻み込まれてしまっている。
どれくらい上っただろうか。もう自分が何段目にいるのか、考える余裕もなかった。ただ機械的に足を動かし続ける。
やがて前方に、ぼんやりとした温かい光が見えてきた。
提灯の光だ。
石段の終わり。その先に、神社の社殿らしき建物が闇の中から静かに浮かび上がっている。
着いた。
ようやくたどり着いたのだ。
最後の力を振り絞り、石段を駆け上がる。そして平らな地面に足を踏み入れた瞬間、私の膝は限界を迎えたようにがくりと折れた。
「……きゃっ!」
レイカさんの体を、地面に落としてしまう。幸い、砂利が敷き詰められた境内だったためひどい怪我にはならなかったようだったが、申し訳なさで胸が痛んだ。
「ごめん、レイカさん……」
私は彼女の隣に倒れ込むようにして座り込んだ。もう指一本動かす気力も残っていない。荒い呼吸を繰り返しながら、ただ夜空を見上げる。木々の隙間から見える空は相変わらず、星一つない闇に閉ざされていた。
その時だった。
社殿の奥からさっと衣擦れの音がして、一人の人物が姿を現した。
その姿に、私は思わず息を呑んだ。
若い女性だった。おそらく私とそう年は変わらないだろう。長く艶やかな黒髪を低い位置で一つに束ね、白衣と緋色の袴という巫女の装束を身にまとっている。
その顔立ちは整ってはいたが、レイカさんのような華やかさはない。むしろ、どこか近寄りがたいような凛とした空気をその全身から放っていた。月明かりもないこの暗闇の中で、彼女の白い肌だけが内側から淡い光を放っているかのように見えた。
彼女は境内の真ん中で倒れている私たちを一瞥すると、何の驚きも見せずに静かにこちらへと歩み寄ってきた。その足取りには何の迷いもなかった。
「……お待ちしておりました」
涼やかで、けれどどこか感情の温度を感じさせない声だった。
「あなたが鮫島サヤカさん。そして、そちらが西園寺レイカさんですね」
「は、はい……」
私はかろうじてそう答えた。マダム・オリビアが話を通してくれている。その事実に私は心の底から安堵した。
「オリビア様よりお話は伺っております。よくぞご無事で、ここまで」
巫女は淡々とそう言った。その瞳は深い森の湖のように、静かで底が見えない。彼女は私たちの姿を見ても一切動揺する様子を見せなかった。まるでこのような異常事態に慣れきっているかのように。
彼女は私の隣でぐったりと横たわるレイカさんのそばに、静かに膝をついた。そしてその白い指先を、レイカさんの額にそっと触れさせる。
「……ひどい。魂のほとんどを持っていかれている」
ぽつりと呟かれたその言葉に、私の背筋が凍りついた。
「そ、そんな……! レイカさんは助かりますよね!?」
「……五分、といったところでしょう」
「ごふん!?」
「ええ。もし、あなたが後五分ここに到着するのが遅れていたら、彼女の魂は完全に、向こう側へと引きずり込まれていた。そうなれば、いかなる手段をもってしても呼び戻すことは叶わなかった」
その、あまりにも淡々とした口調が、逆に事態の深刻さを私に突きつけてくる。
私はごくりと、乾いた喉を鳴らした。
「ですが、幸い間に合った。まだかろうじてこちらの世界に繋ぎ止められている。助かる道は、ただ一つだけ残されています」
「ほ、本当ですか!?」
「ええ」
巫女はこくりと頷くと、ゆっくりと立ち上がった。そして私にその静かな視線を向ける。
「あなたたちが聞いた声は、オリビア様から伺った通り『黄泉の国の呼び声』そのものです。古くからこの土地の特定の場所に、現世と常世の境界がひどく曖昧になる『穴』が開くことがある。あなたたちは運悪く、その『穴』の真上にあった公衆電話を使って向こう側の声を直接聞いてしまった」
「黄泉の国……」
そのあまりにも現実離れした言葉に、私はただ呆然とするしかなかった。
「その声は聞いた者の魂に直接作用する。生命力を奪い、徐々に、徐々に向こう側へと引きずり込んでいく。通常の除霊や、お祓いでは到底太刀打ちできない強力な呪いです」
「じゃあ、どうすれば……」
「助かる方法は、ただ一つ」
巫女はそう言うと、社殿の奥を指差した。
その先はさらに深い闇に閉ざされている。
「この神社のさらに奥。決して人の足を踏み入れてはならない聖域があります。そこに注連縄で厳重に封印された、一つの間がある。『鎮めの間』。そこで夜明けまで特別な儀式を受け続けること。それだけがあなたたちの魂を浄化するための、唯一の方法です」
「鎮めの間……」
その重々しい響きを持つ言葉を、私は口の中で繰り返した。
「ただし」
巫女はそこで一度、言葉を切った。
その瞳が私をまっすぐに射抜く。
「儀式は決して楽なものではありません。儀式の間、呪いはその身を消されまいと激しく抵抗するでしょう。あなたたちの心の、一番弱い部分に付け込んできます。幻聴や幻覚を見せ、あなたたちの心を折りにくる」
「幻覚……」
「それに屈してしまえば、儀式は失敗に終わります。そうなればもう二度と助かる道はない。あなたたちの魂は完全に呪いに飲み込まれることになる」
その言葉は静かだったが、絶対的な重みを持っていた。
私はごくりと息を呑んだ。
心の、一番弱い部分。
今の私に、そんなものに立ち向かうだけの強さが残っているだろうか。
恐怖が冷たい霧のように、私の心を覆い尽くしていく。
私のその表情の変化を、巫女は見逃さなかった。
「……怖いですか?」
「……っ」
私は言葉に詰まった。
怖い。
怖いに決まっている。
死ぬかもしれないという恐怖。
正気を失ってしまうかもしれないという恐怖。
けれど、それ以上に。
「……レイカさんを、助けたい」
私の口から絞り出すように、その言葉が漏れた。
そうだ。
私が今ここにいる理由は、それだけだ。
彼女がいなければ。
私の世界はもう、色を失ってしまう。
あの退屈で息の詰まる灰色の世界に、戻ってしまう。
それだけは、絶対に嫌だ。
「……やります」
私は巫女の目をまっすぐに見つめ返して、言った。
「儀式を受けさせてください。絶対に、呪いには負けません」
その、自分でも驚くほど力強い言葉。
それを聞いた巫女は初めて、その表情をわずかに緩めた。
それは笑みと呼ぶにはあまりにもかすかな変化だったが。
その唇の端に、ほんの少しだけ温かいものが宿ったように見えた。
「……覚悟は、決まったようですね」
彼女はそう言うと、私に背を向けた。
「では、こちらへ。私が『鎮めの間』までご案内します」
巫女はぐったりとしているレイカさんの体を、ひょいと軽々とその細い腕で抱え上げた。その信じられないような光景に、私はただ目を丸くするしかなかった。
彼女はレイカさんをまるで軽い荷物でも運ぶかのように小脇に抱えると、闇の中へと歩き始めた。
私は慌ててその後を追った。
社殿の脇にある小さな脇道を、進んでいく。
道は整備されておらず、木の根があちこちで剥き出しになっていた。
周囲の木々がさらにその密度を増していく。
まるで世界の奥へ奥へと進んでいくかのような、不思議な感覚。
やがて前方に、一つの古びた小さな建物が見えてきた。
それは本殿とは明らかに違う、質素で、しかしどこか厳かな空気をまとった小さな社だった。
その唯一の入り口である木製の扉には、太く真新しい注連縄が何重にも固く巻き付けられている。
注連縄には白い紙垂がいくつも吊り下げられていた。
ここだ。
ここが『鎮めの間』。
「……ここからは、あなた一人です」
巫女は建物の前でぴたりと足を止めた。
「私は外から儀式が無事に終わるよう祈りを捧げます。ですが、中のあなたを直接助けることはできない」
「……はい」
「夜明けまで、あとおよそ四時間。心を強く持ちなさい」
彼女はそう言うと、慣れた手つきで扉に巻き付けられた注連縄を解き始めた。
ぎ、ぎぎ……と縄が擦れる音が静かな森の中に響く。
全ての注連縄が解かれる。
そして巫女は、その重たい木製の扉をゆっくりと押し開けた。
中から、ひやりとした空気が流れ出してくる。
それはただ冷たいだけではない。
長い長い年月をこの場所で過ごしてきた、濃密な気の流れ。
そして、かすかに古い木の匂いと香の匂いがした。
中は完全な闇だった。
「さあ、入りなさい」
巫女は抱えていたレイカさんの体を、私にそっと手渡した。
私は彼女の体をしっかりと抱きしめる。
そして、意を決してその闇の中へと足を踏み入れた。
一歩、中へ入った瞬間。
背後で、ぎい、と重たい音を立てて扉が閉められた。
ごとり、と外からかんぬきがかけられる音がする。
完全な闇と静寂。
私はこの聖域に閉じ込められたのだ。
レイカさんと、二人きりで。
私は手探りで壁を伝い、ゆっくりとその場に座り込んだ。
抱きかかえたレイカさんの体を自分の膝の上にそっと横たえる。
彼女の浅い呼吸だけが、この静寂の中で唯一の音だった。
儀式はもう始まっているのだろうか。
何をすればいいのか、分からない。
ただ目を閉じて、夜が明けるのを待つしかないのか。
私がそう思った、その時だった。
キィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ
耳の奥で、あの呪いの音が再びその音量を増し始めた。
先ほどよりも、ずっと、ずっと大きく。
はっきりと。
それはもはや、ただのノイズではなかった。
その音の羅列の中に、明確な意思のようなものが感じられた。
私を嘲笑うかのような、悪意。
私を絶望させようとする、明確な意図。
呪いが、牙を剥いたのだ。
『……サヤカ……』
不意に頭の中に直接、声が響いた。
それは誰の声でもなかった。男でも女でもない。幼くも老いてもいない。
ただ冷たく、どこまでも冷たい声。
『……おまえは、ひとりだ……』
その言葉と同時に、私の意識は暗闇の中へと急速に引きずり込まれていった。
目の前の完全な闇がぐにゃりと歪む。
そして、そこに一つの光景が浮かび上がってきた。
ざあ、ざあと雨が窓ガラスを叩く音。
薄暗い小学校の教室。
放課後、誰もいなくなった教室で私は一人、自分の席に座っていた。
机の上には、ぐちゃぐちゃに破かれた教科書とノート。
床には泥のついた上履きが転がっている。
私の、上履きだ。
さっきまで、クラスの男子たちにサッカーボール代わりに蹴られていた。
私は泣いていなかった。
ただ、唇を固く固く結んで、窓の外を見つめていた。
雨に濡れた校庭。
そこでは傘を差したクラスメイトたちが、楽しそうに笑いながら下校していく。
その中に、私をいじめていたあの子たちの顔もあった。
誰も、私のことなど気にも留めていない。
まるで私がこの教室に存在していないかのように。
そうだ。
私はこのクラスで孤立していた。
自分の意見を少しだけはっきりと言ってしまった、ただそれだけのことで。
次の日から、誰も私と口を利いてくれなくなった。
私の机はゴミ箱にされた。
持ち物は隠されたり、壊されたりした。
先生に言っても無駄だった。
『気のせいじゃないか』『みんなと、仲良くしなさい』
そう言われるだけだった。
誰も私の味方ではなかった。
私はこの世界でたった一人だった。
自分の存在が消えてしまったかのような、途方もない孤独。
冷たい、絶望。
あの時感じた、あの感情が今、私の心を再び支配していく。
幻覚だ。
これは呪いが見せているただの幻。
そう頭では分かっている。
けれど、この肌を刺すような孤独感はあまりにもリアルだった。
教室の冷たい空気。
雨の湿った匂い。
遠くで聞こえるクラスメイトたちの楽しそうな笑い声。
その一つ一つが私の心を容赦なく抉っていく。
『……そうだ……おまえは、あの頃からずっとひとりだった……』
頭の中に再び、あの声が響く。
『……誰も、おまえのことなど見ていない……』
『……誰も、おまえのことなど必要としていない……』
『……おまえは、この世界に必要のない存在なのだ……』
その言葉は甘い毒のように、私の心に染み渡っていく。
そうだ。
そうだったのかもしれない。
私はずっと一人だった。
誰とも深く関わらないことで、自分を守ってきた。
傷つかないように。
これ以上、孤独にならないように。
平穏な日常。
私が求めていたのは、それだったはずだ。
なのに。
『……あの女も、そうだ……』
声は続ける。
『……あの女も、いずれおまえの前からいなくなる……』
『……おまえは、またひとりに、なるのだ……』
『……それが、おまえの運命なのだから……』
その言葉に私の心はぐらりと大きく揺れた。
そうだ。
レイカさんもいつかいなくなってしまうのかもしれない。
また転校してしまうかもしれない。
あるいは私のことなど飽きてしまって、どこかへ行ってしまうかもしれない。
そうしたら、私はまた一人になる。
あの退屈で静かで、色のない一人の世界に戻るのだ。
それが、怖い。
心の底から怖いと、思ってしまった。
『……ならば、いっそここで全てを終わらせてしまえ……』
声は囁きかける。
悪魔の誘い。
『……このまま、この冷たい絶望の中に身を委ねてしまえば、もう傷つくこともない……』
『……もう、孤独に怯えることもない……』
『……さあ、楽になるのだ……』
その言葉はひどく魅力的だった。
そうだ。
もう疲れた。
戦うのも、抵抗するのも。
このまま、この冷たい闇の中に沈んでしまえたら。
どれだけ楽になれるだろう。
私の意識がゆっくりと、しかし確実にその心地よい絶望の底へと沈んでいく。
膝の上で眠るレイカさんの温かささえも、少しずつ遠のいていくようだった。
もう、いいか。
これで、終わりにしよう。
私がそう諦めかけた、その瞬間だった。
スマートフォンの地図が示す『白蛇神社』は、小高い丘の上にあるようだった。住宅街を抜け、緩やかな上り坂に差し掛かる。アスファルトの道が途切れ、目の前に現れたのは闇の中にどこまでも続いているかのように見える、長い長い石段だった。その入り口には古びた石造りの鳥居が、まるで異世界への門のように静かにたたずんでいる。
「……はぁっ、はあっ……!」
鳥居をくぐった瞬間、空気がわずかに変わったのを感じた。まとわりつくような夏の夜の湿気がすっと薄れ、代わりにひんやりとした清浄な空気が肌を撫でる。植物の匂い。土の匂い。それは明らかに麓の住宅街とは違う、神聖な場所が持つ特別な匂いだった。
背後で、何かが蠢く気配が遠のいたような気がした。あのじっとりとした視線が鳥居の向こう側で、ためらっているかのように感じられる。
マダム・オリビアの言った通りだ。神社の境内は奴らにとって、簡単には踏み入れない領域なのだろう。
ほんのわずかな安堵が私の胸に広がる。しかし、まだ安心はできない。完全に奴らを振り切ったわけではないのだ。
「……あと、少し……」
私は自分に言い聞かせるように呟くと、目の前の石段を見上げた。終わりが見えない。けれど行くしかないのだ。
一段、また一段と鉛のように重い足を、持ち上げる。レイカさんを担いだままの体勢では、バランスを取るのも一苦労だった。何度かよろけて、石段に手をつきそうになる。そのたびに奥歯を食いしばり、必死に体勢を立て直した。
耳の奥で、まだあの音が鳴っている。キィィィ……という甲高いノイズ。それは少しだけ小さくなったような気もしたが、決して消えてはくれなかった。この呪いは私の魂に、深く、深く刻み込まれてしまっている。
どれくらい上っただろうか。もう自分が何段目にいるのか、考える余裕もなかった。ただ機械的に足を動かし続ける。
やがて前方に、ぼんやりとした温かい光が見えてきた。
提灯の光だ。
石段の終わり。その先に、神社の社殿らしき建物が闇の中から静かに浮かび上がっている。
着いた。
ようやくたどり着いたのだ。
最後の力を振り絞り、石段を駆け上がる。そして平らな地面に足を踏み入れた瞬間、私の膝は限界を迎えたようにがくりと折れた。
「……きゃっ!」
レイカさんの体を、地面に落としてしまう。幸い、砂利が敷き詰められた境内だったためひどい怪我にはならなかったようだったが、申し訳なさで胸が痛んだ。
「ごめん、レイカさん……」
私は彼女の隣に倒れ込むようにして座り込んだ。もう指一本動かす気力も残っていない。荒い呼吸を繰り返しながら、ただ夜空を見上げる。木々の隙間から見える空は相変わらず、星一つない闇に閉ざされていた。
その時だった。
社殿の奥からさっと衣擦れの音がして、一人の人物が姿を現した。
その姿に、私は思わず息を呑んだ。
若い女性だった。おそらく私とそう年は変わらないだろう。長く艶やかな黒髪を低い位置で一つに束ね、白衣と緋色の袴という巫女の装束を身にまとっている。
その顔立ちは整ってはいたが、レイカさんのような華やかさはない。むしろ、どこか近寄りがたいような凛とした空気をその全身から放っていた。月明かりもないこの暗闇の中で、彼女の白い肌だけが内側から淡い光を放っているかのように見えた。
彼女は境内の真ん中で倒れている私たちを一瞥すると、何の驚きも見せずに静かにこちらへと歩み寄ってきた。その足取りには何の迷いもなかった。
「……お待ちしておりました」
涼やかで、けれどどこか感情の温度を感じさせない声だった。
「あなたが鮫島サヤカさん。そして、そちらが西園寺レイカさんですね」
「は、はい……」
私はかろうじてそう答えた。マダム・オリビアが話を通してくれている。その事実に私は心の底から安堵した。
「オリビア様よりお話は伺っております。よくぞご無事で、ここまで」
巫女は淡々とそう言った。その瞳は深い森の湖のように、静かで底が見えない。彼女は私たちの姿を見ても一切動揺する様子を見せなかった。まるでこのような異常事態に慣れきっているかのように。
彼女は私の隣でぐったりと横たわるレイカさんのそばに、静かに膝をついた。そしてその白い指先を、レイカさんの額にそっと触れさせる。
「……ひどい。魂のほとんどを持っていかれている」
ぽつりと呟かれたその言葉に、私の背筋が凍りついた。
「そ、そんな……! レイカさんは助かりますよね!?」
「……五分、といったところでしょう」
「ごふん!?」
「ええ。もし、あなたが後五分ここに到着するのが遅れていたら、彼女の魂は完全に、向こう側へと引きずり込まれていた。そうなれば、いかなる手段をもってしても呼び戻すことは叶わなかった」
その、あまりにも淡々とした口調が、逆に事態の深刻さを私に突きつけてくる。
私はごくりと、乾いた喉を鳴らした。
「ですが、幸い間に合った。まだかろうじてこちらの世界に繋ぎ止められている。助かる道は、ただ一つだけ残されています」
「ほ、本当ですか!?」
「ええ」
巫女はこくりと頷くと、ゆっくりと立ち上がった。そして私にその静かな視線を向ける。
「あなたたちが聞いた声は、オリビア様から伺った通り『黄泉の国の呼び声』そのものです。古くからこの土地の特定の場所に、現世と常世の境界がひどく曖昧になる『穴』が開くことがある。あなたたちは運悪く、その『穴』の真上にあった公衆電話を使って向こう側の声を直接聞いてしまった」
「黄泉の国……」
そのあまりにも現実離れした言葉に、私はただ呆然とするしかなかった。
「その声は聞いた者の魂に直接作用する。生命力を奪い、徐々に、徐々に向こう側へと引きずり込んでいく。通常の除霊や、お祓いでは到底太刀打ちできない強力な呪いです」
「じゃあ、どうすれば……」
「助かる方法は、ただ一つ」
巫女はそう言うと、社殿の奥を指差した。
その先はさらに深い闇に閉ざされている。
「この神社のさらに奥。決して人の足を踏み入れてはならない聖域があります。そこに注連縄で厳重に封印された、一つの間がある。『鎮めの間』。そこで夜明けまで特別な儀式を受け続けること。それだけがあなたたちの魂を浄化するための、唯一の方法です」
「鎮めの間……」
その重々しい響きを持つ言葉を、私は口の中で繰り返した。
「ただし」
巫女はそこで一度、言葉を切った。
その瞳が私をまっすぐに射抜く。
「儀式は決して楽なものではありません。儀式の間、呪いはその身を消されまいと激しく抵抗するでしょう。あなたたちの心の、一番弱い部分に付け込んできます。幻聴や幻覚を見せ、あなたたちの心を折りにくる」
「幻覚……」
「それに屈してしまえば、儀式は失敗に終わります。そうなればもう二度と助かる道はない。あなたたちの魂は完全に呪いに飲み込まれることになる」
その言葉は静かだったが、絶対的な重みを持っていた。
私はごくりと息を呑んだ。
心の、一番弱い部分。
今の私に、そんなものに立ち向かうだけの強さが残っているだろうか。
恐怖が冷たい霧のように、私の心を覆い尽くしていく。
私のその表情の変化を、巫女は見逃さなかった。
「……怖いですか?」
「……っ」
私は言葉に詰まった。
怖い。
怖いに決まっている。
死ぬかもしれないという恐怖。
正気を失ってしまうかもしれないという恐怖。
けれど、それ以上に。
「……レイカさんを、助けたい」
私の口から絞り出すように、その言葉が漏れた。
そうだ。
私が今ここにいる理由は、それだけだ。
彼女がいなければ。
私の世界はもう、色を失ってしまう。
あの退屈で息の詰まる灰色の世界に、戻ってしまう。
それだけは、絶対に嫌だ。
「……やります」
私は巫女の目をまっすぐに見つめ返して、言った。
「儀式を受けさせてください。絶対に、呪いには負けません」
その、自分でも驚くほど力強い言葉。
それを聞いた巫女は初めて、その表情をわずかに緩めた。
それは笑みと呼ぶにはあまりにもかすかな変化だったが。
その唇の端に、ほんの少しだけ温かいものが宿ったように見えた。
「……覚悟は、決まったようですね」
彼女はそう言うと、私に背を向けた。
「では、こちらへ。私が『鎮めの間』までご案内します」
巫女はぐったりとしているレイカさんの体を、ひょいと軽々とその細い腕で抱え上げた。その信じられないような光景に、私はただ目を丸くするしかなかった。
彼女はレイカさんをまるで軽い荷物でも運ぶかのように小脇に抱えると、闇の中へと歩き始めた。
私は慌ててその後を追った。
社殿の脇にある小さな脇道を、進んでいく。
道は整備されておらず、木の根があちこちで剥き出しになっていた。
周囲の木々がさらにその密度を増していく。
まるで世界の奥へ奥へと進んでいくかのような、不思議な感覚。
やがて前方に、一つの古びた小さな建物が見えてきた。
それは本殿とは明らかに違う、質素で、しかしどこか厳かな空気をまとった小さな社だった。
その唯一の入り口である木製の扉には、太く真新しい注連縄が何重にも固く巻き付けられている。
注連縄には白い紙垂がいくつも吊り下げられていた。
ここだ。
ここが『鎮めの間』。
「……ここからは、あなた一人です」
巫女は建物の前でぴたりと足を止めた。
「私は外から儀式が無事に終わるよう祈りを捧げます。ですが、中のあなたを直接助けることはできない」
「……はい」
「夜明けまで、あとおよそ四時間。心を強く持ちなさい」
彼女はそう言うと、慣れた手つきで扉に巻き付けられた注連縄を解き始めた。
ぎ、ぎぎ……と縄が擦れる音が静かな森の中に響く。
全ての注連縄が解かれる。
そして巫女は、その重たい木製の扉をゆっくりと押し開けた。
中から、ひやりとした空気が流れ出してくる。
それはただ冷たいだけではない。
長い長い年月をこの場所で過ごしてきた、濃密な気の流れ。
そして、かすかに古い木の匂いと香の匂いがした。
中は完全な闇だった。
「さあ、入りなさい」
巫女は抱えていたレイカさんの体を、私にそっと手渡した。
私は彼女の体をしっかりと抱きしめる。
そして、意を決してその闇の中へと足を踏み入れた。
一歩、中へ入った瞬間。
背後で、ぎい、と重たい音を立てて扉が閉められた。
ごとり、と外からかんぬきがかけられる音がする。
完全な闇と静寂。
私はこの聖域に閉じ込められたのだ。
レイカさんと、二人きりで。
私は手探りで壁を伝い、ゆっくりとその場に座り込んだ。
抱きかかえたレイカさんの体を自分の膝の上にそっと横たえる。
彼女の浅い呼吸だけが、この静寂の中で唯一の音だった。
儀式はもう始まっているのだろうか。
何をすればいいのか、分からない。
ただ目を閉じて、夜が明けるのを待つしかないのか。
私がそう思った、その時だった。
キィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ
耳の奥で、あの呪いの音が再びその音量を増し始めた。
先ほどよりも、ずっと、ずっと大きく。
はっきりと。
それはもはや、ただのノイズではなかった。
その音の羅列の中に、明確な意思のようなものが感じられた。
私を嘲笑うかのような、悪意。
私を絶望させようとする、明確な意図。
呪いが、牙を剥いたのだ。
『……サヤカ……』
不意に頭の中に直接、声が響いた。
それは誰の声でもなかった。男でも女でもない。幼くも老いてもいない。
ただ冷たく、どこまでも冷たい声。
『……おまえは、ひとりだ……』
その言葉と同時に、私の意識は暗闇の中へと急速に引きずり込まれていった。
目の前の完全な闇がぐにゃりと歪む。
そして、そこに一つの光景が浮かび上がってきた。
ざあ、ざあと雨が窓ガラスを叩く音。
薄暗い小学校の教室。
放課後、誰もいなくなった教室で私は一人、自分の席に座っていた。
机の上には、ぐちゃぐちゃに破かれた教科書とノート。
床には泥のついた上履きが転がっている。
私の、上履きだ。
さっきまで、クラスの男子たちにサッカーボール代わりに蹴られていた。
私は泣いていなかった。
ただ、唇を固く固く結んで、窓の外を見つめていた。
雨に濡れた校庭。
そこでは傘を差したクラスメイトたちが、楽しそうに笑いながら下校していく。
その中に、私をいじめていたあの子たちの顔もあった。
誰も、私のことなど気にも留めていない。
まるで私がこの教室に存在していないかのように。
そうだ。
私はこのクラスで孤立していた。
自分の意見を少しだけはっきりと言ってしまった、ただそれだけのことで。
次の日から、誰も私と口を利いてくれなくなった。
私の机はゴミ箱にされた。
持ち物は隠されたり、壊されたりした。
先生に言っても無駄だった。
『気のせいじゃないか』『みんなと、仲良くしなさい』
そう言われるだけだった。
誰も私の味方ではなかった。
私はこの世界でたった一人だった。
自分の存在が消えてしまったかのような、途方もない孤独。
冷たい、絶望。
あの時感じた、あの感情が今、私の心を再び支配していく。
幻覚だ。
これは呪いが見せているただの幻。
そう頭では分かっている。
けれど、この肌を刺すような孤独感はあまりにもリアルだった。
教室の冷たい空気。
雨の湿った匂い。
遠くで聞こえるクラスメイトたちの楽しそうな笑い声。
その一つ一つが私の心を容赦なく抉っていく。
『……そうだ……おまえは、あの頃からずっとひとりだった……』
頭の中に再び、あの声が響く。
『……誰も、おまえのことなど見ていない……』
『……誰も、おまえのことなど必要としていない……』
『……おまえは、この世界に必要のない存在なのだ……』
その言葉は甘い毒のように、私の心に染み渡っていく。
そうだ。
そうだったのかもしれない。
私はずっと一人だった。
誰とも深く関わらないことで、自分を守ってきた。
傷つかないように。
これ以上、孤独にならないように。
平穏な日常。
私が求めていたのは、それだったはずだ。
なのに。
『……あの女も、そうだ……』
声は続ける。
『……あの女も、いずれおまえの前からいなくなる……』
『……おまえは、またひとりに、なるのだ……』
『……それが、おまえの運命なのだから……』
その言葉に私の心はぐらりと大きく揺れた。
そうだ。
レイカさんもいつかいなくなってしまうのかもしれない。
また転校してしまうかもしれない。
あるいは私のことなど飽きてしまって、どこかへ行ってしまうかもしれない。
そうしたら、私はまた一人になる。
あの退屈で静かで、色のない一人の世界に戻るのだ。
それが、怖い。
心の底から怖いと、思ってしまった。
『……ならば、いっそここで全てを終わらせてしまえ……』
声は囁きかける。
悪魔の誘い。
『……このまま、この冷たい絶望の中に身を委ねてしまえば、もう傷つくこともない……』
『……もう、孤独に怯えることもない……』
『……さあ、楽になるのだ……』
その言葉はひどく魅力的だった。
そうだ。
もう疲れた。
戦うのも、抵抗するのも。
このまま、この冷たい闇の中に沈んでしまえたら。
どれだけ楽になれるだろう。
私の意識がゆっくりと、しかし確実にその心地よい絶望の底へと沈んでいく。
膝の上で眠るレイカさんの温かささえも、少しずつ遠のいていくようだった。
もう、いいか。
これで、終わりにしよう。
私がそう諦めかけた、その瞬間だった。