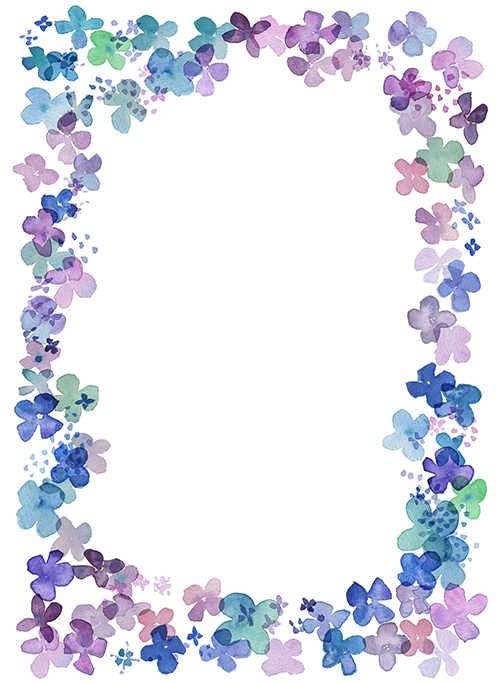アスファルトを蹴る自分のスニーカーの音だけが、やけに大きく耳に響く。
荒い呼吸が喉に張り付いて、ひゅう、ひゅうと鳴っている。肩に担いだレイカさんの体は意識がないせいか、ずしりと重い。けれどその重さだけが、今の私をこの現実世界に繋ぎとめている唯一の楔のようでもあった。
「はあっ、はあっ……!」
どこへ向かっているのか、自分でも分からなかった。ただあの場所から、あの電話ボックスから一刻も早く離れたかった。背後で蠢いていた、あの黒いナニカたち。あれに捕まったら終わりだ。魂ごと喰われてしまう。そんな根拠のない、しかし絶対的な確信があった。
振り返る勇気はない。けれど、肌を刺すようなじっとりとした視線を感じる。追いかけてきている。間違いなく、私たちの後を。
耳の奥ではまだ、あの音が反響していた。黒板を爪で引っ掻く音、熟れた果実を踏み潰す音、砂嵐のノイズ。それらが一つになった、魂を汚染する呪いの旋律。その音が聞こえるたびに、頭蓋骨の真ん中を熱い針でかき混ぜられるような激痛が走った。
「……っ、う……!」
込み上げてくる吐き気を必死にこらえる。視界がぐらぐらと揺れる。街灯の頼りない光が滲んで、伸びて、歪んで見える。
まずい。このままでは倒れる。
私は近くの路地の暗がりに、転がり込むようにして身を隠した。コンクリートの壁に背中を預け、ずるずるとその場に座り込む。担いでいたレイカさんの体を、そっと横たえた。
「レイカさん……しっかりして……」
呼びかけても返事はない。彼女の顔は月の光も届かないこの暗闇の中ですら、はっきりと分かるほどに真っ白だった。唇はわずかに紫色を帯びている。かろうじて上下する胸の動きだけが、彼女がまだ生きていることを示していた。
直接あの呪いの声を耳にしてしまった彼女の衰弱は、私よりもずっとずっと激しい。このままでは本当に死んでしまうかもしれない。
どうすればいい。
どうすれば、彼女を助けられる。
救急車? いや、だめだ。なんて説明するんだ。『友達が、呪いの電話を聞いて倒れました』なんて、信じてもらえるはずがない。頭のおかしい子供の悪質ないたずらだと思われるのが関の山だ。
警察? もっとあり得ない。
パニックで思考がまとまらない。ぐるぐると、同じ場所を堂々巡りしている。
助けを呼ばないと。
でも、誰に?
この、常識を超えた出来事を理解してくれる、誰かに。
「……あ」
その時、私の脳裏に一つの記憶が閃光のように蘇った。
北校舎の『お墓』へ向かう前、レイカさんが自信満々に言っていた、あの言葉。
『私、西園寺家のコネクションを使い、日本屈指の霊能力者の方々を、すでに数名スタンバイさせてありますの』
そうだ。霊能力者。
今のこの状況を打開できるとしたら、もうそういう人たちしかいない。
私はほとんど無意識のうちに、レイカさんが身につけていた小さなショルダーバッグに手を伸ばしていた。中にはハンカチやリップクリームといった、ごく普通の少女が持つものと一緒に、彼女のスマートフォンが静かに入っていた。
これだ。
私は震える指でそのスマートフォンのロックを解除しようとした。しかし当然ながら、パスコードが設定されている。
くそっ、どうすれば。
指紋認証は、意識のない彼女の指では反応しない。顔認証もこの暗闇では無理だ。
万事休すか。
私が諦めかけた、その時だった。
ふと、パスコード入力画面の背景に設定された画像が目に入った。
それは夕日に照らされた、見覚えのある住宅街の風景。そして、そこに立つ私の不機嫌そうな顔。
あの時、彼女が勝手に撮った、あの写真だった。
そして、その写真の隅に小さく手書きの文字のようなものが書き加えられている。
『S.S & R.S』
サヤカ・サメジマ、と、レイカ・サイオンジ。
私たちのイニシャル。
そのあまりにも乙女チックな発想に、この状況で思わず顔が熱くなるのを感じた。
けれど、それだけではない。
その写真が撮影された、日付。
彼女と私が出会った、あの日。
もしかして。
私は祈るような気持ちで、その日付の数字をパスコードとして入力した。
カチリ、と軽い音がして、スマートフォンのロックが解除された。
「……やった」
安堵と、それから少しだけ複雑な気持ちが胸に込み上げてくる。
あの迷惑な出会いを、彼女はそんなふうに大切に思っていてくれたのか。
感傷に浸っている場合ではなかった。
私はすぐに連絡先のアプリを開き、目的のリストを探した。
あった。『緊急時霊的サポート』と名付けられたもの。
その中には十数名の名前と電話番号が、ずらりと並んでいた。
『恐山の最終兵器 マダム・キョウコ』
『琉球ユタの末裔 神里カナ』
『サイキック・ソルジャー JIN』
……どれもこれも、胡散臭いにもほどがある。
私は迷った。誰にかければいいんだ。こんなふざけた名前のリストの中から、本物を見つけ出せというのか。
いや、迷っている時間はない。
私はそのリストの一番上にあった名前に、指をかけた。
『万物対話師 マダム・オリビア』
一番、胡散臭い。
けれど、一番上にあるということは、レイカさんが最も信頼している人物だということかもしれない。
私は藁にもすがる思いでその名前をタップし、通話ボタンを押した。
プルルルル……。
プルルルル……。
コール音が静かな路地に虚しく響く。
出てくれ。
お願いだから、出てくれ。
深夜だということは分かっている。けれど、人の命がかかっているんだ。
五回、六回とコール音が繰り返される。
もう、ダメか。
私が諦めて電話を切ろうとした、その時だった。
「……はぁい」
不意に電話の向こうから、声が聞こえた。
それは妙に間延びした、眠たそうな中年女性の声だった。
電話の向こう側で、ふあと大きなあくびをする音まで聞こえてくる。
「あ、あのっ!」
私は慌てて声を張り上げた。
「んー……?どちらさまぁ……?今、何時だと、思ってるのかしらぁ……?」
そのあまりにも呑気で緊張感のない声に、私の全身から急速に力が抜けていくのを感じた。
終わった。
完全に間違えた。
この人は偽物だ。ただの詐欺師か、あるいはふざけた名前で商売をしている悪質な占い師か何かだ。
絶望が私の心を黒く塗りつぶしていく。
「……すみません、間違えました」
私が力なくそう言って電話を切ろうとした、その瞬間。
「あらぁん、待ちなさいよぉ」
電話の向こうの女は私の言葉を遮った。
「その声……。あなた、レイカお嬢様じゃないわねぇ?お友達ぃ?」
「……え?」
「お嬢様から何か、聞いてるわぁ。確か、サメジマ……だったかしらぁ?運命の友だとか、なんとかぁ」
その言葉に、私ははっとした。
この人は、レイカさんのことを知っている。
もしかしたら、本物なのかもしれない。
いや、でも、この胡散臭さは、一体……。
「そうです! 鮫島です! 助けてください!レイカさんが……西園寺さんが、大変なんです!」
私はもう見境なく叫んでいた。
「あらあらぁ、大変って、なぁにぃ?また何か、変なものでも拾ってきちゃったのかしらぁ、あの子はぁ」
「電話です! 呪いの電話!廃病院の前にある公衆電話で変な声を聞いて、それでレイカさんが倒れて……!」
私はパニックになりながら、支離滅裂に状況を説明した。
黒いナニカに追いかけられていることも。
耳の奥でまだ、あの音が鳴り続けていることも。
女は私の話を、相変わらず眠たそうな相槌を打ちながら聞いていた。
「ふぅん……。はいはい、はいはい。廃病院の公衆電話ねぇ……」
そのあまりにも他人事のような口調に、私の堪忍袋の緒がぷつりと切れた。
「聞いてるんですか!?こっちは人が死にそうだって言ってるの!あなた、本当に霊能力者なの!?」
私の怒声が響く。
それを聞いた瞬間、電話の向こうの空気が一変した。
「……旧・月宮総合病院前。錆びた十円玉を使ったのね?」
その声から、先ほどまでの間延びした響きは嘘のように消え去っていた。
低く、冷静で、有無を言わさぬ凄みのある声。
まるで別人だった。
「……え?」
あまりの変化に、私は戸惑いの声を上げる。
「答えなさい。声を聞いたのは、お嬢様だけ?それとも、あなたも?」
「わ、私も……少しだけ、聞こえました」
「そう。だから、まだ正気でいられるのね」
女は淡々とそう言った。その声には一切の感情がこもっていない。
「いい、よく聞きなさい。あなたたちが手を出したのは、ただの都市伝説じゃない。それは古くからこの土地に根付く、『黄泉の国の呼び声』そのものよ」
「よみの、くに……?」
「今、あなたたちの周りに黒い影のようなものが見えてるはずよ。それは呼び声に引き寄せられた亡者や低級な霊の類。今のあなたたちは奴らにとって、極上のご馳走に見えている。すぐにそこから離れなさい」
その言葉はあまりにも的確に、今の私たちの状況を言い当てていた。
この人は、本物だ。
心の底から、そう確信した。
「で、でも、どこへ逃げれば……!」
「落ち着きなさい。パニックは奴らの思う壺よ。いい? 今から私が言う場所へ向かうの。そこ以外に、あなたたちが助かる道はない」
その有無を言わさぬ力強い言葉に、私はただこくりと頷くことしかできなかった。
「この町の、小高い丘の上にある古い神社を知ってる?」
「神社……?」
「白蛇神社よ。古くからこの土地の怪異を鎮めてきた特別な場所。今すぐそこへ走りなさい。神社の境内に入れば、奴らも簡単には手出しできないはず」
「しらへび、じんじゃ……」
聞いたことのない名前だった。けれど、もう迷っている暇はない。
「神社の場所は、お嬢様のスマートフォンの地図アプリで検索すればすぐに出るわ。いいわね? 絶対に寄り道はしないこと。何があっても振り返らないこと。そして神社に着いたら、そこにいる巫女に全てを話しなさい。話は私から通しておく」
「わ、分かりました!」
「……それから」
女はそこで一度、言葉を切った。
「あなた、よくやったわね。一人でお嬢様をここまで」
その、不意にほんの少しだけ温かみを含んだ声に、私の目から熱いものがこみ上げてきた。
「必ず、助かる。だから、諦めないで」
その言葉を最後に、電話は一方的に切れた。
ツー、ツー、という無機質な音が耳に響く。
私はスマートフォンの画面を呆然と見つめていた。
嵐のような電話だった。
けれどその嵐は、私の心の中にあった絶望という名の分厚い暗雲を吹き飛ばしてくれた。
助かる。
助かる道がある。
その事実が、私の体に再び力を与えてくれた。
「……行くよ、レイカさん」
私はぐったりと横たわる彼女の体を、再び肩に担ぎ上げた。
先ほどよりも少しだけ軽く感じたのは、きっと気のせいではないだろう。
スマートフォンの地図アプリを起動する。
『白蛇神社』。
検索すると、すぐにその場所が表示された。
ここから歩いて二十分ほどの距離。
走ればもっと早く着ける。
私は路地の暗がりから飛び出した。
目指す場所は決まった。
もう、迷わない。
耳の奥でまだ、あの呪いの音が鳴り続けている。
けれど、もう負ける気はしなかった。
絶対にたどり着いてみせる。
そして絶対に、この迷惑で手のかかる、私のたった一人の『運命の友』を助けてみせる。
夏の夜の生ぬるい空気の中を、私はただひたすらに走り続けた。
遠くで神社のものらしき深い森のシルエットが、闇の中から浮かび上がって見えた。
荒い呼吸が喉に張り付いて、ひゅう、ひゅうと鳴っている。肩に担いだレイカさんの体は意識がないせいか、ずしりと重い。けれどその重さだけが、今の私をこの現実世界に繋ぎとめている唯一の楔のようでもあった。
「はあっ、はあっ……!」
どこへ向かっているのか、自分でも分からなかった。ただあの場所から、あの電話ボックスから一刻も早く離れたかった。背後で蠢いていた、あの黒いナニカたち。あれに捕まったら終わりだ。魂ごと喰われてしまう。そんな根拠のない、しかし絶対的な確信があった。
振り返る勇気はない。けれど、肌を刺すようなじっとりとした視線を感じる。追いかけてきている。間違いなく、私たちの後を。
耳の奥ではまだ、あの音が反響していた。黒板を爪で引っ掻く音、熟れた果実を踏み潰す音、砂嵐のノイズ。それらが一つになった、魂を汚染する呪いの旋律。その音が聞こえるたびに、頭蓋骨の真ん中を熱い針でかき混ぜられるような激痛が走った。
「……っ、う……!」
込み上げてくる吐き気を必死にこらえる。視界がぐらぐらと揺れる。街灯の頼りない光が滲んで、伸びて、歪んで見える。
まずい。このままでは倒れる。
私は近くの路地の暗がりに、転がり込むようにして身を隠した。コンクリートの壁に背中を預け、ずるずるとその場に座り込む。担いでいたレイカさんの体を、そっと横たえた。
「レイカさん……しっかりして……」
呼びかけても返事はない。彼女の顔は月の光も届かないこの暗闇の中ですら、はっきりと分かるほどに真っ白だった。唇はわずかに紫色を帯びている。かろうじて上下する胸の動きだけが、彼女がまだ生きていることを示していた。
直接あの呪いの声を耳にしてしまった彼女の衰弱は、私よりもずっとずっと激しい。このままでは本当に死んでしまうかもしれない。
どうすればいい。
どうすれば、彼女を助けられる。
救急車? いや、だめだ。なんて説明するんだ。『友達が、呪いの電話を聞いて倒れました』なんて、信じてもらえるはずがない。頭のおかしい子供の悪質ないたずらだと思われるのが関の山だ。
警察? もっとあり得ない。
パニックで思考がまとまらない。ぐるぐると、同じ場所を堂々巡りしている。
助けを呼ばないと。
でも、誰に?
この、常識を超えた出来事を理解してくれる、誰かに。
「……あ」
その時、私の脳裏に一つの記憶が閃光のように蘇った。
北校舎の『お墓』へ向かう前、レイカさんが自信満々に言っていた、あの言葉。
『私、西園寺家のコネクションを使い、日本屈指の霊能力者の方々を、すでに数名スタンバイさせてありますの』
そうだ。霊能力者。
今のこの状況を打開できるとしたら、もうそういう人たちしかいない。
私はほとんど無意識のうちに、レイカさんが身につけていた小さなショルダーバッグに手を伸ばしていた。中にはハンカチやリップクリームといった、ごく普通の少女が持つものと一緒に、彼女のスマートフォンが静かに入っていた。
これだ。
私は震える指でそのスマートフォンのロックを解除しようとした。しかし当然ながら、パスコードが設定されている。
くそっ、どうすれば。
指紋認証は、意識のない彼女の指では反応しない。顔認証もこの暗闇では無理だ。
万事休すか。
私が諦めかけた、その時だった。
ふと、パスコード入力画面の背景に設定された画像が目に入った。
それは夕日に照らされた、見覚えのある住宅街の風景。そして、そこに立つ私の不機嫌そうな顔。
あの時、彼女が勝手に撮った、あの写真だった。
そして、その写真の隅に小さく手書きの文字のようなものが書き加えられている。
『S.S & R.S』
サヤカ・サメジマ、と、レイカ・サイオンジ。
私たちのイニシャル。
そのあまりにも乙女チックな発想に、この状況で思わず顔が熱くなるのを感じた。
けれど、それだけではない。
その写真が撮影された、日付。
彼女と私が出会った、あの日。
もしかして。
私は祈るような気持ちで、その日付の数字をパスコードとして入力した。
カチリ、と軽い音がして、スマートフォンのロックが解除された。
「……やった」
安堵と、それから少しだけ複雑な気持ちが胸に込み上げてくる。
あの迷惑な出会いを、彼女はそんなふうに大切に思っていてくれたのか。
感傷に浸っている場合ではなかった。
私はすぐに連絡先のアプリを開き、目的のリストを探した。
あった。『緊急時霊的サポート』と名付けられたもの。
その中には十数名の名前と電話番号が、ずらりと並んでいた。
『恐山の最終兵器 マダム・キョウコ』
『琉球ユタの末裔 神里カナ』
『サイキック・ソルジャー JIN』
……どれもこれも、胡散臭いにもほどがある。
私は迷った。誰にかければいいんだ。こんなふざけた名前のリストの中から、本物を見つけ出せというのか。
いや、迷っている時間はない。
私はそのリストの一番上にあった名前に、指をかけた。
『万物対話師 マダム・オリビア』
一番、胡散臭い。
けれど、一番上にあるということは、レイカさんが最も信頼している人物だということかもしれない。
私は藁にもすがる思いでその名前をタップし、通話ボタンを押した。
プルルルル……。
プルルルル……。
コール音が静かな路地に虚しく響く。
出てくれ。
お願いだから、出てくれ。
深夜だということは分かっている。けれど、人の命がかかっているんだ。
五回、六回とコール音が繰り返される。
もう、ダメか。
私が諦めて電話を切ろうとした、その時だった。
「……はぁい」
不意に電話の向こうから、声が聞こえた。
それは妙に間延びした、眠たそうな中年女性の声だった。
電話の向こう側で、ふあと大きなあくびをする音まで聞こえてくる。
「あ、あのっ!」
私は慌てて声を張り上げた。
「んー……?どちらさまぁ……?今、何時だと、思ってるのかしらぁ……?」
そのあまりにも呑気で緊張感のない声に、私の全身から急速に力が抜けていくのを感じた。
終わった。
完全に間違えた。
この人は偽物だ。ただの詐欺師か、あるいはふざけた名前で商売をしている悪質な占い師か何かだ。
絶望が私の心を黒く塗りつぶしていく。
「……すみません、間違えました」
私が力なくそう言って電話を切ろうとした、その瞬間。
「あらぁん、待ちなさいよぉ」
電話の向こうの女は私の言葉を遮った。
「その声……。あなた、レイカお嬢様じゃないわねぇ?お友達ぃ?」
「……え?」
「お嬢様から何か、聞いてるわぁ。確か、サメジマ……だったかしらぁ?運命の友だとか、なんとかぁ」
その言葉に、私ははっとした。
この人は、レイカさんのことを知っている。
もしかしたら、本物なのかもしれない。
いや、でも、この胡散臭さは、一体……。
「そうです! 鮫島です! 助けてください!レイカさんが……西園寺さんが、大変なんです!」
私はもう見境なく叫んでいた。
「あらあらぁ、大変って、なぁにぃ?また何か、変なものでも拾ってきちゃったのかしらぁ、あの子はぁ」
「電話です! 呪いの電話!廃病院の前にある公衆電話で変な声を聞いて、それでレイカさんが倒れて……!」
私はパニックになりながら、支離滅裂に状況を説明した。
黒いナニカに追いかけられていることも。
耳の奥でまだ、あの音が鳴り続けていることも。
女は私の話を、相変わらず眠たそうな相槌を打ちながら聞いていた。
「ふぅん……。はいはい、はいはい。廃病院の公衆電話ねぇ……」
そのあまりにも他人事のような口調に、私の堪忍袋の緒がぷつりと切れた。
「聞いてるんですか!?こっちは人が死にそうだって言ってるの!あなた、本当に霊能力者なの!?」
私の怒声が響く。
それを聞いた瞬間、電話の向こうの空気が一変した。
「……旧・月宮総合病院前。錆びた十円玉を使ったのね?」
その声から、先ほどまでの間延びした響きは嘘のように消え去っていた。
低く、冷静で、有無を言わさぬ凄みのある声。
まるで別人だった。
「……え?」
あまりの変化に、私は戸惑いの声を上げる。
「答えなさい。声を聞いたのは、お嬢様だけ?それとも、あなたも?」
「わ、私も……少しだけ、聞こえました」
「そう。だから、まだ正気でいられるのね」
女は淡々とそう言った。その声には一切の感情がこもっていない。
「いい、よく聞きなさい。あなたたちが手を出したのは、ただの都市伝説じゃない。それは古くからこの土地に根付く、『黄泉の国の呼び声』そのものよ」
「よみの、くに……?」
「今、あなたたちの周りに黒い影のようなものが見えてるはずよ。それは呼び声に引き寄せられた亡者や低級な霊の類。今のあなたたちは奴らにとって、極上のご馳走に見えている。すぐにそこから離れなさい」
その言葉はあまりにも的確に、今の私たちの状況を言い当てていた。
この人は、本物だ。
心の底から、そう確信した。
「で、でも、どこへ逃げれば……!」
「落ち着きなさい。パニックは奴らの思う壺よ。いい? 今から私が言う場所へ向かうの。そこ以外に、あなたたちが助かる道はない」
その有無を言わさぬ力強い言葉に、私はただこくりと頷くことしかできなかった。
「この町の、小高い丘の上にある古い神社を知ってる?」
「神社……?」
「白蛇神社よ。古くからこの土地の怪異を鎮めてきた特別な場所。今すぐそこへ走りなさい。神社の境内に入れば、奴らも簡単には手出しできないはず」
「しらへび、じんじゃ……」
聞いたことのない名前だった。けれど、もう迷っている暇はない。
「神社の場所は、お嬢様のスマートフォンの地図アプリで検索すればすぐに出るわ。いいわね? 絶対に寄り道はしないこと。何があっても振り返らないこと。そして神社に着いたら、そこにいる巫女に全てを話しなさい。話は私から通しておく」
「わ、分かりました!」
「……それから」
女はそこで一度、言葉を切った。
「あなた、よくやったわね。一人でお嬢様をここまで」
その、不意にほんの少しだけ温かみを含んだ声に、私の目から熱いものがこみ上げてきた。
「必ず、助かる。だから、諦めないで」
その言葉を最後に、電話は一方的に切れた。
ツー、ツー、という無機質な音が耳に響く。
私はスマートフォンの画面を呆然と見つめていた。
嵐のような電話だった。
けれどその嵐は、私の心の中にあった絶望という名の分厚い暗雲を吹き飛ばしてくれた。
助かる。
助かる道がある。
その事実が、私の体に再び力を与えてくれた。
「……行くよ、レイカさん」
私はぐったりと横たわる彼女の体を、再び肩に担ぎ上げた。
先ほどよりも少しだけ軽く感じたのは、きっと気のせいではないだろう。
スマートフォンの地図アプリを起動する。
『白蛇神社』。
検索すると、すぐにその場所が表示された。
ここから歩いて二十分ほどの距離。
走ればもっと早く着ける。
私は路地の暗がりから飛び出した。
目指す場所は決まった。
もう、迷わない。
耳の奥でまだ、あの呪いの音が鳴り続けている。
けれど、もう負ける気はしなかった。
絶対にたどり着いてみせる。
そして絶対に、この迷惑で手のかかる、私のたった一人の『運命の友』を助けてみせる。
夏の夜の生ぬるい空気の中を、私はただひたすらに走り続けた。
遠くで神社のものらしき深い森のシルエットが、闇の中から浮かび上がって見えた。