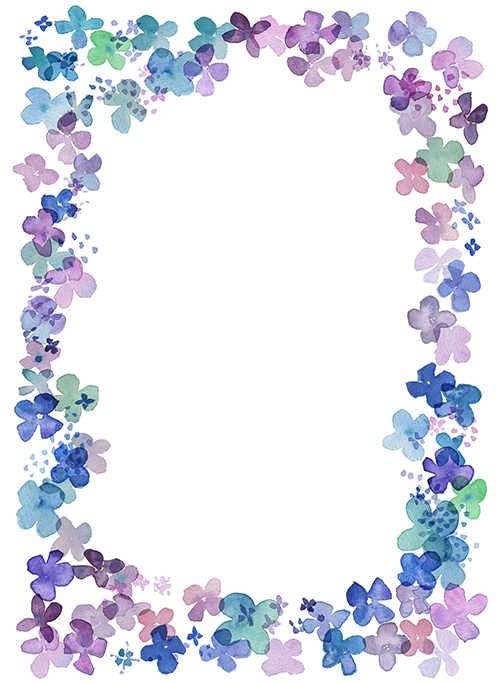カチリ、という無機質な音。
それは世界が終わる音のようにも、あるいは新しい世界が始まる音のようにも聞こえた。
コール音が止んだ電話ボックスの中は、しんと静まり返っている。私の耳に届くのは自分の呼吸の音と、隣に立つレイカさんのかすかな息遣いだけ。夏の夜の虫の声さえも、どこか遠くへ行ってしまったかのようだった。
繋がった。
本当に、繋がってしまったのだ。あの、この世ならざる場所に。
私は固唾を飲んでレイカさんの横顔を見つめた。彼女は受話器を耳に当てたまま、石のように固まっている。その表情は街灯の頼りない光に照らされて、青白く見えた。
「……もしもし?」
やがて、彼女の唇からか細い声が漏れた。それはいつもの自信に満ちた彼女の声とは似ても似つかない、弱々しく、そして怯えを含んだ響きを持っていた。
返事はない。
受話器の向こうは、ただ沈黙を守っているようだった。
「……もしもし? どなたか、いらっしゃいますの?」
レイカさんがもう一度問いかける。その声は先ほどよりもさらに震えていた。
やはり、ただのいたずら電話だったのだろうか。あるいは回線が混線して、どこか無関係な場所へ繋がってしまったとか。
そうであってほしい。
心の底から、そう願った。
私がわずかに安堵しかけた、その時だった。
「……あ」
レイカさんの口から、短い、驚きとも恐怖ともつかない声が吐き出された。
そして次の瞬間、彼女の顔から全ての表情が綺麗に抜け落ちた。
驚きも、恐怖も、好奇心さえも。まるで真っ白な仮面を被ったかのように、その美しい顔は完全な『無』になった。瞳は大きく見開かれている。けれど、その黒曜石のような瞳は何も映してはいなかった。焦点が合わず、ただ虚空の、そのさらに向こう側を見つめている。
体がぴくりとも動かない。受話器を耳に当てたその不自然な姿勢のまま、彼女は完全に硬直してしまっていた。
「……レイカさん?」
私はおそるおそる、彼女の名前を呼んだ。
返事はない。
彼女はまるで、精巧に作られた蝋人形のようだった。生きている人間の持つ微細な体の動きや温かみが、彼女からは完全に失われている。
「ねえ、レイカさん! しっかりして!」
私は彼女の肩を掴み、揺さぶった。
しかし、その体は驚くほど硬かった。まるで一本の硬い棒を揺さぶっているかのようだ。何の反応も示さない。
何かがおかしい。
明らかに、異常だ。
電話の向こう側で、一体何が起こっているんだ。
「レイカさん、聞こえる!? 返事をして!」
私はパニックになりながら叫んだ。
彼女の耳に当てられた受話器。全ての元凶はあれだ。
私は彼女の手からその受話器を無理やり奪い取ろうとした。
「離して、レイカさん! その電話、危ない!」
しかし、彼女の力は信じられないほど強かった。
受話器を握りしめたその手は、まるで万力のように固くびくともしない。それどころか、彼女はさらに強く受話器を自分の耳へと押し付けている。まるで、そこから聞こえてくる『何か』から逃れまいとするかのように。
そのあまりにも異様な光景に、私の背筋をぞくりと冷たいものが走り抜けた。
「やめて、レイカさん! お願いだから、それを離して!」
私は半ば泣き叫ぶようにして、彼女の腕にしがみついた。
その細い腕を力いっぱい引っぱる。
彼女の体は少しも動かない。
私が彼女の腕を掴み、無理やり引き剥がそうとさらに力を込めた、まさにその瞬間だった。
私の耳に、それが届いてしまった。
レイカさんが耳に押し当てている受話器から、わずかに音が漏れ聞こえてきたのだ。
それは声と呼べるようなものではなかった。
音と呼ぶことさえ、はばかられるような冒涜的な響き。
キィィィィィィィィィィィ…………。
黒板を鋭い爪で力いっぱい引っ掻いたような、甲高いノイズ。
それだけではない。
そのノイズの奥で、何かが蠢いている。
ぐちゅ、ぐちゅ、と熟れた果実を踏み潰すような湿った音。
ざあ、ざあ、と電波の届かない場所でラジオのチューニングを合わせようとしているかのような砂嵐の音。
それらの、およそこの世の音とは思えない不快な音の断片がいくつも、何重にも重なり合っている。
それは、音楽ではない。
言葉でもない。
ただ純粋な悪意と狂気だけを煮詰めて凝縮し、音という形にしたかのような呪いの塊。
その音を耳が認識した瞬間、私の頭蓋骨のちょうど真ん中あたりを、まるで熱した鉄の杭で内側から思いきり抉られるかのような激しい痛みが襲った。
「……っ!」
思わず声にならない悲鳴を上げて、その場にうずくまる。
頭が割れるように痛い。
胃の奥から何かがせり上がってくるような、強烈な吐き気。
耳の奥で、あの不快な音がこびりついたように鳴り続けている。
キィィィィィィ……ぐちゅ、ぐちゅ……ざあ、ざあ……。
それは鼓膜を揺らすただの音波ではなかった。
脳に直接焼き付けられる、呪いの刻印。
一度聞いてしまったら、もう二度と忘れることのできない、魂を汚染する音。
私が激しい頭痛と吐き気に耐えながらかろうじて顔を上げると、目の前で信じられない光景が広がっていた。
レイカさんが、まるで糸が切れた操り人形のように、ゆっくりとその場に崩れ落ちていく。
彼女の手から、受話器が滑り落ちた。
ごとり、と乾いた音を立てて受話器がコンクリートの床に転がる。
そこから、あの呪いの音が電話ボックスの中にはっきりと響き渡った。
キィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ
「レイカさん……っ!」
私は床に倒れ込んだ彼女の元へ、這うようにして駆け寄った。
彼女はぐったりとして意識がない。顔は紙のように真っ白で、唇からは血の気が失せている。呼吸はかろうじてしているようだったが、浅く不規則だった。
「しっかりして! 目を覚まして!」
彼女の体を揺さぶるが、反応はない。
どうすればいい。
救急車を呼ばないと。
いや、でも、なんて説明すればいいんだ。『友達が、呪いの電話を聞いて倒れました』なんて、信じてもらえるはずがない。
パニックで思考がまとまらない。
耳の奥ではまだ、あの音が鳴り続けている。
頭が痛い。
気持ちが悪い。
視界がぐらぐらと揺れている。
ふと、何かの気配を感じて顔を上げた。
電話ボックスの外。
街灯の頼りない光が照らす、その闇の中に。
何かが、いる。
それははっきりとした形を持っていなかった。
ただ、そこにある闇が周囲の闇よりも一段と濃くなっているように見えた。
陽炎のように、ゆらゆらとその輪郭が揺れている。
一つではない。
二つ、三つ……。
私たちのいる電話ボックスを取り囲むようにして、その黒い不定形なナニカがいくつも、いくつも集まり始めていた。
それはまるで血の匂いを嗅ぎつけた、飢えた獣のようだった。
あの呪いの声に引き寄せられてきたのか。
あるいはあの声そのものが、形となって現れようとしているのか。
分からない。
分かるのはただ一つ。
あれは絶対に、この世のものではない。
関わってはいけない、危険なナニカだ。
ひゅっと喉が鳴った。
体が動かない。
恐怖で金縛りにあったかのように、指一本動かすことができない。
黒いナニカは、ゆっくりと、しかし確実にこちらへにじり寄ってくる。
まずい。
このままでは、飲み込まれる。
「……いやっ!」
その瞬間、私の体は考えるよりも先に動いていた。
火事場の馬鹿力、というやつだろうか。
私は意識のないレイカさんの体を無理やり肩に担ぎ上げた。思ったよりもずっと軽い。けれど今の私には、それが世界の全てであるかのように重くのしかかってきた。
「……逃げる……!」
私は自分に言い聞かせるようにそう呟くと、電話ボックスの扉を蹴破るようにして飛び出した。
どこへというあてはない。
ただ、この場所から一刻も早く離れなければ。
あの黒いナニカから、できるだけ遠くへ。
背後で、あのナニカたちが蠢く気配がした。
追いかけてきている。
振り返る勇気はなかった。
ただ、前へ、前へと足を動かす。
レイカさんを担いだまま、もつれる足を必死に動かす。
耳の奥で鳴り続ける、呪いの音。
割れるような頭痛。
込み上げてくる吐き気。
そして、背後からじりじりと迫ってくる、得体の知れないナニカの気配。
意識が遠のきそうになる。
ここで倒れたら、終わりだ。
二人とも、あのナニカに飲み込まれてしまう。
「……しっかり、しろ……っ!」
私は自分を叱咤した。
レイカさんを守らないと。
私が彼女をこんな場所に連れてきてしまったのだから。
いや、違う。
彼女が私を無理やり連れてきたんだ。
もう、どっちでもいい。
ただ、このまま二人で終わるわけにはいかない。
夏の夜の生ぬるい空気の中を、命からがら逃げ出した。
それは世界が終わる音のようにも、あるいは新しい世界が始まる音のようにも聞こえた。
コール音が止んだ電話ボックスの中は、しんと静まり返っている。私の耳に届くのは自分の呼吸の音と、隣に立つレイカさんのかすかな息遣いだけ。夏の夜の虫の声さえも、どこか遠くへ行ってしまったかのようだった。
繋がった。
本当に、繋がってしまったのだ。あの、この世ならざる場所に。
私は固唾を飲んでレイカさんの横顔を見つめた。彼女は受話器を耳に当てたまま、石のように固まっている。その表情は街灯の頼りない光に照らされて、青白く見えた。
「……もしもし?」
やがて、彼女の唇からか細い声が漏れた。それはいつもの自信に満ちた彼女の声とは似ても似つかない、弱々しく、そして怯えを含んだ響きを持っていた。
返事はない。
受話器の向こうは、ただ沈黙を守っているようだった。
「……もしもし? どなたか、いらっしゃいますの?」
レイカさんがもう一度問いかける。その声は先ほどよりもさらに震えていた。
やはり、ただのいたずら電話だったのだろうか。あるいは回線が混線して、どこか無関係な場所へ繋がってしまったとか。
そうであってほしい。
心の底から、そう願った。
私がわずかに安堵しかけた、その時だった。
「……あ」
レイカさんの口から、短い、驚きとも恐怖ともつかない声が吐き出された。
そして次の瞬間、彼女の顔から全ての表情が綺麗に抜け落ちた。
驚きも、恐怖も、好奇心さえも。まるで真っ白な仮面を被ったかのように、その美しい顔は完全な『無』になった。瞳は大きく見開かれている。けれど、その黒曜石のような瞳は何も映してはいなかった。焦点が合わず、ただ虚空の、そのさらに向こう側を見つめている。
体がぴくりとも動かない。受話器を耳に当てたその不自然な姿勢のまま、彼女は完全に硬直してしまっていた。
「……レイカさん?」
私はおそるおそる、彼女の名前を呼んだ。
返事はない。
彼女はまるで、精巧に作られた蝋人形のようだった。生きている人間の持つ微細な体の動きや温かみが、彼女からは完全に失われている。
「ねえ、レイカさん! しっかりして!」
私は彼女の肩を掴み、揺さぶった。
しかし、その体は驚くほど硬かった。まるで一本の硬い棒を揺さぶっているかのようだ。何の反応も示さない。
何かがおかしい。
明らかに、異常だ。
電話の向こう側で、一体何が起こっているんだ。
「レイカさん、聞こえる!? 返事をして!」
私はパニックになりながら叫んだ。
彼女の耳に当てられた受話器。全ての元凶はあれだ。
私は彼女の手からその受話器を無理やり奪い取ろうとした。
「離して、レイカさん! その電話、危ない!」
しかし、彼女の力は信じられないほど強かった。
受話器を握りしめたその手は、まるで万力のように固くびくともしない。それどころか、彼女はさらに強く受話器を自分の耳へと押し付けている。まるで、そこから聞こえてくる『何か』から逃れまいとするかのように。
そのあまりにも異様な光景に、私の背筋をぞくりと冷たいものが走り抜けた。
「やめて、レイカさん! お願いだから、それを離して!」
私は半ば泣き叫ぶようにして、彼女の腕にしがみついた。
その細い腕を力いっぱい引っぱる。
彼女の体は少しも動かない。
私が彼女の腕を掴み、無理やり引き剥がそうとさらに力を込めた、まさにその瞬間だった。
私の耳に、それが届いてしまった。
レイカさんが耳に押し当てている受話器から、わずかに音が漏れ聞こえてきたのだ。
それは声と呼べるようなものではなかった。
音と呼ぶことさえ、はばかられるような冒涜的な響き。
キィィィィィィィィィィィ…………。
黒板を鋭い爪で力いっぱい引っ掻いたような、甲高いノイズ。
それだけではない。
そのノイズの奥で、何かが蠢いている。
ぐちゅ、ぐちゅ、と熟れた果実を踏み潰すような湿った音。
ざあ、ざあ、と電波の届かない場所でラジオのチューニングを合わせようとしているかのような砂嵐の音。
それらの、およそこの世の音とは思えない不快な音の断片がいくつも、何重にも重なり合っている。
それは、音楽ではない。
言葉でもない。
ただ純粋な悪意と狂気だけを煮詰めて凝縮し、音という形にしたかのような呪いの塊。
その音を耳が認識した瞬間、私の頭蓋骨のちょうど真ん中あたりを、まるで熱した鉄の杭で内側から思いきり抉られるかのような激しい痛みが襲った。
「……っ!」
思わず声にならない悲鳴を上げて、その場にうずくまる。
頭が割れるように痛い。
胃の奥から何かがせり上がってくるような、強烈な吐き気。
耳の奥で、あの不快な音がこびりついたように鳴り続けている。
キィィィィィィ……ぐちゅ、ぐちゅ……ざあ、ざあ……。
それは鼓膜を揺らすただの音波ではなかった。
脳に直接焼き付けられる、呪いの刻印。
一度聞いてしまったら、もう二度と忘れることのできない、魂を汚染する音。
私が激しい頭痛と吐き気に耐えながらかろうじて顔を上げると、目の前で信じられない光景が広がっていた。
レイカさんが、まるで糸が切れた操り人形のように、ゆっくりとその場に崩れ落ちていく。
彼女の手から、受話器が滑り落ちた。
ごとり、と乾いた音を立てて受話器がコンクリートの床に転がる。
そこから、あの呪いの音が電話ボックスの中にはっきりと響き渡った。
キィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ
「レイカさん……っ!」
私は床に倒れ込んだ彼女の元へ、這うようにして駆け寄った。
彼女はぐったりとして意識がない。顔は紙のように真っ白で、唇からは血の気が失せている。呼吸はかろうじてしているようだったが、浅く不規則だった。
「しっかりして! 目を覚まして!」
彼女の体を揺さぶるが、反応はない。
どうすればいい。
救急車を呼ばないと。
いや、でも、なんて説明すればいいんだ。『友達が、呪いの電話を聞いて倒れました』なんて、信じてもらえるはずがない。
パニックで思考がまとまらない。
耳の奥ではまだ、あの音が鳴り続けている。
頭が痛い。
気持ちが悪い。
視界がぐらぐらと揺れている。
ふと、何かの気配を感じて顔を上げた。
電話ボックスの外。
街灯の頼りない光が照らす、その闇の中に。
何かが、いる。
それははっきりとした形を持っていなかった。
ただ、そこにある闇が周囲の闇よりも一段と濃くなっているように見えた。
陽炎のように、ゆらゆらとその輪郭が揺れている。
一つではない。
二つ、三つ……。
私たちのいる電話ボックスを取り囲むようにして、その黒い不定形なナニカがいくつも、いくつも集まり始めていた。
それはまるで血の匂いを嗅ぎつけた、飢えた獣のようだった。
あの呪いの声に引き寄せられてきたのか。
あるいはあの声そのものが、形となって現れようとしているのか。
分からない。
分かるのはただ一つ。
あれは絶対に、この世のものではない。
関わってはいけない、危険なナニカだ。
ひゅっと喉が鳴った。
体が動かない。
恐怖で金縛りにあったかのように、指一本動かすことができない。
黒いナニカは、ゆっくりと、しかし確実にこちらへにじり寄ってくる。
まずい。
このままでは、飲み込まれる。
「……いやっ!」
その瞬間、私の体は考えるよりも先に動いていた。
火事場の馬鹿力、というやつだろうか。
私は意識のないレイカさんの体を無理やり肩に担ぎ上げた。思ったよりもずっと軽い。けれど今の私には、それが世界の全てであるかのように重くのしかかってきた。
「……逃げる……!」
私は自分に言い聞かせるようにそう呟くと、電話ボックスの扉を蹴破るようにして飛び出した。
どこへというあてはない。
ただ、この場所から一刻も早く離れなければ。
あの黒いナニカから、できるだけ遠くへ。
背後で、あのナニカたちが蠢く気配がした。
追いかけてきている。
振り返る勇気はなかった。
ただ、前へ、前へと足を動かす。
レイカさんを担いだまま、もつれる足を必死に動かす。
耳の奥で鳴り続ける、呪いの音。
割れるような頭痛。
込み上げてくる吐き気。
そして、背後からじりじりと迫ってくる、得体の知れないナニカの気配。
意識が遠のきそうになる。
ここで倒れたら、終わりだ。
二人とも、あのナニカに飲み込まれてしまう。
「……しっかり、しろ……っ!」
私は自分を叱咤した。
レイカさんを守らないと。
私が彼女をこんな場所に連れてきてしまったのだから。
いや、違う。
彼女が私を無理やり連れてきたんだ。
もう、どっちでもいい。
ただ、このまま二人で終わるわけにはいかない。
夏の夜の生ぬるい空気の中を、命からがら逃げ出した。