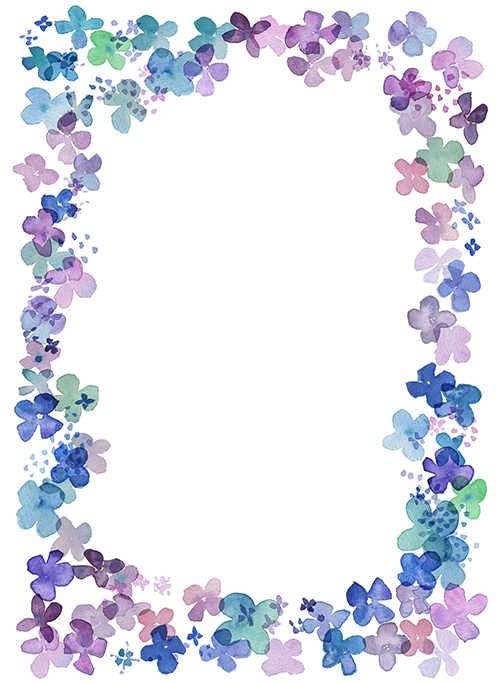深夜、という言葉がこれほどまでにしっくりくる時間帯が他にあるだろうか。街灯の頼りない光がぽつりぽつりと照らすアスファルトの道は、昼間の喧騒が嘘のように静まり返っている。時折、遠くを走り去る車の乾いた走行音が聞こえるだけで、あとは私たちの足音と夏の夜特有のまとわりつくような虫の声だけが、この世界の全てだった。
私の隣を歩く西園寺レイカさんは、これからピクニックにでも出かけるかのような、実に楽しげな足取りだった。その手には、探検グッズが満載らしいパンパンに膨れたリュックサックが揺れている。その軽やかさとは対照的に、私の足取りはまるで足首に鉛の塊でも結び付けられたかのように、一歩一歩が重かった。
「素晴らしい夜ですわね、サヤカ」
レイカさんが、うっとりとした声で夜空を見上げた。
「月も隠れ、星の光も街の明かりに遮られている。まさに怪異と邂逅するには、これ以上ないほど完璧な舞台設定ですわ」
「……全然、素晴らしくないんだけど」
私は自分の腕をさすりながら、ぶっきらぼうに答えた。生ぬるい夜風が汗ばんだ肌を撫でていく。それがひどく不快だった。
「大体、どうしてこんな時間に行かなきゃいけないのよ。昼間じゃダメなの?」
「まあ、サヤカ。何を今更おっしゃいますの」
レイカさんは、心底呆れたとでも言いたげな顔でこちらを振り返った。
「都市伝説『招かざる電話』のルール、覚えていらっしゃいますこと? 『深夜零時に、錆びた十円玉で電話をかける』。このルールを一つでも違えては、儀式は成立いたしません。オカルトとはすなわち、手順と形式の様式美。その厳格なルールの中にこそ、真理へと至る道が隠されているのですわ」
彼女は得意げに胸を張って、そんなことを言う。私にはただの悪趣味な肝試しに、もっともらしい理屈をつけているだけのようにしか聞こえなかった。
私たちはレイカさんのマンションを出てから、ずっと歩き続けていた。タクシーを使えばあっという間の距離だったが、彼女は「聖地へ向かうのですから、自らの足で歩みを進めることにこそ意味があるのですわ」などと、またしても意味不明な持論を展開し私の反対を押し切ったのだ。
おかげで私の体力は、目的地にたどり着く前にすでに限界に近づきつつあった。
やがて、前方に黒々とした巨大なシルエットが見えてきた。
旧・月宮総合病院。
数年前に閉鎖されて以来、手入れもされずに放置されたその建物は、まるで巨大な獣が暗闇の中で身を潜めているかのように不気味な存在感を放っていた。窓ガラスはところどころ割れ、壁には蔦がびっしりと絡みついている。その姿は昼間に見ても十分に不気味だが、夜の闇の中ではその禍々しさが何倍にも増して感じられた。
「……うわ」
思わず、声が漏れた。子供の頃、友達と忍び込んでこっぴどく叱られた記憶が蘇る。あの頃はただの薄汚い廃墟としか思っていなかった。けれどレイカさんからあの都市伝説を聞かされた後では、この建物全体が何か良くないものを吸い寄せる、巨大な磁石のように思えてならなかった。
「素晴らしい……。この、澱んだ空気。現世と常世の境界が極めて曖昧になっているのが、肌で感じられますわ」
レイカさんは恍惚とした表情で、廃病院を見上げている。その手にはいつの間にか、あの自作のガラクタ機械『マナライザー』が握られていた。
「この地に満ちる負のエネルギー……。ですが、それはただ不快なだけのものではない。長い年月を経て熟成された、いわばヴィンテージものの霊気とでも言いましょうか。好事家にとっては、たまらない逸品ですわね」
「あなたのその、ワインみたいに例えるの、やめてくれないかな……」
私がうんざりした気分でそう言うと、彼女はくすくすと楽しそうに笑った。
そして、私たちの目的地は、その廃病院のすぐ目の前にあった。
ぽつんと、寂しげに立つ一台の公衆電話ボックス。
赤い屋根の色は長年の雨風に晒されて、どす黒く変色している。ガラスの扉はひび割れ、内側には気味の悪い落書きがいくつも描かれていた。街灯の光がかろうじてその姿を照らし出しているが、その光さえもこの電話ボックスが放つ不吉な雰囲気に吸い込まれてしまいそうだった。
ごくり、と喉が鳴った。
ここだ。
ここが、あの動画で語られていた呪いの舞台。
「……どうやら、噂は本物のようですわね」
レイカさんが声を潜めて呟いた。彼女の視線の先を追うと、電話ボックスの床に何かがきらりと光っているのが見えた。
私はレイカさんと顔を見合わせる。そして、意を決してそのガラスの扉にそっと手をかけた。
ぎい、と錆び付いた蝶番が悲鳴のような音を立てる。
電話ボックスの中はカビと埃の、鼻をつく匂いで満たされていた。受話器はだらりとコードからぶら下がり、ダイヤル式の電話機本体は無数の傷で覆われている。
そして、その床。
薄汚れたコンクリートの床のちょうど真ん中に、それは一枚だけ落ちていた。
赤黒く錆びついた、一枚の十円玉。
その、あまりにも完璧なまでの『舞台装置』を前にして、私の心臓が大きく、どくん、と跳ねた。
嘘だ。
こんなことって、あるのか。
ただの都市伝説じゃなかったのか。
「……素晴らしい。実に、素晴らしいですわ」
レイカさんの声は興奮でわずかに震えていた。彼女はまるで貴重な遺跡でも発見した考古学者のように、その十円玉を食い入るように見つめている。
「この禍々しいまでの霊気……。間違いありませんわ。この十円玉は長年にわたってこの場所で、無数の人々の怨念やこの世ならざるモノからの呼び声を吸い続けてきたのです。もはやただの硬貨ではない。呪いの触媒そのものと化していますわ」
彼女はリュックサックからピンセットと小さなビニール袋を取り出すと、その十円玉を実に手際よく回収した。その動きには一切の迷いがない。
「さて、と」
レイカさんは満足げに頷くと、今度は様々な機材を電話ボックスの内外に次々と設置し始めた。
小型の録音機、電磁波測定器、カメラ、そして方位磁石。
「これは?」
「万が一、向こう側との交信に成功した場合に備えて、あらゆるデータを記録しておく必要がありますわ。声、温度、磁場の変化……。これらの客観的なデータこそが、オカルトを科学の領域へと昇華させるための第一歩なのですから」
彼女は真剣な顔でそう語る。その瞳はもはや、ただの好奇心だけではない。未知の真理を探求しようとする、真摯な研究者のそれだった。
そのあまりにも場違いな真剣さに、私の恐怖は少しだけ薄らいでいた。
この人は、本気なのだ。
心の底から、本気でこんな馬鹿げたことを信じている。
その純粋さが、呆れると同時にどこか羨ましくさえあった。
全ての準備が整った。
あとは、運命の時を待つだけ。
レイカさんは自分のスマートフォンの画面をじっと見つめている。時刻は、午後十一時五十五分を指していた。
深夜零時まで、あと五分。
急に、口の中がからからに乾いていくのを感じた。
「……ねえ、レイカさん」
「なんですの、サヤカ」
「やっぱり、やめない? もう十分でしょ。十円玉も見つかったし、雰囲気も味わったし。これ以上は、本当に危ない気がする」
私の声は自分でも情けないと思うほど、震えていた。
しかしレイカさんはスマートフォンから目を離さないまま、静かに首を横に振った。
「いいえ。ここまで来て、引き返すわけにはまいりませんわ」
「でも……」
「大丈夫ですわ、サヤカ」
彼女はそこで初めて、こちらを向いた。
その顔にはいつもの自信に満ちた笑みはなかった。
代わりに浮かんでいたのは、緊張と興奮と、そしてほんのわずかな恐怖の色。
彼女も、怖がっているのだ。
その事実に、私は少しだけ驚いた。
「わたくしがついておりますもの。それに、あなたも一緒ですわ。二人なら、きっと大丈夫」
その言葉は、何の根拠もない気休めに過ぎなかった。
けれど、その時の私にはそれがどんなお守りよりも心強く聞こえた。
私は黙って、こくりと頷いた。
沈黙が訪れる。
虫の声だけがやけに大きく耳に響く。
一分が、まるで一時間のように長く感じられた。
スマートフォンの画面の数字が、23:59に変わる。
あと、一分。
レイカさんがごくりと喉を鳴らす音が、やけに大きく聞こえた。
彼女はビニール袋から、あの錆びた十円玉を取り出した。
そして、それを電話機の硬貨投入口へと、ゆっくりと近づけていく。
私の心臓が、大きく、大きく脈打っている。
もう、後戻りはできない。
そして。
スマートフォンの数字が、00:00に変わった。
カチャン。
レイカさんの指が、十円玉を投入口へと押し込んだ。
静まり返った夜の闇に、そのあまりにも無機質な金属音が響き渡る。
彼女は震える指で受話器を取り上げた。
そして動画で紹介されていたという呪いの番号を、一つ、一つゆっくりとダイヤルしていく。
じ……。
じ……。
ダイヤルが回る音。
その古めかしい音が、私の鼓膜を不気味に揺らした。
全ての番号を回し終える。
レイカさんは受話器を自分の耳にそっと当てた。
私も息を殺して、その様子を見守る。
何も、起こらない。
ただ無音の時間が過ぎていくだけ。
「……やっぱり、ただの噂だったんじゃ」
私がそう言いかけた、その時だった。
プルルルル……。
受話器の向こうから、コール音が聞こえてきた。
レイカさんの肩が、びくりと大きく跳ねる。
繋がった。
本当に、繋がってしまった。
プルルルル……。
プルルルル……。
コール音は二回、三回と無機質に繰り返される。
誰も、出ない。
このまま誰も出ずに、切れてくれれば……。
そう、願った。
四回目のコール音が鳴り響いた、その直後だった。
カチリ。
不意にコール音が途切れた。
そして、電話の向こう側で何かが繋がったことを示す、小さな硬い音がした。
私の隣を歩く西園寺レイカさんは、これからピクニックにでも出かけるかのような、実に楽しげな足取りだった。その手には、探検グッズが満載らしいパンパンに膨れたリュックサックが揺れている。その軽やかさとは対照的に、私の足取りはまるで足首に鉛の塊でも結び付けられたかのように、一歩一歩が重かった。
「素晴らしい夜ですわね、サヤカ」
レイカさんが、うっとりとした声で夜空を見上げた。
「月も隠れ、星の光も街の明かりに遮られている。まさに怪異と邂逅するには、これ以上ないほど完璧な舞台設定ですわ」
「……全然、素晴らしくないんだけど」
私は自分の腕をさすりながら、ぶっきらぼうに答えた。生ぬるい夜風が汗ばんだ肌を撫でていく。それがひどく不快だった。
「大体、どうしてこんな時間に行かなきゃいけないのよ。昼間じゃダメなの?」
「まあ、サヤカ。何を今更おっしゃいますの」
レイカさんは、心底呆れたとでも言いたげな顔でこちらを振り返った。
「都市伝説『招かざる電話』のルール、覚えていらっしゃいますこと? 『深夜零時に、錆びた十円玉で電話をかける』。このルールを一つでも違えては、儀式は成立いたしません。オカルトとはすなわち、手順と形式の様式美。その厳格なルールの中にこそ、真理へと至る道が隠されているのですわ」
彼女は得意げに胸を張って、そんなことを言う。私にはただの悪趣味な肝試しに、もっともらしい理屈をつけているだけのようにしか聞こえなかった。
私たちはレイカさんのマンションを出てから、ずっと歩き続けていた。タクシーを使えばあっという間の距離だったが、彼女は「聖地へ向かうのですから、自らの足で歩みを進めることにこそ意味があるのですわ」などと、またしても意味不明な持論を展開し私の反対を押し切ったのだ。
おかげで私の体力は、目的地にたどり着く前にすでに限界に近づきつつあった。
やがて、前方に黒々とした巨大なシルエットが見えてきた。
旧・月宮総合病院。
数年前に閉鎖されて以来、手入れもされずに放置されたその建物は、まるで巨大な獣が暗闇の中で身を潜めているかのように不気味な存在感を放っていた。窓ガラスはところどころ割れ、壁には蔦がびっしりと絡みついている。その姿は昼間に見ても十分に不気味だが、夜の闇の中ではその禍々しさが何倍にも増して感じられた。
「……うわ」
思わず、声が漏れた。子供の頃、友達と忍び込んでこっぴどく叱られた記憶が蘇る。あの頃はただの薄汚い廃墟としか思っていなかった。けれどレイカさんからあの都市伝説を聞かされた後では、この建物全体が何か良くないものを吸い寄せる、巨大な磁石のように思えてならなかった。
「素晴らしい……。この、澱んだ空気。現世と常世の境界が極めて曖昧になっているのが、肌で感じられますわ」
レイカさんは恍惚とした表情で、廃病院を見上げている。その手にはいつの間にか、あの自作のガラクタ機械『マナライザー』が握られていた。
「この地に満ちる負のエネルギー……。ですが、それはただ不快なだけのものではない。長い年月を経て熟成された、いわばヴィンテージものの霊気とでも言いましょうか。好事家にとっては、たまらない逸品ですわね」
「あなたのその、ワインみたいに例えるの、やめてくれないかな……」
私がうんざりした気分でそう言うと、彼女はくすくすと楽しそうに笑った。
そして、私たちの目的地は、その廃病院のすぐ目の前にあった。
ぽつんと、寂しげに立つ一台の公衆電話ボックス。
赤い屋根の色は長年の雨風に晒されて、どす黒く変色している。ガラスの扉はひび割れ、内側には気味の悪い落書きがいくつも描かれていた。街灯の光がかろうじてその姿を照らし出しているが、その光さえもこの電話ボックスが放つ不吉な雰囲気に吸い込まれてしまいそうだった。
ごくり、と喉が鳴った。
ここだ。
ここが、あの動画で語られていた呪いの舞台。
「……どうやら、噂は本物のようですわね」
レイカさんが声を潜めて呟いた。彼女の視線の先を追うと、電話ボックスの床に何かがきらりと光っているのが見えた。
私はレイカさんと顔を見合わせる。そして、意を決してそのガラスの扉にそっと手をかけた。
ぎい、と錆び付いた蝶番が悲鳴のような音を立てる。
電話ボックスの中はカビと埃の、鼻をつく匂いで満たされていた。受話器はだらりとコードからぶら下がり、ダイヤル式の電話機本体は無数の傷で覆われている。
そして、その床。
薄汚れたコンクリートの床のちょうど真ん中に、それは一枚だけ落ちていた。
赤黒く錆びついた、一枚の十円玉。
その、あまりにも完璧なまでの『舞台装置』を前にして、私の心臓が大きく、どくん、と跳ねた。
嘘だ。
こんなことって、あるのか。
ただの都市伝説じゃなかったのか。
「……素晴らしい。実に、素晴らしいですわ」
レイカさんの声は興奮でわずかに震えていた。彼女はまるで貴重な遺跡でも発見した考古学者のように、その十円玉を食い入るように見つめている。
「この禍々しいまでの霊気……。間違いありませんわ。この十円玉は長年にわたってこの場所で、無数の人々の怨念やこの世ならざるモノからの呼び声を吸い続けてきたのです。もはやただの硬貨ではない。呪いの触媒そのものと化していますわ」
彼女はリュックサックからピンセットと小さなビニール袋を取り出すと、その十円玉を実に手際よく回収した。その動きには一切の迷いがない。
「さて、と」
レイカさんは満足げに頷くと、今度は様々な機材を電話ボックスの内外に次々と設置し始めた。
小型の録音機、電磁波測定器、カメラ、そして方位磁石。
「これは?」
「万が一、向こう側との交信に成功した場合に備えて、あらゆるデータを記録しておく必要がありますわ。声、温度、磁場の変化……。これらの客観的なデータこそが、オカルトを科学の領域へと昇華させるための第一歩なのですから」
彼女は真剣な顔でそう語る。その瞳はもはや、ただの好奇心だけではない。未知の真理を探求しようとする、真摯な研究者のそれだった。
そのあまりにも場違いな真剣さに、私の恐怖は少しだけ薄らいでいた。
この人は、本気なのだ。
心の底から、本気でこんな馬鹿げたことを信じている。
その純粋さが、呆れると同時にどこか羨ましくさえあった。
全ての準備が整った。
あとは、運命の時を待つだけ。
レイカさんは自分のスマートフォンの画面をじっと見つめている。時刻は、午後十一時五十五分を指していた。
深夜零時まで、あと五分。
急に、口の中がからからに乾いていくのを感じた。
「……ねえ、レイカさん」
「なんですの、サヤカ」
「やっぱり、やめない? もう十分でしょ。十円玉も見つかったし、雰囲気も味わったし。これ以上は、本当に危ない気がする」
私の声は自分でも情けないと思うほど、震えていた。
しかしレイカさんはスマートフォンから目を離さないまま、静かに首を横に振った。
「いいえ。ここまで来て、引き返すわけにはまいりませんわ」
「でも……」
「大丈夫ですわ、サヤカ」
彼女はそこで初めて、こちらを向いた。
その顔にはいつもの自信に満ちた笑みはなかった。
代わりに浮かんでいたのは、緊張と興奮と、そしてほんのわずかな恐怖の色。
彼女も、怖がっているのだ。
その事実に、私は少しだけ驚いた。
「わたくしがついておりますもの。それに、あなたも一緒ですわ。二人なら、きっと大丈夫」
その言葉は、何の根拠もない気休めに過ぎなかった。
けれど、その時の私にはそれがどんなお守りよりも心強く聞こえた。
私は黙って、こくりと頷いた。
沈黙が訪れる。
虫の声だけがやけに大きく耳に響く。
一分が、まるで一時間のように長く感じられた。
スマートフォンの画面の数字が、23:59に変わる。
あと、一分。
レイカさんがごくりと喉を鳴らす音が、やけに大きく聞こえた。
彼女はビニール袋から、あの錆びた十円玉を取り出した。
そして、それを電話機の硬貨投入口へと、ゆっくりと近づけていく。
私の心臓が、大きく、大きく脈打っている。
もう、後戻りはできない。
そして。
スマートフォンの数字が、00:00に変わった。
カチャン。
レイカさんの指が、十円玉を投入口へと押し込んだ。
静まり返った夜の闇に、そのあまりにも無機質な金属音が響き渡る。
彼女は震える指で受話器を取り上げた。
そして動画で紹介されていたという呪いの番号を、一つ、一つゆっくりとダイヤルしていく。
じ……。
じ……。
ダイヤルが回る音。
その古めかしい音が、私の鼓膜を不気味に揺らした。
全ての番号を回し終える。
レイカさんは受話器を自分の耳にそっと当てた。
私も息を殺して、その様子を見守る。
何も、起こらない。
ただ無音の時間が過ぎていくだけ。
「……やっぱり、ただの噂だったんじゃ」
私がそう言いかけた、その時だった。
プルルルル……。
受話器の向こうから、コール音が聞こえてきた。
レイカさんの肩が、びくりと大きく跳ねる。
繋がった。
本当に、繋がってしまった。
プルルルル……。
プルルルル……。
コール音は二回、三回と無機質に繰り返される。
誰も、出ない。
このまま誰も出ずに、切れてくれれば……。
そう、願った。
四回目のコール音が鳴り響いた、その直後だった。
カチリ。
不意にコール音が途切れた。
そして、電話の向こう側で何かが繋がったことを示す、小さな硬い音がした。