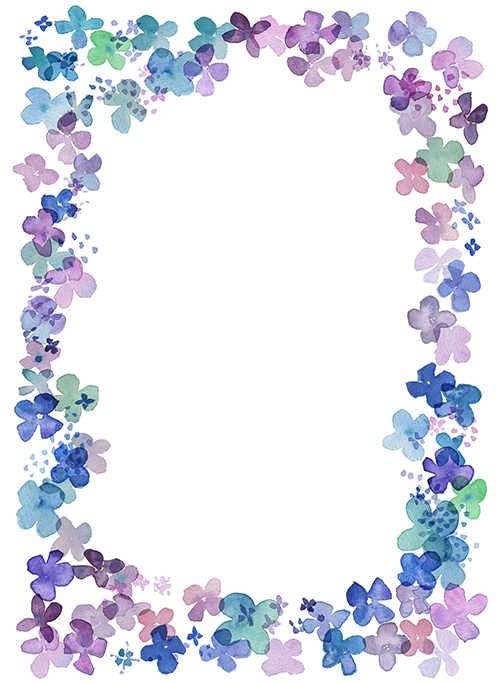夏休みが始まって、一週間が経った。
じりじりと肌を焼くような日差しと、どこまでも青い空。鳴り響く蝉の声。学生にとって特別なこの期間が、私にとってはただ退屈な日常の延長でしかなかった。学校という名の檻から解放されたのはいいけれど、かといって特別にやりたいことがあるわけでもない。冷房の効いた自室で、ただぼんやりと時間を溶かしていく。それは、西園寺レイカという名の『厄災』が私の人生に現れる前の、あの静かで平穏だった日々に少しだけ似ていた。
少しだけ、だ。
決定的に違うのは、私の手元にあるスマートフォンが、一日に何度もけたたましく通知音を鳴らすようになったこと。そして、その通知の送り主が常に同じ人物であるということだった。
『サヤカ! 今すぐこの動画をご覧くださいまし! 驚くべきことに、チュパカブラの正体は宇宙人が作り出した生物兵器だったという説が……』
『サヤカ! 大変ですわ! わたくしの部屋で、ついにオーブの撮影に成功いたしました! おそらく、わたくしの曾祖母様の霊ですわ!』
『サヤカ! この心霊写真、どう思われます? わたくしの見立てでは、これは低級霊の仕業などではなく、もっと高次元の存在からの……』
メッセージには必ずと言っていいほど、怪しげなURLかピンボケした画像が添付されている。私はそのほとんどを既読無視という大人の対応で受け流していたが、彼女の鋼の精神はそんなことでは少しもへこたれないようだった。
今日もまた、ベッドの上で意味もなくゴロゴロと転がっていると、軽快な通知音が鳴り響いた。画面に表示された名前を見て、私は本日何度目になるか分からないため息をつく。
『サヤカ、今日のご予定は?』
珍しく、普通の文章だった。オカルトのオの字も含まれていない。そのことが、逆によろしくない予感を私の胸に芽生えさせた。嵐の前の静けさ、という言葉が頭をよぎる。
『特にないけど』
正直にそう返信してしまったのは、私の完全な失策だった。送信ボタンを押した直後に後悔したが、もう遅い。数秒も経たないうちに『既読』の文字が表示され、即座に返信が来た。
『奇遇です! わたくしもですの! でしたら、これからわたくしのマンションにいらっしゃいませんこと? 一緒に、お料理を楽しみましょう!』
料理。
その、あまりにも健全で女子高生らしい単語の響きと、西園寺レイカという人物像が、私の頭の中でうまく結びつかなかった。
脳裏に、あの悪夢が鮮明に蘇る。赤黒いご飯の上に転がる、指の形をしたソーセージ。こちらを無数に見つめてくる、うずらの卵の目玉。
あのオカルト弁当の惨劇を、まさかまた繰り返すつもりなのだろうか。
『何を作るの?』
私は警戒心を最大限に高めながら、そう問い返した。返答次第では、急な腹痛を訴えて断る準備はできている。
『それは来てのお楽しみですわ。腕によりをかけて、サヤカをおもてなしいたします』
そう返ってきたメッセージには、可愛らしい猫がウインクしているスタンプが添えられていた。そのあまりのあざとさに、私はスマートフォンの画面に向かって思わず顔をしかめてしまう。
結局、私は彼女の誘いを断り切れなかった。あの真っ白な空間で意識を失っていた彼女の姿を思い出してしまうと、どうにも強く出られない自分がいる。それに、正直なところ、一人で過ごすこの退屈な時間にも飽り飽りしていたのかもしれない。
この厄介な非日常に、私はとっくの昔に毒されてしまっているのだ。
◇
指定された住所は、私の家から電車で三十分ほどの場所にある高級住宅街の一角だった。そびえ立つタワーマンションは、まるで天を突くかのような威圧感を放っている。エントランスはホテルのロビーのように広々としており、コンシェルジュまで常駐していた。
完全に、場違いだ。
私は、ごく普通のTシャツとジーンズという自分の服装を、無意味に見下ろした。
こんな場所に来るなら、もう少しマシな格好をしてくるべきだったか。いや、そもそも私がこんな場所に来ること自体が間違いなのだ。
しかし、約束を破るほど、私は非常識な人間ではない。
意を決して、エントランスの自動ドアをくぐる。その先には、コンシェルジュの女性が完璧な営業スマイルでこちらに歩み寄ってきた。
「何か御用でしょうか?」
「あ、あの、西園寺さんのお宅に……」
私がレイカさんの名前を出すと、女性の表情がわずかに、しかし確かに緊張を帯びたものに変わった。
「西園寺様でございますね。伺っております。最上階の、四十階でございます」
彼女は深々と頭を下げると、私を専用エレベーターへと案内してくれた。そのあまりにも丁寧な対応に、私はただただ縮こまるしかない。
エレベーターはほとんど音も立てずに上昇していく。耳が少しだけつんとする。あっという間に四十階に到着し、重厚な扉が開くと、そこには長い廊下が一本だけまっすぐに伸びていた。どうやら、このフロア全てが西園寺家の住居らしい。
現実感がない。
玄関の前に立つと、まるで私の到着を待っていたかのように、内側から扉が静かに開いた。
「ようこそいらっしゃいました、サヤカ」
出迎えてくれたのは、エプロン姿のレイカさんだった。フリルのついた可愛らしいデザインのエプロンも、彼女が身につけるとどこかの高級ブランドのドレスのように見えてしまうから不思議だ。
「さあ、どうぞお入りになって」
促されるままに足を踏み入れた先は、私が今まで生きてきた中で見たどんな家とも違っていた。高い天井、磨き上げられた大理石の床、そして窓の外に広がる、街を一望できる絶景。リビングに置かれたソファだけで、私の部屋が丸ごと入ってしまいそうだった。
「……すごい、とこ住んでるんだね」
「そうですこと? わたくしにとっては、これが普通ですけれど」
彼女は悪びれる様子もなく、にこりと微笑んだ。そのあまりにもあっけらかんとした態度に、私はもはや呆れる気力も湧いてこない。住む世界が違う、とはまさにこのことだ。
「さあ、キッチンはこちらですわ。さっそく始めましょう」
レイカさんに案内されたキッチンは、最新鋭の調理器具がずらりと並んだ、まるでショールームのような空間だった。中央には大きなアイランドキッチンが鎮座している。
「で、何を作るの?」
「本日は、夏にぴったりの冷製パスタと、特製のデザートを」
デザート、という単語に私の体が無意識にこわばる。
「……ちなみに、そのデザートって、どんな?」
「ふふ、それは完成してからのお楽しみですわ。さあ、まずは野菜を切りましょう。サヤカはトマトをお願いできますこと?」
彼女はそう言うと、冷蔵庫から見たこともないほど色鮮やかな野菜を次々と取り出していく。
私は一抹の不安を抱えながらも、差し出された包丁を握りしめた。
意外なことに、料理はごく普通に進んでいった。レイカさんの手際は驚くほど良く、その動きには一切の無駄がない。普段から自分で料理をしているのだろうか。その完璧超人ぶりに、私はまたしても感心させられてしまう。
やがて、彩りも鮮やかな、見るからに美味しそうな冷製パスタが完成した。
「どうぞ、召し上がれ」
ダイニングテーブルに運ばれたパスタは、レストランで出てきてもおかしくないほどのクオリティだった。私は恐る恐る、フォークで一口、口に運ぶ。
「……美味しい」
思わず、本音が漏れた。トマトの酸味とバジルの爽やかな香り、そして上質なオリーブオイルの風味が、絶妙なバランスで口の中に広がっていく。
「まあ、お口に合ってよかったですわ」
レイカさんは満足げに微笑んだ。
もしかしたら、私の心配は杞憂だったのかもしれない。彼女も、例の意味不明なオカルト弁当の失敗に懲りて、少しは常識というものを学んだのかもしれない。
そんな淡い期待を抱きながら、私たちは和やかな雰囲気で食事を進めていった。
そして。
デザートの時間がやってきた。
「さあ、サヤカ。お待たせいたしましたわ。こちらが、わたくしたちを次なる次元へと誘うための、特別な儀式ですの」
にこやかな笑顔と共に、私の目の前に置かれたのは四角いガラスの器だった。
その瞬間、私の淡い期待は予想もしなかった方向へと裏切られた。
器の中には、どこか病的な、それでいて奇妙なほど均一な淡い黄色のムースが満たされていた。その表面は不自然なほど滑らかで、まるでプラスチックのようだ。よく見ると、ムースの表面には規則的な薄い茶色の線が引かれている。それは古いオフィスビルの、染みのついた壁紙の模様にそっくりだった。
どこか無機質で食欲をそそらない色合いでありながら、マンゴーかパッションフルーツのような南国の果実を思わせる甘い香りを微かに放っている。
「こちらが、海外のネットロアで語られる異次元空間『The Backrooms』を、わたくしなりに再現した、食べるリミナルスペース『バックルームの一室』ですわ」
自信満々に解説する彼女の顔は一点の曇りもなく、晴れやかですらあった。全く私には理解できない用語ばかりだったけれど。
ただ、それでも私一つだけ、理解できた。それは彼女は本気で、これを素晴らしい儀式か何かだと信じている、ということだった。
「現実世界から稀に『noclip』……つまり外れ落ちてしまうと迷い込む、無限に続く黄色い部屋。湿ったカーペットの匂いと、蛍光灯の不快なハム音だけが響く、永遠の迷宮……」
レイカさんはそう言うと、小さなガラス瓶を取り出した。中には透明な液体に浸かった黒い粒が入っている。
「これは『エンティティの残滓』。これを振りかけることで、このデザートは完成しますのよ」
彼女がその液体――おそらくは黒ゴマをシロップに漬けたものだろう――をムースの上に数粒散らす。
ダメだ。この人は何も変わっていなかった。私の常識が、私の価値観が一切通用しない、異世界の住人なのだ。
「……いただきます」
私はもはや抵抗を諦め、魅入られたようにそう呟いた。
そして、スプーンを手に取り、その古いオフィスビルの『壁紙』ような色合いの食べ物にスプーンを差し入れる。
スプーンですくい上げた黄色いムースを、私はゆっくりと口に運んだ。舌に触れた瞬間、なめらかでひんやりとした感触が広がる。そして次の瞬間、私の予想を完全に裏切る豊潤な味わいが口内を駆け巡った。
濃厚なマンゴーの甘みと、パッションフルーツのきゅんとするような酸味。後から追いかけてくる、ココナッツミルクのまろやかなコク。見た目の不気味さからは到底想像もつかない、完璧なバランスで計算され尽くした南国の味。
……美味しい。
そう認めたくはないけれど、認めざるを得ないほどにそれは美味しかった。
何なのよ、これ。
見た目はこんなに悪趣味で、コンセプトは意味不明なオカルトなのに、どうして味だけはこんなにも本格的なんだろうか。そのことが無性に腹立たしかった。
料理もできて、デザートも作れて、その上、呪術的な儀式まで完璧にこなすというのか、この人は。その完璧さが、私のちっぽけなプライドを容赦なく打ちのめしてくる。
悔しい。けれど、スプーンを動かす手は止まらなかった。
◇
非常に疲れる、デザートタイムをなんとか乗り切り、私たちはリビングの巨大なソファでくつろいでいた。窓の外では、太陽がゆっくりと西に傾き始めている。
私の精神的な疲労とは裏腹に、レイカさんは実に上機嫌だった。
「やはり、サヤカと過ごす時間は格別ですわ。一人で怪異を研究するのも悪くはありませんが、こうして『運命の友』と語らいながら過ごすひとときは、何物にも代えがたい」
「……語らった記憶は、あんまりないけどね」
私がぼそりと呟くと、彼女はくすくすと楽しそうに笑った。
そして、おもむろにテーブルの上に置いてあったスマートフォンを手に取った。
「そういえばサヤカ。最近わたくしが夢中になっているものを、ご存じですこと?」
「知ってるよ。あの、変な動画でしょ」
「まあ、変だなんて。心外ですわ」
彼女は少しだけ唇を尖らせると、慣れた手つきでスマートフォンの画面を操作し始めた。やがて、スピーカーから軽快で、しかしどこか不穏なオープニング音楽が流れ出す。
「『YAMI-Tube』ですわ。現代のネットロアや都市伝説を、独自の視点で実に鋭く、そして面白おかしく解説してくれる、素晴らしいチャンネルなのです」
画面に映し出されたのは、派手な髪色をした、やけにテンションの高い男性だった。
「ヤッホー! 闇の世界へようこそ! みんなの闇先案内人、YAMIだよ! 今日のテーマは、これだ!」
画面に、どぎついフォントで『絶対にかけちゃダメ!? 呪いの電話番号、『招かざる電話』の真相に迫る!』というテロップが、効果音と共に表示される。
「また、物騒な話だね……」
私はソファに深く体を沈めながら、うんざりした気分で呟いた。
YAMIと名乗るその配信者は、実に軽薄な口調でその都市伝説について語り始めた。
「みんな、知ってる? 深夜零時ぴったりにある特定の番号にかけると、向こう側……つまり、この世ならざる場所に繋がっちゃうっていう、ヤバい電話の噂。それが今回特集する『招かざる電話』さ!」
画面には不気味なイラストや心霊写真らしきものが次々と表示される。そのたびに大げさな効果音が鳴り響き、YAMIはわざとらしい悲鳴を上げてみせた。
「この方のエンターテイナーとしての手腕は、実に評価できますわ。恐怖を煽るタイミング、緩急の付け方、視聴者を飽きさせないための工夫。全てが計算し尽くされている」
レイカさんは腕を組んで、まるで評論家のように真剣な表情で頷いている。
私には、ただの悪趣味な動画にしか見えなかったけれど。
「でね、この『招かざる電話』、実はその舞台となる場所が、かなり具体的に特定されてるんだよね。それがどこかっていうと……」
YAMIは、そこでもったいぶるように一度言葉を切った。そして、カメラに向かってにやりと不気味な笑みを浮かべる。
「なんと、とある場所にある、廃病院の前にある公衆電話なんだ!」
画面に、一枚の写真が大きく表示された。
蔦に覆われた古びた病院の建物。その前にぽつんと寂しげに立つ、赤い公衆電話ボックス。
その光景に、私は見覚えがあった。
いや、見覚えがある、どころではない。
それは私の家のすぐ近所にある廃病院だった。子供の頃、肝試しで忍び込んでひどく怒られた、あの場所に間違いなかった。
「旧・月宮総合病院。数年前に閉鎖されて、今じゃ地元じゃ有名な心霊スポットになってるらしいんだけどね。その目の前にある公衆電話ボックスが、ヤバいらしいんだ。なんでも、電話ボックスの床にはいつも、赤黒く錆びた十円玉が、一枚だけ落ちてるんだってさ」
YAMIは興奮した様子でまくし立てる。
「そして、深夜零時にその錆びた十円玉を使ってある番号に電話をかけると……」
ごくりと、隣でレイカさんが固唾を飲む音が聞こえた。彼女の瞳はもう、画面に釘付けになっている。
「電話の向こうから、この世のものとは思えない不気味な声が聞こえてくるらしいんだ。その声を聞いちまった奴は、みんなおかしくなっちまうって話さ。魂を、持っていかれちまう、ってね……」
動画は、YAMIの「信じるか信じないかは、君次第!」というお決まりのセリフで締めくくられた。
軽快なエンディングテーマが流れ、画面には他の動画へのリンクが表示される。
しかしレイカさんは動画が終わっても、スマートフォンの画面を食い入るように見つめたまま動かなかった。
嫌な、予感がした。
とてつもなく、嫌な予感が。
やがて、彼女はゆっくりと、本当にゆっくりとこちらを振り返った。
その顔には、私が今まで見たこともないほどの純粋で、無垢で、そして最高に厄介な表情が浮かんでいた。
「……サヤカ」
彼女は震える声で私の名前を呼んだ。
「今の見たことありますわよね? 今の場所、知っていますわよね?」
「……うん、まあ」
「私たちの家から、歩いて行ける距離ですわ」
「……そうだね」
私の気の抜けた返事とは対照的に、彼女の興奮は最高潮に達しているようだった。彼女はソファから勢いよく立ち上がると、私の両肩をがっしと掴んだ。その瞳は燃えるように輝いている。
「これは、もう単なる偶然ではございませんわ!」
彼女は、高らかに、それはもう実に高らかに宣言した。
「これは運命! 私たちに与えられた大いなる天啓なのです! さあ、サヤカ! 決まりですわ! 今夜、この『招かざる電話』の謎を、二人で解き明かしに行きましょう!」
やはり、そう来たか。
私は心の底から、深くて長いため息をついた。
もう驚きもしない。彼女の発想が常に私の予想の斜め上を行くことには、とっくの昔に慣れてしまっていた。
「絶対に、嫌」
私はきっぱりと、そして明確にそう言い放った。掴まれた肩を力ずくで振り払う。
「冗談じゃない! どうして私が、そんな気味の悪い場所に行かなきゃいけないの!廃病院の前にある公衆電話なんて、聞いただけで鳥肌が立つわ! 私はオカルトも怪談も心霊スポットも、全部、全部、大嫌いなの!」
私の、魂からの叫び。
しかし、目の前の『厄災』にはその叫びは全く届いていないようだった。
レイカさんは私の剣幕に怯むどころか、むしろ、うっとりとした表情でほう、と感嘆のため息を漏らした。
「素晴らしいですわ、サヤカ! その、魂の底からの拒絶! それこそが、あなたが本物の……」
「そのパターンは、もういいから!」
私は彼女の言葉を大声で遮った。
もう彼女のペースに巻き込まれてたまるか。
「とにかく、私は行かない! 絶対に行かないからね! 一人で、好きなだけ行ってきたらいいじゃない!」
そう言って、私はぷいとそっぽを向いた。
これで諦めてくれるだろう。
そう、思った。
しかし、西園寺レイカという人間は私の想像を常にはるかに超えてくる。
「まあ、つれないことをおっしゃいますの」
彼女は、少しだけ悲しそうな声を出した。
「わたくし、一人では心細いですのに。もし万が一、本物の悪霊にでも襲われたら、どうすれば……」
「大丈夫よ。あなたなら、悪霊相手にオカルト談義を吹っかけて、逆に論破できるから」
「ひどいですわ、サヤカ。わたくしはか弱い乙女ですのよ?」
か弱い乙女が、訳のわからない呪いのデザートなど作るものか。
私が冷たい視線を送ると、彼女は作戦を変えたようだった。
「……分かりましたわ。サヤカがそこまでおっしゃるのなら、仕方ありません」
彼女はしゅんと肩を落とすと、力なくソファに座り込んだ。
「ですが、これだけは覚えておいてくださいな。この怪異は、私たちのすぐそばに潜んでいるのです。もしサヤカが、夜中に一人で家に帰る途中で、あの公衆電話の前を通りかかったとしたら……」
彼女はそこで一度、言葉を切った。
そして、私の顔をじっと見つめてくる。
その瞳の奥に、悪戯っぽい光が宿った。
「電話ボックスの中から、呼び声が聞こえてくるかもしれませんわよ……? 『サヤカ……サヤカ……』って」
その言葉に、私の背筋をぞくりと冷たいものが走り抜けた。
そうだ。
あの廃病院は、私の家のすぐ近所なのだ。
夜、遅くなったら、必ずその前を通る。
いつもは何とも思っていなかった、あの赤い公衆電話。
明日から、私は平常心でその前を通り過ぎることができるだろうか。
帰り道で、もしあの電話が鳴り出したら……?
「……っ!」
想像してしまい、私は思わず自分の腕を抱きしめた。
レイカさんはそんな私の反応を見て、にやりと勝利を確信した笑みを浮かべた。
「ふふ、ご安心くださいな、サヤカ。わたくしがついておりますもの。安全対策は万全ですわ。清めの塩も、最新鋭の電磁波測定器も、高名な霊能力者の連絡先も、全て準備してあります」
彼女は自信満々に胸を張った。
その姿は、頼もしいというよりは、やはり最高に厄介だった。
「……何かあったら、すぐに帰るからね」
私の口から絞り出すように、その言葉が漏れた。
それを聞いた瞬間、レイカさんの顔がぱあっと花が咲くように輝いた。
「まあサヤカ! やはりあなたなら、分かってくださると信じておりましたわ!」
彼女は心底嬉しそうにそう言うと、私に力強く抱きついてきた。
ふわりと、いつもの品のいい花の香りが私の鼻先をかすめる。
その温かさが、なぜだかひどく虚しかった。
じりじりと肌を焼くような日差しと、どこまでも青い空。鳴り響く蝉の声。学生にとって特別なこの期間が、私にとってはただ退屈な日常の延長でしかなかった。学校という名の檻から解放されたのはいいけれど、かといって特別にやりたいことがあるわけでもない。冷房の効いた自室で、ただぼんやりと時間を溶かしていく。それは、西園寺レイカという名の『厄災』が私の人生に現れる前の、あの静かで平穏だった日々に少しだけ似ていた。
少しだけ、だ。
決定的に違うのは、私の手元にあるスマートフォンが、一日に何度もけたたましく通知音を鳴らすようになったこと。そして、その通知の送り主が常に同じ人物であるということだった。
『サヤカ! 今すぐこの動画をご覧くださいまし! 驚くべきことに、チュパカブラの正体は宇宙人が作り出した生物兵器だったという説が……』
『サヤカ! 大変ですわ! わたくしの部屋で、ついにオーブの撮影に成功いたしました! おそらく、わたくしの曾祖母様の霊ですわ!』
『サヤカ! この心霊写真、どう思われます? わたくしの見立てでは、これは低級霊の仕業などではなく、もっと高次元の存在からの……』
メッセージには必ずと言っていいほど、怪しげなURLかピンボケした画像が添付されている。私はそのほとんどを既読無視という大人の対応で受け流していたが、彼女の鋼の精神はそんなことでは少しもへこたれないようだった。
今日もまた、ベッドの上で意味もなくゴロゴロと転がっていると、軽快な通知音が鳴り響いた。画面に表示された名前を見て、私は本日何度目になるか分からないため息をつく。
『サヤカ、今日のご予定は?』
珍しく、普通の文章だった。オカルトのオの字も含まれていない。そのことが、逆によろしくない予感を私の胸に芽生えさせた。嵐の前の静けさ、という言葉が頭をよぎる。
『特にないけど』
正直にそう返信してしまったのは、私の完全な失策だった。送信ボタンを押した直後に後悔したが、もう遅い。数秒も経たないうちに『既読』の文字が表示され、即座に返信が来た。
『奇遇です! わたくしもですの! でしたら、これからわたくしのマンションにいらっしゃいませんこと? 一緒に、お料理を楽しみましょう!』
料理。
その、あまりにも健全で女子高生らしい単語の響きと、西園寺レイカという人物像が、私の頭の中でうまく結びつかなかった。
脳裏に、あの悪夢が鮮明に蘇る。赤黒いご飯の上に転がる、指の形をしたソーセージ。こちらを無数に見つめてくる、うずらの卵の目玉。
あのオカルト弁当の惨劇を、まさかまた繰り返すつもりなのだろうか。
『何を作るの?』
私は警戒心を最大限に高めながら、そう問い返した。返答次第では、急な腹痛を訴えて断る準備はできている。
『それは来てのお楽しみですわ。腕によりをかけて、サヤカをおもてなしいたします』
そう返ってきたメッセージには、可愛らしい猫がウインクしているスタンプが添えられていた。そのあまりのあざとさに、私はスマートフォンの画面に向かって思わず顔をしかめてしまう。
結局、私は彼女の誘いを断り切れなかった。あの真っ白な空間で意識を失っていた彼女の姿を思い出してしまうと、どうにも強く出られない自分がいる。それに、正直なところ、一人で過ごすこの退屈な時間にも飽り飽りしていたのかもしれない。
この厄介な非日常に、私はとっくの昔に毒されてしまっているのだ。
◇
指定された住所は、私の家から電車で三十分ほどの場所にある高級住宅街の一角だった。そびえ立つタワーマンションは、まるで天を突くかのような威圧感を放っている。エントランスはホテルのロビーのように広々としており、コンシェルジュまで常駐していた。
完全に、場違いだ。
私は、ごく普通のTシャツとジーンズという自分の服装を、無意味に見下ろした。
こんな場所に来るなら、もう少しマシな格好をしてくるべきだったか。いや、そもそも私がこんな場所に来ること自体が間違いなのだ。
しかし、約束を破るほど、私は非常識な人間ではない。
意を決して、エントランスの自動ドアをくぐる。その先には、コンシェルジュの女性が完璧な営業スマイルでこちらに歩み寄ってきた。
「何か御用でしょうか?」
「あ、あの、西園寺さんのお宅に……」
私がレイカさんの名前を出すと、女性の表情がわずかに、しかし確かに緊張を帯びたものに変わった。
「西園寺様でございますね。伺っております。最上階の、四十階でございます」
彼女は深々と頭を下げると、私を専用エレベーターへと案内してくれた。そのあまりにも丁寧な対応に、私はただただ縮こまるしかない。
エレベーターはほとんど音も立てずに上昇していく。耳が少しだけつんとする。あっという間に四十階に到着し、重厚な扉が開くと、そこには長い廊下が一本だけまっすぐに伸びていた。どうやら、このフロア全てが西園寺家の住居らしい。
現実感がない。
玄関の前に立つと、まるで私の到着を待っていたかのように、内側から扉が静かに開いた。
「ようこそいらっしゃいました、サヤカ」
出迎えてくれたのは、エプロン姿のレイカさんだった。フリルのついた可愛らしいデザインのエプロンも、彼女が身につけるとどこかの高級ブランドのドレスのように見えてしまうから不思議だ。
「さあ、どうぞお入りになって」
促されるままに足を踏み入れた先は、私が今まで生きてきた中で見たどんな家とも違っていた。高い天井、磨き上げられた大理石の床、そして窓の外に広がる、街を一望できる絶景。リビングに置かれたソファだけで、私の部屋が丸ごと入ってしまいそうだった。
「……すごい、とこ住んでるんだね」
「そうですこと? わたくしにとっては、これが普通ですけれど」
彼女は悪びれる様子もなく、にこりと微笑んだ。そのあまりにもあっけらかんとした態度に、私はもはや呆れる気力も湧いてこない。住む世界が違う、とはまさにこのことだ。
「さあ、キッチンはこちらですわ。さっそく始めましょう」
レイカさんに案内されたキッチンは、最新鋭の調理器具がずらりと並んだ、まるでショールームのような空間だった。中央には大きなアイランドキッチンが鎮座している。
「で、何を作るの?」
「本日は、夏にぴったりの冷製パスタと、特製のデザートを」
デザート、という単語に私の体が無意識にこわばる。
「……ちなみに、そのデザートって、どんな?」
「ふふ、それは完成してからのお楽しみですわ。さあ、まずは野菜を切りましょう。サヤカはトマトをお願いできますこと?」
彼女はそう言うと、冷蔵庫から見たこともないほど色鮮やかな野菜を次々と取り出していく。
私は一抹の不安を抱えながらも、差し出された包丁を握りしめた。
意外なことに、料理はごく普通に進んでいった。レイカさんの手際は驚くほど良く、その動きには一切の無駄がない。普段から自分で料理をしているのだろうか。その完璧超人ぶりに、私はまたしても感心させられてしまう。
やがて、彩りも鮮やかな、見るからに美味しそうな冷製パスタが完成した。
「どうぞ、召し上がれ」
ダイニングテーブルに運ばれたパスタは、レストランで出てきてもおかしくないほどのクオリティだった。私は恐る恐る、フォークで一口、口に運ぶ。
「……美味しい」
思わず、本音が漏れた。トマトの酸味とバジルの爽やかな香り、そして上質なオリーブオイルの風味が、絶妙なバランスで口の中に広がっていく。
「まあ、お口に合ってよかったですわ」
レイカさんは満足げに微笑んだ。
もしかしたら、私の心配は杞憂だったのかもしれない。彼女も、例の意味不明なオカルト弁当の失敗に懲りて、少しは常識というものを学んだのかもしれない。
そんな淡い期待を抱きながら、私たちは和やかな雰囲気で食事を進めていった。
そして。
デザートの時間がやってきた。
「さあ、サヤカ。お待たせいたしましたわ。こちらが、わたくしたちを次なる次元へと誘うための、特別な儀式ですの」
にこやかな笑顔と共に、私の目の前に置かれたのは四角いガラスの器だった。
その瞬間、私の淡い期待は予想もしなかった方向へと裏切られた。
器の中には、どこか病的な、それでいて奇妙なほど均一な淡い黄色のムースが満たされていた。その表面は不自然なほど滑らかで、まるでプラスチックのようだ。よく見ると、ムースの表面には規則的な薄い茶色の線が引かれている。それは古いオフィスビルの、染みのついた壁紙の模様にそっくりだった。
どこか無機質で食欲をそそらない色合いでありながら、マンゴーかパッションフルーツのような南国の果実を思わせる甘い香りを微かに放っている。
「こちらが、海外のネットロアで語られる異次元空間『The Backrooms』を、わたくしなりに再現した、食べるリミナルスペース『バックルームの一室』ですわ」
自信満々に解説する彼女の顔は一点の曇りもなく、晴れやかですらあった。全く私には理解できない用語ばかりだったけれど。
ただ、それでも私一つだけ、理解できた。それは彼女は本気で、これを素晴らしい儀式か何かだと信じている、ということだった。
「現実世界から稀に『noclip』……つまり外れ落ちてしまうと迷い込む、無限に続く黄色い部屋。湿ったカーペットの匂いと、蛍光灯の不快なハム音だけが響く、永遠の迷宮……」
レイカさんはそう言うと、小さなガラス瓶を取り出した。中には透明な液体に浸かった黒い粒が入っている。
「これは『エンティティの残滓』。これを振りかけることで、このデザートは完成しますのよ」
彼女がその液体――おそらくは黒ゴマをシロップに漬けたものだろう――をムースの上に数粒散らす。
ダメだ。この人は何も変わっていなかった。私の常識が、私の価値観が一切通用しない、異世界の住人なのだ。
「……いただきます」
私はもはや抵抗を諦め、魅入られたようにそう呟いた。
そして、スプーンを手に取り、その古いオフィスビルの『壁紙』ような色合いの食べ物にスプーンを差し入れる。
スプーンですくい上げた黄色いムースを、私はゆっくりと口に運んだ。舌に触れた瞬間、なめらかでひんやりとした感触が広がる。そして次の瞬間、私の予想を完全に裏切る豊潤な味わいが口内を駆け巡った。
濃厚なマンゴーの甘みと、パッションフルーツのきゅんとするような酸味。後から追いかけてくる、ココナッツミルクのまろやかなコク。見た目の不気味さからは到底想像もつかない、完璧なバランスで計算され尽くした南国の味。
……美味しい。
そう認めたくはないけれど、認めざるを得ないほどにそれは美味しかった。
何なのよ、これ。
見た目はこんなに悪趣味で、コンセプトは意味不明なオカルトなのに、どうして味だけはこんなにも本格的なんだろうか。そのことが無性に腹立たしかった。
料理もできて、デザートも作れて、その上、呪術的な儀式まで完璧にこなすというのか、この人は。その完璧さが、私のちっぽけなプライドを容赦なく打ちのめしてくる。
悔しい。けれど、スプーンを動かす手は止まらなかった。
◇
非常に疲れる、デザートタイムをなんとか乗り切り、私たちはリビングの巨大なソファでくつろいでいた。窓の外では、太陽がゆっくりと西に傾き始めている。
私の精神的な疲労とは裏腹に、レイカさんは実に上機嫌だった。
「やはり、サヤカと過ごす時間は格別ですわ。一人で怪異を研究するのも悪くはありませんが、こうして『運命の友』と語らいながら過ごすひとときは、何物にも代えがたい」
「……語らった記憶は、あんまりないけどね」
私がぼそりと呟くと、彼女はくすくすと楽しそうに笑った。
そして、おもむろにテーブルの上に置いてあったスマートフォンを手に取った。
「そういえばサヤカ。最近わたくしが夢中になっているものを、ご存じですこと?」
「知ってるよ。あの、変な動画でしょ」
「まあ、変だなんて。心外ですわ」
彼女は少しだけ唇を尖らせると、慣れた手つきでスマートフォンの画面を操作し始めた。やがて、スピーカーから軽快で、しかしどこか不穏なオープニング音楽が流れ出す。
「『YAMI-Tube』ですわ。現代のネットロアや都市伝説を、独自の視点で実に鋭く、そして面白おかしく解説してくれる、素晴らしいチャンネルなのです」
画面に映し出されたのは、派手な髪色をした、やけにテンションの高い男性だった。
「ヤッホー! 闇の世界へようこそ! みんなの闇先案内人、YAMIだよ! 今日のテーマは、これだ!」
画面に、どぎついフォントで『絶対にかけちゃダメ!? 呪いの電話番号、『招かざる電話』の真相に迫る!』というテロップが、効果音と共に表示される。
「また、物騒な話だね……」
私はソファに深く体を沈めながら、うんざりした気分で呟いた。
YAMIと名乗るその配信者は、実に軽薄な口調でその都市伝説について語り始めた。
「みんな、知ってる? 深夜零時ぴったりにある特定の番号にかけると、向こう側……つまり、この世ならざる場所に繋がっちゃうっていう、ヤバい電話の噂。それが今回特集する『招かざる電話』さ!」
画面には不気味なイラストや心霊写真らしきものが次々と表示される。そのたびに大げさな効果音が鳴り響き、YAMIはわざとらしい悲鳴を上げてみせた。
「この方のエンターテイナーとしての手腕は、実に評価できますわ。恐怖を煽るタイミング、緩急の付け方、視聴者を飽きさせないための工夫。全てが計算し尽くされている」
レイカさんは腕を組んで、まるで評論家のように真剣な表情で頷いている。
私には、ただの悪趣味な動画にしか見えなかったけれど。
「でね、この『招かざる電話』、実はその舞台となる場所が、かなり具体的に特定されてるんだよね。それがどこかっていうと……」
YAMIは、そこでもったいぶるように一度言葉を切った。そして、カメラに向かってにやりと不気味な笑みを浮かべる。
「なんと、とある場所にある、廃病院の前にある公衆電話なんだ!」
画面に、一枚の写真が大きく表示された。
蔦に覆われた古びた病院の建物。その前にぽつんと寂しげに立つ、赤い公衆電話ボックス。
その光景に、私は見覚えがあった。
いや、見覚えがある、どころではない。
それは私の家のすぐ近所にある廃病院だった。子供の頃、肝試しで忍び込んでひどく怒られた、あの場所に間違いなかった。
「旧・月宮総合病院。数年前に閉鎖されて、今じゃ地元じゃ有名な心霊スポットになってるらしいんだけどね。その目の前にある公衆電話ボックスが、ヤバいらしいんだ。なんでも、電話ボックスの床にはいつも、赤黒く錆びた十円玉が、一枚だけ落ちてるんだってさ」
YAMIは興奮した様子でまくし立てる。
「そして、深夜零時にその錆びた十円玉を使ってある番号に電話をかけると……」
ごくりと、隣でレイカさんが固唾を飲む音が聞こえた。彼女の瞳はもう、画面に釘付けになっている。
「電話の向こうから、この世のものとは思えない不気味な声が聞こえてくるらしいんだ。その声を聞いちまった奴は、みんなおかしくなっちまうって話さ。魂を、持っていかれちまう、ってね……」
動画は、YAMIの「信じるか信じないかは、君次第!」というお決まりのセリフで締めくくられた。
軽快なエンディングテーマが流れ、画面には他の動画へのリンクが表示される。
しかしレイカさんは動画が終わっても、スマートフォンの画面を食い入るように見つめたまま動かなかった。
嫌な、予感がした。
とてつもなく、嫌な予感が。
やがて、彼女はゆっくりと、本当にゆっくりとこちらを振り返った。
その顔には、私が今まで見たこともないほどの純粋で、無垢で、そして最高に厄介な表情が浮かんでいた。
「……サヤカ」
彼女は震える声で私の名前を呼んだ。
「今の見たことありますわよね? 今の場所、知っていますわよね?」
「……うん、まあ」
「私たちの家から、歩いて行ける距離ですわ」
「……そうだね」
私の気の抜けた返事とは対照的に、彼女の興奮は最高潮に達しているようだった。彼女はソファから勢いよく立ち上がると、私の両肩をがっしと掴んだ。その瞳は燃えるように輝いている。
「これは、もう単なる偶然ではございませんわ!」
彼女は、高らかに、それはもう実に高らかに宣言した。
「これは運命! 私たちに与えられた大いなる天啓なのです! さあ、サヤカ! 決まりですわ! 今夜、この『招かざる電話』の謎を、二人で解き明かしに行きましょう!」
やはり、そう来たか。
私は心の底から、深くて長いため息をついた。
もう驚きもしない。彼女の発想が常に私の予想の斜め上を行くことには、とっくの昔に慣れてしまっていた。
「絶対に、嫌」
私はきっぱりと、そして明確にそう言い放った。掴まれた肩を力ずくで振り払う。
「冗談じゃない! どうして私が、そんな気味の悪い場所に行かなきゃいけないの!廃病院の前にある公衆電話なんて、聞いただけで鳥肌が立つわ! 私はオカルトも怪談も心霊スポットも、全部、全部、大嫌いなの!」
私の、魂からの叫び。
しかし、目の前の『厄災』にはその叫びは全く届いていないようだった。
レイカさんは私の剣幕に怯むどころか、むしろ、うっとりとした表情でほう、と感嘆のため息を漏らした。
「素晴らしいですわ、サヤカ! その、魂の底からの拒絶! それこそが、あなたが本物の……」
「そのパターンは、もういいから!」
私は彼女の言葉を大声で遮った。
もう彼女のペースに巻き込まれてたまるか。
「とにかく、私は行かない! 絶対に行かないからね! 一人で、好きなだけ行ってきたらいいじゃない!」
そう言って、私はぷいとそっぽを向いた。
これで諦めてくれるだろう。
そう、思った。
しかし、西園寺レイカという人間は私の想像を常にはるかに超えてくる。
「まあ、つれないことをおっしゃいますの」
彼女は、少しだけ悲しそうな声を出した。
「わたくし、一人では心細いですのに。もし万が一、本物の悪霊にでも襲われたら、どうすれば……」
「大丈夫よ。あなたなら、悪霊相手にオカルト談義を吹っかけて、逆に論破できるから」
「ひどいですわ、サヤカ。わたくしはか弱い乙女ですのよ?」
か弱い乙女が、訳のわからない呪いのデザートなど作るものか。
私が冷たい視線を送ると、彼女は作戦を変えたようだった。
「……分かりましたわ。サヤカがそこまでおっしゃるのなら、仕方ありません」
彼女はしゅんと肩を落とすと、力なくソファに座り込んだ。
「ですが、これだけは覚えておいてくださいな。この怪異は、私たちのすぐそばに潜んでいるのです。もしサヤカが、夜中に一人で家に帰る途中で、あの公衆電話の前を通りかかったとしたら……」
彼女はそこで一度、言葉を切った。
そして、私の顔をじっと見つめてくる。
その瞳の奥に、悪戯っぽい光が宿った。
「電話ボックスの中から、呼び声が聞こえてくるかもしれませんわよ……? 『サヤカ……サヤカ……』って」
その言葉に、私の背筋をぞくりと冷たいものが走り抜けた。
そうだ。
あの廃病院は、私の家のすぐ近所なのだ。
夜、遅くなったら、必ずその前を通る。
いつもは何とも思っていなかった、あの赤い公衆電話。
明日から、私は平常心でその前を通り過ぎることができるだろうか。
帰り道で、もしあの電話が鳴り出したら……?
「……っ!」
想像してしまい、私は思わず自分の腕を抱きしめた。
レイカさんはそんな私の反応を見て、にやりと勝利を確信した笑みを浮かべた。
「ふふ、ご安心くださいな、サヤカ。わたくしがついておりますもの。安全対策は万全ですわ。清めの塩も、最新鋭の電磁波測定器も、高名な霊能力者の連絡先も、全て準備してあります」
彼女は自信満々に胸を張った。
その姿は、頼もしいというよりは、やはり最高に厄介だった。
「……何かあったら、すぐに帰るからね」
私の口から絞り出すように、その言葉が漏れた。
それを聞いた瞬間、レイカさんの顔がぱあっと花が咲くように輝いた。
「まあサヤカ! やはりあなたなら、分かってくださると信じておりましたわ!」
彼女は心底嬉しそうにそう言うと、私に力強く抱きついてきた。
ふわりと、いつもの品のいい花の香りが私の鼻先をかすめる。
その温かさが、なぜだかひどく虚しかった。