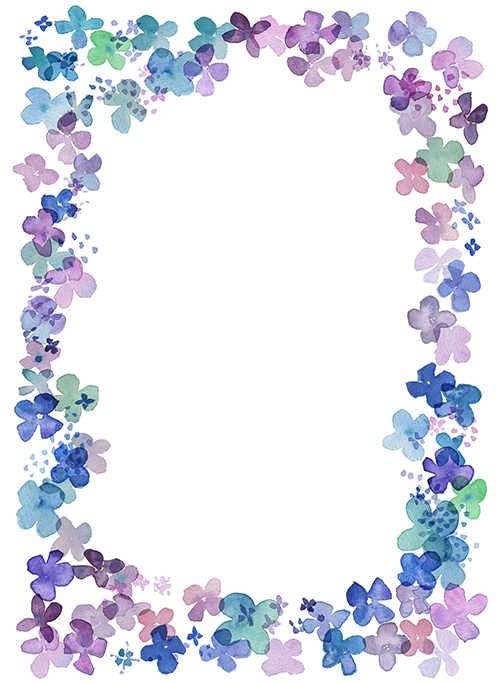私の日常は、もはや私の知るそれとは全く異なり、その姿を完全に変えてしまっていた。
以前の水面のように静かで変化のない、けれどどこか息苦しさのあった日々は、まるで遠い昔の夢物語のようだ。今の私の毎日は例えるなら、常に強火にかけられ、いつ噴きこぼれるか分からない鍋を隣で見張っているようなものだった。
もちろん、その鍋の具材であり最大の火力でもあるのは、私の隣の席に座る『運命の友』、西園寺レイカさん、その人である。
「サヤカ! ご覧になってくださいまし! この驚くべき映像を!」
休み時間。私が窓の外を眺めてぼんやりと過ごそうとしていた、ほんのわずかな平穏は、今日もまた彼女の張りのある声によっていとも簡単に打ち破られた。
振り返ると、レイカさんが目をきらきらと輝かせながらスマートフォンをこちらに突きつけている。その画面には、薄暗い廃墟の中を大げさな身振り手振りで歩き回る、派手な髪色の男性が映し出されていた。
「また、それ見てるの……」
私は本日何度目になるか分からないため息を、心の奥底から絞り出した。
彼女が最近、それこそ三度のご飯よりも夢中になっているもの。それは、チャンネル登録者数が数百万を誇るという超人気オカルト系動画チャンネル、通称『YAMI-Tube』だった。
心霊スポットへの突撃取材や都市伝説の真偽を検証するといった内容を、面白おかしく、そして少々過剰な演出で配信する、まあよくあるタイプのチャンネルだ。
レイカさんはこのチャンネルの動画を、まるで学術論文でも読み解くかのように毎日毎日、熱心に視聴していた。
「この配信者、ヤミ様は実に興味深い人物ですわ。一見するとただの軽薄なエンターテイナー。ですが時折、その考察の中に本質を的確に射抜く鋭い視点が散見されるのです。特にこの間の『きさらぎ駅は異世界へのターミナルか』というテーマの動画における、量子力学的な観点からのアプローチは、実に、実に素晴らしいものでしたわ……!」
うっとりとした表情で、彼女は一人語り始める。その瞳はもう私を見ていない。彼女はスマートフォンの小さな画面の向こうに広がる、広大なオカルトの世界へとその意識を飛ばしている。
私はそんな彼女の横顔を眺めながら、再び深いため息をついた。
きさらぎ駅。コトリバコ。鮫島事件。決して座ってはいけない席。
レイカさんと出会ってからというもの、私の頭の中には聞きたくもないオカルト知識が否応なく蓄積されていっていた。今ではクラスの誰よりもネットロアに詳しくなってしまった自信がある。全く嬉しくない自信だった。
「ねえサヤカ。このヤミ様が動画の中で使用しているこの霊体探知機……わたくしの自作した『マナライザー』の初期モデルと、内部構造が酷似していることにお気づきですこと?」
「気づかないし、気づきたくもない」
「これはもう単なる偶然ではございませんわ。おそらくヤミ様もわたくしも、同じ『真理』の源流に無意識のうちにアクセスしている……ええ、そうとしか考えられませんわ!」
一人で興奮し、一人で納得する。いつもの光景だ。
以前の私なら、こんな会話に付き合わされること自体が耐え難い苦痛だっただろう。けれど今は違う。もちろん面倒だという気持ちに変わりはない。けれどそれと同時に、どこかで『また始まった』と呆れながらも受け入れてしまっている自分がいることにも気づいていた。
あの全てが消え去った、色のない世界を経験してしまったからだろうか。
この迷惑で騒々しくて、常識の通じないやり取りこそが今の私の『日常』なのだと、心のどこかで認めてしまっているのかもしれない。
◇
そんな騒がしくも、どこか慣れてしまった日々が続いていた、ある日の放課後だった。
ホームルームが終わり、生徒たちが部活や帰宅の準備でざわめく中、レイカさんがいつになく真剣な、それでいて興奮を抑えきれないといった表情で私の机に詰め寄ってきた。その手にはもちろん、例の動画が再生されたままのスマートフォンが握られている。
「サヤカ! 大変ですわ!」
「……今度は、何?」
私はカバンに教科書を詰めながら、うんざりした気分で応じた。どうせまたどこかのマイナーな都市伝説か、あるいはヤミ様とやらの新動画の話だろう。
「ヤミ様の最新動画で、とんでもない情報が公開されましたの!」
「はいはい、よかったね」
「よくありませんわ! これは私たちにとって聞き捨てならない、重大な情報なのですから!」
彼女は私の肩をがっしと掴むと、そのアーモンド形の瞳でまっすぐに私を見つめてきた。その瞳の奥にはいつもの、純粋な好奇心と探究心の色が燃え盛る炎のように揺らめいている。
これは、まずい。
私の経験則が、けたたましく警鐘を鳴らしていた。この目の色をした時の彼女は、絶対にろくなことを言い出さない。
「ヤミ様が次なる検証の地として紹介していた、とあるパワースポット……それがなんと、この町のすぐ近郊にあるそうなのです!」
パワースポット。その比較的穏やかな響きに、私はほんの少しだけ警戒を緩めた。心霊スポットとか呪いの場所とか、そういう物騒な単語ではなかったからだ。
「へえ、そうなんだ。で?」
「で? ではございませんわ!」
彼女は私のその気の抜けた返事に、信じられないとでも言いたげな顔で声を大きくした。
「決まっているでしょう! さあサヤカ! 今すぐ検証に向かいましょう!」
「……は?」
一瞬、彼女が何を言っているのか理解できなかった。
今すぐ? 検証に? 誰が? 私と、あなたが?
「絶対に嫌!」
私は間髪入れずに、きっぱりとそう言い放った。
冗談じゃない。もうこりごりなのだ。あなたのその底なしの好奇心に付き合わされて、命がけの体験をするのは。あの真っ白な空間で感じた途方もない恐怖と孤独は、まだ私の記憶に生々しくこびりついている。
「まあサヤカ。どうしてですの? 今回は危険な場所ではございませんのよ?」
「あなたの言う『危険じゃない』は全く信用できないの! 大体パワースポットなんてただの観光地でしょ。そんなところに行って、一体何を検証するっていうのよ」
「もちろん、そこに宿るとされる神霊の存在ですわ!」
彼女は胸を張って、高らかに宣言した。
「その場所は『双葉の楠』と呼ばれ、古くから縁結びにご利益があるとして多くの人々の信仰を集めてきたそうですの。二本の巨大な楠が根元で一つに結びついている、それはそれは神秘的な神木……。その神木に宿るとされる高位の霊的存在の霊的波動を、このわたくしの『マナライザー』で精密に測定し、その実在を科学的に証明するのです! ああ、なんて胸が躍る計画でしょう!」
うっとりとした表情で彼女はそう語る。その壮大な計画とやらは、私にとっては迷惑千万な与太話でしかなかった。
「縁結びの神様を科学的に証明? 罰当たりなことよく考えつくわね……。とにかく私は行かないから。一人で行ってきたら?」
「まあ、つれないことをおっしゃいますの。サヤカがいてくださらなければ意味がありませんわ」
「どうしてよ」
「あなたは私の『運命の友』であると同時に、強力な霊的エネルギーを引き寄せる最高の『触媒』でもあるのですから。あなたというアンテナがなければ、いかなる高位の霊的存在も観測することは叶いませんのよ」
触媒。アンテナ。
彼女は私を一体なんだと思っているのだろうか。便利なオカルトグッズか何かと勘違いしているのではないだろうか。
「とにかく嫌なものは嫌!もうあなたの趣味に付き合うのはうんざりなのよ!」
私が半ば本気で声を荒らげた、その時だった。
レイカさんはふっと真顔になると、どこか悲しげな色を目に浮かべてぽつりと呟いた。
「……そうですか。サヤカがそこまでおっしゃるのでしたら、仕方ありませんわね」
そのあまりにも予想外のしおらしい態度に、私は思わず虚を突かれた。
いつもならここからさらに、あの手この手で私を言いくるめようとしてくるはずなのに。
「では今回は、わたくし一人で参りますわ。……少し、心細いですけれど」
彼女は力なくそう言うと、寂しそうに微笑んでくるりと私に背を向けた。そのか細く頼りなげな後ろ姿。それは私の知っている、自信満々で傲岸不遜な西園寺レイカの姿とはあまりにもかけ離れていた。
私の胸が、ちくりと痛んだ。
これは、罠だ。
分かっている。これは私を同行させるための、彼女の新たな作戦に違いない。
けれど。
けれど、このまま、一人で向かったとしたら?
私に見捨てられて一人でしょんぼりとパワースポットへ向かう彼女の姿。
そしてもし、そこで何か良からぬものにでも遭遇してしまったら?
彼女は確かに知識は豊富だが、根本的なところでどこか抜けている。私がついていないと、とんでもないヘマをしでかす可能性は大いにある。
あの真っ白な空間で、人形のように意識を失っていた彼女の姿が脳裏をよぎった。
もう、あんな思いはしたくない。
「……はあ」
私は天を仰いで、今日一番深くて長いため息をついた。
もう、どうにでもなれ。
「……分かったわよ! 行けばいいんでしょ、行けば!」
私がそう叫んだ瞬間。
私に背を向けていたはずのレイカさんが、満面の笑みで勢いよくこちらを振り返った。その顔には先ほどまでの悲しげな色は微塵も残っていなかった。
「まあサヤカ! やはりあなたなら、分かってくださると信じておりましたわ!」
やっぱり、私を誘うための交渉だったのか。
私はがっくりと肩を落とした。
この『運命の友』の手のひらの上で、私は一体どこまで転がされ続けるのだろうか。
「……何かあったらすぐに帰るからね。絶対に、すぐに帰るから!」
私は念を押すように、何度もそう繰り返した。
その言葉にレイカさんはこくりと力強く頷くと、私の手をがっしと掴んだ。
「ええ、もちろんですわ! さあ参りましょう! 私たちの新たな聖地巡礼へ!」
こうして私はまたしても、彼女の予測不能な非日常へと引きずり込まれていくことになったのだった。
◇
電車とバスを乗り継いで、私たちが目的の『双葉の楠』がある公園にたどり着いたのは、それから一時間ほど後のことだった。
そこは私の想像していたような、鬱蒼とした森の中にある場所ではなかった。綺麗に整備された広々とした公園。その一角に、その神木はまるで空を支えるかのように雄大にそびえ立っていた。
二本の、見上げるほど巨大な楠。その太い幹が地面のすぐ上で複雑に絡み合い、完全に一つに癒合している。その姿はまさに、自然が作り出した壮大な芸術作品のようだった。
公園の中は多くの人々で賑わっていた。芝生の上でボール遊びをする家族連れ。ベンチに座って談笑する老夫婦。そして神木の前で手を合わせて静かに祈りを捧げる、若いカップルたち。
どこを見ても平和で穏やかな光景が広がっている。あの学校の怪奇現象『お墓』と呼ばれた教室で感じたような、不吉な気配はどこにもない。
私はその和やかな空気に、心の底から安堵した。
「……よかった。普通のいい場所じゃない」
「ええ、そうですわね」
隣でレイカさんも満足げに頷いている。
「この地に満ちる清浄な生命エネルギー……いわゆるプラーナ、あるいはエーテルとでも呼ぶべきでしょうか。素晴らしい。実に素晴らしいですわ」
彼女はうっとりとした表情で神木を見上げている。その手にはいつの間にか、あの怪しげな自作の機械――『マナライザー』が握られていた。
それはガイガーカウンターを改造したかのような、無骨な見た目の機械だった。いくつものメーターと意味の分からないスイッチが取り付けられており、先端からは針金のようなアンテナが何本も突き出している。
彼女はその機械を恭しく両手で構えると、神木に向かってゆっくりとかざした。
「おお……! ご覧なさいサヤカ! この『マナライザー』がこの地に満ちるマナの濃度を、極めて高い数値で示しておりますわ! やはりこの神木には我々の理解を超えた、何らかの超常的な力が宿っている……間違いありません!」
彼女は一人で興奮し、メーターの数値を手帳に熱心に書き留めている。その姿は周囲の和やかな風景から明らかに浮いていた。何人かの通行人が怪訝な顔でこちらをちらちらと見ているのが分かる。
私はたまらない羞恥心に襲われ、彼女からそっと距離を取った。
「あなた、その機械がただのガラクタだって、まだ気づかないの……」
私が呆れ果ててそう呟いた、まさにその時だった。
ビビビビビッ!!
突如として、レイカさんの持つ『マナライザー』がけたたましい警告音を鳴り響かせたのだ。
静かだった公園に、その耳障りな電子音が不釣り合いに響き渡る。
見ると、機械のメーターの針が振り切れんばかりに左右へ激しく揺れていた。赤い警告ランプが狂ったようにチカチкаと点滅している。
「こ、これは……!?」
レイカさんの顔からいつもの余裕が消え、驚愕の色が浮かんだ。
「ありえませんわ……!これほどの強力なエネルギー反応……!先ほどの神木から発せられる霊的波動など、比較にならないほどの圧倒的なパワーです!」
彼女は狼狽しながらも機械を構え直し、そのエネルギーの発生源を探るようにきょろきょろと周囲を見回した。
「間違いありませんわサヤカ! 我々の感知範囲内に、極めて強大な霊的存在が急速に接近しています!」
そのあまりにも真に迫った声に、私の背筋を冷たいものがすっと走り抜けた。
嘘だ。
そんなはずはない。
ここはこんなにも平和で穏やかな場所なのに。
レイカさんは私を庇うようにぐっと前に出ると、鋭い視線で辺りを睨みつけた。その姿はまるで、見えない敵と対峙する熟練の戦士のようだった。
私も思わずごくりと喉を鳴らした。
警告音はますますその音量を上げていく。
ビビビビビッ! ビビビビビッ!
心臓が大きく脈打つのが分かった。
一体何が、近づいてきているというのか。
近くでは大音量の演歌が聞こえた。
…演歌?
ただ、これは誰かが歌っているようなものではない、質の悪いスピーカーから聞こえてくるような…
私はその演歌が聞こえてきた方向を見た。
◇
演歌の音源は、私たちのすぐそばのベンチに座っていた一人の高齢のお爺さん。
そのお爺さんが、やたらと年季の入った古い携帯ラジオを持っていて、そこから曲が流れてきていた。
次の瞬間、お爺さんはポケットをまさぐり始めた。イヤホンでも耳に付けたかったのか、携帯ラジオを操作する。
演歌が消えた。
お爺さんが、ラジオを切ったのだ。
その瞬間。
レイカさんの『マナライザー』の警告音がぴたりと止むのは、ほぼ同時だった。
そういえば、さっき、あのラジオから大音量で演歌が流れ出すのと、ほとんど同じタイミングで狂ったように反応していた気がする。
「……」
「……」
私とレイカさんは顔を見合わせたまま、言葉を失った。
次の瞬間、お爺さんはイヤホンを装着して、再びラジオを操作する。
ビビビビビッ! ビビビビビッ!
ただ公園の穏やかな午後の空気とともに、再び、警告音が鳴り始めた。
「……どうやら今回は、ただのノイズだったようですわね」
長い長い沈黙の後、レイカさんがぽつりとそう呟いた。
私はその場にへなへなと座り込みそうになった。全身からどっと力が抜けていくのが分かる。
「……もう、帰る」
「ええ、そうしましょう」
レイカさんは何事もなかったかのようににこりと微笑むと、そのガラクタ機械を手際よくカバンへとしまい込んだ。
帰り道。
夕日に染まるバスの車内で、私は窓の外を流れる景色を眺めながら、今日のあの馬鹿馬鹿しい騒動を反芻していた。
「サヤカ。今日の検証でまた一つ、貴重なデータが取れましたわ」
隣の席で、レイカさんが満足げにそう言った。
「何のデータよ……。あなたの機械がただのガラクタだって証明されただけでしょ」
「いいえ、違いますわ。あのラジオが発した特定の周波数の電波が『マナライザー』に、あれほどまでの干渉を引き起こした……。これは霊的エネルギーと電磁波との間に、何らかの未知の相関関係が存在することを示唆する、画期的な発見ですのよ! ああ、ヤミ様もきっとこの事実にまだお気づきではありますまい。彼の次の動画が実に楽しみですこと」
彼女はもう、次の探求へとその心を馳せているようだった。
私はその、どこまでも前向きで底抜けに能天気な横顔を、ただ呆れ果てて見つめることしかできなかった。
以前の水面のように静かで変化のない、けれどどこか息苦しさのあった日々は、まるで遠い昔の夢物語のようだ。今の私の毎日は例えるなら、常に強火にかけられ、いつ噴きこぼれるか分からない鍋を隣で見張っているようなものだった。
もちろん、その鍋の具材であり最大の火力でもあるのは、私の隣の席に座る『運命の友』、西園寺レイカさん、その人である。
「サヤカ! ご覧になってくださいまし! この驚くべき映像を!」
休み時間。私が窓の外を眺めてぼんやりと過ごそうとしていた、ほんのわずかな平穏は、今日もまた彼女の張りのある声によっていとも簡単に打ち破られた。
振り返ると、レイカさんが目をきらきらと輝かせながらスマートフォンをこちらに突きつけている。その画面には、薄暗い廃墟の中を大げさな身振り手振りで歩き回る、派手な髪色の男性が映し出されていた。
「また、それ見てるの……」
私は本日何度目になるか分からないため息を、心の奥底から絞り出した。
彼女が最近、それこそ三度のご飯よりも夢中になっているもの。それは、チャンネル登録者数が数百万を誇るという超人気オカルト系動画チャンネル、通称『YAMI-Tube』だった。
心霊スポットへの突撃取材や都市伝説の真偽を検証するといった内容を、面白おかしく、そして少々過剰な演出で配信する、まあよくあるタイプのチャンネルだ。
レイカさんはこのチャンネルの動画を、まるで学術論文でも読み解くかのように毎日毎日、熱心に視聴していた。
「この配信者、ヤミ様は実に興味深い人物ですわ。一見するとただの軽薄なエンターテイナー。ですが時折、その考察の中に本質を的確に射抜く鋭い視点が散見されるのです。特にこの間の『きさらぎ駅は異世界へのターミナルか』というテーマの動画における、量子力学的な観点からのアプローチは、実に、実に素晴らしいものでしたわ……!」
うっとりとした表情で、彼女は一人語り始める。その瞳はもう私を見ていない。彼女はスマートフォンの小さな画面の向こうに広がる、広大なオカルトの世界へとその意識を飛ばしている。
私はそんな彼女の横顔を眺めながら、再び深いため息をついた。
きさらぎ駅。コトリバコ。鮫島事件。決して座ってはいけない席。
レイカさんと出会ってからというもの、私の頭の中には聞きたくもないオカルト知識が否応なく蓄積されていっていた。今ではクラスの誰よりもネットロアに詳しくなってしまった自信がある。全く嬉しくない自信だった。
「ねえサヤカ。このヤミ様が動画の中で使用しているこの霊体探知機……わたくしの自作した『マナライザー』の初期モデルと、内部構造が酷似していることにお気づきですこと?」
「気づかないし、気づきたくもない」
「これはもう単なる偶然ではございませんわ。おそらくヤミ様もわたくしも、同じ『真理』の源流に無意識のうちにアクセスしている……ええ、そうとしか考えられませんわ!」
一人で興奮し、一人で納得する。いつもの光景だ。
以前の私なら、こんな会話に付き合わされること自体が耐え難い苦痛だっただろう。けれど今は違う。もちろん面倒だという気持ちに変わりはない。けれどそれと同時に、どこかで『また始まった』と呆れながらも受け入れてしまっている自分がいることにも気づいていた。
あの全てが消え去った、色のない世界を経験してしまったからだろうか。
この迷惑で騒々しくて、常識の通じないやり取りこそが今の私の『日常』なのだと、心のどこかで認めてしまっているのかもしれない。
◇
そんな騒がしくも、どこか慣れてしまった日々が続いていた、ある日の放課後だった。
ホームルームが終わり、生徒たちが部活や帰宅の準備でざわめく中、レイカさんがいつになく真剣な、それでいて興奮を抑えきれないといった表情で私の机に詰め寄ってきた。その手にはもちろん、例の動画が再生されたままのスマートフォンが握られている。
「サヤカ! 大変ですわ!」
「……今度は、何?」
私はカバンに教科書を詰めながら、うんざりした気分で応じた。どうせまたどこかのマイナーな都市伝説か、あるいはヤミ様とやらの新動画の話だろう。
「ヤミ様の最新動画で、とんでもない情報が公開されましたの!」
「はいはい、よかったね」
「よくありませんわ! これは私たちにとって聞き捨てならない、重大な情報なのですから!」
彼女は私の肩をがっしと掴むと、そのアーモンド形の瞳でまっすぐに私を見つめてきた。その瞳の奥にはいつもの、純粋な好奇心と探究心の色が燃え盛る炎のように揺らめいている。
これは、まずい。
私の経験則が、けたたましく警鐘を鳴らしていた。この目の色をした時の彼女は、絶対にろくなことを言い出さない。
「ヤミ様が次なる検証の地として紹介していた、とあるパワースポット……それがなんと、この町のすぐ近郊にあるそうなのです!」
パワースポット。その比較的穏やかな響きに、私はほんの少しだけ警戒を緩めた。心霊スポットとか呪いの場所とか、そういう物騒な単語ではなかったからだ。
「へえ、そうなんだ。で?」
「で? ではございませんわ!」
彼女は私のその気の抜けた返事に、信じられないとでも言いたげな顔で声を大きくした。
「決まっているでしょう! さあサヤカ! 今すぐ検証に向かいましょう!」
「……は?」
一瞬、彼女が何を言っているのか理解できなかった。
今すぐ? 検証に? 誰が? 私と、あなたが?
「絶対に嫌!」
私は間髪入れずに、きっぱりとそう言い放った。
冗談じゃない。もうこりごりなのだ。あなたのその底なしの好奇心に付き合わされて、命がけの体験をするのは。あの真っ白な空間で感じた途方もない恐怖と孤独は、まだ私の記憶に生々しくこびりついている。
「まあサヤカ。どうしてですの? 今回は危険な場所ではございませんのよ?」
「あなたの言う『危険じゃない』は全く信用できないの! 大体パワースポットなんてただの観光地でしょ。そんなところに行って、一体何を検証するっていうのよ」
「もちろん、そこに宿るとされる神霊の存在ですわ!」
彼女は胸を張って、高らかに宣言した。
「その場所は『双葉の楠』と呼ばれ、古くから縁結びにご利益があるとして多くの人々の信仰を集めてきたそうですの。二本の巨大な楠が根元で一つに結びついている、それはそれは神秘的な神木……。その神木に宿るとされる高位の霊的存在の霊的波動を、このわたくしの『マナライザー』で精密に測定し、その実在を科学的に証明するのです! ああ、なんて胸が躍る計画でしょう!」
うっとりとした表情で彼女はそう語る。その壮大な計画とやらは、私にとっては迷惑千万な与太話でしかなかった。
「縁結びの神様を科学的に証明? 罰当たりなことよく考えつくわね……。とにかく私は行かないから。一人で行ってきたら?」
「まあ、つれないことをおっしゃいますの。サヤカがいてくださらなければ意味がありませんわ」
「どうしてよ」
「あなたは私の『運命の友』であると同時に、強力な霊的エネルギーを引き寄せる最高の『触媒』でもあるのですから。あなたというアンテナがなければ、いかなる高位の霊的存在も観測することは叶いませんのよ」
触媒。アンテナ。
彼女は私を一体なんだと思っているのだろうか。便利なオカルトグッズか何かと勘違いしているのではないだろうか。
「とにかく嫌なものは嫌!もうあなたの趣味に付き合うのはうんざりなのよ!」
私が半ば本気で声を荒らげた、その時だった。
レイカさんはふっと真顔になると、どこか悲しげな色を目に浮かべてぽつりと呟いた。
「……そうですか。サヤカがそこまでおっしゃるのでしたら、仕方ありませんわね」
そのあまりにも予想外のしおらしい態度に、私は思わず虚を突かれた。
いつもならここからさらに、あの手この手で私を言いくるめようとしてくるはずなのに。
「では今回は、わたくし一人で参りますわ。……少し、心細いですけれど」
彼女は力なくそう言うと、寂しそうに微笑んでくるりと私に背を向けた。そのか細く頼りなげな後ろ姿。それは私の知っている、自信満々で傲岸不遜な西園寺レイカの姿とはあまりにもかけ離れていた。
私の胸が、ちくりと痛んだ。
これは、罠だ。
分かっている。これは私を同行させるための、彼女の新たな作戦に違いない。
けれど。
けれど、このまま、一人で向かったとしたら?
私に見捨てられて一人でしょんぼりとパワースポットへ向かう彼女の姿。
そしてもし、そこで何か良からぬものにでも遭遇してしまったら?
彼女は確かに知識は豊富だが、根本的なところでどこか抜けている。私がついていないと、とんでもないヘマをしでかす可能性は大いにある。
あの真っ白な空間で、人形のように意識を失っていた彼女の姿が脳裏をよぎった。
もう、あんな思いはしたくない。
「……はあ」
私は天を仰いで、今日一番深くて長いため息をついた。
もう、どうにでもなれ。
「……分かったわよ! 行けばいいんでしょ、行けば!」
私がそう叫んだ瞬間。
私に背を向けていたはずのレイカさんが、満面の笑みで勢いよくこちらを振り返った。その顔には先ほどまでの悲しげな色は微塵も残っていなかった。
「まあサヤカ! やはりあなたなら、分かってくださると信じておりましたわ!」
やっぱり、私を誘うための交渉だったのか。
私はがっくりと肩を落とした。
この『運命の友』の手のひらの上で、私は一体どこまで転がされ続けるのだろうか。
「……何かあったらすぐに帰るからね。絶対に、すぐに帰るから!」
私は念を押すように、何度もそう繰り返した。
その言葉にレイカさんはこくりと力強く頷くと、私の手をがっしと掴んだ。
「ええ、もちろんですわ! さあ参りましょう! 私たちの新たな聖地巡礼へ!」
こうして私はまたしても、彼女の予測不能な非日常へと引きずり込まれていくことになったのだった。
◇
電車とバスを乗り継いで、私たちが目的の『双葉の楠』がある公園にたどり着いたのは、それから一時間ほど後のことだった。
そこは私の想像していたような、鬱蒼とした森の中にある場所ではなかった。綺麗に整備された広々とした公園。その一角に、その神木はまるで空を支えるかのように雄大にそびえ立っていた。
二本の、見上げるほど巨大な楠。その太い幹が地面のすぐ上で複雑に絡み合い、完全に一つに癒合している。その姿はまさに、自然が作り出した壮大な芸術作品のようだった。
公園の中は多くの人々で賑わっていた。芝生の上でボール遊びをする家族連れ。ベンチに座って談笑する老夫婦。そして神木の前で手を合わせて静かに祈りを捧げる、若いカップルたち。
どこを見ても平和で穏やかな光景が広がっている。あの学校の怪奇現象『お墓』と呼ばれた教室で感じたような、不吉な気配はどこにもない。
私はその和やかな空気に、心の底から安堵した。
「……よかった。普通のいい場所じゃない」
「ええ、そうですわね」
隣でレイカさんも満足げに頷いている。
「この地に満ちる清浄な生命エネルギー……いわゆるプラーナ、あるいはエーテルとでも呼ぶべきでしょうか。素晴らしい。実に素晴らしいですわ」
彼女はうっとりとした表情で神木を見上げている。その手にはいつの間にか、あの怪しげな自作の機械――『マナライザー』が握られていた。
それはガイガーカウンターを改造したかのような、無骨な見た目の機械だった。いくつものメーターと意味の分からないスイッチが取り付けられており、先端からは針金のようなアンテナが何本も突き出している。
彼女はその機械を恭しく両手で構えると、神木に向かってゆっくりとかざした。
「おお……! ご覧なさいサヤカ! この『マナライザー』がこの地に満ちるマナの濃度を、極めて高い数値で示しておりますわ! やはりこの神木には我々の理解を超えた、何らかの超常的な力が宿っている……間違いありません!」
彼女は一人で興奮し、メーターの数値を手帳に熱心に書き留めている。その姿は周囲の和やかな風景から明らかに浮いていた。何人かの通行人が怪訝な顔でこちらをちらちらと見ているのが分かる。
私はたまらない羞恥心に襲われ、彼女からそっと距離を取った。
「あなた、その機械がただのガラクタだって、まだ気づかないの……」
私が呆れ果ててそう呟いた、まさにその時だった。
ビビビビビッ!!
突如として、レイカさんの持つ『マナライザー』がけたたましい警告音を鳴り響かせたのだ。
静かだった公園に、その耳障りな電子音が不釣り合いに響き渡る。
見ると、機械のメーターの針が振り切れんばかりに左右へ激しく揺れていた。赤い警告ランプが狂ったようにチカチкаと点滅している。
「こ、これは……!?」
レイカさんの顔からいつもの余裕が消え、驚愕の色が浮かんだ。
「ありえませんわ……!これほどの強力なエネルギー反応……!先ほどの神木から発せられる霊的波動など、比較にならないほどの圧倒的なパワーです!」
彼女は狼狽しながらも機械を構え直し、そのエネルギーの発生源を探るようにきょろきょろと周囲を見回した。
「間違いありませんわサヤカ! 我々の感知範囲内に、極めて強大な霊的存在が急速に接近しています!」
そのあまりにも真に迫った声に、私の背筋を冷たいものがすっと走り抜けた。
嘘だ。
そんなはずはない。
ここはこんなにも平和で穏やかな場所なのに。
レイカさんは私を庇うようにぐっと前に出ると、鋭い視線で辺りを睨みつけた。その姿はまるで、見えない敵と対峙する熟練の戦士のようだった。
私も思わずごくりと喉を鳴らした。
警告音はますますその音量を上げていく。
ビビビビビッ! ビビビビビッ!
心臓が大きく脈打つのが分かった。
一体何が、近づいてきているというのか。
近くでは大音量の演歌が聞こえた。
…演歌?
ただ、これは誰かが歌っているようなものではない、質の悪いスピーカーから聞こえてくるような…
私はその演歌が聞こえてきた方向を見た。
◇
演歌の音源は、私たちのすぐそばのベンチに座っていた一人の高齢のお爺さん。
そのお爺さんが、やたらと年季の入った古い携帯ラジオを持っていて、そこから曲が流れてきていた。
次の瞬間、お爺さんはポケットをまさぐり始めた。イヤホンでも耳に付けたかったのか、携帯ラジオを操作する。
演歌が消えた。
お爺さんが、ラジオを切ったのだ。
その瞬間。
レイカさんの『マナライザー』の警告音がぴたりと止むのは、ほぼ同時だった。
そういえば、さっき、あのラジオから大音量で演歌が流れ出すのと、ほとんど同じタイミングで狂ったように反応していた気がする。
「……」
「……」
私とレイカさんは顔を見合わせたまま、言葉を失った。
次の瞬間、お爺さんはイヤホンを装着して、再びラジオを操作する。
ビビビビビッ! ビビビビビッ!
ただ公園の穏やかな午後の空気とともに、再び、警告音が鳴り始めた。
「……どうやら今回は、ただのノイズだったようですわね」
長い長い沈黙の後、レイカさんがぽつりとそう呟いた。
私はその場にへなへなと座り込みそうになった。全身からどっと力が抜けていくのが分かる。
「……もう、帰る」
「ええ、そうしましょう」
レイカさんは何事もなかったかのようににこりと微笑むと、そのガラクタ機械を手際よくカバンへとしまい込んだ。
帰り道。
夕日に染まるバスの車内で、私は窓の外を流れる景色を眺めながら、今日のあの馬鹿馬鹿しい騒動を反芻していた。
「サヤカ。今日の検証でまた一つ、貴重なデータが取れましたわ」
隣の席で、レイカさんが満足げにそう言った。
「何のデータよ……。あなたの機械がただのガラクタだって証明されただけでしょ」
「いいえ、違いますわ。あのラジオが発した特定の周波数の電波が『マナライザー』に、あれほどまでの干渉を引き起こした……。これは霊的エネルギーと電磁波との間に、何らかの未知の相関関係が存在することを示唆する、画期的な発見ですのよ! ああ、ヤミ様もきっとこの事実にまだお気づきではありますまい。彼の次の動画が実に楽しみですこと」
彼女はもう、次の探求へとその心を馳せているようだった。
私はその、どこまでも前向きで底抜けに能天気な横顔を、ただ呆れ果てて見つめることしかできなかった。