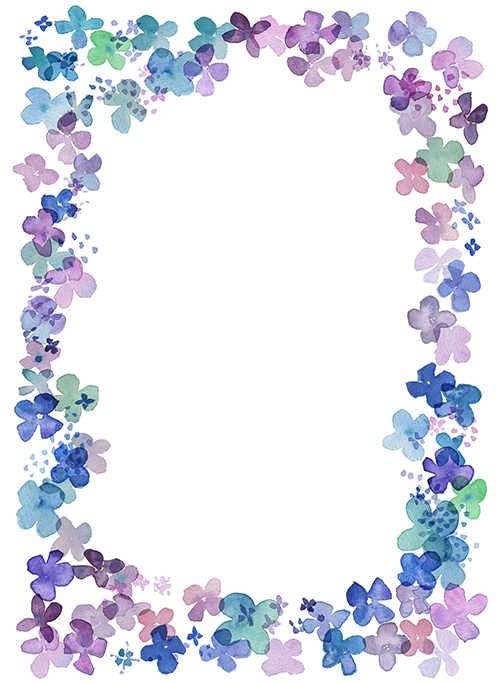ありふれている、という言葉ほど、私にとって心地の良い響きを持つものはない。
昨日と同じ時間に目を覚まし、昨日と同じ道を歩いて学校へ向かう。昨日と同じ席に座り、昨日と同じ顔ぶれと当たり障りのない会話を交わす。変化のない日々の繰り返し。刺激もなければ、大きな喜びもない。けれど、そこには確かな平穏があった。私は、その何でもない日常が、他の何よりも大切だった。この先もずっと、卒業するその日まで、この退屈で安心な毎日が続いていく。そう、信じて疑っていなかった。
少なくとも、彼女がこの教室に現れるまでは。
「はーい、席に着けー。ホームルーム始めるぞー」
予鈴が鳴り終わり、本鈴が鳴り響くのとほぼ同時に、担任の教師が教室の扉を開けて入ってくる。その手には出席簿。いつも通りの光景。生徒たちのざわめきが少しずつ小さくなっていく。私も、隣の席の友人と続けていた昨日のテレビ番組の話を切り上げ、背筋を伸ばして正面の黒板に向き直った。
「えー、今日は皆に転校生を紹介する」
その一言が、教室の空気をわずかに揺らした。転校生。この時期にというのは少し珍しいかもしれない。ちらほらと、誰だろう、男か女か、といった囁き声が聞こえてくる。私の興味は、そのどちらでもなかった。誰が来ようと、私の日常に大きな影響があるはずもない。せいぜい、クラスの人間関係の力学が少しだけ変化する程度。それだって、私のような教室の隅で静かに過ごすタイプの人間には、ほとんど関係のない話だ。
「入れ」
担任の短い声に促され、教室の前方の扉が静かに開いた。そして、一人の女子生徒が、まるでそこだけ世界の法則が違うかのような、ゆったりとした足取りで中へと入ってくる。
その瞬間、教室から完全に音が消えた。
艶のある長い黒髪。小さな顔には、西洋の精巧な人形を思わせる整った目鼻立ちが配置されている。肌は透けるように白く、指定の制服を着ているはずなのに、彼女が身に纏うと、それはどこかの高級ブランドが仕立てた特別な一着のように見えた。
現実感がない。
まるで、出来の良いアニメかゲームのキャラクターが、画面の中からそのまま抜け出してきたかのようだ。
「西園寺レイカさんだ。ご家庭の都合で、今日からこのクラスで一緒に勉強することになった。皆、仲良くしてやってくれ」
担任の紹介の言葉も、どこか遠くに聞こえる。クラスの誰もが、息をすることさえ忘れて、その転校生――西園寺レイカさんの姿に見入っていた。男子生徒は分かりやすく顔を赤らめ、女子生徒たちも、憧れと、ほんの少しの戸惑いが入り混じったような表情で彼女を見つめている。
もちろん、私もその一人だった。ただ、私の感情は、憧れや好意とは少し違っていた。どちらかと言えば、それは畏怖に近い。明らかに、住む世界の違う人間が来てしまった。そんな感覚。私の求める『平穏な日常』という城の、分厚い壁の外にいるべき存在。それが、どういうわけか、今、城のど真ん中に立っている。
「西園寺です。どうぞ、よろしくお願いいたします」
凛、と表現するのが正しいだろうか。涼やかで、けれど冷たいわけではない。聞く者の耳にすっと馴染む声だった。完璧な角度で腰を折り、優雅に頭を下げる。その一連の動きには、何一つ無駄がなかった。
「何か質問のある者は?」
担任がそう言うと、数人の生徒が、ためらいがちに手を挙げた。
「はい、そこのお前」
「えっと、西園寺さんはどこの学校から来たんですか?」
クラスの男子グループの中心にいる、快活な性格の男子生徒からの質問だった。誰もが気になっていることだろう。
「以前は、都内にある私立の女子校に通っておりました」
彼女はにこやかに、そして淀みなく答える。その校名は、私でも知っている。厳格なことで有名な、正真正銘のお嬢様学校だ。なるほど、と教室のあちこちから納得したような声が漏れる。あの立ち居振る舞いも、納得がいく。
「じゃあ、次は……」
「はい!」
今度は、女子のグループの一人が、元気よく手を挙げた。
「西園寺さんって、もしかして、あの西園寺グループの……?」
その言葉に、教室が再びざわめく。西園寺グループ。日本経済を動かしているとまで言われる、巨大企業体だ。テレビのニュースや新聞でも、その名前を見ない日はない。まさか、とは思う。そんな大企業の令嬢が、こんなごく普通の都立高校に転校してくるなんて、あり得るのだろうか。
全ての視線が、再び彼女に集まる。肯定も否定もせず、西園寺さんはただ、優雅な微笑みを浮かべている。
「皆様のご想像にお任せいたしますわ」
煙に巻くような答え。しかし、その言い方、その雰囲気は、質問に対する何より雄弁な肯定に聞こえた。教室の興奮が、一段と高まるのが肌で感じられる。すごいのが来たぞ、と誰もが思っている。
私だけが、一人、冷めた頭で考えていた。面倒なことになった、と。財閥の令嬢だろうがそうでなかろうが、どちらにしても、彼女は『普通』ではない。彼女がいるだけで、この教室は、私が今まで慣れ親しんできた場所とは違う、何か別のものに変わってしまうだろう。
「えー、まあ、そんなわけだ。席は……そうだな、一番後ろの窓際、鮫島の隣が空いてるな。西園寺、あそこでいいか?」
担任の言葉に、私は自分の耳を疑った。
今、何と。
私の、隣?
そんな、馬鹿な。教室には、他にも空席があったはずだ。どうしてよりによって、一番目立たないこの場所を。私の平穏を守るための、最後の砦とも言うべきこの聖域を。
私が内心の動揺を処理できずにいると、西園寺さんは、こくりと小さく頷いた。そして、ゆっくりとこちらへ向かって歩き始める。その一歩一歩が、私の心の平穏を踏み潰していく音のように聞こえた。
クラス中の視線が、彼女の動きに合わせて移動してくる。その視線が、最終的に私に突き刺さる。やめてくれ。私は見世物じゃない。
西園寺さんは、私の机の横でぴたりと足を止めると、にっこりと微笑みかけてきた。
「これから、よろしくお願いいたしますね」
「……あ、はい。こちらこそ」
かろうじて、それだけを口にするのが精一杯だった。彼女から、ふわりと、品のいい花の香りがした。
これが、全ての始まりだった。私の退屈で、愛おしい日常が、非日常という名の濁流に飲み込まれていく、その序章に過ぎなかったのだ。
◇
西園寺レイカという人間は、私の想像をあらゆる面で超えていた。
彼女は、休み時間になるたびに、クラスの中心にいた。転校初日とは思えないほど、自然に、当たり前のように。男子も女子も、誰もが彼女と話したがった。そして彼女は、どんな相手に対しても、どんな話題に対しても、実に楽しそうに、そして的確に対応してみせた。そのコミュニケーション能力は、もはや芸術の域に達しているとさえ思えた。
財閥の令嬢という立場を鼻にかける様子は微塵もない。むしろ、自分から積極的に輪の中に入っていき、相手の懐にするりと入り込んでしまう。その天真爛漫な明るさは、人を惹きつけてやまない、一種の才能なのだろう。
もちろん、そんな彼女と私が、休み時間に言葉を交わすことはなかった。彼女は常に誰かに囲まれていたし、私も、あえてその輪に加わろうとは思わなかったからだ。それでいい。隣の席になったとはいえ、住む世界が違うのだ。授業中に教科書の貸し借りをする程度の、当たり障りのない関係。それが、私にとっては理想だった。
その理想が、いとも簡単に崩れ去ったのは、昼休みを知らせるチャイムが鳴った直後のことだった。
弁当を持って席を立とうとした私に、背後から声がかかった。
「あの、よろしいでしょうか」
振り返ると、そこには西園寺さんが立っていた。いつの間にか、彼女の周りにいた人だかりは消えている。その手には、生徒名簿らしきファイルが握られていた。
「はい、なんでしょう」
「先ほど、先生があなたのお名前を呼ぶのを聞いて、少し気になったことがございまして」
彼女はそう言うと、ファイルを開き、指で一つの名前を指し示した。そこに書かれていたのは、もちろん私の名前だ。
「あなたは鮫島サヤカさんとおっしゃるのですね?」
「ええ、そうですけど……」
それが何か問題でも、と続けようとした私の言葉は、彼女の次のひと言によって、完全に遮られた。
「……鮫島」
彼女は、私の名字を、まるで貴重な宝石でも口にするかのように、ゆっくりと、そして熱のこもった声で繰り返した。
「やはり、あの『鮫島』なのですね……!」
その瞬間、彼女の雰囲気ががらりと変わった。それまでの優雅で社交的な微笑みは消え、代わりに、瞳の奥に、何かを探求するような、燃え立つような色が浮かんでいる。そのあまりの変化に、私は思わず一歩後ずさった。
「あの……『あの』って、どの……?」
「ご存じないのですか? いえ、ご存じないはずがない。当事者なのですから」
何を言っているんだ、この人は。私の頭の中は、疑問符で埋め尽くされる。当事者? 何の?
私の困惑をよそに、西園寺さんは、まるで長年追い求めていた真理に辿り着いた学者のような口調で、一人語り始めた。
「『鮫島事件』……。ネットロアの中でも特に謎多き事件として語り継がれる、現代の神隠し。その存在は語られるものの、誰もその詳細を知らない。知ろうとすれば、たちまち身に危険が及ぶとされ、多くのネットユーザーが恐怖のうちに口を閉ざしたという、あの伝説の……!」
さめじまじけん。
初めて聞く単語だった。いや、あるいは、どこかで目にしたことがあったのかもしれない。ネットの海を漂っていれば、時折、奇妙な単語に出くわすことはある。けれど、自分の名字が冠された、そんな物騒な事件など、全くもって記憶になかった。
「いや、あの、私、そういうの全然知らなくて……」
「隠す必要はありませんわ。その名字を背負う者として、真実を語りたがらないお気持ちは、痛いほど理解できます。ですが、私は違う。私は、あなたの味方です」
話が全く噛み合っていない。味方だと言われても、何のだというのか。私はただ、この状況からどうやって抜け出すか、そればかりを考えていた。
周りを見ると、教室に残っていた生徒たちが、何事かとこちらを遠巻きに見ている。その視線が、痛い。
「私は長年、この国のあらゆる怪異や都市伝説を研究してまいりました。古くは古事記に記された神々の逸話から、最新のネットロアまで。その中でも、この『鮫島事件』は、私にとって特別な意味を持つ、長年の研究テーマだったのです」
彼女は、うっとりとした表情でそう語る。その瞳は、もう私を見ていなかった。彼女は、彼女自身の作り上げた世界の中で、一人、壮大な物語を紡いでいる。
なるほど。
ようやく、理解した。
この人は、いわゆる『そっち側』の人間なのだ。オカルトとか、都市伝説とか、そういう非科学的なものが、三度のご飯より好きなタイプ。そして、私のありふれた名字を、何か特別なものと結びつけて、勝手に興奮している。
つまり、とてつもなく、面倒くさい。
「まさか、転校したこの場所で、その伝説の中心人物に出会えるなんて……。これはもう、単なる偶然ではありません。ええ、断じて」
彼女は一度言葉を切ると、再び、その熱っぽい視線を私に向けた。そして、私の両手を、有無を言わさぬ力で、がっしと掴んだ。
冷たい、けれど、驚くほど力のこもった手だった。
「これは運命ですわ!」
彼女は、教室中に響き渡るような、朗々とした声で言い放った。
「鮫島サヤカさん! あなたこそ、私が探し求めていた、たった一人の『運命の友』なのです!」
高らかに、それはもう、実に高らかに。まるで舞台役者がクライマックスの台詞を叫ぶかのように。
教室中の視線が、面白いほど綺麗に、私と彼女の二人に集中した。誰もが、何が起こっているのか理解できず、ただ呆然とこちらを見ている。もちろん、私もその一人だ。
運命の友。
その言葉が、私の頭の中で、意味をなさない音の響きとして、ただぐるぐると回り続けていた。
掴まれた両手が、熱い。いや、熱いのは彼女の手か、それとも冷や汗で濡れた私の手か。もう、何も分からなかった。
ただ一つ、確信できることがある。
私の平穏な毎日は、今日、この瞬間、完全に、そして決定的に、終わりを告げたのだ。
目の前で満面の笑みを浮かべる、美しくも迷惑千万なこの転校生によって。
茫然自失の私を置き去りにして、教室は昼休みの喧騒を取り戻していく。周りの生徒たちは、先ほどの劇的な場面を興奮気味に囁き合いながら、ちらちらとこちらに視線を送ってくる。その視線が痛い。
私はただ、自分の席で固まっていた。昼食をとる気力もわかない。そんな私の前に、ふわりと影が落ちた。
「さあ、サヤカ。さっそく友情を深めるために、ご一緒にお昼をいただきましょう」
顔を上げると、そこには西園寺さんが、いつの間にか用意したらしい、ピンクのお弁当箱を手に微笑んでいた。
「あ、いや、私は友達と……」
言い訳を探す私の言葉を遮り、彼女は当然のように私の前の席に腰を下ろした。彼女のお弁当が、机の上に、ことり、と上品な音を立てて置かれる。
「まあ、他人行儀ですわ。どうぞレイカとお呼びくださいな。ね、サヤカ」
ぐい、と顔を寄せられる。今日、何度目かに感じる品のいい花の香りが鼻先をかすめた。近い。物理的にも、精神的にも、彼女は躊躇なくパーソナルスペースに侵入してくる。
「私たちは、運命によって引き合わされた友なのですから。遠慮は無用ですわ」
きらきらとした、一点の曇りもない瞳。その純粋さが、何よりも厄介だった。彼女の中に、悪意や計算といったものが見えれば、まだ対処のしようもある。けれど、彼女は本気で、心の底から、私との間に特別な繋がりがあると信じ込んでいるのだ。善意百パーセントの暴走。それほど、手に負えないものはない。
「……じゃあ、レイカ、さん」
「はい、サヤカ!」
私がようやくそう口にすると、彼女は花が咲くように、ぱあっと表情を輝かせた。そして満足げに頷くと、ぱかり、とお重の蓋を開ける。中には、彩りも鮮やかな、料亭の仕出しと見紛うばかりの料理が、寸分の隙間なく詰められていた。
「どうぞ、遠慮なさらず。……あら、サヤカのお弁当は、とても可愛らしいですわね」
私の、ごく普通の卵焼きとウインナーが入った弁当を覗き込み、彼女は無邪気に微笑む。
「ですが、ご安心くださいな。明日は、私がもっと素晴らしいお弁当を用意してきますわ。サヤカの度肝を抜くような、特別なものを。友情の証です」
その言葉に、私は美味しいお弁当への期待よりも、何か得体の知れない恐怖を感じていた。
結局、私は彼女の勢いに押し切られる形で、レイカさんと昼食を共にすることになった。周囲の席の生徒たちが、好奇と、そして明らかな同情が入り混じった目でこちらを見ているのが分かる。やめてくれ。そんな目で見ないでくれ。私は被害者なんだ。
◇
なんとか、レイカさんとの昼休みが終わり、午後の授業が始まっても、レイカさんの勢いはとどまることを知らなかった。
その日の午後の授業中も、レイカさんからの見えない圧力は続いた。私が少しでも分からないという顔をすれば、すかさず「大丈夫ですか、サヤカ?」と小声で尋ねてくる。私がノートを取る手が止まれば、「ここの部分、私のノートを見ます?」と、完璧に整理されたノートをこちらに見せてくる。その親切の一つ一つが、私にとっては『鮫島事件の当事者』という、身に覚えのない役割を強制されているようで、息が詰まりそうだった。
授業の合間の短い休み時間になれば、状況はさらに悪化する。午前中、彼女の周りにできていた人だかりは、今や私と彼女の二人を中心にして形成されていた。
「レイカさんって、本当にあの西園寺グループのご令嬢なの?」
「サヤカって、レイカさんと昔からの知り合いだったりする?」
質問の矛先は、レイカさんだけでなく、私にも向けられる。そのたびに、私は曖昧に笑って首を振ることしかできない。レイカさんは、そんな私を助けるどころか、むしろ楽しんでいるようにさえ見えた。
「サヤカは私の『特別』なのです。ね?」
そう言って、私の肩に手を置き、にっこりと微笑む。その一言で、周囲の好奇心はさらに燃え上がる。私は、まるで珍しい生き物でも見せられているかのような、居心地の悪さを感じていた。
平穏な日常は、もうどこにもない。私の城は、外からやってきた侵略者によって、完全に占拠されてしまったのだ。
昨日と同じ時間に目を覚まし、昨日と同じ道を歩いて学校へ向かう。昨日と同じ席に座り、昨日と同じ顔ぶれと当たり障りのない会話を交わす。変化のない日々の繰り返し。刺激もなければ、大きな喜びもない。けれど、そこには確かな平穏があった。私は、その何でもない日常が、他の何よりも大切だった。この先もずっと、卒業するその日まで、この退屈で安心な毎日が続いていく。そう、信じて疑っていなかった。
少なくとも、彼女がこの教室に現れるまでは。
「はーい、席に着けー。ホームルーム始めるぞー」
予鈴が鳴り終わり、本鈴が鳴り響くのとほぼ同時に、担任の教師が教室の扉を開けて入ってくる。その手には出席簿。いつも通りの光景。生徒たちのざわめきが少しずつ小さくなっていく。私も、隣の席の友人と続けていた昨日のテレビ番組の話を切り上げ、背筋を伸ばして正面の黒板に向き直った。
「えー、今日は皆に転校生を紹介する」
その一言が、教室の空気をわずかに揺らした。転校生。この時期にというのは少し珍しいかもしれない。ちらほらと、誰だろう、男か女か、といった囁き声が聞こえてくる。私の興味は、そのどちらでもなかった。誰が来ようと、私の日常に大きな影響があるはずもない。せいぜい、クラスの人間関係の力学が少しだけ変化する程度。それだって、私のような教室の隅で静かに過ごすタイプの人間には、ほとんど関係のない話だ。
「入れ」
担任の短い声に促され、教室の前方の扉が静かに開いた。そして、一人の女子生徒が、まるでそこだけ世界の法則が違うかのような、ゆったりとした足取りで中へと入ってくる。
その瞬間、教室から完全に音が消えた。
艶のある長い黒髪。小さな顔には、西洋の精巧な人形を思わせる整った目鼻立ちが配置されている。肌は透けるように白く、指定の制服を着ているはずなのに、彼女が身に纏うと、それはどこかの高級ブランドが仕立てた特別な一着のように見えた。
現実感がない。
まるで、出来の良いアニメかゲームのキャラクターが、画面の中からそのまま抜け出してきたかのようだ。
「西園寺レイカさんだ。ご家庭の都合で、今日からこのクラスで一緒に勉強することになった。皆、仲良くしてやってくれ」
担任の紹介の言葉も、どこか遠くに聞こえる。クラスの誰もが、息をすることさえ忘れて、その転校生――西園寺レイカさんの姿に見入っていた。男子生徒は分かりやすく顔を赤らめ、女子生徒たちも、憧れと、ほんの少しの戸惑いが入り混じったような表情で彼女を見つめている。
もちろん、私もその一人だった。ただ、私の感情は、憧れや好意とは少し違っていた。どちらかと言えば、それは畏怖に近い。明らかに、住む世界の違う人間が来てしまった。そんな感覚。私の求める『平穏な日常』という城の、分厚い壁の外にいるべき存在。それが、どういうわけか、今、城のど真ん中に立っている。
「西園寺です。どうぞ、よろしくお願いいたします」
凛、と表現するのが正しいだろうか。涼やかで、けれど冷たいわけではない。聞く者の耳にすっと馴染む声だった。完璧な角度で腰を折り、優雅に頭を下げる。その一連の動きには、何一つ無駄がなかった。
「何か質問のある者は?」
担任がそう言うと、数人の生徒が、ためらいがちに手を挙げた。
「はい、そこのお前」
「えっと、西園寺さんはどこの学校から来たんですか?」
クラスの男子グループの中心にいる、快活な性格の男子生徒からの質問だった。誰もが気になっていることだろう。
「以前は、都内にある私立の女子校に通っておりました」
彼女はにこやかに、そして淀みなく答える。その校名は、私でも知っている。厳格なことで有名な、正真正銘のお嬢様学校だ。なるほど、と教室のあちこちから納得したような声が漏れる。あの立ち居振る舞いも、納得がいく。
「じゃあ、次は……」
「はい!」
今度は、女子のグループの一人が、元気よく手を挙げた。
「西園寺さんって、もしかして、あの西園寺グループの……?」
その言葉に、教室が再びざわめく。西園寺グループ。日本経済を動かしているとまで言われる、巨大企業体だ。テレビのニュースや新聞でも、その名前を見ない日はない。まさか、とは思う。そんな大企業の令嬢が、こんなごく普通の都立高校に転校してくるなんて、あり得るのだろうか。
全ての視線が、再び彼女に集まる。肯定も否定もせず、西園寺さんはただ、優雅な微笑みを浮かべている。
「皆様のご想像にお任せいたしますわ」
煙に巻くような答え。しかし、その言い方、その雰囲気は、質問に対する何より雄弁な肯定に聞こえた。教室の興奮が、一段と高まるのが肌で感じられる。すごいのが来たぞ、と誰もが思っている。
私だけが、一人、冷めた頭で考えていた。面倒なことになった、と。財閥の令嬢だろうがそうでなかろうが、どちらにしても、彼女は『普通』ではない。彼女がいるだけで、この教室は、私が今まで慣れ親しんできた場所とは違う、何か別のものに変わってしまうだろう。
「えー、まあ、そんなわけだ。席は……そうだな、一番後ろの窓際、鮫島の隣が空いてるな。西園寺、あそこでいいか?」
担任の言葉に、私は自分の耳を疑った。
今、何と。
私の、隣?
そんな、馬鹿な。教室には、他にも空席があったはずだ。どうしてよりによって、一番目立たないこの場所を。私の平穏を守るための、最後の砦とも言うべきこの聖域を。
私が内心の動揺を処理できずにいると、西園寺さんは、こくりと小さく頷いた。そして、ゆっくりとこちらへ向かって歩き始める。その一歩一歩が、私の心の平穏を踏み潰していく音のように聞こえた。
クラス中の視線が、彼女の動きに合わせて移動してくる。その視線が、最終的に私に突き刺さる。やめてくれ。私は見世物じゃない。
西園寺さんは、私の机の横でぴたりと足を止めると、にっこりと微笑みかけてきた。
「これから、よろしくお願いいたしますね」
「……あ、はい。こちらこそ」
かろうじて、それだけを口にするのが精一杯だった。彼女から、ふわりと、品のいい花の香りがした。
これが、全ての始まりだった。私の退屈で、愛おしい日常が、非日常という名の濁流に飲み込まれていく、その序章に過ぎなかったのだ。
◇
西園寺レイカという人間は、私の想像をあらゆる面で超えていた。
彼女は、休み時間になるたびに、クラスの中心にいた。転校初日とは思えないほど、自然に、当たり前のように。男子も女子も、誰もが彼女と話したがった。そして彼女は、どんな相手に対しても、どんな話題に対しても、実に楽しそうに、そして的確に対応してみせた。そのコミュニケーション能力は、もはや芸術の域に達しているとさえ思えた。
財閥の令嬢という立場を鼻にかける様子は微塵もない。むしろ、自分から積極的に輪の中に入っていき、相手の懐にするりと入り込んでしまう。その天真爛漫な明るさは、人を惹きつけてやまない、一種の才能なのだろう。
もちろん、そんな彼女と私が、休み時間に言葉を交わすことはなかった。彼女は常に誰かに囲まれていたし、私も、あえてその輪に加わろうとは思わなかったからだ。それでいい。隣の席になったとはいえ、住む世界が違うのだ。授業中に教科書の貸し借りをする程度の、当たり障りのない関係。それが、私にとっては理想だった。
その理想が、いとも簡単に崩れ去ったのは、昼休みを知らせるチャイムが鳴った直後のことだった。
弁当を持って席を立とうとした私に、背後から声がかかった。
「あの、よろしいでしょうか」
振り返ると、そこには西園寺さんが立っていた。いつの間にか、彼女の周りにいた人だかりは消えている。その手には、生徒名簿らしきファイルが握られていた。
「はい、なんでしょう」
「先ほど、先生があなたのお名前を呼ぶのを聞いて、少し気になったことがございまして」
彼女はそう言うと、ファイルを開き、指で一つの名前を指し示した。そこに書かれていたのは、もちろん私の名前だ。
「あなたは鮫島サヤカさんとおっしゃるのですね?」
「ええ、そうですけど……」
それが何か問題でも、と続けようとした私の言葉は、彼女の次のひと言によって、完全に遮られた。
「……鮫島」
彼女は、私の名字を、まるで貴重な宝石でも口にするかのように、ゆっくりと、そして熱のこもった声で繰り返した。
「やはり、あの『鮫島』なのですね……!」
その瞬間、彼女の雰囲気ががらりと変わった。それまでの優雅で社交的な微笑みは消え、代わりに、瞳の奥に、何かを探求するような、燃え立つような色が浮かんでいる。そのあまりの変化に、私は思わず一歩後ずさった。
「あの……『あの』って、どの……?」
「ご存じないのですか? いえ、ご存じないはずがない。当事者なのですから」
何を言っているんだ、この人は。私の頭の中は、疑問符で埋め尽くされる。当事者? 何の?
私の困惑をよそに、西園寺さんは、まるで長年追い求めていた真理に辿り着いた学者のような口調で、一人語り始めた。
「『鮫島事件』……。ネットロアの中でも特に謎多き事件として語り継がれる、現代の神隠し。その存在は語られるものの、誰もその詳細を知らない。知ろうとすれば、たちまち身に危険が及ぶとされ、多くのネットユーザーが恐怖のうちに口を閉ざしたという、あの伝説の……!」
さめじまじけん。
初めて聞く単語だった。いや、あるいは、どこかで目にしたことがあったのかもしれない。ネットの海を漂っていれば、時折、奇妙な単語に出くわすことはある。けれど、自分の名字が冠された、そんな物騒な事件など、全くもって記憶になかった。
「いや、あの、私、そういうの全然知らなくて……」
「隠す必要はありませんわ。その名字を背負う者として、真実を語りたがらないお気持ちは、痛いほど理解できます。ですが、私は違う。私は、あなたの味方です」
話が全く噛み合っていない。味方だと言われても、何のだというのか。私はただ、この状況からどうやって抜け出すか、そればかりを考えていた。
周りを見ると、教室に残っていた生徒たちが、何事かとこちらを遠巻きに見ている。その視線が、痛い。
「私は長年、この国のあらゆる怪異や都市伝説を研究してまいりました。古くは古事記に記された神々の逸話から、最新のネットロアまで。その中でも、この『鮫島事件』は、私にとって特別な意味を持つ、長年の研究テーマだったのです」
彼女は、うっとりとした表情でそう語る。その瞳は、もう私を見ていなかった。彼女は、彼女自身の作り上げた世界の中で、一人、壮大な物語を紡いでいる。
なるほど。
ようやく、理解した。
この人は、いわゆる『そっち側』の人間なのだ。オカルトとか、都市伝説とか、そういう非科学的なものが、三度のご飯より好きなタイプ。そして、私のありふれた名字を、何か特別なものと結びつけて、勝手に興奮している。
つまり、とてつもなく、面倒くさい。
「まさか、転校したこの場所で、その伝説の中心人物に出会えるなんて……。これはもう、単なる偶然ではありません。ええ、断じて」
彼女は一度言葉を切ると、再び、その熱っぽい視線を私に向けた。そして、私の両手を、有無を言わさぬ力で、がっしと掴んだ。
冷たい、けれど、驚くほど力のこもった手だった。
「これは運命ですわ!」
彼女は、教室中に響き渡るような、朗々とした声で言い放った。
「鮫島サヤカさん! あなたこそ、私が探し求めていた、たった一人の『運命の友』なのです!」
高らかに、それはもう、実に高らかに。まるで舞台役者がクライマックスの台詞を叫ぶかのように。
教室中の視線が、面白いほど綺麗に、私と彼女の二人に集中した。誰もが、何が起こっているのか理解できず、ただ呆然とこちらを見ている。もちろん、私もその一人だ。
運命の友。
その言葉が、私の頭の中で、意味をなさない音の響きとして、ただぐるぐると回り続けていた。
掴まれた両手が、熱い。いや、熱いのは彼女の手か、それとも冷や汗で濡れた私の手か。もう、何も分からなかった。
ただ一つ、確信できることがある。
私の平穏な毎日は、今日、この瞬間、完全に、そして決定的に、終わりを告げたのだ。
目の前で満面の笑みを浮かべる、美しくも迷惑千万なこの転校生によって。
茫然自失の私を置き去りにして、教室は昼休みの喧騒を取り戻していく。周りの生徒たちは、先ほどの劇的な場面を興奮気味に囁き合いながら、ちらちらとこちらに視線を送ってくる。その視線が痛い。
私はただ、自分の席で固まっていた。昼食をとる気力もわかない。そんな私の前に、ふわりと影が落ちた。
「さあ、サヤカ。さっそく友情を深めるために、ご一緒にお昼をいただきましょう」
顔を上げると、そこには西園寺さんが、いつの間にか用意したらしい、ピンクのお弁当箱を手に微笑んでいた。
「あ、いや、私は友達と……」
言い訳を探す私の言葉を遮り、彼女は当然のように私の前の席に腰を下ろした。彼女のお弁当が、机の上に、ことり、と上品な音を立てて置かれる。
「まあ、他人行儀ですわ。どうぞレイカとお呼びくださいな。ね、サヤカ」
ぐい、と顔を寄せられる。今日、何度目かに感じる品のいい花の香りが鼻先をかすめた。近い。物理的にも、精神的にも、彼女は躊躇なくパーソナルスペースに侵入してくる。
「私たちは、運命によって引き合わされた友なのですから。遠慮は無用ですわ」
きらきらとした、一点の曇りもない瞳。その純粋さが、何よりも厄介だった。彼女の中に、悪意や計算といったものが見えれば、まだ対処のしようもある。けれど、彼女は本気で、心の底から、私との間に特別な繋がりがあると信じ込んでいるのだ。善意百パーセントの暴走。それほど、手に負えないものはない。
「……じゃあ、レイカ、さん」
「はい、サヤカ!」
私がようやくそう口にすると、彼女は花が咲くように、ぱあっと表情を輝かせた。そして満足げに頷くと、ぱかり、とお重の蓋を開ける。中には、彩りも鮮やかな、料亭の仕出しと見紛うばかりの料理が、寸分の隙間なく詰められていた。
「どうぞ、遠慮なさらず。……あら、サヤカのお弁当は、とても可愛らしいですわね」
私の、ごく普通の卵焼きとウインナーが入った弁当を覗き込み、彼女は無邪気に微笑む。
「ですが、ご安心くださいな。明日は、私がもっと素晴らしいお弁当を用意してきますわ。サヤカの度肝を抜くような、特別なものを。友情の証です」
その言葉に、私は美味しいお弁当への期待よりも、何か得体の知れない恐怖を感じていた。
結局、私は彼女の勢いに押し切られる形で、レイカさんと昼食を共にすることになった。周囲の席の生徒たちが、好奇と、そして明らかな同情が入り混じった目でこちらを見ているのが分かる。やめてくれ。そんな目で見ないでくれ。私は被害者なんだ。
◇
なんとか、レイカさんとの昼休みが終わり、午後の授業が始まっても、レイカさんの勢いはとどまることを知らなかった。
その日の午後の授業中も、レイカさんからの見えない圧力は続いた。私が少しでも分からないという顔をすれば、すかさず「大丈夫ですか、サヤカ?」と小声で尋ねてくる。私がノートを取る手が止まれば、「ここの部分、私のノートを見ます?」と、完璧に整理されたノートをこちらに見せてくる。その親切の一つ一つが、私にとっては『鮫島事件の当事者』という、身に覚えのない役割を強制されているようで、息が詰まりそうだった。
授業の合間の短い休み時間になれば、状況はさらに悪化する。午前中、彼女の周りにできていた人だかりは、今や私と彼女の二人を中心にして形成されていた。
「レイカさんって、本当にあの西園寺グループのご令嬢なの?」
「サヤカって、レイカさんと昔からの知り合いだったりする?」
質問の矛先は、レイカさんだけでなく、私にも向けられる。そのたびに、私は曖昧に笑って首を振ることしかできない。レイカさんは、そんな私を助けるどころか、むしろ楽しんでいるようにさえ見えた。
「サヤカは私の『特別』なのです。ね?」
そう言って、私の肩に手を置き、にっこりと微笑む。その一言で、周囲の好奇心はさらに燃え上がる。私は、まるで珍しい生き物でも見せられているかのような、居心地の悪さを感じていた。
平穏な日常は、もうどこにもない。私の城は、外からやってきた侵略者によって、完全に占拠されてしまったのだ。