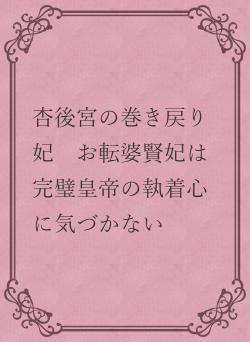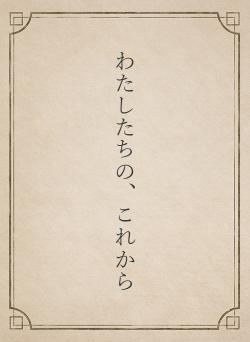その日の夜。
美鈴は、妖の森の入口で立ちすくんでいた。
「どうしましょう」
鬱蒼とした森を見上げ、美鈴の心は暗い気持ちに覆われていた。
日中、大事にしていた鈴のかんざしを理人に捨てられてしまった。
理人の屋敷の執事が妖の森に捨ててきたらしいが、人間はこの森に入ってはならないから、きっとこのあたりの入口から森に向かって投げたのだろう。森の中に入らなくてもすぐに見つかると思っていたのだが、いくら探しても見つからない。
美鈴は、理人との面会が終わるとすぐに森の手前までやってきて、着物が汚れるのもいとわず、地面に這いつくばってかんざしを探していた。
いつのまにか日が暮れていた。
――あとは森の中に入って探すしかないのかしら。
夜はあやかしの活動時間だ。
人間が妖の森に立ち入るのは禁忌とされている。
だが、あのかんざしがないと、美鈴は外に出るのが怖くて仕方がない。それに、大事な人にもらった大事な思い出の品を諦めたくない。
美鈴は恐怖で震える足を叱咤して、一歩を踏み出した。
静寂に包まれた森に、ふくろうの鳴き声が響きわたる。
森の中は外から見て想像していたとおり四方に草木が生い茂っていた。だが、石が敷き詰められた一本道が作られていて、草履でも思っていたより楽に歩ける。
この森に来たのは、幼いころに迷い込んでしまったとき以来だ。あのときのことは覚えていないのだが、あやかしの甘言に乗せられてかなり奥深くまで歩いていってしまい、あちらとこちらの世界の境目まで行ってしまった。
あのお方が助けてくれなければ、いまごろ美鈴の命はなかっただろう。
それにしても、あのお方はどうしてこんな森の奥にいたのだろうか。人間の男性だとずっと思い込んでいたけれど、よく考えると親切なあやかしだった可能性もある。
地面に目を凝らしながらしばらく歩いてみるも、幸いなことにあやかしと遭遇することはなかった。
しかしかんざしは見つからない。
そもそも、街灯の明かりもない暗闇で、小さなかんざしを見つけるのは至難の業だ。
美鈴は、妖の森の入口で立ちすくんでいた。
「どうしましょう」
鬱蒼とした森を見上げ、美鈴の心は暗い気持ちに覆われていた。
日中、大事にしていた鈴のかんざしを理人に捨てられてしまった。
理人の屋敷の執事が妖の森に捨ててきたらしいが、人間はこの森に入ってはならないから、きっとこのあたりの入口から森に向かって投げたのだろう。森の中に入らなくてもすぐに見つかると思っていたのだが、いくら探しても見つからない。
美鈴は、理人との面会が終わるとすぐに森の手前までやってきて、着物が汚れるのもいとわず、地面に這いつくばってかんざしを探していた。
いつのまにか日が暮れていた。
――あとは森の中に入って探すしかないのかしら。
夜はあやかしの活動時間だ。
人間が妖の森に立ち入るのは禁忌とされている。
だが、あのかんざしがないと、美鈴は外に出るのが怖くて仕方がない。それに、大事な人にもらった大事な思い出の品を諦めたくない。
美鈴は恐怖で震える足を叱咤して、一歩を踏み出した。
静寂に包まれた森に、ふくろうの鳴き声が響きわたる。
森の中は外から見て想像していたとおり四方に草木が生い茂っていた。だが、石が敷き詰められた一本道が作られていて、草履でも思っていたより楽に歩ける。
この森に来たのは、幼いころに迷い込んでしまったとき以来だ。あのときのことは覚えていないのだが、あやかしの甘言に乗せられてかなり奥深くまで歩いていってしまい、あちらとこちらの世界の境目まで行ってしまった。
あのお方が助けてくれなければ、いまごろ美鈴の命はなかっただろう。
それにしても、あのお方はどうしてこんな森の奥にいたのだろうか。人間の男性だとずっと思い込んでいたけれど、よく考えると親切なあやかしだった可能性もある。
地面に目を凝らしながらしばらく歩いてみるも、幸いなことにあやかしと遭遇することはなかった。
しかしかんざしは見つからない。
そもそも、街灯の明かりもない暗闇で、小さなかんざしを見つけるのは至難の業だ。