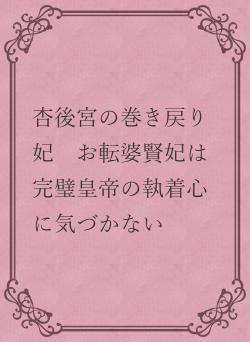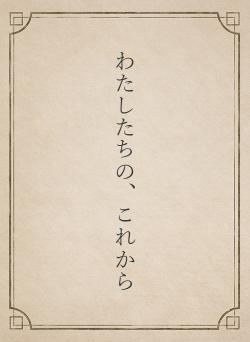『おじょうちゃん、かわいいかんざしをつけているね』
うしろから声をかけられ、背筋に冷たいものが走る。
あやかしの声だ。
美鈴は思わず振り返りそうになるのを、すんでのところでとどまる。だめだとわかっていても振り返ってしまいそうになるような、なんとも言えない魅惑的な声なのだ。
『あれぇ、おじょうちゃん。わしの声が聞こえているんじゃぁないかい』
通常、鷹羽家の人間のように陰陽師の力を持っていないと、あやかしを見ることはできない。
しかし、たとえ見えなくても、あやかしの声が人間の頭に響くことがある。意味のわからない言語のはずなのに、なぜだか急に言葉が輪郭を持って頭に流れ込んでくるのだ。
そういうときに、決してあやかしの声に反応してはいけない。この国の人間が呼ぶところの「あちらの世界」、つまりあやかしの世界に連れていかれてしまうからだ。
人間とあやかしは会話をすることができないと言われている。しかし、鷹羽家で無能と蔑まれている美鈴は、実はあやかしの言語を理解し、かれらと対話する能力を持っていた。
あやかしと対話することができるとはいえ、むやみにしゃべることは危険だ。かれらは気まぐれだ。心を開いてくれたと思ったら、鋭いかぎづめで四肢を切り裂いてくることもある。知らないうちにあちらの世界に連れていかれるかもしれない。
あやかしは人の理解の外にいる存在。
だから、美鈴はこの能力を使わないように心がけていた。
あやかしを祓う力は持たず、特殊な力を持って生まれた美鈴。そのせいかわからないが、幼いころから大小さまざまなあやかしにいたずらをされていた。
この力は亡くなった母以外は知らない。母曰く、会話するだけではなく、あやかしを引き寄せる能力があるのかもしれないそうだ。
陰陽師の力を持たない母には、あやかしは見えない。だから、母が言っていたことが本当かもわからない。
無心で雑踏をかき分けていると、いつの間にかあやかしの声は聞こえなくなっていた。
知らぬ間に息をするのも忘れていたようで、心臓がばくばくと音を立てている。美鈴は大きなため息をついた。
鈴のかんざしにそっと手を添える。このかんざしは、幼いころ、こちらとあちらの狭間に迷い込んだときに、助けてくれた人がくれたものだ。
『これを身につけていれば、あやかしが近づいてくることはない』
年々効力が薄まっているが、たしかにかんざしを挿していると、いまでも弱いあやかしなら近寄ってこない。
――守ってくださってありがとうございます。
幼いころのことで記憶はあやふやだが、たしか濡れ羽色の髪と深紅の瞳の背の高い男性だった。その人は、すぐにいなくなってしまった。
せめて名前を聞いておけばよかった。お礼を言えなかったことがいまでも心残りだった。
うしろから声をかけられ、背筋に冷たいものが走る。
あやかしの声だ。
美鈴は思わず振り返りそうになるのを、すんでのところでとどまる。だめだとわかっていても振り返ってしまいそうになるような、なんとも言えない魅惑的な声なのだ。
『あれぇ、おじょうちゃん。わしの声が聞こえているんじゃぁないかい』
通常、鷹羽家の人間のように陰陽師の力を持っていないと、あやかしを見ることはできない。
しかし、たとえ見えなくても、あやかしの声が人間の頭に響くことがある。意味のわからない言語のはずなのに、なぜだか急に言葉が輪郭を持って頭に流れ込んでくるのだ。
そういうときに、決してあやかしの声に反応してはいけない。この国の人間が呼ぶところの「あちらの世界」、つまりあやかしの世界に連れていかれてしまうからだ。
人間とあやかしは会話をすることができないと言われている。しかし、鷹羽家で無能と蔑まれている美鈴は、実はあやかしの言語を理解し、かれらと対話する能力を持っていた。
あやかしと対話することができるとはいえ、むやみにしゃべることは危険だ。かれらは気まぐれだ。心を開いてくれたと思ったら、鋭いかぎづめで四肢を切り裂いてくることもある。知らないうちにあちらの世界に連れていかれるかもしれない。
あやかしは人の理解の外にいる存在。
だから、美鈴はこの能力を使わないように心がけていた。
あやかしを祓う力は持たず、特殊な力を持って生まれた美鈴。そのせいかわからないが、幼いころから大小さまざまなあやかしにいたずらをされていた。
この力は亡くなった母以外は知らない。母曰く、会話するだけではなく、あやかしを引き寄せる能力があるのかもしれないそうだ。
陰陽師の力を持たない母には、あやかしは見えない。だから、母が言っていたことが本当かもわからない。
無心で雑踏をかき分けていると、いつの間にかあやかしの声は聞こえなくなっていた。
知らぬ間に息をするのも忘れていたようで、心臓がばくばくと音を立てている。美鈴は大きなため息をついた。
鈴のかんざしにそっと手を添える。このかんざしは、幼いころ、こちらとあちらの狭間に迷い込んだときに、助けてくれた人がくれたものだ。
『これを身につけていれば、あやかしが近づいてくることはない』
年々効力が薄まっているが、たしかにかんざしを挿していると、いまでも弱いあやかしなら近寄ってこない。
――守ってくださってありがとうございます。
幼いころのことで記憶はあやふやだが、たしか濡れ羽色の髪と深紅の瞳の背の高い男性だった。その人は、すぐにいなくなってしまった。
せめて名前を聞いておけばよかった。お礼を言えなかったことがいまでも心残りだった。