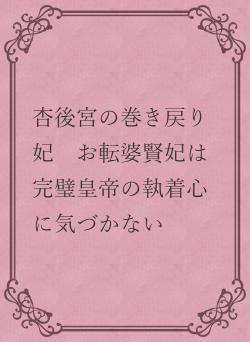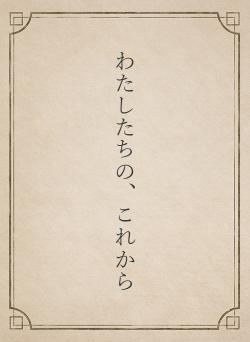妹のわがままをやりすごした美鈴は、許嫁である理人の家に向かっていた。
寿香に足止めをされたせいで、予定より屋敷を出るのが遅くなってしまった。もちろん家の馬車を使うことは許されていないし、路面電車に乗るお金も持っていない。歩いて三十分ほどの道のりを、美鈴は小走りで急ぐ。
午後の帝都は、人々で賑わっていた。
学校帰りの女学生の群れ、買い物帰りの町娘、新聞を小脇に急ぐスーツの男性。それらの人の群れを縫うように、石造りの地面を軽やかに蹴って進む。
――慌てて身支度してきたけれど、大丈夫かしら。
ちらりと自分の服装に目を向ける。
帝都の婦女子の間では昨今、洋装が流行していた。ワンピースやロングスカートをおしゃれに着こなす娘たちを横目に、美鈴は肩を落とす。
洋服を買うお金はもちろんない。父や義母が買い与えてくれることもない。
美鈴は母が遺した数少ない着物を大事に着まわしていた。今日は五月の帝都の涼しい気候に合わせて、縹色のさわやかな色合いの着物を選んだ。髪はハーフアップにして、いつも外出する際につけている鈴のかんざしを挿している。美鈴が歩くたびに、ちりんちりんと涼やかな音が響く。
久しぶりに許嫁と会うことに緊張しながら歩いていた美鈴は、ふといやな気配を感じて足を止めた。
人ならざるもののにおい――たとえるなら獣のようなにおいがあたりに立ち込める。
あやかしの気配だ。
周囲にあやかしが見える人はいないようで、誰も気づいていない。人々のかしましいおしゃべりが響く帝都で一人、美鈴は目を閉じて深呼吸をする。
無意識のうちに鈴のかんざしに触れていた。
――大丈夫よ。あのお方が守ってくれる。
そのとき。
寿香に足止めをされたせいで、予定より屋敷を出るのが遅くなってしまった。もちろん家の馬車を使うことは許されていないし、路面電車に乗るお金も持っていない。歩いて三十分ほどの道のりを、美鈴は小走りで急ぐ。
午後の帝都は、人々で賑わっていた。
学校帰りの女学生の群れ、買い物帰りの町娘、新聞を小脇に急ぐスーツの男性。それらの人の群れを縫うように、石造りの地面を軽やかに蹴って進む。
――慌てて身支度してきたけれど、大丈夫かしら。
ちらりと自分の服装に目を向ける。
帝都の婦女子の間では昨今、洋装が流行していた。ワンピースやロングスカートをおしゃれに着こなす娘たちを横目に、美鈴は肩を落とす。
洋服を買うお金はもちろんない。父や義母が買い与えてくれることもない。
美鈴は母が遺した数少ない着物を大事に着まわしていた。今日は五月の帝都の涼しい気候に合わせて、縹色のさわやかな色合いの着物を選んだ。髪はハーフアップにして、いつも外出する際につけている鈴のかんざしを挿している。美鈴が歩くたびに、ちりんちりんと涼やかな音が響く。
久しぶりに許嫁と会うことに緊張しながら歩いていた美鈴は、ふといやな気配を感じて足を止めた。
人ならざるもののにおい――たとえるなら獣のようなにおいがあたりに立ち込める。
あやかしの気配だ。
周囲にあやかしが見える人はいないようで、誰も気づいていない。人々のかしましいおしゃべりが響く帝都で一人、美鈴は目を閉じて深呼吸をする。
無意識のうちに鈴のかんざしに触れていた。
――大丈夫よ。あのお方が守ってくれる。
そのとき。