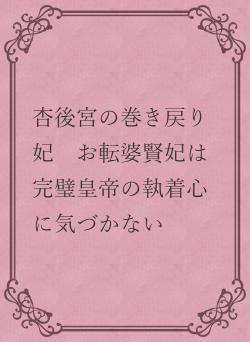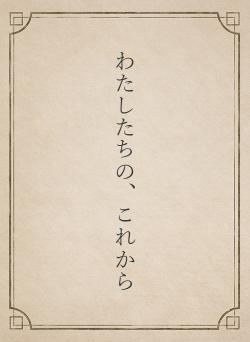目が覚めると、自室の布団の上だった。
右手が温かいような気がして目を向けると、朔太郎に手を握られていた。顔はいつも以上に白く、額には汗が滲んでいる。その隣には百が丸まっていた。
「……統領さま」
か細い声に気づいた朔太郎は、はっとして美鈴を見た。
「具合はどうだ」
「大丈夫です。ご心配をおかけしました」
朔太郎に手伝ってもらい、体を起こす。近ごろ体調不良が続いていたが、またみなに心配をかけてしまい申し訳ない気持ちになる。
膝の上に乗ってきた百を撫でながら早く回復しなければと思っていると、いちとはつが戸を開けて入ってきた。
「ご懐妊ですわ」
「おめでとうございますわ」
「え……?」
――懐妊……?
おずおずと自分の腹を触ってみるが、着物越しにほんのりと温かい人肌が伝わってくる以外はなにも感じない。信じられない思いで朔太郎に目を向けると、ゆっくりとうなずかれる。
「これで美鈴の妖力も安定するはずだ」
「どういうことでしょうか」
「あやかしは人間と交わることで、人間の妖力を吸い取ることができる。きみの体は大量の妖力を持て余していたから、体に収まりきらない妖力を毎夜吸い取って、体に負担がかからないように調整していた」
朔太郎の寝室を訪れたあの日以来、寝室は一緒の部屋を使うようになった。たしかに妻の務めも果たしていたが……
「毎夜ですって!」
「まあ!」
いちとはつがきゃあきゃあと騒ぎはじめ、美鈴はカッと顔が熱くなる。
百を撫でる手が強くなってしまい、「痛いのじゃ」と手をはたかれてしまう。
「あ、あの、交わるというのは」
「体液の交換だ。接吻でも、せ――」
淡々と説明しようとする朔太郎の声を、大声を出して遮った。いちとはつ、それに百がいるのになんてことを言おうとしているのだ。朔太郎は目を丸くしていたが、真面目な顔で「体に障るぞ」と告げてきた。
ぼんやりしていた頭が冴えると、ふと先ほどの理人の言葉を思い出す。どう切り出そうか迷っていると、朔太郎に「どうした」と問われる。
美鈴は、寿香の懐妊が嘘だったことや、鷹羽家がこの森に攻めてくるという話を説明した。
右手が温かいような気がして目を向けると、朔太郎に手を握られていた。顔はいつも以上に白く、額には汗が滲んでいる。その隣には百が丸まっていた。
「……統領さま」
か細い声に気づいた朔太郎は、はっとして美鈴を見た。
「具合はどうだ」
「大丈夫です。ご心配をおかけしました」
朔太郎に手伝ってもらい、体を起こす。近ごろ体調不良が続いていたが、またみなに心配をかけてしまい申し訳ない気持ちになる。
膝の上に乗ってきた百を撫でながら早く回復しなければと思っていると、いちとはつが戸を開けて入ってきた。
「ご懐妊ですわ」
「おめでとうございますわ」
「え……?」
――懐妊……?
おずおずと自分の腹を触ってみるが、着物越しにほんのりと温かい人肌が伝わってくる以外はなにも感じない。信じられない思いで朔太郎に目を向けると、ゆっくりとうなずかれる。
「これで美鈴の妖力も安定するはずだ」
「どういうことでしょうか」
「あやかしは人間と交わることで、人間の妖力を吸い取ることができる。きみの体は大量の妖力を持て余していたから、体に収まりきらない妖力を毎夜吸い取って、体に負担がかからないように調整していた」
朔太郎の寝室を訪れたあの日以来、寝室は一緒の部屋を使うようになった。たしかに妻の務めも果たしていたが……
「毎夜ですって!」
「まあ!」
いちとはつがきゃあきゃあと騒ぎはじめ、美鈴はカッと顔が熱くなる。
百を撫でる手が強くなってしまい、「痛いのじゃ」と手をはたかれてしまう。
「あ、あの、交わるというのは」
「体液の交換だ。接吻でも、せ――」
淡々と説明しようとする朔太郎の声を、大声を出して遮った。いちとはつ、それに百がいるのになんてことを言おうとしているのだ。朔太郎は目を丸くしていたが、真面目な顔で「体に障るぞ」と告げてきた。
ぼんやりしていた頭が冴えると、ふと先ほどの理人の言葉を思い出す。どう切り出そうか迷っていると、朔太郎に「どうした」と問われる。
美鈴は、寿香の懐妊が嘘だったことや、鷹羽家がこの森に攻めてくるという話を説明した。