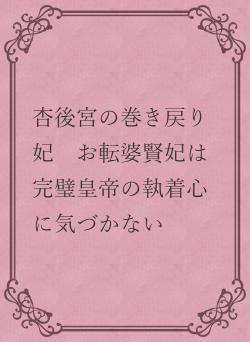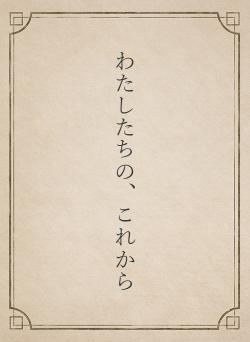それから、朔太郎はぽつりぽつりと言葉を紡いだ。
いつしか美鈴を見守ることが日課になっていたこと。あやかしという立場上、鷹羽家で虐げられる美鈴を助けることができなくて歯がゆい思いをしていたこと。許嫁がいると知り、悲嘆にくれたこと。許嫁が幸せにしてくれればよいと自分を納得させたのもつかの間、彼が不貞を働いていると知ったこと。そして、許嫁との関係がなくなったときには、自分が一番に迎えようと思っていたこと。
「ずっと前からきみに惹かれていた」
畳を見つめながらしゃべっていた朔太郎は、そう言うと顔をあげた。穏やかな顔で見つめられ、美鈴は胸が高鳴る。美鈴としては、日常の些細な感情の変化を教えてもらえればよかったのだが、思っていなかった展開になり、鼓動が速くなる。
朔太郎はふと顔を逸らすと、「もういいだろう」とつぶやいた。よく見ると耳がほんのり朱色に染まっている。
「ほかになにか聞きたいことはあるか」
「い、いえ、ございません」
美鈴がここにいることは、朔太郎が望んでいたことだった。
どうしたら役に立てるのかはわからないが、自分の存在を受け入れてもらえていることを言葉で知ることができただけで、美鈴は言いようのない充足感を覚えていた。
安心すると、急に眠気が襲ってくる。そういえば、いつもならとっくに眠っている時間だ。
美鈴がうつらうつらしていると、朔太郎はふと口を開いた。
「ここで眠っていくか」
「よろしいのですか」
「ああ、布団は一組しかないから、きみさえいやでなければだが」
朔太郎はそう言うと、乱暴に髪をかきあげる。そのしぐさが妙に艶っぽくて、美鈴はどきりとする。
すっかり忘れていたが、夜半に夫婦が寝室に二人きり。じわじわと頬が熱くなる。
でも、美鈴はいまのこの満ち足りた気持ちにもう少し浸っていたかった。
「いやではございません。わたしたちは、その、夫婦なのですから……」
恥じらう気持ちを精一杯隠して朔太郎を見上げると、ふっと微笑まれる。
「おいで」
朔太郎の腕の中にすっぽりと収まる。
耳を澄ますと、わずかに心臓の音が聞こえてくる。
――わたしと同じで、少し早いわ。
人間とあやかし。種族間の越えられない壁はこれからも訪れるのだろうが、こうやっていると同じ生き物なのだと安心できる。
白檀の香りに包まれながら、美鈴は目を閉じた。
いつしか美鈴を見守ることが日課になっていたこと。あやかしという立場上、鷹羽家で虐げられる美鈴を助けることができなくて歯がゆい思いをしていたこと。許嫁がいると知り、悲嘆にくれたこと。許嫁が幸せにしてくれればよいと自分を納得させたのもつかの間、彼が不貞を働いていると知ったこと。そして、許嫁との関係がなくなったときには、自分が一番に迎えようと思っていたこと。
「ずっと前からきみに惹かれていた」
畳を見つめながらしゃべっていた朔太郎は、そう言うと顔をあげた。穏やかな顔で見つめられ、美鈴は胸が高鳴る。美鈴としては、日常の些細な感情の変化を教えてもらえればよかったのだが、思っていなかった展開になり、鼓動が速くなる。
朔太郎はふと顔を逸らすと、「もういいだろう」とつぶやいた。よく見ると耳がほんのり朱色に染まっている。
「ほかになにか聞きたいことはあるか」
「い、いえ、ございません」
美鈴がここにいることは、朔太郎が望んでいたことだった。
どうしたら役に立てるのかはわからないが、自分の存在を受け入れてもらえていることを言葉で知ることができただけで、美鈴は言いようのない充足感を覚えていた。
安心すると、急に眠気が襲ってくる。そういえば、いつもならとっくに眠っている時間だ。
美鈴がうつらうつらしていると、朔太郎はふと口を開いた。
「ここで眠っていくか」
「よろしいのですか」
「ああ、布団は一組しかないから、きみさえいやでなければだが」
朔太郎はそう言うと、乱暴に髪をかきあげる。そのしぐさが妙に艶っぽくて、美鈴はどきりとする。
すっかり忘れていたが、夜半に夫婦が寝室に二人きり。じわじわと頬が熱くなる。
でも、美鈴はいまのこの満ち足りた気持ちにもう少し浸っていたかった。
「いやではございません。わたしたちは、その、夫婦なのですから……」
恥じらう気持ちを精一杯隠して朔太郎を見上げると、ふっと微笑まれる。
「おいで」
朔太郎の腕の中にすっぽりと収まる。
耳を澄ますと、わずかに心臓の音が聞こえてくる。
――わたしと同じで、少し早いわ。
人間とあやかし。種族間の越えられない壁はこれからも訪れるのだろうが、こうやっていると同じ生き物なのだと安心できる。
白檀の香りに包まれながら、美鈴は目を閉じた。