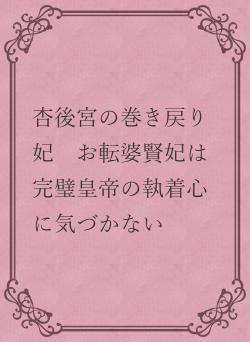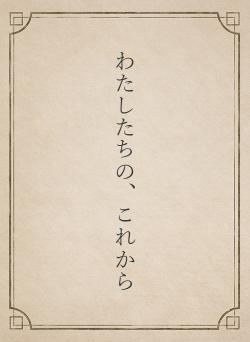あくる日の午後。
窓から差し込む日差しが心地よい。日なたで百が昼寝をしているのを横目に、美鈴は窓の掃除に励んでいた。いちとはつも近くを掃除している。美鈴は、近ごろ考えていたことを二人に相談することにした。
「ねえ、いちとはつ」
「なんでしょう、美鈴さま」
「あのね。わたし、統領さまのことをもっと知りたいの」
窓を拭いていた手を止め、意を決してそう言う。
こわごわといちとはつの様子をうかがうと、二人とも目を見合わせて興奮気味に手をたたいた。
「それなら妙案がありますわ!」
「ありますの!」
「な、なにかしら」
いちとはつはそう叫ぶと、駆け寄ってきて美鈴の手をとった。
二人の勢いに圧され、美鈴はのけぞる。
「夜遅い時間に、統領さまの寝室におじゃましてみればいいのです」
「そうですわ!」
美鈴は二人の言いたいことがわからず、首をかしげる。
そんな美鈴にかまうことなく、二人は説明を続ける。
「本日の夜、統領さまはいつもより早くお帰りになる予定ですわ」
「ですわ」
「でも、寝る前におじゃまなんてしてしまったら、ご迷惑じゃないかしら。そもそも統領さまはわたしが夜中まで起きていることをよく思わないご様子だし」
統領の仕事で忙しい朔太郎は、夜遅い時間に帰ってくることが多い。朔太郎が帰宅していなくても、美鈴は遠慮なく寝るように言われていた。
家主より先に寝るなんて申し訳ない気持ちでいっぱいだが、一度、言いつけを破って玄関で迎えたところとんでもなく機嫌が悪くなったので、それ以来守るようにしている。
あのときの朔太郎の表情は一生忘れないだろう。いつも無表情な彼だが、怒ると鬼のように眉を吊り上げ、深く深くため息をつくのだ。これが怒ったときの彼なのだと美鈴は胸に刻んだ。
「美鈴さまなら大丈夫ですわ。いちと」
「はつが保証いたしますわ」
「そ、そう……?」
いちとはつは胸を叩いてにかっと笑う。
困惑して目をそらすと、騒がしかったのか、寝ていたはずの百が毛づくろいをしていた。美鈴の不安な気持ちなどまったく気にせず、あくびをしている。
百はつまらなそうに口を開いた。
「よくわからないが、統領さまに会いたいなら、会えるときに部屋に行ってみればいいのじゃ」
ずっと寝ていたのでこちらの話は聞いていないと思っていた。
驚きつつも、美鈴は「たしかにそうね」と返事をした。
窓から差し込む日差しが心地よい。日なたで百が昼寝をしているのを横目に、美鈴は窓の掃除に励んでいた。いちとはつも近くを掃除している。美鈴は、近ごろ考えていたことを二人に相談することにした。
「ねえ、いちとはつ」
「なんでしょう、美鈴さま」
「あのね。わたし、統領さまのことをもっと知りたいの」
窓を拭いていた手を止め、意を決してそう言う。
こわごわといちとはつの様子をうかがうと、二人とも目を見合わせて興奮気味に手をたたいた。
「それなら妙案がありますわ!」
「ありますの!」
「な、なにかしら」
いちとはつはそう叫ぶと、駆け寄ってきて美鈴の手をとった。
二人の勢いに圧され、美鈴はのけぞる。
「夜遅い時間に、統領さまの寝室におじゃましてみればいいのです」
「そうですわ!」
美鈴は二人の言いたいことがわからず、首をかしげる。
そんな美鈴にかまうことなく、二人は説明を続ける。
「本日の夜、統領さまはいつもより早くお帰りになる予定ですわ」
「ですわ」
「でも、寝る前におじゃまなんてしてしまったら、ご迷惑じゃないかしら。そもそも統領さまはわたしが夜中まで起きていることをよく思わないご様子だし」
統領の仕事で忙しい朔太郎は、夜遅い時間に帰ってくることが多い。朔太郎が帰宅していなくても、美鈴は遠慮なく寝るように言われていた。
家主より先に寝るなんて申し訳ない気持ちでいっぱいだが、一度、言いつけを破って玄関で迎えたところとんでもなく機嫌が悪くなったので、それ以来守るようにしている。
あのときの朔太郎の表情は一生忘れないだろう。いつも無表情な彼だが、怒ると鬼のように眉を吊り上げ、深く深くため息をつくのだ。これが怒ったときの彼なのだと美鈴は胸に刻んだ。
「美鈴さまなら大丈夫ですわ。いちと」
「はつが保証いたしますわ」
「そ、そう……?」
いちとはつは胸を叩いてにかっと笑う。
困惑して目をそらすと、騒がしかったのか、寝ていたはずの百が毛づくろいをしていた。美鈴の不安な気持ちなどまったく気にせず、あくびをしている。
百はつまらなそうに口を開いた。
「よくわからないが、統領さまに会いたいなら、会えるときに部屋に行ってみればいいのじゃ」
ずっと寝ていたのでこちらの話は聞いていないと思っていた。
驚きつつも、美鈴は「たしかにそうね」と返事をした。