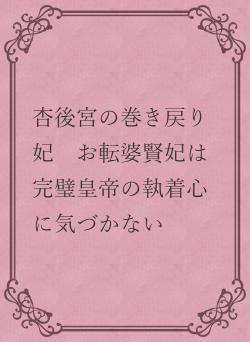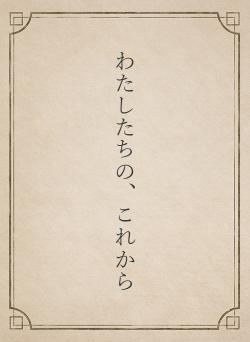「うまいぞ」
「……よかったです」
朔太郎に褒められ、心がほんのり温かくなる。美鈴も口をつけてみると悪くない味で、がんばって用意した甲斐があったと満足感を覚える。
「これも美鈴がつくったのか」
「はい」
「きのうの朝餉もきみが作ったのだろう」
美鈴はぱっと顔をあげる。
「どうしておわかりになったのですか」
「いちとはつがつくったことのない献立だった。鱧の吸い物がとくにうまかった」
――やっぱりこの人は怖い人じゃないわ。
口下手で顔に感情がでないだけで、よく周りを見ている。
「ありがとうございます」
忙しい朔太郎とかぎられた時間で交流をするなかで、美鈴は彼のことをもっと知りたいと思うようになっていた。
朔太郎は不器用ながらも優しい人だ。
いつも美鈴が不自由をしていないか気にかけてくれる。
でも、美鈴だって朔太郎のことを知り、少しくらいは支えになりたいと思っている。
「……よかったです」
朔太郎に褒められ、心がほんのり温かくなる。美鈴も口をつけてみると悪くない味で、がんばって用意した甲斐があったと満足感を覚える。
「これも美鈴がつくったのか」
「はい」
「きのうの朝餉もきみが作ったのだろう」
美鈴はぱっと顔をあげる。
「どうしておわかりになったのですか」
「いちとはつがつくったことのない献立だった。鱧の吸い物がとくにうまかった」
――やっぱりこの人は怖い人じゃないわ。
口下手で顔に感情がでないだけで、よく周りを見ている。
「ありがとうございます」
忙しい朔太郎とかぎられた時間で交流をするなかで、美鈴は彼のことをもっと知りたいと思うようになっていた。
朔太郎は不器用ながらも優しい人だ。
いつも美鈴が不自由をしていないか気にかけてくれる。
でも、美鈴だって朔太郎のことを知り、少しくらいは支えになりたいと思っている。