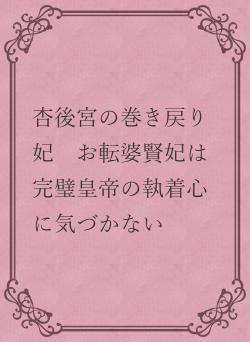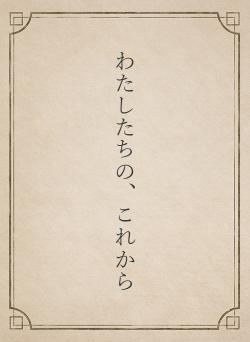理不尽に殴られることもなく、いきなり𠮟責が飛んでくることもなく、これまでの人生が嘘のように穏やかな日々が続いていた。
あやかしの妻になるという信じられない事態が起こっているものの、厳しい環境に身を置いていた美鈴にとっては、平和な環境に感謝しこそすれ、ここを出ていきたいなどと思うことは断じてなかった。
ただ毎日、いちとはつの仕事を手伝ったり、百と遊んだりして過ごしている。屋敷にはいちとはつ以外のあやかしは住んでいないらしく、日々の家事はかなり大変なのだそうだ。
ちなみに、百は猫のように気まぐれなあやかしだから、調子のいいときしか手伝おうとしない。
今日も美鈴は、いちとはつとともに台所に立ち、夕餉をつくっていた。
久しぶりに早く帰ってきた朔太郎に夕食の準備ができたことを伝えにいく。自室で難しい顔をして書物を読んでいた朔太郎は、美鈴の存在に気づくと顔をあげた。
「お夕飯ができました」
「ああ、いま行く」
――なにを読んでいたのかしら。
怖い顔をしていても怒っているわけではなく、だいたいのことは聞けば教えてくれる。
しばらくともに生活をしてみて朔太郎の性格をなんとなく把握したものの、やはりなんでもかんでも質問するのは悪いと思って遠慮していた。向こうの口数の少なさに合わせなければならない。
ただ、知りたい気持ちだけが募っていく。
二人で食卓を囲み、静かな時間を過ごす。
朔太郎が夏野菜の揚げびたしに手を伸ばしたとき、美鈴は思わず「あっ」と言ってしまった。
「どうした」
「あ、いえ、その……」
揚げびたしは美鈴がつくったものだった。
毎日忙しく過ごす朔太郎は、あやかしとはいえ疲れているだろう。そんな彼のために、さっぱりと食べられて体にいいものを提供したいと、いちとはつに相談していたのだ。
二人とも「統領さまも喜んでくださりますわ」と言ってくれたのだが……
あやかしの妻になるという信じられない事態が起こっているものの、厳しい環境に身を置いていた美鈴にとっては、平和な環境に感謝しこそすれ、ここを出ていきたいなどと思うことは断じてなかった。
ただ毎日、いちとはつの仕事を手伝ったり、百と遊んだりして過ごしている。屋敷にはいちとはつ以外のあやかしは住んでいないらしく、日々の家事はかなり大変なのだそうだ。
ちなみに、百は猫のように気まぐれなあやかしだから、調子のいいときしか手伝おうとしない。
今日も美鈴は、いちとはつとともに台所に立ち、夕餉をつくっていた。
久しぶりに早く帰ってきた朔太郎に夕食の準備ができたことを伝えにいく。自室で難しい顔をして書物を読んでいた朔太郎は、美鈴の存在に気づくと顔をあげた。
「お夕飯ができました」
「ああ、いま行く」
――なにを読んでいたのかしら。
怖い顔をしていても怒っているわけではなく、だいたいのことは聞けば教えてくれる。
しばらくともに生活をしてみて朔太郎の性格をなんとなく把握したものの、やはりなんでもかんでも質問するのは悪いと思って遠慮していた。向こうの口数の少なさに合わせなければならない。
ただ、知りたい気持ちだけが募っていく。
二人で食卓を囲み、静かな時間を過ごす。
朔太郎が夏野菜の揚げびたしに手を伸ばしたとき、美鈴は思わず「あっ」と言ってしまった。
「どうした」
「あ、いえ、その……」
揚げびたしは美鈴がつくったものだった。
毎日忙しく過ごす朔太郎は、あやかしとはいえ疲れているだろう。そんな彼のために、さっぱりと食べられて体にいいものを提供したいと、いちとはつに相談していたのだ。
二人とも「統領さまも喜んでくださりますわ」と言ってくれたのだが……