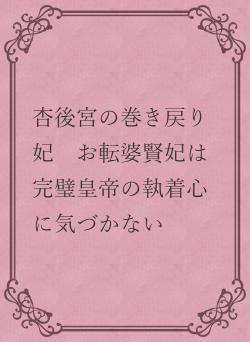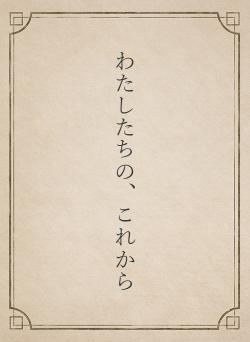「で、なにを言いたかったのだろうか」
朔太郎の部屋で向かい合い、いちとはつが持ってきた夕餉をつまんでいると、唐突にそう問われた。
「はい?」
「なにか言いたいことがあったのだろう。だから玄関まで迎えにきてくれたのだと思ったのだが」
間違いではないのだが、正解でもない。
美鈴はただ、朔太郎の顔が見たくて、彼が帰ってきたと知るや否や玄関まで走ったのだ。
――近ごろのわたし、変ね。
心のなかで考えごとをしていると、朔太郎の目線を感じて顔をあげる。
美鈴は箸を置いて、姿勢を正した。
「お礼をお伝えしたくて」
「礼?」
「昔このかんざしをくださったのは、統領さまですよね」
懐に忍ばせていた鈴のかんざしを取り出す。
朔太郎はかんざしを一瞥すると、気まずそうに目をそらしてつぶやいた。
「……とうに忘れられていると思っていた」
「ようやくお会いできました。お名前をおうかがいするのを忘れて、お礼が遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。このかんざしのおかげで、悪いあやかしにいたずらされることが減ってずいぶん楽になったんです」
「完全になくなりはしなかっただろう」
「はい?」
朔太郎の声がよく聞こえず、美鈴は聞き返す。
「いや、なんでもない」
「お部屋もお食事もお着物も、ありがとうございます。その、わたしなんかにどうしてここまで――」
「それは、美鈴は私の妻になったのだから当然のことだろう」
「つ、妻……!?」
すっとんきょうな声が静かな夜の屋敷に響く。美鈴は慌てて口を押さえた。
たしかに好待遇すぎて戸惑ってはいたが、そんな話になっているなんて思いもしなかった。いちもはつもなにも言ってこないから、ただただ好意にあまえていたのだ。
美鈴が目を白黒させていると、朔太郎は不満げに眉をひそめた。
――よく見ると感情がわかりやすい方……ってそうじゃなくて。
「どういうことでしょうか」
「なにをそんなに驚いているのだ。あやかしの手をとるということはそういうことだ」
思ってもみなかった事態になっていて、頭が追いつかない。ただただ相槌を打つことしかできない。ぼんやりしていると、朔太郎が追い打ちをかけるように「そもそも」と言った。
「あんな男と共になるくらいなら攫ってしまおうと何度思ったことか。だが、人が定めた決まりごとにあやかしは立ち入ることはできない。だから、許嫁という関係が壊れるのを待っていたのだ」
「待っていたって……」
「あの日から、ずっと美鈴を見守っていた」
朔太郎は居住まいを正して、正面から美鈴を見据える。
「先日は鷹羽の屋敷に美鈴を迎えにいくだけだったのだが、あやかしを数名連れていったせいで騒ぎになってしまった。襲撃するつもりは断じてなかった。ただ、陰陽師の攻撃を防御したつもりが、少し力が強すぎて危害を加えてしまったかもしれない……誰も死んでいないはずだが」
昨今の平和な世では、陰陽師が実戦経験を積む場はなかなかないらしいが、それでも歴史ある鷹羽家の人間だ。
義妹や家の人間が、血反吐を吐きながら厳しい鍛錬に明け暮れているのを知っている。幼いころはこっそり道場の裏手に忍び込み、うらやましかったり、妬ましかったり、自分が情けなかったり、さまざまな気持ちを抱きながら、鍛錬の様子を眺めていた。
あやかしと戦にでもならないかぎりは、死ぬことはないだろう。
そんなことを考えていると、朔太郎の視線を感じて顔をあげる。真剣な瞳で見つめられ、美鈴は背筋を伸ばす。
「いやだったか?」
「い、いいえ」
「ならよかった」
朔太郎は心底ほっとしたように微笑んだ。
――はじめて笑ってくださったわ。
思っていたような冷たい方ではなかったし、ずいぶん強引だけど、美鈴はまったくもっていやではなかった。
朔太郎は言いたいことを言い終えたのか、黙々と食事をしている。美鈴はふたたび訪れた静かな時間に安心感を覚え、箸をとったのだった。
朔太郎の部屋で向かい合い、いちとはつが持ってきた夕餉をつまんでいると、唐突にそう問われた。
「はい?」
「なにか言いたいことがあったのだろう。だから玄関まで迎えにきてくれたのだと思ったのだが」
間違いではないのだが、正解でもない。
美鈴はただ、朔太郎の顔が見たくて、彼が帰ってきたと知るや否や玄関まで走ったのだ。
――近ごろのわたし、変ね。
心のなかで考えごとをしていると、朔太郎の目線を感じて顔をあげる。
美鈴は箸を置いて、姿勢を正した。
「お礼をお伝えしたくて」
「礼?」
「昔このかんざしをくださったのは、統領さまですよね」
懐に忍ばせていた鈴のかんざしを取り出す。
朔太郎はかんざしを一瞥すると、気まずそうに目をそらしてつぶやいた。
「……とうに忘れられていると思っていた」
「ようやくお会いできました。お名前をおうかがいするのを忘れて、お礼が遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。このかんざしのおかげで、悪いあやかしにいたずらされることが減ってずいぶん楽になったんです」
「完全になくなりはしなかっただろう」
「はい?」
朔太郎の声がよく聞こえず、美鈴は聞き返す。
「いや、なんでもない」
「お部屋もお食事もお着物も、ありがとうございます。その、わたしなんかにどうしてここまで――」
「それは、美鈴は私の妻になったのだから当然のことだろう」
「つ、妻……!?」
すっとんきょうな声が静かな夜の屋敷に響く。美鈴は慌てて口を押さえた。
たしかに好待遇すぎて戸惑ってはいたが、そんな話になっているなんて思いもしなかった。いちもはつもなにも言ってこないから、ただただ好意にあまえていたのだ。
美鈴が目を白黒させていると、朔太郎は不満げに眉をひそめた。
――よく見ると感情がわかりやすい方……ってそうじゃなくて。
「どういうことでしょうか」
「なにをそんなに驚いているのだ。あやかしの手をとるということはそういうことだ」
思ってもみなかった事態になっていて、頭が追いつかない。ただただ相槌を打つことしかできない。ぼんやりしていると、朔太郎が追い打ちをかけるように「そもそも」と言った。
「あんな男と共になるくらいなら攫ってしまおうと何度思ったことか。だが、人が定めた決まりごとにあやかしは立ち入ることはできない。だから、許嫁という関係が壊れるのを待っていたのだ」
「待っていたって……」
「あの日から、ずっと美鈴を見守っていた」
朔太郎は居住まいを正して、正面から美鈴を見据える。
「先日は鷹羽の屋敷に美鈴を迎えにいくだけだったのだが、あやかしを数名連れていったせいで騒ぎになってしまった。襲撃するつもりは断じてなかった。ただ、陰陽師の攻撃を防御したつもりが、少し力が強すぎて危害を加えてしまったかもしれない……誰も死んでいないはずだが」
昨今の平和な世では、陰陽師が実戦経験を積む場はなかなかないらしいが、それでも歴史ある鷹羽家の人間だ。
義妹や家の人間が、血反吐を吐きながら厳しい鍛錬に明け暮れているのを知っている。幼いころはこっそり道場の裏手に忍び込み、うらやましかったり、妬ましかったり、自分が情けなかったり、さまざまな気持ちを抱きながら、鍛錬の様子を眺めていた。
あやかしと戦にでもならないかぎりは、死ぬことはないだろう。
そんなことを考えていると、朔太郎の視線を感じて顔をあげる。真剣な瞳で見つめられ、美鈴は背筋を伸ばす。
「いやだったか?」
「い、いいえ」
「ならよかった」
朔太郎は心底ほっとしたように微笑んだ。
――はじめて笑ってくださったわ。
思っていたような冷たい方ではなかったし、ずいぶん強引だけど、美鈴はまったくもっていやではなかった。
朔太郎は言いたいことを言い終えたのか、黙々と食事をしている。美鈴はふたたび訪れた静かな時間に安心感を覚え、箸をとったのだった。