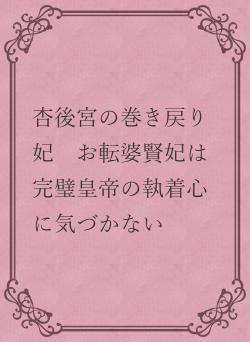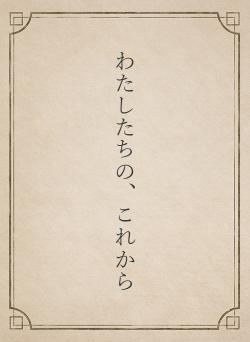朔太郎の屋敷でお世話になりはじめてから数日が経った。
生まれてからほとんどの時間を粗末な納屋で生活していた美鈴は、立派な一人部屋を与えられて戸惑っていた。さらに、清潔で可憐な着物が毎日提供され、温かい食事が三食もついてくる。夢見心地のまま、双子のいちとはつにお世話をしてもらいながら、百とともに平穏な日々を過ごしていた。
――夢みたいだわ。
おそらく朔太郎は昔、迷子の美鈴を助けてくれたあやかしだ。
だいぶ遅くなってしまったが、そのお礼も伝えたいのだが、統領の仕事が忙しいらしく、日中は屋敷にいないことがほとんどだった。いまのところ、美鈴が起きている時間に帰ってくることはなく、朝も知らない間に消えていた。
あやかしの統領の仕事がどのようなものなのかは想像もつかなかったが、過労で倒れないかと体が心配だった。
いちとはつに聞いてみると、「人間との戦もないですし、最近は忙しくないほうですわよ」「あやかしは人間よりも生命力が強いですから、問題ないですわ」と言われてしまった。
窓の外に目を向けると、もうすっかり夕暮れ時だった。今日も朔太郎は帰ってこないかもしれない。
半ばあきらめかけたそのとき、玄関の戸がガラガラと音を立てて開いた。
美鈴は身なりを整えるのも忘れて廊下に出る。慌てて玄関まで走っていくと、朔太郎が沓脱石をまたぐところだった。朔太郎は美鈴の姿を認めると、わずかに顔をしかめる。
「おかえりなさいませ」
「ああ」
朔太郎の着物からわずかに森のにおいがする。一日中外にいたのだろうか。
ちらりと見ると、朔太郎は沓脱石に片足を置いて、止まっていた。美鈴が玄関に立っているから中に入れないらしい。
「あ、ごめんなさい」
脇に退くと、朔太郎は草履を脱いで玄関に上がってくる。
「起きていたのか」
「はい、まだ夕方ですので」
朔太郎から話しかけられて、美鈴の体温がわずかに上がる。
言葉少なな彼だが、おしゃべりが嫌いというわけではないようで、質問をすればだいたい返事がかえってくる。それに、ときどきこうやって気遣ってくれるのだ。
そんな静かな交流に、美鈴は居心地のよさを覚えはじめていた。
仕事は大変だったのか、なにをしていたのか、好きな食べ物はなんなのか。聞いてみたいことは山ほどあった。
美鈴は頬が上気していないか心配になりながら、口を開く。
「あ、あの」
「なんだ」
しかし、朔太郎の言葉は冷たかった。
舞い上がっていた気持ちが急激に萎む。自分だけはしゃいでいたみたいで馬鹿みたいだ。
――理人さんと違って、なんだか怖い人。
思わずそう考えてしまい、すぐにハッとする。不貞を働いた理人と比べるなんて失礼極まりない。しかも、理人のあの優しさは、いまから思うと美鈴をいいように支配するためのものだったように思える。
美鈴は頭を振り、「いえ、なんでもございません」と返事をした。
すると、朔太郎は眉間のしわをいっそう深くした。
「言いたいことがあったのだろう」
「あ、いえ……」
朔太郎の真顔の圧におされて、美鈴は口ごもる。玄関に気まずい空気が流れはじめたとき、どこからかいちとはつが現れた。
「統領さまは顔は怖いですけれど、優しいあやかしですわよ」
「そうですわよ」
朔太郎はいちとはつに荷物を預けると、「余計なことを言うな」とぴしゃりと言う。二人はコロコロと笑い声を響かせた。
感情がわからない人だがどうやら怒ってるわけではないようで、美鈴は安堵する。
「お食事の準備はできていますが、いかがいたしますか」
「美鈴はもう食べたのか」
「いいえ、まだです。統領さまとご一緒できたらと思って……」
そう言いかけると、朔太郎がぱっと顔をあげた。
美鈴の考えていることを理解しようとせんばかりにじっと見つめてくる。美鈴は恥ずかしくなって顔を背けた。
「部屋に運んでくれ。美鈴と食べよう」
生まれてからほとんどの時間を粗末な納屋で生活していた美鈴は、立派な一人部屋を与えられて戸惑っていた。さらに、清潔で可憐な着物が毎日提供され、温かい食事が三食もついてくる。夢見心地のまま、双子のいちとはつにお世話をしてもらいながら、百とともに平穏な日々を過ごしていた。
――夢みたいだわ。
おそらく朔太郎は昔、迷子の美鈴を助けてくれたあやかしだ。
だいぶ遅くなってしまったが、そのお礼も伝えたいのだが、統領の仕事が忙しいらしく、日中は屋敷にいないことがほとんどだった。いまのところ、美鈴が起きている時間に帰ってくることはなく、朝も知らない間に消えていた。
あやかしの統領の仕事がどのようなものなのかは想像もつかなかったが、過労で倒れないかと体が心配だった。
いちとはつに聞いてみると、「人間との戦もないですし、最近は忙しくないほうですわよ」「あやかしは人間よりも生命力が強いですから、問題ないですわ」と言われてしまった。
窓の外に目を向けると、もうすっかり夕暮れ時だった。今日も朔太郎は帰ってこないかもしれない。
半ばあきらめかけたそのとき、玄関の戸がガラガラと音を立てて開いた。
美鈴は身なりを整えるのも忘れて廊下に出る。慌てて玄関まで走っていくと、朔太郎が沓脱石をまたぐところだった。朔太郎は美鈴の姿を認めると、わずかに顔をしかめる。
「おかえりなさいませ」
「ああ」
朔太郎の着物からわずかに森のにおいがする。一日中外にいたのだろうか。
ちらりと見ると、朔太郎は沓脱石に片足を置いて、止まっていた。美鈴が玄関に立っているから中に入れないらしい。
「あ、ごめんなさい」
脇に退くと、朔太郎は草履を脱いで玄関に上がってくる。
「起きていたのか」
「はい、まだ夕方ですので」
朔太郎から話しかけられて、美鈴の体温がわずかに上がる。
言葉少なな彼だが、おしゃべりが嫌いというわけではないようで、質問をすればだいたい返事がかえってくる。それに、ときどきこうやって気遣ってくれるのだ。
そんな静かな交流に、美鈴は居心地のよさを覚えはじめていた。
仕事は大変だったのか、なにをしていたのか、好きな食べ物はなんなのか。聞いてみたいことは山ほどあった。
美鈴は頬が上気していないか心配になりながら、口を開く。
「あ、あの」
「なんだ」
しかし、朔太郎の言葉は冷たかった。
舞い上がっていた気持ちが急激に萎む。自分だけはしゃいでいたみたいで馬鹿みたいだ。
――理人さんと違って、なんだか怖い人。
思わずそう考えてしまい、すぐにハッとする。不貞を働いた理人と比べるなんて失礼極まりない。しかも、理人のあの優しさは、いまから思うと美鈴をいいように支配するためのものだったように思える。
美鈴は頭を振り、「いえ、なんでもございません」と返事をした。
すると、朔太郎は眉間のしわをいっそう深くした。
「言いたいことがあったのだろう」
「あ、いえ……」
朔太郎の真顔の圧におされて、美鈴は口ごもる。玄関に気まずい空気が流れはじめたとき、どこからかいちとはつが現れた。
「統領さまは顔は怖いですけれど、優しいあやかしですわよ」
「そうですわよ」
朔太郎はいちとはつに荷物を預けると、「余計なことを言うな」とぴしゃりと言う。二人はコロコロと笑い声を響かせた。
感情がわからない人だがどうやら怒ってるわけではないようで、美鈴は安堵する。
「お食事の準備はできていますが、いかがいたしますか」
「美鈴はもう食べたのか」
「いいえ、まだです。統領さまとご一緒できたらと思って……」
そう言いかけると、朔太郎がぱっと顔をあげた。
美鈴の考えていることを理解しようとせんばかりにじっと見つめてくる。美鈴は恥ずかしくなって顔を背けた。
「部屋に運んでくれ。美鈴と食べよう」