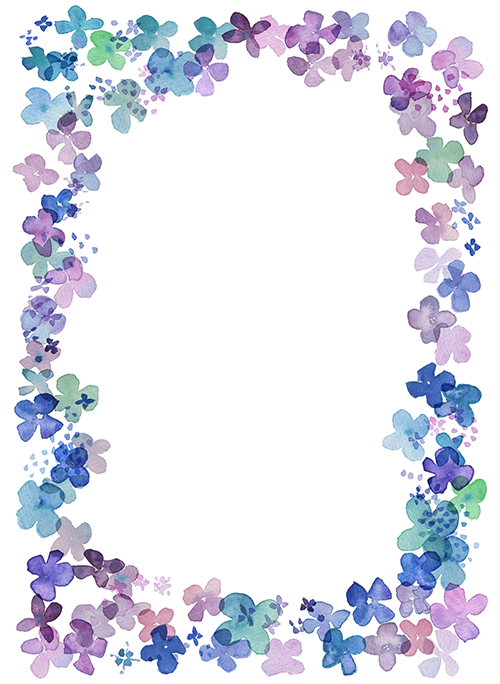4月も半分を過ぎた。薄暗いホームのベンチに私は座っていた。大学の最寄りの人のいない駅。何もない駅。あるとしたらホームにある自販機ぐらい。終電の時間はとっくに過ぎて、私しかいない。
私は、座りながら、ぼーっと薄暗い中の線路を眺めている。薄暗くて深くて、まるで、崖下みたいだな、なんてことを思ってしまう。
改札を出る、どころか立ち上がる気力も沸かない。頭の中でぐるぐるぐるぐると巡るこれまでの出来事が、私の全ての気力を奪っていっていた。
――
志望大学に落ちて、滑り止めの大学に入ることになった。判定も自己採点もきっと大丈夫だったはず、なのに。
実家から電車で二時間の、隣県の私立大学。私が取りたい資格のある大学が、現実的に通える範囲にはここしかなくて、この学校に通うしか無かった。オープンキャンパスも何も行っていない、施設の充実度も志望大学の方が上。資格が取れる、以外は全く興味の惹かれなかった学校。志望大学に入れば一人暮らしを許可されていたけれど、違う大学だから、一人暮らしは出来なくて、家から通うことになった。
――まさか落ちちゃうなんて……。
――浪人したい? そんな余裕ないわよ。その場所で頑張りなさい。
――余裕だったはずなのにな。
――努力不足だったんじゃないか?
優しかったお父さんとお母さんも、私が落ちてから変わってしまった。
家に帰ればお母さんは溜息。お父さんはああだったら、こうだったら、みたいなことばかりを言う。高校時代まで、毎日帰っていたはずの家なのに、ひどく、居心地が悪い。「遅くまで頑張ってたのに」も「努力だってしたのに」も結果の前じゃ通用しない。
「大学はどこに行っても楽しい」といろんな人が言ってたし、インターネットでもそんな風に言われていた。でも、全然そんなことはない。
授業も興味がある分野をいくつか取ったけれども、ただ周りの雰囲気に飲み込まれながら話すので精一杯。楽しく受ける、というよりはプレッシャーに追われながら授業を受けていた。
友達も出来なかった。近い学校、だったり知ってる、土地だったり、同じサークルを希望している、とかで、既にある程度の仲良しグループ、みたいなのが出来ていて、私が入り込む隙間がない。一人で過ごしていた。
一人だけ、授業で、話しかけてくれた子がいた。佐伯博人くん。
月曜2限の文学の授業で「ここ座っていい?」って言われた。ブリーチした金髪にピアスとシルバーアクセサリー。綺麗な顔立ちをしている、って分かるけれども、怖そう、が先行してしまった。無意識に私の心が身構えてしまう。
「一年?」
「は、はい……」
「名前は?」
「え、えっと……安芸、冬乃です……」
「そっか。タメか」
「あの、お名前は……」
「佐伯博人。あんた、どっから来たの?」
「み、短崎(みじかさき)です……」
「そっか」
そこで会話は途切れてしまった。低い声、ぶっきらぼうな物言い。「あんた」呼び。私の人生の中では触れあわなかったタイプの人で、なんだか、距離を取ってしまって、話しかけられても、そこで終わってしまう。同じ授業、何度か隣になったけれど、緊張して、そして心の中でバリアみたいなのを張っているのか、上手く返せず、英語の教科書の例文、みたいな感じで終わってしまった。
サークルも見学には行ったけれど、見学に行くだけで疲れてしまった。通学距離と、やりたいことを合わせても、興味が沸くところはなくて。
なんにも、楽しくない日々を過ごしていた。
金曜日の今日も、一人ぼっちで過ごして、ベンチで一人、学食で買ったパンを食べていた。高校時代の部活のグループLIMEを縋るようにして眺める。卒業式から全然動いていない。みんなのアイコンは充実した大学生活、みたいに変わっていた。充実しているところに連絡なんて出来ない。
頭の中で巡らせていく。その時に浮かんだ顔。垂れ目がちの綺麗な、優しい顔。
--安芸さん
高めの、柔らかい声が私の中にふわっとよぎって、少しだけ寂しさが紛れた。
「木場くん……」
一人のベンチ、つい、彼の名前を呼んでしまった。高校時代、同じクラスだった木場徹(きばとおる)くん。木場くんは、私の憧れの人。同じ志望校を受けるのが縁で仲良くなった。優しそうな垂れ目が印象的な綺麗な男の子。
――え、安芸さんも星ノ大、受けるの? 一緒に頑張ろうよ!
――わかんないとこない? 俺さ、国語苦手だからさ、安芸さん、教えてくれない。
――安芸さん、頑張り屋さんだからさ、きっと受かるよ!
地味で、そんなにおしゃべりが得意じゃない私にも、何度も話しかけてくれて。その度に、嬉しかった。
高めの、でも柔らかい声。すらっとした長い指。さらさらの黒髪。たわいのないやりとりの一つ一つが、私の大事な宝物になっていた。はっきりとこの感情に名前が付いていて、受かったら、ちゃんと、想いを伝えよう、とも想ってた。そして、もっと、木場くんとやりとりを続けたいって思ってたのに。
木場くんは志望校に受かった、私は落ちてしまった。
――そっか、残念だったね。
――でもさ、またどっかで遊ぼうよ。大学、電車使えばすぐでしょ?
――いつでも連絡していいから!
進路が決まった後も、木場くんは優しくて。何度も連絡したい、って思った。でも、木場くんも忙しいと思うから、って、連絡を控えてしまっていた。
でも、もう、耐えきれなかった。どうにも出来なかった。
木場くん。私、どうすればいい? 私、木場くんと同じ大学に行きたかった。今からでもどうにかならないかな。声、聴きたいな。助けて、欲しい。
そんな思いが溢れてくる。
もう、限界だった。今、お昼だから、もしかしたら、
LIMEのトップページを開いた。通知が入っている。
「っ……!?」
瞬間、見えてしまった通知に、私は目を見開いた。「最近更新されました」の通知欄。木場くんのLIMEのアイコンが変わっている。心臓が乱れる。いや、サークルの写真とかかもしれない。震える指で、「木場徹」と書かれた彼のLIMEプロフィールをタップする。
「あ……」
指に力を込めて、携帯を落としそうになるのを必死に堪えた。海を背景にして、私とは比べものにならないくらいに綺麗な女の人とほっぺたをくっつけて幸せそうにピースする木場くんが、画面にはっきりと表示されていた。
木場くん、彼女さん、出来たんだ……。
優しくて素敵な人だから彼女さんが出来るのは当然だって、分かってるはずなのに。
その後は、どうしたか全く覚えていない。何も見たくなくて、携帯の電源だけは切っていた。家に帰るために改札を出て、ホームに着いたことは覚えている。そこが、もう限界。ベンチから動けなくなってしまって、ずーっとぼんやりと、過ごしていた。
――
頭の中の走馬灯めいたものが一瞬緩んで、現実世界に緩やかに戻っていた。
「……」
気がつけば、私はベンチから離れてホームに立っていた。超えてはいけない黄色の点字ブロックを越えて。立って歩いていたことすら意識してないくらいに弱っていたんだと思う。
電車が通っていないホームを覗き込む。やっぱり、奈落の底、みたいだ。今の私の、心、みたいに暗い。
「………………」
電車は来ない。でも、ここから落ちて、頭を打てば、もしかしたら楽になれるかもしれない。この奈落の中でずっと待てば、始発の電車が来るかもしれない。
なんでもいい、今よりも楽になれるのかもしれない。ふわふわとした、どこか、夢の中にいるような、そんな感覚で、衝動的に私は足を踏み出した。重力に任せて、身体が前のめりになっていって……。
「っ……!?」
けれども、私の身体に走ったのは、落ちる、とは、違う感覚だった。
私の腕が、がしりと掴まれて、重力に逆らった。重力に逆らったまま、間髪入れずにぎゅう、っと私の身体が抱きしめられる。私よりもずっと力が強い。そのまま、私の身体はホームに戻っていく。
ゆっくりと抱きしめる腕の力が解けた。私より背の高い人。ベンチ側に押し込められるようにして私の身体が押される。その時、初めて抱きしめた人の顔を見た。
「佐伯、くん……」
そこにいたのは、佐伯くん。もう次に来る電車はないのに。どうして佐伯くんがこんなところにいるんだろう。
佐伯くんは睨むような、怒っているような表情で私のことをじっと見つめている。ただ、そのなかに、泣きそうな表情が混じっているように感じてしまった。
「何やってるんだよ!」
けれども、彼の表情、をじっくりと見ている余裕は一瞬でかき消されてしまう。私達しかいないホームに響く彼の怒鳴り声。反射的にびくっ、と肩をふるわせてしまった。
「こんな誰もいないとこでぼさっとしてて、かと思えば線路の方にふらふら行って、落っこちそうになって、何考えてるんだよ! 危ないだろ!」
佐伯くんはすごい剣幕で怒鳴っている。ただ、それは、八つ当たり、とか理不尽なものでは全然ない。怒っているはずなのに、どこか泣いているような表情をしている。どうしてか、は分からないけれど、私のことを心配してくれてる、っていうのは分かる。でも、佐伯くんの勢いに圧倒されて、私はその場に立っていることしか出来ない。どこか、現実味がない。
「あんた、死にたいのか!?」
あんた、死にたいのか。
「っ……!」
その言葉が脳内に突き刺さって、急に、目を覚ましたような感覚になる。
今までしようとしていたことが、現実的な、目の前で突きつけられている、みたいな感じがして、そのまま、私の身体がぶるぶると恐怖で震えていく。そのまま、私の身体が、立っている体勢を保てなくなって、小さく丸まってしまう。小さく丸まりながら、私はぶるぶると震えている。
私、とんでもないことをしようとしていた、っていう怖さとか、これからどうすればいいんだろう、とか、もしかしたら、死にたかったのかもしれない、みたいな、もう何もわかんない、ぐちゃぐちゃの感情が私の頭の中を支配して、ホームのコンクリートが歪んでいく。 そのまま、コンクリートの上、雨のように私の涙が落ちていく。
「おい、大丈夫か……!?」
佐伯くんの声色が、怒鳴り、から戸惑いになる。私は首を横に振る。全然、大丈夫じゃない。
「具合悪いのか……!? 怪我してるのか!? どっか痛いのか?」
佐伯くんは焦ったような声を出している。私は顔を上げた。歪んでいる世界の中で、ひどく戸惑った顔の佐伯くんが見える。さっきの怒鳴っていた時の怖い顔、ではない。怖さはない。でも、涙は止まらない。
泣きながら私は首を横に振る。具合が悪いわけではない。もう、何もかも、分からなかった。
「怖かったよな。急に怒鳴ったりして……。悪かった……」
さっきの怒鳴り、じゃなくて、狼狽えているのが分かる声。
佐伯くんの手が背中に触れる。そのまま、なだめるような柔らかな手つきで、私のことを撫でる。
怖い、と思っていた佐伯くんに対して、なぜか分からないけれど、その動きを受け入れていた。服越しに伝わる佐伯くんの手は、心地よくって。
佐伯くんは私が落ち着くまで、そっと、背中を撫でてくれていた。
「悪かった。怒鳴って。あんたが心配で、思わず……」
「ううん。大丈夫……」
しばらくして、私の涙が落ち着いた後、佐伯くんと一緒に改札を出た。悪かった、と何度も謝ってくれた。
駅のベンチ。隣あって座る。
「……何かあったのか?」
「……………………」
佐伯くんから向けられる視線は、探るような、でも、ひどく柔らかいもの。まだ、全部を話しきる、までに心を許しているわけじゃなくって、私は沈黙してしまう。
「……家、短崎だっけ」
「……うん」
「家まで送るか? 車停めてるし、多分高速使えば結構速く着くだろうし」
首を横に振る。携帯の電源は怖くてまだ、付けてないけれど、きっと、お父さんも、お母さんも、怒ってる。お父さんとお母さんが怖くなって、私は少し縮こまった。
「……そっか」
佐伯くんも、もしかして察したのかもしれない。事情を分かった、みたいな声色をしている。
しん、とした駅の中。「そうだ」と、佐伯くんが口にした。その声はどこか楽しいことを思いついた、みたいな声だった。
「じゃ、俺と、夜遊びするか。車で10分。いいとこ」
「え……?」
「大丈夫。もちろん、“そういうこと”はしないから」
「……」
正直、佐伯くんの姿でその言葉を信じろ、って言うのは、今の私にはなかなか難しい。綺麗な顔をしているけれど、今日の佐伯くんの姿も、漫画の広告とかでよく見る怖いお兄さん、みたいな姿をしているから。それに、こんな時間に外を出歩いたことなんてないから。
「じゃ、指切りに誓うよ」
「指切り……?」
「そ、指切り。俺だって針千本飲まされるのは嫌だからさ」
そんな風なことを言いながら、小指をぴ、と立てて出される。駅のベンチの電灯に照らされた綺麗な指。指切り、なんて方法を持ち出すなんてなかなかない。その言葉で、なんだか私の警戒心、みたいなのが少し解ける。恐る恐る小指を伸ばして、彼の手に結びつける。少し低い指の温度が伝わった。
「ゆーびきりげんまんうそついたらはりせんぼんのーます、ゆびきった!」
私の方を柔らかい表情で見つめながら、低い、でも無邪気な声色で、歌を歌いながら大きく手を動かす佐伯くん。その姿はなんだか、小さなこども、みたいなので、疑い、みたいなのは少し晴れた。
まだ、全てを話せるくらいに、完全に心を開く、まではいっていないけれど。
「それじゃ、行くか」
ここで、朝まで過ごすんだったら、ついていくのもいいのかもしれない。そんなことを考えてしまった。
佐伯くんの車に乗り込んだ。シートベルトを付ける。
「……そういえば、佐伯くん、なんであそこにいたの?」
終電はもうない。どうしてあんなところにいたんだろう。
「飲み物買いに」
「飲み物? 出口にもなかったっけ? 自販機」
「あそこの自販機に売ってるレモネード、買おうと思って。売り切れだったけど」
「なるほど……。好きなの?」
「まあ……。恩人がすごい好きだったんだよ」
「恩人?」
「…………お世話になった人がいるんだ」
佐伯くんが少し口ごもったような感じがしたから、「そう、なんだ」と言って会話を終えた。佐伯くんは少しの間のあと、そのまま、話題を変えるのと同じようにしてエンジンをかけた。もしかして、あまり深く訊いちゃいけないことだったのかもしれないな、と思いながらも、車は走り始めた。
「ここから10分くらい運転するから」
「わかった……。どこ行くの?」
「いいとこだよ。怖いとこじゃない。本当に何もしないから」
「……うん」
話しつつ、夜の道をすいすいと運転していく佐伯くん。私の家の方面からは逆方向の道。
この状況で何もしてない、から本当に何もないんだと思う。そこに関しては信じることにした。
「そういえば嫌いな食べ物とかあるか?」
「……特には」
「なら、大丈夫だな」
そういえば、昼から何も食べてない。でも、あんまりお腹、空いてないな。そんなことをぼんやりと考えながら、車に揺られる。
ぽつぽつと明かりが見えていた夜道、から、街が見えてくる。大学から数駅離れた、栄えている街。終電で真っ直ぐ帰るから、来るのは初めて。
10分ほど走ったところで、佐伯くんの運転する車が有料駐車場に入った。停車する。
「お疲れ、着いたぞ」
「あ、うん……、ありがとう」
車を降りる。 がやがやとした人の声が聞こえてくる。まるで夜じゃないみたいだ。終電以降だというのに随分と明るい。
「それじゃあ、行くぞ」
私はきょろきょろ、戸惑いながら辺りを見る。飲み屋さんとかがあるのか人がいっぱいいて、昼間よりも賑やかな雰囲気すら感じる。
そういえば、夜の町なんて歩いたことがなかった。少し緊張が走る。まるで親鳥についていくひな鳥、みたいな感じで佐伯くんの後ろに着いていく。
その時、ちら、と佐伯くんが私の方に視線を向けた。
「……慣れてないのか?」
ちょっと緊張しながらこくりと頷く。
「そっか。悪いな」
「えっ……!?」
佐伯くんがす、と手を伸ばした。繋ごう、と言う風に。私がそっと手を伸ばすと、佐伯くんは私の手をぎゅ、と包み込む。
「絶対に手、離すなよ」
それは、親切心、からしたのか、そうじゃないのかは分からない。物心ついた後、男の人と、こんな風に手を繋ぐのって、初めてだから少し緊張した。でも、嫌、ではなかった。嫌、じゃなくて、どこか心地よさすら覚えてしまった。心臓が、少し甘く撥ねた。一瞬、木場くんといるときと似た感覚すら、覚えてしまった。
「着いたぞ」
「え……?」
10分くらい歩いて、辿り着いたのは、チェーン店のファミリーレストランだった。佐伯くんは、何も言わずにその中に入っていく。時間が時間だから人は少ないけどちらちらとはいた。一番奥の席を案内されて。なんとなく、席に着くまで手は繋ぎっぱなしになっていた。
席に私達は向かい合って座る。水が置かれた後、そこでふう、と息を吐いた。
「えっと、どうして、レストランに……?」
「ここ、24時間空いてるレストラン。ここだったらある程度目があるからなんも出来ないし、腹減ったら食えるだろ?」
「そ、そうだね……」
「ま、話したくなかったら、メシ食うだけでもいいし」
す、と私の方にメニュー表を渡してくれた。
「え……」
「頼むなら、何でも好きなもの頼んでいいぞ。バイト代入ったから」
私は、少し戸惑ってしまう。何でも好きなもの、なんて言われたことない。ほとんど喋ったことのない人にそんなことを言われても、何を頼めばいいか分からない。あまり、お腹も空いていないかもしれない。
「そ、それじゃあ……、水、で……?」
「水はおかわり自由だ。もしかして、あんま腹減ってないのか?」
頷く。お腹が空いてない、もそうだし、どうすればいいか、も分からなかったから。
「そっか。それじゃあ、俺、先に頼むから、頼みたくなったら頼んで」
佐伯くんはベルを押して、来てくれた店員さんに対して、いくつかぽんぽんと注文を言っていた。
「お待たせしました。フライドポテトです」
店員さんがフライドポテトを持ってきてくれる。ふわっと漂う香ばしい匂い。
「食うか?」
「え、えっと……」
私が、どう答えればいいか分からずにしていた時だった。ぐう、とお腹の音が鳴った。
「ほら、ポテト」
「……。えっと……」
私の方にポテトの皿を差し出された。食べろ、と言わんばかりに。
「……、いただき、ます……」
恐る恐る、一つ口に入れた。濃い塩味のポテトを咀嚼して飲み込む。濃い塩味、じわりと、全身に染みこんでいくような感覚。
「どうだ?」
「……おい、しい」
瞬間、私の目から、涙が溢れてくる。なんだろう。急に、生き返った、というか、そういう気分。美味しいのと、我に返ったような感覚。私がもう一回泣き出したことによって、佐伯くんはぎょっとした表情を見せる。
「ポテト、嫌だったか?」
「あのね、…………」
ポテトのしょっぱさの残像を味わいながら、私は、泣きながら、これまでのことを話した。
「ともだちも、できない……」
「うん」
「すきなひとも、かのじょがいて……」
「うん」
「おとうさんと、おかあさんも、ずっと……」
「うん」
「もう、いなく、なりたかった……」
佐伯くんはずーっと、私の話を、頷いて訊いてくれた。支離滅裂で、頭の中のことを取り出したように話したのに、嫌な顔をせずに訊いてくれて。それが、私に取って嬉しかった。
どのぐらい時間が経ったんだろう。
「そっか。ありがとな。話してくれて」
佐伯くんは、ひどくやさしい声で、私の方を見て、微笑んでくれた。柔らかい、安心出来るような表情。なんだか、それだけで、今まで溜め込んでいた、暗いものが、全部消えた気がした。佐伯くんの瞳に映っていた私は、随分とすっきりとした表情をしている。
「うん、もう、ありがとう。大丈夫」
「そっか」
なんか、すっきりしたら、本格的に、お腹が空いてしまった。
「なんか、食べるか?」
「うん……」
メニュー表を開く。一番お手頃で美味しそうだな、と思ったグラタンをお願いした。
グラタンを食べて、ポテトをつまんで、二人で時間を過ごす。
「なるか、友達」
そんな時に、佐伯くんが突然口にする。
「え?」
「すぐ、じゃなくてもいいからさ」
「なんで……?」
「俺がなりたいの。それにさ、そうやって拠り所があるとさ、いいだろ」
「……うん」
「心のどこかにさ、“何かあったらこいつのとこに行けるから~” みたいなのがあれば、なんとなく楽だろ」
不意に思い出した、木場くんのこと。思い出して、目の奥がつん、となる。でもその感覚も、脳内の木場くんも、目の前で、心配そうな表情をしている佐伯くんに消されてしまった。
「どうした?」
「ううん、大丈夫。ありがとう……」
いつの間にか、朝になっていた。始発はもう何本か過ぎていて。私達は、元いた駅に戻ることになった。
「本当に、家まで送っていかなくて大丈夫か?」
「うん、大丈夫。ありがとう」
あの駅のそばの駐車場で車が止まる。家まで送っていくか、って言われたけれども断った。今日は土曜日。せっかくのお休み、運転させるのも申し訳ないな、って思って。
車から私達は降りた。元いた駅が見える。
「……」
駅の方を眺めながら、ふと、突然、振ってくるように思った。佐伯くん、どうして私のこと、助けてくれたんだろう。「飲み物を」みたいな理由であそこにいたけれど。その前から、私に声かけてくれたりとかしたから。
「そういえば、どうして、私のこと、声かけたの……?」
「気になってたんだよ。お前のこと」
「え……?」
「昔の俺と同じ顔してて。恩人に助けてもらえる前の俺の顔」
「恩人?」
「そ、俺の恩人。いろいろとすごい人。で、これは恩人の服装のまねっこ」
「そう、なんだね……」
でも、昔の俺、とか恩人、の話をしていた時に、少し寂しそうな、苦しそうな顔をしてたから、私はそれ以上は訊けなかった。
「……ごめんね」
「何が?」
「……その、いろいろ」
「いいよ。別に」
いろんな意味を含んだごめんね、だ。もしかして、私は、勘違いしていたのかもしれない。見た目とかで、怖い人、みたいに思ってしまったのかもしれない。
「そうだ。あの、お代、とかは。ガソリン代とか、ご飯代、とか……?」
奢る、とは言ったけれども、何も払わないのもなんだか申し訳ない。
「別に……、あ。じゃあ……」
少し考えた後、佐伯くんは言う。
「来週の月曜、文学の授業で俺と会う。それでいいよ」
「え……?」
佐伯くんはスマートフォンを取り出した。そして「連絡先、交換するか」と口にする。私は頷いて、スマートフォンの電源をようやく入れる。いくつもの通知が溜まっていた。
「あと、なんかあったら、俺にすぐ連絡すること。遠慮なんてしなくていいから。俺も、お前に連絡する」
「ありがとう……」
心配してくれている。なんだか嬉しかった。そして、私の胸の中には、柔らかな、どこかで抱いたことのある感覚が走っていた。
「じゃあな。また、月曜日、学校で」
「うん」
駐車場から出て、私は歩いていく。駅の中に入った時だった。着信音が響く。「お母さん」という文字。
「……もしもし、お母さん」
「冬乃!? 今、どこにいるの!? 元気!? 怪我とかしてない!?」
泣きながら、でも安心したって分かるお母さんの声。随分と、心配を掛けてしまったんだな、って思った。
「うん、ごめんね。いろいろあって……」
「ごめんね、はお母さん達のセリフ。今から迎えに行くから……!」
「ううん、大丈夫。ちゃんと帰れるから。今、電車、来るから」
ホームは既に人がちらちらといる。無人、ではあるけれど、大学とか、あと少し行った所の観光地の経由駅、だから人はいる。
ホームの底、を見る前に電車が来て、そして私は乗り込んだ。家に帰る方向の電車だ。
「冬乃!」
家の扉。鍵は閉まっていなかった。けど、開けた瞬間、お母さんが勢いよく私の方に向かっていく。お母さんが、どんな表情をしているか分からないまま、ぎゅううっ!と私の身体が力強く抱きしめられる。
「……ごめんね」
お父さんもお母さんも、仕事を休んでいた。お母さんも目を腫らしていて、お父さんも、今まで見たことないくらいに狼狽えている。
「……冬乃、大丈夫か?」
「……うん。ごめんなさい」
「……。ごめんね。一番大変なのは、冬乃だったのにね。なんで、お母さん、あんなに責めるようなこと、言っちゃったんだろうね……」
「……。お前に、期待を押しつけてたんだろう。すまなかった……」
父さんも、母さんも、私のことを、応援してくれていた。だから、その分、ショックだったのかもしれない。
「……大学、辞めたいか?」
「え……?」
「その、なんとかすれば、今からでも……」
「そう、お母さんも、もっと仕事を増やせば……!」
私は、首を横に振る。
「ありがとう。もう少し、頑張ってみる」
「そうか……」
「分かった。もし、つらかったら、言ってね。もう、あんなこと、言わないから」
「眠いでしょう。少し、休んだら?」
「……うん」
母さんの言葉で、私は部屋へと戻った。
ベッドの上、心地いい感触に浸り、うとうととしかけた時だった。LIMEの通知音。佐伯くんからLIMEが来ていた。
“大丈夫か?”
一文だけ。ぶっきらぼうな、でも優しさの伝わるメッセージ。
“ありがとう、おかげで、もう大丈夫“
返信を終えて、どこかふわふわとした、あたたかな感覚の中、私は瞼を閉じる。
頭の中を巡っていた、奈落の底みたいな光景は、全部、佐伯くんとの時間で塗りつぶされていた。
私は、座りながら、ぼーっと薄暗い中の線路を眺めている。薄暗くて深くて、まるで、崖下みたいだな、なんてことを思ってしまう。
改札を出る、どころか立ち上がる気力も沸かない。頭の中でぐるぐるぐるぐると巡るこれまでの出来事が、私の全ての気力を奪っていっていた。
――
志望大学に落ちて、滑り止めの大学に入ることになった。判定も自己採点もきっと大丈夫だったはず、なのに。
実家から電車で二時間の、隣県の私立大学。私が取りたい資格のある大学が、現実的に通える範囲にはここしかなくて、この学校に通うしか無かった。オープンキャンパスも何も行っていない、施設の充実度も志望大学の方が上。資格が取れる、以外は全く興味の惹かれなかった学校。志望大学に入れば一人暮らしを許可されていたけれど、違う大学だから、一人暮らしは出来なくて、家から通うことになった。
――まさか落ちちゃうなんて……。
――浪人したい? そんな余裕ないわよ。その場所で頑張りなさい。
――余裕だったはずなのにな。
――努力不足だったんじゃないか?
優しかったお父さんとお母さんも、私が落ちてから変わってしまった。
家に帰ればお母さんは溜息。お父さんはああだったら、こうだったら、みたいなことばかりを言う。高校時代まで、毎日帰っていたはずの家なのに、ひどく、居心地が悪い。「遅くまで頑張ってたのに」も「努力だってしたのに」も結果の前じゃ通用しない。
「大学はどこに行っても楽しい」といろんな人が言ってたし、インターネットでもそんな風に言われていた。でも、全然そんなことはない。
授業も興味がある分野をいくつか取ったけれども、ただ周りの雰囲気に飲み込まれながら話すので精一杯。楽しく受ける、というよりはプレッシャーに追われながら授業を受けていた。
友達も出来なかった。近い学校、だったり知ってる、土地だったり、同じサークルを希望している、とかで、既にある程度の仲良しグループ、みたいなのが出来ていて、私が入り込む隙間がない。一人で過ごしていた。
一人だけ、授業で、話しかけてくれた子がいた。佐伯博人くん。
月曜2限の文学の授業で「ここ座っていい?」って言われた。ブリーチした金髪にピアスとシルバーアクセサリー。綺麗な顔立ちをしている、って分かるけれども、怖そう、が先行してしまった。無意識に私の心が身構えてしまう。
「一年?」
「は、はい……」
「名前は?」
「え、えっと……安芸、冬乃です……」
「そっか。タメか」
「あの、お名前は……」
「佐伯博人。あんた、どっから来たの?」
「み、短崎(みじかさき)です……」
「そっか」
そこで会話は途切れてしまった。低い声、ぶっきらぼうな物言い。「あんた」呼び。私の人生の中では触れあわなかったタイプの人で、なんだか、距離を取ってしまって、話しかけられても、そこで終わってしまう。同じ授業、何度か隣になったけれど、緊張して、そして心の中でバリアみたいなのを張っているのか、上手く返せず、英語の教科書の例文、みたいな感じで終わってしまった。
サークルも見学には行ったけれど、見学に行くだけで疲れてしまった。通学距離と、やりたいことを合わせても、興味が沸くところはなくて。
なんにも、楽しくない日々を過ごしていた。
金曜日の今日も、一人ぼっちで過ごして、ベンチで一人、学食で買ったパンを食べていた。高校時代の部活のグループLIMEを縋るようにして眺める。卒業式から全然動いていない。みんなのアイコンは充実した大学生活、みたいに変わっていた。充実しているところに連絡なんて出来ない。
頭の中で巡らせていく。その時に浮かんだ顔。垂れ目がちの綺麗な、優しい顔。
--安芸さん
高めの、柔らかい声が私の中にふわっとよぎって、少しだけ寂しさが紛れた。
「木場くん……」
一人のベンチ、つい、彼の名前を呼んでしまった。高校時代、同じクラスだった木場徹(きばとおる)くん。木場くんは、私の憧れの人。同じ志望校を受けるのが縁で仲良くなった。優しそうな垂れ目が印象的な綺麗な男の子。
――え、安芸さんも星ノ大、受けるの? 一緒に頑張ろうよ!
――わかんないとこない? 俺さ、国語苦手だからさ、安芸さん、教えてくれない。
――安芸さん、頑張り屋さんだからさ、きっと受かるよ!
地味で、そんなにおしゃべりが得意じゃない私にも、何度も話しかけてくれて。その度に、嬉しかった。
高めの、でも柔らかい声。すらっとした長い指。さらさらの黒髪。たわいのないやりとりの一つ一つが、私の大事な宝物になっていた。はっきりとこの感情に名前が付いていて、受かったら、ちゃんと、想いを伝えよう、とも想ってた。そして、もっと、木場くんとやりとりを続けたいって思ってたのに。
木場くんは志望校に受かった、私は落ちてしまった。
――そっか、残念だったね。
――でもさ、またどっかで遊ぼうよ。大学、電車使えばすぐでしょ?
――いつでも連絡していいから!
進路が決まった後も、木場くんは優しくて。何度も連絡したい、って思った。でも、木場くんも忙しいと思うから、って、連絡を控えてしまっていた。
でも、もう、耐えきれなかった。どうにも出来なかった。
木場くん。私、どうすればいい? 私、木場くんと同じ大学に行きたかった。今からでもどうにかならないかな。声、聴きたいな。助けて、欲しい。
そんな思いが溢れてくる。
もう、限界だった。今、お昼だから、もしかしたら、
LIMEのトップページを開いた。通知が入っている。
「っ……!?」
瞬間、見えてしまった通知に、私は目を見開いた。「最近更新されました」の通知欄。木場くんのLIMEのアイコンが変わっている。心臓が乱れる。いや、サークルの写真とかかもしれない。震える指で、「木場徹」と書かれた彼のLIMEプロフィールをタップする。
「あ……」
指に力を込めて、携帯を落としそうになるのを必死に堪えた。海を背景にして、私とは比べものにならないくらいに綺麗な女の人とほっぺたをくっつけて幸せそうにピースする木場くんが、画面にはっきりと表示されていた。
木場くん、彼女さん、出来たんだ……。
優しくて素敵な人だから彼女さんが出来るのは当然だって、分かってるはずなのに。
その後は、どうしたか全く覚えていない。何も見たくなくて、携帯の電源だけは切っていた。家に帰るために改札を出て、ホームに着いたことは覚えている。そこが、もう限界。ベンチから動けなくなってしまって、ずーっとぼんやりと、過ごしていた。
――
頭の中の走馬灯めいたものが一瞬緩んで、現実世界に緩やかに戻っていた。
「……」
気がつけば、私はベンチから離れてホームに立っていた。超えてはいけない黄色の点字ブロックを越えて。立って歩いていたことすら意識してないくらいに弱っていたんだと思う。
電車が通っていないホームを覗き込む。やっぱり、奈落の底、みたいだ。今の私の、心、みたいに暗い。
「………………」
電車は来ない。でも、ここから落ちて、頭を打てば、もしかしたら楽になれるかもしれない。この奈落の中でずっと待てば、始発の電車が来るかもしれない。
なんでもいい、今よりも楽になれるのかもしれない。ふわふわとした、どこか、夢の中にいるような、そんな感覚で、衝動的に私は足を踏み出した。重力に任せて、身体が前のめりになっていって……。
「っ……!?」
けれども、私の身体に走ったのは、落ちる、とは、違う感覚だった。
私の腕が、がしりと掴まれて、重力に逆らった。重力に逆らったまま、間髪入れずにぎゅう、っと私の身体が抱きしめられる。私よりもずっと力が強い。そのまま、私の身体はホームに戻っていく。
ゆっくりと抱きしめる腕の力が解けた。私より背の高い人。ベンチ側に押し込められるようにして私の身体が押される。その時、初めて抱きしめた人の顔を見た。
「佐伯、くん……」
そこにいたのは、佐伯くん。もう次に来る電車はないのに。どうして佐伯くんがこんなところにいるんだろう。
佐伯くんは睨むような、怒っているような表情で私のことをじっと見つめている。ただ、そのなかに、泣きそうな表情が混じっているように感じてしまった。
「何やってるんだよ!」
けれども、彼の表情、をじっくりと見ている余裕は一瞬でかき消されてしまう。私達しかいないホームに響く彼の怒鳴り声。反射的にびくっ、と肩をふるわせてしまった。
「こんな誰もいないとこでぼさっとしてて、かと思えば線路の方にふらふら行って、落っこちそうになって、何考えてるんだよ! 危ないだろ!」
佐伯くんはすごい剣幕で怒鳴っている。ただ、それは、八つ当たり、とか理不尽なものでは全然ない。怒っているはずなのに、どこか泣いているような表情をしている。どうしてか、は分からないけれど、私のことを心配してくれてる、っていうのは分かる。でも、佐伯くんの勢いに圧倒されて、私はその場に立っていることしか出来ない。どこか、現実味がない。
「あんた、死にたいのか!?」
あんた、死にたいのか。
「っ……!」
その言葉が脳内に突き刺さって、急に、目を覚ましたような感覚になる。
今までしようとしていたことが、現実的な、目の前で突きつけられている、みたいな感じがして、そのまま、私の身体がぶるぶると恐怖で震えていく。そのまま、私の身体が、立っている体勢を保てなくなって、小さく丸まってしまう。小さく丸まりながら、私はぶるぶると震えている。
私、とんでもないことをしようとしていた、っていう怖さとか、これからどうすればいいんだろう、とか、もしかしたら、死にたかったのかもしれない、みたいな、もう何もわかんない、ぐちゃぐちゃの感情が私の頭の中を支配して、ホームのコンクリートが歪んでいく。 そのまま、コンクリートの上、雨のように私の涙が落ちていく。
「おい、大丈夫か……!?」
佐伯くんの声色が、怒鳴り、から戸惑いになる。私は首を横に振る。全然、大丈夫じゃない。
「具合悪いのか……!? 怪我してるのか!? どっか痛いのか?」
佐伯くんは焦ったような声を出している。私は顔を上げた。歪んでいる世界の中で、ひどく戸惑った顔の佐伯くんが見える。さっきの怒鳴っていた時の怖い顔、ではない。怖さはない。でも、涙は止まらない。
泣きながら私は首を横に振る。具合が悪いわけではない。もう、何もかも、分からなかった。
「怖かったよな。急に怒鳴ったりして……。悪かった……」
さっきの怒鳴り、じゃなくて、狼狽えているのが分かる声。
佐伯くんの手が背中に触れる。そのまま、なだめるような柔らかな手つきで、私のことを撫でる。
怖い、と思っていた佐伯くんに対して、なぜか分からないけれど、その動きを受け入れていた。服越しに伝わる佐伯くんの手は、心地よくって。
佐伯くんは私が落ち着くまで、そっと、背中を撫でてくれていた。
「悪かった。怒鳴って。あんたが心配で、思わず……」
「ううん。大丈夫……」
しばらくして、私の涙が落ち着いた後、佐伯くんと一緒に改札を出た。悪かった、と何度も謝ってくれた。
駅のベンチ。隣あって座る。
「……何かあったのか?」
「……………………」
佐伯くんから向けられる視線は、探るような、でも、ひどく柔らかいもの。まだ、全部を話しきる、までに心を許しているわけじゃなくって、私は沈黙してしまう。
「……家、短崎だっけ」
「……うん」
「家まで送るか? 車停めてるし、多分高速使えば結構速く着くだろうし」
首を横に振る。携帯の電源は怖くてまだ、付けてないけれど、きっと、お父さんも、お母さんも、怒ってる。お父さんとお母さんが怖くなって、私は少し縮こまった。
「……そっか」
佐伯くんも、もしかして察したのかもしれない。事情を分かった、みたいな声色をしている。
しん、とした駅の中。「そうだ」と、佐伯くんが口にした。その声はどこか楽しいことを思いついた、みたいな声だった。
「じゃ、俺と、夜遊びするか。車で10分。いいとこ」
「え……?」
「大丈夫。もちろん、“そういうこと”はしないから」
「……」
正直、佐伯くんの姿でその言葉を信じろ、って言うのは、今の私にはなかなか難しい。綺麗な顔をしているけれど、今日の佐伯くんの姿も、漫画の広告とかでよく見る怖いお兄さん、みたいな姿をしているから。それに、こんな時間に外を出歩いたことなんてないから。
「じゃ、指切りに誓うよ」
「指切り……?」
「そ、指切り。俺だって針千本飲まされるのは嫌だからさ」
そんな風なことを言いながら、小指をぴ、と立てて出される。駅のベンチの電灯に照らされた綺麗な指。指切り、なんて方法を持ち出すなんてなかなかない。その言葉で、なんだか私の警戒心、みたいなのが少し解ける。恐る恐る小指を伸ばして、彼の手に結びつける。少し低い指の温度が伝わった。
「ゆーびきりげんまんうそついたらはりせんぼんのーます、ゆびきった!」
私の方を柔らかい表情で見つめながら、低い、でも無邪気な声色で、歌を歌いながら大きく手を動かす佐伯くん。その姿はなんだか、小さなこども、みたいなので、疑い、みたいなのは少し晴れた。
まだ、全てを話せるくらいに、完全に心を開く、まではいっていないけれど。
「それじゃ、行くか」
ここで、朝まで過ごすんだったら、ついていくのもいいのかもしれない。そんなことを考えてしまった。
佐伯くんの車に乗り込んだ。シートベルトを付ける。
「……そういえば、佐伯くん、なんであそこにいたの?」
終電はもうない。どうしてあんなところにいたんだろう。
「飲み物買いに」
「飲み物? 出口にもなかったっけ? 自販機」
「あそこの自販機に売ってるレモネード、買おうと思って。売り切れだったけど」
「なるほど……。好きなの?」
「まあ……。恩人がすごい好きだったんだよ」
「恩人?」
「…………お世話になった人がいるんだ」
佐伯くんが少し口ごもったような感じがしたから、「そう、なんだ」と言って会話を終えた。佐伯くんは少しの間のあと、そのまま、話題を変えるのと同じようにしてエンジンをかけた。もしかして、あまり深く訊いちゃいけないことだったのかもしれないな、と思いながらも、車は走り始めた。
「ここから10分くらい運転するから」
「わかった……。どこ行くの?」
「いいとこだよ。怖いとこじゃない。本当に何もしないから」
「……うん」
話しつつ、夜の道をすいすいと運転していく佐伯くん。私の家の方面からは逆方向の道。
この状況で何もしてない、から本当に何もないんだと思う。そこに関しては信じることにした。
「そういえば嫌いな食べ物とかあるか?」
「……特には」
「なら、大丈夫だな」
そういえば、昼から何も食べてない。でも、あんまりお腹、空いてないな。そんなことをぼんやりと考えながら、車に揺られる。
ぽつぽつと明かりが見えていた夜道、から、街が見えてくる。大学から数駅離れた、栄えている街。終電で真っ直ぐ帰るから、来るのは初めて。
10分ほど走ったところで、佐伯くんの運転する車が有料駐車場に入った。停車する。
「お疲れ、着いたぞ」
「あ、うん……、ありがとう」
車を降りる。 がやがやとした人の声が聞こえてくる。まるで夜じゃないみたいだ。終電以降だというのに随分と明るい。
「それじゃあ、行くぞ」
私はきょろきょろ、戸惑いながら辺りを見る。飲み屋さんとかがあるのか人がいっぱいいて、昼間よりも賑やかな雰囲気すら感じる。
そういえば、夜の町なんて歩いたことがなかった。少し緊張が走る。まるで親鳥についていくひな鳥、みたいな感じで佐伯くんの後ろに着いていく。
その時、ちら、と佐伯くんが私の方に視線を向けた。
「……慣れてないのか?」
ちょっと緊張しながらこくりと頷く。
「そっか。悪いな」
「えっ……!?」
佐伯くんがす、と手を伸ばした。繋ごう、と言う風に。私がそっと手を伸ばすと、佐伯くんは私の手をぎゅ、と包み込む。
「絶対に手、離すなよ」
それは、親切心、からしたのか、そうじゃないのかは分からない。物心ついた後、男の人と、こんな風に手を繋ぐのって、初めてだから少し緊張した。でも、嫌、ではなかった。嫌、じゃなくて、どこか心地よさすら覚えてしまった。心臓が、少し甘く撥ねた。一瞬、木場くんといるときと似た感覚すら、覚えてしまった。
「着いたぞ」
「え……?」
10分くらい歩いて、辿り着いたのは、チェーン店のファミリーレストランだった。佐伯くんは、何も言わずにその中に入っていく。時間が時間だから人は少ないけどちらちらとはいた。一番奥の席を案内されて。なんとなく、席に着くまで手は繋ぎっぱなしになっていた。
席に私達は向かい合って座る。水が置かれた後、そこでふう、と息を吐いた。
「えっと、どうして、レストランに……?」
「ここ、24時間空いてるレストラン。ここだったらある程度目があるからなんも出来ないし、腹減ったら食えるだろ?」
「そ、そうだね……」
「ま、話したくなかったら、メシ食うだけでもいいし」
す、と私の方にメニュー表を渡してくれた。
「え……」
「頼むなら、何でも好きなもの頼んでいいぞ。バイト代入ったから」
私は、少し戸惑ってしまう。何でも好きなもの、なんて言われたことない。ほとんど喋ったことのない人にそんなことを言われても、何を頼めばいいか分からない。あまり、お腹も空いていないかもしれない。
「そ、それじゃあ……、水、で……?」
「水はおかわり自由だ。もしかして、あんま腹減ってないのか?」
頷く。お腹が空いてない、もそうだし、どうすればいいか、も分からなかったから。
「そっか。それじゃあ、俺、先に頼むから、頼みたくなったら頼んで」
佐伯くんはベルを押して、来てくれた店員さんに対して、いくつかぽんぽんと注文を言っていた。
「お待たせしました。フライドポテトです」
店員さんがフライドポテトを持ってきてくれる。ふわっと漂う香ばしい匂い。
「食うか?」
「え、えっと……」
私が、どう答えればいいか分からずにしていた時だった。ぐう、とお腹の音が鳴った。
「ほら、ポテト」
「……。えっと……」
私の方にポテトの皿を差し出された。食べろ、と言わんばかりに。
「……、いただき、ます……」
恐る恐る、一つ口に入れた。濃い塩味のポテトを咀嚼して飲み込む。濃い塩味、じわりと、全身に染みこんでいくような感覚。
「どうだ?」
「……おい、しい」
瞬間、私の目から、涙が溢れてくる。なんだろう。急に、生き返った、というか、そういう気分。美味しいのと、我に返ったような感覚。私がもう一回泣き出したことによって、佐伯くんはぎょっとした表情を見せる。
「ポテト、嫌だったか?」
「あのね、…………」
ポテトのしょっぱさの残像を味わいながら、私は、泣きながら、これまでのことを話した。
「ともだちも、できない……」
「うん」
「すきなひとも、かのじょがいて……」
「うん」
「おとうさんと、おかあさんも、ずっと……」
「うん」
「もう、いなく、なりたかった……」
佐伯くんはずーっと、私の話を、頷いて訊いてくれた。支離滅裂で、頭の中のことを取り出したように話したのに、嫌な顔をせずに訊いてくれて。それが、私に取って嬉しかった。
どのぐらい時間が経ったんだろう。
「そっか。ありがとな。話してくれて」
佐伯くんは、ひどくやさしい声で、私の方を見て、微笑んでくれた。柔らかい、安心出来るような表情。なんだか、それだけで、今まで溜め込んでいた、暗いものが、全部消えた気がした。佐伯くんの瞳に映っていた私は、随分とすっきりとした表情をしている。
「うん、もう、ありがとう。大丈夫」
「そっか」
なんか、すっきりしたら、本格的に、お腹が空いてしまった。
「なんか、食べるか?」
「うん……」
メニュー表を開く。一番お手頃で美味しそうだな、と思ったグラタンをお願いした。
グラタンを食べて、ポテトをつまんで、二人で時間を過ごす。
「なるか、友達」
そんな時に、佐伯くんが突然口にする。
「え?」
「すぐ、じゃなくてもいいからさ」
「なんで……?」
「俺がなりたいの。それにさ、そうやって拠り所があるとさ、いいだろ」
「……うん」
「心のどこかにさ、“何かあったらこいつのとこに行けるから~” みたいなのがあれば、なんとなく楽だろ」
不意に思い出した、木場くんのこと。思い出して、目の奥がつん、となる。でもその感覚も、脳内の木場くんも、目の前で、心配そうな表情をしている佐伯くんに消されてしまった。
「どうした?」
「ううん、大丈夫。ありがとう……」
いつの間にか、朝になっていた。始発はもう何本か過ぎていて。私達は、元いた駅に戻ることになった。
「本当に、家まで送っていかなくて大丈夫か?」
「うん、大丈夫。ありがとう」
あの駅のそばの駐車場で車が止まる。家まで送っていくか、って言われたけれども断った。今日は土曜日。せっかくのお休み、運転させるのも申し訳ないな、って思って。
車から私達は降りた。元いた駅が見える。
「……」
駅の方を眺めながら、ふと、突然、振ってくるように思った。佐伯くん、どうして私のこと、助けてくれたんだろう。「飲み物を」みたいな理由であそこにいたけれど。その前から、私に声かけてくれたりとかしたから。
「そういえば、どうして、私のこと、声かけたの……?」
「気になってたんだよ。お前のこと」
「え……?」
「昔の俺と同じ顔してて。恩人に助けてもらえる前の俺の顔」
「恩人?」
「そ、俺の恩人。いろいろとすごい人。で、これは恩人の服装のまねっこ」
「そう、なんだね……」
でも、昔の俺、とか恩人、の話をしていた時に、少し寂しそうな、苦しそうな顔をしてたから、私はそれ以上は訊けなかった。
「……ごめんね」
「何が?」
「……その、いろいろ」
「いいよ。別に」
いろんな意味を含んだごめんね、だ。もしかして、私は、勘違いしていたのかもしれない。見た目とかで、怖い人、みたいに思ってしまったのかもしれない。
「そうだ。あの、お代、とかは。ガソリン代とか、ご飯代、とか……?」
奢る、とは言ったけれども、何も払わないのもなんだか申し訳ない。
「別に……、あ。じゃあ……」
少し考えた後、佐伯くんは言う。
「来週の月曜、文学の授業で俺と会う。それでいいよ」
「え……?」
佐伯くんはスマートフォンを取り出した。そして「連絡先、交換するか」と口にする。私は頷いて、スマートフォンの電源をようやく入れる。いくつもの通知が溜まっていた。
「あと、なんかあったら、俺にすぐ連絡すること。遠慮なんてしなくていいから。俺も、お前に連絡する」
「ありがとう……」
心配してくれている。なんだか嬉しかった。そして、私の胸の中には、柔らかな、どこかで抱いたことのある感覚が走っていた。
「じゃあな。また、月曜日、学校で」
「うん」
駐車場から出て、私は歩いていく。駅の中に入った時だった。着信音が響く。「お母さん」という文字。
「……もしもし、お母さん」
「冬乃!? 今、どこにいるの!? 元気!? 怪我とかしてない!?」
泣きながら、でも安心したって分かるお母さんの声。随分と、心配を掛けてしまったんだな、って思った。
「うん、ごめんね。いろいろあって……」
「ごめんね、はお母さん達のセリフ。今から迎えに行くから……!」
「ううん、大丈夫。ちゃんと帰れるから。今、電車、来るから」
ホームは既に人がちらちらといる。無人、ではあるけれど、大学とか、あと少し行った所の観光地の経由駅、だから人はいる。
ホームの底、を見る前に電車が来て、そして私は乗り込んだ。家に帰る方向の電車だ。
「冬乃!」
家の扉。鍵は閉まっていなかった。けど、開けた瞬間、お母さんが勢いよく私の方に向かっていく。お母さんが、どんな表情をしているか分からないまま、ぎゅううっ!と私の身体が力強く抱きしめられる。
「……ごめんね」
お父さんもお母さんも、仕事を休んでいた。お母さんも目を腫らしていて、お父さんも、今まで見たことないくらいに狼狽えている。
「……冬乃、大丈夫か?」
「……うん。ごめんなさい」
「……。ごめんね。一番大変なのは、冬乃だったのにね。なんで、お母さん、あんなに責めるようなこと、言っちゃったんだろうね……」
「……。お前に、期待を押しつけてたんだろう。すまなかった……」
父さんも、母さんも、私のことを、応援してくれていた。だから、その分、ショックだったのかもしれない。
「……大学、辞めたいか?」
「え……?」
「その、なんとかすれば、今からでも……」
「そう、お母さんも、もっと仕事を増やせば……!」
私は、首を横に振る。
「ありがとう。もう少し、頑張ってみる」
「そうか……」
「分かった。もし、つらかったら、言ってね。もう、あんなこと、言わないから」
「眠いでしょう。少し、休んだら?」
「……うん」
母さんの言葉で、私は部屋へと戻った。
ベッドの上、心地いい感触に浸り、うとうととしかけた時だった。LIMEの通知音。佐伯くんからLIMEが来ていた。
“大丈夫か?”
一文だけ。ぶっきらぼうな、でも優しさの伝わるメッセージ。
“ありがとう、おかげで、もう大丈夫“
返信を終えて、どこかふわふわとした、あたたかな感覚の中、私は瞼を閉じる。
頭の中を巡っていた、奈落の底みたいな光景は、全部、佐伯くんとの時間で塗りつぶされていた。