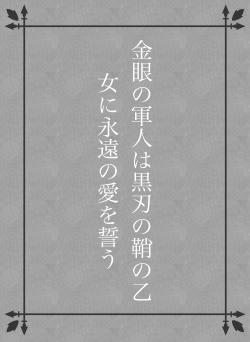『織田のやつ、遠距離恋愛は無理だって言われて彼女に振られたらしいぞ。平気そうにしてるけど、相当落ち込んでるんじゃないか?』
送別会の最中、そんな話を小耳に挟んだ。
(期待しちゃダメ)
幹事として次から次へとテーブルに届けられるビール瓶を運んでいた私は、入り口から最も遠い席に座る彼にチラリと目をやった。
時刻はすでに深夜零時を回っている。送別会も終盤だ。二十人ほどが集まる狭い座敷席には、最後の賑わいとばかりに底抜けに明るい笑い声が響いていた。
そんな中、ほとんどシラフの私は黙ってカシスオレンジの細いグラスを傾けた。
アルコール度数低めの飲みやすいカシスリキュールはどうも合わないみたいで、独特の甘ったるさで喉が焼けそうになる。
それでも私はグラスの中身を最後まで飲み干した。
カランと鳴った氷が、なけなしの勇気を後押ししてくれるように思える。
(今日しかない)
穂積理央、二十八歳。
――私は今夜この想いにケリをつけることにした。
◇
「織田が異動なんて寂しくなるな~」
「俺もです」
「あっちの営業所に行っても元気でな」
「ありがとうございます」
足もとが覚束ない泥酔気味の上司から思い切り肩をバシンと叩かれた織田くんは、いつものように顔をくしゃくしゃにして笑った。
同い年とは思えない童顔で、笑うと目が細くなるのが彼――織田政春の笑い方の特徴だ。
そんな織田くんと一緒に働くのも六月の月末、最後の金曜日である今日でおしまい。
彼は七月から飛行機で二時間もかかる遠く離れた街にある営業所へ異動するのだ。
「もう荷造りは済んでるのか?」
「はい、明日引っ越し業者が来る予定です」
「本当に急な話だったよなあ」
「そうですねえ。まあ、でもサラリーマンですから」
私は織田くんの後方約二メートルの辺りに陣取り、延々と続きそうな彼らの話に耳を傾けた。
織田くんの送別会は二次会、三次会を経て深夜零時過ぎにようやくお開きになった。
駅前にはまだ彼との別れを惜しむ社員が何人か残っている。
それでも、最終電車の到着を知らせるアナウンスが流れ始めると、改札の中にひとり、またひとりと吸い込まれていく。
「元気にやれよ!」
「ありがとうございます」
最後まで残った猛者たちを全員見送り終えたら、ようやく織田くんとふたりきりになる。
終電後の駅前ロータリーは閑散としていた。先ほど終電が発車したばかりの駅にはすでにシャッターが降りている。
人通りもまばらで、待ち合いのタクシー乗り場にすら人がいない。
ポツンとまばらに灯る頼りない街灯が月明かりよりも眩しい。
生ぬるい湿った風が吹き抜け、緊張で強張る頬をそっと撫でていった。
私は肩から下げたトートバッグを持つ手にぎゅっと力を込めた。
「織田くん」
覚悟を持って話しかけると、織田くんは改札に向かって振っていた腕を下ろし、クルリと後ろを振り返った。
「穂積、今日は送別会の幹事ありがとう。大変だっただろう」
「別に大したことじゃないから」
自分でも可愛くない言い方だと思う。
本当は織田くんのことを考えながら、どこがいいか一生懸命探したのに、ひねくれ者の私は正直に伝えられない。
そんな私を織田くんは大抵笑って許してくれる。
「ははっ。さっすが穂積。頼もしいな~」
笑いを誘ったつもりはなかったけれど、酔っぱらっているせいでツボに入ったのか彼はゲラゲラと声を上げた。
彼女に振られて落ち込んでいると聞いていたのに、そんな素振りは一切見られない。
(いつもと同じだ)
特に変わった様子は見られない彼の姿に、なぜかがっかりしている自分がいる。
やはり、織田くんにとって私は単なる同僚にすぎないようだ。
(これで最後なんて嘘みたい)
同期として五年間。同じ部署に配属されてから、ずっと一緒に切磋琢磨して働いてきたのに、来週から織田くんがいないのかと思うと、胸の奥がざわざわする。
私はまだ彼との別れを受け入れられていない。
「穂積は地下鉄だよな。あっちの駅まで送るよ」
ようやく笑いがおさまった織田くんは、地下鉄の駅がある大通りに足を向けた。
ここから最寄りの駅はふたつ。繁華街から近いJRと、少し離れた位置にある地下鉄。
JRの方が会社に近いので、地下鉄を使う人は少数派だ。
――だから、彼は知らないのだ。
「送ってもらわなくていいよ。もう終電はないから」
そう言うと、織田くんの足がピタリと止まった。
「……マジで?」
ひと呼吸遅れて、聞き返される。
「うん。終電の時間、間違えちゃった。最後まで残ってるなんて初めてだから」
もちろん、終電を逃したのはわざと。織田くんを言いくるめるための方便だ。
「最後まで残ってなくてもよかったのに……」
次の瞬間、織田くんははああっと深いため息をついた。
「いざというときに織田くんをお宅まで送るのも幹事の私の役目かなっと思って。送別会の主役が酔っ払って、醜態をさらすのはさすがに可哀想じゃん?」
まあ、そんな心配も結局杞憂に終わった。
織田くんは酩酊することなく送別会を終えたわけで、いわゆる建前というやつだ。
「それで?始発までいったいどうするつもり?」
「タクシーで帰る」
「金曜の夜だぞ。そんな簡単に捕まらないって」
「じゃあ歩いて帰る」
「歩いて帰る!?夜中にひとりで歩いていたら危ないと思わないのか?」
「平気だよ。車通りの激しい大通りを歩くから」
「平気なわけあるかよ……」
そう言うと織田くんは小難しい顔しながら眉間を押さえた。
そして、腹の中を探るかのように、じいっと私を見下ろす。本当に歩いて帰るつもりなのか、疑っているようだ。
(もしかしてバレてる?)
下心を見透かされた気がして、彼の顔がまともに見られなくなる。
私は織田くんと目を合わせないように、赤茶色の地面のタイルの継ぎ目に向かってそっと呟いた。
「織田くんの部屋に行きたいな」
織田くんの部屋はコンクリート打ちぱなっしのデザイナーズマンション。やや広めの1LDK。
ここから歩いて二十分ぐらいだ。
「だめ?」
冗談っぽくおどけたつもりだったが、織田くんが小さく息を吐いたのが聞こえた。
考えなしの発言が彼を困らせているのが、よくわかる。
「ふたりきりになったらさすがにまずいだろう?彼女でもないのに」
織田くんは強めの口調で、なけなしの訴えを退けた。
(これはキツイなあ……)
胸を走った痛みをこらえるように、トートバッグの持ち手を掴む力が強くなる。
織田くんの家なら何度もお邪魔したことがある。会社からも近いので、もっぱら宅飲みの会場にされていたから。
人目を気にせずゆっくり話ができる場所が他に思いつかなかったわけだが、織田くんはそんなつもり、さらさらないみたい。
「今は引っ越しの荷物で散らかってるし、とにかく無理だから」
頑なに拒絶されると、余計に落ち込んでしまう。
今日で最後だからと大目に見てもらえないみたい。
「しょうがないな。このままひとりで帰すわけにもいかないし、俺も付き合う。そうと決まれば、まずは腹ごしらえだな」
織田くんはそう言うと、近くのコンビニに向かって歩き始めた。私も後に続く。
「まだ食べるの?」
「酒ばっかり飲んでたからな。腹減ってんの」
主役である織田くんのテーブルには代わるがわる人がやって来ては、グラスに酒を注いでいった。
織田くんは誰ひとりとせず乾杯を断らず、全員に感謝の言葉を述べていた。
誰にでも優しくて、面倒見が良くて、頼りになるから、慕う人がたくさんいたのだろう。
送別会で隣に座っていた後輩ちゃんから密かに想いを寄せられていたなんて、カメより鈍い織田くんは気づいていない。
彼女が織田くんに話しかける度に、私がヤキモキしていたことすらも知らなかったでしょう?
「穂積はこれだろ?」
コンビニに辿り着いた私たちは、食べ物を調達する前に飲み物を選ぶことにした。
織田くんが冷蔵庫から取り出したのは私がいつも飲んでいる炭酸水。
(覚えていてくれたんだ)
さり気ない気遣いに、ソワソワと落ち着かなくなる。
織田くんは自分にはプロテインバーとゼリー飲料、それとミネラルウォーターを選び、カゴをレジまで持っていった。
「ピリ辛キチンをふたつください」
ダメ押しでレジ横のホットスナックを買ったら、イートインコーナーに横並びで座りふたりしてコンビニチキンを頬張る。
「うわ~おいしいっ!」
「この時間のチキンは美味すぎるよな」
自分で思っていた以上にお腹が空いていたのか、コンビニキチンに夢中になってかぶりつく。
右隣では織田くんがあっという間にチキンを完食していた。
「よく入るね。送別会でも結構食べてなかった?」
「お通しのアジの南蛮漬けばっかりな。まったく、あいつら悪ふざけの極みだろ」
一次会の会場となった和食ダイニングでは、織田くんの好物であるアジの南蛮漬けがお通しだった。
誰が最初か忘れてしまったけれど、王様に捧げる貢物のごとく織田くんのもとに南蛮漬けが集結していた。
「おかげさまで胃の中でアジが泳ぎ回ってる。肉で中和しないと生態系が崩れそう」
「あははっ!」
断ればいいのに、律儀にすべて胃の中に収めるところが織田くんらしい。
「ひらきじゃなくて、頭が残ってるタイプだったもんねー」
「そうそう。一口で食べるのにちょうどいい大きさの……」
「ふふっ!」
思い出したらより笑えてくる。あの時の織田くんはまるでペンギンみたいにアジをせっせと口に運んでいた。
「もう一個食べようか迷うな」
すっかり手持ち無沙汰になった織田くんは、悩まし気にレジをチラチラと眺め始めた。
「そんなにコンビニチキン、好きだっけ?」
「本当は肉まんの方が好きだけどな。ほら今は夏だから」
冬場は大活躍の蒸し器だが、残念ながら今は空っぽだ。
「冬場は残業で疲れたときにいつも肉まんを食べながら帰ってたな」
「へえ、そうなんだ」
「悲しきかな。健康診断の結果が悪くて、冬の終わりとともにお別れしたんだよなあ……」
哀愁が漂うため息に、私は思わず吹き出した。こういう風に飾らないところが織田くんの美点だ。
「笑うなよ!」
「ごめん、ごめん!」
一応謝るけれど、先に笑わせてきたのはそちらだ。私に落ち度はないと思う。
「ほら食べ終わったら行くぞ」
「うん」
織田くんから遅れること五分。ようやくチキンを完食した私は椅子から立ち上がった。
コンビニの外に出ると、夜の闇が一層濃くなっていた。夜明けまであとどれぐらいの時間が残されているだろう。
◇
織田くんが連れてきてくれたのは、朝八時まで営業している温浴施設だった。
「穂積、こっち」
織田くんはあちこち視線を彷徨わせていた私を手招きした。慣れているのか案内図を見ずにスタスタと歩いていく。
「いつも来てるの?」
「まあな」
手際がいいと思ったら、どうやら織田くん御用達だったらしい。
ささっと受付を済ませ、館内着とタオルのセットを受け取ったら、浴場の入口へ向かう。
「じゃあ。三十分後にここ集合な」
織田くんはそう言うと、男湯の暖簾の向こうに消えていった。
私も彼に倣い、女湯へ足を踏み入れる。指定されたロッカーに荷物を入れ、服を脱いでいるときにはたと気がつく。
甚平タイプのゆるゆるの館内着は色気もへったくれもない。
(まあ、今さら取り繕ったってしょうがないか)
同期として切磋琢磨した五年間で、織田くんにはあられもない姿を何回も目撃されている。なんなら尻拭いまでさせている。
(取引先に嫌味を言われて悔しくて号泣したのは二年目だっけ?階段ですっ転んで、足を捻ったのは割と最近だったかも……)
あのとき、織田くんは辛抱強く愚痴を聞いてくれて、プレゼン資料の見直しにも付き合ってくれた。最寄りの薬局まで湿布を買いに走り、帰りは家まで送ってくれた。
こうして考えてみると、織田くんには迷惑をかけてばかりだ。
今だって現在進行形で迷惑をかけている。本当なら今頃彼は明日の引っ越しに備え、家のベッドで寝ているはずだったのに。
(どうやって切り出そう……)
私は湯船から立ち上る湯気を眺めながら、ぼんやり考えた。
――完全にタイミングを逃してしまった。
のんびりコンビニチキンを食べて、風呂に浸かっている場合ではない。
このままでは何も伝えられないまま、夜が明けてしまう。
(ちゃんと言えるかな)
だんだんと心配になってくる。わざと終電を逃しておいてなにも言えなければ、織田くんを引き留めた意味がない。
うんうん唸ったものの、残念ながら考えはまとまらず、湯当たりする前にお風呂をあとにする。
髪を乾かし館内着に着替えたら、スマホだけを持ちだし、暖簾を再びくぐり抜ける。
織田くんはどこかと視線を巡らせれば、廊下の隅にあるベンチに腰掛けていた。
「お待たせ」
そっと駆け寄り隣に座ると、スマホを覗いていた織田くんが顔を上げる。
「予想より全然早かったな。もっと長風呂かと思ってた」
普段はお互いスーツとオフィスカジュアル同士。装いが違うだけで、なぜかドギマギしてしまう。これだけは何回経験しても慣れない。
「穂積も飲む?奢るよ」
織田くんの傍らには飲みかけのコーヒー牛乳の瓶が置いてあった。
お言葉に甘えて、私も一本ご馳走になることにした。
「風呂上がりのコーヒー牛乳ってなんで美味いんだろうな」
「本能が欲してるから?」
「プールの後にアイスが食べたくなるのもおんなじ原理だよなー」
真夜中って不思議だ。どうでもいい会話がいつまでも続く上に、なんでもない出来事がとてつもない哲学を秘めているように感じられる。
深夜の温浴施設にはそれなりに人がいるが、皆似たような会話を繰り広げているのかもしれない。
「深夜なのに結構人が多いんだね」
「みんな始発待ちなんだろ」
「ふーん」
「もしかして、終電逃すの初めて?」
「そうだね」
そう答えると、織田くんは途端に怪訝そうな顔つきになった。
終電を逃したことがないって、そんなにおかしい?
「学生時代は門限が厳しかったし、社会人になってからも終電まで外にいるなんてなかったなー」
「まあ、でも。そうだよな。穂積ってなんだかんだいって、いいとこのお嬢様だしな。切符の買い方も知らないぐらい」
「もうっ!その話はやめて!」
私は恥ずかしさのあまり、頭を抱えて悶えた。
あれは入社したての新人の頃。出張で新幹線に乗る必要があった際に、チケットの発券方法がわからず、恥を忍んでこっそり織田くんに尋ねたのだ。
旅行の時はたいてい誰かと一緒だったし、ひとりで券売機を使うなんて滅多になかったんだから仕方ない。
「私たち、本当に正反対だよね」
童顔でついついからかわれがちだけれど、織田くんは見た目以上のしっかり者。
対する私は見かけこそ真面目だが、まあまあの粗忽者。
(だからこそ余計に織田くんに惹かれたのかもしれない)
自分にはない輝きを放っているからこそ、憧れを抱いてしまうものなのかもしれない。
(織田くんはどういうつもりなんだろう)
朝まで一緒にいてくれるのは嬉しいけれど、肝心の織田くんの気持ちがちっともわからない。
そんな私の心情など知ってか知らずか、織田くんは最後に残ったコーヒー牛乳を飲み干すと、スッと立ち上がった。
「空き瓶片付けてくるから、ここで待ってて」
「うん。わかった」
私の分の空き瓶を受け取ると、自販機の方へ歩いて行く。
ひとりになり、ふと館内にある時計に目をやると衝撃が走る。
(うわっ!もう三時?)
知らぬ間に針が進んでいたようだ。
まだ何も話せていないのに、時間だけが経っている。なんてこった。
私が焦り始めたそのときだ。
「お姉さん、ひとり?」
私は見知らぬ男性二人組に話しかけられた。ニヤニヤと笑っていて、どう見ても感じが悪い。
「え、あの……」
なぜ話しかけられたのかわからず、反応が遅れてしまう。最初に強く拒絶しなかったのが災いして、彼らはとんだ勘違いをしていく。
「ひとりで暇してるんでしょ?よかったら俺たちとどっかいかない?」
終電後の温浴施設は格好のナンパスポットでもあるらしい。そんなの聞いてない。
「なあ――」
「穂積」
聞き慣れた声がナンパ男たちの軽薄な台詞を遮って安堵する。
「織田くん」
私は助けを求めるように戻ってきた織田くんを仰ぎ見た。
「彼女になんか用?」
織田くんがギロリと睨みつけると、男たちはそそくさと退散していった。
「目を離してごめん」
「織田くんが悪いわけじゃないから」
「もう少しゆっくりしたかったけど、もう出るか」
先ほどまで漂っていたなごやかな雰囲気は、どこかに消え失せていた。
◇
温浴施設を出ると、既に空が明るくなり始めていた。
私たちは無言のまま大通りを歩き、最後に小さな公園へたどり着いた。
「眠くない?」
「平気」
虚勢を張ったわけじゃない。自分でも不思議なほど眠気を感じなかった。
夜明けまでは、あとわずか。噴水の前にあったベンチにふたりで腰掛け、その時を今か今かと待つ。
(いつもの公園じゃないみたい)
昼間は大勢の人で賑わっている公園が、時間帯を変えるだけで全く異なる顔を見せる。
明け方にさえずる鳥の声、風で揺れる木々のざわめきに、人間よりもその他の生き物の息吹を強く感じる。
ありふれた日常の中に、こんな風景があるなんて知らなかった。
しかし、そんな非日常もそろそろ終わりを告げる。
役目を終えた夜のカーテンがゆっくりと空を駆け上り、青とオレンジのグラデーションの境目がなくなっていく。
喉の渇きをおぼえた私はトートバッグから飲みかけの炭酸水のボトルを取り出した。
蓋を回すとプシュッと炭酸が抜ける。パチパチと弾けていた泡の音は時間が経つと次第に聞こえなくなっていった。
(この想いもいつか消える)
どれだけ固く封じ込めたって蓋を開けてしまえば、終わりが始まる。
降り積もったこの想いも、口にしたら消えてなくなってしまう?
そんなことを考えながら炭酸水を飲み干すと、今度は織田くんがおもむろに口を開いた。
「あのさ、俺になんか話があるんだろう?」
核心をついた問いかけに、私の心臓がドクンドクンと早鐘を打つ。
(言わなきゃ)
『今までありがとう。あっちに行っても頑張ってね』
彼のためにも笑顔で見送るって決めていたはずなのに、唇が震えて上手く声が出せなかった。
これ以上、先延ばしにはできない。弾けて消えた想いの行く末をまだ考えたくないなんて、わがままにもほどがある。
それでも織田くんは私が話し出すのを辛抱強く待ってくれた。
私は現実逃避のように、ぎゅっと目を瞑った。その刹那、どこかで電車が揺れ動く規則正しい音が耳に飛び込んでくる。
「始発が動き出したみたいだね。私、もう行くね」
私はそう言うとベンチから立ち上がり、トートバッグを引っ掴んで走り出した。
「穂積っ!」
私は織田くんの声を振り切り、猛然と走った。走って走って、公園が見なくなったところでようやく足を止める。
息切れしながら祈るような想いで空を見上げる。
(お願い。まだ朝にならないでっ……)
朝になったら織田くんがこの街からいなくなってしまう。
髪を無造作にかき上げるところも、メールをチェックする真剣な横顔とか、袖をまくる仕草だって、まだ忘れたくない。
(織田くんが好き)
最後の思い出にするつもりだったのに、たったひと晩の間にまた『好き』が増えてしまった。
『さよなら』なんて言えない。だからといって、『好き』だとも伝えられない。
『遠距離恋愛なんて私にはできない。だから……ただの同僚に戻ろう』
――全部終わらせたのは他ならぬ私だから。
(ああ、もう……。最悪……)
彼への未練を断ち切るためにキチンとお別れを言うつもりだったのに、とんだ誤算だ。
でも、これでよかったのかもしれない。
織田くんは私のことなんてとっくに忘れて前を向いている。
きっと何年後かに再会した時には、恋心なんてすっかり消え去っていることだろう。
私は目尻に滲んだ涙を指で拭い、再び歩き始めた。やみくもに走ったせいで、ここがどこかもわからない。
(始発も動き出したみたいだし帰ろう)
地下鉄の始発まではまだ少し時間があるが、どこかで適当に時間を潰そう。
スマホのナビを頼りにひとまず駅へ向かおうとしたそのとき、誰かにグイっと肩を掴まれた。
「理央っ!」
「な、んで?」
私の肩を掴んだのは汗だくの織田くんだった。
「お前が泣きながら走っていくからだろう!」
織田くんは私の左手をむんずと掴み、駅とは逆方向へ大通りを駆け抜けていく。
一カ月ぶりに重ね合わせた左手の温もりに、涙がこぼれ落ちそうになる。
「ごめんね、政春くん」
追いかけてきてくれた嬉しさと後ろめたさで謝れば、織田くんが呆れたように言い放つ。
「……ただの同僚に戻ろうって言ったのはそっちのくせに」
社内恋愛なんて、誰かにバレたら面倒だからと秘密の関係を続けて約二年。
最初に彼から転勤を知らされた時、遠距離恋愛なんて絶対に無理だと思った。
遠くなる距離に絶望して、気持ちが離れてしまうのが怖かった。
それならばいっそ、仲の良かった今の関係のまますべてを終わらせた方がいいんじゃないかって、自分から別れを告げた。
でも、よくわかった。
私にはまだ織田くんが必要だ。
「私、まだ政春くんの彼女でいていいかな?」
織田くんの手を握り返し、震える声で尋ねる。
いつもみたいに名前で呼んでくれたということは期待してもいい?
「あーもう!」
織田くんは人目を憚らず叫び、うなじを掻きむしった。次の瞬間、私は織田くんの腕の中にすっぽりと包まれていた。
「だから距離なんて関係ないって言ったじゃん……!」
抱きしめられる腕の力強さに彼の苦悩を知る。
(私だけじゃないんだ)
安心しきって胸に顔を埋めると、ドクドクと波打つ心臓の鼓動を感じた。
汗で湿り気を帯びたシャツがこんなにも愛おしい。
「会いたいって言われたら、すぐに飛んでいくから」
「うん」
「電話もする」
「うん」
「メッセージもすぐに返信するようにするから……」
「それはウソでしょ」
仕事の時は即レスのくせにプライベートのときは返信が遅い。今まで何度このネタで喧嘩したことか。
「少しは信用しろよ……」
これには織田くんも渋い表情だった。
たぶん、メッセージの返信速度は今後も変わらないだろう。それでもかまわない。
「とりあえず、うちに来るか?」
「彼女じゃないやつは入れないって言ってたじゃん」
「ごめん、俺が悪かった。許してください」
恨めしげに睨むと、たまらず織田くんは両手を合わせ許しを請う。
数時間後には離ればなれになってしまう私たちに残された時間はあまりにも少ない。
抱きしめられているうちに、空には太陽が昇った。
降り注ぐ陽光はまるで私たちの門出を祝福しているみたい。
いつの間にか夜明けは怖くなくなっていた。
おわり