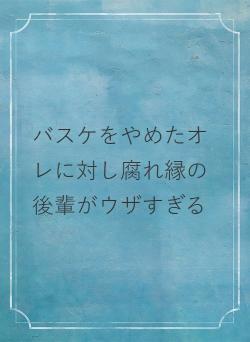「ここです」
私はその言葉を聞き、上を見上げる。そこには立派な一軒家があった。
「ここなのね」
そう、私は呟き、中に入る。中は暗い。当然だ。今はもう1時半、明るい方がおかしいのだから。
すぐに彼の部屋へと上げられた。
「ちょっと待ってくださいね、今すぐ僕がもう一枚の布団を持ってきますから」
そう言って工藤君は移動した。
一人になると途端に心細くなる。
暗い部屋の中、色々と雑念が私に襲い掛かる。
少し忘れていたはずなのに。
私はそっと、スカートのすそを掴む。これも私が、今日のために精一杯おしゃれしてきたものだ。
ああ、無駄になったなっと。しかも今も体調がしんどいし。イライラがぶり返してくる。
「ああ、もう」
大声で叫ぶわけには行かない。私はそっと静かに叫ぶ。
工藤君、早く戻ってきて。
「ただいま」
そう、工藤君は笑いかけてくれる。
私は、そんな工藤君の足に縋りついた。
「どうしたんですか?」
工藤君は、その場で座り込み、私の顔をじっと見る。
「そんな不安がらなくても、僕は先輩の味方です。安心してください」
そう、にっこりと笑う彼。
「どこにもいかないで」
「どこにもいきません」
その言葉を聞いて、私はほっとした。あの男のように別の場所へと、私を置いて行くような真似はしないんだと。
「ねえ、工藤君、どうしてそんなに優しいの?」
「僕は優しくないですよ。ただ、今優しいのはそうですね、先輩の事が心配だからです」
「心配って……」
「僕は先輩の笑顔が好きですから」
その笑顔でその言葉を言われたら、私も笑顔になるしかないよ。
「ありがとう」
そう言って私は彼の足から手を離した。
「隣で寝るのがいい? それとも離れて寝たい?」
悪戯っぽく言う工藤君。
「隣で寝たい、かな」
不安な気持ちがいっぱいだ。隣に人の気配を感じたほうが、寝やすいと思う。
それに体調も良くない。いざという時に誰かに面倒を見てもらいたいという気持ちもある。
「分かった」
そう微笑んで彼は自分のお布団の隣に布団を置いた。
本当に工藤君の家に泊まるんだなと、今再実感する。
一応工藤君も男の子だ。だけど、童顔な彼は安心が出来る。
だって、純粋な良心のみで動いている感じがするのだから。
「ねえ、先輩」
「どう……したの?」
「体調はどうですか?」
「ん、と。だいぶましにはなったかな」
「それは良かった」
そう言うと、工藤君は私の体に触れてきた。
「な、なに?」
「先輩から、あの男の姿を消すためですよ」
それを聞いて工藤君の方に振り返ると、工藤君は少し悪い顔をしていた。
あれ、手は出さないって言ってたのに。
「先輩って疑わないんですね。僕だって一応男の子ですよ」
「そ、そうだけど。工藤君って酷いことしないじゃない」
「それは先輩から見た僕ですよ」
そして優しく抱きしめてくれる。
「先輩、僕からこれからの提案をさせてもらえませんか?」
「どうしたの?」
私は訊く。急に雰囲気が変わって行った。
「僕と付き合ってくれませんか?」
唐突でびっくりした。
急に酒で訛っていた脳が活性化された気がした。
「急にどうしたの?」
「僕は、そんな立派な人間ではありません。僕はずっと先輩に恋焦がれてきたんです」
「ずっと?」
という事はあの、文フリで一緒に本を売った時も、私の惚気話を聞いてた時も、学園祭の準備を一緒にしてた時も私のことを思ってたの?
「ごめんなさい。僕が今していることはクズだと思います。でも、僕はずっと先輩の惚気話をずっと、恨めしく思いながら聞いていたんです。だって、僕は先輩の事が好きなんですから。」
そうだったんだ。実は酷いことをしてたんだなと、ふと感じた。
「ごめんなさい。こんなタイミングで告白してしまって……ごめんなさい、忘れてください」
それからしばらく時間が経った。
私は今工藤君と背中合わせで寝ている。けれど、今も先程の言葉が脳裏に残っている。
『僕は先輩の事が好きなんですから』
その言葉が。
幸い強引に襲おうなんて言う気はなさそうだ。
それは安心だし、先ほどの工藤君のいいぶりからにしても、きっと悪いことをしたと思っているのだろう。
そう、私を好意を持って家に連れてきたことを。バッティングセンターに連れてきてしまったことを。
もしかしたらバッティングセンターに連れてきたことでさえ、わざとなのかもしれない。
でも、それだけで、工藤君の事を嫌えるかと言われると、答えは完全にNOだと思う。
眠たい頭で考える。私は彼の好意に対してどういう答えを返したらいいのだろう。
唯一恨むべくは今気持ちを口にしたことだろうか。
何しろ、そのせいでまた頭痛がしてきた。
色々と頭が働きすぎて、また気持ち悪くなってきた。
うぅ、眠い。
でも、気持ちは言わなければ。そう、今脳に浮かんでいる言葉を。
「私を……」
その言葉を聞いて工藤君がこちらを見る。
「私を、好きにさせるなら努力してよ」
「というと?」
「私からあの男の幻想を奪う努力をして」
私はそう言った。
すると、彼は私に抱き着いてきた。
「ちょっ」
「好きにならせる努力をしたらいいんでしょ」
「そう言われても……」
確か、
「襲わない約束じゃなかったっけ」
「そうでした?」
にやにやとしている。
「でも、そう言うならやめます」
「っ」
肌の感触がなくなった瞬間、『寂しい』という感情が芽生えてしまった。
そして私は離れようとする彼のパジャマを一掴みした。
「先輩が僕の事を求めるんですね」
そう言って彼はまた酒をひと飲みする。
その後、私にまた触れて来る。
決してエッチな事ではない。ただのじゃれくりあいというのが正解だろう。
だけど、なんとなくそれが楽しくて、
この夜が終わってほしくないとさえ思った。
この二人の空間が終わってほしくないって。
私にとって工藤君はただの後輩だった。かわいい、私についてくる健気な後輩。
なのに、こんな一面を備えているとは本当に思っていなかった。
私は……彼の気持ちを受け入れるべきなのではないだろうか。動機は不純だけど、それでも私を慰めてくれたのだし。
「ねえ、工藤君、バッティングセンターに連れて行ったのは故意? それともうっかり?」
私が体調を崩すことを理解してなのかどうかだ。
「それはうっかりです。家に連れて行くのは断られたので、どこかでストレス発散してもらう予定でした」
「そう、それを聞けて安心した」
私は彼の方をじっと見る。
「よく見たら、流伽よりもいい男ね」
「え?」
私の突然の言葉に驚いた様子を見せて来る。
「とりあえず答えは明日出すわ。酒が抜けきった後にね」
「はいっ!!」
そう、元気よく言う彼の姿を見ると、私はドキッと顔を紅潮させてしまった。
「照れてるんですか?」
「照れてない!」
わたしはそう、強く否定すると、睡魔が襲い掛かりすぐに睡眠へと落ちた。