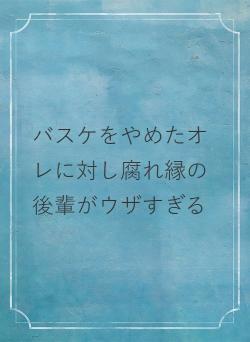「先輩?」
声が聞こえる。
「先輩!!」
私は重たい瞼を開ける。するとそこにいたのは私の入っている部活。文芸部の後輩、工藤孝明くんだ。
なんでここにいるんだろ。
いや……ああ、そうか。そう言えばここは私の大学の近く。
いても不思議じゃないか。
「先輩、本当に何があったんですか?」
「お酒を飲み過ぎたのよ。所謂自棄酒っていうやつね」
そう、小声で言葉を紡いでいく。
「そうですか」
そして、彼はスマホを開く。時刻を確認しているのだろう。
「終電大丈夫ですか?」
「たぶん大丈夫じゃないかも」
終電はもうない。もう逃した。否、わざと逃した。
「じゃあ僕の家に来ませんか?」
その発言は予想外だった。だって、男の人が自分から誘うって。
いや、それは普通だ。
なにもおかしなことはしていないのだから。
「それは……」
私だって女だ。男の人の家にはいったらどうなるかなんてわかっている。
私はこの子、工藤君を信用してないわけじゃない。でも、一人暮らしの彼の家に行くにはリスクが高いのだ。
「だめ」
私ははっきりと否定した。すると彼は困ったようにまゆをひそめた。
そして言い放った。
「何があったんですか?」
その言葉に私はまた悲しみを思い出した。また酒の高揚感が勝っている。けど、
言いたくなってしまう。
私の悲しみを全て。
「めんどくさい話だけどいいの?」
私はおずおずと訊いた。
その言葉に対して工藤君は黙って頷いた。
私はそれに安心した。だって、訊いてほしかったから。心の中の子のストレスを吐き出したかったから。
「じゃあ聞いてくれる? 私の話を」
そして私は今までの事を話した。今までの彼との日々を彼との出会いを、そして昨日の出来事を。
彼は私の元カレの馴れ初めとか惚気話とかを知ってるはずだ。
だって、私は普段からそう言う話をしてたから。
だけど、彼は黙って私の話を聞いてくれた。
ありがたい。感謝しなきゃならない。だって、私の心は多少晴れたのだから。
「なるほど」
彼はうんうんと頷く。
「それはつらかったですね」
そして慰めてくれた。ありがたい。
「なら、僕と一緒に来て欲しい場所があるんです」
「どこ?」
「着たらわかりますよ」
結局どこに行くのかも教えてもらえないまま彼について行く。
謎だ。
「ここです」
「ここは?」
暗いからよく見えないけど、ここはバッティングセンターだ。
「まだやってるの?」
「はい、ここは僕の親が経営する店なんです」
「勝手に使っていいの?」
「はい、あとで僕は起こられるかもしれませんが」
そうてへっと笑う工藤君。今は彼のやさしさに甘えよう。
「最初はどれくらいがいいの?」
「そうですね。70キロにしてみましょう」
「それが最適なの?」
「いえ、僕は野球やったことないので。でも、すかっとしますよ」
その言葉を聞き、「お願いします」と言った。
早速球が飛び出してきた。私はバッドが出なかった。
だって速くはないけど、バットに当てるのは難しすぎる。
それにお酒も聞いているから、あまり強くは振れないし。
プロの人は150キロとかのボールを打つというけど、それは凄い事なんだ。
「速度下げましょうか?」
「これでいい」
私はそう言って球が飛ばされる。
まだふらふらするし、中々狙えない。けど、なんとなく当てたい。そう、思い集中する。
三球目、私は捉えた。
いい当たりじゃないと分かるけど、なんだか楽しい。
「なんで別の女が好きなのよ」
打つ。
「なんで好きじゃなくなったタイミングで別れ話をしないのよ」
打つ。
「なんで、高級レストランで振る話なのよ」
打つ。
「勘違いするじゃない」
打つ打つ打つ。
苛々を解消しながらひたすらにバッドを振った。
素かっという感覚ではないけど、でも段々とストレスが解消されていく感じがする。
だけど、あれ、段々としんどくなってくる。
「あれ?」
体がふらふらとしてくる。めまいがしてくる。体に力が入らない。
あれ、おかしいな。気持ち悪くなってきた。
「大丈夫ですか――」
その言葉を最後に、私の意識は失われた。
「目が覚めましたか?」
私が目を開けると、目の前に工藤君の姿があった。
「あれから目を覚まさないので心配したんですよ」
「私、気絶してたの?」
「はい、バッティングセンターで」
私が寝転がっている場所、そこはベンチの上だった。
うっ、又吐き気が。
私は、手で口を押えるとすぐさま胃の中のものが吐き出される。
「ごめんなさい。酒飲んでるときに運動が好ましくないこと忘れてました」
そうだった。私は酒を飲んでいた。そりゃ吐き気がするわけだ。
というか、常識的に考えたら明らかにそうじゃない。私馬鹿だ。
まるで二日酔いの症状だ。いや、元々そこまでの酒を飲み切っていたのだった。
それがさらにひどくなったというだけの事。
「ごめんね、また迷惑をかけるね」
「迷惑なんてかけてくださいよ」
そう胸を強くたたいた。
「僕は先輩の後輩ですから」
そう、胸をトンと叩く彼の姿は何となく逞しいと思った。
「それに今の状況は半分は僕のせいですから」
確かにバッティングセンターに誘ったのは工藤君だ。
とはいえ、そばにいてくれるのはありがたい。とりあえず気持ち悪い。
「うぅ」
私は彼の服を掴む。
「どこか寝られる場所を」
そう呟き、工藤君は上を見る。
「少し歩けますか?」
「ええ、歩けるけど」
「なら、僕の家に来ませんか?」
その言葉に私は思わず「え?」と呟いた。
「欲とかじゃありません。寝られる場所をと思いまして」
そういう事、私は理解した。
「分かった」
私は頷いた。
「その代わり手は出さないでね」
「出すわけないですよ。僕の命を懸けます」
「あまり信用ならない代償ね」
「なら、10万円で」
急に、現実的な数字が出てきてクスッと笑った。
勿論本当に襲い掛かれて来られたら十万じゃすまないと思うけど。
「立てますか?」
「う、うん」
私は彼の肩を借りながら歩き出す。
まだ足元がおぼつかない。
まだ、しんどいのだと理解した。
なんだか情けない。私は振られたストレスで酒を浴びるほど飲み、結果として工藤君に迷惑をかけているのだから。
私の歩みの遅さのせいで、工藤君の足も遅くなっている。
申し訳ない事ばかりだ。