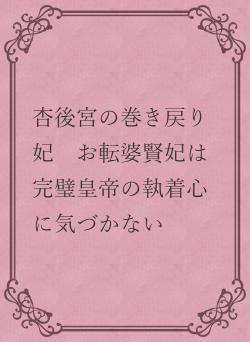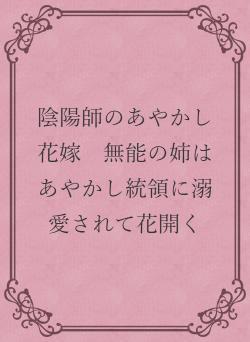そのころのわたしたちといえば、金曜日の夜に渋谷のTSUTAYAで待ち合わせをして、すぐ近くの映画館でレイトショーを観るのがお決まりのデートコースだった。
大学四年生の最後の日も、ちょうど金曜日だった。
地元の高校で出会い、東京の違う大学に進んだわたしたち。
音楽や小説が好きというだいたい同じ趣味を持ち、ブロッコリーと納豆と満員電車がきらいで、ご飯屋さんでメニューを選ぶとだいたい同じものを指さす。
彼は、わたしとの共通点を見つけるたびに、「これって運命だね」なんて歯の浮くようなセリフをうれしそうに言う。そんなとき、わたしは恥ずかしいようなくすぐったいような気持ちになるのだ。
高校生のときも、大学生になってサークルやゼミで忙しくなっても、わたしたちは変わらなかった。
だから、社会人になってもきっと大丈夫――
わたし――高城依織は、渋谷のTSUTAYAでぼうっと本棚を眺めていた。
偶然立ち止まったのは、いつもなら通り過ぎる写真集コーナー。こぢんまりした一角で平積みされた写真集の表紙に写る、フィルムカメラを構えた女性がなぜか目に留まった。
ワンピースを着た女性は、日本家屋の庭のようなところに立っていた。取るに足らない日常の風景、そんなテーマなのだろうか。
帯の推薦文や裏表紙を眺めていると、ふとタイトルに目が行く。
『わたしたちの、これから』
箔押しされたタイトルを指でなぞる。
うっすらと冷たくて、ほんのりひりひりする独特の感触がした。
中を見ようと手に取ったタイミングで、背後から大きな影が落ちた。
「見ぃつけた」
ひそひそと声をかけられてうしろを振り返ると、彼――喜野遥が立っていた。
わたしと目が合うと、いつものように口がにぃっと横に開いて笑顔になる。
彼の笑顔はテディベアみたいだと、わたしはひそかに思っている。
目が小さくて人懐っこい顔立ちの彼は、長身なもののどちらかというと細身なのにもかかわらず、笑うとなぜかテディベアを思い出させる。あの、IKEAに売っているおっきいくまの人形にそっくりなのだ。
本人に言っても伝わらないと思うから、わたしだけの秘密なんだけど。
「いつもの階にいないから探したよ」
遥は口では文句を言いつつも、にこにこ笑顔のままで、まったく怒っているようには見えない。
「ごめん、連絡入れておけばよかった」
謝らなければいけないのに、つられて頬がゆるんでしまう。
それを見た遥は、笑顔のまま口をとがらせた。
「依織、本屋でスマホ見ないでしょ?」
「そんなことないよ。調べものとかするときもあるし」
ちょうど今日、読みたいと思っていた新刊のタイトルを思い出せず、探し回ったあげくに見つからなかったので、仕方なく検索の力に頼ったはずだ。
ショルダーバッグからスマホを取り出してみると、ロック画面に遥からのメッセージが表示されていた。
遥は「ほら」と言い、いたずらが成功した子どものように笑う。本屋独特の橙色の照明が、まるで写真集の彼女のように、彼の笑顔を思い出のなかの一コマのように照らした。
この取るに足らないやり取りや景色も、あしたになれば思い出になる。そして、いつかは忘れてしまう。
わたしはむっとしていたことも忘れて、なんとも言えない気持ちになる。
すぐにはっとして、頭に浮かんだことを振り払った。
「……着くの早かったね」
「あ、そうそう。教授の話が思ったよりも早く終わったんだ」
遥は今日、ゼミの送別会に参加していた。
「飲み会になると話が長いんだ。普段は質問しないと教えてくれないくせに」と遥からいつも愚痴を聞いていたから、もっと遅くなると思っていたのだ。
送別会といいつつも、大学近くの飲み屋で開かれるただの飲み会だそうで、今日の遥はラフな装いだった。濃い緑色のカジュアルなセーターからは白いTシャツがのぞいていて、ジーンズに、いつもの大きなリュックを背負っている。
一方のわたしは予定がなかったものの、ついこのあいだ古着屋で買った花柄のワンピースを大学生のうちに着ておきたくて、昼間から渋谷をぶらついていた。
「最後の日なのにね。あ、最後の日だからなのかな」
「いや、ただ酔いつぶれただけだよ。最寄りが近い子たちが送っていった」
時刻はすでに二十一時半をまわっていた。
スマホを取り出したついでに、今日はどんな映画が上映されているか調べる。
きのう公開されたばかりの洋画、アニメ映画、モキュメンタリー風のホラー映画の三択。時間が遅いこともあって、いまから観られる映画はかなり限られていた。
――このなかだったら強く惹かれる作品はないけど、しいて言うなら洋画かな。
洋楽、とくにイギリスとアメリカのロックバンドが好きな遥も、きっと洋画を選ぶだろう。そう思いつつ、「観たいのある?」と声をかける。
「どうしようかな……あ、これはどう?」
彼が指さしたのは、最近話題のモキュメンタリー風のホラー映画だった。
「え?」
思わず彼を見上げると、目が合う。
わたしの勢いに驚いたのか、そこにテディベアの笑顔はなかった。
遥もわたしもホラーはきらいではないが、進んでは観ないほうだった。だから、彼の選択を意外に思ったのだ。
それに、いつもなにかを選ぶときは、同じものを指さしていたのに――
「こういうの、あんまり好きじゃないと思っていたから、ちょっとびっくりしちゃった」
「うーん。まあ、たまには気分を換えてみるのもいいかなって」
彼はそう言うと、へらりと笑った。
わたしは「そう」と返すことしかできない。
「あと十五分ではじまるっぽいね。そろそろ行こうか。依織、この写真集、買うの?」
「うん、そうしようかな」
手に持っていた写真集をあらためて見る。帯は折れていないし、カバーに傷も見当たらない。
レジを探して歩き出そうとするわたしとは対照的に、遥は動かなかった。
不思議に思って振り返ると、遥は不満があるようにもただ眠たいようにも見える、なんとも言えない顔をしていた。
「どうしたの?」
「……いや、依織こそめずらしいなと思って。活字中毒はやめたの?」
「活字中毒って」
わたしは小さく笑う。
とにもかくにも小説――そのなかでも純文学が大好きなわたしのことを、遥は「活字中毒」と言ってよくからかった。遥は漫画や大衆文学は好んで読むものの、純文学はよほどのことがないかぎり手が伸びないらしい。
そんな遥はロックバンドが好きだ。彼こそ、やれマイケミだやれオアシスだと騒ぐ、立派な「洋楽かぶれ」なのだが。
「わたしも気分転換しようかなって思って。もう社会人になるしね」
――社会人。
四月から遥とわたしはまた別々の進路に進む。
どちらかが言い出したわけでもないし、二人で約束したわけではないが、社会人という三文字を、わたしたちはなぜか言わないようにしていた。
それなのに、つい口に出してしまった。
なんの意味のないつぶやきのはずが、とたんに重い空気が流れる。
わたしは「お会計してくる」とつぶやいてその場を去った。
◇ ◇ ◇
深夜の映画館は、人がいようといまいと、本来の輝きを取り戻したかのようにきらめいて見える。エレベーターを降りた瞬間から空気が違うのだ。この時間帯の映画館が、わたしは好きだった。
照明の一つとっても、ついさっき新品に取り替えたとでも言わんばかりにポスターを照らしているし、軽食売り場から見える機械のなかでポップコーンたちが踊っている。
映画の感想を言い合う人々、このあとのロマンチックな夜を想像している恋人たち、トイレに駆けこむ人の群れ。そんな人々で溢れる館内を、わたしたちは言葉を交わさずに歩く。
映画を観終わって、映画館を出るまではしゃべらない。
これも、わたしたちの間でいつのまにかできていた決まりごとだった。
わたしも遥も、上映直後の余韻に浸ったり、感想を整理したりするのは、一人でしたい派なのだ。
小気味よい音が鳴り、エレベーターが開く。
外に出ると、わたしはようやく口を開いた。
「気分転換で選んだ映画はどうでしたか?」
「俺には刺さらなかった、かも。依織は?」
「同じく」
わたしがそう言うと、四六時中やむことのない渋谷の喧噪が、ちょうどのタイミングで一瞬だけ時を止めたかのように静まり返る。
遥とわたしは同じタイミングで噴き出した。
「あそこの演出はないよね」「しらけちゃった」「ホラー映画ってああいうもんなのかな」「でも演技はよかった」「音楽もかっこよかったと思う」「あの小説のオマージュが入ってたの気づいた?」などと互いに好き勝手言って笑い合う。
映画館の入口か近くの飲食店で映画の余韻に浸るのも、お決まりの流れだった。
今日はお互いに言いたいことがとくに多い日だったので、次から次へと文句や感想が出てくる。
しばらく映画館の入口でしばらくそんなことをしていると、ふと遥が腕時計に目を向けた。
「あ、終電」
そうつぶやいて、文字盤を見せてくる。
時刻はすでに二十四時半をまわっていた。すでに最終電車の時刻を五分過ぎている。
信じられなくてスマホの時計を確認するが、本当に二十四時半だった。
「うそ!」
「なんかいつもより長い映画だなぁと思っていたんだけど、つまんないからじゃなかったんだ」
スマホケースに挟んでいた半券をよく見ると、終了時間が書かれていた。たしかに、上映時間は一般的な映画よりは少し長めだった。
とはいえ、最終電車に間に合わない時間ではない。感想タイムが長引いたのがいけなかった。
わたしはおそるおそる「どうする……?」と尋ねる。一人暮らしをしている互いの家に泊まることもあったが、今日はとくに約束していなかった。横浜の自分の家までは、タクシーでどのくらいの値段になるのか見当もつかない。
「じゃあ、コンビニでアイスとか買って、俺の家まで歩いて帰ろうよ。おもしろそうじゃない?」
「え、三茶まで歩くの? 遠くない……?」
「意外とすぐなんじゃないかな」
渋谷から三軒茶屋まで歩いたらどのくらいかかるのか、ついスマホで調べようとすると、画面が暗くなる。
顔をあげると、遥がにぃっと笑っていた。
「だめだめ、時間わかったらつまんないじゃん」
「……わたしのこと、男子高校生とかだと思ってる? そんなに体力ないよ」
「無理になったらタクシーに乗ればいいよ。決まり!」
◇ ◇ ◇
一度テンションがあがった遥を止めるのはなかなか難しい。
わたしたちは結局、遥が暮らす三軒茶屋のアパートまで歩くことになった。
遥は片手に紙パックのレモンティー、わたしの手にはホットコーヒーとさっき買った写真集が入ったレジ袋。春とはいえまだ三月の渋谷の夜は意外と寒くて、二人ともアイスを買う気にはならなかった。
真夜中から朝にかけての、世界中の空気が入れ替わって、新品の朝の気配が漂いはじめる時間帯が好きだと知ったのは、大学生になってからだ。
まだ肌寒い春の夜風を感じながら、恋人と夜道を歩くのは、言いようのない浮遊感があった。
そんなわたしをちらりと見て、遥はいつもより大人びた笑顔を浮かべた。
「依織、楽しそう」
「うん……まあ、思ったよりはだいぶ楽しい」
「ならよかった。俺、夜の散歩好きじゃん? いつか依織とこういうことしたいって思ってたんだよね」
「言ってくれればいいのに」
「『眠い』って言って断るでしょう」
「そうかも」
なんてことのない話をしながら、歩き続ける。
どのくらい歩いたのか、どのくらい時間が経ったのかはもうわからなかった。
ふと、横断歩道の信号が点滅する。
ペースを落とすわたしとは反対に、遥は軽やかに走り出した。が、すぐにわたしが立ち止まったのに気づき、遥はうしろを振り返る。
その顔は、どこまでも困惑していた。
「依織、どうした? 疲れた?」
気づけば、わたしの頬には涙が伝っていた。
『走ったらもったいないよ。信号待ちの時間ぶん、もっと依織と一緒にいられるんだから』
遥がそう言って笑っていたのは、高校三年生の冬、受験まっただなかの時期のことだった。
あのときからずっと、遥は信号が点滅してもけっして走らなかった。もしかしたらそれよりも前から信号は走らない派だったのかもしれないが、わたしはとにかく彼の言葉がうれしかったのだ。
遥の歩みに合わせてスピードを落とすあの瞬間が、好きだったのに。
「依織?」
駆け寄る遥の声は、あのころより少し低くなったものの、相変わらず穏やかだった。
いつまでも変わらない彼が好き。
環境の変化やいっときの感情に流されて、少しずつ変わりゆく彼なんて知りたくない。
彼の顔が見たくなくて、わたしはしゃがみこんだ。
「社会人」という言葉や、未来のことを口にしなくなったのは、いつからだっただろうか。
今日と少し先の未来のことだけ考える遥。少し前から四月からの生活に心を奪われて、彼のなかで徐々にわたしの存在は薄れていた。そんなことに気づかないわたしではない。
一方、いつだってもう戻れない過去と来るかわからない将来に怯えるわたしの心にも、いまを生きる彼を置いておくほどの心の隙間はなかった。
彼の家についたら、まずはシャワーを浴びて、ビートルズだかAC/DCだかのTシャツを借りて、コンビニで買ったお酒を二人で飲む。それから、恋人だけの時間が訪れる。
それで、その先は?
朝が来て、わたしたちはきっと別れ話をするのだろう。
わたしはみっともなく泣くだろうか。
遥はがらにもなく苛立ちをあらわにするだろうか。
真夜中と朝のちょうど真ん中の風が吹き抜けると、写真集が入ったレジ袋がうるさく主張しだす。
『わたしたちの、これから』は、きっと訪れない。
でも――
もう少しだけ変わらない二人を演じていたい。
わたしは写真集の彼女にそう誓った。