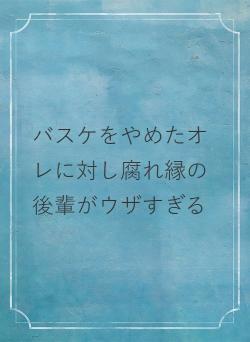「美味しい」
光はそう言いながら、牛丼の超大盛りガツガツと食べていた。
「それで光これからどうするの?」
「まあ、サボりとかはあいつらが上手くやってくれるだろ」
あいつらが悪いしな。てか面倒くさい。
「まあ、俺が思うのは、あれいじめじゃねえかと思うんだよね。雅子のことを悪く言ってさ。俺は許せねえ」
多数で一人をいじめることをいじめというのなら、あれはまさにいじめだろう。
俺だって一対一ないしは一体二とかだったら戦ってただろう。
だが、あの状況多数のクラスメイトの痛いなと見る目が合った。そんな状況で戦えるわけがない。
「まあでも今はたぶん先生が探してるかもしれないし、最悪警察に捜索されているかもしれないしなあ。どうするか」
今の世の中逃げられるほど甘い社会ではない。別に俺は犯罪をしたわけではないが、今は知っている人に会いたくはない。
「じゃあ八方塞がりってこと?」
「まあそうなるな、まあでもこれであとがないんだ、再対決の時にはまた言い負かす方法を考えたらいいさ」
二体一だったら勝てるかもしれない。さっきのは多数に無勢去ったからな。
「うん」
「あの、すみません」
一人の中年の店員が光に声をかける。
「なんですか?」
「さっきから誰と話されているのですか?」
「雅子だよ」
真面目な顔で言う。何を当たり前のことを聞いているんだ。
ああ、いや、そうか。こいつは雅子のことが見えないのか。
「でもそこには誰もいないように見えるのですが」
「いや、いるよ。まさにここに」
もうごり押すか。
今更曲げたくはない。
それにむかつく。
俺はただ雅子と話しているだけなのに。
「でも、あなた一人ですよね」
「いるよ、目に見えないのか?」
俺の怒りはデットヒートしていく。
「ふざけるなよ、ここにちゃんといるだろ、ほら!!」
もう雅子のことを知らない人は許せん。俺の怒りは向こう見ずかもしれないが。もうどうでもいい。カッとなったらもう止まらない。
中年の店員はビビって逃げ出した。
「おい、ふざけんな。逃げるなよ」
逃げたらストレス解消できないだろ。
厨房
「すみません、警察ですか? ここに頭がおかしい奴がいるんです、ええ、ええ、ああ、なるほどすぐに来てくれると。大盛り頼んでましたからすぐには食べ終わらないと思います。はい、はい、すぐにきてください」
学校
「神城が見つかったって本当ですか?」
山本が同僚の教師に聞く。
「ええ、牛丼屋さんでご飯を食べてたらしいです」
「向かった方がいいですよね」
「はい」
「あの子たちはどうしましょうか」
「呼んだ方がいいと思いますね」
「分かりました」
教室
「すみません、大嶺と篠宮はいますか?」
「はい」
「はい」
二人が返事をする。
「神城くんが見つかったらしいです、それでよければ重要参考人としてきていただけないかと」
「分かりました、すぐ行きます」
凛子はそう言った。
「でも出席日数とかどうなるんですか?」
末広は言う。それを聞いて凛子は確かにと思った。
まともな質問でもある。
光どうこう以前に学生なのだ。
別に出席日数で留年とかするほど休んでいる訳ではないのたが。
「それはこっちの方で出席ということにしときます」
「分かりました」
警察署
「聞いているのか? 黙ってていいと言うのか」
「……」
「はあ、埒が明かんな、おい、親御さんとかはまだか?」
「まだみたいです」
奥から声がする。
「とはいえ、このまま黙秘を続けても意味がないぞ、状況が悪くなるだけだ。我々は君の敵じゃないんだよ」
「俺にとっては雅子の存在を否定する人間はみんな敵だ」
もうどうでもいい。なんで俺が怒られなくちゃいけないんだ。
「でもな、その雅子さんはもう亡くなっているんだろう」
巡査部長である三条は冷静に言う。
「いや、俺の隣に存在しているから、存在している」
「いや光、私もう死んでるから、死んでることは肯定してもいいんじゃないの?」
「雅子は黙っといてくれ」
「えー。でも私は死んでるわけだし」
「面倒くさいな。生存してるでもいいだろ」
「もうそれでいいよ」
「やった!」
「……新島巡査、どう思う?」
「幻覚でも見ているんでしょうか」
「まあ、そうとしか思えないな。ただそれは幽霊と幻覚を見ている可能性、そこから考えて幻覚を見ている可能性の方が高いと言うだけだ。もし幻覚を見ている可能性がゼロになったらそれは、幽霊が見えていることにならないか」
「でも、幽霊がいると証明もできませんよ、話によると彼は亡くなられたあの人の彼氏だったらしいので、彼女しか知らないことを聞いての証明はできないでしょう」
こういう場合、最もわかりやすい手は幽霊の情報を聞くことだ。そうすることで幽霊の存在をある程度認めることができるかもしれない。ただ、それが通用するのは幽霊と人間があまり接点のない場合だけだ。
「そこなんだよな、ここまでくると、我々警察の仕事から離れてくるのかもしれんな」
「ですね」
「お待たせしました、神城の担任である山本です」
「クラスメイトの篠宮です」
「クラスメイトの大嶺です」
三人は到着するとすぐに自己紹介をした。
「ああ、待っていました」
三条巡査部長が返事をした。
「それで何があったか、神城くんは話しましたか?」
「いえ、それが何も、むしろまた雅子さんと話されてて」
「何か状況のことを言えばいいですか?」
「はい、そうですね」
「えっと、何があったかと言いますと」
末広は話をし始める。
「なるほどそういうことでしたか」
「はい、私が悪いんです。不用意に責めたりしたから」
「それはあなたの責任じゃないと思いますよ。ただこの状況が好ましくないのも事実ですね。何か解決方法があればよいのですが」
そう言いながら三条は考える。
「もしかしたらこれは病院か、もし幽霊が見えていることが事実だとしたら寺に行くかの二択でしょうね。いやはや、まさか私の口から幽霊の可能性を肯定する言葉が出てくるとは思いませんでしたよ」
「ということは、もし寺に行ってだめだったら病院に入れる感じですよね」
「はい、そうですね。幸い知り合いに寺の住職さんがいるので、連絡してみましょう」
そう言って三条は携帯を取り出して電話をし始める。
「これでうまくいくといいけど」
「ああ、俺だってあいつが苦しんでいるのを見たくないし、もし幽霊がいるっていうのが事実だったら、そのことを受け止めなくちゃいけないしな」
あの時は頭ごなしに否定したが、もしその可能性があるのなら辻褄が合うことになる。
「はい」
「連絡が取れました、しかし、親御さんがまだ来ていない以上予約を取るのは無理ですね、まさか今の状態の彼を一人で送り出すわけにはいかないですし」
「俺が連れていきますよ」
「私も行きます」
「わかりました、では預けるとしましょう」