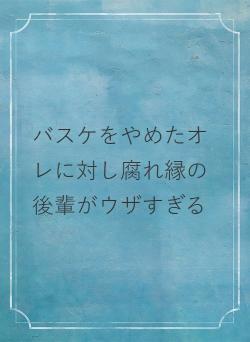「おはよう、末広」
「ああ、おはよう」
「大嶺さんおはよー」
雅子が末広が聞こえてないのを承知で末広に話しかける。返事が来るわけないのによく喋りかけるな。
「昨日はなんかすまん」
挨拶は早々に末広に謝る。
「どうしたんだ? いきなり」
末広は不思議そうな顔をした。
「白状するよ、俺には今も雅子が見えているんだ」
意を決して言い放った。正直言って反応が怖い。また変なやつと思われるのだろうか。
今お母さんがおかしい今、末広しか頼りにならない。こう見えても親友だ。雅子の存在を認めて貰えるかもしれない。
「お前、まだ現実が見えてないのか」
そう言われてしまった。昨日の母さんとの件があるし、そう言われることは十分覚悟していた。
だが、覚悟していても実際言われるとやはりキツイ。
「見えてるよ、見えてるからこそ雅子が見えてるって言っているんだ」
だが、そんな気持ちを振り払って、さらに言う。
現実が見えているかと言われたら難しいところだが、まずは雅子が見えてることを認めて貰えないと。
「お前な、そんなこと言ったって雅子は帰ってこないぞ」
まずい、まただ、またこれだ。
雅子が見えてることを理解してもらえない。トラウマが再来してしまう。
「まあそんなこと言われるのは覚悟していたよ。でも雅子がここにいるという事実を捻じ曲げるわけにはいかないんだ。信じてくれ末広」
俺は事実を言っているだけなのだ。何も悪いことはしていない。
「すまん、それを言い張るなら、なんかそう言う施設行ったほうがいいと思うわ。その施設がどんなんかわからんけどな」
そう末広は笑いながら言う。こっちは本気なんだがな。
「末広…」
俺は呟いてみる。だが返事は返ってこない。
そのまま一時間目の授業が始まったが、怖くて末広の顔を直視することができない。何を考えて、何を思ってあんなに理解してくれないのか。だが、顔を直視出来ないのは末広も同様みたいだ。なにしろ視線を感じないのだ。
休み時間。
「光、ちょっといいか?」
「なんだ?」
末広が話しかけてくる。なんだ? 理解してくれるのか?
「昨日の告白結局断ったのか?」
「ああ」
案外普通の質問をしてきた。これは末広なりの考えなのか?関係を修復する為のやつなのか? それとも……。
「今からでも付き合えよ」
「なんでだよ」
昨日は俺の選択を理解してくれていたじゃねえか。
「現実に戻るチャンスだからだ」
ふざけんな! お前もその考えかよ。
「みんなみんな現実に戻れ戻れって、今の雅子との生活が俺にとっての現実なんだよ。それが別の女と付き合えって、付き合えるわけがない。母さんだけじゃなく、お前にまで言われたら本当に頭おかしくなりそうなんだよ」
その理論が本当に納得出来ない。母さんに続き末広までその理論に乗っかってくるとは。末広の場合、原因は絶対俺がああ言ったからだろう、だが、許せるわけではない。ほんとお母さんも末広も凛子もみんなおかしい。
「すまん光」
末広はそう言って、無言のままトイレに向かった。そんなこと言われたら俺が悪いみたいじゃねえか。くそ、どうすりゃ良いんだ。
★★★★★
「違うんだ、そうじゃ無いんだ、俺はお前のことを思って言っただけなんだ」
そう末広はトイレの中で一人呟く。彼には凛子がどんな人物なのか全く知らないのだが、それでも雅子を乗り越えなくては、光の人生はおかしくなってしまう。
少なくとも今の見えない物を見えるように振る舞う光にはだ。
「このままじゃいけない、光の人生、青春はおかしくなる。現実に戻って来い、光」
そう末広は誰もいない空間で一人呟いた。
★★★★★
「光」
雅子は光に話しかける。
「ごめんな、今まで学校で寂しい思いをさせて。今日からはお前が見えてることを隠そうなんてしない。今日からは学校でも話せるぞ」
もうこうなったらどうとでもなれだ。末広からは俺がおかしい狂人に見えるのだろうか。だがもうこんな味方がいない絶望的な状況下ではそんなことはもはやどうでもいい。
「そうなんだけど、私のためにあんな口論までして大丈夫?」
雅子としては昨日の言葉は、軽く言ったつもりだったのだろう。だが、俺がしたいのだ。もちろん大丈夫な訳がない。
だが、もう逃げるのはやめにする。
「大丈夫だ、百人の友達よりも一人の彼女の方が大事だ」
クラスメイトの目線を感じる。若干恥ずかしいが、もうどうどでもなれ!
「光、みんなが見ているけど」
「ああ、見せとけ、みんなは雅子が見えてないからそう思うだけなんだ。雅子が見えてたらただの普通の会話さ。何も心配することはないよ」
そう言って光は雅子の頭を撫でるが、空を切るだけだった。
「でも、でも、現実が見えてないって言ってたよ」
「それは大丈夫、言わせてたらいいんだよ」
「うん」
「光、やっぱり考え直してくれ」
末広が教室に入り話しかけてくる。
「すまん、末広、もう先生来てる」
「あ、ああたしかに」
末広は勢いを殺されて、微妙な顔をしている。
「光考え直してくれ」
授業が終わると同時に末広が言ってきた。
「何が?」
答えはわかっている。だが、今の俺には余裕が無い。末広相手だろうと容赦するつもりはない。
「現実に戻って来いよ」
あ、例の定形文か。
「またそういうことか。俺は何を言われても雅子から離れるわけにはいかない。それに末広、雅子の気持ちがわかるか? 急に俺以外の人から認識されなくなったんだぞ。それがどんなに辛いか、寂しいか、考えたことあるのか?」
別の切り口で攻めてみる。雅子が授業中に教えてくれた提案だ。
「……俺には理解出来ない」
「俺は何回も考えてるんだ。何回も何回も何回も、雅子がこんなこと考えてるだろうなとか、こんな気持ちだろうな、とか色々、様々なことを考えてる。お前にはこの愛をわからないだろうな」
「光」
そう言って雅子は俺を抱きしめるが、やはりスカッと俺の体を雅子の手がすり抜けるだけだった。
「だから悪いな、お前が言う現実には戻れない、戻れるわけがない」
「もう俺にはどうすることもできないのか? 俺にはお前が狂っているようにしか見えないんだよ」
俺が狂ってる? それを言うならお前らだろう。
「すみません」
昼休みに凛子が訪ねてきた。余計な人が来てしまった。
「何だ?」
返事をする。
「昨日はすみませんでした、急に家を訪ねて」
「ああ、そのことか」
謝られても許すつもりは無いけど。
「それで、もう一回チャンスをくれませんか?」
「ああ、おはよう」
「大嶺さんおはよー」
雅子が末広が聞こえてないのを承知で末広に話しかける。返事が来るわけないのによく喋りかけるな。
「昨日はなんかすまん」
挨拶は早々に末広に謝る。
「どうしたんだ? いきなり」
末広は不思議そうな顔をした。
「白状するよ、俺には今も雅子が見えているんだ」
意を決して言い放った。正直言って反応が怖い。また変なやつと思われるのだろうか。
今お母さんがおかしい今、末広しか頼りにならない。こう見えても親友だ。雅子の存在を認めて貰えるかもしれない。
「お前、まだ現実が見えてないのか」
そう言われてしまった。昨日の母さんとの件があるし、そう言われることは十分覚悟していた。
だが、覚悟していても実際言われるとやはりキツイ。
「見えてるよ、見えてるからこそ雅子が見えてるって言っているんだ」
だが、そんな気持ちを振り払って、さらに言う。
現実が見えているかと言われたら難しいところだが、まずは雅子が見えてることを認めて貰えないと。
「お前な、そんなこと言ったって雅子は帰ってこないぞ」
まずい、まただ、またこれだ。
雅子が見えてることを理解してもらえない。トラウマが再来してしまう。
「まあそんなこと言われるのは覚悟していたよ。でも雅子がここにいるという事実を捻じ曲げるわけにはいかないんだ。信じてくれ末広」
俺は事実を言っているだけなのだ。何も悪いことはしていない。
「すまん、それを言い張るなら、なんかそう言う施設行ったほうがいいと思うわ。その施設がどんなんかわからんけどな」
そう末広は笑いながら言う。こっちは本気なんだがな。
「末広…」
俺は呟いてみる。だが返事は返ってこない。
そのまま一時間目の授業が始まったが、怖くて末広の顔を直視することができない。何を考えて、何を思ってあんなに理解してくれないのか。だが、顔を直視出来ないのは末広も同様みたいだ。なにしろ視線を感じないのだ。
休み時間。
「光、ちょっといいか?」
「なんだ?」
末広が話しかけてくる。なんだ? 理解してくれるのか?
「昨日の告白結局断ったのか?」
「ああ」
案外普通の質問をしてきた。これは末広なりの考えなのか?関係を修復する為のやつなのか? それとも……。
「今からでも付き合えよ」
「なんでだよ」
昨日は俺の選択を理解してくれていたじゃねえか。
「現実に戻るチャンスだからだ」
ふざけんな! お前もその考えかよ。
「みんなみんな現実に戻れ戻れって、今の雅子との生活が俺にとっての現実なんだよ。それが別の女と付き合えって、付き合えるわけがない。母さんだけじゃなく、お前にまで言われたら本当に頭おかしくなりそうなんだよ」
その理論が本当に納得出来ない。母さんに続き末広までその理論に乗っかってくるとは。末広の場合、原因は絶対俺がああ言ったからだろう、だが、許せるわけではない。ほんとお母さんも末広も凛子もみんなおかしい。
「すまん光」
末広はそう言って、無言のままトイレに向かった。そんなこと言われたら俺が悪いみたいじゃねえか。くそ、どうすりゃ良いんだ。
★★★★★
「違うんだ、そうじゃ無いんだ、俺はお前のことを思って言っただけなんだ」
そう末広はトイレの中で一人呟く。彼には凛子がどんな人物なのか全く知らないのだが、それでも雅子を乗り越えなくては、光の人生はおかしくなってしまう。
少なくとも今の見えない物を見えるように振る舞う光にはだ。
「このままじゃいけない、光の人生、青春はおかしくなる。現実に戻って来い、光」
そう末広は誰もいない空間で一人呟いた。
★★★★★
「光」
雅子は光に話しかける。
「ごめんな、今まで学校で寂しい思いをさせて。今日からはお前が見えてることを隠そうなんてしない。今日からは学校でも話せるぞ」
もうこうなったらどうとでもなれだ。末広からは俺がおかしい狂人に見えるのだろうか。だがもうこんな味方がいない絶望的な状況下ではそんなことはもはやどうでもいい。
「そうなんだけど、私のためにあんな口論までして大丈夫?」
雅子としては昨日の言葉は、軽く言ったつもりだったのだろう。だが、俺がしたいのだ。もちろん大丈夫な訳がない。
だが、もう逃げるのはやめにする。
「大丈夫だ、百人の友達よりも一人の彼女の方が大事だ」
クラスメイトの目線を感じる。若干恥ずかしいが、もうどうどでもなれ!
「光、みんなが見ているけど」
「ああ、見せとけ、みんなは雅子が見えてないからそう思うだけなんだ。雅子が見えてたらただの普通の会話さ。何も心配することはないよ」
そう言って光は雅子の頭を撫でるが、空を切るだけだった。
「でも、でも、現実が見えてないって言ってたよ」
「それは大丈夫、言わせてたらいいんだよ」
「うん」
「光、やっぱり考え直してくれ」
末広が教室に入り話しかけてくる。
「すまん、末広、もう先生来てる」
「あ、ああたしかに」
末広は勢いを殺されて、微妙な顔をしている。
「光考え直してくれ」
授業が終わると同時に末広が言ってきた。
「何が?」
答えはわかっている。だが、今の俺には余裕が無い。末広相手だろうと容赦するつもりはない。
「現実に戻って来いよ」
あ、例の定形文か。
「またそういうことか。俺は何を言われても雅子から離れるわけにはいかない。それに末広、雅子の気持ちがわかるか? 急に俺以外の人から認識されなくなったんだぞ。それがどんなに辛いか、寂しいか、考えたことあるのか?」
別の切り口で攻めてみる。雅子が授業中に教えてくれた提案だ。
「……俺には理解出来ない」
「俺は何回も考えてるんだ。何回も何回も何回も、雅子がこんなこと考えてるだろうなとか、こんな気持ちだろうな、とか色々、様々なことを考えてる。お前にはこの愛をわからないだろうな」
「光」
そう言って雅子は俺を抱きしめるが、やはりスカッと俺の体を雅子の手がすり抜けるだけだった。
「だから悪いな、お前が言う現実には戻れない、戻れるわけがない」
「もう俺にはどうすることもできないのか? 俺にはお前が狂っているようにしか見えないんだよ」
俺が狂ってる? それを言うならお前らだろう。
「すみません」
昼休みに凛子が訪ねてきた。余計な人が来てしまった。
「何だ?」
返事をする。
「昨日はすみませんでした、急に家を訪ねて」
「ああ、そのことか」
謝られても許すつもりは無いけど。
「それで、もう一回チャンスをくれませんか?」