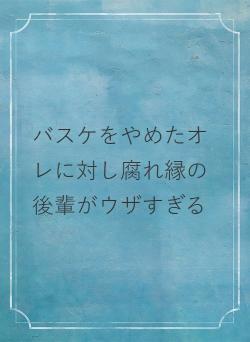「おはよー」
葛飾雅子が俺こと神城光に乗っかりながら話しかけてくる。正直言ってうざい。
「うるさい」
そう軽く怒鳴った。幽霊には重さがないが、朝に大声で叫ばれては目覚めが悪い。それに、なんとなくだが、乗っかられるのも嫌なものだ。
「いいじゃん、カップルだもん」
「はあ、いつも変な起こし方するなよ」
カップルだから良いという事でも無い。
「いいじゃん、学校に遅れないように起こしてあげたんだから」
「まあそれは感謝するよ」
今の時刻は七時四十分、確かにそろそろ起きないとやばい時間だ。
「さーて一緒に朝ごはん食べに行きますか」
「お前はもう死んでるから食べれないけどな」
死人は全てを通り抜けてしまう。
壁とかはもちろん、食事や、服、この世のあらゆる物が。ちなみに今の雅子の着ている服は亡くなった時の服そのままだ。
「そんなこと言わなくていいじゃん、私は現世にいるよ」
「でも、お前幽霊じゃねえかよ」
「私は幽霊なんかじゃありません、生きています」
「そうは言ってもお前は俺以外の人には見れねえだろ」
そう、雅子はもう亡くなっているのだ。
三ヶ月前に彼女が光の家から自分の家に帰るその時にトラックに轢かれて、即死だったのだ。
その時俺はいつものように雅子が普通に家に来るものだと思っていた。いつもの日常が待っていると思っていた。
しかし、現実は残酷だった。雅子はその日家に帰って来ず。待ち続ける間に、俺の家の電話がなった。親がいなかったから俺が電話を取った。どっかのアンケートとか、おじさんならとかだと思っていた。だが、内容は違った。
俺がその内容を聞いた時に状況を理解するのに時間がかかった。
雅子が死んだと言うのだ。その言葉をすぐに飲み込める人などこの世にいないだろう。
まさか彼女がこんな形でいなくなるとは全くもって思っていなかった。これからも一緒に楽しく暮らせるのかと思っていた。
しかもその日はくしくも俺の誕生日だったのだ。彼女に祝ってもらう予定だった正にその日に事故が起きたのだ。
つまり俺の誕生日と雅子の命日が重なる形になってしまった。しかし、驚くのはそのあとだった。俺がお葬式の日に泣き喚いていると、目の前に幽霊である雅子が現れたのだ。
その状況を理解するのに時間がかかったのだが、理解するや否や、喜び、大声で歓声を上げた。その時の喜びようと言えば、周りの人に状況を考えろと怒られたぐらいだ。だが、叫ばないでどうする。喜びを表現しないでどうする。だが、周りのみんなは不思議な顔をしていた。
つまり、雅子は俺以外の人には見えなかったのだ。俺の後母親、雅子の両親を含めた誰にもだ。だが俺は周りの人に雅子の存在を認識してもらえなくても、今こうして雅子と暮らしているという事実だけで満足しているのだ。本当はみんなにも雅子の存在を認識して欲しいだけだけど。
「ほんじゃあ朝ごはん食べに行くか」
「ええ、行きましょう」
「お母さん、今日のご飯は何?」
「卵焼きとソーセージよ」
「普通の料理だな」
「文句言わないの」
「まあいただきます」
「味はどう? おいしい?」
雅子が聞く。俺はその質問に対し、声を出して答えるわけにはいかないので、グットマークを手で作る。
「おいしいんだ。いいなー、私も食べたい」
雅子はうらやましがっているようだ。
相も変わらず俺は無視する。
「ねえ、光、早く食べないと時間ないんじゃない?」
雅子が純粋な目で言ってくる。わかってるよそんなこと! うるさいなあ。
実際ここ最近雅子は俺が返事できないことをいいことに好きかって言ってくるのだ。
「ねえ、光、あの戦争まだ続くらしいの。核爆弾が使われるのが怖いね」
俺の母さんである恵はそのようなことを言う。
「ああ、怖いな。最近犯罪も増えてるしな。本当いいニュースがないもんだ」
最近銀行強盗やら、通り魔事件、教師の痴漢など、様々な悪いニュースがある。さらに遠方の地で、大国同士で戦争を始めたものだから困ったものだ。
そんなことを考えながらソーセージをおかずにご飯を食べた。
学校
「よう、光」
俺の親友である大峰末広がおはようと言ってきた。
「ああ、おはよう」
「しかしもう葛飾さんが死んでからもう今日で三か月か」
末広が悲しそうな顔をしてそう言った、彼もまた雅子が幽霊の状態ながらここに存在している知らないのだ。俺はそれが悲しい、言いたいのに言えないのだ。こんなに辛いことはない。
「私はここにいるよー」
そう言って雅子は末広の顔に向かって手を振りまくる。
しかし当然のことながら末広は気づかず、雅子は相変わらず悲しそうな顔をしている。
「もう、私のために悲しまないでいいからね」
だが末広にその声は届かない。だがその声が聞こえてる俺は笑いをこらえるのが大変だ。
雅子が必死に話しかけてるのに末広にはその声が届かない。まるでコントのような状況だ。いつもなら耐えられるのだが、今回は末広が悲しそうな顔をしていることも相待って、堪えきれそうにない。
「何笑ってるんだよ光、一番悲しいのはお前じゃねえのかよ。確かにお前が泣いても葛飾さんは帰ってこない、でも笑うのは違うだろ。お前、不謹慎だぞ!」
笑いを堪えきれていなかったようだ。
確かに末広が言っていることは正論である、俺が幽霊である雅子が見えていることを除くとだが。
「笑ってるんじゃないよ、思い出し笑いだよ」
俺はそう言い訳をする。思い出し笑いであることは全くもって嘘ではあるが、もし雅子が生きているということを言ってしまったらまだ引きづっていると言われるかもしれない。
現に俺は過去に言ってしまったことがある。その時は全く相手にされず、哀れそうな顔をされたのだ。
あの時末広は俺が現実を直視できていないと思っていたのだろう。あの事件の七ヶ月前に父親が病気で亡くなっていたのもあり、おかしくなっていたとも思っていたのだろう。
だが、過ぎたことだ。今思い返しても意味がない。
「思い出し笑いでも不謹慎すぎるけどな」
「ああ、それは悪かった」
俺は形だけの謝罪をする。雅子が見えている俺には謝る理由がないのだ。雅子に謝れと言われても、ここにいるんだし。
「ひーかる、もう私が生きていることをもう言っちゃえば?」
雅子がそう俺に問う。俺の答えは同然NOだ。
そんなことを言ったら、また幽霊と話している頭やばいやつになってしまう恐れがある。
「ねーえ言っちゃおうよ」
うるさいなあ。
「ねえさあ言っちゃおうよ」
そろそろイライラしてきた、こっちは返事ができねえんだよと言いたくなる。うざい。
「そういやお前机の中に入っているそのおしゃれな手紙は? お前まさか誰かにその手紙を渡すわけではあるまいな」
「え? 俺もしらん」
俺は机の中を取り出し、その手紙を取る。
「なんだ? これは」
その手紙を読む。内容はというと告白の手紙、それも実名を入れてのだ。その手紙によると放課後に校舎裏で待っているらしい。
「おい、お前どうするんだよ」
「断るよ、そりゃあ。雅子の件があるし」
「おう、それでこそ俺の親友だ」
とは言ったが裏では雅子が「断れ」「断れ」「断れ」「断れ」と言っているのだ。そんなところでもしも受けようかなと言ったら呪い殺される可能性がある。勿論雅子が本当に呪い殺すとは思わないけど。
そしてそのまま授業が始まった。俺は必死で先生の言っていることをメモで取る。その一方雅子は暇そうにする。一人だけ勉強しなくていいの少しだけムカつく。
まあそれも仕方ないだろう。ムカつくけど。彼女はノートをとるための手がないのだ。実際、雅子がノートを取ろうとしても手で鉛筆を取れないのだ。
「ねえ光、数学のこの問題の答えたぶん違うよ」
雅子が光に言う。ノートに、「違うのか?」 と、書く。
「うん、たぶんどっかで計算ミスしてる。たぶん、ここ」
雅子が指さす。そこには七✖️十三=八十九と書いてあった。凡ミスだろう。
「ありがとう」
そう、俺はノートに書いて感謝を伝える。凡ミスを指摘してくれるほど嬉しい事はない。誰だってミスはするのだ。
「それでね、最近犯罪多いのやばいよね」
俺はノートに「今授業中だから話しかけないで」と書いた。普通に集中したい。
「えーいいじゃん、私暇なんだよ。いいじゃん話そうよ」
「先生の話を聞いたら面白いと思うぞ」とノートに書く。
「私、勉強しても意味ないし」
「悲しいこと言うなよ」とノートに書く。
「じゃあ私の話に付き合ってよ。この前駅であった殺傷事件、あれ犯人まだ捕まってないんだよね、光も気をつけないとダメだよ。光も幽霊になる保証ないんだから、ってねえ、光聞いてる?」
「聞いてない」とノートに書く。
「なんでよ、聞いてよ。まじで、もう一人死んだらどうする? 重大事件だよ。最近この手の事件多いし、警察手を焼いてるみたいだし、もうどうしようもないよね」
「なんか、雅子楽しそうだな。不謹慎だぞ」とノートに書く。
「不謹慎だっていいじゃない、私、楽しいよ。こんな事件たまにしかないしさ」
「お前変わらないよな。俺お前のこと好きやけど、ここだけは受け付けないわ。事件の被害者に申し訳ないとか思わないの?」とノートに書く。
雅子のこの性格は死ぬ前からずっとなのだ。三つ子の魂百までとはよく言ったものだ。だが、最近の治安の悪化で悪いニュースが増えたからか、心無しかヒートアップしてる気がする。俺はいつも被害者目線で見るが、雅子は事件の重大さにしか目を向けないのだ。
「思わない、全然思わない」
「お前ひどいな」とノートに書く。
「そんなこと言わないでよ、謝って」
そう言いながら雅子は俺の視界を遮る。
「お前マジでやめろ」
俺はノートにそう書く。これでは授業のノートをとれない。
「嫌でーす」
「ごめんなさい、雅子様の悪口はもう未来永劫言いません」
と無心でノートに書く。雅子様の機嫌を取らないといけないのだ。
「それでいいの」
雅子はそう言って笑う。
放課後
俺はすぐさま呼び出された場所に行く。当然告白を断るためにだ。
「あ、こんにちは」
「ああ、こんにちは」
「あのー急に呼び出してしまってすみません。単刀直入に言います。私と付き合ってくれませんか?」
その場にいた雉宮凛子が俺に対して告白をした。
葛飾雅子が俺こと神城光に乗っかりながら話しかけてくる。正直言ってうざい。
「うるさい」
そう軽く怒鳴った。幽霊には重さがないが、朝に大声で叫ばれては目覚めが悪い。それに、なんとなくだが、乗っかられるのも嫌なものだ。
「いいじゃん、カップルだもん」
「はあ、いつも変な起こし方するなよ」
カップルだから良いという事でも無い。
「いいじゃん、学校に遅れないように起こしてあげたんだから」
「まあそれは感謝するよ」
今の時刻は七時四十分、確かにそろそろ起きないとやばい時間だ。
「さーて一緒に朝ごはん食べに行きますか」
「お前はもう死んでるから食べれないけどな」
死人は全てを通り抜けてしまう。
壁とかはもちろん、食事や、服、この世のあらゆる物が。ちなみに今の雅子の着ている服は亡くなった時の服そのままだ。
「そんなこと言わなくていいじゃん、私は現世にいるよ」
「でも、お前幽霊じゃねえかよ」
「私は幽霊なんかじゃありません、生きています」
「そうは言ってもお前は俺以外の人には見れねえだろ」
そう、雅子はもう亡くなっているのだ。
三ヶ月前に彼女が光の家から自分の家に帰るその時にトラックに轢かれて、即死だったのだ。
その時俺はいつものように雅子が普通に家に来るものだと思っていた。いつもの日常が待っていると思っていた。
しかし、現実は残酷だった。雅子はその日家に帰って来ず。待ち続ける間に、俺の家の電話がなった。親がいなかったから俺が電話を取った。どっかのアンケートとか、おじさんならとかだと思っていた。だが、内容は違った。
俺がその内容を聞いた時に状況を理解するのに時間がかかった。
雅子が死んだと言うのだ。その言葉をすぐに飲み込める人などこの世にいないだろう。
まさか彼女がこんな形でいなくなるとは全くもって思っていなかった。これからも一緒に楽しく暮らせるのかと思っていた。
しかもその日はくしくも俺の誕生日だったのだ。彼女に祝ってもらう予定だった正にその日に事故が起きたのだ。
つまり俺の誕生日と雅子の命日が重なる形になってしまった。しかし、驚くのはそのあとだった。俺がお葬式の日に泣き喚いていると、目の前に幽霊である雅子が現れたのだ。
その状況を理解するのに時間がかかったのだが、理解するや否や、喜び、大声で歓声を上げた。その時の喜びようと言えば、周りの人に状況を考えろと怒られたぐらいだ。だが、叫ばないでどうする。喜びを表現しないでどうする。だが、周りのみんなは不思議な顔をしていた。
つまり、雅子は俺以外の人には見えなかったのだ。俺の後母親、雅子の両親を含めた誰にもだ。だが俺は周りの人に雅子の存在を認識してもらえなくても、今こうして雅子と暮らしているという事実だけで満足しているのだ。本当はみんなにも雅子の存在を認識して欲しいだけだけど。
「ほんじゃあ朝ごはん食べに行くか」
「ええ、行きましょう」
「お母さん、今日のご飯は何?」
「卵焼きとソーセージよ」
「普通の料理だな」
「文句言わないの」
「まあいただきます」
「味はどう? おいしい?」
雅子が聞く。俺はその質問に対し、声を出して答えるわけにはいかないので、グットマークを手で作る。
「おいしいんだ。いいなー、私も食べたい」
雅子はうらやましがっているようだ。
相も変わらず俺は無視する。
「ねえ、光、早く食べないと時間ないんじゃない?」
雅子が純粋な目で言ってくる。わかってるよそんなこと! うるさいなあ。
実際ここ最近雅子は俺が返事できないことをいいことに好きかって言ってくるのだ。
「ねえ、光、あの戦争まだ続くらしいの。核爆弾が使われるのが怖いね」
俺の母さんである恵はそのようなことを言う。
「ああ、怖いな。最近犯罪も増えてるしな。本当いいニュースがないもんだ」
最近銀行強盗やら、通り魔事件、教師の痴漢など、様々な悪いニュースがある。さらに遠方の地で、大国同士で戦争を始めたものだから困ったものだ。
そんなことを考えながらソーセージをおかずにご飯を食べた。
学校
「よう、光」
俺の親友である大峰末広がおはようと言ってきた。
「ああ、おはよう」
「しかしもう葛飾さんが死んでからもう今日で三か月か」
末広が悲しそうな顔をしてそう言った、彼もまた雅子が幽霊の状態ながらここに存在している知らないのだ。俺はそれが悲しい、言いたいのに言えないのだ。こんなに辛いことはない。
「私はここにいるよー」
そう言って雅子は末広の顔に向かって手を振りまくる。
しかし当然のことながら末広は気づかず、雅子は相変わらず悲しそうな顔をしている。
「もう、私のために悲しまないでいいからね」
だが末広にその声は届かない。だがその声が聞こえてる俺は笑いをこらえるのが大変だ。
雅子が必死に話しかけてるのに末広にはその声が届かない。まるでコントのような状況だ。いつもなら耐えられるのだが、今回は末広が悲しそうな顔をしていることも相待って、堪えきれそうにない。
「何笑ってるんだよ光、一番悲しいのはお前じゃねえのかよ。確かにお前が泣いても葛飾さんは帰ってこない、でも笑うのは違うだろ。お前、不謹慎だぞ!」
笑いを堪えきれていなかったようだ。
確かに末広が言っていることは正論である、俺が幽霊である雅子が見えていることを除くとだが。
「笑ってるんじゃないよ、思い出し笑いだよ」
俺はそう言い訳をする。思い出し笑いであることは全くもって嘘ではあるが、もし雅子が生きているということを言ってしまったらまだ引きづっていると言われるかもしれない。
現に俺は過去に言ってしまったことがある。その時は全く相手にされず、哀れそうな顔をされたのだ。
あの時末広は俺が現実を直視できていないと思っていたのだろう。あの事件の七ヶ月前に父親が病気で亡くなっていたのもあり、おかしくなっていたとも思っていたのだろう。
だが、過ぎたことだ。今思い返しても意味がない。
「思い出し笑いでも不謹慎すぎるけどな」
「ああ、それは悪かった」
俺は形だけの謝罪をする。雅子が見えている俺には謝る理由がないのだ。雅子に謝れと言われても、ここにいるんだし。
「ひーかる、もう私が生きていることをもう言っちゃえば?」
雅子がそう俺に問う。俺の答えは同然NOだ。
そんなことを言ったら、また幽霊と話している頭やばいやつになってしまう恐れがある。
「ねーえ言っちゃおうよ」
うるさいなあ。
「ねえさあ言っちゃおうよ」
そろそろイライラしてきた、こっちは返事ができねえんだよと言いたくなる。うざい。
「そういやお前机の中に入っているそのおしゃれな手紙は? お前まさか誰かにその手紙を渡すわけではあるまいな」
「え? 俺もしらん」
俺は机の中を取り出し、その手紙を取る。
「なんだ? これは」
その手紙を読む。内容はというと告白の手紙、それも実名を入れてのだ。その手紙によると放課後に校舎裏で待っているらしい。
「おい、お前どうするんだよ」
「断るよ、そりゃあ。雅子の件があるし」
「おう、それでこそ俺の親友だ」
とは言ったが裏では雅子が「断れ」「断れ」「断れ」「断れ」と言っているのだ。そんなところでもしも受けようかなと言ったら呪い殺される可能性がある。勿論雅子が本当に呪い殺すとは思わないけど。
そしてそのまま授業が始まった。俺は必死で先生の言っていることをメモで取る。その一方雅子は暇そうにする。一人だけ勉強しなくていいの少しだけムカつく。
まあそれも仕方ないだろう。ムカつくけど。彼女はノートをとるための手がないのだ。実際、雅子がノートを取ろうとしても手で鉛筆を取れないのだ。
「ねえ光、数学のこの問題の答えたぶん違うよ」
雅子が光に言う。ノートに、「違うのか?」 と、書く。
「うん、たぶんどっかで計算ミスしてる。たぶん、ここ」
雅子が指さす。そこには七✖️十三=八十九と書いてあった。凡ミスだろう。
「ありがとう」
そう、俺はノートに書いて感謝を伝える。凡ミスを指摘してくれるほど嬉しい事はない。誰だってミスはするのだ。
「それでね、最近犯罪多いのやばいよね」
俺はノートに「今授業中だから話しかけないで」と書いた。普通に集中したい。
「えーいいじゃん、私暇なんだよ。いいじゃん話そうよ」
「先生の話を聞いたら面白いと思うぞ」とノートに書く。
「私、勉強しても意味ないし」
「悲しいこと言うなよ」とノートに書く。
「じゃあ私の話に付き合ってよ。この前駅であった殺傷事件、あれ犯人まだ捕まってないんだよね、光も気をつけないとダメだよ。光も幽霊になる保証ないんだから、ってねえ、光聞いてる?」
「聞いてない」とノートに書く。
「なんでよ、聞いてよ。まじで、もう一人死んだらどうする? 重大事件だよ。最近この手の事件多いし、警察手を焼いてるみたいだし、もうどうしようもないよね」
「なんか、雅子楽しそうだな。不謹慎だぞ」とノートに書く。
「不謹慎だっていいじゃない、私、楽しいよ。こんな事件たまにしかないしさ」
「お前変わらないよな。俺お前のこと好きやけど、ここだけは受け付けないわ。事件の被害者に申し訳ないとか思わないの?」とノートに書く。
雅子のこの性格は死ぬ前からずっとなのだ。三つ子の魂百までとはよく言ったものだ。だが、最近の治安の悪化で悪いニュースが増えたからか、心無しかヒートアップしてる気がする。俺はいつも被害者目線で見るが、雅子は事件の重大さにしか目を向けないのだ。
「思わない、全然思わない」
「お前ひどいな」とノートに書く。
「そんなこと言わないでよ、謝って」
そう言いながら雅子は俺の視界を遮る。
「お前マジでやめろ」
俺はノートにそう書く。これでは授業のノートをとれない。
「嫌でーす」
「ごめんなさい、雅子様の悪口はもう未来永劫言いません」
と無心でノートに書く。雅子様の機嫌を取らないといけないのだ。
「それでいいの」
雅子はそう言って笑う。
放課後
俺はすぐさま呼び出された場所に行く。当然告白を断るためにだ。
「あ、こんにちは」
「ああ、こんにちは」
「あのー急に呼び出してしまってすみません。単刀直入に言います。私と付き合ってくれませんか?」
その場にいた雉宮凛子が俺に対して告白をした。