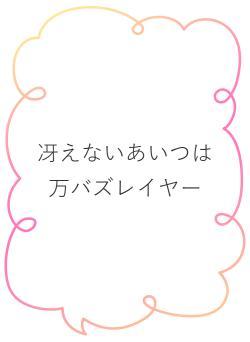目を覚ました苗が最初に見たものは、夜空に浮かぶ黄金色の満月だった。
風のない夜だ。空気はべたりと湿気を帯びていて、甘く蕩けるような植物の香りが辺りを満たしている。どこかで不気味に鳥が鳴く。不規則で騒がしい虫たちの声が聞こえてくる。辺りの様子をうかがうように視線を動かせば、鬱蒼と生い茂る木々が苗のことを見下ろしていた。
その状況は以前にも体験したことがあり、苗は震える声でつぶやいた。
「いや……何で。どうして」
そこは死に戻る前、首切様に首を落とされたのと同じ場所だった。両手と両足は麻縄で縛られていて、どう足掻いても逃げ出すことは叶わない。全身がズキズキと痛むのは、紫を殺した罰として殴る蹴るの暴行を受けたから。何もかもが死に戻る前と同じ状況だった。
息を止めて気配を殺す。どうかこの場所に彼が現れないことを必死で願う。しかし苗の願いが天に届くことはなく、間もなく虫たちの鳴き声は止み、草を踏み分ける音が聞こえてきた。
あざけるように笑うひび割れ模様の面、狒々を思わせる紅毛、闇夜にまぎれるためにあつらわれたような黒無地の着物、そして月光を浴びて輝く研ぎ澄まされた刃。
「――首切様」
満月を背に立つ首切様を、苗は力なく見上げた。死に戻る前の苗は、首切様を前に己の無実を訴えたけれど、もう同じことをする気力はなかった。無実を訴えたところで聞き入れられることはない。もう数秒と経たずに苗は死ぬ。あの輝く刃に首を落とされて。
(お母様、ごめんなさい。せっかく手に入れた機会を無駄にしてしまった。私は未来を、運命を、変えることができなかった)
様々な思い出が走馬灯として頭の中を巡った。その大半がろくでもなく苦痛に溢れたものだったが、篝との思い出だけが眩しく輝いていた。
幽世山の洞穴で出会った鬼の青年は、苗の世界に射し込んだ一筋の光。篝と一緒に過ごす時間は、苗につらい現実を忘れさせてくれた。
(もう一度、会いたかったな……)
ぽろりと瞳から涙が溢れた。
死の直前に顔を思い出して、初めて彼を恋い慕っていたのだと気がついた。だけどもう想いを伝えることは叶わないから、どうか彼の未来が幸に溢れたものであることを願う。
「……さよなら、篝」
苗は目を閉じ、身体から力を抜いた。きたるべき最期に備えるために。少しでも痛みを感じないように。
ひゅうと風を切る音がした。
静寂は破れ、また虫たちの鳴き声が聞こえ始めた。湿気を帯びた風が吹き抜けていく。まばらに生えた草木を満月が照らしている。
「…………え?」
苗はおそるおそる目を開いた。
あれだけはっきりと死の足音を聞いたというのに、苗は死んでいなかった。首切様が振り落ろした刃は苗の手足を縛っていた麻縄を切り、役目を終えたとばかりに鞘に納められていた。
「苗」
ひび割れ模様の面の向こうから優しい声を聞いた。それほ苗を傷つけようとする人の声ではなく、苗は困惑した。
「あ……貴方は?」
呼びかけに応えるように面が外された。血で染め上げたかのような紅髪をひたいに流した彼は、かがり火色の目を細め、苗の顔を愛おしむように見つめていた。
髪の色こそ違えど、それは苗が死の淵でもう一度会いたいと願った篝だった。
◇
あるところに、人間の血を受け継いだ鬼がいた。鬼は燃えるような緋色の髪を持ち、見た目こそ立派な鬼だったが、心は鬼よりも人間に近かった。他者の命を奪うことを好まず、生きるために人間の魂を喰らう行為さえ苦痛と感じていた。
鬼は、人間の世界で一人の少女を見つけた。戦で家族を亡くした哀れな少女だった。鬼は正体を隠して少女に近づいた。身寄りがないのならば魂も喰いやすかろうと思ったからだ。
しかし、鬼は少女を喰えなかった。それどころか少女の心優しさに惹かれ、野山で採った食べ物を届けるまでになった。鬼は、鬼であることを隠し少女とともに生きたいと願った。
鬼の願いは叶わなかった。鬼の母親が少女の存在に気づき、息子を誑かされてはならぬと少女を八つ裂きにしたからだ。鬼は怒り狂ったが、権力を持つ母親の前ではできることなど何もなかった。人間を殺すべき鬼の身でありながら、人間のように人間を愛したことを罪とされ、人間界にある小さな山の洞穴へと幽閉された。
母親は言った。「満月の夜だけお前を自由にしてあげる。1000人の人間を殺して鬼の心を取り戻しなさい。そうすれば黄泉の国へと帰らせてあげるから」
鬼は答えた。「俺はむやみと人間を殺したくはない。殺せと言うのならば、罪を犯した人間だけを殺すと誓う。お前が八つ裂きにした少女の魂に誓う」
鬼は己の誓いを忠実に守った。満月の夜に付近の村へと赴き、牢屋に入れられた罪人の首を切って回った。いつしか鬼は罪人を裁く『首切様』として祀られるようになり、鬼が村へと赴かずとも、裁かれるべき罪人が山へと届けられるようになった。
しかし時が過ぎるにつれ、村の人々は首切様の存在を忘れていった。村独自の自警団や留置場が整備され、罪人が正しく裁かれるようになったからだ。
首切様の存在はいつしか伝承となった。子どもたちが『幽世山には首切様がいるらしいよ』と噂話をするだけの陽炎のような存在だ。その頃には鬼も生きる気力を失っていた。相手が罪人とはいえ、人間を殺すことは鬼にとって苦痛でしかなく、1000人の人間を殺してまで黄泉の国に戻りたいとは到底思えなかった。
このまま洞穴の中で死のう、と鬼は考えた。鬼の肉体は人間よりもはるかに強靱だが、魂を喰わずにいればいつかは死ぬ。生きる目的もないのだからそれで構わないと思った。
苗という名前の美しい少女が、洞穴にやってくるまでは――
◇
「……篝は、人間を愛してしまったから黄泉の国を追い出されたのね」
篝の胸元に背中を預けながら、苗は言った。二人分の着物越しに篝の体温が伝わってくる。鬼であったとしてもその温かさは人間と変わらない。
苗は一度、篝に殺された。自分を殺した男が目の前にいるというのに、恐ろしさは感じず、それどころか篝の腕に抱かれていることが幸せだった。
「彼女は何という名前だったの?」
「里子だ。不遇な境遇に置かれながらも他人を思いやる優しい少女だった」
「そう……」
篝は木の幹に背中を預け、苗はそんな篝に背中を預けながら、たくさんの話をした。篝は自分が首切様になった経緯を、苗は罪人として幽世山に連れてこられた経緯を。包み隠さずに話せば、互いに特別な存在に慣れた気がした。
「篝は……これからどうするの?」
「……どうすることもできない。俺が自由に歩けるのは満月の夜だけで、朝が来ればまた洞穴に閉じ込められてしまうから」
そうだよね、と苗は相槌を打った。
「私は……これからどうすればいいのかしら……」
答えを求めるでもなくぽつりと零した。
苗は首切様に殺されなかったが、苗に着せられた罪が消えてなくなることはない。屋敷に戻ることはできないし、三条家に追従する村の人々が苗を匿ってくれるとも思えない。付近の村へ移住しようにも、その村に苗の噂が伝わってしまえば結局は同じ事だ。
(命は助かったけれど、親殺しの罪を着せられた私が生きていく道なんてないのかもしれない……)
苗は生きることを諦めつつあった。機会を与えられてもなお大切な母親を守ることができなかった。苗はこれから誰と寄り添い生きていけばいいのだろう。味方もなく、犯してもいない罪を償うために生を繋ぐくらいなら、いっそこの場で命など捨ててしまった方が幸せなのやも。
生きる気力を失くす苗の耳に、篝の声が届いた。
「苗……俺はできそこないの鬼だ。機会を与えられてもなお、心まで鬼になることができなかった」
苗は黙って篝の言葉に耳を傾けた。
「でも俺は……今だけは鬼になりたい。髪の毛の一束まで鬼になりたい。そうすれば苗を守ることができるから。俺の隣に苗の居場所を作ってあげられるから」
篝の、苗を抱く腕に力がこもった。
「苗、俺の心になってくれないか。一人では鬼になれない俺のために、今だけでいいから苗の心を貸してくれ。必ずや幸せにすると誓うから」
苗は篝の顔を見つめた。強い意志を湛えた瞳が苗のことを見下ろしていた。人間の営みをいとも容易く焼き尽くす業火のように赤く、美しい。苗は不意に気がついた。
(ああ、そうか……お母様は死んでしまったけれど、私には篝がいるんだ)
死に戻り、懸命に人の運命を変えようとした。しかし苗は誰の運命も変えることができなかった。暴力事件を起こした男は首切様に首を落とされ、紫は霧江の策略によって死んでいった。
初めから、苗の力では人間の運命を変えることはできなかったのだ。苗に変えられたのは篝に関わることだけ。人間の運命は変えることができずとも、鬼の運命ならば変えることができた。
篝ができそこないの鬼だというのなら、足りない部分は苗が補ってあげればいい。篝が一人では鬼になれないというのなら、二人で鬼になればいい。苗は微笑みながら答えた。
「いいよ、私が篝の心になってあげる」
篝は苗のひたいにこつんと自分のひたいを当てて、穏やかな表情で「ありがとう」と言った。
◇
霧江は上機嫌で寝支度をしていた。今日は霧江にとって最高の一日だった。大嫌いな義妹に母殺しの罪を着せ、首切様の住まう幽世山に置き去りにした。今頃は首のない死体となって冷たい地面に横たわっているはずだ。
「薄汚い女中の分際で、私の一之助を誑かすから悪いのよ。本当にいい気味だわ」
霧江は、苗に母親殺しの罪を着せるべく、紫の薬に毒を混ぜた。苗が毒に気がついたことは想定外だったが、若い女中に金を握らせ苗の行動を見張らせた。薬が川に捨てられたことを知った霧江は、そのことを女中に証言させ、苗に母殺しの罪を着せることに成功した――。
光子と源嗣は、霧江の悪巧みに薄々感付いていたのかもしれない。しかし光子は苗と紫を嫌っているし、源嗣は彼女たちの件に関して知らず存ぜずな態度を貫いている。霧江が罪に問われることはありえなかった。
霧江が寝間着の腰紐を締めたとき、座敷の襖がすぅと開いた。霧江は首をひねり、薄く開いた襖の隙間に呼びかけた。
「お母様、なぁに?」
霧江の座敷の襖を、前置きもなく開けようとする人物は光子しかいない。今夜も光子がやってきたものだろうと思ったが、襖の向こうから光子の声が聞こえない。薄く空いた襖からは、冷たい冷気が音もなく流れ込んでくるだけ。
「……お母様?」
霧江が怪しみながら呼びかけた次の瞬間、襖は勢いよく開かれた。同時に鞠のような物が投げ入れられる。どん、と鈍い音を立てて畳に落ちたそれは、霧江が人生で一度も見たことがないものだった。
「ひ……ひぎゃああああっ!」
光子の生首だった。だらりと開いた口からは赤黒い舌が覗き、光を失くした両目は虚空を見つめていた。切り口からはまだ鮮血が流れ出している。光子が絶命したのはつい先ほどの出来事だということだ。
霧江は光子の生首から目を逸らすこともできず、尻餅をついてがたがたと震えた。恐ろしさに腰が抜けて立つこともままならなかった。
「だ、誰なの……そこにいるのは誰なのよ!」
霧江が開け放たれた襖の向こう側に向かって叫ぶと、暗闇からまず現れたのは血に濡れた刃だった。続いてひび割れ模様の面をつけた男が姿を現し、紅髪を揺らしながら敷居をまたぐ。
霧江は唖然としてつぶやいた。
「どうして首切様がここにいるの……どうしてお母様を殺すのよ……何も悪いことなんてしていないじゃない!」
そのとき、「霧子ねえ様」と聞き慣れた声で名前を呼ばれた。幽世山に置き去りにしたはずの苗だった。首切様の背後に半身を隠し、感情のない瞳で霧子のことを見据えている。霧江にはもう何が何だかわからなかった。
「お前、首切様に殺されたはずじゃ――」
霧子の言葉を遮って、苗はまた「ねえ様」と呼びかけた。
「私、幸せになんてならなくてよかったの。お母様と2人で誰の目にも留まらず、食うに困らない生活ができればそれで幸せだったの」
「は……?」
「でも霧子ねえ様は……いえ、この村の人たちは私からお母様を奪った。助けを求めても手を差し伸べず、薬も与えず見殺しにした。だから私はお前達を裁くため鬼切様の心になったのよ」
苗の声は落ち着いていたが、ふつふつと静かな憎しみをたぎらせていた。
ふいに霧江は、首切様ではなく苗の存在が恐ろしくなった。見下し蔑み続けた少女が、か細い身体に殺意をみなぎらせ霧江の元へと戻ってきた。手遊びで振り回していた刃が、いつか自分の首を切ることになるなど想像もしなかった。
「ち、違う! 私は何も悪くない! 確かに薬に毒を入れたのは私だけど、紫は毒を飲んでいないのだから私の罪にはならないはずよ! そうでしょう!?」
霧江は畳の上を後ずさりながら必死で言い逃れようとした。他人を殺そうとした身でありながら、自分が死ぬことは馬鹿みたいに恐ろしかった。
私のせいじゃない、私は悪くない、欺瞞に満ちた訴えが届くことはない。首切様はまだそこにいる。右手には血濡れの刃を握りしめて。
「……あああああ! この糞女! やっぱりお前は性根の腐った売女よ! 一之介様を誑かしたように首切様を誑かしたんでしょう! そうじゃなきゃ、お前のような蛆虫の言葉に首切様が耳を傾けるはずがない!」
霧子は半狂乱で叫んだ。髪を振り乱し、目を血走らせ、一之助を奪われては堪らぬと苗を糾弾したときと同じように。
あのときと違うのは、生殺与奪の権利を握っているのが霧江ではなく苗だということ。
「殺して、篝」
「ああ」
霧江の頭上に刃が振りかざされた。首筋にすさまじい衝撃を感じたのを最後に、霧江の意識はぷつりと途絶え、それきり永遠に覚めることはなかった。
◇
慶光六年八月五日。
高嶺郡の南方に位置する月霞村にて、不可解な大量殺人事件が発生。被害者の数は1000人を越え、全員が鋭利な刃物で首を切り落とされて絶命していた。被害者の中には月霞村の村長である三条源嗣、家内である三条光子、三条霧江も含まれる。
生き残った村人は16歳未満の子どもに限り、皆が同じ証言をした。『三条家の使用人が首切様を連れてきて、村人たちを次々に殺したのだ』と。
調査は隣村である奥笹村の自警団が担当し、首切様の伝説が残る幽世山を中心に大規模な捜索がなされた。しかし首切様と思われる人物はおろか、三条家の使用人である朝倉苗の姿すら見つけることは叶わなかった。
かろうじて見つけられた物は、洞穴の内部に残された血脂にまみれた刀と、血飛沫を浴びたひび割れ模様の面だけだった。
彼らの行方を知る者はいない。fin.
風のない夜だ。空気はべたりと湿気を帯びていて、甘く蕩けるような植物の香りが辺りを満たしている。どこかで不気味に鳥が鳴く。不規則で騒がしい虫たちの声が聞こえてくる。辺りの様子をうかがうように視線を動かせば、鬱蒼と生い茂る木々が苗のことを見下ろしていた。
その状況は以前にも体験したことがあり、苗は震える声でつぶやいた。
「いや……何で。どうして」
そこは死に戻る前、首切様に首を落とされたのと同じ場所だった。両手と両足は麻縄で縛られていて、どう足掻いても逃げ出すことは叶わない。全身がズキズキと痛むのは、紫を殺した罰として殴る蹴るの暴行を受けたから。何もかもが死に戻る前と同じ状況だった。
息を止めて気配を殺す。どうかこの場所に彼が現れないことを必死で願う。しかし苗の願いが天に届くことはなく、間もなく虫たちの鳴き声は止み、草を踏み分ける音が聞こえてきた。
あざけるように笑うひび割れ模様の面、狒々を思わせる紅毛、闇夜にまぎれるためにあつらわれたような黒無地の着物、そして月光を浴びて輝く研ぎ澄まされた刃。
「――首切様」
満月を背に立つ首切様を、苗は力なく見上げた。死に戻る前の苗は、首切様を前に己の無実を訴えたけれど、もう同じことをする気力はなかった。無実を訴えたところで聞き入れられることはない。もう数秒と経たずに苗は死ぬ。あの輝く刃に首を落とされて。
(お母様、ごめんなさい。せっかく手に入れた機会を無駄にしてしまった。私は未来を、運命を、変えることができなかった)
様々な思い出が走馬灯として頭の中を巡った。その大半がろくでもなく苦痛に溢れたものだったが、篝との思い出だけが眩しく輝いていた。
幽世山の洞穴で出会った鬼の青年は、苗の世界に射し込んだ一筋の光。篝と一緒に過ごす時間は、苗につらい現実を忘れさせてくれた。
(もう一度、会いたかったな……)
ぽろりと瞳から涙が溢れた。
死の直前に顔を思い出して、初めて彼を恋い慕っていたのだと気がついた。だけどもう想いを伝えることは叶わないから、どうか彼の未来が幸に溢れたものであることを願う。
「……さよなら、篝」
苗は目を閉じ、身体から力を抜いた。きたるべき最期に備えるために。少しでも痛みを感じないように。
ひゅうと風を切る音がした。
静寂は破れ、また虫たちの鳴き声が聞こえ始めた。湿気を帯びた風が吹き抜けていく。まばらに生えた草木を満月が照らしている。
「…………え?」
苗はおそるおそる目を開いた。
あれだけはっきりと死の足音を聞いたというのに、苗は死んでいなかった。首切様が振り落ろした刃は苗の手足を縛っていた麻縄を切り、役目を終えたとばかりに鞘に納められていた。
「苗」
ひび割れ模様の面の向こうから優しい声を聞いた。それほ苗を傷つけようとする人の声ではなく、苗は困惑した。
「あ……貴方は?」
呼びかけに応えるように面が外された。血で染め上げたかのような紅髪をひたいに流した彼は、かがり火色の目を細め、苗の顔を愛おしむように見つめていた。
髪の色こそ違えど、それは苗が死の淵でもう一度会いたいと願った篝だった。
◇
あるところに、人間の血を受け継いだ鬼がいた。鬼は燃えるような緋色の髪を持ち、見た目こそ立派な鬼だったが、心は鬼よりも人間に近かった。他者の命を奪うことを好まず、生きるために人間の魂を喰らう行為さえ苦痛と感じていた。
鬼は、人間の世界で一人の少女を見つけた。戦で家族を亡くした哀れな少女だった。鬼は正体を隠して少女に近づいた。身寄りがないのならば魂も喰いやすかろうと思ったからだ。
しかし、鬼は少女を喰えなかった。それどころか少女の心優しさに惹かれ、野山で採った食べ物を届けるまでになった。鬼は、鬼であることを隠し少女とともに生きたいと願った。
鬼の願いは叶わなかった。鬼の母親が少女の存在に気づき、息子を誑かされてはならぬと少女を八つ裂きにしたからだ。鬼は怒り狂ったが、権力を持つ母親の前ではできることなど何もなかった。人間を殺すべき鬼の身でありながら、人間のように人間を愛したことを罪とされ、人間界にある小さな山の洞穴へと幽閉された。
母親は言った。「満月の夜だけお前を自由にしてあげる。1000人の人間を殺して鬼の心を取り戻しなさい。そうすれば黄泉の国へと帰らせてあげるから」
鬼は答えた。「俺はむやみと人間を殺したくはない。殺せと言うのならば、罪を犯した人間だけを殺すと誓う。お前が八つ裂きにした少女の魂に誓う」
鬼は己の誓いを忠実に守った。満月の夜に付近の村へと赴き、牢屋に入れられた罪人の首を切って回った。いつしか鬼は罪人を裁く『首切様』として祀られるようになり、鬼が村へと赴かずとも、裁かれるべき罪人が山へと届けられるようになった。
しかし時が過ぎるにつれ、村の人々は首切様の存在を忘れていった。村独自の自警団や留置場が整備され、罪人が正しく裁かれるようになったからだ。
首切様の存在はいつしか伝承となった。子どもたちが『幽世山には首切様がいるらしいよ』と噂話をするだけの陽炎のような存在だ。その頃には鬼も生きる気力を失っていた。相手が罪人とはいえ、人間を殺すことは鬼にとって苦痛でしかなく、1000人の人間を殺してまで黄泉の国に戻りたいとは到底思えなかった。
このまま洞穴の中で死のう、と鬼は考えた。鬼の肉体は人間よりもはるかに強靱だが、魂を喰わずにいればいつかは死ぬ。生きる目的もないのだからそれで構わないと思った。
苗という名前の美しい少女が、洞穴にやってくるまでは――
◇
「……篝は、人間を愛してしまったから黄泉の国を追い出されたのね」
篝の胸元に背中を預けながら、苗は言った。二人分の着物越しに篝の体温が伝わってくる。鬼であったとしてもその温かさは人間と変わらない。
苗は一度、篝に殺された。自分を殺した男が目の前にいるというのに、恐ろしさは感じず、それどころか篝の腕に抱かれていることが幸せだった。
「彼女は何という名前だったの?」
「里子だ。不遇な境遇に置かれながらも他人を思いやる優しい少女だった」
「そう……」
篝は木の幹に背中を預け、苗はそんな篝に背中を預けながら、たくさんの話をした。篝は自分が首切様になった経緯を、苗は罪人として幽世山に連れてこられた経緯を。包み隠さずに話せば、互いに特別な存在に慣れた気がした。
「篝は……これからどうするの?」
「……どうすることもできない。俺が自由に歩けるのは満月の夜だけで、朝が来ればまた洞穴に閉じ込められてしまうから」
そうだよね、と苗は相槌を打った。
「私は……これからどうすればいいのかしら……」
答えを求めるでもなくぽつりと零した。
苗は首切様に殺されなかったが、苗に着せられた罪が消えてなくなることはない。屋敷に戻ることはできないし、三条家に追従する村の人々が苗を匿ってくれるとも思えない。付近の村へ移住しようにも、その村に苗の噂が伝わってしまえば結局は同じ事だ。
(命は助かったけれど、親殺しの罪を着せられた私が生きていく道なんてないのかもしれない……)
苗は生きることを諦めつつあった。機会を与えられてもなお大切な母親を守ることができなかった。苗はこれから誰と寄り添い生きていけばいいのだろう。味方もなく、犯してもいない罪を償うために生を繋ぐくらいなら、いっそこの場で命など捨ててしまった方が幸せなのやも。
生きる気力を失くす苗の耳に、篝の声が届いた。
「苗……俺はできそこないの鬼だ。機会を与えられてもなお、心まで鬼になることができなかった」
苗は黙って篝の言葉に耳を傾けた。
「でも俺は……今だけは鬼になりたい。髪の毛の一束まで鬼になりたい。そうすれば苗を守ることができるから。俺の隣に苗の居場所を作ってあげられるから」
篝の、苗を抱く腕に力がこもった。
「苗、俺の心になってくれないか。一人では鬼になれない俺のために、今だけでいいから苗の心を貸してくれ。必ずや幸せにすると誓うから」
苗は篝の顔を見つめた。強い意志を湛えた瞳が苗のことを見下ろしていた。人間の営みをいとも容易く焼き尽くす業火のように赤く、美しい。苗は不意に気がついた。
(ああ、そうか……お母様は死んでしまったけれど、私には篝がいるんだ)
死に戻り、懸命に人の運命を変えようとした。しかし苗は誰の運命も変えることができなかった。暴力事件を起こした男は首切様に首を落とされ、紫は霧江の策略によって死んでいった。
初めから、苗の力では人間の運命を変えることはできなかったのだ。苗に変えられたのは篝に関わることだけ。人間の運命は変えることができずとも、鬼の運命ならば変えることができた。
篝ができそこないの鬼だというのなら、足りない部分は苗が補ってあげればいい。篝が一人では鬼になれないというのなら、二人で鬼になればいい。苗は微笑みながら答えた。
「いいよ、私が篝の心になってあげる」
篝は苗のひたいにこつんと自分のひたいを当てて、穏やかな表情で「ありがとう」と言った。
◇
霧江は上機嫌で寝支度をしていた。今日は霧江にとって最高の一日だった。大嫌いな義妹に母殺しの罪を着せ、首切様の住まう幽世山に置き去りにした。今頃は首のない死体となって冷たい地面に横たわっているはずだ。
「薄汚い女中の分際で、私の一之助を誑かすから悪いのよ。本当にいい気味だわ」
霧江は、苗に母親殺しの罪を着せるべく、紫の薬に毒を混ぜた。苗が毒に気がついたことは想定外だったが、若い女中に金を握らせ苗の行動を見張らせた。薬が川に捨てられたことを知った霧江は、そのことを女中に証言させ、苗に母殺しの罪を着せることに成功した――。
光子と源嗣は、霧江の悪巧みに薄々感付いていたのかもしれない。しかし光子は苗と紫を嫌っているし、源嗣は彼女たちの件に関して知らず存ぜずな態度を貫いている。霧江が罪に問われることはありえなかった。
霧江が寝間着の腰紐を締めたとき、座敷の襖がすぅと開いた。霧江は首をひねり、薄く開いた襖の隙間に呼びかけた。
「お母様、なぁに?」
霧江の座敷の襖を、前置きもなく開けようとする人物は光子しかいない。今夜も光子がやってきたものだろうと思ったが、襖の向こうから光子の声が聞こえない。薄く空いた襖からは、冷たい冷気が音もなく流れ込んでくるだけ。
「……お母様?」
霧江が怪しみながら呼びかけた次の瞬間、襖は勢いよく開かれた。同時に鞠のような物が投げ入れられる。どん、と鈍い音を立てて畳に落ちたそれは、霧江が人生で一度も見たことがないものだった。
「ひ……ひぎゃああああっ!」
光子の生首だった。だらりと開いた口からは赤黒い舌が覗き、光を失くした両目は虚空を見つめていた。切り口からはまだ鮮血が流れ出している。光子が絶命したのはつい先ほどの出来事だということだ。
霧江は光子の生首から目を逸らすこともできず、尻餅をついてがたがたと震えた。恐ろしさに腰が抜けて立つこともままならなかった。
「だ、誰なの……そこにいるのは誰なのよ!」
霧江が開け放たれた襖の向こう側に向かって叫ぶと、暗闇からまず現れたのは血に濡れた刃だった。続いてひび割れ模様の面をつけた男が姿を現し、紅髪を揺らしながら敷居をまたぐ。
霧江は唖然としてつぶやいた。
「どうして首切様がここにいるの……どうしてお母様を殺すのよ……何も悪いことなんてしていないじゃない!」
そのとき、「霧子ねえ様」と聞き慣れた声で名前を呼ばれた。幽世山に置き去りにしたはずの苗だった。首切様の背後に半身を隠し、感情のない瞳で霧子のことを見据えている。霧江にはもう何が何だかわからなかった。
「お前、首切様に殺されたはずじゃ――」
霧子の言葉を遮って、苗はまた「ねえ様」と呼びかけた。
「私、幸せになんてならなくてよかったの。お母様と2人で誰の目にも留まらず、食うに困らない生活ができればそれで幸せだったの」
「は……?」
「でも霧子ねえ様は……いえ、この村の人たちは私からお母様を奪った。助けを求めても手を差し伸べず、薬も与えず見殺しにした。だから私はお前達を裁くため鬼切様の心になったのよ」
苗の声は落ち着いていたが、ふつふつと静かな憎しみをたぎらせていた。
ふいに霧江は、首切様ではなく苗の存在が恐ろしくなった。見下し蔑み続けた少女が、か細い身体に殺意をみなぎらせ霧江の元へと戻ってきた。手遊びで振り回していた刃が、いつか自分の首を切ることになるなど想像もしなかった。
「ち、違う! 私は何も悪くない! 確かに薬に毒を入れたのは私だけど、紫は毒を飲んでいないのだから私の罪にはならないはずよ! そうでしょう!?」
霧江は畳の上を後ずさりながら必死で言い逃れようとした。他人を殺そうとした身でありながら、自分が死ぬことは馬鹿みたいに恐ろしかった。
私のせいじゃない、私は悪くない、欺瞞に満ちた訴えが届くことはない。首切様はまだそこにいる。右手には血濡れの刃を握りしめて。
「……あああああ! この糞女! やっぱりお前は性根の腐った売女よ! 一之介様を誑かしたように首切様を誑かしたんでしょう! そうじゃなきゃ、お前のような蛆虫の言葉に首切様が耳を傾けるはずがない!」
霧子は半狂乱で叫んだ。髪を振り乱し、目を血走らせ、一之助を奪われては堪らぬと苗を糾弾したときと同じように。
あのときと違うのは、生殺与奪の権利を握っているのが霧江ではなく苗だということ。
「殺して、篝」
「ああ」
霧江の頭上に刃が振りかざされた。首筋にすさまじい衝撃を感じたのを最後に、霧江の意識はぷつりと途絶え、それきり永遠に覚めることはなかった。
◇
慶光六年八月五日。
高嶺郡の南方に位置する月霞村にて、不可解な大量殺人事件が発生。被害者の数は1000人を越え、全員が鋭利な刃物で首を切り落とされて絶命していた。被害者の中には月霞村の村長である三条源嗣、家内である三条光子、三条霧江も含まれる。
生き残った村人は16歳未満の子どもに限り、皆が同じ証言をした。『三条家の使用人が首切様を連れてきて、村人たちを次々に殺したのだ』と。
調査は隣村である奥笹村の自警団が担当し、首切様の伝説が残る幽世山を中心に大規模な捜索がなされた。しかし首切様と思われる人物はおろか、三条家の使用人である朝倉苗の姿すら見つけることは叶わなかった。
かろうじて見つけられた物は、洞穴の内部に残された血脂にまみれた刀と、血飛沫を浴びたひび割れ模様の面だけだった。
彼らの行方を知る者はいない。fin.