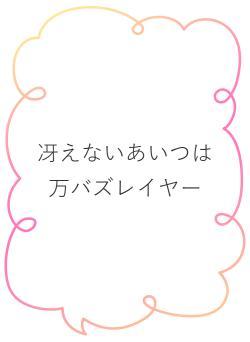苗が洞穴を去ったあと、篝の元を訪れる人があった。
その女性は毒々しい赤紫の着物に漆黒の羽織を合わせ、腰まである真っ赤な髪を揺らしながら、篝に向かって笑いかけた。
「ごきげんよう、篝。元気そうで何よりだわ」
篝は女性を睨みながら毒づいた。
「俺が、元気そうに見えるのか?」
「思っていたよりもずっと元気だわ。最後に会ったのはもう100年も前のことだもの。死にかけているか、本当に死んでいてもおかしくないと思った」
女性はけらけらと耳障りな声で笑う。彼女の名前は鏡花――黄泉の国の治める鬼王の一人であり、篝の生みの母親だ。そして300年前、篝をこの洞穴に幽閉した人物でもある。齢は500を優に越える長命の鬼だというのに、その見た目は少女のように若々しい。真っ赤な紅を引いた唇の鮮やかで艶やかなこと。
「それで、今日は何の用だ? ようやく俺をここから出す気になったのか?」
「まさか、だってお前はまだ罪を償っていないもの。ただお前の無様な姿を見にきただけよ」
あっさりと言い切られてしまったので、篝はこれ見よがしに溜息をついた。
「……馬鹿馬鹿しい。何が罪だ。俺の行いが罪だと言うのなら、この人間の世界は罪人で溢れてしまうだろうに」
「そうね。もしお前が人間だったなら、あの愚かな行いを罪と言われることもなかったでしょう。でよお前は鬼よ。それも黄泉の国を治める鬼王の子。だからお前は髪の毛の一筋まで鬼でなければならない」
「……」
今から300年前、篝はとある過ちを犯した。その過ちは篝にとっては些細なことだったが、母親である鏡花の言により重罪と見なされ、黄泉の国から追放された。
いや、追放というのは大げさだろうか。篝にはまだ黄泉の国に帰る道が残されているのだから。
「篝。いい加減、目を覚ましなさい」
鏡花は腰をかがめて篝の頰をなでた。鎖に繋がれた我が子を愛おしむように。
「私はお前に贖罪の機会を与えている。その機会を無下にしているのは他でもないお前よ。罪を償い、一刻も早く黄泉の国へ戻っていらっしゃい。そうすれば、私の持つ富と地位をそのままお前に譲り渡してあげましょう」
そろそろ王でいることにも疲れたのよ、と鏡花は言った。
100年ぶりのそこで会話は終わり、鏡花は洞穴から出ていこうとした。その背中に、篝は遠慮がちに問いかけた。
「……もしも俺が罪を償えば、人間を一人、黄泉の国に連れ帰ってもいいか?」
鏡花は歩みを止め、怪訝な表情で振り返った。
「まさかその人間は、若い女?」
「そうだ」
「……呆れた。これだけの罰を受けてもなお、お前は人間に心を移すのね」
やれやれと大げさに肩を竦め、それから強い口調で言い放った。
「無理よ、人間を黄泉の国に招き入れることは許されない」
「だが、俺の父親は人間のはずだ。母上がとある人間の男を見初め、伴侶とすべく黄泉の国に連れ帰ったのだと聞いている」
「……あら、何よ。知ってたの」
鏡花は目を丸くした。篝は父親の顔を知らない。篝が産まれてすぐに亡くなってしまったからだ。死の理由を鏡花の口から直接聞いたことはないが、女中たちの噂話を耳にしたことがあった。
篝の父親は人間だ。鏡花が人間の男を黄泉の国に連れ帰り、伴侶とした。そうして産まれた子どもが篝だ。しかし人間の身体では黄泉の国の瘴気にいくばくも絶えることができず、彼は若くして命を落としたのだ――と。
「母上が人間の男を伴侶としたのなら、俺にもそれが許されるのではないか?」
篝の声は洞穴の内部に大きく響き渡った。
鏡花はしばらく考えこんでいたが、やがて紅を引いた唇をゆっくりと開いた。
「……私が愛した男は、人間でありながら心は鬼だった。戰場で500の命を屠った根っからの戦人よ。女子供を殺すことも、捕らえた敵を拷問することも苦とは感じていなかった。だから私は彼に惹かれたの。人間の身でありながら鬼の心を宿すその歪さに」
鏡花は唇を撫でながら言葉を続ける。
「お前が愛した女は鬼の心を持っているかしら? いえ、そんなことはありえない。お前が愛するくらいなのだから、さぞかし健気で優しい少女でしょうね。ただ優しいだけの女など次期鬼王の隣にふさわしくない」
篝は何も言い返せなかった。
鏡花の言うとおり、苗は心優しい少女だ。薄汚れて弱りきった篝のために、何度も食べ物を持ってきてくれた。腹は膨れなくとも、そうして気にかけてもらえることが嬉しかった。篝は苗と過ごす時間が――苗のことが好きだった。
苗は哀れな少女だ。苗は自身の境遇を語らないが、着古してすり切れた着物と、気の毒になるくらい痩せた身体が苗の境遇を物語っていた。着物からのぞく腕や足に、真新しい傷跡を見たこともある。
今日、洞穴にやってくる前、苗は泣いていたのだろう。なぜ泣いていたのかはわからない。尋ねたところで苗は教えてくれないだろうし、知ったところで今の篝は苗を助けることができない。
でも、もし叶うのなら篝は苗を助けたかった。たとえ己の信念を捨て去ったとしても。髪の毛の一束まで鬼になったとしても。
「もう話すこともないようだし、私は帰るわよ。次は黄泉の国で会えることを願っているわ。――私の可愛い篝」
そうして鏡花は去っていった。
◇
一之助との出会いから一週間と数日が過ぎた。
食事も与えられない日々を想像していたが、予想に違い、苗は平穏な毎日を送ることができていた。煙管の灰を落とされるでもない、罵倒を吐きかけられるでもない、不気味さを覚えるほどの平穏な日々。
その日、仕事を終えた苗は、2人分の夕食を持って紫のいる小屋を訪れた。最近は無茶な仕事を言いつけられることがないため、紫と2人でゆっくりと夕食をとることができている。母娘水入らずのかけがえのない時間だ。
「お母様、体調はどう?」
小さなあじの開きを箸先でつつきながら苗は尋ねた。
「何も問題はないわ。だから心配しなくて大丈夫」
「そう……」
紫の言葉がまったくの強がりであることを苗は知っていた。紫の病状は悪い。激しい咳と一緒に血を吐くことが一日に何度もあり、食事をとってもすぐに戻してしまう。手足は枯れ木のように痩せ細り、落ちくぼんだ眼窩に生気はない。
そうまでなってもやはり医者を呼ぶことは許されず、紫の元には日々たくさんの針仕事が持ち込まれる。本当ならば一日の大半を寝て過ごさなければならない状態だというのに、紫は命の絶えかけた身体に鞭を打って仕事を続けている。苗にはどうすることもできなかった。
(霧江ねえ様がお母様の薬に毒を盛るのは1か月後……何もできないまま、ここまで来てしまった)
苗は憂鬱な表情で食事を終え、紫の薬を用意するために席を立った。山で採ってきた薬草を乾燥させた苗手製の薬。どれだけの効果があるのかはわからないが、医者も薬師も頼れない状況ではこれくらいしかできることがなかった。
「……あら?」
座敷の隅にある薬箱を開けた苗は、かすかな違和感を覚えた。手のひら大の小さな薬箱の中には、乾燥させた数種類の薬草が入れられているのだが、昼食時よりも薬草の量が増えている気がした。
(まさか……)
苗は風を通すための小窓から空を見上げた。雲のない夜空には、左端が少しだけ欠けた月が浮いている。明日は満月だ。
鼓動は一気に跳ね上がり、苗は薬箱の蓋を勢いよく閉めた。死に戻る前、霧江は満月の前日に紫の薬に毒を盛った。1か月のずれはあれど今日と同じ状況だ。
(どうして……霧江ねえ様が行動を起こすのはまだ1か月先のはずなのに。私が、予定よりも早く市之助と出会ってしまったから? 運命がずれてしまったの?)
苗が唖然と佇んでいると、横顔に紫の不安そうな声があたった。
「苗……どうしたの?」
苗は慌てて笑った。
「あ……何でもないの。ちょっと薬を切らしてしまったみたいで。明日の朝、山に行って採ってくるわね……」
「あら、そう……私は大丈夫だから、無理しないでね」
その場は曖昧にごまかして薬箱を持ち出し、中身はすべて近くの川に捨てた。母の命を救ったのだという満足感はあれど、この判断が思いもよらない未来を招くとは想像もしなかった。
◇
まだ日も昇らない頃だというのに、襖の向こうがいやに騒がしかった。苗が眠い目をこすりながら起き上がると、座敷の襖が開き、中年の女中が飛び込んできた。そして慌てふためきながら意味のわからないことを言った。
「苗! あんたの母親が亡くなってるよ!」
「え?」
何度も反芻すれば意味は理解できたが、苗は女中の言葉をすぐに信じることはできなかった。そんなはずはない。嘘に決まっている。どこか夢見心地のまま紫のいる小屋へと向かう。
早朝だというのに、小屋の周囲にはたくさんの女中が集まっていた。苗が人混みをかきわけ小屋の中に入ると、狭苦しい座敷は血の匂いで満たされていた。血だまりの中心に紫が倒れている。苦しそうに両目を見開き、口からはおびただしい量の喀血を流して。
「嘘……お母様、どうして」
苗は愕然としてふらふらと紫に歩み寄った。もうそれは紫ではなく、かつて紫だったもの。骨と皮だけになった手足にぬくもりはなく、石のように冷たく固まっている。彼女はもう口を開かない、痩せた手で苗を撫でることもない。まともな薬も与えられずこき使われて、血だまりに沈む屍となってしまった。
思いがけない母の死を前に心は動きを止め、苗は呆然自失と屍のかたわらに座り込んでいた。視界の端でいくつかの人影が動く。霧江と、光子と、源嗣、そして村医者。
ああ、ようやく紫の元に医者がやってきた。すべてはもう手遅れなのに。
「……間違いなくご臨終ですね。吐いた血が器官に逆流したものと思われます。呼吸ができずかなり苦しんだのではないかと」
診察らしい診察をすることもなく医者は告げた。苦しみに満ちた表情を隠すように、紫の顔には白い布が被せられる。「病気だったんだもの、仕方ないわよね」と女中の誰かが言った。「ろくに食事もできていないようだったしね」「最近は見るからに弱っていたもの」と口々に。
光子は何も言わなかったが、「汚れ物が一つ片付いた」とさっぱりした表情を浮かべていた。源嗣は「畳を張り替えねばならん」と迷惑そうにつぶやき、霧江は血の匂いを避けるように着物の袖口で口元を覆っている。紫の死は、彼らの心を一寸たりとも動かしていないようだ。
座敷の隅にいた若い女中が、ぶるぶると肩を震わせながら口を開いたのはそのときだった。
「あの……私、見ました。昨晩……」
「昨晩、何を見たんだ?」
先を促したのは源嗣で、女中は恐れ多さに身を縮めながら必死に証言した。
「昨晩、近くの川で怪しい人影を見たんです。薬箱を傾けて、中の薬を捨てているようでした……そこにいる苗が」
「――え?」
全員の視線が苗の方へと向いた。苗は驚き、そして困惑した。昨晩、確かに苗は紫の薬を川に捨てた。毒が混じった薬を、紫が誤って飲んでしまわないようにとの配慮だった。三条家の屋敷からさほど離れた川ではなかったし、周囲の人通りも気にはしていなかったから、誰かに見られていたとしても不思議ではない。
でもなぜ今、女中はそのことを証言したのだろう? よりにもよってこれだけ大勢の人がいる場所で。
苗の疑問はすぐに解消することとなった。一歩前へと進み出た霧江が、喜色満面で女中の証言を要約したからだ。言葉の端々に苗への悪意をにじませて。
「皆、聞いたかしら? 苗は母親の薬を川に捨てたそうよ。命を繋ぐ大切な薬を捨ててしまうなんて、よほど母親のことが憎かったみたいね」
「え……」
「薬を飲めなかったせいで病気が悪化して死んだのだとすれば、苗が母親を殺したも同然だわ!」
違う、と苗は叫んだ。
「確かに私はお母様の薬を捨てたわ。でもそれは、薬に毒が混ぜられていたからよ!」
「毒ぅ? どうしてそんなことがわかるのよ。味見でもしたっていうの?」
「それは――」
苗は言葉に詰まった。薬に毒が混ぜられていることに気がついたのは、死に戻る前の記憶があったからだ。記憶がなければ、違和感を覚えながらもいつもどおり薬を飲ませていただろう。霧江が苗を憎んでいるのだとしても、まさか紫を殺そうとまでするとは想像もできなかったから。
「……何よ、言い訳できないの? ああ、わかったわ。あんたが母親の薬に毒を盛ったんでしょう。毎日毎日、死にぞこないの看病をするのは大変だものね。でも直前で怖気づいて毒を飲ませることができず、証拠を隠滅するために川へ捨てた――というところかしら?」
霧江の表情は嗜虐心に満ちていた。苗を貶めることが楽しくて仕方ないというように嗤う。
苗は瞬時に霧江の思惑を理解した。霧江は、紫の死を殺人に仕立て上げようとしている。言うまでもなく殺人犯役は苗だ。すべては苗を消すためのくだらない策略。
だがこの村では三条家の言は絶対だ。三条家の人々が黒といえば、白いものも黒くなる。
「――面倒なことをしてくれたな、苗」
吐き捨てるような声のあと、したたかに頬を殴られた。脳が揺れ、なすすべもなく畳へと倒れ込む。
苗を殴ったのは源嗣だった。こぶしを握り、害虫を見るかのごとく苗のことをねめつけている。苗は必死に言い募ろうとしたが、意識が朦朧として「あ、う……」と喘ぐことしかできなかった。
「屋敷に置いてやった恩を仇で返すとは、とんでもない奴だ。自警団に引き渡そうにも、三条家は親を殺すような女中を雇っていたと不名誉な噂が流れてしまうではないか」
(私がお母様を殺したですって……? 医者も呼ばず、薬も与えず、よくもそんなことを……)
抵抗することも反論することもできないまま、苗の意識は暗闇へと飲み込まれていく。
意識がぷつりと途絶える寸前、甘えるような霧江の声を聞いた。
「ねぇお父様。自警団には連絡せず、幽世山に連れて行きましょうよ。そうすれば――」
その女性は毒々しい赤紫の着物に漆黒の羽織を合わせ、腰まである真っ赤な髪を揺らしながら、篝に向かって笑いかけた。
「ごきげんよう、篝。元気そうで何よりだわ」
篝は女性を睨みながら毒づいた。
「俺が、元気そうに見えるのか?」
「思っていたよりもずっと元気だわ。最後に会ったのはもう100年も前のことだもの。死にかけているか、本当に死んでいてもおかしくないと思った」
女性はけらけらと耳障りな声で笑う。彼女の名前は鏡花――黄泉の国の治める鬼王の一人であり、篝の生みの母親だ。そして300年前、篝をこの洞穴に幽閉した人物でもある。齢は500を優に越える長命の鬼だというのに、その見た目は少女のように若々しい。真っ赤な紅を引いた唇の鮮やかで艶やかなこと。
「それで、今日は何の用だ? ようやく俺をここから出す気になったのか?」
「まさか、だってお前はまだ罪を償っていないもの。ただお前の無様な姿を見にきただけよ」
あっさりと言い切られてしまったので、篝はこれ見よがしに溜息をついた。
「……馬鹿馬鹿しい。何が罪だ。俺の行いが罪だと言うのなら、この人間の世界は罪人で溢れてしまうだろうに」
「そうね。もしお前が人間だったなら、あの愚かな行いを罪と言われることもなかったでしょう。でよお前は鬼よ。それも黄泉の国を治める鬼王の子。だからお前は髪の毛の一筋まで鬼でなければならない」
「……」
今から300年前、篝はとある過ちを犯した。その過ちは篝にとっては些細なことだったが、母親である鏡花の言により重罪と見なされ、黄泉の国から追放された。
いや、追放というのは大げさだろうか。篝にはまだ黄泉の国に帰る道が残されているのだから。
「篝。いい加減、目を覚ましなさい」
鏡花は腰をかがめて篝の頰をなでた。鎖に繋がれた我が子を愛おしむように。
「私はお前に贖罪の機会を与えている。その機会を無下にしているのは他でもないお前よ。罪を償い、一刻も早く黄泉の国へ戻っていらっしゃい。そうすれば、私の持つ富と地位をそのままお前に譲り渡してあげましょう」
そろそろ王でいることにも疲れたのよ、と鏡花は言った。
100年ぶりのそこで会話は終わり、鏡花は洞穴から出ていこうとした。その背中に、篝は遠慮がちに問いかけた。
「……もしも俺が罪を償えば、人間を一人、黄泉の国に連れ帰ってもいいか?」
鏡花は歩みを止め、怪訝な表情で振り返った。
「まさかその人間は、若い女?」
「そうだ」
「……呆れた。これだけの罰を受けてもなお、お前は人間に心を移すのね」
やれやれと大げさに肩を竦め、それから強い口調で言い放った。
「無理よ、人間を黄泉の国に招き入れることは許されない」
「だが、俺の父親は人間のはずだ。母上がとある人間の男を見初め、伴侶とすべく黄泉の国に連れ帰ったのだと聞いている」
「……あら、何よ。知ってたの」
鏡花は目を丸くした。篝は父親の顔を知らない。篝が産まれてすぐに亡くなってしまったからだ。死の理由を鏡花の口から直接聞いたことはないが、女中たちの噂話を耳にしたことがあった。
篝の父親は人間だ。鏡花が人間の男を黄泉の国に連れ帰り、伴侶とした。そうして産まれた子どもが篝だ。しかし人間の身体では黄泉の国の瘴気にいくばくも絶えることができず、彼は若くして命を落としたのだ――と。
「母上が人間の男を伴侶としたのなら、俺にもそれが許されるのではないか?」
篝の声は洞穴の内部に大きく響き渡った。
鏡花はしばらく考えこんでいたが、やがて紅を引いた唇をゆっくりと開いた。
「……私が愛した男は、人間でありながら心は鬼だった。戰場で500の命を屠った根っからの戦人よ。女子供を殺すことも、捕らえた敵を拷問することも苦とは感じていなかった。だから私は彼に惹かれたの。人間の身でありながら鬼の心を宿すその歪さに」
鏡花は唇を撫でながら言葉を続ける。
「お前が愛した女は鬼の心を持っているかしら? いえ、そんなことはありえない。お前が愛するくらいなのだから、さぞかし健気で優しい少女でしょうね。ただ優しいだけの女など次期鬼王の隣にふさわしくない」
篝は何も言い返せなかった。
鏡花の言うとおり、苗は心優しい少女だ。薄汚れて弱りきった篝のために、何度も食べ物を持ってきてくれた。腹は膨れなくとも、そうして気にかけてもらえることが嬉しかった。篝は苗と過ごす時間が――苗のことが好きだった。
苗は哀れな少女だ。苗は自身の境遇を語らないが、着古してすり切れた着物と、気の毒になるくらい痩せた身体が苗の境遇を物語っていた。着物からのぞく腕や足に、真新しい傷跡を見たこともある。
今日、洞穴にやってくる前、苗は泣いていたのだろう。なぜ泣いていたのかはわからない。尋ねたところで苗は教えてくれないだろうし、知ったところで今の篝は苗を助けることができない。
でも、もし叶うのなら篝は苗を助けたかった。たとえ己の信念を捨て去ったとしても。髪の毛の一束まで鬼になったとしても。
「もう話すこともないようだし、私は帰るわよ。次は黄泉の国で会えることを願っているわ。――私の可愛い篝」
そうして鏡花は去っていった。
◇
一之助との出会いから一週間と数日が過ぎた。
食事も与えられない日々を想像していたが、予想に違い、苗は平穏な毎日を送ることができていた。煙管の灰を落とされるでもない、罵倒を吐きかけられるでもない、不気味さを覚えるほどの平穏な日々。
その日、仕事を終えた苗は、2人分の夕食を持って紫のいる小屋を訪れた。最近は無茶な仕事を言いつけられることがないため、紫と2人でゆっくりと夕食をとることができている。母娘水入らずのかけがえのない時間だ。
「お母様、体調はどう?」
小さなあじの開きを箸先でつつきながら苗は尋ねた。
「何も問題はないわ。だから心配しなくて大丈夫」
「そう……」
紫の言葉がまったくの強がりであることを苗は知っていた。紫の病状は悪い。激しい咳と一緒に血を吐くことが一日に何度もあり、食事をとってもすぐに戻してしまう。手足は枯れ木のように痩せ細り、落ちくぼんだ眼窩に生気はない。
そうまでなってもやはり医者を呼ぶことは許されず、紫の元には日々たくさんの針仕事が持ち込まれる。本当ならば一日の大半を寝て過ごさなければならない状態だというのに、紫は命の絶えかけた身体に鞭を打って仕事を続けている。苗にはどうすることもできなかった。
(霧江ねえ様がお母様の薬に毒を盛るのは1か月後……何もできないまま、ここまで来てしまった)
苗は憂鬱な表情で食事を終え、紫の薬を用意するために席を立った。山で採ってきた薬草を乾燥させた苗手製の薬。どれだけの効果があるのかはわからないが、医者も薬師も頼れない状況ではこれくらいしかできることがなかった。
「……あら?」
座敷の隅にある薬箱を開けた苗は、かすかな違和感を覚えた。手のひら大の小さな薬箱の中には、乾燥させた数種類の薬草が入れられているのだが、昼食時よりも薬草の量が増えている気がした。
(まさか……)
苗は風を通すための小窓から空を見上げた。雲のない夜空には、左端が少しだけ欠けた月が浮いている。明日は満月だ。
鼓動は一気に跳ね上がり、苗は薬箱の蓋を勢いよく閉めた。死に戻る前、霧江は満月の前日に紫の薬に毒を盛った。1か月のずれはあれど今日と同じ状況だ。
(どうして……霧江ねえ様が行動を起こすのはまだ1か月先のはずなのに。私が、予定よりも早く市之助と出会ってしまったから? 運命がずれてしまったの?)
苗が唖然と佇んでいると、横顔に紫の不安そうな声があたった。
「苗……どうしたの?」
苗は慌てて笑った。
「あ……何でもないの。ちょっと薬を切らしてしまったみたいで。明日の朝、山に行って採ってくるわね……」
「あら、そう……私は大丈夫だから、無理しないでね」
その場は曖昧にごまかして薬箱を持ち出し、中身はすべて近くの川に捨てた。母の命を救ったのだという満足感はあれど、この判断が思いもよらない未来を招くとは想像もしなかった。
◇
まだ日も昇らない頃だというのに、襖の向こうがいやに騒がしかった。苗が眠い目をこすりながら起き上がると、座敷の襖が開き、中年の女中が飛び込んできた。そして慌てふためきながら意味のわからないことを言った。
「苗! あんたの母親が亡くなってるよ!」
「え?」
何度も反芻すれば意味は理解できたが、苗は女中の言葉をすぐに信じることはできなかった。そんなはずはない。嘘に決まっている。どこか夢見心地のまま紫のいる小屋へと向かう。
早朝だというのに、小屋の周囲にはたくさんの女中が集まっていた。苗が人混みをかきわけ小屋の中に入ると、狭苦しい座敷は血の匂いで満たされていた。血だまりの中心に紫が倒れている。苦しそうに両目を見開き、口からはおびただしい量の喀血を流して。
「嘘……お母様、どうして」
苗は愕然としてふらふらと紫に歩み寄った。もうそれは紫ではなく、かつて紫だったもの。骨と皮だけになった手足にぬくもりはなく、石のように冷たく固まっている。彼女はもう口を開かない、痩せた手で苗を撫でることもない。まともな薬も与えられずこき使われて、血だまりに沈む屍となってしまった。
思いがけない母の死を前に心は動きを止め、苗は呆然自失と屍のかたわらに座り込んでいた。視界の端でいくつかの人影が動く。霧江と、光子と、源嗣、そして村医者。
ああ、ようやく紫の元に医者がやってきた。すべてはもう手遅れなのに。
「……間違いなくご臨終ですね。吐いた血が器官に逆流したものと思われます。呼吸ができずかなり苦しんだのではないかと」
診察らしい診察をすることもなく医者は告げた。苦しみに満ちた表情を隠すように、紫の顔には白い布が被せられる。「病気だったんだもの、仕方ないわよね」と女中の誰かが言った。「ろくに食事もできていないようだったしね」「最近は見るからに弱っていたもの」と口々に。
光子は何も言わなかったが、「汚れ物が一つ片付いた」とさっぱりした表情を浮かべていた。源嗣は「畳を張り替えねばならん」と迷惑そうにつぶやき、霧江は血の匂いを避けるように着物の袖口で口元を覆っている。紫の死は、彼らの心を一寸たりとも動かしていないようだ。
座敷の隅にいた若い女中が、ぶるぶると肩を震わせながら口を開いたのはそのときだった。
「あの……私、見ました。昨晩……」
「昨晩、何を見たんだ?」
先を促したのは源嗣で、女中は恐れ多さに身を縮めながら必死に証言した。
「昨晩、近くの川で怪しい人影を見たんです。薬箱を傾けて、中の薬を捨てているようでした……そこにいる苗が」
「――え?」
全員の視線が苗の方へと向いた。苗は驚き、そして困惑した。昨晩、確かに苗は紫の薬を川に捨てた。毒が混じった薬を、紫が誤って飲んでしまわないようにとの配慮だった。三条家の屋敷からさほど離れた川ではなかったし、周囲の人通りも気にはしていなかったから、誰かに見られていたとしても不思議ではない。
でもなぜ今、女中はそのことを証言したのだろう? よりにもよってこれだけ大勢の人がいる場所で。
苗の疑問はすぐに解消することとなった。一歩前へと進み出た霧江が、喜色満面で女中の証言を要約したからだ。言葉の端々に苗への悪意をにじませて。
「皆、聞いたかしら? 苗は母親の薬を川に捨てたそうよ。命を繋ぐ大切な薬を捨ててしまうなんて、よほど母親のことが憎かったみたいね」
「え……」
「薬を飲めなかったせいで病気が悪化して死んだのだとすれば、苗が母親を殺したも同然だわ!」
違う、と苗は叫んだ。
「確かに私はお母様の薬を捨てたわ。でもそれは、薬に毒が混ぜられていたからよ!」
「毒ぅ? どうしてそんなことがわかるのよ。味見でもしたっていうの?」
「それは――」
苗は言葉に詰まった。薬に毒が混ぜられていることに気がついたのは、死に戻る前の記憶があったからだ。記憶がなければ、違和感を覚えながらもいつもどおり薬を飲ませていただろう。霧江が苗を憎んでいるのだとしても、まさか紫を殺そうとまでするとは想像もできなかったから。
「……何よ、言い訳できないの? ああ、わかったわ。あんたが母親の薬に毒を盛ったんでしょう。毎日毎日、死にぞこないの看病をするのは大変だものね。でも直前で怖気づいて毒を飲ませることができず、証拠を隠滅するために川へ捨てた――というところかしら?」
霧江の表情は嗜虐心に満ちていた。苗を貶めることが楽しくて仕方ないというように嗤う。
苗は瞬時に霧江の思惑を理解した。霧江は、紫の死を殺人に仕立て上げようとしている。言うまでもなく殺人犯役は苗だ。すべては苗を消すためのくだらない策略。
だがこの村では三条家の言は絶対だ。三条家の人々が黒といえば、白いものも黒くなる。
「――面倒なことをしてくれたな、苗」
吐き捨てるような声のあと、したたかに頬を殴られた。脳が揺れ、なすすべもなく畳へと倒れ込む。
苗を殴ったのは源嗣だった。こぶしを握り、害虫を見るかのごとく苗のことをねめつけている。苗は必死に言い募ろうとしたが、意識が朦朧として「あ、う……」と喘ぐことしかできなかった。
「屋敷に置いてやった恩を仇で返すとは、とんでもない奴だ。自警団に引き渡そうにも、三条家は親を殺すような女中を雇っていたと不名誉な噂が流れてしまうではないか」
(私がお母様を殺したですって……? 医者も呼ばず、薬も与えず、よくもそんなことを……)
抵抗することも反論することもできないまま、苗の意識は暗闇へと飲み込まれていく。
意識がぷつりと途絶える寸前、甘えるような霧江の声を聞いた。
「ねぇお父様。自警団には連絡せず、幽世山に連れて行きましょうよ。そうすれば――」