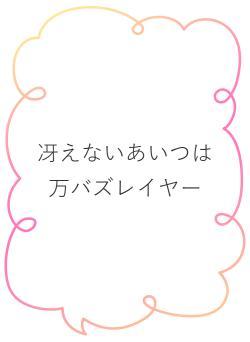暴力事件を起こした男が死体となって発見されてからというもの、村は首切様の噂で持ちきりとなった。言い伝えの中の存在だった首切様は、実在の神として人々に恐れられるようになった。
満月の夜から三週間が過ぎ、噂が少しずつ落ち着きを見せ始めた頃。
その日、三条家の人々は朝から大忙しだった。霧江の婚約者である香坂市之助が、結婚前の挨拶と称して三条家を訪れるからだ。女中たちは掃除に茶菓子の準備にと忙しなく働き、源嗣と光子も身支度に忙しい。
霧江に至っては、早朝から自室にこもり派手な着物を畳いっぱいに広げていた。襖の間からは「市之助様はどの着物がお好きかしら」と浮かれた声が漏れ出してくる。
そんなお祭り騒ぎの真っただ中にいても、苗はこれっぽっちも楽しい気分になれなかった。理由は色々とある。紫の容体が良くないこと、満月の夜の出来事がたびたび夢に出ること。そして一番の理由は――市之助が苗にとって不吉な存在だということ。
今日からおよそ半月後、苗はお使い先の商店で市之助と会う。大きな味噌樽を抱えた苗を不憫に思い、市之助が馬車で屋敷まで送ってくれるのだが、そのことが霧江の耳に入り殴られる蹴られるの散々な目に合うのだ。
市之助を奪われると極端な妄想を働かせた霧江は、苗を始末するべく紫の薬に毒を盛る。毒を飲んだ紫は死に、濡れ衣を着せられた苗は罪人として首切様に首を落とされる。市之助との出会いが、苗と紫に最悪の最期をもたらすということだ。だから苗は市之助の存在が恐ろしい。
「ちょっと、そこの役立たず」
苗が玄関先の掃き掃除をしていると、霧江が話しかけてきた。歌舞伎役者さながらの濃い化粧に、目がチカチカするような花車の着物。背後に2人の女中を従えた霧江は、ここ数か月の間で一番の上機嫌だ。
「……何でしょう」
「わかってると思うけど、市之助様の前に顔を出すんじゃないわよ。こんな不細工で薄汚い女中を雇っていると知れたら三条家の恥だもの」
「わかりました」
わざわざ言われなくても市之助と顔を合わせる気などなかったので、苗は素直にうなずいた。霧江もそれ以上、苗に構うつもりはないようで、鼻歌を歌いながら門の方へと歩いて行く。「市之助様はまだいらっしゃらないのかしら」と浮かれに浮かれて気味が悪いくらいだ。
(市之助様が滞在している間、どうやって時間を潰そうかしら……。前回は仕事を頼まれることがあるかもしれないと思って座敷に控えていたけれど、最後まで呼ばれることはなかったし……)
苗は少し考え、ぽんと手を打った。
「そうだ、篝のところへ行っていよう。そうすれば絶対に市之助様と顔を合わせることはないわ」
玄関の掃き掃除を終えた苗は、女中の1人に「山で薪を拾ってきます」と断りを入れて屋敷を出た。人気のない裏庭を抜け、裏門の閂を開ける。
満月の夜以降、気分が沈んで常世山から足が遠のいてしまっていた。だから久しぶりに篝と会えることが嬉しかった。
「今日は何を採っていってあげようかしら。そろそろヤマモモが実る頃だから――きゃっ」
裏門から飛び出した苗は、道を通りすがった人と勢いよくぶつかった。踏みとどまろうとしたものの、足元が乱れ尻もちをついてしまう。
「申し訳ありません! お嬢さん、お怪我はありませんか?」
尻をさする苗の目の前に、すっと手のひらが差し出された。大きくて節くれだった男の手だ。苗は戸惑ったが、手を借りないことも失礼な気がしたので、遠慮がちに差し出された手のひらを握り返した。
「こちらこそすみませんでした。急いでいて、よく前を見ていなかったから……」
「そのようですね。一瞬、門から猪が飛び出してきたのかと思いました」
猪のような勢いだったと言いたいのだろうか。苗は頬に熱がのぼるのを感じながら、男性の顔を見上げた。
「っ……」
その男性の顔を直視した瞬間、苗は言葉を失って立ち尽くした。
男性は艶のある黒髪を襟足のあたりで一つに束ね、着物の上に紋付きの羽織をはおっていた。長身もさることながら、背すじを伸ばして凛と立つ姿は美しい。苗の目から見ても美丈夫だとわかるその人物の名前は香坂一之介――苗が絶対に会いたくなかった霧江の婚約者だ。
「あ、あ……」
予想外の出会いに、苗は頭の中が真っ白になった。逃げだそうにも足が竦んで逃げ出すことができなかった。
苗の胸中などいざ知らず、一之介は気さくに話しかけてくる。
「お嬢さんは、三条家に仕えておられるのですの?」
「は、はい……」
「そうですか。私は三条家に婿入りする香坂一之助と申します。本日は三条家の皆様に挨拶にうかがったのですが、早く着いてしまったので月霞村を見て回っていたのですよ。恥ずかしながらゆくは村長を任される身だというのに、村のことを何も知らないもので」
そこで言葉を区切ると、一之助は苗の顔をまじまじと見つめた。
「お嬢さんは、何というお名前ですか?」
苗は質問に答えることなく、一之助に背を向けて逃げ出した。失礼な態度だとは知りながらも、そうせずにはおられなかった。全身に震えが広がり、背中には冷や汗が流れている。
最悪の未来が足音を立てて近づいてきているような気がした。
案の定、というべきだろうか。
その日の夜、苗は霧江に呼び出された。朝には上機嫌だったはずの霧江は、苗の顔を見るや否や「この売女」「薄汚い女狐め」と罵詈雑言を浴びせかけてきた。
話を聞くに、一之助は霧江の前で苗の話を持ち出したようだった。「美しい女中とぶつかった」と話し、苗の名前を聞き出そうとする素振りを見せたのだという。そのことが霧江の神経をとことん逆なでたのだ。
「一之助様に顔を見せるなと言ったのに、この糞女! 女中の分際で私から一之助様を奪うつもりなのね!」
霧江は目を血走らせ、口から唾を飛ばして叫ぶ。
無駄なことだとはわかりながらも、苗は必死に言い募った。
「いえ、決してそんなことは考えていません! 一之助様にお会いすることがないよう、山に薪を拾いに行こうと思ったんです。そうしたら裏門を出たところで偶然、一之助にお会いして……お話もまともにしていないし……」
「まともに話していないなら、なぜ一之助様があんなに気にするのよ! あんたが気を持たせるようなことを言ったんでしょう!」
「私は本当に何も……」
言い合う2人のあいだに白い煙が舞い込んだ。いつの間にやってきたのだろう。座敷の入口には光子が立っていて、優雅な仕草で煙管をくゆらせていた。
「霧江……騙されちゃいけないよ。その女の母親も質の悪い女狐だった。男のことなど何も知らない純朴な顔をしておいて、言葉巧みに私の夫を誑かしたんだ。あの女の血を継いでいるんだから、しょせんそいつも男の股を開くしか能のないあばずれなのさ」
ふぅ、と煙管の煙が顔にかけられた。
苗は言い返せないことが悔しくて仕方なかった。紫は源嗣を誑かしてなどいない。源嗣が、主従関係を盾にして紫に迫ったのだ。
源嗣は女好きで有名な村長だ。誰に責任があるのかを村中の誰もが知っている。三条家の女中も、光子も、霧江でさえも。それでも紫が悪者のように扱われるのは、村長の一族である三条家に逆らうことができないからだ。三条家が黒と言えば、白いものも黒だと見なされる。月霞村はそういう村だ。
光子の登場によりいくらか理性を取り戻した様子の霧江が、荒い息を吐きながら尋ねた。
「お母様……あの女がお父様を誑かしたあと、お母様はどうしたの?」
「躾けたさ。二度と同じ過ちを犯す気にならないように。何日もかけてじっくりと」
ふ、と煙を吐き出した光子は、霧江に煙管を手渡した。霧江は意味がわからないという表情を浮かべていたが、やがて光子の意図を理解したようだった。
「……そうね、反抗的な家畜はしっかり躾けておかないと。また手を噛まれちゃ堪らないわ」
霧江は煙管を手に苗の方へと近づいてくる。
苗の顔からはさっと血の気が引いた。霧江がこれからしようとしていることを悟ってしまったからだ。
「いや……」
苗は首を振って後ずさるが、逃げることなどできるはずもない。霧江がキセルの吸い口に口をつけると、火皿からはゆらりと細い煙が立ち昇るのだった。
◇
「うう……」
苗は重たい足を引きずりながら村の小道を歩いていた。一歩あゆみを進めるたびに、左腕と右足の太ももが指すように痛む。着物に隠れて見ることは叶わないが、その場所にはいくつもの火傷跡があった。霧江に、火のついた煙草の葉を落とされたからだ。恐ろしいことにもその場所は、死に戻る以前、火箸を押しつけられた場所と同じだった。
(どうして何もかもうまくいかないの……まるで未来を変えさせまいと見えない力が働いているみたいに)
努力の甲斐もなく、苗は『市之助との出会い』という引いてはならない破滅への引き金を引いてしまった。まるで切り立った崖の上に立たされているような気持ちだ。後戻りをすることはできず、残された道は底の見えない崖の下へと落ちていくだけ。
道を通りすがった老婆に、藁にもすがる思いで助けを求めた。
「お願い……私たちを助けて……このままでは殺されてしまう……」
老婆は足を止め、面倒な物を見るような目で苗を見た。
「あんた、村長さんとこの女中だろ。あんたを助けると光子さんの恨みを買うんだから、話しかけないでくれ」
冷たく言い放ったあと、老婆は苗の肩を突き飛ばした。強い力ではなかったが、苗はよろめいて地面に座り込んでしまった。道行く村人たちが苗のことを見ている。誰も手を差し伸べてはくれない。
苗は悲しくなった。この村の人々はずっとそうだった。三条家の奥方である光子の恨みを買いたくがないために、苗と紫を蔑ろにした。苗は何度も助けを求めたが、誰一人として応えてはくれなかった。村の薬師に「咳を止めるための薬を処方してほしい」と頼んだときも、金貸しに「必ず返すから、村から出るための金を貸してほしい」と頼んだときも、返ってきた答えはいつだって否だ。
「誰か助けて……お願いだから……」
泣きながら訴えても応えてくれる者はいない。目を合わせることもせず傍らを通り過ぎていく。
絶望の最中、苗はたった一人このつらい現実を忘れさせてくれる人の名を呼んだ。
「篝……」
◇
苗が常世山の洞穴に入ると、すぐに篝の嬉しそうな声が飛んできた。
「苗、久しぶりだな」
「うん……久しぶり。しばらく来られなくてごめんね」
「忙しかったのか?」
「そう、色々と忙しくて……だから今日は食べ物を何も持ってないの、ごめんね」
「構わない。気がまぎれるだけで、どうせ腹は膨れないから」
そういう篝の顔は、心なしか以前よりも血色が良くなったように見えた。痩せて骸骨のようだった身体にも男らしい肉付きが戻りつつある。何か特別なことが起こったのだろうかと疑問を感じながらも、苗はあえて何も訊かなかった。篝の変化を気にかけるだけの余裕が、今の苗にはなかった。
「……何かつらいことがあったのか?」
唐突に、篝が尋ねてきた。見透かすような美しい瞳に覗きこまれて、苗は慌てて笑顔を作った。洞穴が薄暗くてよかった。もしもここが明るい太陽の下だったなら、涙で腫れあがった目元を隠すことができないから。
「別に何も、いつもどおりよ」
「そうか? 俺の気のせいかもしれないが、泣いているように見える」
泣いているよ、と苗は心の中で言った。
(つらくて苦しくて仕方ないの。でもどうすればいいかわからないの)
のどの奥にせりあがる熱の塊を何度も飲み込んで、苗は気丈に笑った。
「本当に大丈夫。仕事が忙しくて少し疲れているだけだから」
「そうか……」
篝はそれ以上、食い下がるようなことはしなかった。鎖に繋がれた身体をもどかしそうに揺らすだけ。
その後は篝と二人、他愛のない話をした。この洞穴で過ごす時間は苗につらい現実を忘れさせてくれる。きっと篝もそうなのだろう。できそこないの鬼と、死に戻りの少女。救いようのない境遇に置かれているからこそ、互いの存在がなくてはならないものになった。
(でも私が死んだら、篝はまた一人ぼっちになってしまうのね……)
苗は申し訳ない気持ちになった。でも同時に、自分の死を悲しんでくれる人がいることが嬉しかった。
苗が死んだら篝は泣いてくれるだろうか。もしもいつか彼の罪が許されて、洞穴の外に出られる日がきたら、朽ち果てた苗の墓前に一束の花を手向けてくれるだろうか。
そう思えば少しだけ救われる気がした。
満月の夜から三週間が過ぎ、噂が少しずつ落ち着きを見せ始めた頃。
その日、三条家の人々は朝から大忙しだった。霧江の婚約者である香坂市之助が、結婚前の挨拶と称して三条家を訪れるからだ。女中たちは掃除に茶菓子の準備にと忙しなく働き、源嗣と光子も身支度に忙しい。
霧江に至っては、早朝から自室にこもり派手な着物を畳いっぱいに広げていた。襖の間からは「市之助様はどの着物がお好きかしら」と浮かれた声が漏れ出してくる。
そんなお祭り騒ぎの真っただ中にいても、苗はこれっぽっちも楽しい気分になれなかった。理由は色々とある。紫の容体が良くないこと、満月の夜の出来事がたびたび夢に出ること。そして一番の理由は――市之助が苗にとって不吉な存在だということ。
今日からおよそ半月後、苗はお使い先の商店で市之助と会う。大きな味噌樽を抱えた苗を不憫に思い、市之助が馬車で屋敷まで送ってくれるのだが、そのことが霧江の耳に入り殴られる蹴られるの散々な目に合うのだ。
市之助を奪われると極端な妄想を働かせた霧江は、苗を始末するべく紫の薬に毒を盛る。毒を飲んだ紫は死に、濡れ衣を着せられた苗は罪人として首切様に首を落とされる。市之助との出会いが、苗と紫に最悪の最期をもたらすということだ。だから苗は市之助の存在が恐ろしい。
「ちょっと、そこの役立たず」
苗が玄関先の掃き掃除をしていると、霧江が話しかけてきた。歌舞伎役者さながらの濃い化粧に、目がチカチカするような花車の着物。背後に2人の女中を従えた霧江は、ここ数か月の間で一番の上機嫌だ。
「……何でしょう」
「わかってると思うけど、市之助様の前に顔を出すんじゃないわよ。こんな不細工で薄汚い女中を雇っていると知れたら三条家の恥だもの」
「わかりました」
わざわざ言われなくても市之助と顔を合わせる気などなかったので、苗は素直にうなずいた。霧江もそれ以上、苗に構うつもりはないようで、鼻歌を歌いながら門の方へと歩いて行く。「市之助様はまだいらっしゃらないのかしら」と浮かれに浮かれて気味が悪いくらいだ。
(市之助様が滞在している間、どうやって時間を潰そうかしら……。前回は仕事を頼まれることがあるかもしれないと思って座敷に控えていたけれど、最後まで呼ばれることはなかったし……)
苗は少し考え、ぽんと手を打った。
「そうだ、篝のところへ行っていよう。そうすれば絶対に市之助様と顔を合わせることはないわ」
玄関の掃き掃除を終えた苗は、女中の1人に「山で薪を拾ってきます」と断りを入れて屋敷を出た。人気のない裏庭を抜け、裏門の閂を開ける。
満月の夜以降、気分が沈んで常世山から足が遠のいてしまっていた。だから久しぶりに篝と会えることが嬉しかった。
「今日は何を採っていってあげようかしら。そろそろヤマモモが実る頃だから――きゃっ」
裏門から飛び出した苗は、道を通りすがった人と勢いよくぶつかった。踏みとどまろうとしたものの、足元が乱れ尻もちをついてしまう。
「申し訳ありません! お嬢さん、お怪我はありませんか?」
尻をさする苗の目の前に、すっと手のひらが差し出された。大きくて節くれだった男の手だ。苗は戸惑ったが、手を借りないことも失礼な気がしたので、遠慮がちに差し出された手のひらを握り返した。
「こちらこそすみませんでした。急いでいて、よく前を見ていなかったから……」
「そのようですね。一瞬、門から猪が飛び出してきたのかと思いました」
猪のような勢いだったと言いたいのだろうか。苗は頬に熱がのぼるのを感じながら、男性の顔を見上げた。
「っ……」
その男性の顔を直視した瞬間、苗は言葉を失って立ち尽くした。
男性は艶のある黒髪を襟足のあたりで一つに束ね、着物の上に紋付きの羽織をはおっていた。長身もさることながら、背すじを伸ばして凛と立つ姿は美しい。苗の目から見ても美丈夫だとわかるその人物の名前は香坂一之介――苗が絶対に会いたくなかった霧江の婚約者だ。
「あ、あ……」
予想外の出会いに、苗は頭の中が真っ白になった。逃げだそうにも足が竦んで逃げ出すことができなかった。
苗の胸中などいざ知らず、一之介は気さくに話しかけてくる。
「お嬢さんは、三条家に仕えておられるのですの?」
「は、はい……」
「そうですか。私は三条家に婿入りする香坂一之助と申します。本日は三条家の皆様に挨拶にうかがったのですが、早く着いてしまったので月霞村を見て回っていたのですよ。恥ずかしながらゆくは村長を任される身だというのに、村のことを何も知らないもので」
そこで言葉を区切ると、一之助は苗の顔をまじまじと見つめた。
「お嬢さんは、何というお名前ですか?」
苗は質問に答えることなく、一之助に背を向けて逃げ出した。失礼な態度だとは知りながらも、そうせずにはおられなかった。全身に震えが広がり、背中には冷や汗が流れている。
最悪の未来が足音を立てて近づいてきているような気がした。
案の定、というべきだろうか。
その日の夜、苗は霧江に呼び出された。朝には上機嫌だったはずの霧江は、苗の顔を見るや否や「この売女」「薄汚い女狐め」と罵詈雑言を浴びせかけてきた。
話を聞くに、一之助は霧江の前で苗の話を持ち出したようだった。「美しい女中とぶつかった」と話し、苗の名前を聞き出そうとする素振りを見せたのだという。そのことが霧江の神経をとことん逆なでたのだ。
「一之助様に顔を見せるなと言ったのに、この糞女! 女中の分際で私から一之助様を奪うつもりなのね!」
霧江は目を血走らせ、口から唾を飛ばして叫ぶ。
無駄なことだとはわかりながらも、苗は必死に言い募った。
「いえ、決してそんなことは考えていません! 一之助様にお会いすることがないよう、山に薪を拾いに行こうと思ったんです。そうしたら裏門を出たところで偶然、一之助にお会いして……お話もまともにしていないし……」
「まともに話していないなら、なぜ一之助様があんなに気にするのよ! あんたが気を持たせるようなことを言ったんでしょう!」
「私は本当に何も……」
言い合う2人のあいだに白い煙が舞い込んだ。いつの間にやってきたのだろう。座敷の入口には光子が立っていて、優雅な仕草で煙管をくゆらせていた。
「霧江……騙されちゃいけないよ。その女の母親も質の悪い女狐だった。男のことなど何も知らない純朴な顔をしておいて、言葉巧みに私の夫を誑かしたんだ。あの女の血を継いでいるんだから、しょせんそいつも男の股を開くしか能のないあばずれなのさ」
ふぅ、と煙管の煙が顔にかけられた。
苗は言い返せないことが悔しくて仕方なかった。紫は源嗣を誑かしてなどいない。源嗣が、主従関係を盾にして紫に迫ったのだ。
源嗣は女好きで有名な村長だ。誰に責任があるのかを村中の誰もが知っている。三条家の女中も、光子も、霧江でさえも。それでも紫が悪者のように扱われるのは、村長の一族である三条家に逆らうことができないからだ。三条家が黒と言えば、白いものも黒だと見なされる。月霞村はそういう村だ。
光子の登場によりいくらか理性を取り戻した様子の霧江が、荒い息を吐きながら尋ねた。
「お母様……あの女がお父様を誑かしたあと、お母様はどうしたの?」
「躾けたさ。二度と同じ過ちを犯す気にならないように。何日もかけてじっくりと」
ふ、と煙を吐き出した光子は、霧江に煙管を手渡した。霧江は意味がわからないという表情を浮かべていたが、やがて光子の意図を理解したようだった。
「……そうね、反抗的な家畜はしっかり躾けておかないと。また手を噛まれちゃ堪らないわ」
霧江は煙管を手に苗の方へと近づいてくる。
苗の顔からはさっと血の気が引いた。霧江がこれからしようとしていることを悟ってしまったからだ。
「いや……」
苗は首を振って後ずさるが、逃げることなどできるはずもない。霧江がキセルの吸い口に口をつけると、火皿からはゆらりと細い煙が立ち昇るのだった。
◇
「うう……」
苗は重たい足を引きずりながら村の小道を歩いていた。一歩あゆみを進めるたびに、左腕と右足の太ももが指すように痛む。着物に隠れて見ることは叶わないが、その場所にはいくつもの火傷跡があった。霧江に、火のついた煙草の葉を落とされたからだ。恐ろしいことにもその場所は、死に戻る以前、火箸を押しつけられた場所と同じだった。
(どうして何もかもうまくいかないの……まるで未来を変えさせまいと見えない力が働いているみたいに)
努力の甲斐もなく、苗は『市之助との出会い』という引いてはならない破滅への引き金を引いてしまった。まるで切り立った崖の上に立たされているような気持ちだ。後戻りをすることはできず、残された道は底の見えない崖の下へと落ちていくだけ。
道を通りすがった老婆に、藁にもすがる思いで助けを求めた。
「お願い……私たちを助けて……このままでは殺されてしまう……」
老婆は足を止め、面倒な物を見るような目で苗を見た。
「あんた、村長さんとこの女中だろ。あんたを助けると光子さんの恨みを買うんだから、話しかけないでくれ」
冷たく言い放ったあと、老婆は苗の肩を突き飛ばした。強い力ではなかったが、苗はよろめいて地面に座り込んでしまった。道行く村人たちが苗のことを見ている。誰も手を差し伸べてはくれない。
苗は悲しくなった。この村の人々はずっとそうだった。三条家の奥方である光子の恨みを買いたくがないために、苗と紫を蔑ろにした。苗は何度も助けを求めたが、誰一人として応えてはくれなかった。村の薬師に「咳を止めるための薬を処方してほしい」と頼んだときも、金貸しに「必ず返すから、村から出るための金を貸してほしい」と頼んだときも、返ってきた答えはいつだって否だ。
「誰か助けて……お願いだから……」
泣きながら訴えても応えてくれる者はいない。目を合わせることもせず傍らを通り過ぎていく。
絶望の最中、苗はたった一人このつらい現実を忘れさせてくれる人の名を呼んだ。
「篝……」
◇
苗が常世山の洞穴に入ると、すぐに篝の嬉しそうな声が飛んできた。
「苗、久しぶりだな」
「うん……久しぶり。しばらく来られなくてごめんね」
「忙しかったのか?」
「そう、色々と忙しくて……だから今日は食べ物を何も持ってないの、ごめんね」
「構わない。気がまぎれるだけで、どうせ腹は膨れないから」
そういう篝の顔は、心なしか以前よりも血色が良くなったように見えた。痩せて骸骨のようだった身体にも男らしい肉付きが戻りつつある。何か特別なことが起こったのだろうかと疑問を感じながらも、苗はあえて何も訊かなかった。篝の変化を気にかけるだけの余裕が、今の苗にはなかった。
「……何かつらいことがあったのか?」
唐突に、篝が尋ねてきた。見透かすような美しい瞳に覗きこまれて、苗は慌てて笑顔を作った。洞穴が薄暗くてよかった。もしもここが明るい太陽の下だったなら、涙で腫れあがった目元を隠すことができないから。
「別に何も、いつもどおりよ」
「そうか? 俺の気のせいかもしれないが、泣いているように見える」
泣いているよ、と苗は心の中で言った。
(つらくて苦しくて仕方ないの。でもどうすればいいかわからないの)
のどの奥にせりあがる熱の塊を何度も飲み込んで、苗は気丈に笑った。
「本当に大丈夫。仕事が忙しくて少し疲れているだけだから」
「そうか……」
篝はそれ以上、食い下がるようなことはしなかった。鎖に繋がれた身体をもどかしそうに揺らすだけ。
その後は篝と二人、他愛のない話をした。この洞穴で過ごす時間は苗につらい現実を忘れさせてくれる。きっと篝もそうなのだろう。できそこないの鬼と、死に戻りの少女。救いようのない境遇に置かれているからこそ、互いの存在がなくてはならないものになった。
(でも私が死んだら、篝はまた一人ぼっちになってしまうのね……)
苗は申し訳ない気持ちになった。でも同時に、自分の死を悲しんでくれる人がいることが嬉しかった。
苗が死んだら篝は泣いてくれるだろうか。もしもいつか彼の罪が許されて、洞穴の外に出られる日がきたら、朽ち果てた苗の墓前に一束の花を手向けてくれるだろうか。
そう思えば少しだけ救われる気がした。