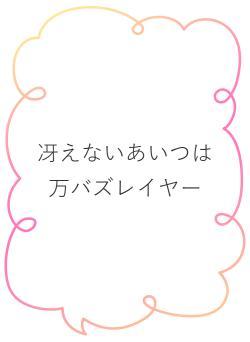篝との出会いから2週間が経とうとしていた。
苗は、仕事の合間を縫っては篝のもとを訪れた。元より苗は面倒な薪拾いを任されることが多かったし、薬草を集めるためにたびたび山へと入っていた。仕事の場所を幽世山へと変えればいいのだから、篝に会いに行くのは難しいことではなかった。
「黄泉の国には、たくさんの鬼が住んでいるの?」
熟れたいちじくの実を小包丁で半分に割りながら、苗は尋ねた。そのいちじくの実は、篝の土産にするために森の中で採ってきた物だ。
「ああ、たくさんいるな。人間の世界ほどではないと思うが」
「どんな暮らしをしているの?」
「人間とそんなに変わらない。服を着て、家に住み、夜は布団に入って眠る」
「ふぅん……食事も人間と変わらない物を食べるの?」
「基本的に変わらないとは思うが……鬼は食事をとらなくても死にはしない。楽しみのために食べている、というのが正しいかもしれない」
苗はまた「ふぅん」と相槌を打った。
篝の話は、よくできたおとぎ話に耳を傾けるようで楽しかった。黄泉の国が本当にあるのかどうかを確かめる術はない。篝が本当に鬼なのかどうかすら定かではない。しかし、この洞穴で過ごす時間は苗につらい現実を忘れさせてくれた。
夏瑠璃の実を持って帰ったことで、火箸を押しつけられるという最悪の折檻は免れたが、苗の生活は死に戻る前と何も変わっていなかった。働けど働けど役立たずと罵られ、理不尽な折檻に怯える日々。気持ちばかりの果実を食べさせたところで、紫の病が良くなることもない。
紫を死なせないためには、何かを変えなければならないということはわかっている。でも何を変えればいいのか、どうやって変えればいいのか、苗にはさっぱりわかなかった。
「……とても甘い匂いがするな。その木の実は食べられるのか?」
篝が、苗の持ついちじくの実を指さして言った。両腕を拘束している鎖が、こすれあって鈍い音を立てる。
「食べられるわ。黄泉の国にいちじくの実は生っていないの?」
「生っているのかもしれないが、俺は食べたことがない。そもそも食事をあまりしなかったから」
「さっき鬼は食事をしなくても死なないと言ったけれど、生きるのに必要な栄養はどこからとっているの?」
さして深い意味もなくした質問だったが、篝は言い淀んで苗の表情をうかがった。
「……鬼は人間の魂を糧にして生きている。数年に一度、あるいは数十年に一度、人間の世界にやってきて好みの人間の魂を喰うんだ」
「……人間を殺すということ?」
「そうだ」
苗は返す言葉を探して黙り込んだ。心臓の鼓動が高まりはしたが、激しい動揺を覚えることはなかった。
人間の世界には鬼に関する伝承が溢れている。そして大半の伝承の中では、鬼は人間を殺す悪しき存在として扱われている。
苗も初めて篝が鬼だと知ったときは、まずそうした印象を抱いたものだ。だから今さら鬼は人間を殺すと言われたところで、さほど驚きはしなかった。
「……俺を軽蔑するか?」
篝はやはり苗の反応をうかがうように尋ねた。上目遣いで苗を見る表情は、まるで飼い主の機嫌をうかがう子犬のよう。彼が鬼だということを思わず忘れてしまいそうだ。
苗は微笑ましさを感じながら優しく答えた。
「少し恐ろしいとは思うけど、軽蔑はしないわ。だって生きるために人間を殺すのでしょう? 人間だって鳥や豚を殺して食べるのだから、同じことだと思うわ」
「そうか……」
篝が見るからにほっとした様子だった。
(篝はずっと寂しかったのかしら)
篝は黄泉の国で罪を犯し、もう何百年もこの場所に幽閉されているのだと言った。話相手もおらず、一人ぼっちで気の遠くなるような時間を過ごしてきた。
だから篝は苗にすがろうとするのだろう。苗がつらい現実を忘れたいがために、篝にすがろうとするのと同じように。
(私と篝は似ている。つらい現実から逃げ出したくて、でもどうすることもできず無意味に足掻いている。私と篝、二人ともが幸せになる方法があればいいのに……)
考えてみたところで名案が思いつくはずもなく、苗は気持ちを切り替えていちじくの皮むきを再開した。綺麗に皮をむいた実は一口大に切り、篝の口先へと持っていく。
「どうぞ。甘くて美味しいのよ」
苗が指先でつまんだいちじくの実を、篝は疑い深く見つめていた。本当は自分で食べてもらえれば手間はないのだが、篝は両腕を鎖で繋がれているため、苗が手ずから食べさせるしか方法がないのだ。
やがて篝はおそるおそるいちじくの実にかじりついた。
「……甘いな。それに不思議な食感だ」
苗はそうでしょう、と言って笑った。
◇
三条家の屋敷へと戻ってきた苗は、背負っていた薪を台所の隅に下ろし、紫のいる小屋へと向かった。日当たりの悪い小屋の中では、紫が痩せた背中を丸めて繕い物をしているところだった。
「お母様! 体調が悪いんだから寝ていないと……」
苗が慌てて裁縫道具を取り上げようとすると、紫はやんわりと制止した。
「このくらいの仕事はやらせてちょうだい。三条家の皆様のご厚意で屋敷に置いていただいているのだから、寝てばかりいては申し訳ないわ……」
「お母様……」
2週間前に吐血をしてからというもの、紫の症状は目に見えて悪くなった。日に数度は呼吸がままならなくなるくらいの激しい咳をして、咳と一緒に少量の血を吐くこともある。食事もほとんどとれず、ただでさえ痩せていた身体は、今では触れれば簡単に崩れてしまいそうだ。
これだけ症状が悪化しても、光子は医者を呼ぶことを許してくれなかった。病人食を与えることも、薬師に薬を調合してもらうことも許されない。
(なぜこんな仕打ちを受けなければならないの……屋敷に置いていただいているとお母様は言うけれど、私たちはただ閉じ込められているだけだわ)
苗は悔しさに涙が零れそうになった。
主の子を身籠ってしまった女中は、本来ならばいくらかの金を積まれてすぐさま解雇される。しかし紫がそうならなかったのは、光子が紫を止め置くことを望んだからだ。
若かりし頃の紫は天女とみまがうほど清楚で美しかった。たとえ瘤つきだとしても、妻として迎えたいと思う男性は少なくなかったはず。光子は、紫が幸せになることが許せなかった。夫を惑わせた憎き女と、その女の子どもを手元に置き、心行くまでいたぶることを選んだ。
だから紫と苗はこの屋敷から逃げることができない。怪我も病気も治してもらうことができず、奴隷のようにこきつかわれている。そして最後には毒を盛られ、汚名を着せられて死んでいく。救いようのない人生だ。
(お母様の運命を変えるためには、いったい何をすればいいの? どうすれば殺されるはずの命を助けることができるの? そもそも――時間が巻き戻されたところで、人の運命とはそう簡単に変えられるものなのかしら?)
必死に考える苗は、小屋に風をとりいれるための小さな窓を見上げた。青空の真ん中には白く霞んだ月が浮いていた。
「あ……」
苗は気がついた。今夜は満月だ。
◇
太陽は山陰に姿を隠し、月霞村は夜に包まれた。
午後の仕事を済ませ、遅めの夕食をかきこんだ苗は、人目を忍んで屋敷から抜け出した。本当はもっと早い時間に行動を起こしたかったのだが、あれこれと雑用を言いつけられてすっかり遅くなってしまった。
苗が向かった先は、首切様の住処であると言われている幽世山だ。今夜は満月。月に一度、首切様が現れる日。
一度は殺された身で満月の夜に幽世山を訪れることは恐ろしいが、苗にはどうしても今夜、幽世山を訪れなければならない理由があった。
首切様の古くから言い伝えられてはいる存在ではあるが、信じる者はほとんどいない。首切様の姿を見たという話も聞いたことがない。しかし今夜、月霞村の住人の常識をくつがえす出来事が起こる。ある村の男が酒に酔って人を殴り、自警団の拘束を免れるために幽世山へと足を踏み入れるのだ。
明朝、男は首のない死体となって発見され、村人たちはにわかに首切様の存在を意識し始めることになる。『首切様はただの伝承ではなく、幽世山に実在する神なのではないか』――と。
苗はその出来事が起こることを知っているからこそ、今夜、幽世山に行こうと思った。もしも苗の力でその男を助けることができれば、それ即ち人の運命は変えられるということだから。紫と苗の運命も変えられるということだから。
(確か……男性の死体は幽世山のふもとで見つかったはずだわ。首切様を祀るための磐座があって、そのすぐ近くで……)
月明かりを頼りに山の中をさまよっていた苗は、間もなく磐座と思われる巨岩を見つけた。磐座とは、神が宿るといわれている神聖な岩のこと。幽世山に社や神社はないが、磐座を神体に見立てて何百年ものあいだ首切様を祀ってきた。
苗の背丈の3倍はあろうかという磐座には、無精ひげを生やした男が力なく座り込んでいた。
「……何だ、お前は?」
苗が男に話かけるよりも早く、男が苗に気がついた。夜風にのって酒の匂いが漂ってくる。どうやら酒に酔って暴力事件を起こした件の男で間違いないようだ。
苗は勇気を出して口を開いた。
「わ、私は……三条家に仕えている女中で……」
「村長んとこの女中が、こんな夜中に何してんだ」
「仕事で失敗をして屋敷から追い出されてしまったの……それで、一晩を超す場所を探しているうちにこんなところに……」
「ああ……お前、村長が女中に産ませた例の娘か。そりゃ屋敷から叩き出されても文句は言えねぇわな」
男は苗を小馬鹿にするように笑った。
人口が1200人ほどの小さな村では、村人の大半が顔見知りだ。そんな村だからこそ、三条源嗣がかつて引き起こした浮気騒動は、子どもを除く村人全員が知っている。
見下されることに悔しさを覚えながらも、苗は男をこの場所から離れさせるべく、作戦通りの言葉を口にした。
「さっき、少し離れたことろで熊に追いかけられたの。とても大きな熊だったわ」
男は急に表情を硬くした。
「それは……本当か?」
「本当よ。お腹を空かせているみたいだったから、ここにいたら貴方も危ない。すぐに山から出た方がいいわ」
「……」
男は考え込んだが、すぐに諦めように舌打ちをした。
「背に腹は代えられねぇ。熊に食い殺されるくらいなら、自警団に示談金を払う方がましか」
ふらふらと立ち上がった男性は、苗に礼を言うこともなくその場を立ち去った。
苗は作戦が成功したことに安堵しながらも、もう少しだけ磐座のそばにいることにした。道に迷ったなどの理由で、男性が引き返してくることがあっては困ると思ったから。
磐座から20歩ばかり離れたところにある木の幹に背中を預け、茂みに身を隠すようにして座りこむ。
(もし明日の朝になっても彼の死体が発見されなかったら、人の運命は変えられるということだわ。うまくいってくれるといいのだけれど……)
苗は祈るように目を閉じた。そしてそのまま、自分でも気がつかないうちに寝入ってしまった。
◇
目が覚めたとき、苗は自分がどこにいるのかわからなかった。目に映るものは鬱蒼と茂る木々、耳に聞こえるものは不規則な虫たちの鳴き声、湿気を帯びた夜風が頬を撫でていく。
(そうだ。私、殺されるはずの男性を助けようと思って……)
苗は眠気眼をこすって磐座の方を見た。そして驚愕した。満月に照らされた磐座の根元には、先ほどと同じように無精ひげの男が座り込んでいるのだから。
「なぜ、どうして彼がまたあそこにいるの」
つぶやく声は虫たちの鳴き声に搔き消された。
苗の存在に気がついていない様子の男は、うつむいてぶつぶつと独り言を零している。「熊がなんだってんだ」「俺は悪くねぇのに示談金なんて払ってたまるか」一度は村に帰ろうとしたものの、考え直して幽世山へと戻ってきてしまったようだ。
(駄目、ここにいてはいけない)
苗は立ち上がり声をあげようとした。でもできなかった。森の中に、草木を掻きわけて歩く不気味な人影を見たからだ。
絶え間なく響いていた虫たちの鳴き声が止んだ。まるでこの場所だけ時間が止まってしまったみたいに。苗はもうただ目を見開いて、ことの成り行きを見守ることしかできなかった。
茂みの中から歩み出たその人影は、満月のもとですらりと刀を抜いた。抜き身の刀が月光を浴びて輝く様は美しい。美しく、そして邪悪だ。
男はようやく近づいてくる人影に気がついた。悲鳴をあげて飛び上がり、慌てて逃げだそうとするものの、足がもつれて転んでしまう。
その頭上に刀が振り上げられた。
「あ――」
苗は咄嗟に目をつぶった。声にならない男の悲鳴と、肉と骨を断つ生々しい音が夜の空気を震わせた。
おそるおそる目を開けたとき、そこにもう刀を持つ人影はなく、首をなくして事切れた男の死体が転がっていた。
胸の奥にせりあがるものを感じ、苗は地面に手をついて吐いた。何度吐いても治まることのない嘔吐感、涙がこみあげてくる。死の瞬間に立ち会ってしまった恐怖心、助けられなかったことはの申し訳なさ、そして――絶望感。
苗が行動を起こしたにも関わらず、男は死んでしまった。死に戻る前と同じように、磐座の前で首切様に首を落とされて。
人間の運命はそう簡単には変わらない。
だとすれば苗と紫に訪れる未来は――
苗は、仕事の合間を縫っては篝のもとを訪れた。元より苗は面倒な薪拾いを任されることが多かったし、薬草を集めるためにたびたび山へと入っていた。仕事の場所を幽世山へと変えればいいのだから、篝に会いに行くのは難しいことではなかった。
「黄泉の国には、たくさんの鬼が住んでいるの?」
熟れたいちじくの実を小包丁で半分に割りながら、苗は尋ねた。そのいちじくの実は、篝の土産にするために森の中で採ってきた物だ。
「ああ、たくさんいるな。人間の世界ほどではないと思うが」
「どんな暮らしをしているの?」
「人間とそんなに変わらない。服を着て、家に住み、夜は布団に入って眠る」
「ふぅん……食事も人間と変わらない物を食べるの?」
「基本的に変わらないとは思うが……鬼は食事をとらなくても死にはしない。楽しみのために食べている、というのが正しいかもしれない」
苗はまた「ふぅん」と相槌を打った。
篝の話は、よくできたおとぎ話に耳を傾けるようで楽しかった。黄泉の国が本当にあるのかどうかを確かめる術はない。篝が本当に鬼なのかどうかすら定かではない。しかし、この洞穴で過ごす時間は苗につらい現実を忘れさせてくれた。
夏瑠璃の実を持って帰ったことで、火箸を押しつけられるという最悪の折檻は免れたが、苗の生活は死に戻る前と何も変わっていなかった。働けど働けど役立たずと罵られ、理不尽な折檻に怯える日々。気持ちばかりの果実を食べさせたところで、紫の病が良くなることもない。
紫を死なせないためには、何かを変えなければならないということはわかっている。でも何を変えればいいのか、どうやって変えればいいのか、苗にはさっぱりわかなかった。
「……とても甘い匂いがするな。その木の実は食べられるのか?」
篝が、苗の持ついちじくの実を指さして言った。両腕を拘束している鎖が、こすれあって鈍い音を立てる。
「食べられるわ。黄泉の国にいちじくの実は生っていないの?」
「生っているのかもしれないが、俺は食べたことがない。そもそも食事をあまりしなかったから」
「さっき鬼は食事をしなくても死なないと言ったけれど、生きるのに必要な栄養はどこからとっているの?」
さして深い意味もなくした質問だったが、篝は言い淀んで苗の表情をうかがった。
「……鬼は人間の魂を糧にして生きている。数年に一度、あるいは数十年に一度、人間の世界にやってきて好みの人間の魂を喰うんだ」
「……人間を殺すということ?」
「そうだ」
苗は返す言葉を探して黙り込んだ。心臓の鼓動が高まりはしたが、激しい動揺を覚えることはなかった。
人間の世界には鬼に関する伝承が溢れている。そして大半の伝承の中では、鬼は人間を殺す悪しき存在として扱われている。
苗も初めて篝が鬼だと知ったときは、まずそうした印象を抱いたものだ。だから今さら鬼は人間を殺すと言われたところで、さほど驚きはしなかった。
「……俺を軽蔑するか?」
篝はやはり苗の反応をうかがうように尋ねた。上目遣いで苗を見る表情は、まるで飼い主の機嫌をうかがう子犬のよう。彼が鬼だということを思わず忘れてしまいそうだ。
苗は微笑ましさを感じながら優しく答えた。
「少し恐ろしいとは思うけど、軽蔑はしないわ。だって生きるために人間を殺すのでしょう? 人間だって鳥や豚を殺して食べるのだから、同じことだと思うわ」
「そうか……」
篝が見るからにほっとした様子だった。
(篝はずっと寂しかったのかしら)
篝は黄泉の国で罪を犯し、もう何百年もこの場所に幽閉されているのだと言った。話相手もおらず、一人ぼっちで気の遠くなるような時間を過ごしてきた。
だから篝は苗にすがろうとするのだろう。苗がつらい現実を忘れたいがために、篝にすがろうとするのと同じように。
(私と篝は似ている。つらい現実から逃げ出したくて、でもどうすることもできず無意味に足掻いている。私と篝、二人ともが幸せになる方法があればいいのに……)
考えてみたところで名案が思いつくはずもなく、苗は気持ちを切り替えていちじくの皮むきを再開した。綺麗に皮をむいた実は一口大に切り、篝の口先へと持っていく。
「どうぞ。甘くて美味しいのよ」
苗が指先でつまんだいちじくの実を、篝は疑い深く見つめていた。本当は自分で食べてもらえれば手間はないのだが、篝は両腕を鎖で繋がれているため、苗が手ずから食べさせるしか方法がないのだ。
やがて篝はおそるおそるいちじくの実にかじりついた。
「……甘いな。それに不思議な食感だ」
苗はそうでしょう、と言って笑った。
◇
三条家の屋敷へと戻ってきた苗は、背負っていた薪を台所の隅に下ろし、紫のいる小屋へと向かった。日当たりの悪い小屋の中では、紫が痩せた背中を丸めて繕い物をしているところだった。
「お母様! 体調が悪いんだから寝ていないと……」
苗が慌てて裁縫道具を取り上げようとすると、紫はやんわりと制止した。
「このくらいの仕事はやらせてちょうだい。三条家の皆様のご厚意で屋敷に置いていただいているのだから、寝てばかりいては申し訳ないわ……」
「お母様……」
2週間前に吐血をしてからというもの、紫の症状は目に見えて悪くなった。日に数度は呼吸がままならなくなるくらいの激しい咳をして、咳と一緒に少量の血を吐くこともある。食事もほとんどとれず、ただでさえ痩せていた身体は、今では触れれば簡単に崩れてしまいそうだ。
これだけ症状が悪化しても、光子は医者を呼ぶことを許してくれなかった。病人食を与えることも、薬師に薬を調合してもらうことも許されない。
(なぜこんな仕打ちを受けなければならないの……屋敷に置いていただいているとお母様は言うけれど、私たちはただ閉じ込められているだけだわ)
苗は悔しさに涙が零れそうになった。
主の子を身籠ってしまった女中は、本来ならばいくらかの金を積まれてすぐさま解雇される。しかし紫がそうならなかったのは、光子が紫を止め置くことを望んだからだ。
若かりし頃の紫は天女とみまがうほど清楚で美しかった。たとえ瘤つきだとしても、妻として迎えたいと思う男性は少なくなかったはず。光子は、紫が幸せになることが許せなかった。夫を惑わせた憎き女と、その女の子どもを手元に置き、心行くまでいたぶることを選んだ。
だから紫と苗はこの屋敷から逃げることができない。怪我も病気も治してもらうことができず、奴隷のようにこきつかわれている。そして最後には毒を盛られ、汚名を着せられて死んでいく。救いようのない人生だ。
(お母様の運命を変えるためには、いったい何をすればいいの? どうすれば殺されるはずの命を助けることができるの? そもそも――時間が巻き戻されたところで、人の運命とはそう簡単に変えられるものなのかしら?)
必死に考える苗は、小屋に風をとりいれるための小さな窓を見上げた。青空の真ん中には白く霞んだ月が浮いていた。
「あ……」
苗は気がついた。今夜は満月だ。
◇
太陽は山陰に姿を隠し、月霞村は夜に包まれた。
午後の仕事を済ませ、遅めの夕食をかきこんだ苗は、人目を忍んで屋敷から抜け出した。本当はもっと早い時間に行動を起こしたかったのだが、あれこれと雑用を言いつけられてすっかり遅くなってしまった。
苗が向かった先は、首切様の住処であると言われている幽世山だ。今夜は満月。月に一度、首切様が現れる日。
一度は殺された身で満月の夜に幽世山を訪れることは恐ろしいが、苗にはどうしても今夜、幽世山を訪れなければならない理由があった。
首切様の古くから言い伝えられてはいる存在ではあるが、信じる者はほとんどいない。首切様の姿を見たという話も聞いたことがない。しかし今夜、月霞村の住人の常識をくつがえす出来事が起こる。ある村の男が酒に酔って人を殴り、自警団の拘束を免れるために幽世山へと足を踏み入れるのだ。
明朝、男は首のない死体となって発見され、村人たちはにわかに首切様の存在を意識し始めることになる。『首切様はただの伝承ではなく、幽世山に実在する神なのではないか』――と。
苗はその出来事が起こることを知っているからこそ、今夜、幽世山に行こうと思った。もしも苗の力でその男を助けることができれば、それ即ち人の運命は変えられるということだから。紫と苗の運命も変えられるということだから。
(確か……男性の死体は幽世山のふもとで見つかったはずだわ。首切様を祀るための磐座があって、そのすぐ近くで……)
月明かりを頼りに山の中をさまよっていた苗は、間もなく磐座と思われる巨岩を見つけた。磐座とは、神が宿るといわれている神聖な岩のこと。幽世山に社や神社はないが、磐座を神体に見立てて何百年ものあいだ首切様を祀ってきた。
苗の背丈の3倍はあろうかという磐座には、無精ひげを生やした男が力なく座り込んでいた。
「……何だ、お前は?」
苗が男に話かけるよりも早く、男が苗に気がついた。夜風にのって酒の匂いが漂ってくる。どうやら酒に酔って暴力事件を起こした件の男で間違いないようだ。
苗は勇気を出して口を開いた。
「わ、私は……三条家に仕えている女中で……」
「村長んとこの女中が、こんな夜中に何してんだ」
「仕事で失敗をして屋敷から追い出されてしまったの……それで、一晩を超す場所を探しているうちにこんなところに……」
「ああ……お前、村長が女中に産ませた例の娘か。そりゃ屋敷から叩き出されても文句は言えねぇわな」
男は苗を小馬鹿にするように笑った。
人口が1200人ほどの小さな村では、村人の大半が顔見知りだ。そんな村だからこそ、三条源嗣がかつて引き起こした浮気騒動は、子どもを除く村人全員が知っている。
見下されることに悔しさを覚えながらも、苗は男をこの場所から離れさせるべく、作戦通りの言葉を口にした。
「さっき、少し離れたことろで熊に追いかけられたの。とても大きな熊だったわ」
男は急に表情を硬くした。
「それは……本当か?」
「本当よ。お腹を空かせているみたいだったから、ここにいたら貴方も危ない。すぐに山から出た方がいいわ」
「……」
男は考え込んだが、すぐに諦めように舌打ちをした。
「背に腹は代えられねぇ。熊に食い殺されるくらいなら、自警団に示談金を払う方がましか」
ふらふらと立ち上がった男性は、苗に礼を言うこともなくその場を立ち去った。
苗は作戦が成功したことに安堵しながらも、もう少しだけ磐座のそばにいることにした。道に迷ったなどの理由で、男性が引き返してくることがあっては困ると思ったから。
磐座から20歩ばかり離れたところにある木の幹に背中を預け、茂みに身を隠すようにして座りこむ。
(もし明日の朝になっても彼の死体が発見されなかったら、人の運命は変えられるということだわ。うまくいってくれるといいのだけれど……)
苗は祈るように目を閉じた。そしてそのまま、自分でも気がつかないうちに寝入ってしまった。
◇
目が覚めたとき、苗は自分がどこにいるのかわからなかった。目に映るものは鬱蒼と茂る木々、耳に聞こえるものは不規則な虫たちの鳴き声、湿気を帯びた夜風が頬を撫でていく。
(そうだ。私、殺されるはずの男性を助けようと思って……)
苗は眠気眼をこすって磐座の方を見た。そして驚愕した。満月に照らされた磐座の根元には、先ほどと同じように無精ひげの男が座り込んでいるのだから。
「なぜ、どうして彼がまたあそこにいるの」
つぶやく声は虫たちの鳴き声に搔き消された。
苗の存在に気がついていない様子の男は、うつむいてぶつぶつと独り言を零している。「熊がなんだってんだ」「俺は悪くねぇのに示談金なんて払ってたまるか」一度は村に帰ろうとしたものの、考え直して幽世山へと戻ってきてしまったようだ。
(駄目、ここにいてはいけない)
苗は立ち上がり声をあげようとした。でもできなかった。森の中に、草木を掻きわけて歩く不気味な人影を見たからだ。
絶え間なく響いていた虫たちの鳴き声が止んだ。まるでこの場所だけ時間が止まってしまったみたいに。苗はもうただ目を見開いて、ことの成り行きを見守ることしかできなかった。
茂みの中から歩み出たその人影は、満月のもとですらりと刀を抜いた。抜き身の刀が月光を浴びて輝く様は美しい。美しく、そして邪悪だ。
男はようやく近づいてくる人影に気がついた。悲鳴をあげて飛び上がり、慌てて逃げだそうとするものの、足がもつれて転んでしまう。
その頭上に刀が振り上げられた。
「あ――」
苗は咄嗟に目をつぶった。声にならない男の悲鳴と、肉と骨を断つ生々しい音が夜の空気を震わせた。
おそるおそる目を開けたとき、そこにもう刀を持つ人影はなく、首をなくして事切れた男の死体が転がっていた。
胸の奥にせりあがるものを感じ、苗は地面に手をついて吐いた。何度吐いても治まることのない嘔吐感、涙がこみあげてくる。死の瞬間に立ち会ってしまった恐怖心、助けられなかったことはの申し訳なさ、そして――絶望感。
苗が行動を起こしたにも関わらず、男は死んでしまった。死に戻る前と同じように、磐座の前で首切様に首を落とされて。
人間の運命はそう簡単には変わらない。
だとすれば苗と紫に訪れる未来は――