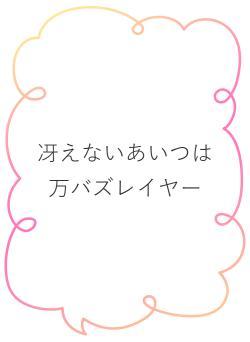紫のいる小屋を出た苗は、人気のない屋敷の廊下を悩ましげに唸りながら歩いていた。両手で抱えた盆の上では、ほとんど手がつけられていない食事がかちゃかちゃと音を立てて揺れる。
(お母様が吐血してから薬に毒を盛られるまで、2カ月以上は時間があったはずだわ。お母様を助けるためには、この2カ月の間に何をすればいいのかしら……)
苗は廊下を歩きながら考え続けた。
苗の腹違いの姉である霧江は、苗に母殺しの罪を着せるべく紫の薬に毒を入れた。それだけ苗のことを嫌っていたということだ。紫を助けるためには、苗と霧江の関係を改善するのがもっとも手っ取り早いのだが。
(霧江ねえ様との関係を改善……そんなことが本当にできるかしら。私のことを蛆虫のように嫌っている人なのに――あ)
廊下の向こうがわに派手な着物がちらついた。主張の強い真っ赤な牡丹に、金刺繍をほどこした桜色の帯。霧江だ。霧江は通りすがりざまに足を止めて、害虫を見るような目つきで苗のことをねめつけた。
「あら嫌だ、こんなところに蛆虫が湧いてるわ。お父様にお願いして早く退治してもらわないと」
こうして存在自体が害悪のように扱われることは日常茶飯事だったので、苗は何も言い返さずに黙っていた。霧江は面白くなさそうに鼻を鳴らす。
ひとつ年上の霧江は、幼少時からずっと苗のことを毛嫌いしていた。苗が不貞行為によって生まれた子だということはもちろんあるが、理由はそれだけではないと苗は感じていた。
霧江はお世辞にも美人だといえる容姿ではない。派手な着物と濃い化粧でごまかしてはいるが、彼女が容姿に劣等感を持っていることは誰の目から見ても明らかだ。対して苗は――苗自身は己の顔立ちを美とも醜とも捉えたことはないのだが――かつて源嗣を魅了した若かりし頃の紫に生き写しだと言われている。
だから霧江は苗が嫌いなのだ。不貞行為の末に生まれた娘が、自分よりも遥かに美しい容姿をしているから。苗を貶め、罵倒することで自尊心を満たそうとしている。
霧江は薄ら笑いながら唇を撫でた。それは霧江が苗をいたぶろうとするときの癖だ。
「そういえば、月の末に一之助様がいらっしゃる予定なのよね。一之助様にお見せするために、手染めの着物をあつらえようと思っていたのだけれど」
「……」
一之助は霧江の婚約者の名前だ。月霞村から馬車で一時間ほどのところにある港町で貿易業を営んでいる香坂家の三男。およそ半年後に三条家に婿入りし、ゆくは源嗣の後を継ぎ月霞村の村長となることが決まっている。容姿端麗で聡明な男性であることから、始まりは政略的な縁談とはいえ、霧江は一之助にたいそう惚れ込んでいた。
「今日中に、夏瑠璃の実をかごいっぱい取ってきなさい。ただ飯食らいを屋敷に置いておきたくはないもの。あのあばずれな母親の分までしっかり働くことね」
苗が返事をするよりも早く、霧江は苗にわざとらしく肩をぶつけて廊下を歩み去っていった。ぶつかられた拍子に椀の汁物がこぼれ、あかぎれた手の甲にかかる。
(……私もお母様も、ただ飯食らいと言われないくらい働いているのに)
霧江の言葉を思い出せば悔しさが募った。
苗は三条家の女中として、朝から晩まで身を粉にして働いている。厠の掃除から早朝の水汲みまで、やれと言われた仕事を断った経験はない。そして紫は病で床に伏しているものの、屋敷中の針仕事を一挙に引き受けている。それだけ働いても光子と霧江には無能扱いされ、もらえる賃金は雀の涙だ。
「文句ばかり言っていても仕方ないわね……。夏瑠璃の実、か……どうしよう」
悩ましげな溜息が零れてしまった。
夏瑠璃の実は、染め物の原料として広く使われている木の実だ。樹木全体が独特の甘い香りを放ち、初夏に美しい瑠璃色の実をみのらせる。
もしも今が初夏であれば夏瑠璃の実を探すことは難しくないが、季節は本格的な夏を迎えようとしている。夏瑠璃の実は大半が採り尽くされて、今から山に入っても見つけることは困難だろう。
霧江はすべてわかった上で、苗に夏瑠璃の実を採ってこいと命じたのだ。
(死に戻る前の私はどうしたんだったかしら……そうだ。山には入ったけど一房しか見つけられなくて、罰として火箸を押しつけられたのよ。息が止まるくらい痛かったわ……)
皮膚を焼かれる痛みを思い出せば足がすくんだ。霧江は何かと理由を見つけては苗を痛めつけようとするが、その中でも火箸は群を抜いた痛みだった。もう二度と味わいたくはない。
どうにかして夏瑠璃の実を集めないと。必死に解決策を探す苗は、やがて一つの名案を思いついた。
「そうだわ。幽世山に行けば、まだ夏瑠璃の実が残っているかもしれない」
首切様が住んでいると言われている幽世山には、滅多に村人は立ち入らない。現に苗も、幽世山に足を踏み入れたのは首切様に首を落とされたあの満月の夜だけだ。
自分が死んだ場所に行くというのは恐ろしくもある。しかし今日は満月の日ではないし、火箸を押しつけられる痛みと比べれば恐怖心など些細なものだ。
食器の片付けを済ませた苗は、大きなかごを背負って幽世山へと向かうのだった。
◇
予想したとおり幽世山にはたくさんの瑠璃の実が実っていた。瑠璃の実だけではない。木苺、いちじく、桑の実、薬の材料になるドクダミや葛の木。贅沢に慣れた光子や霧江は見向きもしないだろうが、苗にとっては宝の山のようだ。
「嬉しい! お母様のお土産にできるわ。あの屋敷では果物なんて食べさせてもらえないもの……」
熟れた木苺を舌にのせると、甘酸っぱさが口いっぱいに広がった。美味しくて次から次へと手が伸びてしまう。満足感に包まれると、悩みばかりの心が少しだけ軽くなった気がした。
苗が背負いかごに半分ほどの実を集めたとき、突然、雨が降り始めた。雨脚はしだいに強くなり、着古した着物の肩を濡らしていく。
(どこか雨宿りできるところはないかしら……)
雨を避けられる場所を探し、森の中を歩きはじめた苗は、数分と立たずに人一人がしゃがんで入れるくらいの小さな洞穴を見つけた。草の生えない岩肌がぽっかりと口を開けたような、薄気味の悪い洞穴だ。
ためらいながらも膝を曲げて洞穴へと潜り込めば、湿気を帯びた土と苔の匂いが鼻をつく。ひゅうと音を立てて風が吹き、緑色の落ち葉が数枚、洞穴の中へと吸い込まれていく。
苗は首をひねって洞穴の奥を見つめた。暗くてよく見えないが、どうやら苗がもぐりこんだ洞窟は奥へと続いてるようだ。
(……どこへ続いているのかしら?)
好奇心を覚えた苗は、背負いかごを下ろし、四つん這いになって洞穴を奥へ奥へと進んでみた。
間もなくして岩肌におおわれた狭苦しい細道を抜けた。入り口はとても狭かったが、洞穴の内部はがらりと広い。天井も壁も、苗が手を伸ばしても届かないくらいだ。
「すごい……秘密基地みたいだわ」
つぶやく声が岩壁に反響した。四方を岩壁に覆われているというのに、洞穴の中には最低限の明るさがある。切り崩されたような岩天井には所々に穴が空いていて、そこから地上の光が射し込んでいるからだ。ごつごつとした岩肌に落ちる光の柱、恐ろしくとも幻想的な風景だ。
苗はまばたくことも忘れて目の前の光景に見入った。
低く掠れた男の声が、岩壁に反響して苗の耳に届いたのはそのときだった。
「――誰か、そこにいるのか?」
「え……」
苗は驚いて、数歩あとずさりをした。空耳かとも思ったが違う。それは確かに人の声で、耳をそばだてればかすかな衣擦れの音と金属のこすれる音が聞こえてくる。
「誰? この洞穴で何をしているの?」
苗が震える声で尋ねると、少し間を置いて返事が返ってきた。
「……囚われている。もう気が遠くなるほど長い時間」
(囚われている……? この洞穴は牢獄か何かだということ?)
苗は男の姿を探し、洞穴を奥の方へと進んだ。
声の主はほどなくして見つかった。両手首を鎖でつながれた若い男が、岩壁を背に力なく座り込んでいた。黒褐色の髪は無造作に背中を流れ、身に着けた着物は元々の色合いがわからないくらい汚れている。頬はこけ、手足は痩せ細り、そうだというのに瞳だけは赤々と美しい色を放っていた。まるで闇を照らすかがり火のように。
苗はしばし男の赤い瞳に魅入り、ふと我に返って尋ねた。
「あなたは……あなたは、罪を犯してここに囚われているの?」
「……そうだ。黄泉の国では決して許されることのない罪を犯した」
「黄泉……? あなたは人間ではないの?」
「違う、俺は鬼だ。罪を犯して居場所をなくした、できそこないの鬼」
最後の方は自嘲するような口調だった。
男の言葉はにわかには信じがたかった。しかし嘘だと決めつけることもできなかった。月霞村の住人は幽世山に近づかない。付近に他の村や集落もないから、男は飲まず食わずでこの洞穴に幽閉されていたことになる。普通の人間ならば7日と生きられないだろう。
「あなたはいつからここに囚われているの?」
「……いつからだろう。200年か300年か、そのくらいだ」
「そんなに……」
苗は目を丸くした。
もしも昨日までの苗だったから、男の言うことを素直には信じられなかっただろう。だが今の苗は違う。夢だと疑いたくなるような出来事をいくつも経験した。言い伝えの中の存在だった首切様と遭遇し、首を落とされ、過去へと戻ってきた。鬼が一人、目の前に現れたところで驚くことなどあるだろうか。
「私はすぐそばの月霞村に住んでいるの。苗、という名前なのだけれど……あなたの名前は?」
苗がうかがうような口調で尋ねると、男は赤く美しい瞳をゆっくりと瞬いて答えた。
「篝」
(お母様が吐血してから薬に毒を盛られるまで、2カ月以上は時間があったはずだわ。お母様を助けるためには、この2カ月の間に何をすればいいのかしら……)
苗は廊下を歩きながら考え続けた。
苗の腹違いの姉である霧江は、苗に母殺しの罪を着せるべく紫の薬に毒を入れた。それだけ苗のことを嫌っていたということだ。紫を助けるためには、苗と霧江の関係を改善するのがもっとも手っ取り早いのだが。
(霧江ねえ様との関係を改善……そんなことが本当にできるかしら。私のことを蛆虫のように嫌っている人なのに――あ)
廊下の向こうがわに派手な着物がちらついた。主張の強い真っ赤な牡丹に、金刺繍をほどこした桜色の帯。霧江だ。霧江は通りすがりざまに足を止めて、害虫を見るような目つきで苗のことをねめつけた。
「あら嫌だ、こんなところに蛆虫が湧いてるわ。お父様にお願いして早く退治してもらわないと」
こうして存在自体が害悪のように扱われることは日常茶飯事だったので、苗は何も言い返さずに黙っていた。霧江は面白くなさそうに鼻を鳴らす。
ひとつ年上の霧江は、幼少時からずっと苗のことを毛嫌いしていた。苗が不貞行為によって生まれた子だということはもちろんあるが、理由はそれだけではないと苗は感じていた。
霧江はお世辞にも美人だといえる容姿ではない。派手な着物と濃い化粧でごまかしてはいるが、彼女が容姿に劣等感を持っていることは誰の目から見ても明らかだ。対して苗は――苗自身は己の顔立ちを美とも醜とも捉えたことはないのだが――かつて源嗣を魅了した若かりし頃の紫に生き写しだと言われている。
だから霧江は苗が嫌いなのだ。不貞行為の末に生まれた娘が、自分よりも遥かに美しい容姿をしているから。苗を貶め、罵倒することで自尊心を満たそうとしている。
霧江は薄ら笑いながら唇を撫でた。それは霧江が苗をいたぶろうとするときの癖だ。
「そういえば、月の末に一之助様がいらっしゃる予定なのよね。一之助様にお見せするために、手染めの着物をあつらえようと思っていたのだけれど」
「……」
一之助は霧江の婚約者の名前だ。月霞村から馬車で一時間ほどのところにある港町で貿易業を営んでいる香坂家の三男。およそ半年後に三条家に婿入りし、ゆくは源嗣の後を継ぎ月霞村の村長となることが決まっている。容姿端麗で聡明な男性であることから、始まりは政略的な縁談とはいえ、霧江は一之助にたいそう惚れ込んでいた。
「今日中に、夏瑠璃の実をかごいっぱい取ってきなさい。ただ飯食らいを屋敷に置いておきたくはないもの。あのあばずれな母親の分までしっかり働くことね」
苗が返事をするよりも早く、霧江は苗にわざとらしく肩をぶつけて廊下を歩み去っていった。ぶつかられた拍子に椀の汁物がこぼれ、あかぎれた手の甲にかかる。
(……私もお母様も、ただ飯食らいと言われないくらい働いているのに)
霧江の言葉を思い出せば悔しさが募った。
苗は三条家の女中として、朝から晩まで身を粉にして働いている。厠の掃除から早朝の水汲みまで、やれと言われた仕事を断った経験はない。そして紫は病で床に伏しているものの、屋敷中の針仕事を一挙に引き受けている。それだけ働いても光子と霧江には無能扱いされ、もらえる賃金は雀の涙だ。
「文句ばかり言っていても仕方ないわね……。夏瑠璃の実、か……どうしよう」
悩ましげな溜息が零れてしまった。
夏瑠璃の実は、染め物の原料として広く使われている木の実だ。樹木全体が独特の甘い香りを放ち、初夏に美しい瑠璃色の実をみのらせる。
もしも今が初夏であれば夏瑠璃の実を探すことは難しくないが、季節は本格的な夏を迎えようとしている。夏瑠璃の実は大半が採り尽くされて、今から山に入っても見つけることは困難だろう。
霧江はすべてわかった上で、苗に夏瑠璃の実を採ってこいと命じたのだ。
(死に戻る前の私はどうしたんだったかしら……そうだ。山には入ったけど一房しか見つけられなくて、罰として火箸を押しつけられたのよ。息が止まるくらい痛かったわ……)
皮膚を焼かれる痛みを思い出せば足がすくんだ。霧江は何かと理由を見つけては苗を痛めつけようとするが、その中でも火箸は群を抜いた痛みだった。もう二度と味わいたくはない。
どうにかして夏瑠璃の実を集めないと。必死に解決策を探す苗は、やがて一つの名案を思いついた。
「そうだわ。幽世山に行けば、まだ夏瑠璃の実が残っているかもしれない」
首切様が住んでいると言われている幽世山には、滅多に村人は立ち入らない。現に苗も、幽世山に足を踏み入れたのは首切様に首を落とされたあの満月の夜だけだ。
自分が死んだ場所に行くというのは恐ろしくもある。しかし今日は満月の日ではないし、火箸を押しつけられる痛みと比べれば恐怖心など些細なものだ。
食器の片付けを済ませた苗は、大きなかごを背負って幽世山へと向かうのだった。
◇
予想したとおり幽世山にはたくさんの瑠璃の実が実っていた。瑠璃の実だけではない。木苺、いちじく、桑の実、薬の材料になるドクダミや葛の木。贅沢に慣れた光子や霧江は見向きもしないだろうが、苗にとっては宝の山のようだ。
「嬉しい! お母様のお土産にできるわ。あの屋敷では果物なんて食べさせてもらえないもの……」
熟れた木苺を舌にのせると、甘酸っぱさが口いっぱいに広がった。美味しくて次から次へと手が伸びてしまう。満足感に包まれると、悩みばかりの心が少しだけ軽くなった気がした。
苗が背負いかごに半分ほどの実を集めたとき、突然、雨が降り始めた。雨脚はしだいに強くなり、着古した着物の肩を濡らしていく。
(どこか雨宿りできるところはないかしら……)
雨を避けられる場所を探し、森の中を歩きはじめた苗は、数分と立たずに人一人がしゃがんで入れるくらいの小さな洞穴を見つけた。草の生えない岩肌がぽっかりと口を開けたような、薄気味の悪い洞穴だ。
ためらいながらも膝を曲げて洞穴へと潜り込めば、湿気を帯びた土と苔の匂いが鼻をつく。ひゅうと音を立てて風が吹き、緑色の落ち葉が数枚、洞穴の中へと吸い込まれていく。
苗は首をひねって洞穴の奥を見つめた。暗くてよく見えないが、どうやら苗がもぐりこんだ洞窟は奥へと続いてるようだ。
(……どこへ続いているのかしら?)
好奇心を覚えた苗は、背負いかごを下ろし、四つん這いになって洞穴を奥へ奥へと進んでみた。
間もなくして岩肌におおわれた狭苦しい細道を抜けた。入り口はとても狭かったが、洞穴の内部はがらりと広い。天井も壁も、苗が手を伸ばしても届かないくらいだ。
「すごい……秘密基地みたいだわ」
つぶやく声が岩壁に反響した。四方を岩壁に覆われているというのに、洞穴の中には最低限の明るさがある。切り崩されたような岩天井には所々に穴が空いていて、そこから地上の光が射し込んでいるからだ。ごつごつとした岩肌に落ちる光の柱、恐ろしくとも幻想的な風景だ。
苗はまばたくことも忘れて目の前の光景に見入った。
低く掠れた男の声が、岩壁に反響して苗の耳に届いたのはそのときだった。
「――誰か、そこにいるのか?」
「え……」
苗は驚いて、数歩あとずさりをした。空耳かとも思ったが違う。それは確かに人の声で、耳をそばだてればかすかな衣擦れの音と金属のこすれる音が聞こえてくる。
「誰? この洞穴で何をしているの?」
苗が震える声で尋ねると、少し間を置いて返事が返ってきた。
「……囚われている。もう気が遠くなるほど長い時間」
(囚われている……? この洞穴は牢獄か何かだということ?)
苗は男の姿を探し、洞穴を奥の方へと進んだ。
声の主はほどなくして見つかった。両手首を鎖でつながれた若い男が、岩壁を背に力なく座り込んでいた。黒褐色の髪は無造作に背中を流れ、身に着けた着物は元々の色合いがわからないくらい汚れている。頬はこけ、手足は痩せ細り、そうだというのに瞳だけは赤々と美しい色を放っていた。まるで闇を照らすかがり火のように。
苗はしばし男の赤い瞳に魅入り、ふと我に返って尋ねた。
「あなたは……あなたは、罪を犯してここに囚われているの?」
「……そうだ。黄泉の国では決して許されることのない罪を犯した」
「黄泉……? あなたは人間ではないの?」
「違う、俺は鬼だ。罪を犯して居場所をなくした、できそこないの鬼」
最後の方は自嘲するような口調だった。
男の言葉はにわかには信じがたかった。しかし嘘だと決めつけることもできなかった。月霞村の住人は幽世山に近づかない。付近に他の村や集落もないから、男は飲まず食わずでこの洞穴に幽閉されていたことになる。普通の人間ならば7日と生きられないだろう。
「あなたはいつからここに囚われているの?」
「……いつからだろう。200年か300年か、そのくらいだ」
「そんなに……」
苗は目を丸くした。
もしも昨日までの苗だったから、男の言うことを素直には信じられなかっただろう。だが今の苗は違う。夢だと疑いたくなるような出来事をいくつも経験した。言い伝えの中の存在だった首切様と遭遇し、首を落とされ、過去へと戻ってきた。鬼が一人、目の前に現れたところで驚くことなどあるだろうか。
「私はすぐそばの月霞村に住んでいるの。苗、という名前なのだけれど……あなたの名前は?」
苗がうかがうような口調で尋ねると、男は赤く美しい瞳をゆっくりと瞬いて答えた。
「篝」