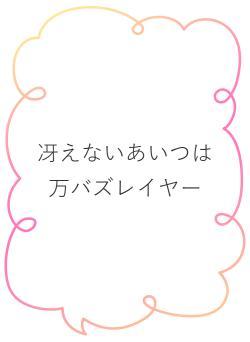目を覚ました苗が最初に見たものは、夜空に浮かぶ黄金色の満月だった。
風のない夜だ。空気はべたりと湿気を帯びていて、甘く蕩けるような植物の香りが辺りを満たしている。どこかで不気味に鳥が鳴く。不規則で騒がしい虫たちの声が聞こえてくる。辺りの様子をうかがうように視線を動かせば、鬱蒼と生い茂る木々が苗のことを見下ろしていた。
(ここは――)
考えようとすると、全身ににぶい痛みを感じた。腕が、足が、背中が、少し身動ぎをするだけでズキズキと痛む。どうして夜の森で寝ていたのか、どうして全身が痛むのか、理由を考えてみてもまどろむ頭では答えに行きつくことができなかった。
ふいに虫たちの泣き声が止んだ。
痛いほどの静寂が辺りを包んだ。
まるで苗のまわりだけ時が止まってしまったみたいだ。
突如として訪れた静寂が恐ろしくなり、苗は身を起こそうとした。しかしそれは叶わなかった。薄汚れた着物のすそから覗く足首には麻縄が幾重にも巻きつけられており、背中に回された手首も同様だ。歩くことはおろか、立ち上がることさえできそうにない。
「いや……何で。どうして」
必死で縄をほどこうとする苗の耳に、草を踏み分ける音が聞こえてきた。足音は徐々に大きくなり、苗のいる場所から少し離れたところで歩みを止めた。
そこにいたのは身震いをするほど恐ろしい風貌の男だった。ひび割れ模様の面は口元だけが苗の存在をあざけるように笑い、狒々を思わせる紅毛が無造作に背中を流れている。黒無地の着物は闇夜にまぎれるためにあつらわれたのだろうか、それとも死者を弔うための喪衣だろうか。
「あ、あ……ぅああ」
絞り出した声は恐怖にかすれていた。苗がその男を見たのは初めてのことだったが、彼が何者であるかはすぐに理解した。
「――首切様」
首切様は、苗が暮らす村に古くから言い伝えられる神の名前だ。月に一度、満月の夜に現れて罪人の首を切る。もっとも首切様の存在は伝承的に言い伝えられてきただけで、その存在を信じる者はほとんどいないのだが。
恐れおののく苗の目の前で、首切様はすらりと刀を抜いた。銀色の刃が月光を受けて輝く。研ぎ澄まされた刃は、痩せ細った苗の首など簡単に切り落とすだろう。
その瞬間、苗は全てを思い出した。なぜ一人で夜の森にいたのかも、なぜ逃げられないように手足を縛られていたのかも、なぜ全身ににぶい痛みを感じたのかも。
恐怖に震える舌を引き剥がし、懸命に訴えた。
「違う! お母様を殺したのは私じゃない! すべて霧江義姉様が仕組んだことよ!」
苗の声は静まり帰った森の中に虚しく響いた。
今朝、病に伏せっていた母が死んだ。治療のために飲んでいた薬に毒が混ぜられていたのだ。真っ先に疑われたのは薬を飲ませた苗だった。無罪を訴えても信じてもらえることはなく、親殺しの罪を着せられた苗は、暴行の末にこの場所へと連れてこられた。首切様が住まう幽世山へと――
「私はお母様を愛していた! 看病が大変だから死んでほしいなんて、そんなこと一度も考えたことはない! これからもずっと一緒に生きていきたいって――」
叫ぶ声には嗚咽が混じった。麻縄と皮膚がこすれ鮮血がにじんだ。どうにかこうにか身体だけは起こし、首切様を見つめ涙を流した。罪人ではないと訴える声が、彼の耳に届くことだけを願って。
だが悲しくも願いは届かなかった。首切様はひび割れた面の向こうから苗を見下ろし、言葉もなく刀を振り上げた。ひゅう、と風を切る音がする。
(ああ……もしもやり直せたのなら)
苗は迫りくる刃を他人事のように眺めた。
(もしもやり直せたのなら、お母様を死なせはしないのに。霧江ねえ様の策略になんて嵌まらないのに。こんな……こんな惨めな最期を迎えはしないのに――)
首筋に今まで感じたことのない激痛が走り、それを最後に緑の意識は途絶えた。
夜空に浮かぶ満月が、少女の哀れな最期を嘲笑うように見下ろしていた。
◇
「いやぁぁぁっ!!」
苗は、絹を裂くような悲鳴をあげて飛び起きた。湿気を吸って重たくなった布団が、痩せた肩からはらりと落ちる。
(ゆ、夢だったの……?)
鐘のように鳴る心臓を抑えながら周囲の様子をうかがえば、見慣れた光景が広がっていた。広さが四畳ばかりの小さな座敷だ。窓がないため座敷全体が薄暗く、淀んだ空気が滞留している。文字を書くための文机と、古臭く黴の生えた衣装箪笥。それと使い古されて煎餅のようになった布団が一組。
目に映る物といえばそれが全てだが、いつもと変わらない光景は苗を安心させてくれた。
(よかった……でも気味が悪くなるくらい生々しい夢だった。縄で縛られた感触も、首を切られた痛みも、まるで本当に経験したことのように覚えている……)
冷えた手のひらで首筋を撫でる。夢の中で首切様に切り落とされた場所だ。母を亡くしたあげく、殺しの罪を着せられて首を落とされるなど、苗にとっては耐えがたい悪夢だ。
「苗! いつまで寝てるつもりだい⁉ さっさと起きて仕事をするんだよ!」
怒声とともに座敷の襖が勢いよく開いた。眉をつりあげているのは、派手な着物に身を包んだ四十路の女性だ。彼女の名は三条光子――苗が女中として仕えている三条家の奥方だ。
まだどこか夢見心地だった気分は一気に現実へと引き戻されて、苗は慌てて布団から這い出し、光子に向かって深々と頭を下げた。
「申し訳ありません! 少し、嫌な夢を見てしまって……」
「嫌な夢ぇ? ひょっとしてあの汚らわしい母親が死ぬ夢でも見たのかい」
苗が驚いて顔をあげると、光子はわざとらしい微笑を浮かべて苗のことを見下ろしていた。
「おや、図星かい。そりゃ景気のいい夢だ。明日にでも仕立屋に行って新しい着物をあつらえるとするか。あの女狐の葬式で着る吉祥文様の着物を」
吉祥文様の着物は、本来なら結婚式や結納など祝いの場で着るための物だ。そのめでたい着物を葬式の場で着ようと光子は言う。母親を蔑む発言だと理解はしながらも、苗は何も言わずに黙っていた。言い返したところで、苗にとって良いことなど起きはしないのだから。
やがて光子は興味をなくしたように笑うのを止めた。
「支度をして廊下の拭き掃除をしな。屋敷中の廊下を拭き終わるまで朝食はなしだ」
吐き捨てるような言葉を残し、光子は座敷を立ち去った。
また一人きりとなった座敷で、苗は安堵の息を吐き出した。
(寝坊を理由に折檻されるかと思ったけれど……叩かれなくてよかった。馬用の鞭で太ももを叩かれたら、また数日間、夜も眠れなくなってしまうから)
着物越しに太ももを撫でる。激痛というほどではないが、かつて光子に鞭で打たれた場所がじくりと痛んだ。三条家の奥方である光子と、彼女の娘である霧江は、何かと理由をつけて苗を折檻することが趣味なのだ。無茶な仕事を言いつけられて、その仕事をこなせなかった罰として折檻を受けた回数は数知れない。
(いけない、考え事をしていないで早く仕事に取りかからないと。廊下の拭き掃除……正午までに終わるといいけれど)
華族の家である三条家の屋敷は広い。廊下の拭き掃除と簡単に言っても、本来ならば女中が数人がかりでこなす仕事だ。苗は身支度もそこそこに大急ぎで座敷を飛び出すのだった。
◇
苗が屋敷中の廊下の拭き掃除を終えたのは、やはり正午も近くなってからのことだった。
朝食をとりに台所へ向かうと、割烹着を着た女中たちがすでに昼飯の準備を進めていて、苗のことを迷惑そうにねめつけた。
「何の用だい?」
「あの……朝飯をいただこうと思って」
「またこんな時間に……後片付けにも手がかかるんだから食事は決まった時間に済ませておくれよ」
「……すみません」
昼飯はいりませんから、と小さな声で付け足したあと、苗は台所の隅に追いやられていた食事をかきこんだ。
炊事の邪魔にならないように洗い物を済ませ、台所の隅に残されたもう1人分の食事を持ってある場所へと向かう。廊下を横切り、四季の花が咲き乱れる中庭を抜け、広大な敷地の隅にぽつりと佇む古びた小屋へと。
苗が仕える三条家は、人口が1200人ほどの月霞村を治める村長の家だ。月霞村唯一の華族の家でもあり、現在の村長の名を三条源嗣という。優秀な村長であるとともに、無類の女好きとして村中に名が知られている人物でもある。
さてそんな源嗣は、妻である光子が娘の霧江を身籠もっているとき、とある過ちを犯した。女中として屋敷に迎え入れたばかりの若く美しい娘と、なかば強引に性関係を持ったのだ。その娘の名は紫――苗の母親だ。
幾度におよぶ性関係の末に、紫は子を身籠もった。それが苗である。つまり苗は源嗣と女中との間に生まれた庶子だということで、光子が苗を毛嫌いする理由がここにある。
「お母様、遅くなってごめんなさい。食事を持ってきたわ」
苗が小屋の扉を開けたとき、紫は痩せた背中を丸めて繕い物をしていた。苗を見てはにかむ紫の顔は、不健康そうではあるが三十代半ばとは思えないほど若々しく美しい。
「苗。いつも食事を運ばせてごめんなさいね」
「ううん、気にしないで。お母様は病気なんだから仕方ないでしょう」
「そうね……早くよくなるといいんだけど」
そう言うと、紫は苦しそうに咳き込んだ。苗は持っていた朝食の盆を置き、呼吸が楽になるようにと紫の背中をさすった。
紫は1年前ほどから病気を患っている。病名はわからない。痰の絡んだ咳と発熱、倦怠感と胸の痛み。病状は悪化の一途をたどり、薬を飲んでもよくなることはない。だから紫は隔離と療養の名目で、この古びた小屋に押し込められていた。そして小屋から出ることを許されない紫に食事を運び、身の回りの世話をするのは苗の仕事だった。
(お母様の病気はどうすればよくなるのかしら。一度きちんとお医者様に見てもらえればあるいは……でも光子様の許しがないことにはお医者様を呼べないし……)
三条家の主は源嗣だが、苗と紫の処遇については光子が権限を握っていた。だから紫の病気が悪化しても医者を呼ぶことができず、気休めに野草からこしらえた薬を飲ませることしかできない。
源嗣も遊び心で手をだした女中と、彼女が産んだ不義の子にさしたる興味はないようで、光子の横暴さを咎めることはない。屋敷に仕える女中たちも光子を敵に回したくないがために追従し、苗と紫の味方となってくれる者は誰一人としていなかった。
「げほっ……!」
ひときわ激しい咳をして、紫は身体をくの字に折り曲げた。口元にあてられた手のひらの、指と指の間から、鮮血がぽたぽたと滴り落ちる。吐血だ。
「お母様――」
苗は驚いて口を開きかけ、しかしそれ以上何も言うことができなかった。紫がそうして血を吐く光景を以前どこかで見たことがある。
(なぜ……なぜこんな気持ちになるの? お母様が血を吐くのは今日が初めてのはずなのに)
苗は、紫を労ることも忘れて思いを巡らせた。そしてすぐに既視感の正体に思い至った。
昨晩の夢の中で、今と同じ光景を見た。母殺しの汚名を着せられ、首切様に首を切り落とされた質の悪い夢。あの夢は夢とは思えないほどよく順序立てられていて、その一つに紫が血を吐く場面があったはずだ。
瞬間、背中に冷水を流されたような気持ちになった。
(違う、あれは夢なんかじゃない。私が現実の世界で体験した出来事だわ。今朝、私は悪夢から覚めたのではなく、首切様に殺されて過去へと戻ってきた……)
にわかには信じがたい事実だが、苗はその考えがただの妄想ではないと確信した。なぜなら苗は夢の中で体験した全ての出来事を、まるで昨日の出来事のように鮮明に覚えているのだから。母を死なせてしまった無念さも、霧江に対する殺意にも似た思いを、そして首切様を目の前にした恐怖心も――
(だとすれば、これは私に与えられた最後の機会……ということかしら。霧江ねえ様が薬に毒を盛ることを知っていれば、みすみすお母様を死なせてしまうことはない。こんな私でも未来を変えることができるかもしれない)
不規則に咳き込む紫の背中をなでながら、苗は決意を固めた口調でつぶやいた。
「絶対に助けてみせるわ、お母様」
風のない夜だ。空気はべたりと湿気を帯びていて、甘く蕩けるような植物の香りが辺りを満たしている。どこかで不気味に鳥が鳴く。不規則で騒がしい虫たちの声が聞こえてくる。辺りの様子をうかがうように視線を動かせば、鬱蒼と生い茂る木々が苗のことを見下ろしていた。
(ここは――)
考えようとすると、全身ににぶい痛みを感じた。腕が、足が、背中が、少し身動ぎをするだけでズキズキと痛む。どうして夜の森で寝ていたのか、どうして全身が痛むのか、理由を考えてみてもまどろむ頭では答えに行きつくことができなかった。
ふいに虫たちの泣き声が止んだ。
痛いほどの静寂が辺りを包んだ。
まるで苗のまわりだけ時が止まってしまったみたいだ。
突如として訪れた静寂が恐ろしくなり、苗は身を起こそうとした。しかしそれは叶わなかった。薄汚れた着物のすそから覗く足首には麻縄が幾重にも巻きつけられており、背中に回された手首も同様だ。歩くことはおろか、立ち上がることさえできそうにない。
「いや……何で。どうして」
必死で縄をほどこうとする苗の耳に、草を踏み分ける音が聞こえてきた。足音は徐々に大きくなり、苗のいる場所から少し離れたところで歩みを止めた。
そこにいたのは身震いをするほど恐ろしい風貌の男だった。ひび割れ模様の面は口元だけが苗の存在をあざけるように笑い、狒々を思わせる紅毛が無造作に背中を流れている。黒無地の着物は闇夜にまぎれるためにあつらわれたのだろうか、それとも死者を弔うための喪衣だろうか。
「あ、あ……ぅああ」
絞り出した声は恐怖にかすれていた。苗がその男を見たのは初めてのことだったが、彼が何者であるかはすぐに理解した。
「――首切様」
首切様は、苗が暮らす村に古くから言い伝えられる神の名前だ。月に一度、満月の夜に現れて罪人の首を切る。もっとも首切様の存在は伝承的に言い伝えられてきただけで、その存在を信じる者はほとんどいないのだが。
恐れおののく苗の目の前で、首切様はすらりと刀を抜いた。銀色の刃が月光を受けて輝く。研ぎ澄まされた刃は、痩せ細った苗の首など簡単に切り落とすだろう。
その瞬間、苗は全てを思い出した。なぜ一人で夜の森にいたのかも、なぜ逃げられないように手足を縛られていたのかも、なぜ全身ににぶい痛みを感じたのかも。
恐怖に震える舌を引き剥がし、懸命に訴えた。
「違う! お母様を殺したのは私じゃない! すべて霧江義姉様が仕組んだことよ!」
苗の声は静まり帰った森の中に虚しく響いた。
今朝、病に伏せっていた母が死んだ。治療のために飲んでいた薬に毒が混ぜられていたのだ。真っ先に疑われたのは薬を飲ませた苗だった。無罪を訴えても信じてもらえることはなく、親殺しの罪を着せられた苗は、暴行の末にこの場所へと連れてこられた。首切様が住まう幽世山へと――
「私はお母様を愛していた! 看病が大変だから死んでほしいなんて、そんなこと一度も考えたことはない! これからもずっと一緒に生きていきたいって――」
叫ぶ声には嗚咽が混じった。麻縄と皮膚がこすれ鮮血がにじんだ。どうにかこうにか身体だけは起こし、首切様を見つめ涙を流した。罪人ではないと訴える声が、彼の耳に届くことだけを願って。
だが悲しくも願いは届かなかった。首切様はひび割れた面の向こうから苗を見下ろし、言葉もなく刀を振り上げた。ひゅう、と風を切る音がする。
(ああ……もしもやり直せたのなら)
苗は迫りくる刃を他人事のように眺めた。
(もしもやり直せたのなら、お母様を死なせはしないのに。霧江ねえ様の策略になんて嵌まらないのに。こんな……こんな惨めな最期を迎えはしないのに――)
首筋に今まで感じたことのない激痛が走り、それを最後に緑の意識は途絶えた。
夜空に浮かぶ満月が、少女の哀れな最期を嘲笑うように見下ろしていた。
◇
「いやぁぁぁっ!!」
苗は、絹を裂くような悲鳴をあげて飛び起きた。湿気を吸って重たくなった布団が、痩せた肩からはらりと落ちる。
(ゆ、夢だったの……?)
鐘のように鳴る心臓を抑えながら周囲の様子をうかがえば、見慣れた光景が広がっていた。広さが四畳ばかりの小さな座敷だ。窓がないため座敷全体が薄暗く、淀んだ空気が滞留している。文字を書くための文机と、古臭く黴の生えた衣装箪笥。それと使い古されて煎餅のようになった布団が一組。
目に映る物といえばそれが全てだが、いつもと変わらない光景は苗を安心させてくれた。
(よかった……でも気味が悪くなるくらい生々しい夢だった。縄で縛られた感触も、首を切られた痛みも、まるで本当に経験したことのように覚えている……)
冷えた手のひらで首筋を撫でる。夢の中で首切様に切り落とされた場所だ。母を亡くしたあげく、殺しの罪を着せられて首を落とされるなど、苗にとっては耐えがたい悪夢だ。
「苗! いつまで寝てるつもりだい⁉ さっさと起きて仕事をするんだよ!」
怒声とともに座敷の襖が勢いよく開いた。眉をつりあげているのは、派手な着物に身を包んだ四十路の女性だ。彼女の名は三条光子――苗が女中として仕えている三条家の奥方だ。
まだどこか夢見心地だった気分は一気に現実へと引き戻されて、苗は慌てて布団から這い出し、光子に向かって深々と頭を下げた。
「申し訳ありません! 少し、嫌な夢を見てしまって……」
「嫌な夢ぇ? ひょっとしてあの汚らわしい母親が死ぬ夢でも見たのかい」
苗が驚いて顔をあげると、光子はわざとらしい微笑を浮かべて苗のことを見下ろしていた。
「おや、図星かい。そりゃ景気のいい夢だ。明日にでも仕立屋に行って新しい着物をあつらえるとするか。あの女狐の葬式で着る吉祥文様の着物を」
吉祥文様の着物は、本来なら結婚式や結納など祝いの場で着るための物だ。そのめでたい着物を葬式の場で着ようと光子は言う。母親を蔑む発言だと理解はしながらも、苗は何も言わずに黙っていた。言い返したところで、苗にとって良いことなど起きはしないのだから。
やがて光子は興味をなくしたように笑うのを止めた。
「支度をして廊下の拭き掃除をしな。屋敷中の廊下を拭き終わるまで朝食はなしだ」
吐き捨てるような言葉を残し、光子は座敷を立ち去った。
また一人きりとなった座敷で、苗は安堵の息を吐き出した。
(寝坊を理由に折檻されるかと思ったけれど……叩かれなくてよかった。馬用の鞭で太ももを叩かれたら、また数日間、夜も眠れなくなってしまうから)
着物越しに太ももを撫でる。激痛というほどではないが、かつて光子に鞭で打たれた場所がじくりと痛んだ。三条家の奥方である光子と、彼女の娘である霧江は、何かと理由をつけて苗を折檻することが趣味なのだ。無茶な仕事を言いつけられて、その仕事をこなせなかった罰として折檻を受けた回数は数知れない。
(いけない、考え事をしていないで早く仕事に取りかからないと。廊下の拭き掃除……正午までに終わるといいけれど)
華族の家である三条家の屋敷は広い。廊下の拭き掃除と簡単に言っても、本来ならば女中が数人がかりでこなす仕事だ。苗は身支度もそこそこに大急ぎで座敷を飛び出すのだった。
◇
苗が屋敷中の廊下の拭き掃除を終えたのは、やはり正午も近くなってからのことだった。
朝食をとりに台所へ向かうと、割烹着を着た女中たちがすでに昼飯の準備を進めていて、苗のことを迷惑そうにねめつけた。
「何の用だい?」
「あの……朝飯をいただこうと思って」
「またこんな時間に……後片付けにも手がかかるんだから食事は決まった時間に済ませておくれよ」
「……すみません」
昼飯はいりませんから、と小さな声で付け足したあと、苗は台所の隅に追いやられていた食事をかきこんだ。
炊事の邪魔にならないように洗い物を済ませ、台所の隅に残されたもう1人分の食事を持ってある場所へと向かう。廊下を横切り、四季の花が咲き乱れる中庭を抜け、広大な敷地の隅にぽつりと佇む古びた小屋へと。
苗が仕える三条家は、人口が1200人ほどの月霞村を治める村長の家だ。月霞村唯一の華族の家でもあり、現在の村長の名を三条源嗣という。優秀な村長であるとともに、無類の女好きとして村中に名が知られている人物でもある。
さてそんな源嗣は、妻である光子が娘の霧江を身籠もっているとき、とある過ちを犯した。女中として屋敷に迎え入れたばかりの若く美しい娘と、なかば強引に性関係を持ったのだ。その娘の名は紫――苗の母親だ。
幾度におよぶ性関係の末に、紫は子を身籠もった。それが苗である。つまり苗は源嗣と女中との間に生まれた庶子だということで、光子が苗を毛嫌いする理由がここにある。
「お母様、遅くなってごめんなさい。食事を持ってきたわ」
苗が小屋の扉を開けたとき、紫は痩せた背中を丸めて繕い物をしていた。苗を見てはにかむ紫の顔は、不健康そうではあるが三十代半ばとは思えないほど若々しく美しい。
「苗。いつも食事を運ばせてごめんなさいね」
「ううん、気にしないで。お母様は病気なんだから仕方ないでしょう」
「そうね……早くよくなるといいんだけど」
そう言うと、紫は苦しそうに咳き込んだ。苗は持っていた朝食の盆を置き、呼吸が楽になるようにと紫の背中をさすった。
紫は1年前ほどから病気を患っている。病名はわからない。痰の絡んだ咳と発熱、倦怠感と胸の痛み。病状は悪化の一途をたどり、薬を飲んでもよくなることはない。だから紫は隔離と療養の名目で、この古びた小屋に押し込められていた。そして小屋から出ることを許されない紫に食事を運び、身の回りの世話をするのは苗の仕事だった。
(お母様の病気はどうすればよくなるのかしら。一度きちんとお医者様に見てもらえればあるいは……でも光子様の許しがないことにはお医者様を呼べないし……)
三条家の主は源嗣だが、苗と紫の処遇については光子が権限を握っていた。だから紫の病気が悪化しても医者を呼ぶことができず、気休めに野草からこしらえた薬を飲ませることしかできない。
源嗣も遊び心で手をだした女中と、彼女が産んだ不義の子にさしたる興味はないようで、光子の横暴さを咎めることはない。屋敷に仕える女中たちも光子を敵に回したくないがために追従し、苗と紫の味方となってくれる者は誰一人としていなかった。
「げほっ……!」
ひときわ激しい咳をして、紫は身体をくの字に折り曲げた。口元にあてられた手のひらの、指と指の間から、鮮血がぽたぽたと滴り落ちる。吐血だ。
「お母様――」
苗は驚いて口を開きかけ、しかしそれ以上何も言うことができなかった。紫がそうして血を吐く光景を以前どこかで見たことがある。
(なぜ……なぜこんな気持ちになるの? お母様が血を吐くのは今日が初めてのはずなのに)
苗は、紫を労ることも忘れて思いを巡らせた。そしてすぐに既視感の正体に思い至った。
昨晩の夢の中で、今と同じ光景を見た。母殺しの汚名を着せられ、首切様に首を切り落とされた質の悪い夢。あの夢は夢とは思えないほどよく順序立てられていて、その一つに紫が血を吐く場面があったはずだ。
瞬間、背中に冷水を流されたような気持ちになった。
(違う、あれは夢なんかじゃない。私が現実の世界で体験した出来事だわ。今朝、私は悪夢から覚めたのではなく、首切様に殺されて過去へと戻ってきた……)
にわかには信じがたい事実だが、苗はその考えがただの妄想ではないと確信した。なぜなら苗は夢の中で体験した全ての出来事を、まるで昨日の出来事のように鮮明に覚えているのだから。母を死なせてしまった無念さも、霧江に対する殺意にも似た思いを、そして首切様を目の前にした恐怖心も――
(だとすれば、これは私に与えられた最後の機会……ということかしら。霧江ねえ様が薬に毒を盛ることを知っていれば、みすみすお母様を死なせてしまうことはない。こんな私でも未来を変えることができるかもしれない)
不規則に咳き込む紫の背中をなでながら、苗は決意を固めた口調でつぶやいた。
「絶対に助けてみせるわ、お母様」