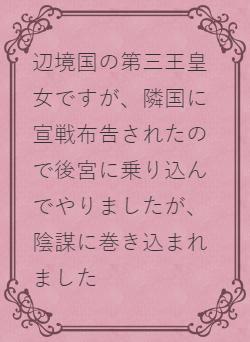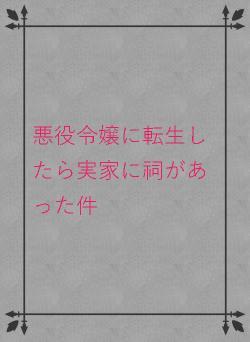数日が経った頃、戸を叩く音がした。
「お姉様、入ってもいい?」
声は紫乃だった。
静かに戸が開き、盆を手にした彼女が姿を見せた。
「お見舞いに来たの。あまり食べてないって聞いたから」
優しい声、優しい笑顔。
その手には、湯気を立てる茶碗と茶菓子が乗っていた。
「これ、私が淹れたの。香りのよい茶葉が手に入ったのよ。気分が落ち着くかと思って」
柚羽がお礼を言おうとしたそのとき、もう一つの影が戸口に現れた。
「失礼いたします」
低く、よく通る声。
見慣れない青年――禰宜の装束を身に着けた男が、静かに二人の間に入る。
「紫乃様、そのお茶と菓子は私がお預かりいたします」
「……は?」
紫乃は眉をひそめた。
「何のつもり? 私はお姉様にお茶を運んできたのよ?」
言葉は柔らかいが、視線は明らかに不快を示していた。
「申し訳ございません。柚羽様は、口にされるもの全て管理されております。決まりでございます」
「そんな決まり、今までなかったはずよ」
紫乃の声が少し鋭くなる。だが青年は一歩も引かない。
「本日より、決まりました」
紫乃はため息をひとつついて盆を青年に渡した。
「……ふうん。まあ、いいわ。お姉様、また来ますわね」
にっこりと微笑みながら、彼女は踵を返す。
戸が閉まる音を背に、柚羽は静かに男を見つめた。
(……そんな決まり、なかったはず)
紫乃が去っていったあとの部屋に、静寂が戻った。
しかし、柚羽の視線は彼女の背中ではなく、その場に残った青年のほうへ向いていた。
白装束の下に深緑の袴。黒い髪はきちんと整えられ、目元は涼やか。
だが――目の前の男には見覚えがなかった。
(この人……誰?)
柚羽は御神楽家に仕える巫女と禰宜、見習いや使用人も含めて全員の顔と名前を覚えていた。
家に関わる者の顔を忘れたことなど一度もない。
「あなた……ここの禰宜じゃないわね」
思わず咎めるような言葉が漏れる。
青年は少しだけ黙ってから、ゆっくりと頷いた。
「申し訳ありません。私は、継杜家から派遣された者で遙真と申します」
静かな口調だったが、その一言で柚羽は目を見開いた。
「……継杜家から?」
「はい。当家では、今回の件について調査を進めております」
そう告げる青年の眼差しは真っ直ぐだった。
「当家の星見は、『あなたが花の巫女である』と告げました。他の占い師の結果も、同様です」
その言葉は、閉ざされていた心の扉をわずかに揺らした。
まだ誰かが信じてくれている。
青年は膝をつき、柚羽の目線と高さを合わせた。
「今夜、ここを出ましょう。柚羽様。私があなたを守ります」
柚羽は、どう答えればいいか迷う。でも外から香る芍薬の香りが、柚羽の背中を押した。
(今月は芍薬の神事があったわ。私はまだ、花の巫女として認められているのかもしれない)
「分かりました」
「お姉様、入ってもいい?」
声は紫乃だった。
静かに戸が開き、盆を手にした彼女が姿を見せた。
「お見舞いに来たの。あまり食べてないって聞いたから」
優しい声、優しい笑顔。
その手には、湯気を立てる茶碗と茶菓子が乗っていた。
「これ、私が淹れたの。香りのよい茶葉が手に入ったのよ。気分が落ち着くかと思って」
柚羽がお礼を言おうとしたそのとき、もう一つの影が戸口に現れた。
「失礼いたします」
低く、よく通る声。
見慣れない青年――禰宜の装束を身に着けた男が、静かに二人の間に入る。
「紫乃様、そのお茶と菓子は私がお預かりいたします」
「……は?」
紫乃は眉をひそめた。
「何のつもり? 私はお姉様にお茶を運んできたのよ?」
言葉は柔らかいが、視線は明らかに不快を示していた。
「申し訳ございません。柚羽様は、口にされるもの全て管理されております。決まりでございます」
「そんな決まり、今までなかったはずよ」
紫乃の声が少し鋭くなる。だが青年は一歩も引かない。
「本日より、決まりました」
紫乃はため息をひとつついて盆を青年に渡した。
「……ふうん。まあ、いいわ。お姉様、また来ますわね」
にっこりと微笑みながら、彼女は踵を返す。
戸が閉まる音を背に、柚羽は静かに男を見つめた。
(……そんな決まり、なかったはず)
紫乃が去っていったあとの部屋に、静寂が戻った。
しかし、柚羽の視線は彼女の背中ではなく、その場に残った青年のほうへ向いていた。
白装束の下に深緑の袴。黒い髪はきちんと整えられ、目元は涼やか。
だが――目の前の男には見覚えがなかった。
(この人……誰?)
柚羽は御神楽家に仕える巫女と禰宜、見習いや使用人も含めて全員の顔と名前を覚えていた。
家に関わる者の顔を忘れたことなど一度もない。
「あなた……ここの禰宜じゃないわね」
思わず咎めるような言葉が漏れる。
青年は少しだけ黙ってから、ゆっくりと頷いた。
「申し訳ありません。私は、継杜家から派遣された者で遙真と申します」
静かな口調だったが、その一言で柚羽は目を見開いた。
「……継杜家から?」
「はい。当家では、今回の件について調査を進めております」
そう告げる青年の眼差しは真っ直ぐだった。
「当家の星見は、『あなたが花の巫女である』と告げました。他の占い師の結果も、同様です」
その言葉は、閉ざされていた心の扉をわずかに揺らした。
まだ誰かが信じてくれている。
青年は膝をつき、柚羽の目線と高さを合わせた。
「今夜、ここを出ましょう。柚羽様。私があなたを守ります」
柚羽は、どう答えればいいか迷う。でも外から香る芍薬の香りが、柚羽の背中を押した。
(今月は芍薬の神事があったわ。私はまだ、花の巫女として認められているのかもしれない)
「分かりました」