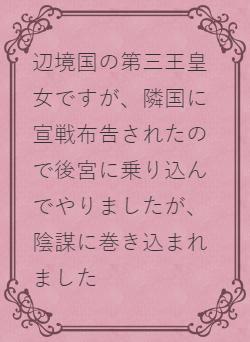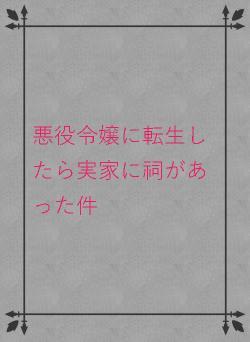そんなある日、柚羽は父から「大切な話がある」と巫女見習いから言づてを受けた。父の元へ向かった柚羽だが、客人でもいるのか何やら騒がしい。
襖の向こうから怒声とも取れる声が漏れ聞こえ、柚羽はびくりとして足を止める。
「……もう限界です! 当主様。御神楽家の名誉のためにも、柚羽様をどうにかするべきです!」
「死人が出て、なお居座らせる理由があるのですか?」
声の主は、屋敷付きの禰宜たちだった。儀式の補佐を務める神職たちは、口々に言葉を重ねていた。
「不吉どころではありません。実際に死人が出ているのです。しかも自殺で二人も……。皆、怯えております」
「死の巫女だと、まことしやかな噂が広まっているのはご存じでしょう? これ以上柚羽様を表に立たせておくなど、正気の沙汰ではありません」
「そうは言っても、なぁ」
父の声は歯切れが悪かった。
「継杜家からの正式な任命がまだ保留のままなのだ。わたしの一存で追い出せば、かえって不敬と取られかねん。あちらの判断を待つしか――」
「では、当家が神を冒涜していると民から噂されてもよいのですか?」
「命を脅かす者が「花の巫女」を名乗るなど、神への冒涜です!」
語気を強める禰宜たちに、柚羽は襖の向こうで立ち尽くすしかなかった。
彼らの言葉が身体に突き刺さって、呼吸が浅くなる。恐怖と憎しみ。そんな負の感情が柚羽に向けられている。
けれどそのとき、部屋の奥から一際澄んだ声が上がった。
「やめてください。それ以上、お姉様を責めるのは間違ってます」
紫乃の声だった。
何故妹が重要な会議に加わっているのか分からないが、少なくとも上座に座り強い発言権を与えられているのは想像できる。
「沙耶が亡くなったのは悲しいことです。でもお姉様が原因だなんて、誰が決めたんですか? 確証もないのに追い出すなんて。私は許しません」
十七歳とは思えない、毅然とした口調だった。
怯えも曖昧さもない。
紫乃が静かに部屋の中央に進み出る衣擦れの音が聞こえる。
「私は姉を信じています。どんな噂が広まっても、家族として、同じ巫女として。信じてあげたいんです」
しばらく沈黙が流れた。
やがて、誰かが軽く咳払いし、禰宜たちは一人、また一人と謝罪の言葉を口にする。
父も黙って紫乃の言葉を聞き、禰宜達の謝罪を受け入れたようだ。
柚羽は廊下に佇んだまま、そっと自分の胸に手を当てた。
(私は紫乃に守られているんだ……)
そう思うべきなのに、どこか違和感が残る。
それでも、自分を庇ってくれる人がいるという事実に、柚羽はほんの少しだけ救われたような気がした。
襖の向こうから怒声とも取れる声が漏れ聞こえ、柚羽はびくりとして足を止める。
「……もう限界です! 当主様。御神楽家の名誉のためにも、柚羽様をどうにかするべきです!」
「死人が出て、なお居座らせる理由があるのですか?」
声の主は、屋敷付きの禰宜たちだった。儀式の補佐を務める神職たちは、口々に言葉を重ねていた。
「不吉どころではありません。実際に死人が出ているのです。しかも自殺で二人も……。皆、怯えております」
「死の巫女だと、まことしやかな噂が広まっているのはご存じでしょう? これ以上柚羽様を表に立たせておくなど、正気の沙汰ではありません」
「そうは言っても、なぁ」
父の声は歯切れが悪かった。
「継杜家からの正式な任命がまだ保留のままなのだ。わたしの一存で追い出せば、かえって不敬と取られかねん。あちらの判断を待つしか――」
「では、当家が神を冒涜していると民から噂されてもよいのですか?」
「命を脅かす者が「花の巫女」を名乗るなど、神への冒涜です!」
語気を強める禰宜たちに、柚羽は襖の向こうで立ち尽くすしかなかった。
彼らの言葉が身体に突き刺さって、呼吸が浅くなる。恐怖と憎しみ。そんな負の感情が柚羽に向けられている。
けれどそのとき、部屋の奥から一際澄んだ声が上がった。
「やめてください。それ以上、お姉様を責めるのは間違ってます」
紫乃の声だった。
何故妹が重要な会議に加わっているのか分からないが、少なくとも上座に座り強い発言権を与えられているのは想像できる。
「沙耶が亡くなったのは悲しいことです。でもお姉様が原因だなんて、誰が決めたんですか? 確証もないのに追い出すなんて。私は許しません」
十七歳とは思えない、毅然とした口調だった。
怯えも曖昧さもない。
紫乃が静かに部屋の中央に進み出る衣擦れの音が聞こえる。
「私は姉を信じています。どんな噂が広まっても、家族として、同じ巫女として。信じてあげたいんです」
しばらく沈黙が流れた。
やがて、誰かが軽く咳払いし、禰宜たちは一人、また一人と謝罪の言葉を口にする。
父も黙って紫乃の言葉を聞き、禰宜達の謝罪を受け入れたようだ。
柚羽は廊下に佇んだまま、そっと自分の胸に手を当てた。
(私は紫乃に守られているんだ……)
そう思うべきなのに、どこか違和感が残る。
それでも、自分を庇ってくれる人がいるという事実に、柚羽はほんの少しだけ救われたような気がした。