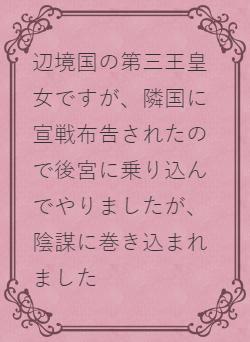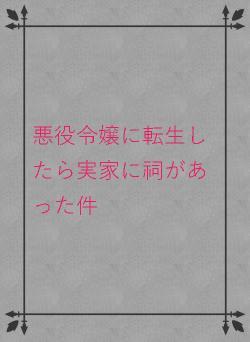紫乃は空を見上げるようにして立ち尽くしていた。
もう視線はどこにも定まらず、手足もただ震えているだけ。
舞う気力は萎え、身体は限界を超えていた。
柚羽は静かに歩み寄り、そっと紫乃に手を差し伸べる。
「紫乃……」
名前を呼ぶ声には、怒りも憐れみもない。
ただ、家族としての記憶と哀しみが滲んでいた。
「……休んで、紫乃。もう、舞わなくていいから」
その声が届いたのか、紫乃はわずかに顔を向け――
「や……ぁ……わたし……わたしが……ッ!」
意味を成さない叫び声と共に、ぐらりと崩れ落ちる。
倒れ込んだその身体は吹き出る汗に濡れ、髪は乱れて肌は赤黒く浮腫んでいた。
全身に巡った毒が、神経と血管を焼き尽くしつつあるのが、見ただけで分かった。
遙真がすぐに駆け寄り、柚羽を抱き寄せる。
「見なくていい。もう、充分だ」
「いいえ、私は見届けなくてはなりません」
紫乃の苦しみから目を背けるのは違う気がしたのだ。
「毒は既に彼女の全身を巡っている。継杜の医師に託すしかない」
遙真の指示で同行していた医師が神楽殿に上がり、紫乃の脈を取ったり緊急用の点滴の用意を始めている。
柚羽は、遙真の胸の中で、小さく震えながらも、なお顔を上げて訊ねた。
「紫乃は……妹は、どうなるの?」
その問いに、遙真は静かに答えた。
「継杜家の管理下にある病院へ送る。療養させるしかない。……紫乃さんは、もはや罪を問える状態ではない」
柚羽の喉が、きゅっと詰まる。
「どこまで回復できるかは、彼女の体力次第だ……しかし回復したとて、罰を受けるよりも辛いだろうね」
そう呟いた遙真の目には、僅かに影が差していた。
舞台の片隅では、神職たちが来客を神楽殿から遠ざけるべく動いている。
その場にいた誰もが、紫乃の姿を見て悟っていた。
――長くは持たない。
全身を痙攣させながら、紫乃は呻き続けている。
声はもはや巫女のものではなく、ただ一人の少女が、救いを求めて漏らすような声だった。
柚羽は、そんな紫乃を前にしても何もできない。
穢れを作り出した紫乃の回復を祈ったところで、神は許さないだろう。
優しさとは、赦すことではない。
哀しみとは、同情することではない。
同じ母のもとに育った妹が、自らの手で壊れていった事実。
それを受け止めるには、ただ、静かに目を逸らさずにいるしかなかった。
柚羽は、涙を流さなかった。
けれど深く胸に痛みを刻んだ。
もう視線はどこにも定まらず、手足もただ震えているだけ。
舞う気力は萎え、身体は限界を超えていた。
柚羽は静かに歩み寄り、そっと紫乃に手を差し伸べる。
「紫乃……」
名前を呼ぶ声には、怒りも憐れみもない。
ただ、家族としての記憶と哀しみが滲んでいた。
「……休んで、紫乃。もう、舞わなくていいから」
その声が届いたのか、紫乃はわずかに顔を向け――
「や……ぁ……わたし……わたしが……ッ!」
意味を成さない叫び声と共に、ぐらりと崩れ落ちる。
倒れ込んだその身体は吹き出る汗に濡れ、髪は乱れて肌は赤黒く浮腫んでいた。
全身に巡った毒が、神経と血管を焼き尽くしつつあるのが、見ただけで分かった。
遙真がすぐに駆け寄り、柚羽を抱き寄せる。
「見なくていい。もう、充分だ」
「いいえ、私は見届けなくてはなりません」
紫乃の苦しみから目を背けるのは違う気がしたのだ。
「毒は既に彼女の全身を巡っている。継杜の医師に託すしかない」
遙真の指示で同行していた医師が神楽殿に上がり、紫乃の脈を取ったり緊急用の点滴の用意を始めている。
柚羽は、遙真の胸の中で、小さく震えながらも、なお顔を上げて訊ねた。
「紫乃は……妹は、どうなるの?」
その問いに、遙真は静かに答えた。
「継杜家の管理下にある病院へ送る。療養させるしかない。……紫乃さんは、もはや罪を問える状態ではない」
柚羽の喉が、きゅっと詰まる。
「どこまで回復できるかは、彼女の体力次第だ……しかし回復したとて、罰を受けるよりも辛いだろうね」
そう呟いた遙真の目には、僅かに影が差していた。
舞台の片隅では、神職たちが来客を神楽殿から遠ざけるべく動いている。
その場にいた誰もが、紫乃の姿を見て悟っていた。
――長くは持たない。
全身を痙攣させながら、紫乃は呻き続けている。
声はもはや巫女のものではなく、ただ一人の少女が、救いを求めて漏らすような声だった。
柚羽は、そんな紫乃を前にしても何もできない。
穢れを作り出した紫乃の回復を祈ったところで、神は許さないだろう。
優しさとは、赦すことではない。
哀しみとは、同情することではない。
同じ母のもとに育った妹が、自らの手で壊れていった事実。
それを受け止めるには、ただ、静かに目を逸らさずにいるしかなかった。
柚羽は、涙を流さなかった。
けれど深く胸に痛みを刻んだ。